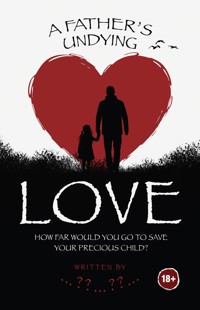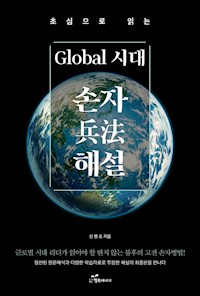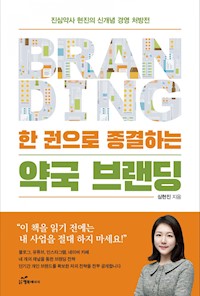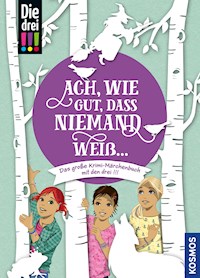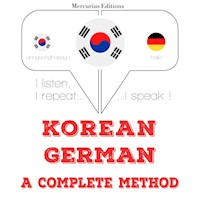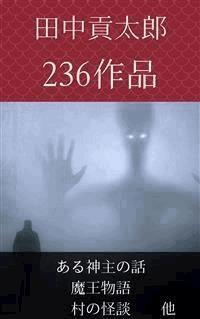
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: micpub.com
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: ja
最新の田中貢太郎の著作236作品を集めた大全です。
田中貢太郎の代表作である魔王の物語、ある神主の話などを全て掲載しています。
田中貢太郎の世界をご堪能ください。
「田中貢太郎は日本の作家、号は桃葉。著作は伝記物、紀行文、随想集、情話物、怪談・奇談など多岐に渡る。著名作に、回顧記・紀行などの文集『貢太郎見聞録』、1929年から総計530回にわたり新聞連載された大作『旋風時代』、翻案物である『日本怪談全集』、『支那怪談全集』がある。ほかに論語、大学・中庸などの経書に関する作品も著すなど、生前に五十数冊を刊行した。」
(Wikipediaより抜粋)
掲載作品一覧
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Guide
表紙
目次
扉
本文
目 次
阿宝
藍瓶
愛卿伝
藍微塵の衣服
赤い花
赤い土の壺
赤い牛
あかんぼの首
悪僧
尼になった老婆
雨夜続志
雨夜草紙
雨夜詞
青い紐
ある神主の話
朝倉一五〇
怪しき旅僧
美女を盗む鬼神
貧乏神物語
忘恩
帽子のない水兵
牡丹燈籠 牡丹燈記
牡丹燈記
文妖伝
豕
竹青
陳宝祠
提燈
長者
太虚司法伝
断橋奇聞
瞳人語
円朝の牡丹燈籠
不動像の行方
藤の瓔珞
富貴発跡司志
風呂供養の話
蛾
蟇の血
雁
月光の下
幻術
義猫の塚
岐阜提燈
義人の姿
義猴記
八人みさきの話
蠅供養
母の変死
母親に憑る霊
花の咲く比
這って来る紐
碧玉の環飾
変災序記
室の中を歩く石
飛行機に乗る怪しい紳士
平山婆
一握の髪の毛
人のいない飛行機
放生津物語
法華僧の怪異
北斗と南斗星
堀切橋の怪異
宝蔵の短刀
位牌田
位牌と鼠
一緒に歩く亡霊
虎杖採り
岩魚の怪
蛇怨
蛇性の婬
地獄の使
人面瘡物語
女賊記
怪談会の怪異
怪談覚帳
海異志
海神に祈る
怪人の眼
怪僧
怪譚小説の話
鍛冶の母
荷花公主
牡蠣船
賈后と小吏
竈の中の顔
亀の子を握ったまま
蟹の怪
簪につけた短冊
累物語
警察署長
金鳳釵記
切支丹転び
狐の手帳
狐と狸
黄英
虎媛
狐狗狸の話
法衣
胡氏
黄燈
首のない騎馬武者
空中に消えた兵曹
黒い蝶
『黒影集』の序詞
車屋の小供
草藪の中
薬指の曲り
嬌娜
真紅な帆の帆前船
魔の電柱
魔王物語
港の妖婦
餅を喫う
萌黄色の茎
狢
村の怪談
娘の生霊
長崎の電話
猫の踊
遁げて往く人魂
「日本怪談全集」序
日本天変地異記
偶人物語
人蔘の精
二通の書翰
庭の怪
沼田の蚊帳
女仙
お化の面
黄金の枕
おいてけ堀
狼の怪
追っかけて来る飛行機
鬼火を追う武士
女の出る蚊帳
女の怪異
女の首
女の姿
唖娘
唖の妖女
男の顔
阿芳の怨霊
雷峯塔物語
令狐生冥夢録
蓮香
レンズに現われた女の姿
陸判
老犬の怪
老狐の怪
轆轤首
掠奪した短刀
涼亭
緑衣人伝
料理番と婢の姿
劉海石
柳毅伝
再生
崔書生
鮭の祟
参宮がえり
皿屋敷
殺神記
青蛙神
西湖主
千匹猿の鍔
仙術修業
戦死者の凱旋
死んでいた狒狒
死人の手
神仙河野久
申陽洞記
白い花赤い茎
白い小犬を抱いた女
白いシヤツの群
白っぽい洋服
死体の匂い
死体を喫う学生
商売の繁昌する家
焦土に残る怪
終電車に乗る妖婆
春心
種梨
酒友
蕎麦餅
蘇生
葬式の行列
水莽草
水郷異聞
水魔
水面に浮んだ女
炭取り
棄轎
雀が森の怪異
雀の宮物語
狸と同棲する人妻
狸と俳人
立山の亡者宿
天長節の式場
天井からぶらさがる足
天井裏の妖婆
賭博の負債
南北の東海道四谷怪談
とんだ屋の客
隧道内の怪火
通魔
竇氏
築地の川獺
机の抽斗
海嘯のあと
鼓の音
宇賀長者物語
馬の顔
海坊主
鷲
火傷した神様
疫病神
山寺の怪
山の怪
山姑の怪
屋根の上の黒猫
妖蛸
妖影
妖女の舞踏する踏切
妖怪記
頼朝の最後
寄席の没落
四谷怪談
指環
雪の夜の怪
雪女
幽霊の衣裳
幽霊の自筆
前妻の怪異
雑木林の中
続黄梁
阿宝
田中貢太郎
粤西えっせいに孫子楚そんしそという名士があった。枝指むつゆびのうえに何所どこかにぼんやりしたところがあったから、よく人にかつがれた。その孫は他所よそへ往って歌妓げいしゃでもいると、遠くから見ただけで逃げて帰った。その事情を知ったものがうまくこしらえて伴つれてきて、歌妓をそばへやってなれなれしくでもさすと、頸くびまで赧あかくして、汗を流してこまった。悪戯者いたずらものどもはそれを面白がっていたが、後には諢名あだなをつけて孫痴そんちといった。
村に豪商があってそこの富力は大名とおんなじ位だといわれていた。従って親類も皆身分がよかった。その豪商に阿宝あほうという女むすめがあって婿になる人を探していた。富豪のうえに女がその地方きっての美人であったから、豪家の少年達は争うて鴈がんの結納ゆいのうを持ちこんで婿になろうとしたが、どれもこれも女の父親の気にいらなかった。その時、孫は細君を亡くして独身でいたが、悪戯者の一人がまたそれに目をつけて、
「君は細君を亡くしているが、阿宝に結婚を申しこんではどうだね」
と言った。孫はふとその気になって自分の境遇のことも考えずに、とうとう媒なこうどをする婆さんに頼んで結婚を申しこんだ。
阿宝の父親は孫の名を聞いたが、あまり貧乏だからと思って躊躇した。そこで媒の婆さんが父親の室へやを出て帰ろうとしていると、阿宝が出てきた。婆さんここぞとおもって、孫生にたのまれてあなたに結婚を申しこんできたところだと言った。阿宝も孫の噂を聞いて知っていたので冗談にしてしまった。
「あの枝指をとってくれるなら、結婚してもいいわ」
婆さんは帰ってきて孫に話した。孫は本気にして、
「そんなことはなんでもないさ」
と言って、婆さんの帰った後で、斧を出してきて、その枝指を断きってしまった。ひどい痛みが脳天に突きぬけるようになると共に、血がどくどくと出て、ほとんど瀕死の状態になった。そして、数日たってはじめてやっと起きることができたので、媒の婆さんの所へ往って傷痕を見せた。婆さんはびっくりして走って往って女に知らした。すると女がまたからかった。
「では、お婆さん、こう言ってちょうだいよ、あなたの馬鹿をとってくれってね」
婆さんは帰ってきてまたそれを孫に話した。孫は、
「婆さん僕は馬鹿じゃないよ、僕を馬鹿というのは間違っているよ」
とやかましく弁解したが、自分の腹の中を女に見せることができないということに気が注ついて、
「阿宝が綺麗だといったところで、天女にはおよばないだろう、高くとまるにもほどがあるじゃないか」
と言ったが、それから阿宝と結婚しようとするの思いはなくなってしまった。
清明の節になった。土地の風習としてその日は女が郊外に出て遊ぶので、軽薄の少年が隊を組んで随ついて往って、口から出まかせに女の美醜を品評するのであった。孫の同窓の友人も強しいて孫を伴れて郊外に往った。すると友人の一人が嘲って言った。
「一度、あの人を見ようと思ってるのじゃないかね」
孫も阿宝のことで自分をからかっているということを知っていたが、女からばかにせられているので、どんな女であるか一度見たいと思って喜んで随いて往った。
ふと見ると遠くの方の樹の下に女が休んでいて、それを少年達が取り巻いて人牆ひとがきをつくっているのが見えた。すると皆が言った。
「あれはきっと阿宝だよ」
急いで往って見ると果して阿宝であった。孫はそれをじっと見た。それは娟麗けんれいならぶものなき女であった。みるみる人が多くなってきた。女は起って急いで往ってしまった。群衆の感情が沸き立って女の頭のことを言い、足のことを言い、それは紛々ふんぷんとして狂人のようであったが、孫は独り考えこんでいた。
孫の友人達はむこうの方へ往ってふりかえった。孫はまだ故もとの所に白痴ばかのようになって立っていた。友人達は声を揃えて呼んでみたが、孫は返事もしなければ見向きもしなかった。友人達は皆で往って引っぱった。
「おい魂が阿宝に随いて往ったのじゃないかい」
孫は考えこんだまま返事もしなかった。皆は孫の平生のぼんやりを知っているので怪しまなかった。そこで皆で手を引いたり後ろから推したりして帰ってきた。そして家へ帰った孫は、すぐ榻ねだいの上にあがって寝たが、終日起きなかった。家の者が気をつけてみると酔ったように解らなくなっていた。呼び起しても醒めなかった。家の者は魂を失ったのではあるまいかと思って、野原へ往って、魂を招く法式を行ったが効がなかった。強いて体を叩いて、
「おい、しっかりしろ、どうしたのだ」
といって訊くと、孫はぼんやりした声で、
「俺は阿宝の家にいるのだ」
と言った。家の者はもうすこし精くわしいことを訊こうと思って問うたが、孫は黙ってしまってもう何も言わなかった。家の者は驚き惑うばかりで理由が解らなかった。
はじめ孫は、阿宝の帰って往くのを見て、捨ててゆけない気になると共に、自分の体がそれに従いて往くのを感じた。そして、やっとその帯の間にひっついたが、べつに叱る者もなかった。とうとう女の家へ帰って、寝る時も坐る時もいつもいっしょにいるようになった。孫は甚だ得意であったが、ひもじいので、一度家へ帰ろうと思っても路が解らなかった。
女は毎晩夢の中で男に愛せられるので、
「あなたは、何人だれ」
と言って訊いた。すると男は、
「私は孫子楚だよ」
と言った。女は心のうちで不思議に思ったが、人に言うべきことでもないから黙っていた。
孫の体は榻に寝てから三日になったが、息がかすかになって今にも滅入りそうになった。家の者はひどく驚いて人を豪商の許へやって、そこで魂を招かしてくれと頼んだので、阿宝の父親は笑って言った。
「ふだん往復したことのない者が、なんで私の家へ魂を遺してゆこう」
孫の家の者はそれでも是非招かしてくれと頼んだので、阿宝の父親もやっと承諾した。そこで巫かんなぎが孫の着ふるしの着物と草で織った敷物をもって豪商へ往った。阿宝はその事情を聞いてひどく駭おどろき、他へ往かさずにすぐに自分の室へあげて魂を招かした。そして巫がその法式を行って帰り、孫の家の門口まで往ったところで、榻の上の孫の体がうめきだしたが、間もなく醒めた。そこで阿宝の室の鏡台はじめ什具じゅうぐの色合や名前を訊いてみると、すこしも違わなかった。阿宝はそのことを伝え聞いてますます駭くと共に、陰ひそかにその情の深いのに感じた。
孫は既に病牀を離れたが、阿宝のことが忘れられないので、時とするとものを忘れた人のようになって考えこむことがあった。そしていつも阿宝の身辺に注意していて、もう一度逢ってみたいと思っていた。四月八日の灌仏会かんぶつえの日がきて、阿宝が水月寺へ参詣するということを聞いて、朝早く往って道中で待っていた。そして車に乗ってくる人を注意していたが、あまりに一心になって見つめていたためにたちくらみがした。
午ごろになって阿宝の車がやっと来た。阿宝は車の中から孫を見つけて、しんなりした手で簾すだれを搴あげて、目もはなさずに見つめた。孫はますます心を動かされて後から従いて往った。阿宝はとうとう侍女に言いつけて孫に尋ねさした。
「失礼ですが、あなたのお名前は」
孫は殷懃いんぎんに言った。
「私は孫子楚というものでございます」
孫の魂はますますぐらついた。そのうちに車は往ってしまった。孫はそこでやっと帰ってきたが帰るとまた病気になって、精神が朦朧となり、食事もせずに夢中になって阿宝の名を呼んだ。そして自分の魂の霊験のなくなったのを恨んだ。
その孫の家には一羽の鸚鵡おうむを飼ってあったが、急に死んでしまったので、児こどもが持ってきて孫の榻の傍で弄いじっていた。孫はそれを見てもし自分が鸚鵡になることができたなら、飛んで女の室へ往けるのだと思った。そして心をそれに注とめていた。と、体がひらりと鸚鵡になって、不意に飛びあがりそのまますぐに阿宝の所へ往った。阿宝は入ってきた鸚鵡を見て喜んでつかまえ、肘に鎖をつけて麻の実を餌にやった。すると孫の鸚鵡は大声で叫んだ。
「お嬢さん、鎖をつけちゃ駄目です、僕は孫子楚ですよ」
阿宝はひどく駭いて鎖を解いた。孫の鸚鵡は動かなかった。そこで女は言った。
「あなたのお心は、心にきざんでおりますけれど、今となっては、禽とりと人と種類がちがいますから、結婚することができないじゃありませんか」
孫の鸚鵡が言った。
「僕は、あなたの側にいられるなら、本望だ」
他の人が餌をやっても食わなかったが、阿宝がやれば食った。そして、阿宝が坐るとその膝の上に止まり、寝るとその榻に止まった。
そんなふうで三日になった。阿宝はそれがひどく気の毒になって、陰に人をやって孫の家の容子ようすを見さした。孫は寝たまま気を失って、已に三日になっていたが、ただ胸のさきが冷えきらないばかりであった。阿宝はそこで言った。
「あなた、能よく人になることができたなら、きっとあなたの、お心に従いましょう」
孫の鸚鵡が言った。
「僕をだますのじゃないのですか」
阿宝は、
「けっしてだましません」
と固く誓った。孫の鸚鵡は目をみはって何か考えているようであったが、暫くして女が髪を結うために履くつを脱いで牀ゆかにあがると、鸚鵡はふいにおりてその履の一つを銜くわえて飛んで往った。阿宝は急いで呼びかえそうとしたが、もう遠くの方へ往ってしまった。そこで女は婆さんの婢じょちゅうに言いつけて、孫の家へ履を探しに往かしたが、婆さんが往ってみると、孫はもう寤さめていた。家の者は鸚鵡が繍ぬいのある履を銜えてきて、下に堕ちて死んだのを見て不思議に思っていると、孫がやがて生きかえって、
「おい履を取ってくれ」
と言った。家の者がその理由を知るに苦しんでいると、そこへ阿宝の家の婆さんが入ってきて、孫を見て、
「その履は何処にあったのです」
と言った。孫は言った。
「これは阿宝と誓いをした物です、あなたから言ってください、僕はお嬢さんの金諾きんだくを忘れないって」
婆さんが帰って往って孫の言ったことを言った。阿宝はますます不思議に思って、わざと婆さんからその容子を母親に話さした。母親はそれを確かめたうえで、
「この人は、評判も悪くはないが、ただ相如そうじょのような貧乏だからね、数年間も婿を選んでいて、そんな貧乏人をもらったとなると、名のある人から笑われるからね」
阿宝は孫に誓っているから決して他へは往かないと言った。阿宝の父親と母親はとうとう女の言葉に従った。
阿宝の父親は孫を入婿にしようかどうかということを評議した。すると阿宝が言った。
「婿は久しく姑しゅうとの家にいるものじゃありません、それにあの人は貧乏人ですから、久しくおれば久しくあるほど人に賤いやしまれます、私は一旦承知しましたから、小屋がけに甘んじます、藜藿あかざのお菜もいといません」
孫はそこで阿宝を親しく迎えて結婚したが、二人は互いに世を隔てて逢った人のように懽よろこんだ。
孫はそれから細君が化粧料として持ってきた金ですこし豊かになった。またいくらか財産もふえたので書物に一生懸命になって、家のことは見向きもしなかった。阿宝はよく貯蓄して、他のことで孫を累わずらわさなかった。三年して家はますます富んだが、孫はたちまち糖尿病のような病気になって死んでしまった。阿宝は悲しんで眠りもしなければ食事も摂らないので、皆がいろいろと勧めたけれども、その言葉を用いなかった。そして夜にまぎれて縊死いししようとした。婢が知って急に救けてよみがえらしたがとうとう食事を摂らなかった。
三日過ぎて親類や友人が集まって、孫の死骸を葬ろうとした。と、棺の中からうめき声が聞えてきた。開けてみると孫は活きかえっていた。
「冥王の前へ往ったところが、冥王は僕が平生の誠実を知っておって部曹ぶそうにしてくれた、すると人が来て、孫部曹の妻がじきにまいりますと言った、で、王は記録を見て、これはまだ死なす者じゃないと言うと、三日も食べずにおりますからと言った、そこで王は僕の方をふりかえって、汝が妻の節義に感じて、いきかえらしてやると言って、馬に乗せて送りかえしてくれたのだ」
それから孫の体はだんだんと回復した。そのうちに官吏登用試験がきた。孫もそれに応ずることになったが、試験場に入る前にあたって、悪戯の少年達はまた孫をからかって、七つ出ることになっている試験の題になぞらえたものを作り、孫を人のいない所へ伴れて往って話した。
「これは某という家へ賄賂を贈って得たものだから、君にあげるよ」
孫はほんとうにして昼夜いろいろと工夫して七つの文章を作った。少年達は隠ひそかに笑いあった。その時試験官は熟なれた題では受験者が前人の文章を模倣するの弊があると思って、力つとめて変った題を出した。その題は皆孫の作った文章に符合していた。そこで孫は郷試に選ばれ、翌年は進士に挙げられて翰林かんりんを授けられた。天子は孫の不思議を聞いて召してお尋ねになった。孫は謹んで申しあげた。天子は非常にお喜びになって、阿宝に拝謁を仰せつけられ、たくさんの下されものがあった。
底本:「中国の怪談(二)」河出文庫、河出書房新社
1987(昭和62)年8月8日初版発行
底本の親本:「支那怪談全集」桃源社
1970(昭和45)年11月30日発行
※「頸くびまで赧あかくして、」は、底本では「頸くびまで赧あかくして、」でしたが、親本を参照して直しました。
入力:Hiroshi_O
校正:門田裕志、小林繁雄
2003年8月3日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
藍瓶
田中貢太郎
玄関の格子戸こうしどがずりずりと開あいて入って来た者があるので、順作は杯さかずきを持ったなりに、その前に坐った女の白粉おしろいをつけた眼の下に曇くもりのある顔をちょと見てから、右斜みぎななめにふりかえって玄関のほうを見た。そこには煤すすけた障子しょうじが陰鬱いんうつな曇日くもりびの色の中に浮いていた。
「何人たれだろう」
何人にも知れないようにそっと引越して来て、まだ中一日たったばかりのところへ、何人がどうして知って来たのだろう、まさか彼ではあるまいと順作は思った。と、障子がすうと開あいて黄きいろな小さな顔が見えた。
「おったか、おったか」
それは出しぬいて犬の子か何かを棄すてるように棄てて来た父親であった。
「あ」
順作はさすがに父親の顔を見ていることができなかった。それにしても荷車まで遠くから頼んで、知れないように知れないようにとして来たのに、どうして知ったのだろうと不思議でたまらなかった。
「電車をおりて、十丁ちょうぐらいだと聞いたが、どうして小こ一里もあるじゃないか、やれ、やれ」
どろどろして灰色に見える小さな縦縞たてじまのある白い単衣ひとえを着た老人は、障子しょうじを締めてよぼよぼと来て茶ちゃぶ台だいの横に坐った。
「よく知れた、ね」
順作はしかたなしにそう云って父親の小さな黄きいろな顔を見た時、その左の眼の上瞼うわまぶたの青黒く腫はれあがっているのに気が注ついた。
「前の車屋の親方が聞いて来てくれたよ、お前が出しぬけに引越したものだから、俺、お大師だいしさんから帰ってまごまごしてると、車屋の親方が来て、お前さんとこの息子は、とんでもねえ奴やつだ、親を棄すてて逃げるなんて、警察へ云ってくが宜いい、俺がいっしょに往いてやろうと云うから、俺がそいつはいけねえ、あれもこれまで商売してて、旨く往かなかったから、都合があって引越したのだ、そいつはいけねえと断ったよ」
「あたりまえよ、不景気で借金が出来たから、ちょと逃げてるのだ、警察なんか怖こわいものか」
「そうとも、そうとも、だから俺、あの親方が、家へ来いと云ってくれたが往かなかったよ」
「よけいなおせっかいだ」
「そうとも、俺は癪しゃくにさわったよ、お前さんとこの息子もいけないが、あの女がいけねえのだ、ちゃぶ屋を渡り歩いた、したたかものだ、とっさんが傍にいると……」
父親のほうはよう見ずに紅あかい手柄てがらをかけた結ゆいたての円髷まるまげの一方を見せながら、火鉢ひばちの火を見ていた女が怒りだした。
「どうせ私は、ちゃぶ屋を渡り歩いた、したたかものですよ」
父親はあわてて云った。
「ま、ま、ま、お前さん、俺は、お前さんの悪口を云うのじゃない、車屋の親方の云ったことを、云ってるところじゃ……」
「どうせ私は、そうですよ、ちゃぶ屋を渡り歩いた、したたかものですよ」
女は父親の顔に怒った眼を向けた。父親の青黒く腫はれあがった左の眼が青くきろきろと光った。
「よけいなことを云うからだ、車屋の痴ばかなんかの云ったことを、お浚さらいするからいけないのだ」
順作はよけいなことを云っていい気もちになっていた女を怒らした闖入者ちんにゅうしゃが憎くて憎くてたまらなかった。
「そ、そ、そりゃわるい、そりゃ俺がわるいが、俺は姐ねえさんの悪口あっこうを云われたから、癪しゃくにさわって、それで云ってるところじゃ、だから車屋の親方が、家へ来て、飯めしも喫くえ、家におれと云ってくれたが、癪にさわったから往かなかったよ」
「それじゃ、どうして知った」
「車屋の壮佼わかいしゅに、荷車の壮佼を知った者があってね」
「そうか」
あんなに旨くやったのにまたしても知られたのかと思って順作は忌いまいましかった。そうした順作の考えのうちには、その前の途中で仲間に逢あったがために知られた引越のことも絡からまっていた。
「まあ、良かった、早く知れて、俺がまごまごしてると、傍はたの者が、よけいなことを云いだすから、姐ねえさんに気のどく……」
老爺おやじの詞ことばを叩き消すように順作が云った。
「いい、それがよけいなことなのだ、なぜ何時いつまでもそんなことを云うのだ」
父親の左の眼が青く鬼魅きみ悪く見えた。父親はじっと伜せがれの顔に眼を移した。
「そうか、そうか、云ってわるいか、わるけりゃ云わない、お前ももう四十を過ぎた考えのある男だから、俺は何も云わん、俺はお前が人様に笑われないように、やってくれるならそれでいい」
女はその時そこにいるのがもうたまらないと云うようにして起たちあがった。単衣ひとえの上に羽織はおった華美はでなお召めしの羽織はおりが陰鬱いんうつな室へやの中に彩あやをこしらえた。順作はそれに気をとられた。
「どこかへ往くのか」
「ちょっとそこまで往って来ますわ」
「どこだね」
「ちょっとそこですわ」
「飯めしを喫くってからにしちゃ、どうだね、俺も往くよ」
「でも、私、ちょっと歩いて来ますわ」
「じゃ、俺も散歩しよう」
「でも、家は」
「家は留守番が出来たから宜いいよ」
「そう」
順作は起たって父親の方を見た。
「腹が空すいたら飯めしを喫くったら宜いいだろう、ちょっと往って来るから」
「宜いとも、宜いとも、往って来るが宜い、俺は遅く物を喫ったから、何も喫いたくない」
女は背後うしろの壁際かべぎわに置いてある鏡台の前へ往って、ちょっと蹲しゃがんで顔を映し、それから玄関の方へ往った。それを見て順作も引きずられるように跟ついて往った。
順作と女は柵のない郊外電車の踏切を越えて、人家と畑地はたちの入り交まじった路みちを歩いて往った。
曇っていた空に雲ぎれがして黄昏ゆうぐれの西の空は樺かば色にいぶっていた。竹垣をした人家の垣根にはコスモスが咲いていたり、畑地の隅すみには薄すすきの穂があった。
「困ったなあ」
「困っちゃったわ」
「田舎いなかへでも往こうか」
「そう、ね、え」
「田舎ならよう来ないだろう」
「でもあんなにしても、判るのだから」
「そうだ」
「どこか穴の中へでも入れとかないかぎりは、追っかけて来るのですわ」
「そうだよ、ほんとに穴倉の中へでも入れときたいね」
「そうよ」
二三人の小供の声で何か歌う声がした。左側に邸址やしきあとらしい空地があって、そこから小供が出て来るところであった。その空地にはおとなの背ぐらいもあるような大きな瓶かめがたくさん俯向うつむけにしてあるのが見えた。
「あれ、なんでしょう」
女が指をさすので順作は考えた。そして、紺屋こうやの瓶ではないかと思った。
「紺屋の瓶のようだね」
「大きいわ、ね、え」
「紺屋の瓶なら大きいよ」
「往ってみましょうか」
「そうね」
二人は空地の中へ折れて往った。短い草が斑まばらに生えて虫が鳴いていた。瓶は十五六箇こもあった。
「小供が入ったらあがれないのね」
「そりゃあがれないだろう」
「重いでしょうか」
「さあ」
順作はうっとりと何か考え込んだが、気が注ついて近くの瓶の傍へ往って、狭せばまっている底のほうに力を入れて押してみた。瓶かめはなかなか重かったがそれでも斜ななめに傾きかけた。
「小供を入れたら出られないでしょうか」
「さあ」
そう云って順作は瓶を離れながら四辺あたりに眼をつらつらとやった。それは己じぶんのやっていることを見ている者がありはしないかと注意するように。
女は順作の容さまをじっと見て何も云わなかった。
「往こう」
二人は空地を出て歩いた。四辺はもう暮れていた。
「おい」
順作はぴたり女に擦すり寄って囁ささやいた。
「帰って厄介者やっかいものを伴つれて来よう」
女は小声で囁きかえした。
「宜いいの」
「宜いさ」
順作と女は家へ帰って来た。父親ははじめに坐っていた処にちょこなんと坐っていた。
「おう、帰ったか、帰ったか」
順作はその父親の詞ことばを受けて云った。
「寄席よせへ往こうと思って、呼びに来た、往こうじゃないか」
「ほう、俺を寄席へ伴つれてってくれるか、そいつはありがたいや、何だかかってるのは」
「落語だよ」
「そうか、姐ねえさんも往くか」
「往くよ」
「そいつはありがたい、伴れてってくれるか」
「じゃ飯めしを喫くって往こう、お父さん喫ったのか」
「俺は喫いたくない、遅く蕎麦そばを喫ったのだから、ひもじけりゃ帰って来て喫うよ、お前達が喫うが宜いい」
「じゃ喫おう」
二人は飯をはじめた。父親は黙りこくって坐っていた。
飯がすむと三人で家を出た。門燈もんとうのすくない街は暗かった。父親は二人の後あとからとぼとぼと体を運んでいた。
三人は黙黙として歩いた。郊外線の電車の線路には電燈がぼつぼつ点ついていた。三人は踏切を越えて歩いた。
虫の声が一めんに聞こえていた。空にはまた一めんに雲がかかっていた。三人は彼かの空地の前へ往った。
「ここを抜けて往こう、近いから」
順作はそう云って、すぐ己じぶんの背後うしろにいる父親のほうを見た。
「そうか、そうか、近い路みちが宜いいとも」
三人は空地の中へ入って往った。瓶かめの傍へ往ったとこで順作が足を止めた。
「お父さん」
「ほい」
「ちょと話がある」
「どんな話だ」
「ちょと蹲しゃがみなよ」
「宜いとも」
父親はそのままそこに蹲んだ。女はそっと父親の顔に注意した。左の腫はれあがっている眼が青くきろきろと光って見えた。と、順作の体が動いて父親の小さな顔は順作の手にした物で包まれてしまった。父親は声も立てなかった。
「それ」
女はその声とともに父親に飛びついてその体を抱き縮すくめた。と、順作の体は傍の瓶に絡からまった。
「それ」
そこにぐうぐうと云うような呻うめきが起った。
「宜いのか」
「宜いわ」
順作と女はそそくさと瓶かめの傍を離れて歩いた。
二人は踏切まで帰って来た。二人の体は電柱に点つけた電燈にぼんやりと照らされた。
電車の響きがすぐ近くでした。
「電車が来た」
順作は女を前さきに立てて走って線路を横ぎろうとした。女が躓つまづいて前のめりに倒れた。順作ははっと思って女を抱きあげようとした、と、そこには女の姿もなければ何もなかった。順作は驚いて眼のせいではないかと思って見なおそうとした。同時に右から来た電車が順作を刎はね飛ばして往った。順作はそのまま意識を失ってしまった。
順作は頭部に裂傷を負い、右の手を折られて附近の病院に収容せられていた。
翌日になって意識の帰って来た順作は、家へ人をやって女を呼びに往ってもらったが、女は留守だと云って来なかった。順作は罪悪が恐ろしくなって逃げたのではないかと思った。順作は女のことよりも罪悪の暴露が恐ろしかった。
翌日になって二人の見知らない男が看護婦に案内せられて入って来た。二人の男の物腰はそれはどうしても刑事であった。順作は顫ふるいあがった。
「警察から来たのだが、あなたは、芝の浜松町×××番地にいて、一昨昨日いっさくさくじつ、ここへ越して来たのですか」
「そうです」
「お父さんと何故なぜいっしょに来なかったのです」
「それは、いろいろ、それは商売のことで、やりくりがあるものですから、何人だれにも知らさずに引越して来たのです、それは爺親おやじも知っております、爺親に聞いてくれたら判ります」
「たしかにそうかね」
「たしかにそうです」
「じゃ、君は未まだ知らないね、君のお父さんは、君が引越した晩に、君のいた家の二階で変死したのだよ」
「え」
順作の驚いたのは昨夜己じぶんの手で瓶かめの下へ伏せた父親が一昨昨夜いっさくさくや死んでいると云う奇怪さであった。しかし、それは云えなかった。
「君はお父さんは何故変死したと思うね」
「私が、私が、新宿の方でカフェーをやって失敗してから、あっちこっちと引越すことは、爺親も承知のうえのことでございました」
順作は奇怪な秘密に就ついていろいろ考えたがどうしても判断がつかなかった。警察からはその後のちも数回詮議に来たので、父親の遺骸いがいの火葬になっていることも判った。
三週間ばかりして順作はすっかり癒なおったので、退院して己じぶんの家へ帰りかけたところで、何時いつの間にかあの空地の前へ出た。見ると空地にはたくさんの人が集まって、何かを中に囲んで見ていた。順作は恐ろしいが見ずには往けないので、こわごわ入って往って人びとの間から覗のぞいた。そこには一つの瓶かめを横に倒した処に見覚えのあるお召めし羽織はおりを着た女の腐爛ふらんした死体が横たわっていた。順作は一眼ひとめ見て気絶してしまった。
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第一巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
愛卿伝
田中貢太郎
胡元こげんの社稷しゃしょくが傾きかけて、これから明が勃興しようとしている頃のことであった。嘉興かこうに羅愛愛らあいあいという娼婦があったが、容貌も美しければ、歌舞音曲の芸能も優れ、詩詞はもっとも得意とするところで、その佳篇麗什かへんれいじゅうは、四方に伝播せられたので、皆から愛し敬うやまわれて愛卿と呼ばれていた。それは芙蓉ふようの花のように美しい中にも、清楚な趣のあった女のように思われる。風流の士は愛卿のことを聞いて、我も我もと身のまわりを飾って狎なれなずもうとしたが、〓(「りっしんべん+(「甍」の「瓦」に代えて「目」)」)学無識ぼうがくむしきの徒は、とても自分達の相手になってくれる女でないと思って、今更ながら己れの愚しさを悟るという有様であった。
ある年のこと、それは夏の十六日の夜のことであった。県中の名士が鴛湖えんこの中にある凌虚閣りょうきょかくへ集まって、涼を取りながら詩酒の宴を催した。空には赤い銅盤のような月が出ていた。愛卿もその席へ呼ばれて、皆といっしょに筆を執ったがまたたくまに四首の詩が出来た。
画閣がかく東頭とうとう涼を納いる
紅蓮こうれんは白蓮はくれんの香かぐわしきに似しかず
一輪りんの明月めいげつ天水てんみずの如し
何いずれの処ところか簫しょうを吹いて鳳凰ほうおうを引く
月は天辺てんぺんに出でて水は湖に在り
微瀾びらん倒さかしまに浸す玉浮図ぎょくふと
簾すだれを掀あげて姐娥そがと共に語らんと欲す
肯あえて霓裳げいしょう一曲きょくを数えんや無いなや
手に弄ろうす双頭そうとう茉莉まつりの枝
曲終って覚えず鬢雲びんうんの欹かたむくことを
珮環はいかん響く処飛仙ひせん過ぐ
願わくは青鸞せいらん一隻を借りて騎のらんことを
曲々たる欄干らんかん正々たる屏へい
六銖しゅ衣ころも薄くして来り凭よるに懶ものうし
夜更けて風露ふうろ涼しきこと如許いくばくぞ
身みは在り瑶台ようだいの第一層に
愛卿の詩を見ると、もう何人たれも筆を持つ者がなかった。
趙という富豪の才子があって、父親が亡くなったので母親と二人で暮していたが、愛卿の才色を慕うのあまり、聘物へいもつを惜まずに迎えて夫人とした。
趙家の人となった愛卿は、身のとりまわしから言葉の端に至るまで、注意に注意を払い、気骨の折れる豪家の家事を遺憾いかんなしに切りもりしたので、趙は可愛がったうえに非常に重んじて、その一言半句も聞き流しにはしなかった。
趙の父親の一族で、吏部尚書りぶしょうしょとなった者があって、それが大都から一封の書を送ってきたが、それには江南で一官職を授けるから上京せよと言ってあった。功名心の盛んな趙は、すぐ上京したいと思ったが、年取った母親のことも気になれば、愛卿を遺して往くことはなおさら気になるので、躊躇していた。
愛卿は趙のそうした顔色を見て言った。
「私が聞いておりますのに、男の子の生れた時は、桑の弧ゆみと蓬よもぎの矢をこしらえて、それで天地四方を射ると申します、これは将来、男が身を立て、名を揚げて、父母を顕わすようにと祝福するためであります、恩愛の情にひかれて、功名の期を逸しては、亡くなられたお父様に対しても不孝になります、お母様のお世話は及ばずながら私がいたします、ただ、お母様はお年を召されておりますうえに、御病身でございますから、それだけはお忘れにならないように」
趙は愛卿に激励せられて、意を決して上京することにした。そこで旅装を調ととのえ、日を期して出発することになり、中堂に酒を置いて、母親と愛卿の三人で別れの觴さかずきをあげた。
その酒が三まわりした時であった。愛卿は趙に向って言った。
「お母様の御健康をお祝しになっては、いかがでございます」
趙はいわれるままに觴を母親の前へ捧げた。
愛卿は立って歌った。それは斉天楽さいてんがくの調べに合わせて作った自作の歌であった。
恩情功名を把りて誤らず
離筵りえんまた金縷きんるを歌う
白髪の慈親じしん
紅顔の幼婦
君去らば誰あって主たらん
流年幾許いくばくぞ
況いわんや悶々愁々
風々雨々
鳳ほう拆くだけ鸞らん分わかる
未だ知らず何いずれの日にか更に相あい聚あつまらん
君が再三分付ぶんぷするを蒙り
堂前に向って侍奉じほうす
辛苦を辞するを休やめ
官誥かんこう花を蟠ばんし
宮袍きゅうほう錦にしきを製す
妻を封じ母を拝するを待たんことを要す
君須すべからく聴取すべし
怕おそる日西山に薄せまって愁阻を生じ易きことを
早く回程かいていを促して
綵衣さいい相対あいたいして舞わん
歌が終った時ぶんには、皆の眼に涙が光っていた。趙を載せて往く舟は、門の前に纜ともづなを解いて待っていた。
趙は酔に力を借って別れを告げて舟へ乗った。愛卿は趙を送って岸へ出て、離れて往く舟に向って白い小さい手端てさきを見せていた。
趙はやがて大都へ往った。往ってみると尚書は病気で官を免ぜられていた。趙は進退に窮して旅館へ入り、故郷へ引返そうか、仕官の口を探そうかと思って迷っているうちに、数ヶ月の日子にっしが経った。
一方故郷の方では、旅に出た我が子の身の上を夜も昼も心配していた趙の母親は、その心配からまた病気がちの体を痛めて、病床の人となった。愛卿は人の手を借らずに、自分で薬を煎じ、粥をこしらえて母親に勧め、また神にその平癒を祈った。
「あの子は、どうしたというだろう、何故便りがないだろう」
母親は愛卿の顔を見るたびに、こんなことをいって聞いた。
「なに、今に何か言ってまいりますよ、それとも官が定ったので、御自分でお迎えにきていらっしゃるかも判りません、御心配なされることはありませんよ」
愛卿はしかたなしにいつもこんなような返事をして慰めていたが、自分でも母親以上に心配していた。
そのうちに半年ばかりになったが、母親の病気はひどくなって、もう愛卿の勧める薬を自分の手で飲むことすらできないようになった。愛卿は枕頭まくらもとに坐って、死に面している老婆の顔を見て泣いていた。と、麻殻あさがらのような痩せた冷たい手がその手にかかった。
「もう私はだめだ、あんたにひどく厄介をかけたが、その返しをすることもできない、このうえ、私の望みは、早くあの子が旅から帰ってくれて、あんたとの間に、児こどもができ、孫ができて、その児や孫達に、あんたが私にしてくれたように、あんたに孝行をさしたい、もし、天がこのことを見ていらっしゃるなら、きっとそうしてくだされる」
母親はそれをやっと言ってから、呼吸いきが絶えてしまった。愛卿はその死骸に取り著いて泣いていた。
愛卿はその母親の死骸を白苧村はくちょそんに葬ったが、心から母親の死を悲しんでいる彼女は、その悲しみのために健康を害して、げっそり体が痩せて見えた。
それは元の至正十七年のことであった。その前年、張士誠ちょうしせいが平江へいこうを陥れたので、江浙左丞相達織帖睦邇こうせつさじょうそうたつしきちょうぼくじが苗軍びょうぐんの軍師楊完ようかんという者に檄を伝えて、江浙の参政の職を授け、それを嘉興で拒ふせがそうとしたところが、規律のない苗軍は掠奪を肆ほしいままにした。
楊完の麾下きかに劉万戸りゅうまんこという者があったが、手兵を連れて突然趙の家へきた。愛卿は大いに驚いて逃げようとしたが、逃げる隙がなくとうとう捕えられて、万戸の前へ引きだされた。
万戸は愛卿の顔を赤濁あかにごりのしたいかつい眼でじっと見ていたが、いきなり抱きかかえて一室の中へ入って往った。愛卿はもう悶掻もがくのをやめていた。万戸の毛もくじゃらの頬はすぐ愛卿の頬の近くにあった。
「体が、体が汚れております、ちょっと湯あみをさしてくださいまし」
万戸はすこし顔を引いて愛卿の顔を見た。
「なりもこんな汚いなりをしております、ちょっとお待ちを願います」
愛卿はにっと笑って万戸の眼を見入った。
「そうか」
万戸もにっと笑って愛卿を下におろした。
愛卿はも一度万戸の方を見て恥かしそうに笑いながら外へ出た。そして、一室へ入って水で体を洗い、静かに、傍かたわらの閤こざしきへ入って往ったが、それっきり出てこなかった。
女のくるのを待っていた万戸は、あまり遅いので不審を起して、探し探し閤の中へ往った。閤の中では愛卿が羅巾らきんを首にかけて縊くびれていた。
万戸は驚いて介抱したが蘇生しないので、綉褥しとねに包んで家の背後の圃中はたなかにある銀杏いちょうの樹の下へ埋めた。
間もなく張士誠は、江浙左丞相達織帖睦邇の許もとへ款かんを通じて、降服したいといってきたので、達丞相は参政周伯埼しゅうはくきなどを平江へやって、これを撫諭ぶゆさし、詔みことのりを以って士誠を大尉にした。
それがために楊参政は殺されて、麾下の軍士は四散した。大都の旅館にいた趙は、故郷へ引返すことに定めて帰ろうとしたところで、嘉興が戦乱の巷になりかけているということを聞いたので、帰ることもできずに家のことを心配していたが、そのうちに士誠が降り楊参政の軍が潰滅した。従って道も通じたので、はじめて舟に乗って帰り、太倉たいそうからあがって往った。
嘉興の城内は、到る処に破壊の痕を止めていた。見覚えのある第宅が無くなっていたり、第宅はあっても住んでいる人が変っていたりした。趙は自分の家のことを心配しながら走るようにして歩いて往った。
家は依然として立っていたが、入口の扉はとれて生え茂った雑草の中に横たわっており、調度のこわれなどが一面に散らかって、それに埃ほこりがうず高くつもっていた。脚下あしもとで黒い小さなものがちょろちょろと動くので、よく見るとそれは鼠であった。
荒廃した家の内からは、返事をする者もなければ、出てくる者もいなかった。趙は驚いて家の中を駈け廻ったが、母親の影も愛卿の影も、その他にも人の影という影は見えなかった。
趙は茫然として中堂の中に立っていた。庭の方で鳥の声がした。それは夕陽の射した庭の樹に一羽の鴞ふくろうがきて啼いているところであった。
淋しい夕暮がきた。趙は母親と愛卿は、楊参政の麾下の掠奪に逢って、どこかへ避難しているだろうと思いだした。彼は翌日知人を訪うて精くわしい容子を聞くことにして、そのあたりを掃除して一夜をそこで明かした。
朝になって趙は、嘉興の東門となった春波門を出て往った。そこには紅橋があった。趙はその側へ往ったところで見覚えのある老人に往き逢った。
「おい、爺じゃないか」
それはもと使っていた僕げなんであった。
「だ、旦那様じゃございませんか」
老人は飛びかかってきそうな容ふうをして言った。
「ああ、俺だよ」
趙は一刻も早く母親と愛卿のことが聞きたかった。
「爺や、お前に聞きたいが、家のお母さんと家内は、どこにいるだろう、お前は知らないのか」
「旦那様は、まだ御存じがないのですか」
「知らない、どうした、お母さんと家内は、どうしたというのだ」
趙はせき込んで言った。
「旦那様、えらいことが出来ております」
老人の眼に涙が湧いて見えた。
「どうした、早く言ってくれ」
「旦那様、びっくりなされちゃいけません、大奥様は御病気でお亡くなりになりますし、若奥様は苗軍びょうぐんの盗人ぬすびとのために、迫られて亡くなられました、なんとも申しあげようがございません」
趙は青い顔をして立ったままで何も言えなかった。
「旦那様、しっかりなすってくださいませ、大奥様が御病気になりますと、若奥様が夜も睡らないで御介抱なさいました、お亡くなりになってからも、若奥様がほとんどお一人で、お墓までおこしらえになりましたが、苗軍がやってきて、劉万戸という盗人が、若奥様を見染めて、迫りましたので、若奥様は閤こざしきへ入ってお亡くなりなさいました」
「そうか、俺が旅に出たばかりに、こんなことになった、俺が悪い、爺や俺は馬鹿者だ」
趙は老人を連れてその足で白苧村にある母親の墓へ往った。墓場には愛卿の手で植えた小松が美くしい緑葉を見せていた。
「これは若奥様のお植えになったものでございます」
老人はまた墓の盛り土へ指をさした。
「これも若奥様が御自身でお造りになりました」
趙は老人と家へ帰って、家の背後の圃中はたなかに立った銀杏の下へ往った。趙は愛卿の死骸を見たかった。
墓が発あばかれて、綉褥しとねに包まれた愛卿の死骸が露われた。趙は我を忘れてそれを開けてみた。
ただちょっと睡っているようにしか見えない生々なまなました死骸であった。趙はその死骸へ手をやって泣いたがそのまま気が遠くなってしまった。
趙は老人の介抱によってやっと我に還った。彼はそこで愛卿の死骸を家の中へ運んで、香湯こうゆで洗い、その姿にふさわしい華美な服を被きせて、棺に納め、それを母親の墓側へ持って往って葬った。
改葬が終ったところで、趙は墓へ向って言った。
「お前は聡明な女であった、凡人ではなかった、わしの心が判っているなら、もとの姿を一度見せておくれ」
趙は家へ帰っても銀杏の下へ往って、これと同じようなことを言ったが、これはその日ばかりでなしに、翌日もその翌日も、毎日のように白苧村の墓と銀杏の下へ往ってそれを言った。
十日近くにもなった頃であった。その晩は家のまわりに暗い闇が垂れさがって、四辺あたりがひっそりしていた。趙は一人中堂にいたが、退屈でしようがないので、いっそ寝ようかと思ったが、どうも寝就ねつかれそうもないので、そのまましかたなしにじっとしていた。と、どこからか泣声のような物声が聞えてきた。趙は不思議に思うてその方へ耳をやった。それは確かに咽むせび泣く泣声であった。
泣声はすぐ近くに聞えた。趙は何者の泣声だろうと思って、起って声のした方へ眼をやったが何も見えなかった。趙はこの時ふと思いだしたことがあった。
「だれ、愛愛じゃないのか、愛愛なら何故すぐきてくれない、愛愛じゃないのか」
趙はこう言ってまた透して見た。
「愛愛でございます、あなたのお言葉に従いましてまいりました」
それは耳の底にこびりついている愛卿の声であった。趙はその方へ眼をやった。人の歩いてくるような気配がして物の影がひらひらとしたが、やがて五足か六足かの前へ白い服を著た人の姿がぼんやりと浮んだ。面長な白い顔も見えた。それは生前そのままの愛卿の姿であったが、ただ首のまわりに黒い巾きれを巻いているだけが違っていた。
愛卿の霊は趙の方を見て拝おじぎをしたが、それが終ると悲しそうな声を出して歌いだした。それは沁園春しんえんしゅんの調にならってこしらえた自作の歌であった。
一別三年
一日三秋
君何ぞ帰らざる
記す尊姑そんこ老病ろうびょう
親みずから薬餌やくじを供す
塋けいを高くして埋葬し
親みずから麻衣まいを曳く
夜は燈花を卜ぼくし
晨あしたに喜鵲きじゃくを占う
雨梨花あめりかを打って昼扉ひるとを掩おおう
誰か知道しらん恩情永く隔へだたり
書信全く稀ならんとは
干戈かんか満目まんもく交こもごも揮ふるう
奈いずくんぞ命薄く時乖そむき
禍機かきを履ふんで鎖金しょうきん帳底ちょうていに向う
猿驚き鶴怨む
香羅巾下こうらきんか
玉と砕け花と飛ぶ
三貞を学ばんことを要せば
須すべからく一死を拆すつべし
旁人ぼうじんに是非を語らるることを免る
君相念いて算除さんじょせよ
画裏に崔徽さいきを見るに非ず
歌の中に啜すすり泣きが交って、詞ことばをなさないところがあった。趙も涙を流してそれを聞いていた。
歌の声は消えるように輟やんだ。趙は夢の覚めたようにして愛卿の側へ往った。
「おいで、お前にはいろいろ礼も言いたい、よくきてくれた」
趙の手と愛卿の手はもう絡みあった。二人は室の中へ入った。
「お前はお母さんのお世話をしてくれたうえに、わしのために節を守ってくれて、なんともお礼の言いようがない、わしは、今、更あらためて礼を言うよ」
「賤いやしい身分の者を、御面倒を見ていただきました、お母様は私がお見送りいたしましたが、思うことの万分の一もできないで、申しわけがありません、賊に迫られて自殺したのは幾分の御恩報じだと思いましたからであります、お礼をおっしゃられては恥かしゅうございます」
「いや、お礼を言う、それにしても、お前を賊に死なしたのは、残念で残念でたまらない、今、お前は冥界めいかいにおるから、お母さんのことも判ってるだろうが、お母さんは、今、どうしていらっしゃる」
「お母様は、罪のない体でしたから、もう人間に生れかえっております」
「お前は、何故、いつまでもそうしておる」
「私は、私の貞烈のために、無錫ぶしゃくの宋そうという家へ、男の子となって生れることになっておりますが、あなたに情縁が重うございますから、一度あなたにお眼にかかるまで、生れ出る月を延ばしております、が、もうお眼にかかりましたから、明日は往って生れます、もしあなたがこれまでの情誼をお忘れにならなければ、一度宋家へ往って、私を御覧になってくださいまし、笑ってその験しるしをお眼にかけます」
趙と愛卿の霊は、手を取りあって寝室へ往って歓会したが、楽しみは生前とすこしも変らなかった。
鶏の声が聞えた。
「私は、帰らなくてはなりません、これでお別れいたします」
愛卿の霊は泣きながら榻ねだいをおりた。趙も後から送って出た。
愛卿の霊は階をおりて三足ばかり往ったが、ふと涙に濡れている顔を此方へ見せた。
「これでいよいよお別れいたします、どうかお大事に」
趙も胸がいっぱいになって言おうと思うことが口に出なかった。
暁の光がうっすらと見えた。と、愛卿の霊は燈の消えるように見えなくなった。室の方を見ると有明の燈の光が消えかかっていた。
趙はその朝、旅装を調えて無錫へ往った。そして、宋という姓の家を尋ねたところがすぐ知れた。趙は半信半疑で往ってみた。妊娠してから二十ヶ月目に生れたという男の子がひいひい泣いていた。それは生まれ落ちるときから輟やめずに泣いているものであった。
趙は主人に逢って、自分のきた事情を話し、主人の承諾を得て産室へ入って往った。今まで泣いていた男の子は、趙を見るなり泣くことをやめてにっと笑った。
宋家ではその子に羅生らせいという名をつけた。趙はその日から宋家の親属しんぞくとなって、往来餽遺おうらいきい、音問を絶たなかった。
底本:「中国の怪談(一)」河出文庫、河出書房新社
1987(昭和62)年5月6日初版発行
底本の親本:「支那怪談全集」桃源社
1970(昭和45)年発行
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
入力:Hiroshi_O
校正:noriko saito
2004年12月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
藍微塵の衣服
田中貢太郎
これは東京の芝区にあった話である。芝区の某町に質屋があって、そこの女房が五歳いつつか六歳むっつになる女の子を残して病死したので、所天ていしゅは後妻を貰った。
後妻と云うのは、気質の従順な、何時いつも愉快そうな顔をしている女で、継子ままこに対しても真の母親のような愛情を見せたので、継子も非常に懐なついて、所天も安心することができた。
が、その後妻が、しばらくすると黙り込んで、あまり口数を利きかないようになり、その女を包んでいた花の咲きそうな温あたたかな雰囲気が無くなって、冷たい強こわばったものとなってしまった。
それに気の注ついたのは、質屋の親類の老人であった。老人は種々の経験からこれは所天が他に気をうつす者があって、女房をかまってやらないから、血の道が悪くなったものだと思った。で、老人はある日、後妻を己じぶんの家へ呼んで聞いてみた。
「どうもこの比ごろは、浮かない顔をしているが、どうしたかね」
「別にどうしたと云うこともありません」
「しかし、何かあるだろう、どうもお前さんは、この比ごろ浮かない顔をしている」
「別に何もないんですよ」
「あるだろう、無いことはない、私の考えでは、彼あれがお前さんをかまわないと思うが、そうじゃないかね」
「いえ、そんなことはありませんよ」
「なら何かね、云ってごらん、お前さんの力になってやるよ」
こうした会話がかわされた後で、後妻は蒼白あおじろい顔をあげて云った。
「私がこんなにしているのは、恐ろしいことがあるからですよ、夜寝ておりますと、仏壇のある方の室へやとこっちとの間の襖ふすまが開あいて、女の人が出て来てお辞儀をするから、もう恐ろしくって恐ろしくって、夜もおっちりと睡ねむったことはありませんが、所天うちに云うのも厭いやだから黙っております」
「どんな女だね」と、老人は聞いてみた。
「壮わかい姝きれいな女ですよ、藍微塵あいみじんの衣服きものを着て、黒襦子くろじゅすの帯を締め、頭髪かみは円髷まるまげに結ゆうております」
「何か云うかね」
「何も云わずに、白い痩やせた手をしとやかに突いて、私の方へ向いてお辞儀するのですよ」
老人はすぐ前妻ではないかと思ったが、それは口へは出さなかった。そして、所天ていしゅを呼びにやって所天を前に据すえて後妻の云ったことを話した。
「藍微塵の衣服きものを着ていたと云うが、何かお前に心当りがあるのか」
藍微塵の衣服きものは前妻が非常に好きで、何時いつも好んで着ていたのを知っている所天は、背筋が寒かった。
「……それは死んだ彼女あれが好きな衣服きものだったのですよ」
老人は頷うなずいてちょいと口をつぐんでいたが、
「なんの心残りがあるんだろう」と半ば独言ひとりごとのように云った。
「そうですとも、弔とむらいはあんなにしてあるし、何も不足はないはずだが」所天ていしゅはこう云った後あとで、傍にいる後妻のほうを見て、「小供はお前があんなに可愛がってくれるし、不足はないはずだ、もし、今度そんなことがあったら、俺が叱しかってやるから、俺を起してくれ」
その翌晩、所天と後妻は、女の子を中にして何時いつものように奥の八畳で寝ていた。そこは土蔵に隣となった室へやで、次に四畳半位の仏壇を置いた室があって、そのさきが縁側えんがわになり、それが土蔵の口に続いていた。
そのうちに後妻の睡ねむりが覚めた。後妻は怖こわごわ眼を開けて暗い中を見た。と、枕頭まくらもとから右横になった仏壇の間との隔へだての襖ふすまが何時いつものように開あいて、また、藍微塵あいみじんの衣服きものを着た女が幻燈に映し出されたようにはっきりと現れて、敷居の上あたりに坐って白い手を突きかけた。後妻はふと所天が己じぶんを起せと云った事を思い出したので、手を延ばして所天の肩を揺ゆすった。
所天が眼を開けて見ると、後妻が己を起しているのですぐそれを悟って首を擡もたげて見た。女はもうお辞儀をやっていた。
「おい、お前は小供をこんなに可愛がって貰ってながら、何の不足があって何時も何時もやってくるのだ」と、所天は叱るように云った、と、女は微かすかな声で云った。
「私はお礼にあがっております」
「そうか、そうか、しかしお前が来ると、これが恐がるからもう来るな」と所天ていしゅが云った。
それと同時に、女の姿は消えたが、それから二度と現れるようなことはなかった。
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第四巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
赤い花
田中貢太郎
明治十七八年と云えば自由民権運動の盛んな時で、新思潮に刺戟しげきせられた全国の青年は、暴戻ぼうれいな政府の圧迫にも屈せず、民権の伸張に奔走していた。その時分のことであった。
東京小石川こいしかわの某町に、葛西かさいと云って、もと幕臣であった富裕な家があって、当主の芳郎よしろうと云うのは仏蘭西フランスがえりの少壮民権家として、先輩から望みを嘱しょくされていた。微曇うすぐもりのした風の無い日であった。芳郎は己じぶんの家に沿うた坂路さかみちを登っていた。その附近の地所は皆葛西家の所有で、一面の雑木林ぞうきばやしであったが、数年前ぜんにその一部分を市へ寄附して坂路を開鑿かいさくしたものであった。芳郎はゆっくりとした足どりでその坂路を登りながら、その日、午後四時から井生村楼いぶむらろうに催される演説会の演説の腹稿ふっこうをこしらえていた。それは芳郎が平生いつもの癖で、熱烈火の如き民権論はこうしてなるのであった。
坂の右側には葛西家の新しくこしらえた土塀どべいがあり、左側には雑木ぞうきを伐きり開いた空地があって、それには竹垣が結ゆってあった。空地の中には四五本の梅の樹があって、それには白い花をつけていた。地べたの枯草の中からは春が萌もえていた。
場末の坂路さかみちは静かで淋しかった。芳郎よしろうはその時、ミルの著書の中にある文句を頭に浮べていたが、何なんかの拍子にふいと見ると、束髪そくはつに赤い花をさした令嬢風の女が己じぶんの前さきを歩いていた。壮わかい芳郎の眼はその花にひきつけられた。冬薔薇のような赤い活いきいきとした花は、鼠ねずみ色にぼかされた四辺あたりの物象の中にみょうにきわ立って見えた。
女もゆっくりと歩いていた。芳郎の足は知らず知らず早くなった。女は坂を登りつめて、平坦な路のむこうにその背後うしろ姿を消しかけた。芳郎はその姿を見失うまいと思って走るようにあがって往った。と、その跫音あしおとが聞えたのか女はちょと揮返ふりかえった。それは白い姝きれいな顔であった。芳郎ははしたない己の行為に気が注ついて立ちどまるように足を遅くした。
芳郎はまた女の美貌に眼をひかれた。どこの令嬢だろう、ああして一人歩いている処を見ると、どこかこの辺に邸やしきがあるだろう、それとすれば、どこの女むすめだろうか、と、彼はその辺あたりに立派な邸を持った豪家ごうかを考えて見たが、彼の知っている限りでは、そう云うような家はなかった。
女の姿は坂の上にかくれて往った。彼はまた急いで坂を登り切った。女の姿はもう見えなかった。坂の上の古い通路とおりは二条ふたすじになっていて、むこう側には杉の生垣いけがきでとり廻まわした寺の墓地があった。彼は右の方を見たり、左の方を見たりした。淋しい通路とおりには歩いている人もなかった。
通路とおりの右になった方は、真直まっすぐになって見渡されたが、左になった方はすぐ折れ曲がっていた。寺の本門ほんもんは左の方にあった。彼は左の方へ曲がって往って、門口かどぐちに大きな石地蔵のある寺の本門の前まで往ったが、とうとう女の姿は見つからなかった。彼はがっかりして引かえして来たが、その束髪そくはつにさした赤い花と、姝きれいな顔は、眼の前にちらちらとしてもう思想を纏まとめようとする気分がなくなっていた。
芳郎はその時二十五歳であった。両親ふたおやともとうに無くなって、他に兄弟と云うものもないので、親類の老人達は彼に結婚させようとして煩うるさく勧めたが、彼はそれに耳を傾けないし、また、彼に財産の多いのと名聞めいぶんがあるのとで、直接に近づいて来る女もあったが、彼はそれにも眼をやらずに、民権運動に熱中しているところであった。
芳郎のその日の演説は、甚はなはだ物たりない力の無い者であった。彼の演説を期待していた同志の者は大おおいに失望するとともに、中には彼があまりに運動に熱中した結果、健康を損ねたのではないかと心配する者もあった。
赤い花をさした女の姿は、芳郎の眼前めさきをはなれなかった。翌日、彼はまたその女に逢あえはしないかと思って、家の傍の坂をあがったりおりたりして、その辺をさまよい歩いたが女には逢わなかった。
その翌日は冷たい雨が降っていた。彼はまたその雨を冒おかして坂を上下したが、その日もとうとう見えなかった。
十日ばかりも彼はこうして女を尋ねたが、どうしても逢えなかった。で、やっと諦あきらめてしまったが、それでも赤い花は眼の前にあった。
一箇月ばかりして、彼はまた演説の腹案ふくあんをこしらえる必要が起ったので、平生いつものように散歩しながら思想を纏まとめるつもりで戸外そとへ出た。
その時はもう春も深くなって、土塀の上に見える邸内の桜は咲きかけていた。芳郎は坂路さかみちを登りながら、二十三年に発布になることになっている憲法のことを考えていた。そして、知らず識しらず坂を登って往って見るともなしにむこうの方を見た。と、束髪に赤い花をさした女の後姿が見えた。それは彼が探している女であった。彼は久しく逢わなかった恋人に逢あったような気になって、すたすたと走って往った。と、女は背後うしろを揮返ふりかえって白い姝きれいな顔を見せた。彼はまたはしたない己おのれの姿に気が注ついたのでちょっと立ちどまった。
女は坂を登ってむこうの方へ往った。芳郎はまた急ぎ足になって坂を登り切った。と、もう女の姿は見えなかった。彼は不審しながら上の路みちを右の方へ往ってみたが、そこにも女の姿はなかった。で、彼はまた左の方へも往ってみたが、とうとう見つけることができなかった。それでも諦あきらめられないので彼は終日その辺を歩いて、その日はとうとう演説にも往かなかった。
赤い花はまた鮮かな色をして芳郎の眼の前にあった。彼はもう何事も手につかないようになって、日日にちにちその辺をさまよい歩くようになったが、その時分からひどく健康が衰えて来たので、親類の者や葛西家に使われている者などが心配して、無理に勧めて彼を熱海あたみへ転地さした。
芳郎の往った家は相模屋さがみやと云う熱海では一流の温泉宿であった。彼はそこに滞在しながら心静かに養生ようじょうすることにしたが、赤い花の女のことが浮んで来ると、みょうに神経的になって夜も眠られなかった。
夏が過ぎて秋口になって来ると、やや彼の健康も回復して来た。彼は東京から見舞に来る同志と政治上の意見を闘わしたり、ちょっとした論文を書いて新聞に送るようになった。
明るい月が出て室へやの中に籠こもっているのも惜おしいような晩が来た。彼はふらりと宿を出て海岸へ往ってみた。月の光にぼかされた海は静かで、磯には有るか無いかの浪が、さ、さ、さ、と云う音をさしていた。
彼は沙すなの上に引きあげられた漁船の間を潜くぐって、魚見岬うおみがさきの方角のほうへ歩いて往ったが、何時いつの間にか倦あいて来たので引っかえしていると、二人の女伴おんなづれが岩の上に腰をかけて話しているのが見えた。そして、その傍を通りながら見ると、一人は令嬢で一人はお供ともの婢じょちゅうらしかった。二人は彼の跫音あしおとを聞きつけて云いあわせたように顔を向けたが、その令嬢の顔は芳郎の眼前めさきに残っている顔にそっくりであった。彼は驚いてその顔を見返したが、束髪そくはつには赤い花は見えなかった。
芳郎は二三歩往き過ぎてから立ちどまった。………もしや、彼かの女ではあるまいか、も一度見なおしてやろうと思って後もどりをしかけると、女伴はもう起たちあがっていた。月の光に浮き出たような二つの女の顔がこちらへ向いた。令嬢の顔ははじめに見たような顔ではなかったが、それでもどこかにちょと似た処があった。
女伴おんなづれは何か囁ささやきながら陸おかの方へあがって往った。芳郎はすぐ往ってしまわれるのが何となく惜おしいように思われたので、往くともなしに後あとから跟ついて往ったが、沈着な平生へいぜいの態度は失わなかった。
女伴は小さな漁師町の間を通って傾斜のある小路こみちを登って往った。芳郎は女伴に怪しまれないようにと思って、よほど距離を置いて歩いた。女伴は時どき笑い声をたてたが背後うしろは向かなかった。
女伴はやがて別荘風の二階家の見える家の中へ入って往った。芳郎は静かにその門口かどぐちに往って月の光に晒さらされた表札ひょうさつに注意した。表札には杉浦と云う二字が書いてあった。……いずれ東京から来ている人だろうが、どうした人だろう、そのうちに何人だれかに聞いてみようと思って、彼は相模屋の方へ帰って往った。赤い花の女の影のようにその女のことが軽く頭にあった。
その翌日になって芳郎の門下同様にしている新聞記者の一人が、彼に論文の依頼かたがた遊びに来た。芳郎はそれに酒などを出して対手あいてになっていたが、ふと杉浦のことを思い出して聞いてみた。
「君は物知りだが、このすぐ前さきに、杉浦と云う別荘があるが、あれはどうした家か知らないかね」
「あ、杉浦、杉浦なら知ってますよ、ありゃあ、有名な御用商人じゃありませんか、きっとそれでしょう」
「そうかも判らないね、昨夜ゆうべ、海岸へ散歩に往ってて、そこの女むすめらしい女おんなを見たよ」
「じゃ、たしかにその杉浦だ、佳よい女おんなでしょう、お気に入ったら、お貰いになったら如何いかがです」
「しかし、ただちょっと見かけただけだよ」
「それでもお目にとまったら、好いじゃありませんか」
「そりゃ、交際をしてみて、先方の気質が好いとなりゃ、貰わないにも限らないが、君は知ってるかね」
「好く知ってます、二人で遊びに往ってみようじゃありませんか」
「主人はこっちにいるだろうか」
「細君さいくんの体が弱いから、この一二年、女むすめをつけて、こっちに置いてありますから、しょっちゅうこっちへ来ております」
新聞記者は芳郎の詞ことばの意味が判ったので、その夜一人で杉浦の別荘へ往って、主人にそれとなく芳郎のことを話した。主人は非常に喜んで翌日自身で相模屋へ来て、芳郎に遊びに来るようにと云って帰ったので、芳郎はその翌日杉浦の別荘へ往った。
杉浦の方では主人と海岸で見た女むすめが出て、芳郎の対手あいてになった。芳郎と主人は碁を打った。
その日から芳郎は杉浦家と接近しはじめた。それとともに女むすめとも親しくなって往った。女むすめの名は喜美代と云った。
秋の終りになると、芳郎と喜美代との間に結婚話が持ちあがって、その約束が出来たところで、芳郎が神経痛のようになったので、その期日が延びることになった。そして、十二月になって芳郎の病気が癒なおると、今度は喜美代の母が病気になったので、二人の結婚はまた春と云うことになった。
芳郎はその間一二度東京へ帰って往ったが、すぐ熱海へ来て相模屋にいた。そして、三月になって熱海の梅が散る時分じぶんになって、喜美代の母親の病気が癒ったので、その間に結婚式をあげようと云うことになった。ところで、その当時政府の民党圧迫がその極に達して、運動ができないようになっていたので、結婚式も杉浦の別荘であげ、芳郎は当分そこで暮らすことになった。
そして期日を定めて、その期日ももう三日の後のちに迫った。芳郎は朝から東京の邸やしきから来ている使用人と結婚の準備に関する相談をしたが、その夜枕に就ついたところで怪しい夢を見た。彼は演説の腹案をこしらえるために、邸の傍の坂路さかみちをあがっていたのであった。そして、前のほうを見ると、赤い花をさした己じぶんが去年から探している女が歩いていた。で、今日こそどうしても見失わないぞと思って走って往ってみると、その日は女は男の来るのを待っているように揮返ふりかえって立っていた。芳郎が近寄ると女はにっと笑って、
「貴郎あなたは私と結婚なさるはずじゃありませんか」
と、束髪にさした赤い花を抜いて彼の手に握らした。花は陽ひの光を握ったようにほのかな温あたたかみがあった。
翌日になると芳郎は東京へ帰ると云いだした。使用人は驚いて止めたがどうしても聞かずに帰って往った。
そして、小石川の邸へ帰った芳郎は、その翌朝よくちょう散歩すると云って家を出たが、間もなく死体となって坂路の登り口の処に斃たおれていた。それを通行人が見つけて邸へ知らしたので、医師も駈かけつけて来たが死因は不明であった。
芳郎の変死の噂が伝わってから、芳郎の父の変死したことも知れて来た。
「あすこの家には、何か大きな祟たたりがあるだろう」
「なんの祟りだ」
「先代もやっぱり、ああして、ただ斃たおれて死んでたと云うことだ」
「よっぽど因縁のある家と見えるぞ、なんだろう」
附近の人びとがこう云って噂をしているところへ、一人の老人が旅から来た。それはもとこの辺に生れたもので、京浜地方を流れ渡っていて乞食こじきのような風をして帰って来たものであった。
「そんじゃ、お前さんは、あすこの葛西さんを知ってるだろう」と、老人の遠縁にあたる男が聞いた。
「お旗下はたもとの葛西さんか、知ってるとも、私なんかは、あすこの構かまえ内うちの林やぶん中へ入って、雉きじや、兎うさぎをとったもんだ」
「そんじゃちょうど好い、聞きたいことがあるが、あすこの家は、昔から何か変なことがある家じゃないかね」
「ああ、そう云やあ、葛西の大旦那は、裏の林やぶの中で、理わけの判らない死方しにかたをしてたよ」
「大旦那と云やあ、今の旦那のお祖父じいさんだね、じゃ三代、変な死方をしたと云うのだね、こりゃ、いよいよただごとじゃないよ」
「すると、大旦那の息子も、その孫も不思議な死方をしたと云うかね」
「何かお前さんに思い当ることはないかね」
「そう、他に思い当ることはないが、一つ怪しいことがあるんだ、今、乃公おれがあの林やぶで雉きじや兎うさぎをとったと云ったね、その時分じゃ、ある時、林の中へ往ってみると、昨日きのうまでなかった処に、土を掘りかえして、物を埋めたような処ができて、そのまわりの落葉へ生なまなました血が滴たれていたがね、それから二三年して、大旦那が死んだとき、人に聞くと、どうもそのあたりらしかったよ、どうも、乃公は、あの血が怪しいと思ってる」
遠縁の男は初めて謎が解けたと云うような顔をした。
「じゃ、お爺さんは、その血のあったあたりを覚えてるかね」
「もう御一新前ごいっしんぜんのことじゃで、はっきり覚えないが、方角位けんとうぐらいはつくだろうよ」
遠縁の者はその老人を伴つれて葛西の邸やしきの傍へ往くと、老人はそこここと方角ほうがくを考えていて、坂路さかみちの登りぐちへ往って、
「このあたりだ」
と云った。そこは芳郎の変死していた処であった。
底本:「日本怪談大全 第一巻 女怪の館」国書刊行会
1995(平成7)年7月10日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第二巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年3月8日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
赤い土の壺
田中貢太郎
永禄えいろく四年の夏のことであった。夕陽の落ちたばかりの長良川ながらがわの磧かわらへ四人伴づれの鵜飼うかいが出て来たが、そのうちの二人は二羽ずつの鵜を左右の手端てさきにとまらし、後あとの二人のうちの一人は艪ろを肩にして、それに徳利とくりや椀わんなどを入れた魚籃びくを掛け、一人は莚包むしろづつみを右の小脇こわきに抱え、左の小脇に焼明たいまつの束を抱えていた。皆同じように襤褸襦袢ぼろじゅばんを一枚着て腰簔こしみのをつけていたが、どこか体のこなしにきりっとしたところがあって、ぬらくらした土地の漁師のようでなかった。
そこは長良川の西岸で、東岸には稲葉山いなばやまが黄昏ゆうぐれの暗い影を曳ひいてそそり立っていたが、その頂いただきの城櫓しろやぐらの白壁には、夕陽の光がちらちらと動いていた。長良川の水はそのあたりで東岸に迫って流れ、西岸には広びろとした磧を見せていた。四人の鵜飼のうちで鵜を持ったほうの一人は、四十前後の痩やせぎすな男で、一人は三十五六の角顔かくがおの体のがっしりした男であった。そして、莚包と焼明を持っているのは、三十前後の背の高い鋭い眼まなこをした男で、艪ろを持っているのは、五十前後の背のずんぐりした白髪しらがの目だつ男であった。四人は昼の暑さのために葉を巻いていた川柳かわやなぎがだらりと葉を延ばして、ひと呼吸いきつこうとでもしているように思われる処を通って、下手しもての方へ往った。暑い陽ひを吸うていた磧かわらの沙すなは鬼魅きみ悪くほかほかしていた。その時莚包むしろづつみと焼明たいまつを持って背の高い男が、鵜うを持った角顔の男のほうを見て、
「鮎あゆを獲とりたいものじゃが」
と云った。すると角顔の男は前岸ぜんがんの樹木の茂みの方をちらと見て、
「獲れるとも、この鵜さえうまく使えば」
と、云って顔で笑った。その拍子に右の手にとまった鵜が飛びたつように羽ばたきをした。莚包と焼明を持った背の高い男も前岸の方へちらと眼をやって、
「そうじゃ、鵜さえうまく使えば、鮎は獲れるに定きまっておる、鵜をうまく使うがかんじんじゃ」
と、これも顔で笑った。前岸の樹木の間には黒い大きな瓦屋根が微かすかに黒く見えていた。それは日蓮宗法国寺ほうこくじに属する法華寺ほっけじの別院であった。他の二人の眼もちらとそれに往った。
本流から岐わかれた一条ひとすじの流れが斜ななめに来て磧かわらの裾すそで岸の竹藪たけやぶに迫っていたが、そこには二三艘そうの小舟が飛とびとびに繋つないであった。四人はその小舟の方へ往った。莚包と焼明を持った背の高い男は、また鵜を持った角顔の男の方を見て、
「寺へ入って和尚おしょうのような真似まねをしておるが、あの痴漢しれもののことじゃ、どんな用心をしておるかも判らん」
と云いかけたところで、艪ろを持っていた男が遮さえぎって、
「鮎の用心なら知れたものじゃ、鮎の話は、まあ、舟へ乗ってからにしよう」
と云った。それを聞くと莚包むしろづつみと焼明たいまつを持った背の高い男は、首を縮すくめるようにして口をつぐんでしまった。そして、一行は無言になって磧かわらの裾すそへ往った。
そこにはもう他に一組の鵜飼うかいがいて、がやがやと云いながら一艘そうの舟をだしているところであった。四方あたりはもうすっかりと暮れていた。
「もう舟を出している者がある、後おくれないように出そう」
艪ろを持っていた男がそう云い云い艪を舟の中へ入れた。すると莚包と焼明を持った男が、その手荷物を舟の中へ入れて、
「それでは舟を出そう」
と、云って竹藪の竹の根本を縛ってある縄のほうへ往った。底の浅い川舟は、やがてその底をざらざらと小石に当てながら流れに浮んだ。
星がまばらに見えだした。莚包と焼明を持っていた背の高い男の点つけた焼明の火が舳へさきにとろとろと燃えだした。小舟は本流へ入って法華寺の別院の前を上流の方へ向っていた。
焼明の火は川のそこここに燃えだした。もう鵜飼がはじまったのであった。彼かの鵜飼の一行も鵜を水に入れた。角顔の体のがっしりした男が舳へさきの鵜匠うじょうになり、痩やせぎすな男が中の鵜匠になり、背の高い眼の鋭い男が篙工さおとりとなり、背のずんぐりした白髪しらがの眼立っていた男が舟乗ふなのりとなって艪ろを漕こいでいた。二人の鵜匠にあやつられている鵜は、水の中に潜もぐっては浮きあがり、浮きあがっては潜って魚うおを獲とった。鵜の口を逃れた魚はきらきらと腹をかえして、中には飛ぶのもあった。そして、鵜が四五尾ひきの魚を喉のどに入れたと思う比ころを見はからって、鵜匠は手縄てなわを曳ひいて舟に曳き寄せ、ぐいとその喉を絞って魚うおを執とるのであった。魚を吐かされてまた魚を覘ねらって往く鵜うの眼は青く澄んでいた。
五六艘そうの鵜飼舟が云いあわしたように一列になった。舟乗りとなっている男は大きな声で云った。
「もうよかろう、それ位ありゃ、肴さかなにゃ十分じゃ、いいかげんに、無益むえきな殺生せっしょうはやめようじゃないか」
すると篙工さおとりとなっていた背の高い男が云った。
「そうじゃ、そうじゃ、無益な殺生はやめよう、やめて早う一杯やろう」
舳へさきの鵜匠うじょうはちょとふり返って中の鵜匠の顔を見て、
「そうじゃなあ、これ位ありゃ、肴は十分ある」
と云った。中の鵜匠はすぐ応じた。
「やめてもよかろう、やめて別院の下の涼すずしいところへ往って、一杯やるとしょうか」
舳の鵜匠はまた云った。
「よかろう、別院の下なら涼しかろう」
二人の鵜匠は手縄を曳ひいて鵜を舟にあげた。労役ろうえきを終った鵜は嬉しそうにそれぞれ羽ばたきをして、大きな喉のどを川風にふくらました。
「それでは別院の下へ往くとしょうか」
舟乗りとなっている男はそう云って舟の方向をぐるりとかえ、別院の方へ向けた。
「この世智辛せちがらい世の中に、皆、いい気なものじゃ」
右隣の舟から笑う声が舟乗りとなっている男の耳にはいった。
「隣の舟で笑っている」
流れに随したがって下る舟は早かった。舟はみるみる別院の下へ往った。そこは断崖になって樹木の根が処どころに垂れていた。舟はその断崖の下へ流れかかるように寄って往った。
「磧かわらなら焼鮎やきあゆができるが、ここじゃ、膾なますより他にはできない、膾でやろう」
「それでは料理をしようか」
舟の火は何時いつの間にか消えてしまった。それと共に舟の中もしんとなったが、しばらくして小さな声が起った。
「これで門出かどでの杯さかずきはすんだ、出かけよう、油断して痴漢しれものを討うちもらすな」
それは舟乗りとなっていた男の声であった。舟の中ではもそもそと物の気配がしはじめたが、やがてひっそりとなった。
稲葉山の城主斎藤義竜さいとうよしたつは、法華寺の別院で涼りょうをとっていた。小肥満こぶとりのした体を脇息きょうそくにもたして、わざと燈ひを遠くの方へ置きながら、二人の少女に後うしろから煽あおがし、庭の樹木の間から見える鵜飼うかいの火を見るともなしに見ているところであった。
義竜は弘治こうじ二年の春、庶腹しょふくの兄弟喜平次きへいじ、孫四郎まごしろうの二人を殺し、続いて父道三どうさんと鷺山さぎやまに戦たたこうて父を滅ほろぼしてからは、美濃みのの守護として得意の絶頂に立っていたが、夏の間は水浴を一日も欠かすことができないので、この数年来、夏が来ると密ひそかにこの別院に隠れて、冷たい清水の湧わく庭前ていぜんの池に水浴するのであった。
「小萩こはぎは来て肩を打て」
義竜がちょと体をずらして云ったので、左の後にいた少女が団扇うちわを置いて、
「は」
と、云って起たちながら、そのまま傍へ寄って小さな拳こぶしを右の肩端かたさきへ持って往った。と、そのとき微かすかな物の気配がした。義竜が不思議に思って顔をあげた時、庭前ていぜんにちらちらと人影が動いた。
「何者だ」
同時に縁側にどかどかとあがった者があった。それはかの鵜飼うかいの四人であった。皆さっきのままのなりで、手に手に白刃はくじんを持っていた。
「悪逆無道あくぎゃくむどうの親殺おやごろしを討ちとりにまいった者じゃ、道家孫八郎どうけまごはちろうの伜せがれ孫太郎まごたろうでござる」
それは背の高い眼の鋭い男であった。
「拙者せっしゃは長井与右衛門ながいよえもんでござる」
それは痩やせぎすな男であった。
「篠山七五郎しのやましちごろう」
それは角顔の男であった。
「拙者は竹腰藤九郎たけのこしとうくろうでござる、お首しるしを頂戴ちょうだいして、先君せんくん道三入道殿にゅうどうどのの修羅しゅらの妄執もうしゅうを晴らす存念でござる」
それは背のずんぐりした白髪しらがの眼だった男であった。皆道三の臣しんで悪逆無道の義竜を殺しに来たところであった。皆きっさきを集めて躍おどりかかろうとした。二人の少女は叫んで逃げて往った。と、義竜の姿が忽然こつぜんと消えて、怪しい白刃はくじんが室へやの中に電光のようにきらきらと閃ひらめくと共に、長井と篠山がばたばたと斃たおれた。竹腰は驚いて横に刀を払ったが、払った拍子に己じぶんの刀が眼に見えない金属に触れてかちりと鳴った。それと同時に室の中に銀色の眼をきろきろと光らした一疋ぴきの大きな蟇がまが見えて、それがぴょんぴょんと飛んで縁側から飛びおり、暗い庭前ていぜんの池の中へどぼんと云う重い音をさして飛び込んだ。
「や」
竹腰が怪しい蟇に注意の眼を向けた時、次の室に詰めていた義竜の近侍きんじが十人ばかり、ばらばらと飛び込んで来た。道家と竹腰は近侍の中にとり込められそうになった。
「道家、時節を待とう」
竹腰はそう云い云い己に向って来た壮わかい近侍の一人を斬きり斃たおして、ひらりと庭に飛びおり、池の傍から崖の木立の方へ逃げて姿を消した。
「それ逃すな」
道家も二人の近侍と斬り結んでいた刀を不意に引いて庭に逃げおり、崖の端はしに往くやいなや、
「えい」
と、云う懸声と共に暗い川の中へ身を躍おどらした。
藪やぶだたみの中にある小さな祠ほこらの前に竹腰と道家が姿をあらわした。竹腰は木の根に縋すがって舟をおり、河の中に飛び込んだ道家を救いあげて、二人で舟を下流にやり、それからあがってきたところであった。
「これからどこへ身を隠そう」
「尾州びしゅうへ往いって、織田殿に身を寄せてもよいが」
二人は身のふり方に就ついて相談しはじめた。竹たけの葉越はごしには二つ三つの星が淋しそうにまたたいていた。
「は、は、は、は、は」
腹の底をさらけだしたような笑い声が鼻の前さきで起った。二人はびっくりして眼を睜みはった。そこにはよぼよぼした老人の姿があった。老人は己じぶんの背たけよりも長い杖つえにすがっていた。
「魔者を討うちもらしたか、あれは、お前さん達の手にはちょと合わないよ、眼に見えない電光いなずまが閃ひらめいて、二人は殺されてしまったな、かあいそうに、だが、銀色の眼のきろきろ光る蟇がまは見たろうな」
と、云って老人はまた笑って、
「しかし、魔者は何時いつまでも増長することはできない、月に暈かさがかかって、北斗ほくとの七星しちせいに白蛇はくじゃのような光がかかったのを見たら、翌朝、陽ひの出ないうちにここへ来るがよい、きっと思いをとげさしてやる」
道家と竹腰は思わず地べたにつッぷした。
「は」
「は」
「しかし、竹腰には縁がない、道家一人が来るがよかろう」
「は」
「は」
二人は暫しばらくつッぷしていたが、それっきり老人の声がしないので、顔をあげてみるともうその姿はなかった。
竹腰と道家はそこから己じぶんの隠かくれ家がに帰って、不思議な老人に教えられた時機の来るのを待っていた。二人はその間の生計たつきに野へ出て獣けものを狩かっていた。
その日も二人は弓を持って朝から出て、広い野の中をあちらこちらとあさっていたが、夕方、一匹の鹿を見つけたので、それを追っかけて往ったが、そのうちに鹿は逃げてしまって、どこへ往ったのか判らなくなった。
気が注ついてみると道家は己一人になっていて、竹腰の姿は見えなかった。彼はもと来た径みちと思われる林の下を引返して、
「竹腰殿、竹腰殿」
と、声をあげて呼んでみたが、林の枝葉えだはを吹く風の音ばかりで人声ひとごえはしなかった。そして、幾等いくら呼んでも返事がないので、隠れ家へ帰ろうと思って呼ぶことをよして歩いた。
林の下は暗かった。道家は早く林の下を出ようと思って歩いたが、朽くち落ちた下枝したえだが重なっていて足をとるので早くは歩けなかった。そして、やっとの思いで林を出てみると、広い草原くさはらのむこうに円い真紅まっかな月が出ていた。
月を見ると道家は、すぐ老人の詞ことばを思いだして暈かさに注意したが、うっすらした靄もやはあったが暈はなかった。道家はまたその草原くさはらの中を歩いた。草原には荊棘いばらが閉じ、雑木ぞうきの枝が横よこたわっていて歩けなかった。
道家はひどく疲労を感じて来た。腰の皮籠かわかごには用意の獣けだものの乾肉ほしにくがあるので空腹は気にしなかった。道家はどこか祠ほこらでもあれば一と眠りして帰ろうと思いだした。彼は眠れるような場所はないかと思って注意しいしい歩いた。
草の中から流れ出た小さな清水の流れがあった。喉のどのかわいている道家はいきなり蹲しゃがんで流れに口をつけた。そして、思うさま飲んで顔をあげたところで、すぐ眼のまえの樹木の陰に一軒の小家こやがあって、そこから焚火たきびの光がもれていた。道家はひどく懐なつかしいのでそのほうへ歩いて往った。彼はべつにその家の中へ泊めてもらおうとは思わなかったが。
一人の老婆が炉いろりの側そばへ坐って炉にかけた鍋の下を焚たいていた。そして、その老婆の後うしろの方には顔の白い一人の女が坐っていた。
「そつじながらお尋ねする、拙者せっしゃは猟に往って路みちに迷った者じゃが、ここは何と云う処じゃ」
道家が声をかけると老婆は顔をあげた。
「それはさぞ、御難儀ごなんぎでございましょう、ここはかがみと云う処でございます、むさくろしい処でおかまいなければ、野の中の一軒家で、夜は涼しゅうございます、お泊りになってくださいませ」
「それでは休ましてもらいたい、食物たべものは持参しておる」
「どうぞお入りくださいませ」
「しからば、一時とき休ましてもらおう」
道家は土間へ入って草鞋わらじを脱ぎ、弓と矢筒やづつを持って脊せをかがめるようにして、老婆の傍の莚むしろの上に坐った。
「それでは、今、お粥かゆをさしあげますから、次の室へやでお休みくださいませ、お道みち、お伴つれ申せ」
老婆は後うしろにいた女に云った。
「いや、食物たべものは持っておる、どうか一と休みさしてもらいたい」
道家は立ったままで女の案内を待っていた。女は起たって恥かしそうにして、
「それでは」
と云って、見つけに垂れた莚をまくった。そこにはほっかりした燈あかりのある室へやがあった。道家はやはり脊をかがめるようにしてその室へ入った。
「そこに枕もございますから、御ごゆっくりお休みなさいませ」
と、云って女は莚をおろした。ほんのりした匂においが室の中にただようた。
「はからずご厄介やっかいに……」
道家は先ず矢と矢筒を壁に立てかけ、それから腰の刀をとって坐った。その室の一方は窓になって月が射さしていた。燈ひと思ったのはその月の光であった。道家はそこで腰から皮籠かごを解といて、その中の乾肉ほしにくを執とって喫くい、それが終ると傍かたわらの木の根の枕を引寄せて寝たが、疲労しているのですぐ眠ってしまった。
そして、眠っているうちに何か枕頭まくらもとで物の気配がするので、ふと気が注ついて眼をうすめに開けてみた。道家は右枕みぎまくらになって寝ていた。大きな蟇がまのようなものがこちら向きに坐って、口をぱくりと開けて眼をぎろぎろとさしているところであった。道家ははっとした。彼は枕頭まくらもとにおいてある刀に手をかけるなり、飛び起きざまに切りつけた。と、大きな地響のような音がした。彼はそのまま一方の窓から飛び出て走った。
雑木ぞうきに突きあたり草の根に足を執とられたりして、しばらく走ったが、べつに追って来る者もないようであるから、立ちどまって後うしろをふりかえった。そこは見覚えのある村の径こみちであった。道家はほっとしてやるともなしに眼を月にやった。西に落ちかけた月の周囲まわりにぼうとした暈かさがかかっていた。
「や」
道家は気が注つくと共に北の空に眼をやった。雲の間になった北斗の七星に白気はっきのようなものがうねうねとかかっていた。道家は刀を鞘さやに収めて立った。
道家は隠れ家に帰らずにそのまま川の堤つつみの竹藪たけやぶの中へ往って、彼かの祠ほこらの前で夜よの明けるのを待った。髯ひげの白いよぼよぼした老人がどこから来るともなしに来て道家の前に立った。
「来たか、昨夜ゆうべお前が魔者の呪のろいを斬きり払ったから、もう通力つうりきを失うしのうた、これを持って往って、見つけたなら、蓋ふたを開けろ、それまでは蓋を開けてはならんぞ」
老人の左の手には小さな赤い土の壺があった。
「今日の丑うしの刻こく、あの寺の正門からずかずか入って往け、それにはここの祠の中を開けると、お前の着て往く物がある、それ、これを持って往け」
老人は壺をさしだした。道家はうやうやしくそれを受けた。
そして、眼をやると老人はもういなかった。そこで祠ほこらの扉を開けた。中には袈裟けさ、頭陀袋ずだぶくろ、笠かさ、手甲てこう、脚絆きゃはんの一切が入っていた。道家は老人の詞ことばに従ってそれを着て旅僧たびそうの姿になり、丑うしの刻こくになって法華寺の別院へ往った。
別院の門のうちには十人ばかりの護衛の武士がいたが咎とがめなかった。彼はずんずん左の厨くりの方へ往って、書院と厨の間になった植込の中へ入り、そこから裏庭の方へ往くと二人の武士が床几しょうぎに眠っていた。庭には彼かの池があって何時いつか見た蟇がまが一疋ぴき浮んでいた。道家はここぞと思って手にしていた壺の蓋ふたをとった。と、壺の口から煙のようにひらひらと閃ひらめいて出た白い蛇が、みるみる池の上に浮んで彼かの蟇に迫り、蟇が水の中に潜もぐらない中うちに巻いてしまった。
「殿様が大変じゃ」
書院の方では口ぐちに騒ぎだした。二三日熱病をわずらっていた義竜よしたつは、その時急にもがきだしてそのまま死んで往った。「織田軍記」には義竜のことを記しるして、「今はあらそふ者もなければ、義竜自ら濃州のうしゅうの守護となつて、悪人ながら威勢ありしに、ためしすくなき大罪人だいざいにんのむくいにや、幾程なく永禄四年に義竜たちまち悪病を煩わずらひ、死去しけり」と、云ってある。
底本:「日本怪談大全 第一巻 女怪の館」国書刊行会
1995(平成7)年7月10日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第一巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年3月8日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
赤い牛
田中貢太郎
長野県の上田市にある上田城は、名将真田幸村の居城として知られているが、その上田城の濠の水を明治初年になって、替え乾ほそうと云う事になった。そして、いよいよその日になると、附近の人びとは好奇心に駆られて、早朝から手伝いやら見物やらで押しかけて来た。
その日は朝からからっと晴れた好天気で、気候も初夏らしく温い日だったので、人びとはお祭り騒ぎで替え乾ぼしをはじめた。そのために作業はずんずんはかどって、水が減るに従って大きな鯉が躍りあがったり、大鯰が浮いたりして、濠の周囲まわりには至るところに喊声かんせいがあがった。
その日私の父も、面白半分その手伝いに往っていたが、正午近くなって濠の水が膝の下ぐらいに減った時、父の周囲にいた人びとが異様な声を立てた。見ると父のいる処から三間げんばかり前の方に当って、一ひとところ水が一間半ばかりの円を描いて渦を巻いていた。
(何だろう)
と、父が思った瞬間、物凄い水音を立てながら、その渦が盛りあがると思う間もなく、全身真紅の色をした動物が半身を露わした。それは、額に太い二本の角のある大きな牛であった。人びとは驚いて逃げ出そうとしたが、牛の方でも驚いたのか、濠から駆けあがって、千曲ちくま川へ飛びこみ、箭やのようにその流れを泳ぎ渡って、小牧山を乗り越え、それから須川の池へ身を隠してしまった。
今でもその替え乾の時に、現場へ往っていて赤い牛を見たという人がある。私も少年の時によくその話を聞かされたものだが、どうしても信じることができないので、作り話だろうと云って父に叱られたことがある。私の父はいいかげんな事を云う人でないから、若もしかすると河馬かばのような水棲動物であったかも判らないと思うが、それにしても河馬が日本にいるという話を聞かないので、どうにも解釈がつきかねる。(植田某氏談)
底本:「伝奇ノ匣6 田中貢太郎日本怪談事典」学研M文庫、学習研究社
2003(平成15)年10月22日初版発行
底本の親本:「新怪談集 実話篇」改造社
1938(昭和13)年
入力:Hiroshi_O
校正:noriko saito
2010年10月20日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
あかんぼの首
田中貢太郎
赤インキの滲んだやうな暑い陽の光があつた。陽の光は谷の下の人家の塀越しに見える若葉を照らしてゐた。若葉の中には塩竈桜か何かであらう、散り残りの白いあざれたやうな花弁があつて、それが青味だつて吹いて来る風に胡蝶のやうにちらちらと散つた。花弁は崖の上の蕗の葉の上にも落ちた。
電車の乗換場の土雨はぬる湯で拭いた顔や襟にまだ滲んでゐるやうな気がした。電車の交叉点の一方は赤煉瓦塀の高い工場になつてゐた。塀に沿うて街路樹の鈴懸の若葉があつた。若葉の枝は狂人のやうに風のために踊つてゐた。黄色に見える土雨はその四辺に佗しい色彩を施してゐた。京子は正午前に行つて来た病院の往きかへりの路のことを浮べてゐた。
京子は重い頭を左枕にして寝てゐた。薄青い電燈の光が掻巻にくるまつた彼女の姿をげんなりと照してゐた。床の中は生暖かで、ほこりのある体をぢつと一所に置いてゐると、その個所が熱ざして来るやうな気持になつた。彼は足や手の先を冷たい所へ所へとやつた。冷たい所へとやつた刹那の感触は心好い嬉しいものであつた。彼はふと夕飯の時に夫の唇から洩れた同情のある言葉を思ひ出した。
「来月の十日頃が来たなら、学校の方も休みになるから、海岸の方へ伴れて行つてやらう、一ヶ月位も呑気にしてをれば癒るだらう、」
砂丘に植ゑた小松の枝振りや、砂の細かな磯際、藍色をした水の色と空の色とが溶け合つた果てしもない海の容などが思ひ出された。それは四五年前結婚した年に、二週間ばかり行つてゐた海岸の印象であつた。ぎらぎら光る陽の光は厭はしかつたが、夕方に小松の葉を動かした風の爽やかさは忘れられなかつた。京子の神経にその風が吹いてゐた。彼は連れていつて貰ふことが出来るものなら、直ぐ明日にでも行きたいと思つた。そして海岸へ行つてその風に吹かれようものなら、斯うした暗いじめじめしたやうな気持はいつぺんになくなつて、体も軽くなるだらうと思つた。彼はそのことを夫に話したいと思つた。そしてそれがはつきりした形になりかけて来ると、もう話して見ようとする気もなくなつた。二階の狭い書斎で海軍省方面の翻訳をしてゐる夫の所へ行くには、きつい梯子段を上がらねばならんし、夫を傍へ来て貰はうとすれば手を鳴らして女中を呼ばねばならなかつた。彼にはそれもこれも憶劫で仕方がなかつた。
京子は右枕に寝返りした。新しい冷たさが手足に心好かつた。彼は一昨年の春に流産をして以来何処といつて定まつた所はないが、始終頭痛がしたり軽い眩暈を感じたり、その上体がだるくて熱ざした。一年ばかり無くなつてゐた月の物も、昨年からあるにはありだしたが、平生も不順勝で時とすると妊娠でないかと思はれるやうなこともあつた。その日も二三日前からだらけてゐた体が、前晩あたりからえらい熱病にでも罹つたやうに、熱ざしてほてるのでかかり付けの医師に行つて来たところであつた。
「嘔気を覚えるやうなことはありませんか、」
医師は妊娠の下地ではないかと疑をおいたらしかつた。月の五六日にあるべき筈の月の物がその時も十日ほど延びてゐた。
勝手の方で瀬戸物を落したやうな音がした。女中が又何かそさうをしたのであらうと思つた。指の先が棒のやうな感じのする赤黒い静脈の蚯蚓のやうに浮あがつた女中の手が其所にあつた。風かそれとも、遠くの方を行く汽車の音とでも云ふやうな、平生も耳に這入つて来る雑音が聞えて来た暗いもやもやした憂鬱がこの雑音に絡らみついてしまつた。彼はだるい体の向を又変へた。
心好い濁のない風が吹いた。と、青い松の葉の一つづつがその風に動いた。その松の葉へは月が射してゐた。黒い松の幹が飛び飛びに見えた。足許にはメリケン粉のやうに白い踏んでも音のしない砂があつた。時々波の音が思ひだしたやうにざあざあと聞えた。京子は無心になつて何も考へないで足の向く儘に歩いて行つた。
ちひさな砂丘をだらだらとおりると、ちひさな川が流れてゐて板橋が渡してあつた。橋の向ふにはぼんやり月の光の射した松林の丘があつて、其所には二三軒の別荘風の家が見えてゐた。そろそろと板橋を渡つた京子は、疲びれて休みたくなつたので、とつ着きの家の方へと行つた。家の前には真砂を敷いたかなり広い路が通じてゐた。彼はその路を横切つて門口へと行つた。門の左右には竹の菱垣をして、船板で拵へた門の扉を閉めてあつた。
門の扉は京子を遮らなかつた。彼は自分の家へでも這入つて行くやうに這入つてしまつた。閉めてあつた玄関の戸も彼女を拒まなかつた。中には四畳半位の玄関の室があつた。彼は其所へ疲びれた足を投げ出して坐つた。室の見付けは壁になつて其所には髪の白い西洋人の半身像の額が懸つてゐた。それは夫の書籍にあつたトルストイと云ふ男の顔に似てゐた。
「トルストイだらうか、」
京子が斯う思つて顔をあげた時赤ん坊の泣声がした。
「おや、此所には赤ん坊があるよ、」
彼は赤ん坊が見たくなつてきた。彼は右側の障子を開けた。其所は茶の間になつて向ふの障子の先は縁側になつてゐた。彼はその縁側を伝つて行つた。赤ん坊の泣声は次の室からであつた。彼はその障子を開けた。二つの床があつて夫婦が枕を此方にして寝てゐた。若い女優髷にした細君は派手なメリンスの巻蒲団に包んだ赤ん坊に乳をあてがつて睡つてゐた。
京子は細君の枕頭にしやがむやうにして赤ん坊を覗き込んだ。丸顔の細君の顔がふと此方を向いた。細君は悪魔でも見たやうに震ひ声を立てた。
「どなたです、どなたです、なにしに来たんです、」
京子は騒がなかつた。
「奥様、騒がなくつても好んですよ、私は赤ん坊を見に来たのですから、」
細君は口をもぐもぐしてやつと彼女の顔を見直した。
「あなたはどなたです、斯うして寝てをる所へ、何しに来たんです、何しに来たんです、」
「私は赤ん坊を見に来たんですよ、」
「赤ん坊を見に来たんですつて、誰にことわつて、寝てゐる所へ這入つて来たんです、失礼ぢやありませんか、早く出て行つて下さい、」
と云つて赤ん坊の泣くのも構はずに後ろを向いて、
「早く起きて下さい、大変です、大変です、」
男が吃驚して跳び起きた。京子もその音に吃驚した。そして彼の気は遠くなつた。
京子は朝飯の給仕をしてゐた。日比谷にある中学校へ行つてゐる夫は背広の間服を着て胡坐をかいてゐた。夫が好きで毎朝の味噌汁に入れることになつてゐるわかめの香がほんのりとしてゐた。京子はそれが鼻に泌み込むやうに思つて仕方がなかつた。どうした連想であつたのか彼はふと海岸の家のことを思ひ出した。
「昨夜、面白いことがあつたんですよ、」
「どうした、」
夫は軽い好奇心を動かしたやうであつた。
「昨夜海岸の砂丘をおりて行くと、ちひさな川があつて、それに板橋が架つてゐるんですよ、その橋を渡ると、向ふに小石を敷いた広い通りがあつて、その通りに沿うて二三軒の家があるぢやありませんか、私はくたびれたから、ちよつと休まうと思つて、船板の門をした家へづんづん這入つて行くと、玄関があつて、それが四畳半位でしたよ。其所で両足を投げ出して休みながら見ますと、壁に西洋人の額が懸つてをるぢやありませんか、それが、何時かあなたに見せて戴いた、トルストイですかね、偉い露西亜の小説家の肖像ですよ、」
「何んだ、それは夢か、」
夫は飯を貰ひながら笑つた。
「それがどうも夢のやうぢや無いんですよ。松の木の色も、葉の色も、波の音も、家の様も、なんでもかでも、ちやんと分つてゐるんですよ、」
「それが夢さ、宵に海岸の話をしてゐたから夢に見んだらう、」
「でも夢ぢやないやうよ、それで玄関で休んでゐると、赤ん坊の泣声がするぢやありませんか、私は赤ん坊が見たくなつたので、右の方から這入つて見ると、茶の間があつて、その先に縁側がありますから、縁側に出て見ると、赤ん坊は直ぐ次の室に寝てゐるやうですから、其所へ這入つて見ると、御夫婦が寝てゐて、奥様は円顔の女優髷にした、それはきつさうな方ですよ、私が赤ん坊を覗いてゐると、眼を覚まして、どなた、何しに来たのだつて怒るんですよ、私は平気で、赤ん坊を見に来たと云つてやると、その奥様が怒つちやつて、大声で旦那を起したもんだから、旦那が寝ぼけて跳び起きたんですよ、私もそれにびつくらした拍子に、何が何やら分らなくなつたんですが、その時が夢の覚めた時でせうよ、」
「だから夢と云つてるぢやないか、夢さ、海岸のことが頭にあつたから、そんな夢を見たんだよ、矢張り体のせいだ、来月は行こう、翻訳の方もその時分に出来上るから、一ヶ月位はゆつくり行つて遊んで来よう、其所で仕事をすれば好い、」
夫は飯の後で茶を飲みながら海岸行の話をしてから出て行つた。京子はその後で飯も食はずにちやぶ台に片肱を突いたなりで考へ込んでゐた。
二人の学生が話しながら通つて行つた。その学生の下駄の音が敷いてある通りの真砂にことことと当つた。小川の上には靄がきれぎれに浮んでゐた。京子は板橋を渡つてしまふと彼の家へと行つた。船板の門の扉も玄関の戸も這入つて行く彼の体を支へなかつた。玄関へあがると昨夜の肖像があるだらうかと思つて眼をやつた。肖像は依然として懸つてゐた。
「今晩こそ意地でも、あの赤ん坊を抱いてやらう、」
京子は又昨夜のやうに茶の間へ通り、茶の間から又縁側へと出て夫婦の寝てゐる室へと行つた。細君は巻蒲団に包んだ赤ん坊を側へ置いて、その方に顔を向けて睡つてゐた。赤ん坊は出来て三月位になるらしい人形のやうな子供であつた。呼吸器に故障のあるらしい夫の寝息が、ぐうぐうと蛙の鳴き声のやうに聞えてゐた。
「男の子であらうか、女の子であらうか、」
京子は無邪気な赤ん坊の寝姿を眺めてゐたが、抱きたくなつたので坐つたままで両手を差し出した。赤ん坊の巻き蒲団にその手が掛つた。細君の眼が開いた。細君の両手は京子の右の手首に蛇のやうにからみついた。
「何をするんです、あなたは何をするんです、」
京子はその権幕に驚いて手を振り放さうとしたが放れなかつた。
「早く起きて下さい、早く、早く、昨夜の奴が来て、坊やを何うかしようと云ふんですよ、早く、」
細君は起きあがつて来て京子を横に突き仆して片手をその髪にかけた。細君は又叫んだ。
「早く起きて下さい、昨夜の奴が赤ん坊を取りに来たんですよ。早く、早く、」
夫は跳び起きた。そして夫の手は京子の頸筋にかかつた。
「よし、此奴か、此奴が昨夜の奴か、」
京子の咽喉は塞がつて来た。細君の意地悪い手は京子の頬や額のあたりにあたつた。京子は苦しみもがいた。
赤ん坊の泣き声が聞えた。京子はその泣声をすこし耳に入れたままで分らなくなつてしまつた。
京子は並んで寝てゐた夫に揺り起されてゐた。夫の何か云ふ声が遠くの方でするやうに思ひながらやつと眼を覚ました。
「何うした、大変うなされてゐるぢやないか、夢を見たんぢやないか、」
京子は眼を開けた。青い電燈の光が自分の肩に懸けた夫の手を照らしてゐた。京子は首から顔にかけて重い痛みが残つてゐた。
「夢でも見たのかね、うなされてゐたよ、」
「どうも夢ではないんですよ、赤ん坊を抱きに行つて、ひどい目にあつたんですよ、奥様に髪を掴まれて顔を滅茶滅茶に摘ままれたり、旦那は旦那で跳び起きて来て私の咽喉を締めつけるんですもの、」
夫は笑ひ出した。
「矢張り体のせいだ、体が悪いと深刻な夢を見るもんだ、」
「夢ぢやないんですよ、本当ですよ、顔を滅茶滅茶に摘ままれたんだから、どうかなつてゐやしない、未だに顔から頸の廻りが痛いんですよ、」
京子は顔に手をやつて、顔一面を撫でた後ちに、夫に見せるやうにした。
「どうもなるもんかね、なつてゐやしないよ、夢ぢやないか」
「でも本当よ、昨夜の家へ又行つて赤ん坊を抱かうとすると、やられたんですよ、何んだか口惜しいんです、」
「それが、矢張り体の具合さ、」
「でも、夢であんなことがあるんでせうか、今でも口惜しいんですよ、あの奥様をどうかして、赤ん坊を取つて来て、投げつけてやりたいと思つたんですよ、」
「やつぱり体だ、体が好けれや、そんな夢は見ないよ、」
月の表を霧のやうな雲が飛んで沖の方からは強い風が吹いてゐた。砂丘の小松の枝が音を立ててゐた。落松葉が顔にかかつた。砂丘をおりて小川の板橋を渡らうとすると、向ふから渡つて来た人があつた。京子は草の中へ寄つて向ふから来るのを待つてゐた。村の人らしい帽子を冠らない老人であつた。老人は京子の顔をぢつと見た後に砂丘の方へとあがつて行つた。
京子は橋を渡つた。京子の心は緊張してゐた。京子はずんずんと船板の門の中へと這入つて行つた。彼はもう壁の額も茶の間も見ずに夫婦の寝室へと這入つた。細君の寝床には赤ん坊ばかりで細君は見えなかつた。
「厠へでも行つてるだらう、宜い所だ、」
京子はいきなり赤ん坊を抱きあげて寝床の上に坐つた。赤ん坊はすやすやと睡つて覚めなかつた。夫の方のぐうぐうと鳴る寝息が耳に付いた。
「この人質を持つてをれば、女がどんなにしても負けることはない、」
京子は斯う思つて勝利者の愉快を感じてゐた。
「大変、大変、あなた、早く起きて下さいよ、又彼奴が来てゐるんですよ、」
入口へ立つた細君が縁側を踏みならすやうにして叫んだ。京子は冷笑を浮べてその顔を見た。
「奥様、今晩は私が勝つたんですよ、人質が此所に居りますから、」
夫の方も起きあがつた。
「何の恨があつて、あなたはそんなことをなさるんです、」
細君は口惜しさうに云つた。
「何にも恨は無いんですよ、恨はないが、この赤ん坊が好きだから抱きに来たんですよ、」
京子は冷笑を浮べて云つた。
「好きでも何んでも、誰に許可を受けて、ここへ這入つて来た、」
夫は立つて京子の方へやつて来た。
「そんなことは聞く必要がない、赤ん坊を抱かすことはならん此方へ寄越せ、」
細君も這入つて来た。
「お寄越しなさい、それは私の赤ん坊ですよ、あなたに抱かすことはなりませんよ、」
京子は子供を抱いたなりで立ちあがつた。
「いくら何んと云つても、この赤ん坊はもう渡しませんよ、」
夫の手は京子の肩にかかつた。細君の手は赤ん坊にかかつた。
「駄目ですよ、」
京子は二人の手を払い除けるやうにして茶の間の方へと行つた。夫婦は叫び声をあげて追つて来た。京子は茶の間へ這入つた。茶の間の電燈の下には、細君の縫ひかけた洗ひ張の着物の畳んだ物と、ちいさな栽縫箱とがあつた。栽縫箱には柄を赤く塗つた花鋏があつた。京子は其鋏を片手に取つて広げながら赤ん坊の首の所へと持つて行つた。夫婦は入口へとやつてきた。
「乱暴するなら、これを斯うするんですよ、」
細君の悲痛な叫びが聞えた。細君の両手は鋏を持つた京子の手にかかつた。京子の手がそのはずみに働いた。赤ん坊の首が血に染まりながらころりと畳の上に落ちた。
京子は夫に抱き竦められて寝床の上にゐた。京子は眼をきよときよとさして四辺を見廻した。
「赤ん坊の首なんかがあるもんか、何所にそんなものがある、」
夫は叱るやうに云つた。京子はそれでも恐ろしさうな眼をして四辺を見てゐた。
「矢張り夢さ、体が悪いからそんな夢を見るんだ、今日は脳病院へ行つて、石川博士に診察して貰はう、体のせゐだよ、」
京子は稍気が静まつて来た。
「夢でせうか、本当に恐ろしかつたんですよ、」
「夢さ、神経衰弱がひどくなると、つまらん夢を見るもんだよ、」
学校の休みになるを待ち兼ねて京子の夫は京子を連れて、海岸へとやつて来た。其所は山裾になつた土地で、山の方には温泉もあつた。二人は先づ友人から聞いた海岸の旅館へ行つてその上で貸間を探すことにして、汽車からおりると海岸へと向つたが、その海岸へは俥で行くと十四五町もあるが、歩けば五町にも足りないと云ふので、雇うた俥屋にトランクを担がして、夫婦はちひさなバスケツトを一つづつ持つて歩いた。
二時を廻つたばかりの所であつた。風の無い蒸し暑い日で松の葉が真つ直ぐに立つてゐた。松原を出はづれて小松の植はつた砂丘をおりと行くと小さな川が流れてゐた。
「何んだか、私こゝは見覚えがあるやうですよ、」
夫の後から歩いてゐた京子が云つた。
「ちいさい時に、誰かと来たことがあるだらう、」
夫は心持ち振り返るやうに左の片頬を見せた。
「此所へ来たことは無いんですよ。お父さんもお母さんも、昔気質で、旅行なんかしなかつたから来やしないんですよ、」
「さうかなあ、」
丘をおりてしまふとちひさな板橋へ来た。板橋の向ふに真砂を敷いた広い路があつた。
「あの路へ出て来るんだね、」
夫は俥屋に向つて云つた。
「さうです、ずつと廻つてここへ来るんですから、十町以上もありまさア、」
俥屋はトランクの肩を換へて片手にした手拭で顔の汗を拭いた。夫は橋を渡つて行つた。水の中には短い葦が一面に生えてゐた。路の向ふにはすこし高まつた松林の丘があつて其所に三軒ばかり別荘風の家があつた。
京子は厭な顔をして橋の向ふのとつつきにある家を見直した。
「あなた、あなた、」
京子は夫に声をかけた。彼女は橋を渡つて行つた。路の上へあがつた夫は彼の方を向いた。
「何だね、」
「いつかの家ね、この家のやうよ、」
夫には合点がゆかなかつた。
「家つて何んだね、」
「あの夢の家ですよ、」
京子の声は震ひを帯びてゐた。夫はその方へ眼をやつた。竹垣を結ふた船板の門の扉が閉まつた家が眼に付いた。夫は笑ひだした。
「そんな馬鹿なことがあるもんか、」
「でも、さうですよ、小松の生えた丘の具合から、この板橋の具合まで、そつくりですよ、だから見覚があると私が云つたんですよ、」
「そんなことは無いさ、無いが、門が閉まつて空家らしいね、空家なら借りたいもんだが、」
トランクを担いだ車夫がやつて来た。
「俥屋さん、この家は空いてるかね、」
「空いてます、」
「一ヶ月位貸さないだらうか、」
「貸さないことは無いでせうが、この家は、変な家ですよ、先月まで此所にゐた東京者が、赤ん坊を妙な女に締め殺されたつて、借り手が無いんですよ、」
夫は妙な顔をして京子をちらと見た。京子は真青な顔をしてゐた。
「ぢや、まあ宿屋へ行つてからのことにしよう、縁起の悪い家はいけない、」
夫は斯う云つて海岸の方へと歩き出した。京子は並ぶやうにして歩いた。二人はもう何も云はなかつた。向ふの方から老人が一人やつて来た。老人は二人にすれ違はうとして京子の顔をぢつと見た。そしてその眼を車夫に移した、車夫とは見知越の顔であつた。二人は立ちながら何か話しだした。
夫と京子の二人は半町ばかり向ふに歩いてゐた。老人と分れた車夫が早足に追いついて来た。
「旦那、今の男があの家の家主ですよ、」
「さうかね、」
夫は斯う云つたきりで何んとも云はなかつた。車夫は京子の方へ言葉をかけた。
「奥様は、一度、此方へお出でになつた事がありますか、今の男が、何処かでお見かけしたやうだと云つてをりますよ、」
京子は返事をしなかつた。
「いや、これは此方は初めてだ、何処か東京へでも来た時に見たんだらう、」
京子と京子の夫は海岸の旅館の二階に通つてゐた。京子は蒼白い眼をして坐つたなりに俯向いてゐた。
「着物を着換へるが好い、何んでもないよ、お前の夢と、変なこととが暗合したんだ、そんな馬鹿馬鹿しい事があるもんか、」
京子はそれでも動かなかつた。夫は洋服を宿の寝衣に着換へながら、女中の置いて行つた茶を飲んでゐた。
「着物でも着換へると、気が変るよ、お着換へよ、」
京子はそれでも返事をしなかつた。番頭が這入つて来た。番頭の手には名刺があつた。
「この方がちよつとお目にかかりたいと申します、」
夫は手に取つて見た。それは警察の名刺であつた。
「警察か、何の用事だらう、」
夫は斯う云つて考へた。
「近頃は、もう、警察がどなたにでも会ひに来て、煩さくて困るんですよ、此所へ通しませうか、」
「では通して貰はう、」
「本当にお気の毒でございます、」
番頭が腰を上げた。
何か恐ろしい叫び声をしながら京子が立ちあがつた。夫が驚いて腰を浮かした時にはもう彼女は廊下へ出てゐた。そして欄干に片足をかけた。夫は追つて行つて抱き止めた。
「何をする、」
夫は斯う云ひながら庭の方に眼を向けた。庭の赤松の傍を京子とすこしも変らない女が駈けて行つた。夫は眼を見張つて抱いてゐる京子の顔を見返した。それでも不思議であるから、又庭の方を見た。駈けて行つた女の姿はもう見えなかつた。京子は夫の手を振り放さうとしてもがき狂うた。
京子の夫の矢島文学士は、翌日恐怖の塊とも云ふやうになつた京子の体を介抱しながら、東京行の汽車の隅に悄然として腰を掛けてゐた。
底本:「伝奇ノ匣6 田中貢太郎日本怪談事典」学研M文庫、学習研究社
2003(平成15)年10月22日初版発行
底本の親本:「黒雨集」大阪毎日新聞社
1923(大正12)年10月25日
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
入力:川山隆
校正:門田裕志
2009年8月12日作成
2012年5月24日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
悪僧
田中貢太郎
何時いつの比ころのことであったか朝鮮の王城おうじょうから南に当る村に鄭ていと云う老宰相が住んでいた。その宰相の家には宣揚せんようと云う独ひとり児ごの秀才があったが、それが十八歳になると父の宰相は、同族の両班ヤンパンの家から一人の女を見つけて来てそれを我が児の嫁にした。
宣揚の夫人となった女は花のような姿をしていた。宣揚は従来いままでにない幸福を感じて、夫人を傍からはなさなかったが、朝鮮の風習として結婚した両班の子弟は、すぐ山寺へ往って独居生活を始め、科挙かきょに応ずることのできるように学問文章を修おさめることになっているので、宣揚もしかたなく夫人を家に残して山寺へ往った。
そして、山寺の一室に行李こうりを解といた宣揚は、遠く本堂の方から漏もれて来る勤行ごんぎょうの声に心を澄まし、松吹く風に耳を洗あろうて読書三昧ざんまいに入ろうとしたが、夫人の唇や頬ほおが文字もんじの上に見えて読書する気になれなかった。しかし、山をくだって夫人の処へ帰って往くと云うことは、父母をはじめ世間の手前もあるのでさすがにそれはしなかったが、そのかわりに壮わかい和尚おしょうに頼んで手紙を夫人の許もとへ送り、その返書を得て朝晩にそれを読みながら、僅わずかに恋恋れんれんの情じょうを慰めていた。
宣揚が山へ登ったのは晩春の比ころであった。そして、暑い夏を送って秋になると、夫人に逢あいたくなって起たってもいてもいられなくなったので、父母を省せいすると云う名目をこしらえて某日あるひ山をおりた。
山の中程には大きな巌石がんせきが屏風びょうぶを立てたように聳そびえた処があった。宣揚はそこまでおりて来ると疲労くたびれて苦しくなって来たので、路みちぶちの巌いわに腰をかけて休んでいた。空には白い雲が飛んで荒っぽい秋風が路の下の方の林に音を立てて吹いていた。宣揚は手巾はんけちで襟元えりもとににじみ出た汗を拭ぬぐいながら、今日帰って往く己じぶんを夫人がどんな顔をして迎えるだろうと思ってその喜んだ顔を想像していた。黒い瞳と朱あかい唇が眼の前にあった。と、背後うしろの方でものの気配がして、宣揚が不審して振返ろうとする間もなく、彼の頭は黒い撃痛を感じて横に倒れた。倒れながら彼の顔は血に染まった。太い棒を手にした壮わかい和尚おしょうが意識を失いかけた彼の眼に映った。
黄金こがねの金具を打った轎かごが町まちの四辻よつつじを南の方へ曲って往った。轎の背後うしろにはお供ともの少女が歩いていた。それは麗うららかな春の夕方で、夕陽ゆうひの中に暖かな微風が吹いていた。慕華館ぼかかんで終日日課の弓を引いていた李張りちょうと云う武科志願の秀才は、このとき弓と矢を肩にして己の家へ帰っていたが、きれいな轎が来るので見るともなしに眼をあげた。と、小さな旋風つむじかぜが起ってそれが薄うっすりと塵ちりを巻きながら、轎夫かごかきの頭の上に巻きあがって青い簾すだれの垂たれを横に吹いた。簾は鳥の飛びたつようにひらひらとあがった。艶麗えんれいな顔をした夫人が坐っていた。李張は女の美にうたれた。この姝きれいな女はどんな秀才の夫人であろう、と、思いながら立ちどまってその轎を見送っていたが、その足は何時いつの間にか轎の往く方へ動きだした。
金粉をまき散らしたような西の空に紅あかい陽ひがどんよりとかくれた。そこここの人家の門口かどぐちに咲いていた李すももの花も灰色になった。きれいな轎かごは郊外にある大きな邸宅の門へ入った。李張は夢が醒さめたようにその前に衝立つったっていたが、心残りがして帰れないのでその邸宅の周囲まわりを歩きはじめた。そして、裏門の方に往ってみると裏門の横手の垣に添うて小さな丘があった。李張はふらふらとその丘の上にあがった。黄昏ゆうぐれの邸内には燭火ともしびの光が二処ふたところからちらちらと漏もれていた。垣はすぐ一跨ひとまたぎのところにあった。彼はそこに佇たたずんで燭ともしびの光を見ていた。
四辺あたりは真暗に暮れてしまって雨気あまけをふくんだ風が出た。李張は何時いつの間にか邸内へ入り、燭の見えている東房とうぼうの方へ往って、そこの窓から内を覗のぞいてみた。内では轎の中にいた夫人が老婆の前で物語らしい書物を読んでいた。老婆は姑しゅうとめらしかった。
老婆を牽ひきつけていた書物の一章が終ったのであった。
「今日はお墓参りに往って、疲労くたびれておりましょうから、もう、それにして置いて、あとは明日あすの晩にしてもらいましょう」
老婆が顔をあげて云った。
「そんなに疲労くたびれはしないですけれども、……では、後あとは明晩にいたしましょう」
夫人は愛嬌あいきょうのある顔を見せて淑しとやかに拝おじぎをして房へやを出て往った。
李張は燭火ともしびの前に浮き出た花のような姿を見たうえに、奥ゆかしいその物ごしを見せられてますますその女が慕したわしくなった。彼は女のさがって往く房へやはどこだろうと考えたあげく、西房せいぼうの方へ往ってその窓から覗のぞいた。東房とうぼうからさがって来た夫人が物悩ましそうに坐って耳を澄すますようにしていた。
遠くの房へやにいる良人おっとの来る跫音あしおとを聞いているだろう、こんな美婦の良人であるから、良人になる人も容貌きりょうの好い男だろうと思った。そう思うと李張は妬ねたましいような気になって来た。そして、己じぶんの行為がばかばかしくなって来た。で、引返そうとしていると庭前にわさきの方に人の跫音がした。彼は己がこうしているのを邸やしきの人が知って、捕えに来たのではないかと思って、そっと窓を離れて傍の竹叢たけむらの中へ身をかくして注意していた。
怪しい人影が戸口に近づいて扉をことことと打ちはじめた。では己ではなかったか、と、李張は安心してその方を見ていた。すると、扉が内から開あいて外の人影は中へ入った。それではここの良人は留守で、不義者が出入しているらしいぞ、と彼はまた竹叢の中から出て窓の処へ往って覗のぞいた。
夫人と壮わかい和尚おしょうが手を執とりあっていた。李張は驚いて眼を睜みはった。そして、今まで美しかった知らず識しらず尊敬していた夫人に対する感情は、忽たちまちがらりと変って汚い醜い腹立たしいものとなった。
夫人は棚のなかから小さな壺つぼを出して来て、それを二つの盃さかずきに注ついで一つを和尚の手に持たし、その一つを己で飲んだ。李張は燃えるように感じる眼をそれにやっていた。
二人は壺の液体を飲みあった。そして、艶なまめかしい囁ささやきを囁きあったが、和尚の態度は夫人以上に醜悪なるものであった。李張はまず和尚を踏み潰つぶしてやりたかった。
和尚は夫人を横抱きにして洞房どうぼうの方へ往こうとした。夫人は抱かれながら両手を和尚の首にからまして朱あかい唇を見せた。李張は手にしていた弓を持ち直して、それに腰につけた矢壺やつぼの矢を抜いて添えた。
和尚はすこし首を屈かがめて夫人の唇を己の頬ほおに受けようとした。と、李張の手にした矢が飛んでその前額ぜんがくから後脳こうのうにかけて貫つらぬいた。夫人の倒れた上に血に染そんだ和尚おしょうの体が重なった。
李張の姿は暗闇の中に消えてしまった。
その夜李張が家へ帰って寝ていると、その枕頭まくらもとへ青い衣きものを着た小柄な秀才が来た。李張はこうして締め切ってある房へやの内へどうして入って来たろうと思って不審して見ていた。と、秀才は恭うやうやしく拝おじぎをした。
「貴君あなたは何方どなたですか」
李張は聞いてみた。
「私は、この南村なんそんに住んでいる、鄭宰相の独ひとり児ごの宣揚と云う者でございますが、今日こんにち貴君あなたに讐かたきを打ってもらいましたから、お礼にあがりました」
秀才は弱よわしい声で云った。李張にはその意味がどうしても判らなかった。彼は黙って秀才の蒼白そうはくな顔を見つめていた。
「これだけ申しましたのでは、貴方あなたにはまだお判りになりますまいが、私はこの三年前ぜん、妻室かないを迎えるとともに、例によって山寺へ往って、学問をしておった者ですが、時おり私の家へ使つかいにやっていた和尚が、妻室かないを誑たぶらかし、二人で共謀して、私が帰省しようとして、山の中途までおりたところを、後うしろからつけて来て撲なぐりつけ、死骸は巌窟いわあなの中にかくして、世間へは虎に喫くわれたと云いふらして、今に妻室かないと密会を続けておりましたが、それが、今晩、貴君あなたに見られて殺されることになり、私の怨うらみも報むくいられましたが、私の両親はまだ何も知らずに、彼かの淫婦いんぷに欺あざむかれておりますから、どうか私の父に逢あって、まず私の死骸を改葬したうえで、淫婦いんぷの始末をしてください、私の死骸は山の中程の、巌石がんせきの聳そびえている処へ往ってくだされば、すぐ判ります、淫婦を白状さすには、貴君あなたに殺された和尚おしょうの死骸を、被ひに包んで床の下にかくしてありますから、それを引出してからやってください」
李張が何か云おうと思っていると、怪しい夢は破れてしまった。
朝になった。李張は前夜何人だれの邸宅とも知らずして往った鄭宰相の処へ往った。
「若旦那の死骸の在る処を知っておる者だ、宰相にお眼にかかりたい」
こう言って門番に取次を請こうと、すぐ大庁たいちょうへ通された。そして、ちょっと待っていると、髯ひげの白い痩やせた老宰相が出て来た。
「伜せがれの死骸の在る処を知っておられると云うのは、貴君あなたかな」
「はい」
「伜は虎に喫くわれて死骸が無いことになっておるが、それでも貴君あなたは知っておられるかな」
「これに就つきましては、いろいろ申しあげたいことがございますが、兎とに角かく、御子息の死骸をお眼にかけたうえで、申しあげます」
「そうか、それでは、その死骸はどこに在あるかな」
「山寺に登る路みちの中程の、巌窟いわあなの中に在ります」
老宰相と李張は馬に乗って、数人の供人ともびとを伴つれて山寺の方へ往った。そして、山の麓ふもとへ着くと、老宰相も李張も馬からおりて、勾配こうばいの急な山路やまじを登って往った。山桜がぽつぽつ咲いていた。十丁ちょうばかりも登ると、屏風びょうぶを立てたような巌石がんせきが路みちを挟んで聳そびえている処へ出た。一番前を歩いていた李張は、夢のなかの秀才が云った処はここだなと思った。が、それでもまだどこと云う見当がつかないのですこし困っていた。
「このあたりかな」
背後うしろの方で老宰相のあえぎあえぎ云うのが聞えた。小さな青い鳥が左側の巌いわの尖とがりにとまって、く、く、くと耳に染しみるように鳴いた。李張の眼がそれに往った。青い鳥はまだ、く、く、くと鳴いていた。……死骸は山の中程の巌石が聳えている処へ往ってくだされば、すぐ判りますと云った秀才の詞ことばが思いだされた。青い鳥は鳴きながら巌の尖を伝って右へ右へ往った。李張はその後あとから跟ついて往った。
青い鳥は巌の一方へ廻ってやはり尖を伝って往ったが、巌が次第に低くなって四辺あたりに荊棘いばらの茂った処へ往くと見えなくなった。李張はその辺あたりへ注意した。巌がぐるりと刳えぐれて地の底深く陥窪おちくぼんだ処が脚下あしもとに見えた。李張は躊躇ちゅうちょせずにその巌窟いわあなへはいった。人の背丈せたけ位の穴が斜ななめにできていた。で、それに跟いて往くと、三畳敷位の広い巌窟になって、その下の微暗うすぐらい処に白骨になりかけた死骸が横よこたわっていた。胆力たんりょくのある李張はその死骸に近寄った。
老宰相と供ともの者は窟あなの口へ来て内を覗のぞいていた。李張は朽くちかけた衣服きものに包まれた白骨を抱いてその眼の前にあらわれた。
「伜せがれだ、伜の衣服きものだ」
老宰相は泣きながら白骨に縋すがりついた。
「閣下、いよいよ御子息にそういありませんならば、更あらためて山寺へお葬ほうむりになるが宜よろしゅうございましょう、そのうえで、私から閣下に申しあげたいことがございます」
李張は白骨を抱いたなりに云った。
「お前さんは神人しんじんだ、どうして伜せがれの死骸がここに在ることを知りなされた」
老宰相は涙を眼に湛たたえて聞いた。
「これは昨夜ゆうべ、御子息が、夢に私にお話になりましたから、知っております」
「ほう、伜が」
「そうでございます、御子息が私の夢にあらわれて、まだ他にもいろいろお話がありました」
「それでは、伜は、虎に喫くわれたのじゃないだろうか」
「虎ではありません、悪漢わるものの手にかかったものであります」
老宰相はまた泣きだした。
老宰相は伜の寡婦かふのいる内房ないぼうの西房せいぼうへ入って往った。寡婦の夫人は愛嬌あいきょうを湛えて舅しゅうとを迎えた。
「今朝けさ、鵲かささぎが鳴いたと思いましたら、お父さまのお出ましがありました」
「ほう、今朝、鵲が鳴いた」と、老宰相は厳いかつい眼をして夫人の顔を見たが、またおもいかえしたように、「二十年も昔のことだが、盗賊が怖こわいので、ここの床の下へ玉を埋うずめてある、それを掘りだして、お前にあげようと思って来た」
「おお、玉を、埋うずめてある玉を、私にくださいます、それはありがとうございますが、お父さまがお手をくださなくっても、何人だれかに申しつけましょう」
「いや、こんなことはまちがいの起り安いものだから、乃公わしがする」
「でも、そんな軽がるしいことは」
夫人は笑顔をして云った。
「好いよ、好いよ、床の板さえ剥はげばすぐだから」
「でも」と、云った夫人は急に思いついたことがあるようにさも耻はずかしそうな顔をして、「お父さま、どうぞ、床をあげることは、ちょっとの間お待ちくださいませ」
「どうしたとお云いだ」
「……私の汚れ物を皆入れてありますから、それを除のける間、ちょっとお母さまのお房へやでお待ちしてくださいませ、すぐ執とり除けますから」
「そんなことは好い、ちょっとそこを退のいてくれ」
「でも」
と、夫人の声は顫ふるえた。
「さ、好いから退いてくれ」
老宰相は強く云って夫人の傍に進んだ。夫人は蒼あおい顔をして立っていたが、急に身を飜ひるがえして入口の扉とを開けて走りでた。出口には李張の手があった。
老宰相は夫人が掴つかまえられたことを見届けると床の板を剥いだ。床の下には被ひに包んだ悪僧の死骸があった。被には生生なまなましい血の斑点があった。
老宰相は使つかいをやって夫人の父と兄を呼んでその面前めんぜんで夫人を鞠問きくもんした。夫人は罪悪を包みかくさず自白した。
夫人の実父の老両班ヤンパンは、いきなり腰の刀を抜いて夫人の咽喉元のどもとを刺した。
その夜よ李張の夢にまた宣揚があらわれた。
「近いうちに謁聖えっせいがありますから、それに応ずるが宜よろしゅうございます、貴君あなたは武科が御志願でございますけれども、まず文科をお受けになるが宜しゅうございます、今回の賜題しだいは私が教えてあげます」
と、云って一つの文章を朗読した。李張は一心になってその文章を暗記した。宣揚は二度も三度も朗朗と誦しょうした。
「お判りになりましたか」
「よく判りました」
「それさえ覚えておれば、必ず及第いたします」
李張は科挙に及第して文官になったが、鄭宰相が陰いんに陽ように推輓すいばんしてくれるのでめきめきと栄達えいたつした。
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第一巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
尼になった老婆
田中貢太郎
なむあみだぶ、なむあみだぶ、こんなことを口にするのは、罪深い業でございますが、門跡様の御下向に就いて思い出しましたから、ちょっと申します。その時は手前もまだ独身で、棒手振ぼてふりを渡世にしておりました時のことでございますから、さあ、文政の二三年、いや、もうすこし後でございましたかな、東本願寺の門跡様が久かたぶりで御下向遊ばすと云うことになりますと、江戸は申すに及ばず、近郷近在にかけて、それはもう煮えかえるような大騒ぎ、わけて熱心な者は、江戸ではとてもお姿が拝めない、箱根あたりまで出かけて往って、お駕籠といっしょに歩いていたなら、万に一つも拝めないと云うことはないと申しましてな、藤沢から小田原にかけて、我も我もと出かけてまいりました。手前も門跡様がお着きになると云う日は、朝から渡世を休んで、鈴ヶ森の手前まで往って待ち受けておりました。ちょうど花の比ころで、陽はまだ高うございました。風の無い暖かな日で、磯際へかけて溢れていた人の額に、汗が出ると云うような暖かさでございました。もう干潮に近い比で、海苔しびを立てた洲が一面にあらわれておりましたが、その日は干潟へおりて、海苔や貝を採る者も一人もないので、白い鴎が我が物顔に遊んでおりました。沖を見ますと、潮曇のようにどんよりと曇って、その間から房州の山が薄すらと見えておりました。
程なく門跡様のお駕籠がまいりましたと見えて、なむあみだぶ、なむあみだぶ、と、念仏を唱える声が波の打つように聞えてまいりました。そうなって来ると、その附近まわりにいた信者達は、狂人きちがいのような眼つきをして、お駕籠を見ようとしましたが、並木や人の頭ですぐは見えません。気の早い者は、それでも、もう、なむあみだぶ、なみあみだぶ、と念仏をはじめました。
先供をしている寺侍の笠が見えたかと思うと、門跡様一行の行列が見えてまいりました。念仏の声はますます高まってまいりました。人びとは前へ前へと出ますから、行列は右に曲り、左に折れて、真直に歩けませんでした。
そのうちに門跡様のお駕籠が眼の前にまいりました。大波の崩れるような念仏の声が四辺あたりに湧きかえりました。門跡様のお駕籠を拝もうとする者が我れ前さきにと雪崩を打って進みましたから、忽ちお駕籠が動かなくなりました。お駕籠の垂れは深ぶかとおろしてありますから、お姿を拝むことはできなかったのです。幸い手前の方におりましたから、お駕籠の中に物の気配のするのをはっきりと感じました。なむあみだぶ、なむあみだぶ、なむあみだぶ。
その時でありました。手前の背後うしろの方から背の高い婆さんが、がむしゃらに人を突き退けるようにして前へ出て来ました。私もすんでのことに、その婆さんに突き飛ばされるところでありました。
「ひどいことをしやがる婆あだ」
「婆さん、後生の悪いことをするない」
などと、その婆さんに向って怒る人もありました。手前も癪に触りましたが、場合が場合でありましたからして、すぐ懐しい朋友ともだちのような気になって、婆さんのすることを見ておりました。婆さんの頭には白髪しらがの小さな髷がありました。婆さんはそのままお駕籠の傍へ寄って往って、垂れを頭ではねのけるようにして、頭をお駕籠の中へ突き入れました。手前はあまりな婆さんの仕打を見てまして、仏罰を恐れないのか、なんと云う後生の悪いことをする婆さんだ、と、怒るよりは、空恐ろしい思いをしましたところで、婆さんの頭は突き戻されるようにお駕籠の中から出るとともにその体は背後うしろへよろよろとなりました。婆さんの額には、門跡様の白い青みがかった姝きれいなお手がかかっておりました。私は門跡様が婆さんを煩がって、お突きになったものだと思いました。婆さんの体のよろけぐあいから申しましても、それは、もう、たしかにお突きになったものであります。
ところで、遠くの方におりました者は、そのわけあいは判りませんから、婆さんの額にかかっておりました門跡様のお手を見ると、門跡様がその婆さんに特別にお手を触れられたものだと見てとりました。
「門跡様のお手が触れた、ありがたいことだ、なむあみだぶ、なむあみだぶ」
「彼あの婆さんの頭に、門跡様のお手が触れた、なむあみだぶ、なむあみだぶ」
「ありがたいことだ、ありがたいことだ」
「もったいない、もったいない、なむあみだぶ、なむあみだぶ」
皆婆さんの周囲まわりに集まって来て、門跡様のお手のかかっていたあたりへ、我も我もとその手を当てだしました。婆さんは迷惑して身をかわそうとしましたが、周囲まわりの人はだんだん多くなってきました。すると一人の壮わかい男が、婆さんの髪の毛を二三本指に撮つまんで抜き執りました。婆さんは痛いので頭を抱えて逃げようとしましたが、人が一ぱいで身動きができません、そのうちまた一人の老人が、壮い男がしたように一撮つまみの髪を撮んで引き抜きました。他にも一人二人、また髪の毛に指をかけました。婆さんはもう泣き声を立てはじめましたが、信心に夢中になっておる人の耳へは入りません。婆さんの髷はこわれました。婆さんを囲んだ者は、もう我れがちに婆さんの髪の毛に指をかけて抜きました。
「助けてくれ、助けてくれ」
婆さんは手を揮って悶掻きましたが、何人だれもそれに耳をかす者はありません。皆門跡様のお手の触ったありがたい毛を抜き執ろうと、一生懸命になって婆さんに武者ぶりつきました。
婆さんはもう気が遠くなって、死人のようになって人波に揉まれておりました。そのうちに婆さんの髪の毛が一本も無くなって、尼さんの天窓あたまになりますと、皆の者は婆さんを捨てて門跡様の行列を追って雪崩れて往きました。私もその雪崩の中へ巻きこまれて往きましたから、その婆さんはどうなったか知りませんが、ほんとうに可哀そうでございました。しかし、これが仏様の思召しでございましょう。なむあみだぶ、なむあみだぶ。
底本:「日本の怪談(二)」河出文庫、河出書房新社
1986(昭和61)年12月4日初版発行
底本の親本:「日本怪談全集」桃源社
1970(昭和45)年初版発行
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
※「頭をお駕籠の中へ突き入れました」の箇所は、底本では「頭をお駕籠へ中へ突き入れました」でしたが、親本を参照して直しました。
入力:Hiroshi_O
校正:小林繁雄、門田裕志
2003年8月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
雨夜続志
田中貢太郎
芝しばの青松寺せいしょうじで自由党志士の追悼会のあった時のことである。その日、山田三造は追悼会に参列したところで、もうとうに歿なくなったと云うことを聞いていた旧友にひょっくり逢あった。それは栃木県のもので、有一館ゆういつかん時代に知りあいになったものである。有一館は政府の圧迫を受けて、解党を余儀なくせられた自由党の過激派の手で経営せられた壮士の養成所であった。山田も旧友もその有一館の館生であった。
旧友は伊沢道之いざわみちゆき、加波山かばさんの暴動の時には宇都宮にいたがために、富松正安等とまつまさやすらと事を共にするの厄やくを免かれることができたが、群馬の暴動は免かれることができなかった。それは明治十七年五月十三日、妙義山麓みょうぎさんろくの陣場じんばヶ原はらに集合した暴徒を指揮して地主高利貸警察署などを屠ほふった兇徒の一人として、十年に近い牢獄生活を送り、出獄後は北海道の開墾に従事したり、樺太からふとへ往ったり、南清なんしんで植民会社を創立したり、その当時の不遇政客の轍てつを踏んで南船北馬なんせんほくば席暖まる遑いとまなしと云う有様であったが、そのうちにばったり消息が無くなって、一二年前ぜん山田の先輩の油井あぶらい伯が歿なくなった時分、伯爵邸へ集まって来たもとの政友の一人に訊きくと、もう歿なくなったと云ったのでほんとうに死んだものだと思っていたところであった。
「やあ、暫しばらく、君は、油井伯の歿くなった時に聞くと、歿くなったと云うことだが、無事だったね、お変りもないかね」
昔のままの薄あばたのある伊沢の赧黒あかくろい顔を見て山田は微笑した。
「死んだも同じことさ、今は仙台にいる小供の処で、一合ごうのおしきせを貰ってるよ、伯の歿くなった時には、ちょうど腎臓が悪くて、生きるか死ぬかと云う場合だったから、つい見舞状も出さなかった、今度は久しぶりで宇都宮へやって来たところで、新聞で知ったからやって来たんだ、多分君にも逢あえるだろう、逢えなかったら、明日あすあたり伯爵家へ往って、君の居処いどころを訊いて尋ねて往こうかと思ってたところだ、どうだね、君は相変らず、椽大てんだいの筆を揮ふるってるじゃないか、時どき雑誌で拝見するよ」
「近比ちかごろは浪人の内職が本職になってね、文章を書いて飯めしを喫くうとは思わなかったよ、お互いに大臣になるか、警視総監になるか、捨売すてうりにしても、知事位にはなれると思ってたからね」
乱暴なつむじ曲りの伊沢の口許くちもとに無邪気な笑わらいが溢あふれた。
「金硫黄きんいおうと塩酸加里えんさんかりを交ぜ合した物を持って、三田辺みたへんをうろついたこともあったね」
「金硫黄と云や、鯉沼こいぬま君はどうだね、まだ無事だろうか」
「さあ、他にちょっと用事があって、鯉沼君のことを訊いてみなかったが、まだ県会議員でもしているのじゃないかね、僕が加波山の事件を免れたのは、鯉沼君に云いつけられて、宇都宮へ県庁の落成式が何時いつあるか、ないかを調べに往ってたためなんだ、鯉沼君は乱暴だね、爆弾の糸を鋏はさみで摘つまみ切ってたまるものかね、あの爆弾が事の破れさ、鯉沼君は隻手かたてを失うし、富松君は加波山へ立て籠こもるしさ、とにかく、壮わかい血気の時でなけりゃできないことさ、なにしろ、お互に壮かったね、なんだか今思ってみると、己じぶんのことでなしに、伝奇小説でも読むような気がするじゃないか」
「皆大臣の夢を見ていたからね、大臣になれりゃ、毎晩、新橋へも往けると思っていたからね、僕の知った男だが、牛肉屋へ往って、大臣になれりゃ、毎晩ここへ来られるねって云ったよ、今日祭る政友の中にも、だいぶ大臣になって、牛肉を毎晩喫くいたいと云う連中があったよ」
「なんだ、政友会の話じゃないか、俺は自由党は好きだが、政友会は大嫌いだよ」
山田と伊沢の話している処へこう云って髯ひげの白い童顔の老人が顔を出したので、二人の話は切れてしまった。続いて追悼式がはじまって読経になり演説になったので、山田はもうすこし旧友と話してみたいと云う興味があったけれども、それが終るまで殆ほとんど一時間半ぐらいは何も云うことができなかった。
式が終って冷酒ひやざけとスルメが出て、百人に近い列席者は故人の追懐談に移ったので、山田はやっと伊沢と詞ことばを交える機会を得たが、それでも最初に逢あった時のような打ちとけた、わだかまりのない話をすることはできなかった。
政界の落伍者の集まりである浪人の多い席であるから、話の落ちて往く処は現代の政党の攻撃であった。山田は奮激の交っているそうした談話に興味を持たなかった。彼は巻煙草を点つけようとしている伊沢に囁ささやくように云った。
「君は、今日、帰りを急ぐかね」
「急ぎはしないよ、久しぶりで、例の牛肉でもつッつこうじゃないか」
「僕もそう思っているところだ、ゆっくり二人で飯めしを喫くいながら話そうじゃないか」
「そうだ、そうしよう」
山田と伊沢は四時比ごろになって寺を出た。晩春はるさきの空気が緩ゆるんで靄もやのような雨雲が、寺の門口かどぐちにある新緑の梢こずえに垂れさがっていた。
「また雨らしいね」
伊沢はまぶしそうな眼をして空を見た。
「そうだ、日が暮れたらやってくるね、でも、風に吹かれるよりは好いじゃないか」こう云いながら山田は伊沢を案内して往く処を考えていた。「君は日本料理が好いかね、それとも、鳥か牛肉が好いかね」
「さっきも何人だれかが云ってたね、大臣になって、毎晩牛肉屋へ往きたいって、僕もやっぱり牛肉の方が好いね」
「そうか、じゃ小さい汚い家だが、僕の往きつけで、ちょっと牛肉を喫わせる家があるから、そこへ往こうか」
二人は寺の前の石橋を渡って左の方へ歩いて往った。
そして、五六町ちょう往ってちょっとした横町よこちょうを右へ折れ曲って往くと、家の数で十軒も往った処の右側の門燈もんとうに「喜楽きらく」と書いた、牛肉屋とかしわ屋を兼ねた小料理屋があった。山田は前さきにたって入って往った。
お千代と云う壮わかい婢じょちゅうが山田の姿を見つけると飛んで出て来た。
「今日はお客様を伴つれて来た、平生いつもの室へやが空いてるかね」
二人は婢に跟ついて二階の六畳の室へ往った。中敷ちゅうじきになった方の障子しょうじが一枚開あいていた。そこからは愛宕あたごの塔が右斜みぎななめに見えていた。伊沢はその中敷に腰を掛けて、ちょっとした歩行にも疲くたびれる足の疲くたびれを治していた。
「僕は、今日、寺へ往く路みちで、そら、あの病院の前を通って、木内種盛きうちたねもり君のことを思ったよ、木内君の死は、ありゃどうしても、ただの病死じゃないね、その当時噂のあったように……」
山田は婢に肴さかなの註文をしていた。
「木内君かね、そうさ、ありゃ、どうしても、青木寛かんに罪があると思うね、僕は、一昨年、油井伯が歿なくなった時分、木内君の夢を見たが、木内君がありありと出て来て、その話をしたよ、青木の奴、去年庭を歩いてて、卒中でひっくりかえって歿くなったが、どうせあんな奴は、ろくな死に方はしないよ、今どこかの病院の院長をしてる彼の小供も、この間、病人の手術が悪かって、病人を殺したので、告訴沙汰になってるのだ」
「そうかな、いくら爵位を得ても、それじゃしかたがないね」
電燈が点ついて陰気な室へやの中が引きたって来た。
「有一館の時代だったら、金硫黄きんいおうと塩酸加里えんさんかりで覘ねらわれるところだったね」
「そうだなあ、曰いわく伊沢道之、曰く山田三造、そう云う壮士に、いの一番に覘われているところだったね」
二人は無邪気に笑い合った。婢じょちゅうが水こんろを持って入って来た。もう一切いっさいの物を二階のあがり口へ持って来てあると見えて、こんろの後あとから広蓋ひろぶたに入れた肉や銚子ちょうしなどを持って来た。鍋の中ではもう汁が煮たっていた。
「この間の方かたはどうして」
婢は山田の顔を見た。山田はすぐ数日前ぜんに伴つれて来た壮わかい新聞記者のことを思いだした。
「どうだ、お気に入りましたかね」
「いやよ、あんないけ好かない男ったらあるものですか、今の新聞記者って云うものは、皆あんなものでしょうか」
「まあ、そう悪く云うなよ、可愛い男じゃないか、あんな男は家を持ったら、家のことはきちんとするよ、細君さいくんになる者は安心だよ」
「でも、厭いやね、あんな男は、いくら金があったって、学問があったって、私なんかは厭だね」
「甚ひどく悪く云うな、では、ふられたね」
伊沢もその仲間入りをして近比ちかごろにない壮わかわかしい気もちになって笑っていたが、何時いつの間にか女をそっちのけにして昔の追懐へその話を持って往った。
「あの時分には、君は一升しょうぐらい飲んだって平気だったが、今でもいくだろうね」
山田は伊沢に盃さかずきをさしながら云った。
「好きは好きだが、毎晩、一合のおしきせがやっとだよ、もう弱ったね、年老としとったからなあ」
「僕も何んかの場合には、三合ぐらいなら飲むこともあるが、少し過ぎるとすぐ二日酔をやってね、いけないのだ、やはり年だね」
「そうだ、年は老とりたくないね、壮わかいうちに早く死ぬる方が、人にも惜まれて好いな、今日の追悼会の人達も生きておる時は、つまらん奴が多かったが、死んでしまや、国士だ、落伍者になって、煤くすぶって死ぬるのはいけないね」
「そうさ、玉砕ぎょくさいさ、人間は玉砕に限るよ」
雨の音が聞えて来た。
「雨だね、落おちついて好いだろう、ゆっくりやって、今晩は久しぶりに、いっしょに寝よう、すぐ近くに寝る処があるからね」
山田は伊沢に酒を酌つぐつもりで銚子ちょうしを持ってみると冷たくなっていた。婢じょちゅうはもう傍にいなかった。山田は手を鳴らした。山田も伊沢もかなり酔うていた。
山田は気が注ついてみると一人になって酒を飲んでいた。伊沢は便所にでも往ったものだろう、まさか己じぶんに黙って一人で帰ったものではあるまいと思って、廊下に音でもしはしまいかと盃さかずきを口の縁ふちに持って往ってから耳を澄ましてみた。
ところで、ぼしゃぼしゃと屋根瓦を洗う雨の音が聞えるばかりで、跫音あしおとらしい物音は聞えなかった。ついすると伊沢は己に黙って帰ったかも判らない。婢を呼んで訊きいてみようと思って、盃を置いて手を鳴ならそうとして両手を合わせていると、ふと己のむこうへ来て坐った者があった。山田は伊沢が便所から帰って来たものだと思った。
「君が帰ったのじゃないかと思って、婢じょちゅうを呼んで、訊きこうとしていたところだ」
山田はこう云って食卓ちゃぶだい越しに眼をやった。三十前後の微髭うすひげの生えた精悍せいかんな眼つきをした男が坐っていた。中古ちゅうぶるになった仙台平せんだいひらの袴はかまの襞ひだが見えていた。山田は見覚えのある人だと思ったがすぐには思いだせなかった。
「どうだ、山田君、君は吾輩を覚えてるかね」
それはその日、伊沢と噂をした木内種盛の昔のままの姿であった。
「木内先生でございますか」
「ああ、木内だ、君とは一昨年、君が油井伯の遺稿を編纂へんさんしている時、逢あったことがあるね、吾輩はあの時、青木寛の一家に復讐した話をして、もうこれから永遠の安静に入ると云ったが、今日は君達はじめ、当年の政友から追悼を受けたので懐かしくなって来た、やって来たついでに、また君に逢いたくなったからね」
山田はいずまいを正してお辞儀をした。
「吾輩が閥族ばつぞく政府に覘ねらわれ、胃腸病で入院中を、閥族に買収せられた青木のために、吾輩の死んだことは、君も知っているはずだ、当時野党の中堅となっていた吾輩を倒して、野党を粉砕したので、予算の大削減にも遭あわず、瀕死ひんしの状態にあった内閣の命脈を、一年ぐらい続けたから、閥族としては、彼に爵位を与える位のことは、何なんでもなかったさ、そこで、吾輩の復讐となったが、満伊みつい商会の支店長となって、米国へ往っていた青木の長男を、女優に迷わせたり、投機に手を出させたりして、会社の金を費つかわせて自殺さしたことと、弟の医学士の五つになる小供を殺し、その次に、医学士の神経を狂わして、細君さいくんと父親の間を疑わせたりしたことは、あの時、君に話したはずだ」
山田は返事のかわりにお辞儀をした。
「話は顛倒てんとうするが、その医学士だ、この二三日前ぜんの新聞にあったから、君も見ているだろう、何とか云う料理屋の主婦おかみの大手術をして、病人がその日の中うちに死んでしまったので、病人の家では、訴訟を起してるが、これも吾輩のやったことじゃ、その医学士は、暫しばらく養生しているうちに、神経の狂くるいもとれて来た、そのうち、あの親父おやじが死んでしまったのだ、それも偶然じゃないのだ、しかし、善良な者はそんなめには遭あわさない、あの料理屋の主婦おかみも、一種の悪党だ、医学士の犠牲にさしてもかまわないから犠牲にしたさ」
「それくらいのことはあっても好いはずです、実に怪けしからん奴です」と山田は憤激したように云った。「吾われは今でも、先生が彼のために歿なくなられたことを思うと、実に彼の肉を喫くっても飽き足らない程に思います」
「おい、おい、山田君、君は何を云ってるのだ、もう帰ろうじゃないか」
伊沢の声がするので山田はびっくりして眼を睜みはった。己じぶんは知らないバーでテーブルに向って腰をかけていた。
「ここは一体どこだ」
「ここは銀座の尾張町おわりちょうの角かどだよ」
「何時いつここへやって来た」
「三十分ぐらい前にやって来たが、君は一体何を云ってるのだ」
「僕か、僕は木内先生の夢を見てたのだよ」と考えて、
「どうもおかしいなあ、木内種盛先生と話をしてたつもりだが」
戸外そとでは雨の音がして硝子がらすに霧のような物が懸かかっていた。電車の音がけたたましく聞えて来た。
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第三巻」改造社
1934(昭和9)年
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
雨夜草紙
田中貢太郎
小さくなった雨が庭の無花果いちじくの葉にぼそぼそと云う音をさしていた。静かな光のじっと沈んだ絵のような電燈の下で、油井あぶらい伯爵の遺稿を整理していた山田三造さんぞうは、机の上に積み重ねた新聞雑誌の切抜きりぬきや、原稿紙などに書いたものを、あれ、これ、と眼をとおして、それに朱筆しゅふでを入れていた。当代の名士で恩師であった油井伯爵が死亡すると、政友や同門からの推薦によって、その遺稿を出版することになり、できるなら百日祭までに、伯爵が晩年の持論であった貴族に関する議論だけでも活字にしたいと思って、編纂へんさんに着手してみると、思いのほかに時間がとれて、仕事が進まないのでその当時は徹夜することも珍しくなかった。
一時間も前から眼を通していた二十頁ページに近い菊判の雑誌の切抜がやっと終った。三造は一服するつもりで、朱筆しゅふでを置き、体を左斜ひだりななめにして火鉢ひばちの傍にある巻煙草の袋を執とり、その中から一本抜いてマッチを点つけた。夜よはよほど更ふけていた。さっき便所へ往った時に十二時と思われる時計の音を聞いたが、それから後のちは時間に対する意識は朦朧もうろうとなっていた。ただ時間と空間に支配せられた、頗すこぶる疲労し切った存在が意識せられるに過ぎなかった。
雨の音はもう聞えなかった。彼は二本目の煙草を点けたところで、その煙が円まるい竹輪麩ちくわふを切ったように一つずつ渦を巻いて、それが繋つながりながら飛んで往くのに気が注ついた。彼は不思議な珍らしい物を見つけたと云う軽い驚異の眼でそれを見ながら、ゆっくりゆっくり煙を吐いた。煙はやはり竹輪麩のように渦を巻いて、それが連続しながら天井の方へ昇って往った。そして、その靡なびきがぴったり止んで動かなくなったかと思うと、その煙の色がみるみる濃くなり、それが引締るようになると、ものの輪廓りんかくがすうと出来た。肩の円みと顔が見えて、仙台平せんだいひらの袴はかまを穿はいた男が眼の前に立った。三造はその中古ちゅうぶるになった袴の襞ひだの具合に見覚えがあった。
「どうだ、山田」
と、前に立った人は懐しそうに云って、机の横に胡座あぐらをかくように坐り、
「伯はくの遺稿は、もうだいぶん進んだかね、あれ程有った伯の政友同志は、皆伯を棄すて去った中で、君達数人が、ほんとうに伯のことを思っていてくれたのは、実に感謝の他はない、吾輩も晩年の伯が甚はなはだお気の毒であったから、いつも傍にいてあげた、君達はたびたび伯から、木内きうちの夢を見たよと云われたことがあるだろう、あれが吾輩の傍にいた証拠だ」
三造は膝ひざを直してかしこまっていた。彼はその場合、何の矛盾も感ぜずに、非常な敬虔けいけんな心を持って先輩に対していた。油井伯爵を首領に戴いただいた野党の中の智嚢ちのうと云われた木内種盛きうちたねもりは、微髭うすひげの生えた口元まで、三十年前ぜんとすこしも変らない精悍せいかんな容貌を持っていた。
「しかし、もう、何も往くべき処へ往った、我が党の足痕あしあとへは、もう新しい世界の隻足かたあしが来ている、吾輩の魂も、これから永遠の安静に入いるべき時が来たから、最後の言げんとして、君にまで懺悔ざんげして置きたいことがあってやって来た」
三造は頭をさげた。
「君は、吾輩が至誠しせい病院で斃たおれたことを覚えているだろう」
眼に残っている金盥かなだらいの血、俄然容態が変って危険に陥おちいったと云う通知を得て、あたふたと駈かけつけて往く先輩の一人に跟ついて、至誠病院の病室へ入った三造は、呼吸いきを引きとったばかりの木内の顔に、白いガーゼのかけてあるのを見た。その枕頭まくらもとには死人の吐いた血が金盥の中に冷たく光っていた。
(しまった、しまった、しまった)
感情家の先輩は、両手をひしと握りしめて、その拳こぶしを胸のあたりで上下に揮ふり動かしながら、床をどしどしと踏んだ。そこには至誠堂病院の院長青木寛かんをはじめ、二三人の医師が粛然しゅくぜんとして立っていた。先輩の眼は院長に往った。
(何故なぜ死んだのです、何故死んだのです、木内君は何故死んだのです)
先輩の眼は憎悪に燃えていた。
(急に容態が変じました、いろいろと手を尽してみましたが、どうも残念でした)
院長はすまして云った。その冷ひややかな調子は三造にまで反感をおこさせた。
(残念と云ってしまえばそれまでだが、この男の体をどう思っているのです)
先輩は怒鳴どなりだした。当時閥族ばつぞく政府へ肉薄して、政府をして窘窮きんきゅうの極に陥おとしいれていた野党の中でも、その中堅とせられている某党の智嚢ちのうの死亡は、野党にとっての一大打撃であった。三造は先輩の憤激するのも無理はないと思った。
(実にお気の毒です)
院長はまた冷ひややかに云った。先輩の眼は金盥かなだらいに往った。先輩の熱した頭はやや醒さめかけていた。
(胃腸の病やまいに、こんなに血を吐くことがあるのですか)
(無いにもかぎりません)
(しかしどうもおかしいのですね、これまで木内君は、ちょいちょい胃腸が悪いが、何時いつも五六日位、口養生くちようじょうさえすれば、すぐ癒なおったし、今度も別に大したこともないが、下宿では政友が押しかけて来て煩うるさいから、保養のつもりで入院すると云ってた位だから、こんなことはあらわれないはずだ)
(私もはじめには、たいしたことはないと思っておりましたが、急にこんなになりました、どうもお気の毒です)
そこへ三四人の同志が来たので、その先輩と院長の応対はそれっきりになったが、その後あとでも同志の中では、三造の先輩と同じように木内の死因に疑いを挟んで、院長と交渉した者もあったと云うことを聞いた。また、その野党の総理であった油井伯爵は、関西方面へ旅行中、旅先でそれを聞いて驚いて帰京したが、これまたその死因を疑って、死体を解剖に附ふすると云って口惜くやしがったけれども、結局そのままになってしまった。三造はその当時、その周囲から口ぐちに、
(木内君は毒殺せられた)
と云うことを聞いた。そして、その院長が次第に社会的に栄達えいたつして、男爵を授さずけられた時にも、
(木内を殺した功こうさ)
と、云うようなことを云う者があって、忘れていた過去の記憶を呼び起されたこともあった。……
「あれは、君、僕はあの時、青木のためにガラスの粉末を飲まされたのだ、それを青木に頼んだ者は、三田尻みたじりと山口さ、実に卑怯千万ひきょうせんばんな奴だが、謀はかりごとは見事図に当って、野党の歩調が乱れ、予算の大削減にも逢あわず、内閣も倒壊せずに済んださ、その時から青木は、もう男爵になることになっていた」
三造はまた頭をさげた。
「僕はこの悪漢に対して、すぐ思い知らしてやろうと思ったが、そのままでは復讐の効力が強くないから、時節の来るのを待っていたのだ、が、その時節がとうとうやって来た、君は昨年から本年にかけて、彼奴あいつの家に大きな不幸の来たのを知ってるだろう、それさ、彼奴は思いのままに男爵になり、金にも名誉にも不足が無くなったので、このうえは、二人の男の子を立派な人間にしたいと思いだした、彼奴が時どき己じぶんの室へやで、細君さいくんや親しい朋友ともだちに向って、
(あの二人さえ、一人前の人間になってくれるなら、もう何も遺憾いかんなことはない)
などと云っているのを見て、僕は、
(今に見ろ、一人前の人間になりかけたところで、復讐してやるぞ)
と呟つぶやいたことがあったさ、それで、二人とも大学を出たので、彼奴は知人の間を運動して、兄の方の小供を満伊みつい商会へ入れ、弟は医科だから、己の経営している病院の副院長と云う事にしたのだ、
復讐の舞台が出来たのだよ、
そこで昨年になって、サンフランシスコの支店長となった兄の子の方から手をくだしたのだ、爺親おやじの血を受けて、意志の強い比較的厳格な奴を、先まずオペラへ引きだして、その座の人気役者で腕の凄い女に関係さして、その手でうんと金を絞らしたら、奴やっこさん苦しくなり、部下となっている遊朋友あそびともだちに勧められて、投機に手を出したところが、みるみる六十万円と云う穴を開けてしまったさ、それで、一方女の方では、年少とししたの情夫があって、奴さんから絞り執とった金を、その情夫と媾曳あいびきの費用にして遊んでいたのを、奴さんうすうす知って、煩悶はんもんしているところへ、投機の一件が本店の方へ知れて、本店から急に呼び返されたのでいよいよ困り、このうえはなんとか身の所置をしなくてはならないと思って、考え考え、ふらふらと彼かの女の許もとへ、足の向くままに往ってみたさ、ホテルの三階になった彼かの女の室へやへは、年少とししたの情夫が来ていて、微暗うすぐらい電燈の下で話していたが、奴さんは入口へ立って扉ドアを叩たたこうとすると、不思議に開あいているので、そのまま静しずかに入って往ったのだ、中の二人は睦むつまじそうに話しているところへ、不意の闖入者ちんにゅうしゃがあったので、びっくりして離れ離れになって起たちあがったが、入って来た者が奴さんだと知ると、平生へいぜいからばかにしきっている女は、
(犬のようにそっと入って来るなんて、貴郎あなたはよっぽど卑怯者ひきょうものですわね)
と云うと、奴さんしかたなく笑いながら、
(そう云ってくれるな、開あいていたから入ったまでだ、たくらんでそっと入ったものじゃないよ)
と、穏かに云ったものの、うすうす知っている情夫の青年と睦じそうにしているところを見せつけられたので、頭の中は穏かでなかった、
(だから日本人は嫌いと云うのですよ、嘘つき、今私が締めた扉ドアが、どうして開あいてるのです、なにか私の秘密でも探ろうと思って、合鍵を持って来て、それで開けたのでしょう、出て往ってください、一刻も置くことはなりません)
と、女は情夫との媾曳あいびきの場所を見られた腹立ちまぎれに怒鳴どなりだした、すると奴やっこさんむらむらとして来た。
(よし、お前のような恩知らずの畜生ちくしょうのところには、おれと云ってもおってやらないさ、帰る)
と云うと、
(帰ってくださいとも、犬のような奴は、一刻も置くことは出来ません、帰ってください、出てください)
と、女は奴さんに向って進んで来て、突き飛ばしそうにする、奴さんも肱ひじを張って女を迎えようとしたが、思い返して室へやの外へ出た、女は追って来て扉ドアをぴしりと締めたさ、室へやの出口には、蒼白あおじろい瓦斯燈がすとうの光があって、その光の中に僕の顔が浮き出ていたが、奴さんは僕の顔を知らないから、
(変な顔が見えたぞ、頭の具合かな)
と、眼をつぶって頭を一つ揮ふったさ、しかし、僕はまだ顔を出していたから、奴さんまた僕の顔を見たが、もうその時は、頭の具合かなどと、己じぶんの頭を疑ってみるような反省力は無くなっている、奴さんは恐れて、螺旋形らせんけいの階段を走りおりて街路とおりへでたのだ、そして、奴さんの意識は朦朧もうろうとなってしまったさ、奴さんは人道じんどうも車道しゃどうも区別なしに歩いていると、荷物かもつ自動車がやって来たさ、奴さんは腹部を引かれて大腸が露出したが、それでも二日ばかり生きていたのだ、君は昨年の九月の新聞に、満伊商会の支店長が過あやまって自動車に轢ひかれて、死亡したと云う記事の載っていたのを読んだことがあるだろう、あれさ」
三造は頷うなずいてみせた。
「今度は医学士の弟の方だが、彼には五歳いつつになる女の子があって、悪漢のお祖父じいさんが、非常に可愛がっていたから、それからさきへやったのだ、むせむせする晩春はるさきのことだ、その小供が二階の窓の下で遊んでたから、二三本の赤い芥子けしの花を見せてやったさ、小供の心はすぐその花へ来た、小供は手を延のべて執とろうとしたが執れない、そこで、
(春はるや、春や)
と、小間使こまづかいを呼んだが、返事がないので、じれて来て、窓へ掻かきあがろうとしたが、あがれない、
(春や、春や、春やってば)
と、今度は怒って呼んだが、それでも小間使はやって来ない、僕はその花を小供の眼から離さないように努力していたものさ、そこで、小供は小さな頭をひねって、その花を執とる法を考えたが、やっと椅子いすのことを思いだして、室へやの中から、よっちょらよっちょらと引張って来て、窓際まどぎわへ据すえ、その上にあがって執ろうとしたが、花が掴つかめないので、窓の敷居の上へ這はいあがって、手を一ぱいに延べたので、そのまま下へ落ちてしまったさ、小供には気の毒だが、悪漢の悲しんでいた容さまが痛快だったね、
医師はその比ころから神経に故障が出来たのだ、ある夜よ、眼を覚してみると、並びの寝台に寝ているはずの細君さいくんの姿が見えないのだ、細君の行動に疑問を抱くようになっていた奴やっこさんは、そっと室へやを出て、廊下を通って父親の居間になっている日本間の方へ往くと、廊下のとっつきの小座敷こざしきで人の気配がするのだ、奴さん、そっと障子際しょうじぎわへ寄って耳を立てると、むし笑いに笑う女の声がするが、それがどうしても細君だ、奴さん頭がかっとなるとともに、体が顫ふるひだしたがすぐ奴さんに自制力が出来た、
(ただ亢奮こうふんする時でないぞ)
と、奴さんは歯をくいしばったのだ、そして、耳を澄まして見ると、女の声は無くなって、父親が何か小さい声で話している声が聞える、
(しかし、あの笑い声は、たしかに彼だ)
奴さんは近比ちかごろ細君の行動の怪しいことから、傍の寝台にいなかったこと、むし笑いに笑った女の声が、たしかに細君の声であったことを思いだして、世界が暗くなったのだ、しかし、
(待てよ、このことは、己じぶんの身にとって、青木一家にとって、極めて重大な事件だ、これは、好く前後を考えたうえの所置にしなければならん)
と、奴さん稍やや精神がはっきりしたので、己の寝室へ帰って往ったのだ、そして、室の中へはいってみると、細君は己の寝台の上ですやすや睡ねむっているのだ、奴さんは己の神経の狂くるいで奇怪な幻を画えがいたことに気が注つかないから、びっくりして眼を睜みはったのだ、そこで奴さんは、その晩のことは己の邪推であったと思うようになったが、それでも細君に対する疑惑は薄らがなかったさ、それから五六日して、夕方芝口しばぐちを散歩していると、背後うしろから一台の自動車が来たが、ふと見ると、それには深ぶかと青い窓掛まどかけを垂れてあった、それが奴やっこさんを追越そうとしたところで、中からちょっと窓掛を捲まいて、白い顔を出した女があった、それが細君さいくんさ、細君はその日三時から本郷ほんごうの公爵家で催す音楽会へ往っている筈はずである、おかしいぞと思って、内を透すかすと、男の隻頬かたほおが見えた、それは父親の顔であった、奴さんの眼前めさきはまた暗んだのさ、
(怪けしからん、怪しからん)
奴さん自暴自棄やけくそになって、もと往ったことのある烏森からすもりの待合まちあいへ往って、女を対手あいてにして酒を飲んでいたが、それも面白くないので、十二時比ころになって自宅うちへ帰ったさ、
(今日は大変面白うございましたよ)
と、奴さんを待っていた細君が悦うれしそうな顔をして云うのを、何も云わずに睨にらみつけたさ、細君はその凄すごい眼の光を見て、どうしたことが出来たのかと思って、口をつぐんではらはらとして立ったのだ、僕はその時、細君の横手になった大きな姿見すがたみの中へ顔を出していたが、二人とも見なかったのだ、それから五六日経たった、奴さんとろとろ睡ねむっていて、眼を開けてみると、また細君がいない、しかし何時いつかの夜のことがあっているので、好く眼を据すえて見定めてみたが、たしかにいないと云うことが判った、が、また便所へ往っていないとも限らないと思って、十分ばかり起きあがらずに待っていたが、細君は入って来ない、そこでまた廊下へ出て、廊下を日本間の方へ往ったのだ、往ってみると、怪しい囁ささやきのしていた室へやの前の雨戸が五六寸開あいているから、それを見ると、その開口あきぐちを広くして裸足はだしで庭へおりたさ、遅い月が出て、庭は明るかった、池の傍を廻って、新緑の匂においのぷんぷんする植込みの下の暗い処を歩いて、仮山つきやまの背後うしろになった四阿屋あずまやの方へ往ったのだ、四阿屋の中には、人のひそひそと話す声がしていた、枝葉の間からそっと覗のぞくと、月の陰になって中にいる人は見えないが、あまえるような女の声はたしかに細君さいくんで、他の声はがすがすする父親の声なのだ、
(なんと云う醜体だ)
と、奴やっこさんは顫ふるひだしたが、忽たちまち引返して己じぶんの寝室へ入り、机の抽斗ひきだしにしまってあった短銃ぴすとるを持って、はじめの処へ往き、また、枝葉の間から眼を出して、四阿屋のなかを透すかして見た、四阿屋の中では話声はしなかったが、もそりもそりと物の気配がしていた、
(畜生ちくしょうどもたしかにいるぞ)
と、奴さんは眼を睜みはったさ、白い手や白い顔がはっきりと暗い中に見えた、奴さんの右の手の短銃ぴすとるの音が大きな音を立てたのだ、
(貴方あなたは何をなさるのです)
奴さんが短銃ぴすとるを持ち出して往く姿をちらと見て、後あとをつけて来た細君が抱きついたのだ、四阿屋の中には僕の影がおったさ、そこへ悪漢の青木が来る、書生が来るして、発狂してしまった奴さんを執とり押えたのだ、その奴さんは、今至誠病院の一室しつで狂い廻って、悪漢の心をさんざんに掻かき乱しているが、もう長いことはないし、悪漢の寿命も今明年こんみょうねんのものさ、僕は思いどおりに復讐することができたが、こうなってみると仇かたきながらも可哀そうだ」
私にこの話を聞かしてくれた仮名かりなの山田三造君は、最後にこんなことを云った。
「それが夢であったか、起きていた時であったか、どうもはっきりしないが、その朝、隣室で小供といっしょに寝ていた妻さいが、昨夜ゆうべ遅くお客さんがありましたね、長いこと何か話してましたね、それからお客さんのかえりに、貴方あなたがお客さんに挨拶あいさつをして、玄関の戸を締めたことを、うつつに覚えておりますよと云ったが、僕にはその覚えがない」
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第三巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
2012年6月16日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
雨夜詞
田中貢太郎
給仕女のお菊さんは今にもぶらりとやつて来さうに思はれる客の来るのを待つてゐた。電燈の青白く燃えだしたばかりの店には、二人の学生が来てそれが入口の右側になつたテーブルに着いて、並んで背後の板壁に背を凭せるやうにしてビールを飲んでゐた。其所にはお菊さんの朋輩のお幸ちやんがゐて、赤い帯を花のやうに見せながら対手をしてゐた。
お菊さんは勝手の出入口の前のテーブルにつけた椅子に腰をかけてゐた。出入口には二筋の白い暖簾がさがつて、それが藍色の着物を着たお菊さんの背景になつてゐた。それは長く降り続いてゐた雨の空が午過ぎから俄に晴れて微熱の加はつて来た、何所からともなしに青葉の香のやうな匂のして来る晩であつた。お菊さんは青いカーテンの垂れさがつてゐる入口の方を見てゐた。見ると云ふよりは聞いてゐた。それはのそりのそりと歩く重だるいやうな足音であつた。
「……何を考へてるの、ゐらつしやいよ、」
お幸ちやんの顔が此方を向いたので、お菊さんは自分が北村さんを待つてゐてうつかりしてゐたことが判つて来た。
「行くわよ、」
「何をそんなに考へ込んでるの、昨夜のあの方のこと、」
それは近くの自動車屋の運転手のことで、お菊さんにはすぐそれと判つた。買つたのか貰つたのか、二三本葉巻を持つて来て、それにあべこべに火を点けながら、俺はこれが好きでね、と云つて喫んだので、二人は店がしまつた後で大笑に笑つたのであつた。
「さうよ、俺は葉巻が好きでね、」
お菊さんは男の声色を強ひながら、右の指を口の縁へ持つて行つて、煙草を喫むやうな真似をした。
「さうよ、さうよ、」
と云つてお幸ちやんが笑ひだした。
「なんだい、なんだい、へんなことを云つてるぢやないか、なんのことだい、」
お幸ちやんと並んでゐた学生の一人がコツプを口にやりながら云つた。
「面白いことよ、これよ、俺はこれが好きでね、何時もあべこべに喫むんだよ、」
お幸ちやんは笑ひながら右の指を二本、口の縁に持つて行つて煙草を喫む真似をした。
「なんだい、その真似は、何人がそんなことをするんだ、云つてごらんよ、何人だね、」
「運転手のハイカラさんよ、」
「運転手つて、自動車か、」
「さうよ、」
「それがどうしたんだ、」
「面白いのよ、昨夜……、」
お幸ちやんはそれから声を一段と小さくして話しだした。お菊さんはまた入口の方に眼をやつて北村さんのことを考へだした。お菊さんの眼の前には、肥つた色の青白い、丸顔の線の軟らかなふわりとした顔が浮かんでゐた。この月になつて雨が降りだした頃から来はじめた客は、魚のフライを注文して淋しさうにビールを飲んだ。
「此所は面白い家だね、これからやつて来るよ、」
と客が心持好ささうに云ふので、
「どうぞ、奥さんに好くお願ひして、ゐらつしやつてくださいまし、」
と笑ふと、
「私には、その奥さんが無いんだ、可愛さうぢやないか、」
客は金の指環の見える手でビールのコツプを持ちながら笑つた。
「御冗談ばつかし、」
「冗談ぢやないよ、本当だよ、先月亡くなつたんだよ、だからかうして飲みに来るんぢやないか、」
その云ひ方が何方かしんみりして嘘のやうでないから、涙ぐましい気持になつた。
「本当、」
「本当とも、だから可愛がつてくれないといけないよ、」
「お気の毒ですわ、ね、え、」
「お気の毒でございますとも、」
客は淋しさうに笑つて飲んでしまつたコツプをくれた。
「一杯ささう、おなじみになる標だ、」
「さう、では、ちよと戴きます、」
「ちよつとは駄目だよ、多く飲まないと忘れて標にならないよ、」
客はビール壜を持つてなみなみと酌をしてくれた。
「では、どつさり戴きます、」
その客は北村さんと云ふ客であつた。
「すぐこの近所でございますの、」
「すぐ其所だよ、先月越して来たばかしなんだ、深川の方にゐてね、」
「大変遠方からいらつしやいましたね、」
「さうだ、深川の方で工場をやつてたが、厭になつたからね、家に使つてる奴に譲つてしまつたんだよ、」
もしかすると奥さんが亡くなつたので、それで何をするのも厭になつて、この山の手に引つ込んだのぢやないかと思つた。
「人を使つてやる仕事は煩さいもんでね、金にはかかはらないよ、」
「さうでございませうね、」
なんの工場であつたか知りたかつたので、
「なんの工場でございます、」
「つまらん工場さ、針工場だよ、」
針工場の意味が判らなかつた。
「針工場つて、どんなことをする工場……、」
「メリヤスを織る針だよ、」
他に何人も客がなくて、それでお幸ちやんが出前を持つて行つたことがあつた。北村さんの右の手は此方の左の手首に絡つてゐた。
「お前さんは何所だね、」
「私、愛知県よ、」
「では、名古屋かね、」
「名古屋の在ですよ、」
「兄弟があるかね、」
「えゝ、兄が二人と、妹が一人あるんですよ、お百姓よ、」
「お前さん、何処かへお嫁にでも行く約束があるの、」
「そんな所ありませんわ、」
「ないことはなからう、お前さんのやうな好い女を、そのままにはしておかないよ、」
「行く所がなくつても、好い人はあるだらう、」
北村さんはあつさりと云つたが、此方の手首に絡んでゐた北村さんの手はほてつてゐた。
「私のやうな者は見向いてくれる方もないんですよ、」
「あるよ、あつたらどうする、……あつたら困るだらう、」
「あつたら有難いんですわ、」
「本当、」
北村さんの眼は此方の眼をまともに見詰めた。……
「をかしいよ、お菊さんはまた考へ込んだよ、あ、あれだよ、お菊さんは……、」
お幸ちやんの声がするので、お菊さんは夢から覚めたやうにしてその方を見た。お幸ちやんは学生に首づたへ手をやられたなりに、学生と並んで板壁に凭れて笑つてゐた。
「お幸ちやんぢやあるまいし、あたいにや、若旦那は無いんだよ、」
「あるわよ、針工場さんがあるわよ、」
「馬鹿、」
お菊さんは云ひ当てられたので、ちよつと気まりが悪るかつた。
「好いわよ、そんなに気まりを悪るがらないだつて、」
お幸ちやんの首つたまを抱いてゐる学生が口を挟んだ。
「針工場つて、何人だい、あの肥つた親爺かい、好く祝儀をくれる、」
「さうよ、針工場の旦那よ、親爺なんて云ふとお菊さんが怒つてよ、」
も一人の学生がそれを聞くとお菊さんの方を見て云つた。
「針工場夫人、此所へお出でよ、お祝に一杯あげやう、」
お菊さんはてれかくしに、
「さう、くださるの、」
と云つて腰をあげて、そのテーブルの方へ歩いて行きかけたところで、痩せた手でカーテンの端を捲つて入つて来た者があつた。背のひよろ長い黒い著物を着た、頬のすつこけた老婆であつた。それは一眼見て料理を注文に来た客であると云ふことが判つた。
「ゐらつしやいまし、」
お菊さんがそのまゝ老婆の前へ行つて立つた。
「出前を頼みたいが、」
お菊さんは見知らないはじめての客であるから、先づ所を聞いた。
「何方様でございませう、」
「はじめてですがね、この先の赤いポストの所を入つて、突きあたつてから、左へ曲つて行くと、寺がありますね、その寺について右に曲つて行くと、もう寺の塀が無くならうとする所に、右に入つて行く露次があるがね、その露次の突きあたりだよ、北村つて云ひます、」
お菊さんはもしかするとあの北村さんの家ではないかと思つた。
「北村さん、宜しうございます、お料理は何に致しませう、」
「魚のフライと、他に一ツなんでも好いから見つくろつておくれよ、家の旦那は時々此方へ来るさうだ、」
果して北村さんであつた。お菊さんはちよつと気まりが悪るかつた。お菊さんはその晩は出前の番であつた。
「魚のフライに、お見つくろいが二品、あはして三品でございますね、」
「さうだよ、早く持つて来ておくれよ、旦那が、今晩は外へ出るのもおつくうだから、家であがるつて待つてるからね、」
老婆はそのまゝひよろひよろとするやうに出て行つた。お菊さんは勝手の方へ行かうとしたが、学生やお幸ちやんに顔を見られるやうな気がした。
「お目出たう、針工場さん、」
お幸ちやんに手をかけてゐた学生が笑つた。
お菊さんは耳門を入ると、右の手に持つてゐた岡持を左の手に持ちかへて、玄関の方を注意した。青醒めたやうな光が坂の下に見る火のやうに下に見えてゐた。入つて来た露次の工合から平坦な土地のやうに感じてゐたその感じを裏切られてしまつた。其所にはたらたらとおりて行く坂路のやうな路があつた。お菊さんは不思議な家だと思ひながら足許に注意しい〳〵歩いた。
萠黄色に見える火の光とも、また見やうによつては蓴菜の茎のやうにも見える物が眼の前に一めんに立つてゐるやうに思はれて来た。そしてその萠黄色の茎は身だけよりも一層長く上に延びてゐて、それに手がかゝつたり頬が触つたりするやうに思はれた、お菊さんは立ち止つた、萠黄色の茎はゆうらりゆうらりと動いてゐるやうに見えた。お菊さんは驚いて眼を上の方にやつた。上の方は薄月がさしたやうにぼうと明るくなつてゐて、其所には蓴菜の葉のやうに円い物が一めんに浮んだやうになつてゐた。
お菊さんは不思議な家へ来たものだと思つた。そして早く玄関へ行つて、北村さんに逢ひたいと思つた。お菊さんは玄関の火に注意した。青醒めたやうな光は遠くの方に見えてゐた。お菊さんは萠黄色の茎に眼をふさいで歩き出した。
「来たのか、来たのか、」
お菊さんは吃驚して立ち止つた。黒い背のひよろ長い物が前に来て立つてゐた。それは先き店へ来た老婆の様であつた。
「遅くなつてすみません、」
「旨い物はさう手取早く出来るもんではないよ、へ、へ、へ、さあ此方へお出でよ、」
老婆は萠黄の茎を分けるやうにしてひよろひよろと歩いて行つた。お菊さんはその後から歩いた其所はもう傾斜はなくなつてゐたが、雲の上にゐるやうで足に踏堪へがなかつた。
「此所だよ、此所からお這入りよ、」
お菊さんはもう玄関のやうな青醒た光の中に立つてゐた。
「旦那、旦那、やつと来ましたよ、」
老婆の声がしたかと思ふと太つた青膨れた北村さんの顔が眼の前に見えて来た。お菊さんはほつとした。その拍子にお菊さんの呼吸があぶくのやうになつて口からぶくぶくと出た。
お菊さんは北村へ出前を持つて行つたきり帰らなかつた。バーでは手分けをして捜索したが、だいいち北村と云ふ家もなければ、何所へ行つたのかさつぱり判らなかつた。しかし客には失踪したとも云へないので、聞く者があると、
「芝の親類へお嫁に行つたんですよ、」
と云つてゐた。ところが或る雨の降る静な晩、時たま店へ来る童顔の頬髯の生えた老人がやつて来た。老人は何所で飲んだのかぐてぐてに酔つて顔を赭くしてゐた。
「おい、一人の女はどうしたんだ、」
と老人が云ふので、お幸ちやんは例によつて、
「芝の親類へお嫁に行つたんですよ、」
と云つた。老人はそれを聞くと、テーブルへ片肱をついてそれで頬を支へながら、こくりこくりとやりだしたが、急に眼を開けて云つた。
「あの女が芝なんかにゐるもんかい、あれや雨で大河からあがつて来た奴に連れて行かれたんだよ、彼奴を何んと思ふんだ、頭から顔からつるつるとしてゐたんだらう、」
老人はかう云つてから、またこくりこくりとやりだした。
底本:「伝奇ノ匣6 田中貢太郎日本怪談事典」学研M文庫、学習研究社
2003(平成15)年10月22日初版発行
底本の親本:「黒雨集」大阪毎日新聞社
1923(大正12)年10月25日
入力:川山隆
校正:門田裕志
2009年8月12日作成
2012年5月24日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
青い紐
田中貢太郎
桃山哲郎は銀座尾張町おわりちょうの角かどになったカフェーでウイスキーを飲んでいた。彼は有楽町の汽車の線路に沿うたちょっとしたカフェーでやった仲間の会合でたりなかった酔よいを充みたしているところであった。
もう客足が斑まばらになってそこには前のすぐストーブの傍のテーブルに、一組三人の客がいるばかりであたりがひっそりして、その店に特有な華やかな空気がなくなっていた。哲郎はその静かな何者にもさまたげられない環境に心をのびのびとさして、夢のような心持で宵に聞いた女の話を浮べていた。
それは放胆ほうたんな露骨な話であった。旧派俳人の子で文学志望者の壮わかい男のした話は、某婦人が奇怪な牛乳を用いたために妊娠したと云う話であった。その晩入会した美術家の一人が入会の挨拶あいさつにかえてした話は、その春歿なくなったという仲間の美術家の話であった。その仲間と云うのは、洋画家で可成かなり天才があり、絵の評判も好く、容貌も悪い方ではなかったが、どうしても細君さいくんになる女が見つからなかった。その見つからないにはすこし理わけがあった。しかし、それはごく親しい兄弟のようにしている友人でなければ判らないことであった。こんなことで洋画家の細君を見つけてやろうとした友人達も、ちょっと手にあましていたところで、そのうちに大阪の方で女学校を卒業した女があって、それが洋画家の足りないところを充みたすことができそうだと云うことになった。で、骨を折って結婚さしてみると、その目ききはすこしもちがわないで、傍はたの者を羨うらやますような仲の好い夫婦が出来た。美術家はその話の中に、
(それこそ、二人は相逢あいあうの遅きを怨うらむと云うほどでしたよ)と云う形容詞を用いて皆を笑わした。
哲郎も腹を抱えて笑ったことを思いだした。美術家はそれから洋画家夫婦にすぐ子供の生れたことを話した。その生れた子供は毎日のように婢じょちゅうの手に抱かれて、正午比ひるごろと夕方家の前へ出ていた。子供はひいひい泣いている時があった。通りかかった知己しりあいの者が訊きくと、
(奥さんは、今、旦那さまとお書斎でお話をしておりましてね)
などと云った。はじめにいた一度結婚したことのある婢は、何故なにゆえかすぐ逃げだしてしまったと云うことも思いだした。彼の考えは頻しきりに放縦ほうじゅうな女の話へ往った。彼は中学生対手あいての雑誌を編輯へんしゅうしている文学者の話した、某劇場の前にいた二人の露西亜ロシア女の処へ往って、葡萄ぶどう酒をたくさん飲まされて帰って来たと云う話を思いだした。と、発育しきった外国婦人の肉体が白くほんのりと彼の眼の前に浮ぶように感じた。
(銀座の某店の前で、ステッキを売っている婆さんに、ステッキを買うふりをして訊くと、女を世話してくれる)
何時いつも話題を多く持っている壮わかい新聞記者の話したことが浮んで来た。そこで彼はそのステッキを売っていると云う老婆に興味を感じて、そこへ頭をやったとこで時間のことが気になって来た。彼はカップに手をやったなりに顔をあげた。
時計は十二時に十五分しかなかった。彼は己じぶんの物たりなさを充みたしてくれる物は、上野の広小路ひろこうじあたりにあるような気がした。彼はすぐ広小路まで帰ろうと思った。そう思うとともに、彼の頭の一方に雨の日の上野駅の印象が浮んだ。その印象の中には赤い柿の実が交まじっていた。彼はその印象をちらちらさしながら勘定かんじょうのことを考えた。
「おい、勘定」
カップにすこし残っていたソーダ水すいを割ったウイスキーを口にしながら上野駅の印象の続きを浮べてみた。雨に暮れかけた上野駅では東北の温泉町からいっしょに帰って来た六七人の者がばらばらになって帰りかけた時、随筆家として世間に知られている親しい友人から呼び止められた。随筆家の友人は土産みやげにと持って来た柿の籠かごをいっしょに持って往って置いてくれと云った。
(おい、けしからんことを云うなよ)
と云って笑ったことを思いだした。随筆家の友人と話題を多く持っている壮わかい新聞記者が、糠雨ぬかあめのちらちら降る中を外の方へ歩いて往った姿も浮んで来た。その二人は前晩ぜんばん泊った温泉町から電報を打って停車場ていしゃじょうもよりの家へ某事を頼んであるので、その家へ往って夜よを明かし、己の家へは翌朝の汽車で帰ったような顔をして帰ると云うことになっていた。彼は二人を見送ってから車を雇い、随筆家の友人の柿もいっしょに積んで、大塚の家へ帰ったことを思いだした。
そこへ十八九に見える姿の好い女給が勘定書かんじょうがきを持って来た。彼はインバの兜衣かくしから蟇口がまぐちを出してその金を払うとともにすぐ腰をあげた。
哲郎は電車に揺られてうっとりとなりながら女のことを考えていた。その女の中には彼かの洋画家の細君さいくんであると云う女の、想像になった長い骨を蒼白あおじろくくるんだ肉体も浮んでいた。
一二年前ぜんに横浜の怪しい家で知った独逸ドイツ人の混血児と云う女の肥った肉体もその中に交まじっていた。それ等らの女の肉体は電車の動くたびに動くような気がした。
客のすくない電車の中は放縦ほうじゅうなとりとめもないことを考えるにはつごうがよかった。彼の頭の中には細ほっそりした小女こおんなの手首の色も浮んで来た。
「……黒門町くろもんちょう」
哲郎は夢から覚めたように眼を開けて己じぶんと云う物に注意してから、今度は車の前の方へ眼をやった。そして、彼は次に来る広小路を乗りすごさないようにと思った。
ちょっと車体に動揺を感じて、それがなくなったところですぐ停とまってしまった。電車はもう広小路へ来ていた。哲郎はすぐ起たっておりた。他にも二人の客がその後うしろからおりて来たが、物の影の走るように彼の傍を通り抜けて電車の前を横切り、大塚早稲田方面の電車の停まる呉服店ごふくてんの角かどの方へ走って往った。
哲郎は微暗うすぐらい中に立っていた。風のない空気の緩んだ街頭はひっそりとして、物音と云っては今彼を乗せて来た電車が交叉点こうさてんを越えて上野のほうへ走っている音だけであるが、それさえ夢の国から来る物音のように耳には響かなかった。四辻よつつじのむこう角かどになったカフェーのガラス戸を開いて、二三人の人影が中からにょこにょこと出て来たがそこにもなんの物音もしなかった。哲郎はその物音のしないのが物たりなかったが、しかし、広小路へ来たと云う満足が彼の気もちを傷つけなかった。彼はとにかくむこうへ往こうと思ってカフェーの方へ歩いた。
廐橋うまやばしのほうから来たらしい電車がやはり何の音もさせないで来るのを見た。哲郎はゆっくりとレールの上を踏んで歩いた。と、後うしろから来て彼の左側をすれすれに通ってむこうへ往こうとする者があった。それは壮わかい小柄な女であった。女は揮ふり返るようにちょと白い顔を見せた。女は長い襟巻えりまきをしていた。
彼はすぐこの女はどうした女であろうと思った。こうして十二時を過ぎているのに一人で歩いているところを見ると、決して正しい生活の女でないと思った。そう思うとともに彼は探していた物を探しあてたような気がした。
「もし、もし」
彼は何か女に云ってみようと思った。と、女はまた白い顔をちらと見せた。
「路みちが判らなくて困ってるのですが」
女の口元が笑うようになって見えた。彼は安心して女の方へ寄ろうとした。と、女の体はひらひらと蝶ちょうの飛ぶようにむこうへ往って、もうカフェーの前を越えていた。彼は失望した。失望するとともにあの女はある種の女ではないと思った。
むこうから鳥打とりうちを冠かぶりインバを着た男が来た。哲郎はこの男は刑事か何かではないかと思った。彼はそうして今女に話しかけようとしたことを思いだして、もしあんな時に追っかけでもしていようものなら、ひどい目に逢あわされたかも判らないと思った。彼はすこし気が咎とがめたが、しかし、むこうの方に幸福が待っているような気がするので、引返そうとする気もしなければ、そこのカフェーへ入ろうとする気も起らなかった。
夜店の後うしろの街路とおりには蜜柑みかんの皮やバナナの皮が散らばっていた。哲郎はそこを歩きながら今の女はどこへ往ったろうと思ってむこうの方を見た。むこうには微暗うすぐらい闇があるばかりで人影は見えなかった。彼は女はどこかこのあたりの者だろうと思った。
哲郎は戸の閉しまった蕎麦屋そばやの前へ来ていた。微かすかに優しい声で笑うのが聞えた。彼はその方へ顔をやった。壮わかい女が電柱に身を隠すようにして笑っていた。それは長い襟巻えりまきで口元を覆うようにしたあの女であった。
「あ」
哲郎はもう何も考える必要はなかった。彼は女の傍へ往った。
「僕は電車に乗って帰るのが惜おしいような気がするから、こうしてぶらぶら歩いてるのです、どうです、いっしょに散歩しませんか、すこし遅いことは遅いが」
女は電柱を離れて寄って来た。黒い眼と地蔵眉じぞうまゆになった眉がきれいであった。
「あなたは、どちらです、遠いのですか」
「近いのですよ」
「どうです、散歩しませんか、どっか暖い物をたべる家でも好いのですが」
「そうね、でも、もう遅いから、私の家へまいりましょう」
「往っても好い、かまわないのですか」
「私、一人ですから好いのですよ」
「下宿でもしているのですか」
「間借をしているのですよ、二階の屋根裏の穢きたない処よ」
「けっこうですな」
もう女は歩きだした。哲郎は何かたべ物でも買って往きたいと思いだしたが、さて何を買って好いやら、この夜更よふけに何があるものやらちょと思いだせなかった。
「何か買って往きましょうか、たべる物でも」
女は顔をこちらに向けた。
「もう何も売ってやしませんわ、好いでしょう、家へ往きゃ何かつまらん物がありますから」
「そうですか」
哲郎は怪しい女の生活を思い出してキューラソー位はあるだろうと思った。彼はもう何も云わずに女に跟ついて歩いた。
女はそこの横町よこちょうを左へ曲った。むこうから待合まちあいの帰りらしい二人の壮わかい男が来たが、その二人の眼は哲郎の方へじろじろと注そそがれた。彼はきまりが悪かった。
「こっちよ」
女の小さな声がした。女は狭い路次ろじを入った。哲郎は暗い処で転ばないようにと脚下あしもとに注意しいしい往った。左の方はトタン塀べいになって、右側に二階建の長屋らしい家の入口が二つ三つ見えた。
「黙ってついてらっしゃい」
女はそこの入口の雨戸をそうと開け、それから格子戸こうしどを開けて入った。哲郎も続いて入ったが、下の人に知れないようにと咳せきもしなかった。
あがり口の右側に二階の梯子段はしごだんが薄うっすらと見えていた。哲郎は女に押あげられるようにされてあがって往った。
上には蒼白あおじろい燈ひの点ついた六畳の室へやがあった。室の中には瀬戸物の火鉢ひばちがあって、それを中に二枚の蒲団ふとんが敷いてあった。むこうの左隅には小さな机があって、その上に秋海棠しゅうかいどうのような微紅うすあかい草花の咲いた鉢はちを乗せてあるのが見えた。
「穢きたない処よ」
女は後うしろの障子しょうじを締めて入って来た。哲郎は立ってインバのボタンをはずしていた。
「お坐りなさいましよ」
女は襟巻えりまきを机の上へ乗せて、その方を背にして一方の蒲団の上に坐った。哲郎もインバを脚下あしもとへ置いてから、女と向きあうようにその青い地に何か魚の絵を置いたメリンスの蒲団の上に坐った。
二人の手と手は火鉢の上で絡みあった。
哲郎は女の顔を見るのがまぶしかった。
「どうです」
哲郎は笑った。彼はそれ以外に云う詞ことばがなかった。
女も笑っていた。女の眼は絡からみあっている哲郎の手端てさきへ来た。
「暖あったかいわ、ね」
「会があって今まで飲んでいたから、暖あったかいでしょう」
「お酒をおあがりになって」
「すこし飲むのです」
「じゃ、お酒をあげましょうか」
「ありますか」
哲郎は形式だけでも酒があると話がしよいと思った。
「ありますわ、私いただかないから、貰ったのをそのままにしてあるわ」
女は顔をあげて右の鴨居かもいの方を見た。そこには小さな棚があってボール箱もあれば木箱も見えていた。
「味はどうですか、青い色をした酒よ」
女がそう云って起たとうとするので、哲郎は絡んでいた指を解いた。と、女は起って棚の黄きいろなボール箱に手をやろうとしたが達とどかなかった。
「執とろう、飲む者が執りましょう」
哲郎は起って女と並んだ時、爪立つまだちを止やめた女の体がもったりと凭もたれて来た。哲郎はその女の体を支えながらボール箱に手をやった。と、今まで気が注つかなかった天井から垂れている青いワナになった紐ひもが、ちらと眼に注つくとともにそれがふわりと首に纏まつわった。彼は左の手でそれを払いのけようとしたところで、凭れかかって来た女の体に石のような力が加わって彼の体を崩してしまった。彼は唸うなり声を立てた。
哲郎が意識を回復した時には、微暗うすぐらい枕頭まくらもとに二人の男が立っていた。
「お前さんは何なんだね、ここへ何しに来たのだね」
哲郎は女に伴つれられて下の人に知らさずにそっと来ていることに気が注ついた。彼はこうなれば女に弁解して貰うより他に手段がないと思った。彼は起きて四辺あたりを見たが女の姿は見えなかった。
「ここにいる女の方といっしょに来たのですが、どこへ往ったのでしょうか」
「ここにいるって、ここには何人だれもいないが、何人にも貸してないから」
「おかしいな、僕はそこの蕎麦屋そばやの前でいっしょになってやって来て、棚に酒があると云って女が執とろうとしたが、棚が高くて執れないから、私が執ってやろうとすると、女が凭もたれかかって来る拍子に、そこの天井からさがってた青い紐ひもが、首へかかって、それっきり知らなくなったのですが」
哲郎は棚の方を見た。紐もなければ古い煤すすけた棚には何も見えなかった。
「判った、よし、好い、まあ、下へお出いで、お前さんに話がある」
それは頬ほおから頤あごにかけて胡麻塩髯ごましおひげの見える労働者のような男であった。哲郎は意味が判らなかったが、腑ふに落ちないことだらけであるから、とにかくくわしいことを聞こうと思って、傍にあるインバを持ち、前さきになっておりて往く二人の後あとから跟ついて往った。
胡麻塩の男はそこの主翁ていしゅで、一人は隣家の男であった。主翁は火のない長火鉢ながひばちの傍で小さな声で云った。
「五六年前ぜんに、バーの女給をしてた女が、なんでも男のことかなんかで、あすこで死んだそうですよ、私達は一昨年移って来て何も見ないが、へんなことがあると云って、貸す人も貸す人も三月とはいないのですよ」
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第一巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
ある神主の話
田中貢太郎
漁師の勘作かんさくはその日もすこしも漁がないので、好きな酒も飲まずに麦粥むぎかゆを啜すすって夕飯ゆうめしをすますと、地炉いろりの前にぽつねんと坐って煙草を喫のんでいた。
「あんなにおった鯉こいが何故なぜ獲とれないかなあ、あの山の陰には一疋ぴきや二疋いないことはなかったが、一体どうしたんだろう」
その夜は生暖な晩であった。地炉に焚たく榾ほだの火が狭い荒屋あばらやの中を照らしていた。
「二尺位ある二疋の鯉……二尺位の鯉が二疋欲しいものだなあ」
勘作は村の豪家ごうかから二尺位ある鯉を二疋揃えて獲ってくれるなら、云うとおりの値で買ってやると注文せられているので、二三日前からその鯉を獲ろうとしているが、鯉は愚おろかろくろく雑魚ざこも獲れなかった。
「網では獲れそうにもないから、明日あすは釣ってみようか、あの淵ふちの傍で釣ってみてもいいな、釣るがよいかも知れないぞ」
勘作は酒の気けがないので、もの足りなくてしかたがなかった。
「勘作さん家かな」
何人たれかが入って来た。漁師仲間の何人かが話しに来たろうと思って庭を見ると、色の白い小柄な男が来て立っていたが勘作には見覚えのない顔であった。
「お前さんは何人であったかな、俺わしはものおぼえが悪いから」
「お前さんは知らないかも判らない、私は近比ちかごろこの村へ来た者だから」
「そうか、それなら、これからおつきあいをしよう、さあ、おあがり」
「そんじゃ、あげてもらおうか」
小柄な男はそう云って地炉いろりの傍へあがった。
「お前さん、国はどこだね」
「東の方だ、東の方からぶらぶらやって来たが、この辺はいい処だね、漁もあるだろう」
「もとはあったが、近比ちかごろはめっきり無くなった」
「そうかなあ」
「それにこの二三日は、すこしもないので、今晩はすきな酒も廃やめている」
「そうか、それはいかんなあ」
「二尺の鯉こいを二疋ひき獲とってくれと、二三日前から頼まれて、この広い湖へ片かたっ端ぱしから網を入れているが、鯉は愚おろか、雑魚ざこもろくろくかかりゃしない」
「そんなことは無い、私は近比ちかごろ来た者だが、それでも鯉の二疋や三疋は、買手を待たして置いても獲って来る」
勘作は出まかせなことを云う対手あいてがおかしくてたまらなかった。彼は大声で笑いだした。
「お前さんが嘘と思うなら、私がこれから往って獲とって来てやろう、網はどこにあるかな」
「網は外の柿の木に乾してあるが、お前さん、狐きつねにでも撮つままれているじゃないか、俺わしはこの浦で二十年来漁師をやっているが、買手を待たして置いて獲る程鯉こいは獲れないよ」
「嘘と思うなら私が獲って来てやろう、待ってるがいい」
小柄な男はひょいと庭へおりて外へ出て往った。勘作は冷笑を浮べながら煙草を喫のんでいたが、櫓ろの音がしだしたので湖に面したほうの障子しょうじを開けてみた。朦朧もうろうとした月の光の射さした水の上に岸を離れたばかりの小舟が浮んで、それが湖心のほうへ動いていた。櫓を押おしている小柄の男の姿も見えていた。
「俺に獲れないものが、あんな、小僧ッ子に獲れてたまるか」
勘作は障子を締めて横になって煙草を喫んでいた。そして、小半時こはんときも経たたないところで跫音あしおとがして小柄な男が帰って来た。勘作が舟の中へ置いてあった空笊からざるを小脇こわきにしていた。
「勘作さん、どうだな、注文の鯉を獲って来たが」
勘作は起きあがって笊の中を覗のぞいた。大きな二尺ばかりの鯉が四疋ひきと、他に鮒ふなや鮠はやなどが数多たくさん入っていた。勘作は驚いて眼を睜みはった。
「注文の鯉を持って往けば、金をくれるだろう、これで一杯買おうじゃないか」
勘作は小柄な男を待たして置いて、その鯉こいを持って鯉の注文を受けている豪家ごうかへ往って二疋ひきを売り、後あとの二疋を宿の旅籠はたごへ売ってその金で酒を買って帰った。
「お前さんの名はなんと云うんだ」
勘作が酒を注つぎながら云うと小柄な男は笑った。
「名はなんでも好いじゃないか、これから朋友ともだちになったから、ちょいちょい飲みに来るよ」
「好いとも、飲もう」
小柄な男は明方まで飲んで帰った。勘作はその男の素性すじょうが不思議でたまらなかった。翌日になって仲間の漁師達に聞いても何人だれも知っている者がなかった。
小柄な男はその夜よをはじめとして折おりおりやって来た。そして勘作が漁がなくて困っていると、彼は勘作の網を持ってちょっとの間どこかへ漁に往ったが、何時いつでも数多たくさんの魚を獲とって来た。
勘作と小柄な男との間は三年ばかり続いた。勘作はもう小柄な男の素性を怪しいとも思わなければ、素性のことを考えもしなかった。某夜あるよ、平生いつものようにその小柄な男がやって来て二人で酒を飲みだした。
「勘作さん、お前さんは、私をなんと思っているかな」
小柄な男が云うと勘作はすまして云った。
「なんとも思っていないよ、俺はお前さんが、鬼でも蛇じゃでもかまわないよ」
「私は人間じゃない」
「どうせ、そんなことだろうと思った、なんだな」
「水におる者だ」
「河童かっぱか」
「河童じゃないが、まあ、そんな者さ」
「それも好かろう」
「ところで、私は不自由だから、ひとつ人間になりたいと思っている」
「どうして人間になる」
「人間の体を借りるつもりだ」
「何時いつ借りる」
「明日あす、午うまの比ころ、この傍の路みちを旅人が通るから、その笠かさを飛ばして、それを執とりに水に入って来るところを引込んで、その体を借りるつもりだ」
「そうすると、その人はどうなる」
「その人間は死ぬるが、私がその体を借りるから、他の人には判らない」
「そんなくだらんことは廃よせ、やはり今までどおりで飲もうじゃないか」
勘作は何時の間にか睡ねむって水の男が帰ったのも知らなかった。そして、朝になって水の男の云った詞ことばをおもいだしたが、気の広い勘作はすぐ忘れてしまって漁に往き、午飯ひるめしに帰って飯をすまし、庭前にわさきの柿の立木たちきに乾ほしてある投網とあみの破れ目を繕つくろうていると、家の傍の路みちを一人の旅人が通って往った。勘作はふと水の男が笠を落すと云ったことを思いだして旅人のほうに眼をやった。と、さらさらと風が吹いて来て旅人の冠きていた笠が、ひらひらと飛んでそれが湖の水際みずぎわに落ちた。と、旅人は慌てて水際へおりて往こうとした。勘作ははっと思った。彼は走って往って大声で止めた。
「おい、おい、水へ入ってはいかん、魔物が棲すんでおるから引込まれる」
旅人は水の中に足を入れようとして止やめた。
「あぶない、あぶない、そこには魔物が棲んでおる」
旅人は笠をそのままにして、路みちへあがって来て勘作に礼を云ってさっさと前方むこうへ往ってしまった。
水の男は勘作の顔を見るなり怒鳴どなりだした。
「やい、勘作さん、おまえさんのような情じょうなしがどこにある、おまえさんはなんの怨うらみがあって、私の仕事の邪魔をした」
勘作は膳前ぜんさきに一本飲んでいるところであった。
「なんだ、なんのことだ」
「なんのことだ、おい勘作さん、とぼけちゃいけないよ、今日、俺が旅人の笠かさを飛ばして、旅人を引込んで、人間になろうとしていると、お前さんが走って来て、そこには魔者が住んでおる、入られんと云ったのを忘れたのか、おい勘作さん、忘れたとは云わせないよ」
「ああ、そのことか、そのことなら覚えている」
「だから、なんの怨みがあって、そんなことをしたかと云っているんだ、それを云ってもらおう」
「そうか、そのことか、そりゃお前さんがいけねえ、お前さんが人間になりたいと思って、他の人間を殺すのは道にはずれている、そりゃ、いくらお前さんと朋友ともだちでも、そんなことはいけねえ、それとも、お前さんは、道にはずれていると思わないのか」
「そりゃ、罪もない人間を殺すのは、ちと気の毒じゃが、それ位のことは、眼をつぶらねばいけない」
「それは己じぶんかっての理窟りくつじゃ、そんな道にはずれたことはいけない、まあお前さんもつまらん望みを起さずに、今までどおりにつきおうて、旨い酒を飲もうじゃないか、まああがるがいい」
水の男は地炉いろりの傍にあがって酒を飲みだした。
「人間になったところで、たいしたこともない、このままで俺と何時いつまでも旨い酒を飲もう」
勘作と水の男は、又三年ばかりの交まじわりを続けたが、某夜あるよ水の男は又勘作に云った。
「今度こそ人間になる決心をした、人間になったら、お前さんの処へ来られる」
「どうして人間になる」
「夫婦喧嘩をしている者があって、女房の方が家を飛び出して来ることになっているから、それを引込むつもりだ」
「そうか、どこでやる」
「この傍へ来る、明日あすの晩の亥いの刻こくじゃ」
翌晩になると勘作は、又水の男の云ったことが気になりだした。彼は亥の刻になると外へ出て湖水縁こすいべりの路みちを歩いた。星の多い夏の夜よであった。と、前方むこうからばたばたと足音をさして走って来る者があった。勘作は星の光に透すかして見た。色の白い女が肌もあらわになって走っている。いよいよ家出女房であると思っていると、女はふと足を止めて水の中へ眼をやった。勘作は背後うしろからそっと往って、今にも飛び込もうとしている女をしっかと抱き止めた。女は勘作の手を揮ふり放はなして飛び込もうとする。二人が争っているところへ女の所天ていしゅはじめ隣家となりの者が三四人やって来た。勘作は女を渡して帰って来た。
水の男はもう勘作の家へ来て坐っていた。
「おい勘作さん、お前さんは、なんと云う意地悪だ、何故なぜ私が人間になる邪魔をする」
勘作は莞爾莞爾にこにこ笑いながら上へあがった。
「お前さんも又、殺生せっしょうなことまでして何故なぜ人間になりたいのだ、そんなことは、ふっつり思い切ったらどうだ」
「思い切れないからこそ、やってるじゃないか、何故邪魔をする」
「お前さんは、そんなことを云うが、お前さんに生命いのちを奪とられて体を借かられる人間の身になってみたらどうだ、俺が邪魔をするわけも判るよ」
「そりゃ、人間には可哀そうさ、だが私の身になったらどうだ」
「お前さんのことは道にはずれているから、そんなことは話にならんさ」
「お前さんは意地悪で困る」
「まあ、酒でも飲もう、宵のあまりがあるから、そいつを飲みながら話そう」
二人の交まじわりは又三年ばかり続いた。そして、その年の春であった。某夜あるよ水の男は勘作が寝ている枕頭まくらもとへ来た。
「私は、お前さんのおかげで悪いこともせずにやってたから、今度、神になって祭られることになった。これからこの湖では余り漁もないし、お前さんも年が往って仕事をするが苦しかろうから、私の処へ来て神主かんぬしになるがよい、場所はこの家の前の路みちを西へ西へと十日ばかり往くと、大きな川がある、その川の土手だからすぐ判る」
翌日になって勘作は、水の男の云ったことを考えてみたがどうも真箇ほんとうにできない。で、そのままにして相変らず漁師をやっていたが、それから水の男も来なければ漁もなくなったので、水の男の云ったことを思い出してその年の秋船も網も捨てて西へ向って出発した。
水が枯れて河原の広広ひろびろとした大きな河が来た。勘作はこの河ではないかと思って、渡船場わたしばにおりようとする河土手になった林の中を注意して歩いていた。と、路みちの上に新しい石磴いしだんがあって、やはり新らしい檜ひのきの小さな鳥居とりいが見えた。勘作はたしかにこれだと思ってその石磴をあがって往った。
夕陽の中を蜻蛉とんぼが二つ三つ飛んでいた。石磴をあがり詰めると檜の香かの紛紛ふんぷんする小社こやしろがあった。勘作はその前に往って頭をさげて拝んだ。
「勘作か、よう来た」
それは聞き覚えのある水の男の声であった。勘作は頭をあげて木連格子きつれごうしの間から中の方を見たがなにも見えなかった。
「二三日のうちに家もできる、それまでは、堂の内で寝るがいい」
勘作は縁えんに腰をかけて、肩に打ちかけた風呂敷包を置いた。
「お前はこれから、村へ往って来るがいい、その石磴いしだんをおりて村の方へ歩いて往くと、牛を牽ひいた老人としよりが来る、その老人としよりに、今、水神様すいじんさまのお告げがあったが、今晩、大水おおみずが出るから、河原へ乾ほしてある稲は、すっかり執とりこまなければならんと云うがいい」
勘作はその詞ことばに従って石磴をおりて往った。そして、土手を内へ入って人家のある方へ歩いていると、果はたして牛を牽いた老人ろうじんがやって来た。
「もし、もし、私は、今、水神様のお告げを受けたから、村へ知らしに往っております、今晩は大水が出るから、河原へ乾してある稲を執りこまないと流れると云うことです」
老人ろうじんは半信半疑の顔をした。
「この天気続きに、おかしいなあ、しかし、神様のお告げと云うことなら、村の衆へ知らすことは知らしてやろう」
老人ろうじんは牛を牽いて帰って往った。勘作はそのまま社やしろへ帰って、堂の上へあがってみると酒や飯めしが三宝さんぽうに盛ってあった。
「勘作、腹が空すいたら、それを喫くうがいい」
勘作はその酒を喫のみ、飯を喫った。水の男は姿を見せなかったが、傍で勘作の対手あいてになった。
その夜よ大水があった。水神のお告げを信じて稲を執り入れた者は無事であったが、それを疑ってそのままにしてあった者は皆流してしまった。
村の人びとは、翌日水神すいじんの告げを知らして来た旅の男を水神の社やしろの内に見つけて、それを神主かんぬしとして置くことになり、社の傍にその住居をかまえた。
底本:「日本怪談大全 第二巻 幽霊の館」国書刊行会
1995(平成7)年8月2日初版第1刷発行
底本の親本:「日本怪談全集 第二巻」改造社
1934(昭和9)年
入力:川山隆
校正:門田裕志
2012年5月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
朝倉一五〇
田中貢太郎
洋画家の橋田庫次くらじ君の話であるが、橋田君は少年の頃、吾川あがわ郡の弘岡村へ使いに往って、日が暮れてから帰って来たが、途中に荒倉あらくらと云う山坂があって、そこには鬼火が出るとか狸がいるとかと云うので、少年の橋田君は鬼魅きみがわるかった。
橋田君はその時自転車に乗っていた。やがて荒倉の麓へ来たので、自転車をおりて、それを押し押しあがって往ったが、暗くはなるし人っ子一人通らないのでひどく淋しかった。そしてやっとの思いで峠へたどりついた。峠には一軒の茶店があって、門口に提灯を点つけた一台の人力車がいたが、それには朝倉一五〇としてあった。朝倉一五〇の提灯を持っているからには、朝倉の車夫であろう。兎とにかく一休しようと思って茶店の入口へ往った。すると傍から声がした。
「哥にいさん、どうせ乗って往きや」
どうせ乗って往きやという事は変ないいまわしであった。橋田君は厭な気がした。そこで、
「うん」
と云ったきりで、茶店へ寄る事もよして、そのまま自転車に飛び乗って坂路を駈けおりた。
かなり勾配のある坂路であるから、自転車はすうすうと滑って往った。そして、中央なかごろまで往ったところで、後から一台の人力車が来て、橋田君の自転車を駈けぬけて走ったが、すこしも轍わだちの音を立てなかった。橋田君はどうした車だろうと思って眼をやった。車には朝倉一五〇の提灯が点いていた。橋田君は眼を睜みはった。一生懸命に駈けおりている自転車を、あれからすぐ追っかけて来たところで、人間わざでは駈けぬけることはできない。橋田君はちょっと変に思った。
やがて麓へおりて、途が二つに岐わかれた処へ往った。その路を左へ往けば、朝倉連隊に往くようになっていた。と、見ると、地の底からでも出て来たように、そこへ一台の人力車が来て、朝倉連隊へ往く方の路へ折れて往った。橋田君はおやと思ってそれに眼をやった。その車にも朝倉一五〇の提灯が点いていた。
底本:「伝奇ノ匣6 田中貢太郎日本怪談事典」学研M文庫、学習研究社
2003(平成15)年10月22日初版発行
底本の親本:「新怪談集 実話篇」改造社
1938(昭和13)年
入力:Hiroshi_O
校正:noriko saito
2010年10月20日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
怪しき旅僧
田中貢太郎
──此の話は武蔵の川越領の中の三ノ町と云う処に起った話になっているが、此の粉本は支那の怪談であることはうけあいである。
それは風の寒い夜のことであった。三ノ町の某ある農家の門口へ、一人の旅僧が来て雨戸を叩いて宿を乞うた。ところで農家ではもう寝ようとしているうえに、主翁ていしゅは冷酷な男であったから初めは寝たふりをして返事をしなかったが、何時までたっても旅僧が去らないので、「もう寝たから、他よそへ往って頼むが好い」と、叱るように云った。
「そうでございましょうが、日が暮れて路がわからないうえに、足を痛めて、もう一足も歩けません、どうかお慈悲に庭の隅へなりと泊めてくださいまし」と、旅僧は疲れ切ったような声で云った。
主翁は返事をしなかった。
「他へ往くと申しましても、暗くて路も判りませんし、足が痛くて一足も歩けませんから、どうぞお慈悲をねがいます……」と、旅僧は動かなかった。
主翁はしかたなく慍おこり慍り起きて来た。
「……寝ておるからほかへ往けと云うに、強情な人じゃ」と、入口の戸を開けて暗い中から頭をだして、「其のかわり、被るものも喫うものも何もないよ」
「いや、もう、寝さしていただけばけっこうでございます」
旅僧は土間へ入って手探りに笠を脱ぎ、草鞋を解いて上にあがった。消えかけた地炉いろりの火の微に残っているのが室へやの真中に見えた。旅僧は其の傍へ往って坐ったが、主翁は何もかまってやらなかった。
「そんじゃ、おまえさんは其処で寝るが好い、私も寝る」と、主翁は其のまま次の室へ往こうとした。
「明りはありますまいか」と、旅僧は呼びとめるように云った。
「はじめに云ったとおり、何もないよ」
主翁は邪慳に云って障子を荒あらしく締めて寝床の中へ入ったが、それでも幾等か気になるので枕頭の障子の破れから覗いた。
と、地炉の火の光で頭だけ朦朧と見えていた旅僧の右の手は、其の時地炉の火の中へ延びて往った。明りが欲しいので火を掻き起しているだろうと思っていると、急に室へやの中が明るくなった。それは旅僧の右の手の指に、一本一本火が点いて燃えているところであった。主翁は恐れて気が遠くなるように感じた。彼は体を動かすこともできないでぶるぶる顫えながら覗いていた。
奇怪な旅僧はやがて左の手で拳をこしらえて、それをいきなり一方の鼻の穴へ押し込んだが、みるみるそれが臂まで入ってしまった。そして、まもなくそれを抜いて鼻を窘めてくさみをするかと思うと、鼻の穴から二三寸ばかりある人形が、蝗の飛ぶようにひょいひょいと飛び出して、二三百ばかりも畳の上に並んだ。旅僧はこれを見て何か顎で合図をすると、其の人形は手に手に鍬を揮って室の中を耕しはじめた。そして、それが終ると何処からともなく水が来て、室の中は立派な水田になった。で、人形どもはそれに籾を蒔いた。籾はみるみる生えて、葉をつけ茎が延びて、白い粉のような花が咲き、実が出来て、それが黄ろく熟した。人形どもは鎌でそれを刈りとって穂をこき、籾をつき、それを箕みにかけてまたたくまに数升の米にした。
人形どもの仕事が終ると、旅僧は大きな口をぱくり開けて、それを掻き集めて一口に飲んでしまった。そして、庭の方を向いて、「来い来い」と云うと、庭の片隅の竈へっついにかけてあった鍋と、水を汲んである手桶がふらふらと歩くように旅僧の傍へ来た。
で、旅僧は其の鍋の中へ米と水を入れて、地炉いろりの自在鉤にかけた後で左右の足を踏み延ばして、それを炉縁に当て何時の間にか傍に来ていた鉈で、膝節から薪を割るようにびしゃびしゃと叩き切って、其の切れを地炉の中にくべると、火が盛んに燃えだして鍋の飯が煮立って来た。旅僧は膝節から下が切れて血みどろになった足を平気で投げだして火をみていたが、やがて飯ができると鍋をおろして手掴みで喫いはじめた。
飯がなくなると、旅僧は手桶の杓をとって一口水を飲んだが、咽喉へ入れたあまりを地炉の火の上へ吐きだした。すると地炉は泥池になって水が溢れるようになるとともに、ふいふいと蓮の葉が浮きだして白と紅くれないの蓮の花が一時にぱっと咲き、数多たくさんの蛙が集まって来て声をそろえて喧しく鳴きだした。
恐れて死んだ人のようになって此の容さまを見ていた主翁ていしゅは、此の時やっと気が注いたのでそっと裏口から這い出て往って隣家の者に話した。隣家の者は、「それこそ妖怪ばけものだ、逃がすな」と云って、各自てんでに棒や鍬を持って主翁に跟いて来た。
そして、裏口からそっと入ってみると、室は元の室へやになって、旅僧は地炉の傍に仰向けになってぐうぐうと鼾をかいて睡っていた。
「睡っている、睡っている」と、手引して来た主翁が小声で囁いた。
「じゃ、そっと往って捕まえろ」と、云って十五六人の男はそろそろと入って往き、不意に飛びかかって旅僧の手足を捕えた。そのうちに一人は其の頭をしかと掴んだ。
と、旅僧は眼を覚して皆の顔を一わたり見渡した。かと思うと、押えつけた人びとの手の下からふっと抜けた。
「それ逃げたぞ」
「叩き殺せ」
皆の者は用意して来た棒や鍬を持って叩き伏せようとしたが、旅僧の姿はひらひらと室の其処此処に閃くばかりでどうすることもできなかった。室の隅に酒を入れてあった大きな徳利が転がっていた。旅僧の姿はひょこひょこと其の中へ入ってしまった。
「妖怪ばけものは徳利に入ったぞ、しっかり蓋をしろ」と、其の口へ栓をした者があった。
「代官所へ持って往こう」と、云って一人の男がそれを持とうとしたが、重くて持ちあがらなかった。
其のうちに徳利は室の中をころがりだした。
「また逃げだしたぞ、しかたがない、徳利を打ち砕け」と、云う者があった。
一人の男が鍬を揮りあげて徳利を微塵に打ち砕こうとした。徳利の中から黒い煙が出るとともに雷のような音がして徳利は二つに破れた。人びとは驚いて後に飛び退った。
旅僧の姿はもう見えなかった。
底本:「日本怪談全集 Ⅱ」桃源社
1974(昭和49)年7月5日発行
1975(昭和50)年7月25日2刷
底本の親本:「日本怪談全集」改造社
1934(昭和9)年
入力:Hiroshi_O
校正:大野裕
2012年9月25日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
美女を盗む鬼神
田中貢太郎
梁りょうの武帝の大同の末年、欧陽紇おうようこつという武人が、南方に出征して長楽という処に至り、その地方の匪乱ひらんか何かを平定して、山間嶮岨さんかんけんその地へ入った。その紇は陣中に妻を携えていたが、その女は色が白く顔が美しかった。するとその地方の人が、
「君は何故美女を携えてここへ来た、ここには鬼神があって、美女と見れば必ず盗むので、往来の者でこの難に罹かかる事がある、君も能よく守るがいい」
と言った。紇はまさかと思って疑ったが、それでも軍士に命じて家の外を衛らし、妻には十余人の侍女をつけて奥深い処に置いてあった。最初の晩は別に何事もなかったが、翌晩は烈しい風が吹き荒れた。夜半よなかになって皆が疲れて睡ったところで、妻と枕を並べて寝ていた紇は、うなされて眼が開いたので、妻の方を見るともう妻の姿が見えない。驚いて起きあがったが、戸締とじまりも宵のままになっているに係わらず、どこへ往ったのか見えない。戸外そとへ出て探そうにも、家の前はすぐ深山になっていて不用意には探せない。朝になるのを待ちかねて探したが、手がかりになる物も見当らなかった。
紇は最愛の妻を失った事であるから大いに怒り悲しんで、
「女を得なければ帰らない」
と心に誓い、朝廷の方へは病気という事にして兵を留め、日にち々付近の山谷の間を探し歩いた。そして月を越えたところで、妻の履いていた韈くつを一つ拾った。それは駐屯地から支那の里程で百里ばかり往った処であった。紇はそこで三十人の精兵を選んで、糧食を余分に用意してまた深山に分け入ったが、十日の後に二百里外の土地へ往った。
そこには南方に当って半天に鑚そそり立った高山があった。その山の麓には谷川が滔々とうとうと流れていた。紇の一行は巌角いわかどを伝い、樹の根に縋って、山の中へ入ったが、往っているうちに、女の笑い戯れる声がした。紇は恠あやしみながらその声をしるべにしてあがって往くと、大きな洞門があって、その前の花の咲き乱れた木の下で、数十人の美女が蝶の舞うように歌い戯れていた。紇の一行が往くと女らは別に驚きもせず、
「何しにここへ来た」
と言った。紇がその訳を話すと、
「その婦おんなならここに来て三月になるが、今は病に罹って寝ている」
と言って、紇を誘いざのうて中へ入った。
病床にいた妻は紇の顔を一眼見ると、手を振って、
「ここへ来ては危険だ、早く出て往け」
と言った。紇を誘いざなうてきた美女達は、
「妾わたしらも君の妻と同じく、鬼神のために奪われてきたもので、久しい者は十年にもなる、この鬼神は能く人を殺すが、百人の者が剣を持って一斉にかかっても勝つことができない、今は他行中であるから帰らないうちに早く往くがよい、もし鬼神を斃そうと思えば、美酒びしゅ一斛こく、犬十頭、麻数十斤を用意してくるがよい、そして、重ねてくる時は、午後にくるがよい、それも、今日から十日という事にして約束しよう」
と言った。
紇は悦よろこんで山をおり、その約束の日を違たがえないように、一切の物を用意して鬼神の棲家すみかへ往った。美女の一人はそれを見て戸外そとへ出てきて、
「鬼神は酒を好み、酔うと、五色の練絹ねりぎぬを以て手足を床に縛らし、一度に躍りあがると、絹は皆切れる、もし、その絹を三幅はば合せて縛ると切れない、今、絹の中に麻を入れて縄にして縛ると、どんな事があっても切れる事がない、そして、鬼神の体は鉄のように固いが、ただ臍ほぞの下五六寸の処を、彼が常に覆いかくすのを見ると、そこから刃やいばが通るらしい」
と言い、また傍の巨巌を指して、
「これは鬼神の食物を斂おさめる処である、酒を花の下に置き、犬をそこここの樹下に繋いでから、時刻のくるまでここに隠れているがよい」
と教えた。
紇はその言葉に従い、酒を置き、犬を繋いで巌の陰に隠れて待っていると、申さるの刻になって白練団びゃくれんだんのような者がどこからともなく飛んできて、洞門の中へ入った。そして、暫くすると鬚のある綺麗な男が白絹の衣服を著、片手に杖を曳き、美女達を伴つれて出てきたが、犬を見つけると、片っ端から躍りかかって引裂いて旨そうに喫くった。犬を喫ってしまうと、美女達は花の下に置いてある酒を取りあげて我さきにと勧めた。男は歓んでそれを飲んでいたが、六七升ばかりも飲むと非常に酔ってきた。美女達はその手を取って洞ほらあなの中へ入ったが、歓び笑う声が一頻ひとしきり聞えてきた。紇は巌の陰で合図のあるのを待っていた。と、美女の一人が出てきて、
「早く早く」
と言って招いた。紇は軍士を率いて洞の中へ突進した。四足を床に縛られた大きな白猿が、敵と見て起きあがろうとしたが、練絹の中に麻縄があるので、引切る事ができないで、眼を電光のように怒らして悶掻もがいた。紇の軍士は競いかかって刀を当てたが、巌鉄のようで刃が通らない。そこで紇は美女の言った事を思いだしてその臍下を刺した。鬼神は、
「これは天が我を滅したものだ、汝らの力の及ぶところでない」
と言い、また、
「汝が妻は既に姙んでいるから、その子を殺さないで置け、必ず賢王に遇うて家を起す」
と言い畢おわって死んだ。
紇はそこで軍士に命じて、鬼神の掠奪してきた財宝を収め、美女の数を検べてみると美女は三十人いた。美女達は鬼神の事を細ごまと話して、
「鬼神に奪われてきた女の中で、色の衰えた者は、いつの間にかいなくなった、鬼神は毎朝、手を洗い、帽子を被り、白い衣の上にやはり白い羅うすものの衣被うわぎを著て、古文字のような物を書いた木簡もっかんを読んだ、読み終るとそれを石の下に置いて、今度は剣を舞わして身を躍らしたが、恰あたかも電光のようであった、食物は定まった物はなく、平生は果実を喫っていたが、犬を非常に悪にくんで、それを見ると一滴の血も滴こぼさないように喫った、午うまの時を過ぎて他山ほかのやまへ飛び往き、晩になって帰ってきたが、欲しいと思った物は得ないということはなかった、女達に対しては言葉つきも丁寧であった、この鬼神は既に一千年の寿命がきて、死期の近い事を予期していた」
と言った。紇は財宝と美女を将いて山をおりたが、美女達はそれぞれその夫を探して帰らした。
翌年になって紇の妻は小供を生んだが、その形は猿に似ていた。後、梁が滅んで陳の朝になると、陳の武帝が紇を攻殺せめころした。紇の従者の江総こうそうという者が、その小供を隠匿して養育したが、至って敏捷活発で、鬼神の言ったとおり、後に文字を識り、書を著わして家名を揚げたのであった。
底本:「中国の怪談(一)」河出文庫、河出書房新社
1987(昭和62)年5月6日初版発行
底本の親本:「支那怪談全集」桃源社
1970(昭和45)年11月30日発行
入力:Hiroshi_O
校正:小林繁雄、門田裕志
2003年9月17日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
貧乏神物語
田中貢太郎
縁起でもない話だが、馬琴の随筆の中にあったのを、数年前から見つけてあったので、ここでそれを云ってみる。考証好きの馬琴は、その短い随筆の中でも、唐山には窮鬼と書くの、蘇東坡に送窮の詩があるの、また、窮鬼を耗とも青とも云うの、玄宗の夢にあらわれた鍾馗の劈さいて啖くらった鬼は、その耗であるのと例の考証をやってから、その筆は「四方よもの赤」に走って、「近世、江戸牛天神の社のほとりに貧乏神の禿倉ほこら有けり。こは何某なにのそれがしとかいいし御家人の、窮してせんかたなきままに、祭れるなりといい伝う。さるを何ものの所為しわざにやありけん。その神体を盗とりて、禿倉のみ残れり」などと云っているが、屁のようなことにも倫理道徳をくっつける馬琴の筆にしては、同じ堅くるしい中にも軽い味がある。
文政四年の夏であった。番町に住む旗下はたもとの用人は、主家の費用をこしらえに、下総にある知行所に往っていた。五百石ばかりの禄米があって旗下としてはかなりな家柄である主家が、その数代不運続きでそれがために何時も知行所から無理な金をとり立ててあるので、とても今度は思うように調達ができまいと思った。その一方で用人は、村役人のしかめ面を眼前めさきに浮べていた。
微曇のした蒸し暑い日で、青あおと続いた稲田の稲の葉がぴりりとも動かなかった。草加そうかの宿が近くなったところで用人は己じぶんの傍を歩いている旅憎に気がついた。それは用人が歩き歩き火打石を打って火を出し、それで煙草を点けて一吸い吸いながらちょと己じぶんの右側を見た時であった。
旅憎は溷鼠染どぶねずみぞめと云っている栲たえの古いどろどろしたような単衣ひとえものを着て、頭かしらに白菅の笠を被り、首に頭陀袋をかけていた。年の比ころは四十過ぎであろう、痩せて頤おとがいの尖った顔は蒼黒く、眼は落ち窪んで青く光っていた。
この見すぼらしい姿を一眼見た用人は、気の毒と思うよりも寧ろ鬼魅きみが悪かった。と、旅僧の方では用人が煙草の火を点けたのを見ると、急いで頭陀袋の中へ手をやって、中から煙管と煙草を執り出し、それを煙管に詰めて用人の傍へ擦り寄って来た。
「どうか火を貸しておくれ」
用人は旅僧に傍へ寄られると臭いような気がするので、呼吸いきをしないようにして黙って煙管の雁首を出すと旅憎は舌を鳴らして吸いつけ、
「や、これはどうも」
と、ちょっと頭をさげて二足三足歩いてから用人に話しかけた。
「貴君あなたは、これから何方どちらへ往きなさる」
「下総の方へ、ね」
「ああ、下総」
「貴僧あなたは何方へ」
「私わしは越谷こしがやへ往こうと思ってな」
「何処からお出でになりました」
「私わしかね、私は番町の──の邸から来たものだ」
用人は驚いて眼を〓(「※」は「目+爭」)った。旅僧の来たと云う邸は己の仕えている邸ではないか、用人はこの売僧奴まいすめ、その邸から来た者が眼の前にいるに好くもそんな出まかせが云えたものだ、しかし待てよ、此奴はなにかためにするところがあって、主家の名を騙かたっているかも判らない、一つぎゅうと云う眼に逢わして置かないと、どんなことをして主家へ迷惑をかけるかも判らないと心で嘲笑って、その顔をじろりと見た。
「──の邸、おかしなことを聞くもんだね」
「何かありますかな」
旅僧は澄まして云って用人の顔を見返した。
「ありますとも、私はその邸の者だが、お前さんに見覚えがないからね」
用人は嘲ってその驚く顔を見ようとしたが旅僧は平気であった。
「見覚えがないかも判らないよ」
「おっと、待ってもらおうか、私は其処の用人だから、毎日詰めていない日はないが、この私が知らない人が、その邸にいる理わけがないよ、きっと邸の名前がちがっているのだろう」
用人はまた嘲笑った。
「ところが違わない」
「違わないことがあるものか、ちがわないと云うなら、お前さんは、邸の名を騙る売僧じゃ」
用人は憤りだした。
「それはお前さんが私わしを知らないから、そう云うのだ、私は三代前から彼あの邸にいるよ、彼の邸は何時も病人だらけで、先代二人は夭折わかじにしている、おまえさんは譜代でないから、昔のことは知らないだろうが、彼の邸では、昔こんなこともあったよ──」
旅僧は用人の聞いている昔主家に起った事件をはじめとして、近比ごろの事件まで手に執るようにくわしく話しだした。用人は驚いて開いた口が塞がらなかった。
「どうだね、お前さん、思いあたることがあるかね」
旅僧はにやりと嘲笑を浮べながら煙草の吹殻を掌にころがして、煙管に新らしい煙草を詰めてそれを吸いつけ、
「寸分もちがっていないだろう、それでもちがうかね」
「よくあってます」
用人は煙草の火の消えたのも忘れていた。
「あってるかね、そりゃあってるよ、毎日邸で見てるからね」
用人は頭を傾げて旅僧が如何なる者であるかを考えようとした。
「私が判るかね」
旅僧は嘲笑いを続けている。
「判りません、どうした方です」
「私わしは貧乏神だよ」
「え」
「三代前から──の邸にいる貧乏神だよ」
「え」
「私わしがいたために、病人ができる、借金はできる、長い間苦しんだが、やっと、その数が竭つきて私は他へ移ることになったから、これから、お前さんの主人の運も開けて、借金も返される」
話のうちに草加の宿は通り過ぎたが、用人は霧の深い谷間にいるような気になっていて気がつかなかった。
「だから、これから、お前さんの心配も無くなるわけだ」
用人はその詞ことばを聞くとなんだか肩に背負っていた重荷が執れたような気がした。
「では、あなた様は、これから何方どちらへお移りになります」
「私わしの往くさきかの、往くさきは、隣の──の邸さ」
「え」
「其処へ移るまでに、すこし暇ができたから、越谷にいる仲間の処へ遊びに来たが、明日はもう移るよ」
用人はその名ざされた家のことを心に浮べた。
「お前さんが嘘と思うなら、好く見ているが好い、明日からその家では、病人ができ、借金ができて、恰好ちょうどお前さんの主人の家のようになるさ」
「え」
「だが、これは決して人にもらしてはならんよ」
「はい」
「じゃ、もう別れよう」
用人がはっと気がついた時にはもう怪しい旅僧はいなかった。其処はもう越谷になっていた。
用人は知行所へ往ったが、度たび無理取立てをしてあるのでとても思うとおりにできまいと心配していた金が、思いのほか多く執れたので、貧乏神の教えもあるし彼は喜び勇んで帰って来た。
底本:「日本の怪談」河出文庫、河出書房新社
1985(昭和60)年12月4日初版発行
底本の親本:「日本怪談全集」桃源社
1970(昭和45)年初版発行
※本作品中には、身体的・精神的資質、職業、地域、階層、民族などに関する不適切な表現が見られます。しかし、作品の時代背景と価値、加えて、作者の抱えた限界を読者自身が認識することの意義を考慮し、底本のままとしました。(青空文庫)
入力:大野晋
校正:松永正敏
2001年2月23日公開
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
忘恩
田中貢太郎
土佐の侍で大塚と云う者があった。格はお馬廻り位であったらしいがたしかなことは判らない。その大塚は至って殺生好きで、狩猟期になると何時も銃を肩にして出かけて往った。
某日あるひそれは晴れた秋の午後であった。雑木の紅葉した山裾を廻って唯とある谷へ往った。薩摩藷などを植えた切畑が谷の入口に見えていた。大塚はその山畑の間の小径を通って、色づいた雑木に夕陽の燃えついたように見える谷の窪地の方へ往こうとした。
一匹の灰色の兎が草の中から飛びだして大塚の前を横切って走った。獲物を見つけた大塚は、肩にしていた銃をそそくさとおろして撃とうとしたが、兎は何処へ往ったかもう見えなかった。大塚は銃を控えて右を見たり左を見たり、また木の下方を透しなどしたが、兎はとうとう見つからなかった。
(折角の獲物を逃がしてしまった、何か一つ大きなものを獲りたいぞ)
大塚はこんなことを云いながら歩きだした。彼は今朝早くから谷から谷をあさっていたが、腰の袋に一羽の山鳥を獲っているだけで他に何も獲っていないので、何か一二疋好い獣を獲りたかった。兎は彼の眼から放れなかった。彼はもしやそこらあたりに隠れていはしないかと思って、注意しいしい歩いた。
大塚は谷の窪地の隅になった処へまで往った。山畑はそこでなくなって、それから勾配のきつい登り坂になるのであった。兎はとてもいないと思ったので、銃を元の通り肩に懸けて二三歩往った。と、思うと、彼の身体は不意に脚下の穴の中へ陥ちて往った。水の少いその山畑を作る人の掘ったものであろう、二丈余りある深い山井戸であった。大塚は驚いて微暗い穴の中を見廻した。幸いにしてこぼれ土のために水のある処は埋まってしまって、僅かに草鞋の端が濡れる位の水しか湧いていなかった。
(古井戸へ陥ち込んだぞ、上へあがらねばならんが、あがれるかしら)
大塚は苔の生えた穴の周囲に注意したが、手掛りにするような処は見つからなかった。上の方はと見ると穴の入口にうっすらした陽の光があった。
(とても、彼処あすこまでは出て往けない、それに人家が遠いから、いくら大声を立てたところで、聞きつけてやって来る者もない、こいつは困ったことになった、腰にはまだ一回分の握飯は持っておるが、とてもそんなことで命を支えられるはずのものでない、こうなるのも前世の約束ごとだろう、しかたがない、井戸の中で餓死に死ぬるは武士の恥じゃ、思い切って切腹しよう、餓死にすることは、武士の恥じゃ)
大塚は肩にしていた銃をおろし、土に背をもたし腕組みして考え込んだ。
(ここで俺がこのまま切腹したとしたなら、家の女房や、小供はどうなるだろう)
彼はもう自殺をするものとして死後のことに就いて考えていた。考えているうちに何か不意に注意を促されたものがあった。彼は顔をあげて井戸の口の方を見た。井戸の口に赤い顔が見えた。
(何人たれか覗いておるぞ、人が来てくれたか、人が)
赤い顔の周囲まわりには白い毛並があった。茶色の二つの眼が光っていた。それは猿であるらしい。
(猿じゃ、人間なら引きあげて貰えるが、猿じゃしかたがない)
大塚はがっかりしたように云った。覗いていた赤い顔がきゃっきゃっと二三回声をたてたかと思うと、もう見えなくなってしまった。
(人間の真似ができると云っても、やっぱり猿は畜生じゃ)
大塚はまた腕を組んで考え込んだ。彼はまた己じぶんの死後のことをそれからそれへと考えていた。その大塚の耳に微かすかな音が入って来た。井戸の口のあたりで風でも吹いているようなどうどうと云う音であった。大塚はまた眼を開けて井戸の口の方を見た。
一掴みばかりの枝屑がぱらぱらと落ちて来た。大塚は顔を伏せてその塵を眼に入れまいとした。枝屑は首筋にも当って落ちた。大塚はまた眼を開けた。一匹の獣が井戸の上を飛び越えた。その影がかすかに入口に射している日の光に綾をした。二三枚の枯葉がまたちらちらと落ちて来た。
(初めのはたしかに猿であったが、今のは何であろう)
大塚はこう思いながらちょっとまた眼をつむって考えた。
(ついすると、猿の千匹伴が、集まって来ているかもわからん、薩摩藷でも執りに来ているだろうが、何しろ猿では助けてもらうことはできんのじゃ)
大塚はもう自殺するより他に道が無いと決心した。決心したもののなるだけなら犬死はしたくなかった。彼の心の底の方には何かしら己じぶんの危難に陥入っているのを知って助けに来てくれる者があるような気がして、刀に手をかけるまでにはゆかなかった。
(何人だれか来そうだぞ、何人か助けに来るような気がするぞ)
彼はこんな気もちでまた上の方に眼をやった。綱のようなものが一尺ほど井戸の口からさがっていた。
(不思議なものが見えて来たぞ、何だろう、何人だれかおるだろうか)
綱のようなものは三尺近くもさがって来た。
(たしかに綱じゃ、何人か俺が落ちたことを知って、助けてくれるために、綱を垂れているのだろうか、さがる、さがる、さがって来た)
綱のようなものはもう五六尺もさがって来た。それは藤葛のような大きな葛であった。葛はもう一丈以上も下へさがって来た。
(それでは、初めに猿と思った赤い顔は、猿でなしに、このあたりの人であったのか、これで俺は助かった)
大塚は穴の上の方を喜びに満ちた眼で見あげた。赤い顔がまた覗いている。それはさっきの顔であったが、赤い眼鼻の周囲まわりに白い毛の生えた大猿の顔であった。
(たしかに猿じゃ、人間ではない、では、猿がこんなことをしてくれているだろうか、そう云えば、さっき井戸の上を飛び渡った獣は、どうも猿らしかった、では猿の群が俺のここに落ちたことを知って、助けてくれようとしているのか)
藤葛はもう二丈余りもさがって大塚の頭へ届きそうになって来た。
(猿でもかまわん、助けてくれるなら、助けてもらおう、この井戸の中からだしてもらおう)
大塚はおろしてあった銃を肩にかけて藤葛の手比てごろになるのを待っていた。藤葛はしだいしだいにおりて来た。大猿の顔はまだ見えていた。大塚はその藤葛を手にしてその端を帯に差してそれを折り返した。きゃっ、きゃっと云う猿の鳴き声が聞えた。それは井戸の口にいる彼の大猿の叫びであった。大塚は手拭を出して二重になった藤葛を縛りつけそれが済むと両手を藤葛へ持ち添えて、引きあげてくれるのを待っていた。
(猿の力で、この身体があがるだろうか)
大塚は身がまえしながら疑っていた。と、藤葛が張りあって来た。やがて彼の身体が宙に浮いた。
(これで俺も助かるらしいぞ、猿に助けられるとは不思議なことじゃ)
大塚の身体は刻々に上へ上へあげられた。大塚は一生懸命に藤葛にすがっていた。そうして、二丈余りも上へあげられて井戸の口に近くなると、その口になった岩に両手を掛けた。そして、一きざみすると身体は帯際まで上に出たのであった。
数千匹もいるであろう数多たくさんの猿が、五六間さきの楢の木の根元に仕掛けた藤葛へすがりついてそれを引っ張っていた。大塚の姿が見えると猿どもは藤葛を捨ててそのあたりへ散らばった。大塚はその数多な猿を見て驚いた。その驚きとともに猿に対する礼心を忘れてしまって、猟好きな好奇心が頭を擡げて来た。井戸の口から覗いていたらしい白毛の大猿が、すぐ横手の草の上に坐って大塚の方を見ていた。
(彼あの猿じゃな、さきに覗いていたのは、立派な猿じゃ、好い猿じゃ、今日は別に何の猟もなかった、彼の猿なら好いな)
大塚はその大猿に注意を向けた。大塚は台尻に巻いた火縄に注意した。微に火が残っていた。彼は銃をおろすなり大猿を狙って火縄をさした。強い銃声とともに大猿は仆れてしまった。と、猿の間に非常な混乱が起って、蜘蛛の子を散らすように八方へ逃げてしまった。
残忍な大塚は大恩ある猿を獲物にして己じぶんの家へ帰って来た。帰って来てその猿を庭の鉤に吊し、手足を洗って明るい行灯の下で暖かな夕食を喫っていた。
「今日は大変なことがあった」
大塚は古井戸に落ちた話から、猿に扶たすけられた話を女房や婢じょちゅうなどに聞かせていた。そして、何かの拍子に行灯の傍を見ると、白い大猿が前足をついて坐っていた。
「猿が」
大塚は鬼魅悪い声を立てて引っくりかえった。
大塚はその夜から病気になって、「猿が、猿が」と叫んでいたが、とうとう死んでしまった。
この大塚家では代々猿と云うことを口にしなかった。もし、それを忘れて口にするものがあると必ず不思議なことがあったと云われている。
底本:「日本の怪談(二)」河出文庫、河出書房新社
1986(昭和61)年12月4日初版発行
底本の親本:「日本怪談全集」桃源社
1970(昭和45)年初版発行
※「(何人たれか覗いておるぞ、」は、底本では「「何人たれか覗いておるぞ、」ですが、親本を参照して直しました。
入力:Hiroshi_O
校正:門田裕志、小林繁雄
2003年7月24日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
帽子のない水兵
田中貢太郎
まだ横須賀行の汽車が電化しない時のことであった。夕方の六時四十分比ごろ、その汽車が田浦を発車したところで、帽子を冠かぶらない蒼あおい顔をした水兵の一人が、影法師のようにふらふら二等車の方へ入って往った。
(またこの間の水兵か)
それに気の注ついた客は、数日前にもやはりそのあたりで、影法師のようなその水兵を見かけていた。その時二等車の方から列車ボーイが出て来た。
「君、この間も見たが、今二等車の方へ往った水兵は、なんだね」
列車ボーイは眼をくるくるとさした。
「帽子のない水兵でしたか」
「そうだよ」
「入って往ったのですか」
「往ったとも、気が注かなかったかね」
「それじゃ、また出たのか」
「出たとは」
「そんなことを云いますよ」
客はその後で、列車ボーイから、三人伴づれの水兵が、田浦方面へ遊びに往っていて、帰りにその一人が帽子を無くしていたので、それがために、途中で轢死れきししていると云うことを聞かされた。
底本:「伝奇ノ匣6 田中貢太郎日本怪談事典」学研M文庫、学習研究社
2003(平成15)年10月22日初版発行
底本の親本:「新怪談集 実話篇」改造社
1938(昭和13)年
入力:Hiroshi_O
校正:noriko saito
2010年10月20日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
牡丹燈籠 牡丹燈記
田中貢太郎
日本の幽霊は普通とろとろと燃える焼酎火しょうちゅうびの上にふうわりと浮いていて、腰から下が無いことになっているが、有名な円朝えんちょうの牡丹燈籠ぼたんどうろうでは、それがからこんからこんと駒下駄こまげたの音をさして生垣いけがきの外を通るので、ちょっと異様な感じを与えるとともに、そのからこんからこんの下駄の音は、牡丹燈籠を読んだ者の神経に何時いつまでも遺のこっていて消えない。
この牡丹燈籠は、「剪燈新話せんとうしんわ」の中の牡丹燈記ぼたんとうきから脱化したものである。剪燈新話は明みんの瞿佑くゆうと云う学者の手になったもので、それぞれ特色のある二十一篇の怪奇談を集めてあるが、この説話集は文明年間に日本に舶来はくらいして、日本近古の怪談小説に影響し、延ひいて江戸文学の礎石そせきの一つとなったものである。
牡丹燈記の話は、明州めいしゅう即ち今の寧波にんぽうに喬生きょうせいと云う妻君さいくんを無くしたばかしの壮わかい男があって、正月十五日の観燈かんとうの晩に門口かどぐちに立っていた。この観燈と漢時代に太た一の神を祭るに火を焚たき列つらねて祭ったと云う遺風から、その夜よは家ごとに燈ともしびを掲げたので、それを観みようとする人が雑沓ざっとうした。本文ほんもんに「初めて其その耦ぐうを喪うしのうて鰥居無聊かんきょむりょう、復また出いでて遊ばず、但ただ門に倚よつて佇立ちょりつするのみ。十五夜や三更こう尽きて遊人ゆうじん漸ようやく稀まれなり。丫鬟あかんを見る。双頭そうとうの牡丹燈ぼたんとうを挑かかげて前導ぜんどうし、一美び後うしろに随したがふ」と云ってあるところを見ると、喬生は妻君さいくんを失うた悲しみがあって、遠くの方へ遊びに往く気にもなれないで、門に倚よりかかってぼつねんとしていたものと見える。そして三更こうがすぎて観燈の人も稀にしか通らないようになった時、稚児髷ちごまげのような髪にした女の児こに、頭かしらに二つの牡丹の花の飾かざりをした燈籠とうろうを持たして怪しい女が出て来たが、その女は年の比ころ十七八の紅裙翠袖こうくんすいしゅうの美人で、月の光にすかしてみると韶顔稚歯しょうがんちしの国色こくしょくであるから、喬生は神魂瓢蕩しんこんひょうとう、己じぶんで己を抑えることができないので、女の後あとになり前さきになりして跟ついて往くと、女がふりかえって微笑しながら、「初めより桑中そうちゅうの期き無くして、乃すなわち月下げっかの遇ぐう有り、偶然に非あらざるに似たり」と持ちかけたので、喬生は、「弊居咫尺へいきょしせき、佳人かじん能よく回顧すべきや否や」と、云って女を己の家へ伴つれて来て歓愛を極めた。素性すじょうを聞くと故もとの奉化県ほうかけんの州判しゅうはんの女むすめで、姓は符ふ、名は麗卿れいきょう、字あざなは淑芳しゅくほう、婢じょちゅうの名は金蓮きんれんであると云った。女おんなはまた父が歿なくなって一家が離散したので、金蓮と二人で月湖げっこの西に僑居かりずまいをしているものだとも云った。
女はその晩を初めとして、日が暮れると来て夜よが明けると帰って往った。半月ばかりして喬生の隣に住んでいる老人が、壁に穴をあけて覗のぞいてみると、喬生がお化粧をした髑髏どくろと並んで坐っているので、大おおいに駭おどろいて翌日喬生に注意するとともに、月湖の西に女がいるかいないかを探りに往かした。喬生は老人の詞ことばに従って湖西こせいへ往って女の家を探ったが何人だれも知った者がなかった。夕方になって湖の中に通じた路みちを帰っていると、そこに湖心寺こしんじと云う寺があったので、ちょっと休んで往こうと思って寺へ入り、東の廊下を通って西の廊下へ往ったところで、廊下の往ゆき詰つめに暗室があって、そこに棺桶かんおけがあって紙を貼はり、故もとの奉化府州判の女むすめ麗卿の柩ひつぎと書いてあった。そして、その柩の前に二つの牡丹の飾のある燈籠を懸かけ、その下に一つの盟器婢子わらにんぎょうを立てて、それには背の処に金蓮と云う文字を書いてあった。喬生は恐れて寺を走り出て隣家まで帰り、その夜よは老人の家に泊めてもらって、翌日玄妙観げんみょうかんと云う道教の寺にいる魏法師ぎほうしの許もとへ往った。魏法師は喬生に二枚の朱符しゅふをくれて、一つを門かどに貼り一つを榻ねだいに貼るように云いつけ、そのうえで二度と湖心寺へ往ってはいけないと云って戒いましめた。
喬生は帰って魏法師に云われたようにしたので、その晩から怪しい女は来なくなった。一月あまりして袞繍橋こんしゅうきょうに住んでいる友人の許へ往って酒を飲み、酔って帰ったが魏法師の戒いましめを忘れて湖心寺のほうの路みちから帰って来た。そして、寺の門の前へ往ってみると、金蓮が出ていて、「娘子じょうし久しく待つ、何ぞ一向いっこう薄情是かくの如ごとくなる」と、云って遂に喬生と倶ともに西廊せいろうへ入って暗室の中へ往くと、彼かの女が坐っていて喬生をせめ、その手を握って柩の前へ往くと、柩の蓋ふたが開ひらいて二人を呑のんでしまった。喬生の隣家の老人は喬生が帰らないので、あちらこちらと尋ねながら湖心寺へ来て、暗室へ往ってみると柩の間から喬生の衣服の裾すそが微かすかに見えていた。で、僧に頼んで柩をあけてもらうと、喬生は女の髑髏どくろと抱きあって死んでいた。
これが牡丹燈籠の原話げんわの梗概こうがいであるが、この原話は寛文かんぷん六年になって、浅井了意あさいりょういのお伽婢子とぎぼうこの中へ飜案ほんあんせられて日本の物語となり、それから有名な円朝の牡丹燈籠となったものである。
伽婢子では牡丹燈籠と云う題になって、場所を京都にしてある。五条京極きょうごくに荻原新之丞おぎわらしんのじょうと云う、近き比ころ妻に後おくれて愛執あいしゅうの涙袖そでに余っている男があって、それが七月十五日の精霊祭しょうりょうまつりをやっている晩、門口かどぐちにたたずんでいると、二十ばかりと見える美人が十四五ばかりの女めの童わらわに美しき牡丹花ぼたんのはなの燈籠を持たして来たので、魂飛び心浮かれて後あとになり前さきになりして跟ついて往くと、女の方から声をかけたので、己じぶんの家へ伴つれて来て和歌を詠よみあって懐おもいを述べ、それから観眤かんじを極めると云う殆ほとんど追字訳ついじやくのような処もあって、原話げんわからすこしも発達していないが、西鶴以前の文章の第一人者と云われている了意の筆になっただけに棄すてがたいところがある。そして、その物語では女は二階堂左衛門尉政宣にかいどうさえもんのじょうまさのぶの息女そくじょ弥子いやことなり、政宣が京都の乱に打死うちじにして家が衰えたので、女めの童わらわと万寿寺ばんじゅじの辺ほとりに住んでいると荻原に云った。荻原は隣家りんかの翁おきなに注意せられて万寿寺に往ってみると浴室の後ろに魂屋たまやがあって、棺かんの前に二階堂左衛門尉政宣の息女弥子吟松院冷月居尼ぎんしょういんれいげつきょにとし、側そばに古き伽婢子とぎぼうこがあって浅茅あさぢと云う名を書き、棺ひつぎの前には牡丹花ぼたんのはなの燈籠の古くなったのを懸かけてあった。荻原は驚いて逃げ帰り、東寺とうじの卿公きょうのきみと云う修験者しゅげんじゃにお符ふだをもらって来て貼はると、怪しい物も来ないようになったので、五十日ばかりして東寺に往って卿公に礼を云って酒を飲み、その帰りに女のことを思いだして、万寿寺に往って寺の中を見ていると、彼かの女が出て来て奥の方へ伴つれて往ったので、荻原の僕しもべは肝きもを潰つぶして逃げ帰り、家の者に知らしたので皆で往ってみると、荻原は女の墓に引込まれて白骨と重なりあって死んでいた。
円朝の牡丹燈籠はこの了意の牡丹燈籠から出発したものである。ただ場所も東京になり物語も複雑になって、怪談は飯島家のお家騒動の挿話のようになっているが、了意の飜案ほんあんから出発したと云うことについては争われないものがある。それはお露つゆと云う女に関係した浪人の萩原はぎわら新三郎の名が、荻原新之丞をもじったものであるにみても判ろう。円朝の物語は長いからここにははぶくとして、新三郎が怪しい女に逢あった晩の数行を引用してみると、「今日きょうしも盆の十三日なれば、精霊棚しょうりょうだなの支度したくなどを致して仕舞ひ、縁側えんがわへ一寸ちょっと敷物を敷き、蚊遣かやりを燻くゆらして新三郎は、白地の浴衣ゆかたを着深草形ふかくさがたの団扇うちわを片手に蚊を払ひながら、冴さえ渡る十三日の月を眺めて居ますと、カラコンカラコンと珍らしく駒下駄こまげたの音をさせて、生垣いけがきの外を通るものがあるから不図ふと見れば先へ立つものは、年頃三十位の大丸髷おおまるまげの人柄のよい年増としまにて、其頃そのころ流行はやった縮緬細工ちりめんざいくの牡丹ぼたん芍薬しゃくやくなどの花の附いた燈籠を提さげ、其後そのあとから十七八とも思われる娘が、髪は文金ぶんきんの高髷たかまげに結ゆい、着物は秋草色染あきくさいろぞめの振袖ふりそでに、緋縮緬ひぢりめんの長襦袢ながじゅばんに繻子しゅすの帯をしどけなく結び、上方風かみがたふうの塗柄ぬりえの団扇うちわを持つてパタリパタリと通る姿を月影に透すかし見るに、どうも飯島の娘お露つゆのやうだから、新三郎は伸び上り、首を差延さしのべて向ふを看みると女も立ち止まり、「マア不思議じゃア御座ございませんか、萩原さま」と、云はれて新三郎も気が浮き、二人を上にあげて歓愛に耽る」と云うことになっているが、この物語では、萩原の裏店うらだなに住む伴蔵ともぞうと云う者が覗のぞいて、白翁堂勇斎はくおうどうゆうさいに知らし、勇斎の注意で萩原は女の住んでいると云う谷中やなかの三崎町みさきちょうへ女の家を探しに往って、新幡随院しんばんずいいんの後うしろで新墓しんはかと牡丹の燈籠を見、それから白翁堂の紹介で、新幡随院の良石和尚りょうせきおしょうの許もとへ往って、お守をもらって怪しい女の来ないようにしたところで、伴蔵が怪しい女にだまされてお守をのけたので、怪しい女は新三郎の家の中へ入って、新三郎をとり殺すと云うことになっている。
元げんの末に方国珍ほうこくちんと云う者が浙東せっとうの地に割拠すると、毎年まいねん正月十五日の上元じょうげんの夜よから五日間、明州みんしゅうで燈籠を点つけさしたので、城内じょうないの者はそれを観みて一晩中遊び戯れた。
それは至正庚子しせいこうしの歳としに当る上元の夜のことであった。家家の簷のきに掲げた燈籠に明るい月が射さして、その燈ひは微紅うすあかくにじんだようにぼんやりとなって見えた。喬生きょうせいも己じぶんの家の門口かどぐちへ立って、観燈の夜よの模様を見ていた。鎮明嶺ちんめいれいの下に住んでいるこの壮わかい男は、近比ちかごろ愛していた女房に死なれたので気病きやまいのようになっているところであった。
風の無い暖かな晩であった。観燈の人人は、面白そうに喋しゃべりあったり笑いあったりして、騒ぎながら喬生の前を往来ゆききした。その人人の中には壮い女の群もあった。女達はきれいな燈籠を持っていた。喬生はその燈に映しだされた女の姿や容貌が、己の女房に似ていでもするといきいきとした眼をしたが、直すぐ力の無い悲しそうな眼になった。
月が傾いて往来の人もとぎれがちになって来た。それでも喬生はぽつねんと立っていた。軽い韈くつの音が耳についた。彼は見るともなしに東の方に眼をやった。婢女じょちゅうであろう稚児髷ちごまげのような髪をした少女に燈籠を持たせて、そのあとから壮い女が歩いて来たが、少女の持っている燈籠の頭かしらには真紅の色のあざやかな二つの牡丹の花の飾かざりがしてあった。彼の眼はその牡丹の花から後あとの女の顔へ往った。女は十七八のしなやかな姿をしていた。彼はうっとりとなっていた。
女は白い歯をちらと見せて喬生の前を通り過ぎた。女は青い上衣うわぎを着ていた。喬生は吸い寄せらるるようにその後あとから歩いて往った。彼の眼の前には女の姿が一ぱいになっていた。彼はすこし歩いたところで、足の遅い女に突きあたりそうになった。で、左斜ひだりななめにそれて女を追い越したが、女と親しみが無くなるような気がするので、足を遅くして女の往き過ぎるのを待って歩いた。と、女は揮ふり返って笑顔を見せた。彼は女と己との隔てが無くなったように思った。
「燈籠を見にいらしたのですか」
「はい、これを伴つれて見物に参りましたが、他に知った方はないし、ちっとも面白くないから帰るところでございます」
女は無邪気なおっとりとした声で云った。
「私は宵からこうしてぶらぶらしているのですが、なんだか燈籠を見る気がしないのです、どうです、私の家は他に家内がいませんから、遠慮する者がありませんが、すこし休んでいらしては」
「そう、では、失礼ですが、ちょっと休まして戴いただきましょうか、くたびれて困ってるところでございますから」
と、云って燈籠を持った少女の方を見返って、
「金蓮、こちら様でちょっと休まして戴きますから、お前もお出いで」
少女は引返して来た。
「直すぐ、その家ですよ」
喬生は己じぶんの家のほうへ指をさした。少女は燈籠を持って前さきに立って往った。二人はその後あとから並んで歩いた。
「ここですよ」
三人は喬生の家の門口かどぐちに来ていた。喬生は扉とを開けて二人の女を内へ入れた。
「あなたのお住居すまいは、どちらですか」
喬生は女の素性すじょうが知りたかった。女は美しい顔に微かすかに疲労の色を見せていた。
「私は湖西こせいに住んでいる者でございます、もとは奉化ほうかの者で、父は州判しゅうはんでございましたが、その父も、母も亡くなって、家が零落れいらくしましたが、他に世話になる、兄弟も親類もないものですから、これと二人で、毎日淋しい日を送ってます、私の姓は符ふで、名は淑芳しゅくほう、字あざなは麗卿れいきょうでございます」
喬生はたよりない女の身が気の毒に思われて来た。
「それはお淋しいでしょう、私も、この比ごろ、家内を亡なくして一人ぼっちになってるのですが、同情しますよ」
「奥様を、お亡なくしなさいました、それは御不自由でございましょう」
「家内を持たない時には、そうでもなかったのですが、一度持って亡なくすると、何だか不自由でしてね」
「そうでございましょうとも」
女はこう云って黒い眼を潤うるませて見せた。喬生はその女と二人でしんみりと話がしたくなった。
「あちらへ往こうじゃありませんか」
女はとうとう一泊して黎明よあけになって帰って往った。喬生はもう亡くなった女房のことは忘れてしまって夜の来るのを待っていた。夜になると女は少女を伴つれてやって来た。軽い小刻こきざみな韈くつの音がすると、喬生は急いで起たって往って扉とを開けた。少女の持った真紅の鮮かな牡丹燈が先まず眼に注ついた。
女は毎晩のように喬生の許もとへ来て黎明よあけになって帰って往った。喬生の家と壁一つを境にして老人が住んでいた。老人は、鰥暮やもめぐらしの喬生が夜になると何人だれかと話しでもしているような声がするので不審した。
「あいつ寝言を云ってるな」
しかし、その声は一晩でなしに二晩三晩と続いた。
「寝言にしちゃおかしいぞ、人も来るようにないが、それとも何人だれかが泊とまりにでも来るだろうか」
老人はこんなことを云いながらやっとこさと腰をあげ、すこし頽くずれて時おり隣の燈ひの漏もれて来る壁の破れの見える処へ往って顔をぴったりつけて好奇ものずきに覗のぞいて見た。喬生が人間の骸骨がいこつと抱き合って榻ねだいに腰をかけていたが、そのとき嬉しそうな声で何か云った。老人は怖れて眼前めさきが暗むような気がした。彼は壁を離れるなり寝床の中へ潜もぐりこんだ。
翌日になって老人は喬生を己じぶんの家へ呼んだ。
「お前さんは、大変なことをやってるが、知ってやってるかな」
老人は物におびえるような声で云った。喬生はその意味が判らなかったが、女のことがあるのでその忠告でないかと思ってきまりが悪かった。
「さあ、なんだろう、私には判らないが」
「判らないことがあるものか、お前さんは、大変なことをやってる、気が注つかないことはないだろう」
女のことにしては老人の顔色や詞ことばがそれとそぐわなかった。
「なんだね」
「なんだも無いものだ、お前さんは、おっかない骸骨と抱き合ってたじゃないか」
「骸骨がいこつ、骸骨って、あれかね」
「笑いごとじゃないよ、お前さんは、おっかない骸骨と、何をしようと云うんだね、お前さんは、邪鬼じゃきに魅みいられてるのだ」
喬生もうす鬼魅きみ悪くなって来た。
「真箇ほんとうかね」
「嘘を云って何になる、わしは、お前さんが毎晩のようにへんなことを云うから、初めは寝言だろうと思ってたが、それでも不思議だから、昨夜ゆうべ、あの壁の破れから覗のぞいて見たのだ、お前さんは、邪鬼に生命いのちを奪とられようとしてるのだ」
「観燈の晩に知りあって、それから毎晩泊りに来てたが、邪鬼だろうか」
「邪鬼も邪鬼、大変な邪鬼だ」
「奉化ほうかの者で、お父さんは州判しゅうはんをしてたと云ったよ、湖西こせいに婢女じょちゅうと二人で暮してると云うのだ、そうかなあ」
「そうとも邪鬼だよ、わしがこんなに云っても真箇と思えないなら、湖西へ往って調べて見るが好いじゃないか、きっとそんな者はいないよ」
「そうか、なあ、たしかに麗卿と云ってたが、じゃ往って調べて見ようか」
その日喬生は月湖げっこの西岸へ往った。湖西の人家は湖に沿うてあっちこっちに点在していた、湖の水は微陽うすびの射さした空の下もとに青どろんで見えた。そこには湖の中へ通じた長い堤つつみもあった。堤には太鼓橋たいこばしになった石橋が処ところどころに架かかって裸木はだかぎの柳の枝が寒そうに垂れていた。
喬生は湖縁こべりを往ったり堤の上を往ったりして、符姓ふせいの家を訊きいてまわった。
「このあたりに、符と云う家はないでしょうか」
「さあ、符、符と云いますか、そんな家は聞きませんね」
「壮わかい女と婢女じょちゅうの二人暮しだと云うのですが」
「壮い女と婢女の二人暮し、そんな家はないようですね」
何人だれに訊いても同じような返事であった。そのうちに夕方になって湖の面おもてがねずみがかって来た。喬生は幾等いくら訊いても女の家が判らないので老人の詞ことばを信ずるようになって来た。彼は無駄骨を折るのが痴ばかばかしくなったので、湖の中の堤どてを通って帰って来た。
湖心寺こしんじと云う寺が堤つつみに沿うて湖の中にあった。古い大きな寺で眺望が好いので遊覧する者が多かった。喬生もそこでひと休みするつもりで寺の中へ往った。
もう夕方のせいでもあろう遊覧の客もいなかった。喬生は腰をおろす処はないかと思って、本堂の東側になった廻廊の中へ入って往った。朱塗しゅぬりの大きな柱が並木のように並んでいた。彼は東側の廻廊から西側の廻廊へ廻ってみた。その西側の廻廊の往き詰めにうす暗い陰気な室へやの入口があった。彼は好奇ものずきにその中を覗のぞいてみた。そこには一個ひとつの棺桶かんおけが置いてあったが、その上に紙を貼はって太い文字が書いてあった。それは「故奉化符州判女麗卿之棺こほうかふしゅうはんじょれいけいのひつぎ」と書いたものであった。喬生は眼を見はった。棺桶の前には牡丹の花の飾かざりをした牡丹燈が懸かけてあった。彼はぶるぶると顫ふるえながら、牡丹燈の下のほうに眼を落した。そこには小さな藁人形わらにんぎょうが置いてあって、その背うしろの貼紙に「金蓮」と書いてあった。
喬生は夢中になって逃げ走った。そして、やっと己じぶんの家の門口かどぐちまで帰って来たが、恐ろしくて入れないのでその足で隣へ往った。
「ああ帰ったか、どうだね、判ったかね」
老人はこう云って訊きいた。喬生の顔は蒼白あおじろくなっていた。
「いや、大変なことがあった、お前さんの云った通りだ」
「そうだろうとも、ぜんたいどんなことがあったね」
「どんなことって、湖西へ往って尋ねたが、判らないので帰ろうと思って、あの湖心寺の前まで来たが、くたびれたので、一ぷくしようと思って、寺の中へ往ってみると、西の廊下の往き詰めに、暗い室へやがあるじゃないか、何をする室だろうと思って、覗のぞいてみると、棺桶かんおけがあって、それに故もとの奉化符州判の女むすめ麗卿の柩ひつぎと書いてあったんだ、麗卿とはあの女おんなの名前だよ」
「じゃ、その女の邪鬼だ、だから云わないことか、お前さんが骸骨がいこつと抱きあっている処を、ちゃんとこの眼で見たのだもの」
「えらいことになった、どうしたら好いだろう、それにあの女の伴つれて来る婢女じょちゅうも、藁わら人形だ、牡丹の飾かざりの燈籠もやっぱりあったんだ、どうしたら好いだろう」
「そうだね、玄妙観げんみょうかんへ往って魏法師ぎほうしに頼むより他に途みちがないね、魏法師は、故もとの開府王真人かいふおうしんじんの弟子で、符籙かじふだにかけては、天下第一じゃ」
喬生は家へ帰るが恐ろしいので、その晩は老人の許もとへ泊めてもらって、翌日になって玄妙観へ出かけて往った。魏法師は喬生の顔を遠くの方からじっと見ていたが、傍そば近くなると、
「えらい妖気だ、なんと思ってここへ来た」
喬生は驚いた。そして、なるほどこの魏法師は豪えらい人であると思った。彼はその前の地べたへ額ひたいを擦すりつけて頼んだ。
「私は邪鬼に魅みいられて、殺されようとしているところでございます、どうかお助けを願います」
魏法師は喬生から理由わけを聞くと朱符しゅふを二枚出した。
「一つを門へ貼はり、一つを榻ねだいへ張るが好い、そしてこれから、二度と湖心寺へ往ってはならんよ」
喬生は家に帰って魏法師の詞ことばに従って朱符を門と榻に貼ったところで、怪しい女はその晩から来なくなった。
一月ばかりすると、喬生の恐怖もやや薄らいで来た。彼は某日あるひ、袞繍橋こんしゅうきょうに住んでいる朋友ともだちのことを思い出して訪ねて往った。朋友は久しぶりに訪ねて来た喬生を留とめて酒を出した。
二人はいろいろの話をしながら飲んでいたが、そのうちに夕方になって陽ひがかげって来た。喬生は驚いて帰りかけたが、遠慮なしに打ちくつろいで飲んだ酒が心地好く出て来たので、彼は伸び伸びした気になって歩いていた。蛙かわずの声が聞えて来た。
喬生は湖縁こべりの路みちを取らずに湖の中の堤つつみを帰っていた。堤の柳は芽を吐ふいてそれが柔かな風に動いていた。彼の体は湖心寺の前へ来ていた。何時いつの間にか日が暮れて夕月が射さしていた。
喬生はふと魏法師の戒いましめを思いだした。彼は厭いやな気がしたので足早あしばやに通り過ぎようとした。
「旦那様」
それは聞き覚えのある女の声であった。喬生は驚いて眼をやった。金蓮が来て前に立っていた。
「お嬢さんがお待ちかねでございます、どうぞいらしてくださいまし」
喬生の手首には金蓮の手が絡からまって来た。喬生はその手を揮ふり放して逃げようとしたが逃げられなかった。金蓮は強い力でぐんぐんと引張った。喬生は濁った靄もやに脚下あしもとを包まれているようで足が自由にならなかった。
「旦那様は、真箇ほんとうに薄情でございますのね」
喬生は金蓮の手を揮り放そうと悶掻もがいたが、どうしても放れなかった。
「そんなになさるものじゃありませんわ」
喬生はもう西側の廻廊の往き詰に伴つれて往かれていた。
「さあ、お入りくださいまし、ここでございます」
喬生は室へやの中へ引き込まれた。真紅の色の鮮かな牡丹燈籠が微白ほのじろく燃えていた。
「あなたは、妖道士ようどうしに騙だまされて、私をお疑いになっておりますが、それはあんまりじゃありませんか、真箇にあなたは、薄情じゃありませんか」
麗卿が燈籠の下にしんなりと坐っていた。喬生はまた逃げようとした。
「真箇にあなたは薄情でございますわ、でもこうしてお眼にかかったからには、どんなことがあってもお帰ししませんわ」
女は起たって来て喬生の手を握った。と、その前にあった棺桶かんおけの蓋ふたが急に開あいた。
「さあ、この中へお入りくださいまし」
女はその棺桶かんおけの中に先まず己じぶんの体を入れて、それから喬生を引き寄せた。棺桶は二人を内にしてそのまま閉じてしまった。
翌日になって喬生の隣の老人は、喬生が帰って来ないので、心配してあちらこちらと探してみたが、どうしても居所が判らない。いろいろ考えた結果あげく、湖心寺の棺桶のことを思いだして、附近の者を頼んでいっしょに湖心寺へ往って、棺桶のある室へやへ往ってみた。
棺桶の蓋ふたから喬生の着ていた衣服きものの端はしが見えていた。老人は驚いて住職を呼んで来た。住職は棺桶の蓋を除とった。喬生は未まだ生きているような壮わかい女の屍しかばねと抱き合うようにして死んでいた。
「この女は奉化州判の符君の女むすめでございますが、今から十二年前ぜん、十七の時に亡くなりましたので、仮にここへ置いてありましたが、その後、符君の処では家をあげて北へ移りましてから、そのままになっておりました」
住職はそれから女おんなと喬生を西門せいもんの方へ葬ほうむったが、その後のち雨曇あまぐもりの日とか月の暗い晩とかには、牡丹燈を点つけた少女を伴つれた喬生と麗卿の姿が見えて、それを見た者は重い病気になった。土地の者は懼おそれ戦おののいて、玄妙観へ往って魏法師にこの怪事を祓はろうてくれと頼んだ。
「わしの符籙かじふだは、事が起らん前さきなら効こうがあるが、こうなってはなんにもならん、四明山しめいざんに鉄冠道人てっかんどうじんと云う偉い方がおられるから、その方に頼むがいい」
土地の者は魏法師の詞ことばに従って、藤葛ふじかずらを攀よじ渓たにを越えて四明山へ往った。四明山の頂上の松の下に小さな草庵そうあんがあって、一人の老人が几つくえによっかかって坐っていた。草庵の前には童子が丹頂たんちょうの鶴を世話していた。人びとは老人の前へ往って礼拝をした。
「わしは、こんな処へ籠こもっている隠者だから、そんなことはできない、それは何かの聞き違いだろう」
人びとは玄妙観の魏法師から教えられて来たと云った。
「そうか、わしは、今年でもう六十年も山をおりたことはないが、饒舌おしゃべりの道士のために、とうとう引っ張り出されるのか」
道人どうじんは鶴の世話をしている童子を呼んで、それを伴つれて山をおりかけたが、鳥の飛ぶようで追ついて往けなかった。人びとがへとへとに疲れて、やっと西門外へ往ったときには、道人はもう方丈ほうじょうの壇だんを構えていた。
やがて道人は壇の上に坐って符かじを書いて焼いた。と、三四人の武士がどこからともなしにやって来た。皆黄きいろな頭巾ずきんを被かぶって、鎧よろいを着、錦にしきの直衣なおしを着けて、手に手に長い戟ほこを持っていた。武士は壇の下へ来て並んで立った。
「この比ころ、邪鬼が祟たたりをして、人民を悩ますから、その者どもを即刻捕えて来い」
武士は道人の命令を聞いてからいずこともなしに往ってしまったが、間もなく喬生、麗卿、金蓮の邪鬼に枷鎖かせをして伴れて来た。
武士は邪鬼にそれぞれ鞭むちを加えた。邪鬼は血塗ちまみれになって叫んだ。
「その方どもは、何故なにゆえに人民を悩ますのじゃ」
道人は先まず喬生からその罪を白状さして、それをいちいち書き留めさした。その邪鬼の口供こうきょうの概略をあげてみると
喬生は、
符女は、
金蓮は、
武士はその供書きょうしょを道人の前にさしだした。道人はこれを見て判決をくだした。