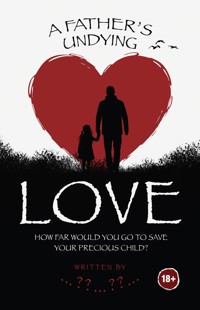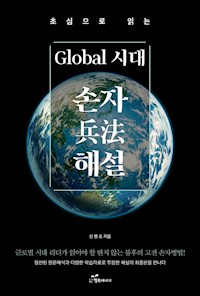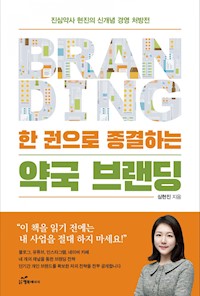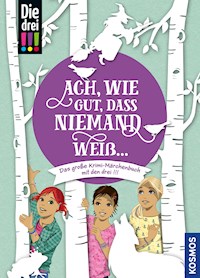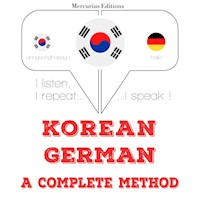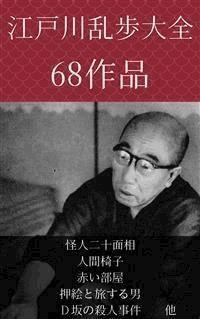
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: micpub.com
- Kategorie: Krimi
- Sprache: ja
最新の江戸川乱歩の作品を集めた大全です。 江戸川乱歩の代表作である怪人二十面相、人間椅子、赤い部屋、押絵と旅する男、D坂の殺人事件などを全て掲載しています。 江戸川乱歩の世界をご堪能ください。 「江戸川乱歩は、大正から昭和期にかけて主に推理小説を得意とした小説家・推理作家である。また、戦後は推理小説専門の評論家としても健筆を揮った。実際に探偵として、岩井三郎探偵事務所(ミリオン資料サービス)に勤務していた経歴を持つ。 本名は平井 太郎(ひらい たろう)。日本推理作家協会初代理事長。 ペンネーム(江戸川乱歩)は作家の、エドガー・アラン・ポーに由来する。」 (Wikipediaより抜粋) <掲載作品一覧> 赤い部屋 赤いカブトムシ 悪魔の紋章 超人ニコラ 大金塊 電人M 毒草 D坂の殺人事件 ふしぎな人 疑惑 五階の窓 灰色の巨人 灰神楽 白昼夢 一人の芭蕉の問題 一人二役 百面相役者 一枚の切符 一寸法師 自作解説 鏡地獄 怪人と少年探偵 怪人二十面相 怪奇四十面相 海底の魔術師 仮面の恐怖王 火星の運河 奇面城の秘密 湖畔亭事件 黒手組 黒蜥蜴 吸血鬼 魔法博士 まほうやしき モノグラム 夢遊病者の死 二癈人 日記帳 人間椅子 二銭銅貨 踊る一寸法師 黄金豹 お勢登場 押絵と旅する男 恐ろしき錯誤 パノラマ島綺譚 サーカスの怪人 青銅の魔人 接吻 心理試験 少年探偵団 算盤が恋を語る話 双生児 探偵小説の「謎」 鉄人Q 鉄塔の怪人 塔上の奇術師 透明怪人 盗難 虎の牙 妻に失恋した男 宇宙怪人 屋根裏の散歩者 妖人ゴング 妖怪博士 指 指環 幽霊
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Guide
表紙
目次
扉
本文
目 次
赤い部屋
赤いカブトムシ
悪魔の紋章
超人ニコラ
大金塊
電人M
毒草
D坂の殺人事件
ふしぎな人
疑惑
五階の窓
灰色の巨人
灰神楽
白昼夢
一人の芭蕉の問題
一人二役
百面相役者
一枚の切符
一寸法師
自作解説
鏡地獄
怪人と少年探偵
怪人二十面相
怪奇四十面相
海底の魔術師
仮面の恐怖王
火星の運河
奇面城の秘密
湖畔亭事件
黒手組
黒蜥蜴
吸血鬼
魔法博士
まほうやしき
モノグラム
夢遊病者の死
二癈人
日記帳
人間椅子
二銭銅貨
踊る一寸法師
黄金豹
お勢登場
押絵と旅する男
恐ろしき錯誤
パノラマ島綺譚
サーカスの怪人
青銅の魔人
接吻
心理試験
少年探偵団
算盤が恋を語る話
双生児
探偵小説の「謎」
鉄人Q
鉄塔の怪人
塔上の奇術師
透明怪人
盗難
虎の牙
妻に失恋した男
宇宙怪人
屋根裏の散歩者
妖人ゴング
妖怪博士
指
指環
幽霊
赤い部屋
江戸川乱歩
異常な興奮を求めて集った、七人のしかつめらしい男が(私もその中の一人だった)態々わざわざ其為そのためにしつらえた「赤い部屋」の、緋色ひいろの天鵞絨びろうどで張った深い肘掛椅子に凭もたれ込んで、今晩の話手が何事か怪異な物語を話し出すのを、今か今かと待構まちかまえていた。
七人の真中には、これも緋色の天鵞絨で覆おおわれた一つの大きな円卓子まるテーブルの上に、古風な彫刻のある燭台しょくだいにさされた、三挺さんちょうの太い蝋燭ろうそくがユラユラと幽かすかに揺れながら燃えていた。
部屋の四周には、窓や入口のドアさえ残さないで、天井から床まで、真紅まっかな重々しい垂絹たれぎぬが豊かな襞ひだを作って懸けられていた。ロマンチックな蝋燭の光が、その静脈から流れ出したばかりの血の様にも、ドス黒い色をした垂絹の表に、我々七人の異様に大きな影法師かげぼうしを投げていた。そして、その影法師は、蝋燭の焔につれて、幾つかの巨大な昆虫でもあるかの様に、垂絹の襞の曲線の上を、伸びたり縮んだりしながら這い歩いていた。
いつもながらその部屋は、私を、丁度とほうもなく大きな生物の心臓の中に坐ってでもいる様な気持にした。私にはその心臓が、大きさに相応したのろさを以もって、ドキンドキンと脈うつ音さえ感じられる様に思えた。
誰も物を云わなかった。私は蝋燭をすかして、向側に腰掛けた人達の赤黒く見える影の多い顔を、何ということなしに見つめていた。それらの顔は、不思議にも、お能の面の様に無表情に微動さえしないかと思われた。
やがて、今晩の話手と定められた新入会員のT氏は、腰掛けたままで、じっと蝋燭の火を見つめながら、次の様に話し始めた。私は、陰影の加減で骸骨の様に見える彼の顎が、物を云う度にガクガクと物淋しく合わさる様子を、奇怪なからくり仕掛けの生人形でも見る様な気持で眺めていた。
私は、自分では確かに正気の積りでいますし、人も亦またその様に取扱って呉くれていますけれど、真実まったく正気なのかどうか分りません。狂人かも知れません。それ程でないとしても、何かの精神病者という様なものかも知れません。兎とに角かく、私という人間は、不思議な程この世の中がつまらないのです。生きているという事が、もうもう退屈で退屈で仕様がないのです。
初めの間うちは、でも、人並みに色々の道楽に耽ふけった時代もありましたけれど、それが何一つ私の生れつきの退屈を慰なぐさめては呉れないで、却かえって、もうこれで世の中の面白いことというものはお仕舞なのか、なあんだつまらないという失望ばかりが残るのでした。で、段々、私は何かをやるのが臆劫おっくうになって来ました。例えば、これこれの遊びは面白い、きっとお前を有頂天にして呉れるだろうという様な話を聞かされますと、おお、そんなものがあったのか、では早速やって見ようと乗気になる代りに、まず頭の中でその面白さを色々と想像して見るのです。そして、さんざん想像を廻めぐらした結果は、いつも「なあに大したことはない」とみくびって了しまうのです。
そんな風で、一時私は文字通り何もしないで、ただ飯を食ったり、起きたり、寝たりするばかりの日を暮していました。そして、頭の中丈だけで色々な空想を廻らしては、これもつまらない、あれも退屈だと、片端かたはしからけなしつけながら、死ぬよりも辛い、それでいて人目には此上このうえもなく安易な生活を送っていました。
これが、私がその日その日のパンに追われる様な境遇だったら、まだよかったのでしょう。仮令たとえ強いられた労働にしろ、兎に角何かすることがあれば幸福です。それとも又、私が飛切りの大金持ででもあったら、もっとよかったかも知れません。私はきっと、その大金の力で、歴史上の暴君達がやった様なすばらしい贅沢ぜいたくや、血腥ちなまぐさい遊戯や、その他様々の楽しみに耽ふけることが出来たでありましょうが、勿論それもかなわぬ願いだとしますと、私はもう、あのお伽噺とぎばなしにある物臭太郎の様に、一層死んで了った方がましな程、淋しくものういその日その日を、ただじっとして暮す他はないのでした。
こんな風に申上げますと、皆さんはきっと「そうだろう、そうだろう、併し世の中の事柄に退屈し切っている点では我々だって決してお前にひけを取りはしないのだ。だからこんなクラブを作って何とかして異常な興奮を求めようとしているのではないか。お前もよくよく退屈なればこそ、今、我々の仲間へ入って来たのであろう。それはもう、お前の退屈していることは、今更ら聞かなくてもよく分っているのだ」とおっしゃるに相違ありません。ほんとうにそうです。私は何もくどくどと退屈の説明をする必要はないのでした。そして、あなた方が、そんな風に退屈がどんなものだかをよく知っていらっしゃると思えばこそ、私は今夜この席に列して、私の変てこな身の上話をお話しようと決心したのでした。
私はこの階下のレストランへはしょっちゅう出入でいりしていまして、自然ここにいらっしゃる御主人とも御心安く、大分以前からこの「赤い部屋」の会のことを聞知っていたばかりでなく、一再いっさいならず入会することを勧められてさえいました。それにも拘かかわらず、そんな話には一も二もなく飛びつき相そうな退屈屋の私が、今日まで入会しなかったのは、私が、失礼な申分かも知れませんけれど、皆さんなどとは比べものにならぬ程退屈し切っていたからです。退屈し過ぎていたからです。
犯罪と探偵の遊戯ですか、降霊術こうれいじゅつ其他そのたの心霊上の様々の実験ですか、Obscene Picture の活動写真や実演やその他のセンジュアルな遊戯ですか、刑務所や、瘋癲病院や、解剖学教室などの参観ですか、まだそういうものに幾らかでも興味を持ち得うるあなた方は幸福です。私は、皆さんが死刑執行のすき見を企てていられると聞いた時でさえ、少しも驚きはしませんでした。といいますのは、私は御主人からそのお話のあった頃には、もうそういうありふれた刺戟しげきには飽き飽きしていたばかりでなく、ある世にもすばらしい遊戯、といっては少し空恐しい気がしますけれど、私にとっては遊戯といってもよい一つの事柄を発見して、その楽しみに夢中になっていたからです。
その遊戯というのは、突然申上げますと、皆さんはびっくりなさるかも知れませんが……、人殺しなんです。ほんとうの殺人なんです。しかも、私はその遊戯を発見してから今日までに百人に近い男や女や子供の命を、ただ退屈をまぎらす目的の為ばかりに、奪って来たのです。あなた方は、では、私が今その恐ろしい罪悪を悔悟かいごして、懺悔ざんげ話をしようとしているかと早合点なさるかも知れませんが、ところが、決してそうではないのです。私は少しも悔悟なぞしてはいません。犯した罪を恐れてもいません。それどころか、ああ何ということでしょう。私は近頃になってその人殺しという血腥い刺戟にすら、もう飽きあきして了ったのです。そして、今度は他人ではなくて自分自身を殺す様な事柄に、あの阿片アヘンの喫煙に耽り始めたのです。流石さすがにこれ丈けは、そんな私にも命は惜しかったと見えまして、我慢に我慢をして来たのですけれど、人殺しさえあきはてては、もう自殺でも目論もくろむ外には、刺戟の求め様がないではありませんか。私はやがて程なく、阿片の毒の為に命をとられて了うでしょう。そう思いますと、せめて筋路の通った話の出来る間に、私は誰れかに私のやって来た事を打開けて置き度いのです。それには、この「赤い部屋」の方々が一番ふさわしくはないでしょうか。
そういう訳で、私は実は皆さんのお仲間入りがし度い為ではなくて、ただ私のこの変な身の上話を聞いて貰い度いばかりに、会員の一人に加えて頂いたのです。そして、幸いにも新入会の者は必ず最初の晩に、何か会の主旨に副そう様なお話をしなければならぬ定きめになっていましたのでこうして今晩その私の望みを果す機会をとらえることが出来た次第なのです。
それは今からざっと三年計ばかり以前のことでした。その頃は今も申上げました様に、あらゆる刺戟に飽きはてて何の生甲斐もなく、丁度一匹の退屈という名前を持った動物ででもある様に、ノラリクラリと日を暮していたのですが、その年の春、といってもまだ寒い時分でしたから多分二月の終りか三月の始め頃だったのでしょう、ある夜、私は一つの妙な出来事にぶつかったのです。私が百人もの命をとる様になったのは、実にその晩の出来事が動機を為なしたのでした。
どこかで夜更しをした私は、もう一時頃でしたろうか。少し酔っぱらっていたと思います。寒い夜なのにブラブラと俥くるまにも乗らないで家路を辿っていました。もう一つ横町を曲ると一町ばかりで私の家だという、その横町を何気なくヒョイと曲りますと、出会頭であいがしらに一人の男が、何か狼狽している様子で慌ててこちらへやって来るのにバッタリぶつかりました。私も驚きましたが男は一層驚いたと見えて暫く黙って衝つっ立っていましたが、おぼろげな街燈の光で私の姿を認めるといきなり「この辺に医者はないか」と尋ねるではありませんか。よく訊きいて見ますと、その男は自動車の運転手で、今そこで一人の老人を(こんな夜中に一人でうろついていた所を見ると多分浮浪の徒だったのでしょう)轢倒ひきたおして大怪我をさせたというのです。なる程見れば、すぐ二三間向うに一台の自動車が停っていて、その側そばに人らしいものが倒れてウーウーと幽かすかにうめいています。交番といっても大分遠方ですし、それに負傷者の苦しみがひどいので、運転手は何はさて置き先ず医者を探そうとしたのに相違ありません。
私はその辺の地理は、自宅の近所のことですから、医院の所在などもよく弁わきまえていましたので早速こう教えてやりました。
「ここを左の方へ二町ばかり行くと左側に赤い軒燈の点ついた家がある。M医院というのだ。そこへ行って叩き起したらいいだろう」
すると運転手はすぐ様助手に手伝わせて、負傷者をそのM医院の方へ運んで行きました。私は彼等の後ろ姿が闇の中に消えるまで、それを見送っていましたが、こんなことに係合っていてもつまらないと思いましたので、やがて家に帰って、──私は独り者なんです。──婆ばあやの敷しいて呉れた床とこへ這入はいって、酔っていたからでしょう、いつになくすぐに眠入ねいって了いました。
実際何でもない事です。若もし私がその儘ままその事件を忘れて了いさえしたら、それっ限きりの話だったのです。ところが、翌日眼を醒さました時、私は前夜の一寸ちょっとした出来事をまだ覚えていました。そしてあの怪我人は助かったかしらなどと、要もないことまで考え始めたものです。すると、私はふと変なことに気がつきました。
「ヤ、俺は大変な間違いをして了ったぞ」
私はびっくりしました。いくら酒に酔っていたとは云いえ、決して正気を失っていた訳ではないのに、私としたことが、何と思ってあの怪我人をM医院などへ担ぎ込ませたのでしょう。
「ここを左の方へ二町ばかり行くと左側に赤い軒燈の点いた家がある……」
というその時の言葉もすっかり覚えています。なぜその代りに、
「ここを右の方へ一町ばかり行くとK病院という外科専門の医者がある」
と云わなかったのでしょう。私の教えたMというのは評判の藪やぶ医者で、しかも外科の方は出来るかどうかさえ疑わしかった程なのです。ところがMとは反対の方角でMよりはもっと近い所に、立派に設備の整ったKという外科病院があるではありませんか。無論私はそれをよく知っていた筈はずなのです。知っていたのに何故間違ったことを教えたか。その時の不思議な心理状態は、今になってもまだよく分りませんが、恐らく胴忘どうわすれとでも云うのでしょうか。
私は少し気懸りになって来たものですから、婆やにそれとなく近所の噂などを探らせて見ますと、どうやら怪我人はM医院の診察室で死んだ鹽梅あんばいなのです。どこの医者でもそんな怪我人なんか担ぎ込まれるのは厭いやがるものです。まして夜半の一時というのですから、無理もありませんがM医院ではいくら戸を叩いても、何のかんのと云って却々なかなか開けて呉れなかったらしいのです。さんざん暇ひまどらせた挙句やっと怪我人を担ぎ込んだ時分には、もう余程手遅れになっていたに相違ありません。でも、その時若しM医院の主が「私は専門医でないから、近所のK病院の方へつれて行け」とでも、指図をしたなら、或あるいは怪我人は助っていたのかも知れませんが、何という無茶なことでしょう。彼は自からその難しい患者を処理しようとしたらしいのです。そしてしくじったのです、何んでも噂によりますとM氏はうろたえて了って、不当に長い間怪我人をいじくりまわしていたとかいうことです。
私はそれを聞いて、何だかこう変な気持になって了いました。
この場合可哀相な老人を殺したものは果して何人なんぴとでしょうか。自動車の運転手とM医師ともに、夫々それぞれ責任のあることは云うまでもありません。そしてそこに法律上の処罰があるとすれば、それは恐らく運転手の過失に対して行われるのでしょうが、事実上最も重大な責任者はこの私だったのではありますまいか。若しその際私がM医院でなくてK病院を教えてやったとすれば、少しのへまもなく怪我人は助かったのかも知れないのです。運転手は単に怪我をさせたばかりです。殺した訳ではないのです。M医師は医術上の技倆が劣っていた為にしくじったのですから、これもあながち咎とがめる所はありません。よし又彼に責を負うべき点があったとしても、その元はと云えば私が不適当なM医院を教えたのが悪いのです。つまり、その時の私の指図次第によって、老人を生かすことも殺すことも出来た訳なのです。それは怪我をさせたのは如何にも運転手でしょう。けれど殺したのはこの私だったのではありますまいか。
これは私の指図が全く偶然の過失だったと考えた場合ですが、若しそれが過失ではなくて、その老人を殺してやろうという私の故意から出たものだったとしたら、一体どういうことになるのでしょう。いうまでもありません。私は事実上殺人罪を犯したものではありませんか。併しかし法律は仮令運転手を罰することはあっても、事実上の殺人者である私というものに対しては、恐らく疑いをかけさえしないでしょう。なぜといって、私と死んだ老人とはまるきり関係のない事がよく分っているのですから。そして仮令疑いをかけられたとしても、私はただ外科医院のあることなど忘れていたと答えさえすればよいではありませんか。それは全然心の中の問題なのです。
皆さん。皆さんは嘗かつてこういう殺人法について考えられたことがおありでしょうか。私はこの自動車事件で始めてそこへ気がついたのですが、考えて見ますと、この世の中は何という険難至極けんのんしごくな場所なのでしょう。いつ私の様な男が、何の理由もなく故意に間違った医者を教えたりして、そうでなければ取止めることが出来た命を、不当に失って了う様な目に合うか分ったものではないのです。
これはその後私が実際やって見て成功したことなのですが、田舎のお婆さんが電車線路を横切ろうと、まさに線路に片足をかけた時に、無論そこには電車ばかりでなく自動車や自転車や馬車や人力車などが織る様に行違っているのですから、そのお婆さんの頭は十分混乱しているに相違ありません。その片足をかけた刹那に、急行電車か何かが疾風しっぷうの様にやって来てお婆さんから二三間の所まで迫ったと仮定します。その際、お婆さんがそれに気附かないでそのまま線路を横切って了えば何のことはないのですが、誰かが大きな声で「お婆さん危いッ」と怒鳴りでもしようものなら、忽たちまち慌てて了って、そのままつき切ろうか、一度後へ引返そうかと、暫しばらくまごつくに相違ありません。そして、若しその電車が、余り間近い為に急停車も出来なかったとしますと、「お婆さん危いッ」というたった一言が、そのお婆さんに大怪我をさせ、悪くすれば命までも取って了わないとは限りません。先きも申上げました通り、私はある時この方法で一人の田舎者をまんまと殺して了ったことがありますよ。
(T氏はここで一寸言葉を切って、気味悪く笑った)
この場合「危いッ」と声をかけた私は明かに殺人者です。併し誰が私の殺意を疑いましょう。何の恨うらみもない見ず知らずの人間を、ただ殺人の興味の為ばかりに、殺そうとしている男があろうなどと想像する人がありましょうか。それに「危いッ」という注意の言葉は、どんな風に解釈して見たって、好意から出たものとしか考えられないのです。表面上では、死者から感謝されこそすれ決して恨まれる理由がないのです。皆さん、何と安全至極な殺人法ではありませんか。
世の中の人は、悪事は必ず法律に触れ相当の処罰を受けるものだと信じて、愚にも安心し切っています。誰にしたって法律が人殺しを見逃そうなどとは想像もしないのです。ところがどうでしょう。今申上げました二つの実例から類推出来る様な少しも法律に触れる気遣いのない殺人法が考えて見ればいくらもあるではありませんか。私はこの事に気附いた時、世の中というものの恐ろしさに戦慄するよりも、そういう罪悪の余地を残して置いて呉れた造物主の余裕を此上もなく愉快に思いました。ほんとうに私はこの発見に狂喜しました。何とすばらしいではありませんか。この方法によりさえすれば、大正の聖代せいだいにこの私丈けは、謂わば斬捨て御免ごめんも同様なのです。
そこで私はこの種の人殺しによって、あの死に相な退屈をまぎらすことを思いつきました。絶対に法律に触れない人殺し、どんなシャーロック・ホームズだって見破ることの出来ない人殺し、ああ何という申分のない眠け醒しでしょう。以来私は三年の間というもの、人を殺す楽しみに耽って、いつの間にかさしもの退屈をすっかり忘れはてていました。皆さん笑ってはいけません。私は戦国時代の豪傑の様に、あの百人斬りを、無論文字通り斬る訳ではありませんけれど、百人の命をとるまでは決して中途でこの殺人を止めないことを、私自身に誓ったのです。
今から三月ばかり前です、私は丁度九十九人だけ済ませました。そして、あと一人になった時先にも申上げました通り私はその人殺しにも、もう飽きあきしてしまったのですが、それは兎も角、ではその九十九人をどんな風にして殺したか。勿論九十九人のどの人にも少しだって恨みがあった訳ではなく、ただ人知れぬ方法とその結果に興味を持ってやった仕事ですから、私は一度も同じやり方を繰返す様なことはしませんでした。一人殺したあとでは、今度はどんな新工夫でやっつけようかと、それを考えるのが又一つの楽しみだったのです。
併し、この席で、私のやった九十九の異った殺人法を悉ことごとく御話する暇もありませんし、それに、今夜私がここへ参りましたのは、そんな個々の殺人方法を告白する為ではなくて、そうした極悪非道の罪悪を犯してまで、退屈を免れ様とした、そして又、遂にはその罪悪にすら飽きはてて、今度はこの私自身を亡ぼそうとしている、世の常ならぬ私の心持をお話して皆さんの御判断を仰ぎたい為なのですから、その殺人方以については、ほんの二三の実例を申上げるに止めて置き度いと存じます。
この方法を発見して間もなくのことでしたが、こんなこともありました。私の近所に一人の按摩あんまがいまして、それが不具などによくあるひどい強情者でした。他人が深切しんせつから色々注意などしてやりますと、却ってそれを逆にとって、目が見えないと思って人を馬鹿にするなそれ位のことはちゃんと俺にだって分っているわいという調子で、必ず相手の言葉にさからったことをやるのです。どうして並み並みの強情さではないのです。
ある日のことでした。私がある大通りを歩いていますと、向うからその強情者の按摩がやって来るのに出逢いました。彼は生意気にも、杖つえを肩に担いで鼻唄を歌いながらヒョッコリヒョッコリと歩いています。丁度その町には昨日から下水の工事が始まっていて、往来の片側には深い穴が掘ってありましたが、彼は盲人のことで片側往来止めの立札など見えませんから、何の気もつかず、その穴のすぐ側を呑気そうに歩いているのです。
それを見ますと、私はふと一つの妙案を思いつきました。そこで、
「やあN君」と按摩の名を呼びかけ、(よく療治を頼んでお互に知り合っていたのです)
「ソラ危いぞ、左へ寄った、左へ寄った」
と怒鳴りました。それを態わざと少し冗談らしい調子でやったのです。というのは、こういえば、彼は日頃の性質から、きっとからかわれたのだと邪推して、左へはよらないで態と右へ寄るに相違ないと考えたからです。案あんの定じょう彼は、
「エヘヘヘ……。御冗談ばっかり」
などと声色こわいろめいた口返答をしながら、矢庭やにわに反対の右の方へ二足三足寄ったものですから、忽ち下水工事の穴の中へ片足を踏み込んで、アッという間に一丈もあるその底へと落ち込んで了いました。私はさも驚いた風を装うて穴の縁へ駈けより、
「うまく行ったかしら」と覗いて見ましたが彼はうち所でも悪かったのか、穴の底にぐったりと横よこたわって、穴のまわりに突出ている鋭い石でついたのでしょう。一分刈りの頭に、赤黒い血がタラタラと流れているのです。それから、舌でも噛切ったと見えて、口や鼻からも同じ様に出血しています。顔色はもう蒼白で、唸り声を出す元気さえありません。
こうして、この按摩は、でもそれから一週間ばかりは虫の息で生きていましたが、遂に絶命して了ったのです。私の計画は見事に成功しました。誰が私を疑いましょう。私はこの按摩を日頃贔屓ひいきにしてよく呼んでいた位で、決して殺人の動機になる様な恨みがあった訳ではなく、それに、表面上は右に陥穽おとしあなのあるのを避けさせようとして、「左へよれ、左へよれ」と教えてやった訳なのですから、私の好意を認める人はあっても、その親切らしい言葉の裏に恐るべき殺意がこめられていたと想像する人があろう筈はないのです。
ああ、何という恐しくも楽しい遊戯だったのでしょう。巧妙なトリックを考え出した時の、恐らく芸術家のそれにも匹敵する、歓喜、そのトリックを実行する時のワクワクした緊張、そして、目的を果した時の云い知れぬ満足、それに又、私の犠牲になった男や女が、殺人者が目の前にいるとも知らず血みどろになって狂い廻る断末魔だんまつまの光景ありさま、最初の間、それらが、どんなにまあ私を有頂天にして呉れたことでしょう。
ある時はこんな事もありました。それは夏のどんよりと曇った日のことでしたが、私はある郊外の文化村とでもいうのでしょう。十軒余りの西洋館がまばらに立並んだ所を歩いていました。そして、丁度その中でも一番立派なコンクリート造りの西洋館の裏手を通りかかった時です。ふと妙なものが私の目に止りました。といいますのは、その時私の鼻先をかすめて勢よく飛んで行った一匹の雀が、その家の屋根から地面へ引張ってあった太い針金に一寸とまると、いきなりはね返された様に下へ落ちて来て、そのまま死んで了ったのです。
変なこともあるものだと思ってよく見ますと、その針金というのは、西洋館の尖った屋根の頂上に立っている避雷針ひらいしんから出ていることが分りました。無論針金には被覆が施されていましたけれど、今雀のとまった部分は、どうしたことかそれがはがれていたのです。私は電気のことはよく知らないのですが、どうかして空中電気の作用とかで、避雷針の針金に強い電流が流れることがあると、どこかで聞いたのを覚えていて、さてはそれだなと気附きました。こんな事に出くわしたのは初めてだったものですから、珍らしいことに思って、私は暫らくそこに立止ってその針金を眺めていたものです。
すると、そこへ、西洋館の横手から、兵隊ごっこかなにかして遊んでいるらしい子供の一団が、ガヤガヤ云いながら出て来ましたが、その中の六ツか七つの小さな男の子が、外ほかの子供達はさっさと向うへ行って了ったのに、一人あとに残って、何をするのかと見ていますと、今の避雷針の針金の手前の小高くなった所に立って、前をまくると、立小便を始めました。それを見た私は、又もや一つの妙計を思いつきました。私は中学時代に水が電気の導体だということを習ったことがあります。今子供が立っている小高い所から、その針金の被覆のとれた部分へ小便をしかけるのは訳のないことです。小便は水ですからやっぱり導体に相違ありません。
そこで私はその子供にこう声をかけました。
「おい坊っちゃん。その針金へ小便をかけて御覧。とどくかい」
すると子供は、
「なあに訳ないや、見てて御覧」
そういったかと思うと、姿勢を換えて、いきなり針金の地の現れた部分を目がけて小便をしかけました。そして、それが針金に届くか届かないに、恐ろしいものではありませんか、子供はビョンと一つ踊る様に跳上ったかと思うと、そこへバッタリ倒れて了いました。あとで聞けば、避雷針にこんな強い電流が流れるのは非常に珍らしいことなのだ相ですが、か様にして、私は生れて始めて、人間の感電して死ぬ所を見た訳です。
この場合も無論、私は少しだって疑いを受ける心配はありませんでした。ただ子供の死骸に取縋とりすがって泣入っている母親に鄭重ていちょうな悔みの言葉を残して、その場を立去りさえすればよいのでした。
これもある夏のことでした。私はこの男を一つ犠牲いけにえにしてやろうと目ざしていたある友人、と云っても決してその男に恨みがあった訳ではなく、長年の間無二の親友としてつき合っていた程の友達なのですが、私には却って、そういう仲のいい友達などを、何にも云わないで、ニコニコしながら、アッという間に死骸にして見たいという異常な望みがあったのです。その友達と一緒に、房州のごく辺鄙なある漁師町へ避暑に出かけたことがあります。無論海水浴場という程の場所ではなく、海にはその部落の赤銅色しゃくどういろの肌をした小わっぱ達がバチャバチャやっている丈だけで、都会からの客といっては私達二人の外には画学生らしい連中が数人、それも海へ入るというよりは其辺の海岸をスケッチブック片手に歩き廻っているに過すぎませんでした。
名の売れている海水浴場の様に、都会の少女達の優美な肉体が見られる訳ではなく、宿といっても東京の木賃宿きちんやど見たいなもので、それに食物もさしみの外のものはまずくて口に合わず、随分淋しい不便な所ではありましたが、その私の友達というのが、私とはまるで違って、そうした鄙ひなびた場所で孤独な生活を味あじわうのが好きな方でしたのと、私は私で、どうかしてこの男をやっつける機会を掴もうとあせっていた際だったものですから、そんな漁師町に数日の間も落ちついていることが出来たのです。
ある日、私はその友達を、海岸の部落から、大分隔った所にある、一寸断崖見たいになった場所へ連れ出しました。そして「飛込みをやるのには持って来いの場所だ」などと云いながら、私は先に立って着物を脱いだものです。友達もいくらか水泳の心得があったものですから「なる程これはいい」と私にならって着物をぬぎました。
そこで、私はその断崖のはしに立って、両手を真直ぐに頭の上に伸ばし「一、二、三」と思切りの声で怒鳴って置いて、ピョンと飛び上ると、見事な弧を描いて、さかしまに前の海面へと飛込みました。
パチャンと身体が水についた時に、胸と腹の呼吸でスイと水を切って、僅わずか二三尺潜もぐる丈けで、飛魚の様に向うの水面へ身体を現すのが「飛込み」の骨こつなんですが、私は小さい時分から水泳が上手で、この「飛込み」なんかも朝飯前の仕事だったのです、そうして、岸から十四五間も離れた水面へ首を出した私は、立泳ぎという奴をやりながら、片手でブルッと顔の水をはらって、
「オーイ、飛込んで見ろ」
と友達に呼びかけました。すると、友達は無論何の気もつかないで、
「よし」と云いながら、私と同じ姿勢をとり、勢よく私のあとを追ってそこへ飛込みました。
ところが、しぶきを立てて海へ潜ったまま、彼は暫くたっても再び姿を見せないではありませんか……。私はそれを予期していました。その海の底には、水面から一間位の所に大きな岩があったのです。私は前持ってそれを探って置き、友達の腕前では「飛込み」をやれば必ず一間以上潜るにきまっている、随ってこの岩に頭をぶつけるに相違ないと見込みをつけてやった仕事なのです。御承知でもありましょうが、「飛込み」の技は上手なもの程、この水を潜る度が少いので、私はそれには十分熟練していたものですから、海底の岩にぶつかる前にうまく向うへ浮上って了ったのですが、友達は「飛込み」にかけてはまだほんの素人だったので、真逆様に海底へ突入って、いやという程頭を岩へぶつけたに相違ないのです。
案の定、暫く待っていますと、彼はポッカリと鮪まぐろの死骸の様に海面に浮上りました。そして波のまにまに漂っています。云うまでもなく彼は気絶しているのです。
私は彼を抱いて岸に泳ぎつき、そのまま部落へ駈け戻って、宿の者に急をつげました。そこで出漁を休んでいた漁師などがやって来て友達を介抱して呉れましたが、ひどく脳を打った為でしょう。もう蘇生そせいの見込みはありませんでした。見ると、頭のてっぺんが五六寸切れて、白い肉がむくれ上っている。その頭の置かれてあった地面には、夥おびただしい血潮が赤黒く固っていました。
あとにも先にも、私が警察の取調を受けたのはたった二度きりですが、その一つがこの場合でした。何分人の見ていない所で起った事件ですから、一応の取調べを受けるのは当然です。併し、私とその友達とは親友の間柄でそれまでにいさかい一つした事もないと分っているのですし、又当時の事情としては、私も彼もその海底に岩のあることを知らず、幸い私は水泳が上手だった為に危い所をのがれたけれども、彼はそれが下手だったばっかりにこの不祥事を惹起ひきおこしたのだということが明白になったものですから、難なく疑うたがいは晴れ、私は却って警察の人達から「友達をなくされてお気の毒です」と悔みの言葉までかけて貰う有様でした。
いや、こんな風に一つ一つ実例を並べていたんでは際限がありません。もうこれ丈け申上げれば、皆さんも私の所謂絶対に法律にふれない殺人法を、大体御分り下すったことと思います。凡てこの調子なんです。ある時はサーカスの見物人の中に混っていて、突然、ここで御話するのは恥しい様な途方もない変てこな姿勢を示して、高い所で綱渡をしていた女芸人の注意を奪い、その女を墜落させて見たり、火事場で、我子を求めて半狂乱の様になっていたどこかの細君に、子供は家の中に寝かせてあるのだ「ソラ泣いている声が聞えるでしょう」などと暗示を与えて、その細君を猛火の中へ飛込ませ、つい焼殺して了ったり、或は又、今や身投げをしようとしている娘の背後から、突然「待った」と頓狂な声をかけて、そうでなければ、身投げを思いとまったかも知れない其娘を、ハッとさせた拍子に水の中へ飛込ませて了ったり、それはお話すれば限りもないのですけれど、もう大分夜も更けたことですし、それに、皆さんもこの様な残酷な話はもうこれ以上御聞きになりたくないでしょうから、最後に少し風変りなのを一つ丈け申上げてよすことに致しましょう。
今まで御話しました所では、私はいつも一度に一人の人間を殺している様に見えますが、そうでない場合も度々あったのです。でなければ、三年足らずの年月の間に、しかも少しも法律にふれない様な方法で、九十九人もの人を殺すことは出来ません。その中でも最も多人数を一度に殺しましたのは、そうです、昨年の春のことでした。皆さんも当時の新聞記事できっと御読みのことと思いますが、中央線の列車が顛覆てんぷくして多くの負傷者や死者を出したことがありますね、あれなんです。
なに馬鹿馬鹿しい程雑作ぞうさもない方法だったのですが、それを実行する土地を探すのには可也かなり手間どりました。ただ最初から中央線の沿線ということ丈けは見当をつけていました。というのは、この線は、私の計画には最も便利な山路を通っているばかりでなく、列車が顛覆した場合にも、中央線には日頃から事故が多いのですから、ああ又かという位で他の線程目立たない利益があったのです。
それにしても、註文通りの場所を見つけるのには仲々なかなか骨が折れました。結局M駅の近くの崖を使うことに決心するまでには、十分一週間はかかりました。M駅には一寸した温泉場がありますので、私はそこのある宿へ泊り込んで、毎日毎日湯に入ったり散歩をしたり、如何いかにも長逗留ながどまりの湯治客らしく見せかけようとしたのです。その為に又十日余り無駄に過さねばなりませんでしたが、やがてもう大丈夫だという時を見計らって、ある日私はいつもの様にその辺の山路を散歩しました。
そして、宿から半里程のある小高い崖の頂上へ辿たどりつき、私はそこでじっと夕闇の迫って来るのを待っていました。その崖の真下には汽車の線路がカーブを描いて走っている、線路の向う側はこちらとは反対に深いけわしい谷になって、その底に一寸した谷川が流れているのが、霞む程遠くに見えています。
暫くすると、予あらかじめ定めて置いた時間になりました。私は、誰れも見ているものはなかったのですけれど、態々一寸つまずく様な恰好をして、これも予め探し出して置いた一つの大きな石塊いしころを蹴飛しました。それは一寸蹴りさえすればきっと崖から丁度線路の上あたりへころがり落ちる様な位置にあったのです。私は若しやりそこなえば幾度でも他の石塊でやり直すつもりだったのですが、見ればその石塊はうまい工合に一本のレールの上にのっかっています。
半時間の後には下り列車がそのレールを通るのです。その時分にはもう真暗になっているでしょうし、その石のある場所はカーブの向側なのですから、運転手が気附く筈はありません。それを見定めると、私は大急ぎで、M駅へと引返し(半里の山路ですからそれには十分じゅうぶん三十分以上を費しました)そこの駅長室へ這入って行って「大変です」とさも慌てた調子で叫んだものです。
「私はここへ湯治に来ているものですが、今半里計り向うの、線路に沿った崖の上へ散歩に行っていて、坂になった所を駈けおりようとする拍子にふと一つの、石塊を崖から下の線路の上へ蹴落して了いました。若しあそこを列車が通ればきっと脱線します。悪くすると谷間へ落ちる様なことがないとも限りません。私はその石をとりのけ様と色々道を探したのですけれど、何分不案内の山のことですから、どうにもあの高い崖を下る方法がないのです。で、ぐずぐずしているよりはと思って、ここへ駈けつけた次第ですが、どうでしょう。至急あれを、取りのけて頂く訳には行きませんでしょうか」
と如何にも心配そうな顔をして申しました。すると駅長は驚いて、
「それは大変だ、今下り列車が通過した処ところです。普通ならあの辺はもう通り過ぎて了った頃ですが……」
というのです。それが私の思う壺でした。そうした問答を繰り返している内に、列車顛覆死傷数知らずという報告が、僅かに危地を脱して駈けつけた、その下り列車の車掌によって齎もたらされました。さあ大騒ぎです。
私は行がかり上一晩Mの警察署へ引ぱられましたが、考えに考えてやった仕事です。手落ちのあろう筈はありません。無論私は大変叱られはしましたけれど、別に処罰を受ける程のこともないのでした。あとで聞きますと、その時の私の行為は刑法第百二十九条とかにさえ、それは五百円以下の罰金刑に過ぎないのですが、あてはまらなかったのだそうです。そういう訳で、私は一つの石塊によって、少しも罰せられることなしに、エーとあれは、そうです、十七人でした。十七人の命を奪うことに成功したのでした。
皆さん。私はこんな風にして九十九人の人命を奪った男なのです。そして、少しでも悔ゆる所か、そんな血腥い刺戟にすら、もう飽きあきして了って、今度は自分自身の命を犠牲にしようとしている男なのです。皆さんは、余りにも残酷な私の所行しょぎょうに、それその様に眉をしかめていらっしゃいます。そうです。これらは普通の人には想像もつかぬ極悪非道の行いに相違ありません。ですが、そういう大罪悪を犯してまで免のがれ度い程の、ひどいひどい退屈を感じなければならなかったこの私の心持も、少しはお察しが願い度いのです、私という男は、そんな悪事をでも企らむ他には、何一つ此人生に生甲斐を発見することが出来なかったのです。皆さんどうか御判断なすって下さい。私は狂人なのでしょうか。あの殺人狂とでもいうものなのでしょうか。
斯様かようにして今夜の話手の、物凄くも奇怪極まる身の上話は終った。彼は幾分血走った、そして白眼勝ちにドロンとした狂人らしい目で、私達聴者ききての顔を一人一人見廻すのだった。併し誰一人之これに答えて批判の口を開くものもなかった。そこには、ただ薄気味悪くチロチロと瞬またたく蝋燭の焔に照らし出された、七人の上気した顔が、微動さえしないで並んでいた。
ふと、ドアのあたりの垂絹の表に、チカリと光ったものがあった。見ていると、その銀色に光ったものが、段々大きくなっていた。それは銀色の丸いもので、丁度満月が密雲を破って現れる様に、赤い垂絹の間から、徐々に全まったき円形を作りながら現われているのであった。私は最初の瞬間から、それが給仕女の両手に捧げられた、我々の飲物を運ぶ大きな銀盆であることを知っていた。でも、不思議にも万象を夢幻化しないでは置かぬこの「赤い部屋」の空気は、その世の常の銀盆を、何かサロメ劇の古井戸の中から奴隷がヌッとつき出す所の、あの予言者の生首の載せられた銀盆の様にも幻想せしめるのであった。そして、銀盆が垂絹から出切って了うと、その後から、青竜刀せいりゅうとうの様な幅の広い、ギラギラしたダンビラが、ニョイと出て来るのではないかとさえ思われるのであった。
だが、そこからは、唇の厚い半裸体の奴隷の代りに、いつもの美しい給仕女が現れた。そして、彼女がさも快活に七人の男の間を立廻って、飲物を配り始めると、その、世間とはまるでかけ離れた幻の部屋に、世間の風が吹き込んで来た様で、何となく不調和な気がし出した。彼女は、この家の階下のレストランの、華やかな歌舞と乱酔とキャアという様な若い女のしだらない悲鳴などを、フワフワとその身辺に漂わせていた。
「そうら、射つよ」
突然Tが、今までの話声と少しも違わない落着いた調子で云った。そして、右手を懐中へ入れると、一つのキラキラ光る物体を取出して、ヌーッと給仕女の方へさし向けた。
アッという私達の声と、バン……というピストルの音と、キャッとたまぎる女の叫びと、それが殆ど同時だった。
無論私達は一斉に席から立上った。併しああ何という仕合せなことであったか、射たれた女は何事もなく、ただこれのみは無慚むざんにも射ちくだかれた飲物の器を前にして、ボンヤリと立っているではないか。
「ワハハハハ……」T氏が狂人の様に笑い出した。
「おもちゃだよ、おもちゃだよ。アハハハ……。花ちゃんまんまと一杯食ったね。ハハハ……」
では、今なおT氏の右手に白煙をはいているあのピストルは、玩具に過ぎなかったのか。
「まあ、びっくりした……。それ、おもちゃなの?」Tとは以前からお馴染なじみらしい給仕女は、でもまだ脣くちびるの色はなかったが、そういいながらT氏の方へ近づいた。
「どれ、貸して御覧なさいよ。まあ、ほんものそっくりだわね」
彼女は、てれかくしの様に、その玩具だという六連発を手にとって、と見こうみしていたが、やがて、
「くやしいから、じゃ、あたしも射ってあげるわ」
いうかと思うと、彼女は左腕を曲げて、その上にピストルの筒口を置き、生意気な恰好でT氏の胸に狙いを定めた。
「君に射てるなら、射ってごらん」T氏はニヤニヤ笑いながら、からかう様に云った。
「うてなくってさ」
バン……前よりは一層鋭い銃声が部屋中に鳴り響いた。
「ウウウウ……」何とも云えぬ気味の悪い唸声うなりごえがしたかと思うと、T氏がヌッと椅子から立上って、バッタリと床の上へ倒れた。そして、手足をバタバタやりながら、苦悶くもんし始めた。
冗談か、冗談にしては余りにも真に迫ったもがき様ではないか。
私達は思わず彼のまわりへ走りよった。隣席となりにいた一人が、卓上の燭台をとって苦悶者の上にさしつけた。見ると、T氏は蒼白な顔を痙攣させて、丁度傷ついた蚯蚓みみずが、クネクネはね廻る様な工合に、身体中の筋肉を伸ばしたり縮めたりしながら、夢中になってもがいていた。そしてだらしなくはだかったその胸の、黒く見える傷口からは彼が動く度に、タラリタラリとまっ紅かな血が、白い皮膚を伝って流れていた。
玩具と見せた六連発の第二発目には実弾が装填してあったのだ。
私達は、長い間、ボンヤリそこに立ったまま、誰一人身動きするものもなかった。奇怪な物語りの後のこの出来事は、私達に余りにも烈しい衝動を与えたのだ。それは時計の目盛から云えば、ほんの僅かな時間だったかも知れない。けれども、少くともその時の私には、私達がそうして何もしないで立っている間が、非常に長い様に思われた。なぜならば、その咄嗟とっさの場合に、苦悶している負傷者を前にして、私の頭には次の様な推理の働く余裕が十分あったのだから。
「意外な出来事に相違ない。併し、よく考えて見ると、これは最初からちゃんと、Tの今夜のプログラムに書いてあった事柄なのではあるまいか。彼は九十九人までは他人を殺したけれど、最後の百人目だけは自分自身の為に残して置いたのではないだろうか。そして、そういうことには最もふさわしいこの『赤い部屋』を、最後の死に場所に選んだのではあるまいか、これは、この男の奇怪極る性質を考え合せると、まんざら見当はずれの想像でもないのだ。そうだ。あの、ピストルを玩具だと信じさせて置いて、給仕女に発砲させた技巧などは、他の殺人の場合と共通の、彼独特のやり方ではないか。こうして置けば、下手人の給仕女は少しも罰せられる心配はない。そこには私達六人もの証人があるのだ、つまり、Tは彼が他人に対してやったと同じ方法を、加害者は少しも罪にならぬ方法を、彼自身に応用したものではないか」
私の外の人達も、皆夫々それぞれの感慨に耽っている様に見えた。そして、それは恐らく私のものと同じだったかも知れない。実際、この場合、そうとより他には考え方がないのだから。
恐ろしい沈黙が一座を支配していた。そこには、うっぷした給仕女の、さも悲しげにすすり泣く声が、しめやかに聞えているばかりだった。「赤い部屋」の蝋燭の光に照らし出された、この一場の悲劇の場面は、この世の出来事としては余りにも夢幻的に見えた。
「ククククク……」
突如、女のすすり泣の外に、もう一つの異様な声が聞えて来た。それは、最早や藻掻もがくことを止めて、ぐったりと死人の様に横わっていた、T氏の口から洩もれるらしく感じられた。氷の様な戦慄が私の背中を這い上った。
「クックックックッ……」
その声は見る見る大きくなって行った。そして、ハッと思う間に、瀕死ひんしのT氏の身体からだがヒョロヒョロと立上った。立上ってもまだ「クックックックッ」という変な声はやまなかった。それは胸の底からしぼり出される苦痛の唸り声の様でもあった。だが……、若しや……オオ、矢張やはりそうだったのか、彼は意外にも、さい前ぜんから耐らないおかしさをじっと噛み殺していたのだった。「皆さん」彼はもう大声に笑い出しながら叫んだ。「皆さん。分りましたか、これが」
すると、ああ、これは又どうしたことであろう。今の今まであの様に泣入っていた給仕女が、いきなり快活に立上ったかと思うと、もうもう耐らないという様に、身体をくの字にして、これも亦また笑いこけるのだった。
「これはね」やがてT氏は、あっけにとられた私達の前に、一つの小さな円筒形のものを、掌にのせてさし出しながら説明した。「牛の膀胱ぼうこうで作った弾丸たまなのですよ。中に赤インキが一杯入れてあって、命中すれば、それが流れ出す仕掛けです。それからね。この弾丸が偽物だったと同じ様に、さっきからの私の身の上話というものはね、始めから了いまで、みんな作りごとなんですよ。でも、私はこれで、仲々お芝居はうまいものでしょう……。さて、退屈屋の皆さん。こんなことでは、皆さんが始終お求めなすっている、あの刺戟とやらにはなりませんでしょうかしら……」
彼がこう種明しをしている間に、今まで彼の助手を勤めた給仕女の気転で階下のスイッチがひねられたのであろう、突如真昼の様な電燈の光が、私達の目を眩惑げんわくさせた。そして、その白く明るい光線は、忽ちにして、部屋の中に漂っていた、あの夢幻的な空気を一掃してしまった。そこには、曝露ばくろされた手品の種が、醜いむくろを曝していた。緋色の垂絹にしろ、緋色の絨氈にしろ、同じ卓子掛テーブルかけや肘掛椅子、はては、あのよしありげな銀の燭台までが、何とみすぼらしく見えたことよ。「赤い部屋」の中には、どこの隅を探して見ても、最早や、夢も幻も、影さえ止とどめていないのだった。
底本:「江戸川乱歩全集 第1巻 屋根裏の散歩者」光文社文庫、光文社
2004(平成16)年7月20日初版1刷発行
2012(平成24)年8月15日7刷発行
底本の親本:「江戸川乱歩全集 第七巻」平凡社
1931(昭和6)年12月
初出:「新青年」博文館
1925(大正14)年4月
※初出時の表題は「連続短篇探偵小説(三)」です。
※「飽き飽き」と「飽きあき」、「深切」と「親切」の混在は、底本通りです。
※底本巻末の編者による語注は省略しました。
入力:門田裕志
校正:岡村和彦
2016年6月10日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
赤いカブトムシ
江戸川乱歩
あるにちよう日のごご、丹下たんげサト子ちゃんと、木村きむらミドリちゃんと、野崎のざきサユリちゃんの三人が、友だちのところへあそびに行ったかえりに、世田谷せたがや区のさびしい町を、手をつないで歩いていました。三人とも、小学校三年生のなかよしです。
「あらっ。」
サト子ちゃんが、なにを見たのか、ぎょっとしたようにたちどまりました。
ミドリちゃんもサユリちゃんもびっくりして、サト子ちゃんの見つめている方をながめました。
すると、道のまん中に、みょうなことがおこっていたのです。むこうのマンホールのてつのふたが、じりり、じりりと、もち上がっているのです。だれか、マンホールの中にいるのでしょうか。
マンホールのふたは、すっかりひらいていました。そして、その下から、黒いマントをきた男の人が、ぬうっとあらわれたのです。その人は、つばのひろい、まっ黒なぼうしをかぶり、大きなめがねをかけ、口ひげがぴんと、両方にはね上がっていて、黒い三かくのあごひげをはやしていました。
せいようあくまみたいな、きみのわるい人です。その人は、マンホールからはい出して、じめんにすっくとたち上がると、三人の方を見て、にやりとわらいました。そして、黒いマントを、こうもりのようにひらひらさせながら、むこうの方へ歩いていくのです。
「あやしい人だわ。ねえ、みんなで、あの人のあとをつけてみましょうよ。」
ミドリちゃんが、小さい声でいいました。ミドリちゃんのにいさんの敏夫としおくんは、しょうねんたんていだんいんなので、ミドリちゃんもそういうたんていみたいなことがすきなのです。サト子ちゃんもサユリちゃんも、ミドリちゃんのいうことは、なんでもきくくせなので、そのまま三人で、黒マントの男のあとをつけていきました。
黒マントは、ひろいはらっぱをとおって、むこうの森の中へはいっていきます。世田谷区のはずれには、はたけもあれば、森もあるのです。ひるまですから、もりへはいるのも、おそろしくはありません。三人は、こわいもの見たさで、どこまでもあとをつけました。
森の中に、一けんのふるいせいようかんがたっていました。
「あらっ、あれはおばけやしきよ。」
「まあ、こわい。どうしましょう。」
そのせいようかんは、むかし、せいよう人がすんでいたのですが、いまはあきやになっていて、そのへんではおばけやしきとよばれています。
三人は、近くにすんでいるので、それをよく知っていました。
夜、せいようかんの二かいのまどから、赤い人だまが、すうっと出ていったのを見た人があるということでした。また、だれもいないせいようかんの中から、きみのわるい女のなき声がきこえてくるといううわさもありました。
三人のしょうじょがにげ出そうとしていますと、あっとおどろくようなことがおこりました。
黒マントの男が、せいようかんの外がわを、するするとのぼっていくではありませんか。はしごもないのに、まるでへびのようにのぼっていくと、二かいのまどの中にすがたをけしてしまいました。
三人はぞっとして、いきなりかけ出そうとしましたが、そのとき、せいようかんの方から、けたたましいさけび声がきこえてきました。
それをきくと、三人とも、思わず、うしろをふりむきました。二かいのまどから、白いかおがのぞいていました。そのかおが、きゃあっとさけんでいるのです。とおいので、はっきり、わかりませんが、三人とおなじくらいの年ごろの、おかっぱの女の子です。その子が、いまにもころされそうにさけんでいるのです。
「きっと、あの黒マントの男がいじめているんだわ。」
三人とも、おなじことを考えました。
まどの女の子は、なにものかの手からのがれようとして、もがいていましたが、とうとう、ずるずるとうしろへひっぱられて、まどからきえてしまいました。そのとき、なき声がぱったりとまったのは、男に口をおさえられたからかもしれません。
三人は、むがむちゅうでかけ出しました。そして、近くのめいめいのうちへかえったのですが、ミドリちゃんは、すぐにこのことをおとうさんと、にいさんの敏夫くんに知らせました。
「おしいことをしたなあ。ぼくがそこにいれば、きっと手がかりをつかんだのに。」
しょうねんたんていだんいんの敏夫くんが、ざんねんそうにいいました。
ミドリちゃんのおとうさんが、けいさつにでんわをかけたので、けいかんたちが森の中のせいようかんにかけつけて、中をしらべましたが、まったくのあきやで、人のかげさえ見えないのでした。せいようあくまのような黒マントの男は、いったいなにものでしょうか。そして、あのかわいそうな女の子は、どうなったのでしょうか。
森の中の、ふるいせいようかんのまどから、小さい女の子が、たすけをもとめてなきさけんでいた、そのあくる日のこと。
ミドリちゃんのにいさんの木村敏夫くんは、さっそく、このことをしょうねんたんていだんちょうの小林こばやしくんに知らせましたので、小林だんちょうが、木村くんのうちへやってきました。
そして、ふたりで森の中のせいようかんをたんけんすることになりました。まっぴるまですから、こわいことはありません。でも、ふたりとも、たんてい七つどうぐのかいちゅうでんとうや、きぬ糸のなわばしごや、よぶこのふえなどは、ちゃんとよういしていました。
小林だんちょうと木村くんは、うすぐらい森の中をとおって、おばけやしきのせいようかんのまえに来ました。入口のドアをおしてみますと、なんなくひらきました。かぎもかかっていないのです。ふたりは中へはいり、ひろいろうかを、足音をたてないようにしてしのびこんでいきました。
かいちゅうでんとうをてらし、長いあいだかかって、一かいと二かいのぜんぶのへやをしらべましたが、だれもいないことがわかりました。まったくのあきやです。
「どうも、このへやがあやしいよ。なぜだかわからないが、そんな気がするんだ。」
一かいのひろいへやにもどったとき、小林くんが、ひとりごとのようにいいました。すると、ちょうどそのとき……。
どこからともなく、かすかに、かすかに、
「おじさん、かんにんして。あっ、こわいっ……たすけてえ……。」
というひめいがきこえてきました。小さい女の子の声のようです。
ふたりはぞっとして、たちすくんだまま、かおを見あわせました。
「ゆか下からきこえてきたようだね。」
小林くんが、くびをかしげながらいいました。するとまた、
「あれっ、いけないっ。早くたすけて。」と、かすかな声が……。
「どこかに、かくし戸があるにちがいない。どこだろう。」
小林くんは、かいちゅうでんとうをてらして、へやじゅうをさがしまわりました。
そのへやには、大きなだんろがついていて、そのだんろの下がわに、まるいぼっちが、ずっとならんでいます。かざりのちょうこくです。小林くんは、そのぼっちを一つ一つ、ゆびでおしてみました。すると、右から七ばんめのぼっちが、ちょうどベルのおしボタンのように、うごくことがわかったのです。小林くんは、それをぐっとおしてみました。すると……。
ガタンという音といっしょに、「あっ。」というさけび声。びっくりしてふりむくと、いままでそこにいた木村くんのすがたが、きえうせていました。
小林くんはびっくりして、そこへかけつけました。すると、ゆかいたに、四かくいあながぽっかりとあいていることがわかりました。ちかしつへのおとしあなです。小林くんが、だんろのぼっちをおしたので、それがひらいたのです。
「木村くん、だいじょうぶか。」
あなの中へ、かいちゅうでんとうをむけてよんでみました。
「う、う、う……だ、だいじょうぶだっ。」
木村くんがくるしそうにこたえました。見ると、あなの下に、すべりだいのようないたが、ずっとつづいています。小林くんは、思いきってそこへとびおりました。
すうっ……とすべりました。そして、どしんと、ちかしつのかたいゆかに、しりもちをつきました。
やっとのことでおき上がって、かいちゅうでんとうをてらしてみますと、そこは十じょうほどの、ひろいちかしつでした。しかし、ひめいをあげた女の子のすがたは、どこにも見えません。むこうのかべに、まっくらなほらあながあいています。そのむこうに、べつなちかしつがあるのでしょうか。
「あっ、きみ。あれ、なんだろう。」
木村くんが、おびえた声で、そのほらあなをゆびさしました。
ふたりのかいちゅうでんとうが、ぱっと、そこをてらしました。
まっくらなほらあなのおくで、ぎらぎら光った、二つのまるいものが、ちゅうにういているのです。そしてそれが、だんだんこちらへ近づいてくるではありませんか。
かいぶつの目です。なにかしらおそろしいものが、こちらへやってくるのです。まるでヤドカリが、かいがらの中からかおを出すように、それが、にゅっとくびを出しました。
「あっ。」
ふたりは、思わず声をたてて、おたがいのからだをだきあいました。
そのからだは、まっかでした。まっかな長い、大きなつの。そのねもとに、ぶきみなとんがった口。二つのぎらぎら光る目。おれまがった六本の長い足……。それは、にんげんほどの大きさの、まっかなカブトムシだったのです。
ああ、ふたりはどうなるのでしょう。
さっき、ひめいをあげたかわいそうな女の子は、いったいどうしたのでしょうか。
小林くんと、だんいんの木村くんが、おばけやしきのせいようかんのちかしつで、にんげんほどもある、大きなまっかなカブトムシに出あいました。
ふたりは、ちかしつのすみで、そのおそろしいかいぶつを見つめていました。かいぶつをてらしている二つのかいちゅうでんとうのわが、ぶるぶるふるえています。
キーッ、キーッと、なんともいえないするどい音がしました。大きなカブトムシのなき声です。そのたびに、あのとんがった口が、ぱくぱくひらくのです。
大きなカブトムシは、長い六本の足を、きみわるく、がくん、がくんとうごかしながら、ちかしつの中をぐるぐると歩きまわりました。
しばらく歩きまわったあとで、いよいよこちらに近づいてきました。カブトムシのせなかは、まっかにてらてらと光っています。ときどき、大きなはねをひらいて、ぶるんとはばたきのようなことをします。そのたびにおそろしい風がおこるのです。もう、二メートルほどに近づいてきました。とび出した大きな目が、ぎょろりと、ふたりをにらんでいます。
いまにもとびかかってくるかと、ふたりは思わずみがまえました。カブトムシは、あと足をまげ、中の足とおしりでちょうしをとって、ぐうっとたち上がり、まえ足をもがもがやっています。きみわるいおなかが、すぐ目のまえに見えました。あのまえ足でつかみかかってくるにちがいないと、いよいよみをかたくしていますと……。
ああ、そのとき、じつにおどろくべきことがおこりました。カブトムシのおなかの中に、ぽかんと、四かくいあながあいたのです。四かくいふたのようなものが、下の方へひらいて、そのふたが、すべりだいのように、ゆかにとどいたのです。すると、おなかの中から、なにかもごもごと、うごめき出してきたではありませんか。
おなかの四かくいあなからはい出してきたのは、長さ五十センチぐらいの、まっかなカブトムシでした。大カブトムシのはらから、中カブトムシが出てきたのです。まさか、子どもを生んだわけではないでしょう。大カブトムシは、プラスチックかなにかでできている作りものかもしれません。そのはらから出てきた中カブトムシも、五十センチもあるのですから、きっと作りものなのでしょう。
中カブトムシは、ゆかにたれたふたのすべりだいをはいおりて、そのへんをぐるぐると歩きまわりました。
大カブトムシのほうは、そのまま、ごろんとあおむけにひっくりかえって、まるでしがいのようにじっとしています。
大きなセミのぬけがらみたいです。
中カブトムシは、ちかしつをぐるぐるまわったあとで、ふたりのまえへ来ると、ぐうっとたち上がりました。大カブトムシとおなじことをするのです。また、おなかに、ぽかんとあながあきました。そして、そこから、こんどは十五センチぐらいの、かわいいカブトムシがはい出してきました。
かわいいといっても、十五センチですから、ほんとうのカブトムシのなんばいもある、からだじゅうまっかなおばけカブトムシです。中カブトムシのほうは、また、セミのぬけがらのように、ごろんところがっています。
十五センチの小カブトムシは、ちょこちょことそのへんをはいまわっていましたが、やがて、ふたりのまえに来ると、またしてもあと足でひょいとたち上がりました。
そして、おなじことをくりかえしたのです。十五センチのカブトムシのおなかに、四センチほどの四かくいあながあいて、そこから、こんどは、ほんものとおなじくらいの大きさのまっかなカブトムシが、ゆかの上にすべり出しました。
ところが、この小さいカブトムシは、十五センチのカブトムシがぬけがらになってころがってしまっても、すこしもうごかないのです。
ゆかにおちたまま、じっとしています。これは、しんでいるのでしょうか。
それにしても、なんてかわいらしく、うつくしいカブトムシなのでしょう。いままでの大カブトムシとちがって、これは、まっかな色がルビーのようで、からだの中まですきとおっています。かわいらしい二つの目は、まるでダイヤのようにかがやいています。
「あっ。」
木村くんが、びっくりするような声をたてました。そのとき、むこうのほらあなの中から、なにか黒いものがはい出してきたからです。
それは、あなから出ると、すっくとたち上がりました。にんげんです。黒いマントをきた、せいようあくまのような、おそろしい人です。
「わははは……。小林くん、ひさしぶりだなあ。わしをわすれたかね。ほら、いつか『おうごんのとら』のとりっこで、ちえくらべをしたまほうはかせだよ。」
小林くんは、思わずまえにすすみ出ました。
「あっ、それじゃ、あのときの……。」
「わははは……。こんどもきみたちは、まんまとわしのけいりゃくにかかったね。」
おばけやしきのちかしつにしのびこんだ小林・木村くんのまえに、黒いマントをきた、せいようあくまのようなおそろしい人があらわれました。
「わしは、いつか、きみたちしょうねんたんていだんと、ちえくらべをしたまほうはかせだよ。じつは、もう一ど、きみたちのちえをためすために、ここへおびきよせたのだ。
このまえは『おうごんのとら』だったが、こんどは、この赤いカブトムシだ。これはルビーでできている。二つの目は、ダイヤモンドだ。わしのだいじなたからものだよ。これをきみたちにわたすから、このまえのようにちえをしぼって、うまくかくしてごらん。わしは、五日のあいだにそれをさがしだして、ぬすんでみせるよ。ぬすまれたら、このちえくらべは、きみたちのまけなのだ。」
それをきくと、「ああ、あのときのまほうはかせだったのか。」
と、やっとあんしんしましたが、でも、まだわからないことがあります。
「きのう、このせいようかんの外がわを、はしごもないのに、するするとのぼっていったのはおじさんだったの。それから、まどからのぞいていた女の子は、どうしたのです。おじさんがいじめていたのでしょう。」
「うふふふ……。あれは、きみたちを、ここへおびきよせる手なのだよ。木村くんのいもうとのミドリちゃんたちが見ているのを知っていて、ふしぎなことをやってみせたのだ。あのときは、このうちのやねから、ほそい、じょうぶな糸のなわばしごがさげてあって、それをつたってのぼったのさ。夕がただから、とおくからは、その糸が見えなかったのだよ。
あのときの女の子は、にんぎょうだよ。ほら、これをごらん。」
まほうはかせは、マントの下にかくしていた、大きなにんぎょうを出してみせました。
「でも、きのうの女の子は、かなしそうなさけび声をたてていたというじゃありませんか。」
小林くんがききかえすと、はかせはにやにやわらって、よこをむきました。
「きゃあ。たすけてえ。」
女の子のおそろしいさけび声がきこえました。ふたりはびっくりして、にんぎょうのかおを見ましたが、べつに、口がうごいているわけでもありません。「ははは……。ふくわじゅつだよ。わしが、口をうごかさないで、女の子の声をまねたのだ。きのうのさけび声は、これだったのだよ。」
このたねあかしをきいて、ふたりは、すっかりあんしんしました。そして、まほうはかせからルビーのカブトムシをうけとると、おばけやしきを出て、小林くんのうちにかえり、おとうさんやおかあさんやミドリちゃんに、そのことを話しました。それから、ふたりで、明智あけちたんていじむしょへいそぎました。そして、明智先生にも、まほうはかせのことをほうこくするのでした。
それからしばらくすると、小林くんがでんわでよびよせた、十人のしょうねんたんていだんいんが、明智たんていじむしょへあつまってきましたが、その中にひとりだけ、女の子がまじっていました。中学一年の宮田みやたユウ子ちゃんという、ついこのごろなかま入りをした、たったひとりのしょうじょだんいんです。年のわりにからだが大きく、いかにもかわいい女の子でした。
「あたし、いいこと思いついたわ。そのカブトムシ、あたしのうちへかくすといいわ。」
みんなでそうだんをしているうちに、ユウ子ちゃんが、そんなことをいいだしました。そして、小林だんちょうの耳に口をよせて、なにか、ひそひそとささやくのでした。
つぎつぎとささやきかわして、ユウ子ちゃんの考えがわかると、みんなは手をたたいて、「それがいい、それがいい。」とさんせいしました。
ユウ子ちゃんは、ルビーのカブトムシをポケットに入れ、その上を手でしっかりおさえて、しょうねんたちにおくられてうちへかえりました。ユウ子ちゃんのうちは、せっこうのおきものを作るのがしょうばいで、うらに、小さなこうばがあるのです。
ユウ子ちゃんは、そのこうばの中へはいっていきました。こうばには、しょうねんのくびや、ビーナス(めがみ)や、花かごをさげた女の子などのせっこうのおきものが、たくさんならんでいます。
すっかりできあがったものもあり、まだできあがらないで、これからつぎあわせるのもあります。ユウ子ちゃんは、このせっこうの中へ、カブトムシをかくそうというのでしょうか。
そんなことで、うまくまほうはかせの目をくらますことができるのでしょうか。なにか、もっとふかい考えがあるのかもしれません。
ユウ子ちゃんが、せっこうのおきもののまん中にしゃがんでいますと、ガラスまどの外に、おそろしいかおがあらわれました。かおじゅうひげにうずまったきたない男が、そっと、中をのぞいているのです。
このひげの男は、いったいなにものなのでしょう。そして、しょうねんたちが手をたたいてよろこんだユウ子ちゃんのちえというのは、どんなことだったのでしょう。
やがて、じつにきみょうなことがおこるのです。この、かおじゅうひげにうずまった、えたいの知れない男が、とほうもないことをやりはじめるのです。
しょうねんたんていだんのたったひとりのしょうじょだんいん、宮田ユウ子ちゃんは、ルビーでできた赤いカブトムシをもって、じぶんのうちのせっこうざいくのこうばにはいって、なにかやっていました。すると、そのとき、まどの外から、かおじゅうひげでうずまった、きたない男が、そっとのぞいていたのです。
そのあくる日の夕がた、ユウ子ちゃんのおうちのある渋谷しぶや区で、つぎつぎとふしぎなことがおこりました。ある町のがくぶちやさんへもじゃもじゃあたまの、きたない男がはいってきて、ショーウインドーにかざってあった、五、六さいのかわいいしょうねんの、くびだけのせっこうぞうをかっていきました。
男は、みせを出ると、さびしいよこちょうに、はいり、あたりを見まわしてから、紙づつみをといて、せっこうのしょうねんのくびを、いきなりじめんにたたきつけ、こなごなにわってしまいました。
せっかくかったせっこうぞうを、なぜわったのでしょう。この男は、気でもちがってしまったのでしょうか。
それから、三十分もすると、その男は、べつの町のびじゅつしょうのみせにあらわれました。そして、そこでも、さっきとおなじしょうねんのくびのせっこうぞうをかい、また、さびしいよこちょうへ来ると、こなみじんにわってしまいました。また、三十分ほどたったころ、こんどは、おなじ渋谷区のあるおやしきへ、あの男がしのびこんでいきました。
その家のおうせつまにも、おなじせっこうのしょうねんのくびがありました。男は、まどからはいりこんでそのくびをぬすみとると、近くのじんじゃの森で、またこなごなにこわしてしまいました。
「だめだ、はいっていない。あのとき、まだつぎあわされていないせっこうは、この三つだけだったのに……。」
男は、とほうにくれたように、たちつくしていました。そのとき、ふいにうしろから、女の子のわらい声がきこえてきました。
男が、びっくりしてふりむくと、大きな木のうしろから出てきたのは、ユウ子ちゃんです。
「おじさん、いっぱいくったわね。このちえくらべは、しょうねんたんていだんのかちよ。
おじさんは、あたしが、せっこうぞうの中へ、赤いカブトムシをかくすのをまどから見ていたのでしょう。ところが、あれは、かくすように見せかけただけなのよ。ほんとうは、もっとべつのところにかくしてあるのよ。」
ユウ子ちゃんは、そういって、さもおもしろそうにわらうのでした。
「そうか、うまくやりやがったな。おれは、あれをぬすもうと思ったが、いつもこうばに人がいたので、ぬすみ出すことができなかった。
しかたがないから、あの三つの子どものくびがはいたつされるのをまって、そのさきを一けんずつまわってこわしてみたが、なんにも出てこなかった。まんまといっぱいくわされたな。わっは、は、は……。」
男は、べつにおこるようすもなく、大わらいをして、それから、ふっとまじめなかおになりました。
「ところがね、おじょうさん。まほうはかせは、もっと上手うわてなんだぜ。おれは、はかせのでしで、きみを、ほうぼうひっぱりまわすやくだったのさ。きみが、おれのあとをつけているまに、まほうはかせが、きみのかくした赤いカブトムシを、ちゃんとぬすみ出してしまったのだよ。は、は、は、は……。」
それをきくと、ユウ子ちゃんは、はっとして、まっさおになってしまいました。
そして、ものもいわず、いきなりどこかへかけだしていくのでした。男は、あとを見おくって、にやりとわらいました。
ユウ子ちゃんは、バスにのっておうちへかえると、小さなシャベルをもって、うら口の外のはらっぱへいそぎました。
ひざまでかくれる草をかきわけて、はらっぱのまん中まで行くと、目じるしの石をとりのけて、その下をシャベルでほりかえし、かくしておいたブリキカンをとり出しました。
「まあ、よかった。あの人、うそをついたのだわ。」
かんの中には、赤いカブトムシが、ちゃんとはいっていたではありませんか。
「うふ、ふ、ふ、ふ。こんどは、きみのほうでいっぱいくったね。」
とつぜんうしろから声がして、さっきの男がたっていました。
「まほうはかせが、ぬすみ出したというのはうそさ。まほうはかせは、このわしだよ。あんなことをいって、きみを、ほんとのかくしばしょに来させたのさ。さあ、そのカブトムシを出しなさい。」
男は、にゅっと手をつき出しました。
ユウ子ちゃんは、まほうはかせにうまくだまされて、赤いカブトムシのかくしばしょを見つけられてしまいました。
そこは、さびしい原っぱですし、あい手はおとなのまほうはかせ。こちらは、小さい子どもですから、どうすることもできません。とうとう、ルビーのカブトムシを、とりあげられてしまいました。
「さあ、こんどは、きみたちがさがす番だよ。わしが、このカブトムシを、ふしぎなばしょへかくすからね。うまく見つけ出してごらん。
は、は、は、は……。かわいそうに、なきべそをかいているね。よしよし、それじゃ、かくしばしょのひみつを、きっと、きみにおしえてあげるよ。まっているがいい。」
まほうはかせは、そういって、どこかへたちさってしまいました。
それから三日めの、おひるすぎのことです。ユウ子ちゃんが、うちのにわであそんでいますと、赤いゴムふうせんが、空からふわふわとおちてきました。
どこかの子どもが、ふうせんの糸をはなして、空へとび上がったのが、力が弱くなっておちてきたのでしょう。
ユウ子ちゃんがそう思って、赤いふうせんをじっと見ていますと、やがてそれは、すぐ目の前のじめんにおちました。
ふうせんには糸がついていて、その糸のはしに、白いものがくくりつけてあります。ユウ子ちゃんは、なんだろうと思って、それをひろってしらべてみました。
それは、紙をこまかくおりたたんだものでした。ていねいにのばしてみると、その紙には、こんなへんなことが書いてあります。
五月二十五日午後三時二十分、一本スギのてっぺんからはいれ。おそろしい番人に注意せよ。
「あらっ、まほうはかせからの手紙だわ。」
ユウ子ちゃんは、むねがどきどきしてきました。
まほうはかせは、このあいだのやくそくをまもって、ユウ子ちゃんに、カブトムシのかくしばしょをおしえてくれたのかもしれません。
ユウ子ちゃんは、すぐにその紙をもって、電車に乗って麹町こうじまちの明智たんていじむしょをたずね、小林しょうねんにそうだんしました。
「五月二十五日といえば、あさってだね。あさって、一本スギのところへ行けばいいんだね。一本スギって、なんだか聞いたことがあるよ。あっ、そうだ。木村敏夫くんの家のそばの、まほうはかせのばけものやしきのむこうに、たしか、一本スギっていうのがあった。木村くんに、でんわで聞いてみよう。」
でんわをかけますと、やっぱりそこに、一本スギという、高いスギの木があることがわかりました。
そして、五月二十五日午後三時に、小林くんたち五人のだんいんが、一本スギのある原っぱへやって来ました。
五人というのは、小林だんちょうとユウ子ちゃんと、木村敏夫くんと、それから、だんいんの中でいちばん力の強い井上一郎いのうえいちろうくんと、野呂一平のろいっぺいくんでした。一平くんは、ノロちゃんというあだ名で、おくびょうものだけれども、すばしこくて、よく気のつく子でした。
「一本スギのてっぺんからはいれって、どういういみだろう。」
小林くんがくびをかしげていますと、ノロちゃんが、とんきょうな声で、
「きっと、てっぺんにあながあいているんだよ。そこからはいるんだよ。ぼく、のぼってみようか。」
といって、こしにまきつけていた長いなわをほどき始めました。
ノロちゃんは、木のぼりのめいじんで、きょうは、スギの木にのぼらなければならないだろうと思って、そのよういをしてきたのです。
ノロちゃんは、なげなわもじょうずでした。その長いなわを、くるくるとまわして、ぱっとスギの木の高いえだになげかけました。そして、一方のはしを、自分のからだにしばりつけ、一方のはしを、みんなにひっぱってもらうのです。
つなひきみたいに、みんながなわをひっぱると、ノロちゃんはそれを力にして、ふといスギのみきを、するするとのぼっていきました。
そして、下のえだまでのぼりつけば、あとは、えだからえだへとつたっていけばいいのです。
ノロちゃんは、とうとう、スギの木のてっぺんまでたどりつきました。
そして、しばらくそのへんをさがしていましたが、
「なんにもないよう。あななんて、どこにもあいていないよう。」
とさけぶ声が、はるかにきこえました。これは、どうしたわけでしょう。
「てっぺんからはいれ。」といったって、あながなければ、はいれないではありませんか。
ノロちゃんは、五分ほども木のてっぺんで、じっとしていましたが、やがて、なにを思ったのか、とんきょうな声で、
「わかったよう。あれだよう、あれをごらん。」
とさけんで、原っぱの一方をゆびさしてみせるのでした。そこには、たいようの光をうけて、一本スギのかげが、長々とよこたわっていました。
みなさん、ノロちゃんは、いったいなにに気づいたのでしょうか。
こんどは、少年たんていだんが、ルビーのカブトムシをさがす番ばんでした。
五月二十五日午後三時二十分、一本スギのてっぺんからはいれ。おそろしい番人に注意せよ。
という手紙のとおりに、小林だんちょうとユウ子ちゃんと、木村くんと井上くんと、ノロちゃんの五人が、世田谷区の一本スギの原っぱへやって来ました。
木のぼりのめいじんのノロちゃんが、高いスギの木のてっぺんへのぼりましたが、はいるあななんて、どこにもありません。ノロちゃんは、しばらく、あたりを見まわしていましたが、なにを思ったのか、原っぱに長くよこたわっているスギの木のかげをゆびさしながら、さけびました。
「あそこだよ。あそこに、入口があるんだよ。」
それを聞くと、小林だんちょうも、はっとそこへ気がつきました。
「ああ、そうだ。てっぺんというのは、スギの木のてっぺんのかげのところなんだ。」
ノロちゃんが木からおりるのをまって、みんなで、スギの木のかげのさきっぽまで行ってみました。
そのへんには、たけの高い草がしげっています。小林くんは、この草の中へふみこんでいってさがしていましたが、やがて、
「あっ、ここにほらあながある。ここが、入口にちがいないよ。」
と、みんなをよびあつめました。それは、さしわたし六十センチぐらいのせまいあなでした。
中はまっくらですから、井上くんと木村くんが、よういのかいちゅうでんとうをつけ、井上くんがさきになって、あなの中へはいこんでいきました。
せまいところは三メートルほどで終り、にわかにあながひろくなって、下の方へ、石だんがついています。もうたって歩けるのです。
石だんをおりると、しょうめんに、大きな鉄のとびらがしまっています。まほうはかせの手紙には、「おそろしい番人に注意せよ。」と書いてありました。きっと、そのおそろしいやつが、とびらのむこうにまちかまえているのだろうと思うと、みんな、むねがどきどきしてきました。
でも、ここまで来て、ひきかえすわけにはいきません。
井上くんは、とびらのとってをつかんでおしてみました。
すると、かぎもかけてないらしく、鉄のとびらは、キイッとぶきみな音をたてて、むこうへひらきました。
かいちゅうでんとうで、その中をてらしてみましたが、なんにもありません。ただ、まっくらなほらあなが、ずっとおくの方へつづいているばかりです。
五人は、井上くんをさきにたてて、おずおずとそのくらやみの中へはいっていきました。
おくびょうもののノロちゃんは、ぶるぶるふるえながら、小林だんちょうについていきました。それに、ユウ子ちゃんは、女の子ですから、まもってやらなければなりません。小林くんは、両手で、ノロちゃんとユウ子ちゃんの手をひいて、すすんでいきます。すこし行くと、ほらあなのまがりかどへ来ました。
そこをひょいとまがると、みんなは「あっ。」といったまま、たちすくんでしまいました。すぐ目の前に、とほうもなく大きなばけものがうずくまっていたからです。そのかおはきいろで、まっ黒なふといしまがついていました。せんめんきほどの大きな目が、やみの中で光っていました。
ステッキをたばにしたような、ふといひげのはえた大きな口、その口から二本の白いきばが、にゅっとつき出ています。トラを百ばいも大きくしたようなばけものです。そのおそろしいかおが、ほらあないっぱいになって、あごが、じめんについているのです。
どこからか、なまぐさい、強い風がふきつけてきました。
「うへへへへ……。かわいい子どもたちが来たな。おいしそうなごちそうだ。いま、たべてやるからな。うへへへへ……。」
おばけのトラが、そんなことをいって、ぶきみにわらいました。その声が、ほらあなにこだまして、なんともいえないおそろしさです。
そして、おばけは、二メートルもあるような大きな口をがっとひらきました。
五人は、にげようとしても、じしゃくでひきつけられたように、どうしてもにげることができません。そして、いつのまにか、おばけのトラの口の前まですいよせられ、つぎつぎと、口の中へのまれてしまいました。
口の中には、まっかな大きなしたがうごめいていました。
五人は、そのしたの上にころがったまま、気をうしなったようになっていました。
それにしても、地のそこに、どうしてこんな大きなばけものがすんでいるのでしょう。ばけものにたべられた子どもたちは、これから、いったいどうなるのでしょうか。
小林くんと木村くんと、ユウ子ちゃんと井上くんと、ノロちゃんの五人は、ルビーのカブトムシをとりかえすために、世田谷区のさびしい原っぱの、ふしぎなほらあなへはいっていきました。
そのほらあなの中には、ふつうのトラの百ばいもある、おばけのトラがねそべっていて、大きな口へ、五人をのみこんでしまいました。
しばらくして気がついてみると、まだ、トラのしたの上にころがったままで、いぶくろの方へのみこまれていくようすもありません。井上くんは、しっかりにぎりしめていたかいちゅうでんとうで、おばけののどのおくをてらしてみました。
すると、このトラののどのおくには、しょくどうも、いぶくろも、なにもないことがわかりました。
くびだけのトラだったのです。もちろん、いきたトラではなくて、きかいじかけの作り物です。すいよせられたと思ったのは、どこかうしろの方から、大きなせんぷうきのようなもので、ふきつけられたのでしょう。
井上くんは、トラの口から外へ出ようとしましたが、もう口はとじられていて、どうしてもあけることができません。
しかたがないので、小林くんとそうだんして、おくの方へ行ってみることにしました。トラののどのおくは、いままでとおなじコンクリートのほらあなです。かいちゅうでんとうでてらしながら、そこをすすんでいきますと、ばったり行きどまりになってしまいました。
「あっ、ここにドアがあるよ。」
ひとりが、やっととおれるほどの小さいドアです。井上くんが、そのドアのとっ手をつかんでひっぱると、なんなくあきました。まるで、きんこのとびらのように、ひどくぶあつい、がんじょうな鉄のドアです。
五人は、その中へはいりました。すると、ふしぎなことに、そのおもいドアが、すうっと、ひとりでにしまってしまったではありませんか。
井上くんはおどろいて、もう一どあけようとしましたが、こんどは、いくらおしてもびくともしません。それにドアのうちがわには、とっ手もなにもなく、すべすべした鉄のいたです。
「おやっ。ここは、どこにも出口のないまるいへやだよ。」
それは、たたみ二じょうくらいの、いどのそこのようなまるいへやでした。
五人は、コンクリートのつつの中にとじこめられてしまったのです。かいちゅうでんとうでてんじょうをてらしてみると、まるいつつは、ずっと上の方へつづいています。まったくいどのそことおなじです。
「おや、あの音はなんだろう。」ノロちゃんが、おびえた声を出しました。
ほんとうに、へんな音がしています。とおくで、モーターがまわっているような音です。
そのとき、かいちゅうでんとうでてんじょうをてらしていた井上くんが、
「あっ、たいへんだっ。」
とさけんだので、みんなびっくりして、その方を見上げました。
じつにおそろしいことが、おこっていたのです。ごらんなさい。てんじょうから、鉄のふたのようなものが、じりじりとおりてくるではありませんか。
まるいつつのうちがわへ、ぴったりはまったあつい鉄のふたです。それが、しずかにおりてくるのです。
鉄のふたは、モーターの力で、すこしのくるいもなくおりてきます。ああ、もう手をのばせばとどくところまでおりてきました。
「みんな、手をのばして、力をあわせて、あれをささえるんだ。でないと、ぼくたち、おしつぶされてしまうよ。」
小林くんはそういって、まず、自分が両手を上げました。
みんなも、そのまねをして、両手を上げて、鉄のふたをおしもどそうとしました。しかし、それは、ひじょうにおもい鉄のかたまりらしく、五人の力では、とてもささえきれません。じりじり、じりじりと、おりてくるのです。それにつれて、ささえている手が、だんだんさがり、とうとう鉄のふたは、みんなのあたまにくっつくほどになりました。
もう、しゃがむほかはありません。そのつぎには、すわってしまいました。それでもまだ、鉄のふたはおりてくるのです。もう、すわっていることもできないようになり、みんなはあおむけにねころんで、両手と両足でささえようとしましたが、やっぱりだめです。なん百キロというおもさの鉄が、ねているかおのすぐそばまでおりてきました。
ユウ子ちゃんは、なきだしました。ノロちゃんもなきだしました。
「たすけてくれえ……。」
井上くんと木村くんが、かなしい声でさけびました。小林くんさえ、なきだしたくなるほどでした。
ああ、五人は、いったいどうなるのでしょう。
少年たんていだんの小林だんちょうと、だんいんの木村くんと、ユウ子ちゃんと、井上くんと、ノロちゃんの五人が、まほうはかせのあんごうをといて、世田谷区のはずれのさびしい原っぱにあるほらあなへはいっていくと、コンクリートのまるいへやにとじこめられ、上からおもい鉄のふたが、じりじりとさがってきました。鉄のふたにはすきまがないから、そのままさがってきたらたいへんです。
みんな、おしつぶされてしんでしまうにきまっているのです。おくびょうもののノロちゃんや、女の子のユウ子ちゃんは、わあわあとなきだしてしまいました。
しかし、だんちょうの小林くんは、しっかりしていました。いそがしくあたまをはたらかせて、どうしたらみんながたすかるかということを、いっしょうけんめいに考えました。
「まほうはかせは、人ごろしなんかするはずがない。こんなおそろしい目にあわせて、ぼくたちのゆうきとちえをためしているんだ。」
それなら、ちえをはたらかせたら、どこかににげ道があるのかもしれません。
そこで小林くんは、かいちゅうでんとうをもったまま、まるいへやのまわりを、ぐるっとはいまわり、コンクリートのかべをしらべてみました。
すると、コンクリートのかべに、六十センチ四方ほどの、四かくな切れ目がついているのを見つけました。
「これが、ひみつのかくし戸かもしれないぞっ。」
力いっぱいおしてみましたが、びくともしません。
「どこかに、これをひらくしかけがあるにちがいない。」
小林くんはすばやく、そのへんを見まわしました。
四かくな切れ目から、すこしはなれたかべの上の方に、コンクリートが小さくふくらんだところがあります。よくしらべてみると、そのぼっちは、コンクリート色にぬった金物かなものであることがわかりました。
「ああ、そうだ。鉄のふたが下までおりたら、ぼくたちがしんでしまうから、下までおりないうちに、にげ出せるしかけになっているのだ。」
「鉄のふたが、このぼっちのところをとおると、ぼっちがおされる。そうすると、ひみつの戸が外へひらくようになっているのだ。」
小林くんは、とっさに、そこへ気がつきました。
「それなら、手でおしたって、ひらくかもしれないぞ。」
そこで、ぼっちにおやゆびをあて、その上に、もう一方の手をかさねて、力いっぱいおしてみました。
ぼっちは、なかなか動きません。たいへんな力がいるのです。小林くんは、からだじゅう、あせびっしょりになりました。でも、がまんをして、うんうんおしつづけていますと、カタンという音がして、四かくな切れ目が、すうっとむこうへひらきました。小林くんのちえとゆうきが、せいこうしたのです。
そこは、にんげんひとりがやっとはってとおれるほどのまっくらなあなでした。小林くんは、みんなをよんで、そのあなへはいこみました。きみがわるいけれども、じっとしていたら、鉄のふたにおしつぶされてしまうだけですから、このあなへにげるほかはないのです。
そのまっくらできゅうくつなあなは、十メートルもつづいていました。
やがて、あたりがきゅうにひろくなりました。外へ出たのでしょうか。いや、そうではありません。まだまっくらです。やはり、地のそこの一室なのです。
たち上がって、かいちゅうでんとうでてらしてみますと、それは、二十じょうもあるような、コンクリートのへやでした。みんなが、そのへやにはいったとき、どこからか、ぎょっとするような声がひびいてきました。
「わははは……。かんしん、かんしん。とうとう、あぶないところをぬけ出したね。だが、まだこれでおしまいじゃないよ。わしの手紙には、『おそろしい番人に注意せよ。』と書いてあった。だい一は大トラ、だい二は鉄のふた、さて、だい三の番人はなんだろうね。おしまいほどおそろしいやつがひかえているからね。ようじんするがいいよ。」
まほうはかせの声です。どこから聞えてくるのかわかりません。きっとてんじょうのすみに、ラウド=スピーカーでもしかけてあるのでしょう。
五人は一かたまりになって、おたがいのからだをだきあってじっとしていました。ノロちゃんのからだが、がたがたふるえているのがよくわかります。
「あれっ、なんだろう。なにか動いているよ。」
木村くんが、むこうのゆかをゆびさしてさけびました。かいちゅうでんとうの光が、さっとその方をてらします。
するとそこに、なんだかきみのわるいことがおこっていました。
地のそこから、みょうなものがむくむくとあらわれてきたのです。
まるいあたまのようなものが出てきました。
それが、見る見る大きくなります。あなもなにもないコンクリートのゆかから、むくむくと上がってくるのです。子どもくらいの大きさになりました。おとなくらいになりました。おとなのばいになりました。おとなの三ばいになりました。大きなあたまの、まっさおなからだの、のっぺらぼうなかいぶつです。それが、きりもなく大きくなっていくのです。
小林くんと、木村くんと、ユウ子ちゃんと、井上くんと、ノロちゃんの五人は、ルビーのカブトムシをとりかえすために、まほうはかせのすみかのちか室へはいっていって、いろいろなおそろしいめにあいました。ちか室には広いへやがあって、五人がそこへはいると、へやのまん中に、むくむくとみょうなかいぶつがあらわれました。
たまごに目と口をつけたような、おかしなやつです。それが、見るまにだんだん大きくなり、おとなの三ばいもあるような大にゅうどうになってしまいました。そして、
「わははははは……。」
と、かみなりのようなわらい声が聞えました。
みんなは、思わずもと来た方へにげだしましたが、せまい入口にはいこもうとして、ふと、うしろを見ますと、おやっ、あのかいぶつは、どこへ行ったのか、かげも形もなくなっていました。かいちゅうでんとうでよくしらべてみましたが、へやは、まったくからっぽで、なにもないのです。
四方のかべはかたいコンクリートで、どこにも出口はありません。
みんなは、いよいよきみがわるくなってきました。
「へんだなあ。あいつ、けむりのようにきえてしまったよ。」
ノロちゃんが、とんきょうな声でいいました。
「あっ、ごらん。なんだか、動いてる。」
またしても、じめんから、ぶきみなものがわき出してきました。まっさおなものです。それが、かおからかた・はら・こしとせり出して、おとなぐらいの大きさになりました。
「あっ、せいどうのまじんだ。」
小林くんがさけびました。ずっと前に、少年たんていだんがたたかった、あのおそろしい、せいどうのまじんと、そっくりなのです。
せいどうでできたような、青いやつです。耳までさけた口で、にやにやわらっています。それが見る見る大きくなって、やっぱりおとなの三ばいほどになりました。あたまがてんじょうにつかえています。
「ギリリリリ、ギリリリリ……。」
はぐるまの音がします。せいどうのまじんの中に、はぐるまがしかけてあるのでしょうか。
「わはははは……。ちんぴらども、よく来たな。きみたちのさがしていた赤いカブトムシは、このわしが持っている。ほら、ここにあるよ。」
まっさおなきょじんは、おそろしい声でそういうと、耳までさけた口をぱっくりあけました。
三日月がたの、まっ黒なほらあなのような口です。
その口から、ぺろぺろと赤いしたを出しました。そのしたの上に、まっかなカブトムシが乗っているではありませんか。
せいどうのまじんは、口の中に、ルビーのカブトムシをかくしていたのです。少年たちはそれを見ると、思わず、「あっ。」とさけびました。しかし、あい手はおそろしいかいぶつです。とりかえすことは、とてもできそうにありません。
「わははは……。これがほしくないのかね。おくびょうなちんぴらどもだな。くやしかったら、わしのかおまでのぼってきてみろ。そして、わしの口の中から、これをとり出せばいいのだ。わはははは……。そのゆうきが、きみたちにあるかね。」
せいどうのまじんは、少年たちをばかにしたように、大きなからだをゆすってわらうのでした。
「ちくしょう。みんな来たまえ。」
おとうさんから、けんどうをならっている、井上一郎くんはそうさけぶと、いきなり、かいぶつの右の足にしがみついていきました。
あいては、おとなの三ばいもあるきょじんです。まるでこれは、すもうとりの足に赤んぼうがしがみついているようです。
そのとき、ガラガラガラッという、おそろしい音がして、あたりが、ぽっと明るくなりました。やみになれたみんなの目には、まぶしくて、目をあけていられないほどの明るさです。
いったい、なにごとが起ったのでしょう。やっと目を開いてみますと、ふしぎふしぎ、ちか室のてんじょうがなくなっているではありませんか。
てんじょうがきかいじかけで、両方へ開くようになっていたのです。上には、青空が見えています。たいようの光が、さんさんとあたりにかがやいています。
「あっ、たいへんだ。井上くんが……。」
小林くんが、びっくりしてさけびました。ほんとうに、たいへんなことが起っていたのです。
ごらんなさい。せいどうのまじんのからだが、すうっとちゅうにういたかと思うと、そのまま、ふわふわ空へまい上がっています。足にしがみついた井上くんも、いっしょにつれたままです。
これも、まほうはかせのまほうでしょうか。
それにしても、これから、いったいどんなことが起るのでしょう。
ちか室のてんじょうが大きく開いて、おとなの三ばいもあるせいどうのまじんが、ふわふわとちゅうにうき、そのまま空の方へまい上がっていきました。
まじんの足にしがみついていた井上一郎くんも、いっしょに、空へまい上がっていくのです。
「おうい、井上君、手をはなせよ。そして、下へとびおりるんだっ。」
下から、小林くんが、大声でさけびました。
まじんの足は、ちか室のゆかから、もう三メートルもうき上がっていましたが、井上くんは思い切って手をはなし、ぱっととびおりました。
そして、コンクリートのゆかにしりもちをついて、かおをしかめています。
「あいつ、赤いカブトムシを口に入れたまま、とんでいってしまったよ。早く追っかけなけりゃあ。」
「よしっ。なわばしごだっ。」
小林くんはそうさけぶと、おなかのシャツの下にまきつけていた、じょうぶなきぬひものなわばしごをするするとほどいて、その一方のはしについている鉄のかぎを、開いたてんじょうへ投げ上げました。
なん度もしくじったあとで、やっとそのかぎが、てんじょうのあなのふちにひっかかったのです。
しょうねんたんていだんのなわばしごは、一本のきぬひもです。それに三十センチごとに大きなむすび玉がついていて、そこへ足のゆびをかけてのぼるのです。
「じゃあ、ぼくがさきにのぼるから、みんな、あとから来るんだよ。」
小林くんはそういって、きぬひものなわばしごをぐんぐんのぼっていくのでした。
そのあとから、みんなのぼりました。ユウ子ちゃんは女の子ですから、井上くんたちが上から手をのばして、引き上げてあげました。
あなの外へ出ると、そこは、草ぼうぼうの原っぱでした。さいしょにのぼった小林くんが、むこうへ走っていくすがたが小さく見えます。いったい、どこへ行こうとするのでしょう。
空を見上げると、せいどうのまじんは、ふうせんのように、高く高くとんでいきます。
「わあ、よくとぶねえ。もう、あんなに小さくなっちゃった。」
ノロちゃんがさけびました。
あとでわかったのですが、せいどうのまじんはあついビニールでできていて、中にかるいガスを入れたものでした。つまり、ふうせんだったのです。
ちか室のゆかに小さなあながあいていて、その下に、また、小べやがあったのです。そこにまほうはかせがかくれていて、あなからビニールのまじんをゆかの上におし出しながら、ポンプでガスをふきこんだのです。
ガスがはいるにしたがって、ビニールのまじんはふくれあがり、しまいには、おとなの三ばいもあるきょじんになってしまったのでした。
せいどうのまじんがものをいったのは、ゆかのあなの下から、まほうはかせが、声をかえてしゃべっていたのです。
まじんが口を開いたのは、あごに細い糸がついていて、それを下からひっぱると口があき、糸をはなすと、口がしまるようになっていたのです。赤いカブトムシは、したにくくりつけてあったのでしょう。
まじんが出る前にあらわれた、たまごのおばけみたいなものも、やっぱりビニールでできていて、一度ガスを入れてふくらまし、みんながにげ出している間に、きゅうにそのガスをぬいたので、ビニールはぺちゃんこになり、ゆかのあなの下へかくれてしまったのです。
ちか室が暗いので、小林くんたちは、その小さなあなのしかけがよく見えなかったのでした。
空のせいどうのまじんは、だんだんすがたを小さくしながら、東の方へとんでいきます。東の方へ風がふいているのでしょう。まじんは、赤いカブトムシを口に入れたまま、その風に送られて、どことも知れずとびさっていきます。
「あっ、もう、見えなくなってしまった。」
木村くんがさけびました。
そのとき、原っぱのむこうから、小林くんがかけもどってくるのが見えました。
「小林さあん、どこへ行ってたの。あいつは、赤いカブトムシを口に入れたまま空へのぼって、もう、見えなくなってしまったよ。」
井上くんがよびかけますと、みんなのそばへかけよってきた小林くんが、いきをはずませて答えました。
「明智先生に、でんわをかけたんだよ。
明智先生に、せいどうのまじんのことを知らせたらね、先生は、すぐに新聞社へでんわしてから、自動車で、あるところへとんでいってくださったんだよ。そして、いまにむこうの空から、みかたがとんでくるんだよ。」
小林くんが、東京の町の方の空をゆびさしました。いったい、空からなにがやって来るのでしょうか。
三十分あまりも待ったでしょうか。もう夕ぐれ近いむこうの空に、ぽつんと、黒いてんのようなものがあらわれました。
「あっ、来た、来た。あれだよ。」
小林くんがうれしそうにいいました。
てんのようなものは、だんだん大きくなって、こちらへ近づいてきます。それは、一台のヘリコプターでした。みなさん、しょうねんたんていだんのみかたというのは、このヘリコプターだったのです。
しょうねんたんていだんのおうえんにやって来たヘリコプターは、強い風をまき起しながら、原っぱのまん中へちゃくりくしました。
「あっ、明智先生だっ。」
小林だんちょうがさけんで、その方へかけ出しました。
ヘリコプターの、すきとおったそうじゅう室のとびらが開いて、明智たんていがおりてきました。
めいたんていは、ひこうきでもヘリコプターでも、そうじゅうできるのです。
明智たんていは、小林くんのでんわをきくと、いそいで新聞社とうちあわせ、新聞社のヘリコプターを、自分でそうじゅうして、とんできたのです。
みんなは明智たんていのまわりをとりかこんで、ちか室でおそろしいめにあったことを、口々に話すのでした。
「よし、それじゃあ、このヘリコプターで、せいどうのまじんを追いかけるんだ。」
明智たんていは、みんなにさしずをしました。
「小林くんと井上くんとふたりだけ、ぼくといっしょに乗りたまえ。それいじょうは乗れない。のこった人は、みんなうちへ帰って、待っていたまえ。きっと、せいどうのまじんをとらえてみせるよ。そして、赤いカブトムシをとりかえしてあげるよ。」
明智たんていと、小林くん・井上くんのふたりがヘリコプターに乗りこみました。
ヘリコプターはまた、おそろしい風を起して、とび上がっていきます。原っぱにのこったノロちゃんと木村くんと、ユウ子ちゃんは、手をふって、それを見送りました。
小林くんと井上くんは、はじめてヘリコプターに乗ったのです。うちゅうりょこうにでも出かけるような気持でした。
ヘリコプターは、高い空を、せいどうのまじんがとびさった東の方へ進んでいきます。
ふりむくと西の空は、まっかな夕やけでした。やがて、日がくれるのです。そのときのよういに、そうじゅう室には、小がたのサーチライトがそなえつけてあります。
せいどうのまじんは、風にはこばれていったのですから、風のふく方へ追いかければよいのです。こちらには風のほかに、プロペラの力があります。きっと、追いつくことができるでしょう。
やがて、夕やけもきえ、見る見るあたりが暗くなってきました。空にはいちめんに、星がまたたき始めました。ちじょうには、いなかの町のでんとうが、これも星のように、ちらほら見えています。上にも星、下にも星、ほんとうにうちゅうりょこうです。
「あっ、先生。あそこに、なんだかとんでいますよ。」
小林くんのさけび声に、ぱっとサーチライトがてんじられました。その光のとどかないほどむこうの空に、なんだか黒っぽいものがふわふわとただよっています。ヘリコプターは、その方へしんろをむけました。
「あっ、やっぱりそうだ。にんげんの形をしている。せいどうのまじんですよ。」
やがてそれが、サーチライトの光の中へはいってきました。たしかに、せいどうのまじんのふうせんです。
「小林くん、これで、あいつのからだをうつんだ。いまに、あいつのすぐよこを通るからね。そのとき、ドアをすこしあけて、右手を出して、うつんだ。」
明智たんていはそういって、小林くんにピストルをわたしました。小林くんはたんていじょしゅですから、ピストルのうちかたは知っています。
明智たんていは、ヘリコプターをうまくそうじゅうして、せいどうのまじんのすぐよこに近づき、そくどをおとしてならんでとぶようにしました。小林くんはいわれたとおり、ドアのすきまから手を出して、まじんのからだにピストルをはっしゃしました。
すぐ目の前をふわふわとんでいたまじんが、ぐらっとゆれました。ピストルのたまがめいちゅうしたのです。つづいて、二はつ、三ぱつ……。
そのたびに、まじんのふうせんは、ぐらっぐらっとゆれるのです。そして、たまのあなから、シューッと、ガスがぬけていくのです。
「よしっ。それでいい。こんどはヘリコプターで、あいつをおさえつけるんだ。」
明智たんていは、ヘリコプターをまじんの前にもっていって、そのままぐっとこうどをさげました。
すると、それにおされて、まじんはよこたおしになり、ヘリコプターのそこにぴったりくっついてしまいました。
「よしっ。このままで、どこかの原っぱへちゃくりくしよう。もう、にがしっこないよ。」
サーチライトを下へむけると、手ごろなばしょを見つけて、たんていはぐんぐんヘリコプターをさげました。そして、まっ暗な畑の中へちゃくりくしたのです。
三人は、ヘリコプターからとび出しました。そして、かいちゅうでんとうをてらして、きたいの下をのぞきました。ビニールのまじんのふうせんは、ガスがぬけ、ぺっちゃんこになって、そこにひっかかっていました。
ひきずり出して口の中をしらべますと、したの上に、赤いルビーのカブトムシが、ちゃんとくっついていたではありませんか。とうとうとりもどすことができたのです。
あくる日、明智たんていじむしょの小林くんのところへ、でんわがかかってきました。まほうはかせからでした。
「きみたちの勝ちだよ。ルビーは、きみたちのものだ。いろいろ苦しめてすまなかったね。だが、あれは、きみたちのちえとゆうきをためすためだったのだよ……。しょうねんたんていだん、おめでとう。明智先生によろしく。」
小林くんはじゅわきをおくと、よこにたって聞いていた明智先生とかおを見あわせて、にっこりわらうのでした。
底本:「新宝島」江戸川乱歩推理文庫、講談社
1988(昭和63)年11月8日第1版発行
初出:「たのしい三年生」講談社
1958(昭和33)年4月~1959(昭和34)年3月
入力:sogo
校正:岡村和彦
2016年6月10日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
悪魔の紋章
江戸川乱歩
法医学界の一権威宗像隆一郎むなかたりゅういちろう博士が、丸の内のビルディングに宗像研究室を設もうけ、犯罪事件の研究と探偵の事業を始めてからもう数年になる。
同研究室は、普通の民間探偵とは違い、其筋そのすじでも手古摺てこずるほどの難事件でなければ、決して手を染めようとはしなかった。所謂いわゆる「迷宮入り」の事件こそ、同研究室の最も歓迎する研究題目であった。宗像博士は、研究室開設第一年にして、すでに二つの難事件を見事に解決し、一躍その名声を高め、爾来じらい年毎ごとに著名の難事件を処理して、現在では、名探偵と云えば、明智小五郎あけちこごろうか宗像隆一郎かというほどに、世に知られていた。
天才明智は、その生活ぶりが飄々ひょうひょうとしていて、何となく捉とらえどころがなく、気に入った事件があれば、支那へでも、印度インドへでも、気軽に飛び出して行って、事務所を留守にすることも多いのに反して、宗像博士の方は、明智のような天才的なところはなかったけれど、あくまで堅実で、科学的で、東京を中心とする事件に限って手がけるという、実際的なやり方であったから、期せずして市民の信頼を博し、警視庁でも、難事件が起ると、一応は必ず宗像研究室の意見を徴ちょうするという程になっていた。
事務所なども、明智の方は住宅兼用の書生しょせい流儀であったのに反して、宗像博士は、家庭生活と仕事とをハッキリ区別して、郊外の住宅から毎日研究室へ通い、博士夫人などは一度も研究室へ顔出しをしたことがなく、又研究室の二人の若い助手は、一度も博士の自宅を訪ねたことがないという、厳格極きわまるやり口であった。
丸の内の一郭かく、赤煉瓦あかれんが貸事務所街のとある入口に、宗像研究室の真鍮しんちゅう看板が光っている。赤煉瓦建ての一階三室が博士の探偵事務所なのだ。
今、その事務所の石段を、這はうようにして上って行く、一人の若い背広服の男がある。二十七八歳であろうか、その辺のサラリー・マンと別に変ったところも見えぬが、ただ異様なのは、トントンと駆け上るべき石段を、まるで爬虫類はちゅうるいででもあるように、ヨタヨタと這い上っていることである。急病でも起したのであろうか、顔色がんしょくは土のように青ざめ、額から鼻の頭にかけて、脂汗あぶらあせが玉をなして吹き出している。
彼はハッハッと、さも苦しげな息を吐きながら、やっと石段を昇り、開いたままのドアを通って、階下の一室に辿たどりつくと、入口のガラス張りのドアに、身体からだをぶッつけるようにして、室内に転がり込んだ。
そこは、宗像博士の依頼者接見室で、三方の壁の書棚には博士の博識を物語るかの如ごとく、内外の書籍がギッシリと詰まっている。室しつの中央には畳一畳敷程の大きな彫刻つきのデスクが置かれ、それを囲んで、やはり古風な彫刻のある肘掛椅子ひじかけいすや長椅子が並んでいる。
「先生、先生はどこです。アア、苦しい。早く、先生……」
若い男は床の上に倒れたまま、喘あえぎ喘ぎ、精一杯の声をふり絞しぼって叫んだ。
すると、唯ただならぬ物音と叫び声に驚いたのであろう、隣の実験室へ通じるドアが開いて、一人の男が顔を出した。これも三十歳程に見える若い事務員風の洋服男である。
「オヤッ、木島きじま君じゃないか。どうしたんだ、その顔色は?」
彼はいきなり室内に駈け込んで、若者を抱き起した。
「アア、小池こいけ君か。せ、先生は? ……早く会いたい。……重大事件だ。……ひ、人が殺される。……今夜だ。今夜殺人が行われる。アア、恐ろしい。……せ、先生に……」
「ナニ、殺人事件だって? 今夜だって? 君はどうしてそれが分ったのだ。一体、誰が殺されるんだ」
小池と呼ばれた若者は、顔色を変えて木島の気違いめいた目を見つめた。
「川手かわての娘だ。……その次は親爺おやじの番だ。みんな、みんなやられるんだ。……せ、先生は? 早く先生にこれを。……この中にすっかり書いてある。それを先生に……」
彼はもがくようにして、胸のポケットを探ると、一通の厚ぼったい洋封筒を取出して、やっとの思いで、大おおデスクの端にのせた。そして、次には同じポケットから、何かしら四角な小さい紙包を掴つかみ出し、さも大切そうに握りしめている。
「先生は今御不在だよ。三十分もすればお帰りになる筈だ。それよりも、君はひどく苦しそうじゃないか。どうしたというんだ」
「あいつに、やられたんだ。毒薬だ。アア、苦しい。水を、水を……」
「よし、今取って来てやるから、待ってろ」
小池は隣室へ飛んで行って、化学実験用のビーカーに水を入れて帰って来ると、病人を抱えるようにして、それを飲ませてやった。
「しっかりしろ。今医者を呼んでやるから」
彼は又病人の側そばを離れて、卓上電話にしがみつくと、附近の医院へ至急来診を頼んだ。
「すぐ来るって。ちょっとの間我慢しろ。だが、一体誰にやられたんだ。誰が君に毒なんか飲ませたんだ」
木島は、半ば白くなった目を見はって、ゾッとするような恐怖の表情を示した。
「あいつだ。……三重さんじゅうの渦巻うずまきだ。……ここに証拠がある。……こいつが殺人鬼だ。アア、恐ろしい」
彼は歯を喰いしばって、もがき苦しみながら、右手に握った小さな紙包みを示した。
「よし、分った。この中に犯人の手掛りがあるんだな。しかし、そいつの名は?」
だが、木島は答えなかった。もう両眼の虹彩こうさいが上瞼うわまぶたに隠れてしまっていた。
「オイ、木島君、木島君、しっかりしろ、名だ。そいつの名を云うんだ」
いくら揺すぶっても、木島の身体は水母くらげのように手応えがなかった。
可哀想に、宗像研究室の若き助手木島は、捜査事業の犠牲となって、遂に無残の最期をとげたのであった。
五分程すると、附近の医師が来診したが、最早や脈搏も鼓動も止った木島を、どうすることも出来なかった。
待ち兼ねた宗像博士が研究室に帰って来たのは、それから四十分程のちであった。
博士は見たところ四十五六歳、黒々とした頭髪を耳の辺で房のように縮らせ、ピンとはねた小さな口髭くちひげ、学者臭く三角に刈った濃い顎髯あごひげ、何物をも見透す鷲わしのように鋭い目には、黒鼈甲縁くろべっこうぶちのロイド眼鏡めがねをかけ、大柄なガッシリした身体を、折目正しい夏のモーニングに包んで、少し反そり身になって、大股に歩を運ぶところ、如何いかにも帝政独逸ドイツ時代の医学博士という趣きであった。
博士は小池助手から、事の次第を聞き取ると、痛ましげに愛弟子まなでしのなきがらを見おろしながら、
「実に気の毒なことをした。木島君の家へは知らせたかね」
と、小池助手に訊たずねた。
「電報を打ちました。やがて駈けつけて来るでしょう。それから警視庁へも電話しました。中村さん驚いてました。すぐ来るということでした」
「ウン、中村君も僕も、川手の事件が、こんなことになろうとは、想像もしていなかったからね。中村君なんか、被害妄想だろうって、取り合わなかったくらいだ。それが、木島君がこんな目に合う程では、余程よほど大物らしいね」
「木島君は、何だか非常に怖がっていました。恐ろしい、恐ろしいと言いつづけて死んで行きました」
「ウン、そうだろう。予告して殺人をするくらいの奴やつだから、余程兇悪な犯人に違いない。小池君、外ほかの事件は放って置いて、今日からこの事件に全力を尽そう。木島君の敵討かたきうちをしなけりゃならないからね」
話しているところへ、慌あわただしい靴音がして、警視庁の中村捜査係長が入って来た。鼠色の背広姿である。
彼は木島の死体を見ると、帽子を取って黙礼したが、驚きの表情を隠しもせず、宗像博士を顧かえりみて云った。
「こんなことになろうとは思いもよらなかった。油断でした。あなたの部下をこんな目に合わせて、実に何とも申訳ありません」
「イヤ、それはお互たがいです。僕だって、これ程の相手と思えば、木島君一人に任せてなんぞ置かなかったでしょうからね」
「電話の話では、木島君は何か犯人の手掛りを持って帰ったということでしたが」
係長が小池助手を振返った。
「エエ、これです。この封筒の中に詳しく報告を書いて置いたと云っていました」
小池が大デスクの上の例の洋封筒を取って差出すのを、宗像博士が受取って、裏表を調べながら呟つぶやいた。
「オヤ、この封筒は銀座ぎんざのアトランチスの封筒じゃないか。すると、木島君はあのカフェで、用紙と封筒を借りて、これを書いたんだな」
如何にも、封筒の隅に、カフェ・アトランチスの名が印刷されていた。
博士は卓上の鋏はさみを取って、丁寧に封筒の端を切ると、厚ぼったい書翰箋しょかんせんを抜き出して、開いて見た。
「オイ、小池君、確かにこれに違いないね? 君は何か思い違いをしてやしないかね。それとも、木島君が倒れてから、誰かこの部屋へ入ったものはなかったかね」
博士が妙な顔をして、小池助手にただした。
「イイエ、僕は一歩もこの部屋を出ませんでした。誰も来たものなぞありません。どうかしたのですか。その封筒は確かに木島君が内ポケットから出して、そこへ置いたままなんです」
「見給たまえ、これだ」
博士は用箋を中村係長と小池助手の前に差出して、パラパラとめくって見せたが、不思議なことに、それはただの白紙の束に過ぎなかった。文字なぞ一字も書いてはないのだ。
「変だなア、まさか木島君が、白紙を封筒に入れて、大切そうに持って来る訳わけはないが」
中村氏が、狐きつねにつままれたような顔をした。
宗像博士は、唇を噛かんで暫しばらく黙っていたが、突然、白紙の束を紙屑籠かみくずかごに投げ入れると、決定的な口調で云った。
「小池君、すぐアトランチスへ行って、木島君が用紙と封筒を借りたあとで、誰かと話をしなかったか、同じテーブルに胡乱うろんな奴がいなかったか調べてくれ給え。そいつが犯人か、少くとも犯人の相棒に違いない。木島君の油断している隙に、報告書の入った封筒と、この白紙の封筒とすり換えたんだ。毒を飲ませたのも、同じ奴かも知れない。出来るだけ詳細に調べてくれ給え」
「承知しました。しかし、もう一つ、木島君が持って来たものがあるんです。死体の右手をごらん下さい。そこに掴んでいるものは、余程大切な証拠品らしいんです。……では、僕失礼します」
小池助手はテキパキと云い捨てて、帽子を掴むと、いきなり外へ飛び出して行った。
小池助手を見送ると、宗像博士は死体の上に屈かがんで、その手を調べた。小さな紙包を握っている。死んでもこれだけは手放すまいとするかの如く、固く固く握りしめている。博士は死人の指を一本一本引きはなして、やっとそれをもぎ取ることが出来た。
何か小さな板切れのようなものが、丁寧に幾重いくえにも紙を巻いて、紐ひもでくくってある。博士は隣りの実験室から、一枚のガラス板を持って来て、紙包をその上に乗せ、なるべくそれに手をふれないように、ナイフとピンセットを使って、紐を切り、紙を解いて行った。
博士も無言、それをじっと見つめている捜査係長も無言、ただ時々ナイフやピンセットがガラス板に触れて、カチカチと小さな音を立てるばかり、まるで、手術室のような薄気味悪い静けさであった。
「なあんだ、靴箆くつべらじゃありませんか」
中村係長が頓狂とんきょうな声を出した。如何にも紙包の品物は、一枚の小型の象牙色ぞうげいろをしたセルロイド製のありふれた靴箆である。
木島助手は気でも違ったのであろうか。封筒の中へ大切そうに白紙の束を入れていたかと思うと、今度は御丁寧な靴箆の紙包だ。一体こんなものに何の意味があるというのだろう。
しかし、博士は別に意外らしい様子もなく、さも大切そうに、その靴箆の端をソッと摘つまむと、窓からの光線にすかして見たが、その時分にはもう、窓の外に夕闇が迫っていて、十分調べることが出来なかったので、部屋の隅のスイッチを押して電燈をつけ、その光の下で、靴箆を入念に検査した。
「指紋ですか」
中村係長が、やっとそこへ気がついて訊ねた。
「そうです。しかし……」
博士は吸いつけられたように靴箆の表面に見入って、振り向こうともしないのである。
「外側の指紋は皆重なり合っていて、はっきりしないが、内側に一つだけ、非常に明瞭な奴がある。拇指おやゆびの指紋らしい。オヤ、これは不思議だ。中村君、実に妙な指紋ですよ。僕はこんな不思議な指紋を見たことがない。まるでお化けだ。それとも僕の目がどうかしているのかしら」
「どれです」
中村氏が近づいて、博士の手元を覗き込んだ。
「ホラ、こいつですよ。すかしてごらんなさい。完全な指紋でしょう。別に重なり合ってはいない。しかし、ホラ、渦が三つもあるじゃありませんか」
「そういえば、なる程、妙な指紋らしいが、このままじゃ、よく見分けられませんね」
「拡大して見ましょう。こちらへ来て下さい」
博士は靴箆を持って、先に立って隣りの実験室へ入って行った。中村係長もそのあとにつづく。
十坪程の部屋である。一方の窓に面して大きな白木の化学実験台があり、その上に大小様々のガラス器具、顕微鏡などが置かれ、一方には夥おびただしい瓶の並んだ薬品棚が立っている、化学実験室と調剤室とを一緒にしたような眺めだ。
又別の隅には、大型写真器、紫外線、赤外線、レントゲンの機械まで揃っている。それらの間に、黒い幻燈器械の箱が、頑丈がんじょうな三脚にのせて置いてある。実物幻燈器械なのだ。これによって指紋は元より、あらゆる微細びさいな品物を拡大して、スクリーン上に映し出すことが出来る。指紋は紙や板に捺おされたものと限らない。ガラス瓶びんであろうが、ドアの把手ハンドルであろうが、コップであろうが、ピストルであろうが、それらの実物の指紋の部分を、直ちに拡大して映写することが出来る。博士自慢の装置である。
中村捜査係長は、この部屋へは度々たびたび入ったことがあるのだが、入る度毎ごとに、まるで警視庁の鑑識課をそのまま縮小したようだと感じないではいられなかった。イヤ、この部屋には鑑識課にもないような、宗像博士創案の奇妙な器械も少くはないのだ。
博士は先ず靴箆を実験台の上に置いて、指紋の部分に黒色粉末を塗り、隆線を黒く染めてから、窓の紐ひもを引いて厚い黒繻子くろしゅすのカーテンを閉め、部屋を暗室にすると、幻燈内の電燈を点火し、靴箆を器械に挿入して、ピントを合せた。
忽たちまち部屋の一方の壁のスクリーン上に、巨大な指紋の幻燈が映し出された。五分にも足らぬ拇指の指紋が、三尺四方程に拡大され、指紋の隆線の一本一本が黒い紐のように渦巻いている。
博士も係長も、暗闇の中でじっとそれを見つめたまま、暫しばらくは口を利くことさえ出来なかった。二人とも、指紋ではなくて、何かしらえたいの知れぬ化物に睨にらみつけられているような、不思議な気味悪さを感じたからだ。
アア、何という奇怪な指紋であろう。一箇の指紋に三つの渦巻があるのだ。大小二つの渦巻が上部に並び、その下に横に長い渦巻がある。じっと見ていると、異様な生きものの顔のように見えて来る。上部の二つの渦巻は怪物の目玉、その下の渦巻はニヤニヤと笑った口である。
「中村君、こんな指紋を見たことがありますか」
闇の中から、博士の低い声が訊ねた。
「ありませんね。僕も相当色々な指紋を見ていますが、こんな変な奴には出くわしたことがありません。指紋の分類では変態紋へんたいもんに属するのでしょうね。渦巻が二つ抱き合っているのは、たまに出くわしますが、渦巻が三つもあって、こんなお化みたいな顔をしている奴やつは、全く例がありません。三重渦状紋とでも云うのでしょうか」
「如何にも、三重渦状紋に違いない。これはもう隆線を数えるまでもありませんよ。一目で分る。広い世間に、こんな妙な指紋を持った人間は、二人とあるまいからね」
「拵こしらえたものじゃないでしょうね」
「イヤ、拵えたものでは、こんなにうまく行きませんよ。この位に拡大して見れば、拵えものなれば、どこか不自然なところがあって、じき見破ることが出来るのですが、これには少しも不自然な点がない」
そして、闇の中の二人は、目と口のある巨大な指紋に圧迫されたかの如く、又黙り込んでしまった。
暫らくして、中村係長の声。
「それにしても、木島君は、この妙な指紋をどうして手に入れたのでしょう。この靴箆が犯人の持物とすれば、木島君は犯人に会っている訳ですね。直接犯人から掠かすめて来たものじゃないでしょうか」
「そうとしか考えられません」
「残念なことをしたなア。木島君さえ生きていてくれたら、易々と犯人を捉えることが出来たかも知れないのに」
「犯人はそれを恐れたから、先手を打って毒を呑のませ、その上、報告書まで抜き取ってしまったのです。実に抜け目のない奴だ。中村君、これは余程大物ですよ」
「あの強情な木島君が、恐ろしい恐ろしいと云いつづけていたそうですからね」
「そうです。木島君は、そんな弱音を吐くような男じゃなかった。それだけに、僕らは余程用心しなけりゃいけない。……川手の家は、あなたの方から手配がしてありますか」
博士は心配らしく、せかせかと訊ねた。
「イヤ、何もして居りません。今日までは川手の訴えを本気に受取っていなかったのです。しかし、こうなれば、捨てては置けません」
「すぐ手配をして下さい。木島君をこんな目に合せたからは、犯人の方でも事を急ぐに違いない。一刻を争う問題です」
「おっしゃるまでもありません。今からすぐ帰って手配をします。今夜は川手の家へ三人ばかり私服をやって、厳重に警戒させましょう」
「是非ぜひそうして下さい。僕も行くといいんだけれど、死骸を抛ほうって置く訳に行きません。僕は明日の朝、川手氏を訪問して見ることにしましょう」
「じゃ、急ぎますから、これで」
中村係長は云い捨てて、あたふたと夕闇の街路へ駈け出して行った。
あとに残った宗像博士は、幻燈の始末をすると、指紋の靴箆をガラスの容器に入れて、鋼鉄製の書類入れの抽斗ひきだしに納め、厳重に鍵をかけた。次の間には、部下の無残な死体が、元のままの姿で横たわっている。今に家族のものが駈けつけて来るであろう。又検事局から検視の一行も来るであろう。しかし、それを待つ間、このままの姿では可哀想だ。
博士は奥の部屋から一枚の白布を探し出して来て、黙祷もくとうしながら、それをフワリと死体の上に着せてやった。
H製糖株式会社取締役川手庄太郎しょうたろう氏は、ここ一カ月ほど前から、差出人不明の脅迫状に悩まされていた。
「拙者せっしゃは貴殿に深き恨うらみを抱くものである。長の年月としつきを、拙者は、ただ貴殿への復讐準備の為に費ついやして来た。今や準備は全く整った。愈々いよいよ恨みをはらす時が来たのだ。貴殿一家は間もなく鏖みなごろしに会うであろう。一人ずつ、一人ずつ、次々と世にもいまわしき最期をとげるであろう」
という意味の手紙が、毎日のように配達された。一通毎に筆蹟ひっせきが違っていた。ひどく下手な乱暴な書体であった。差出局の消印もその度毎に違っていたし、封筒も用紙も最もありふれた安物で、全く差出人の所在をつきとめる手掛りがなかった。
脅迫は必ずしも手紙ばかりではなかった。ある時は電話口にえたいの知れぬ声が響いた。
「川手君、久しぶりだなア。僕の声が分るかね、ホホホホホホ。君には美しい娘さんが二人あるねえ。僕はね、先まず手初めに、その娘さんの方から片づけることに極きめているんだよ。ホホホホホホ」
非常に優しい鼻声であった。恐らく電話口で鼻を抑えて物を云っていたのであろう。彼は一言喋しゃべる度に、ホホホホホホホと女のように笑ったが、その奇妙な笑い声が川手氏を心の底から震ふるい上らせてしまった。
無論むろん声には聞き覚えがなかった。局に問合せて見ると、自働電話からという答えで、やっぱり相手の正体を掴む手掛りがなかった。
川手氏は今年四十七歳、無一文から現在の資産を築き上げた人物だけに、事業上の敵などは数知れずあったし、事業以外の関係でも、随分ずいぶんむごたらしい目に会わせた相手がないではなかった。だが、それらの記憶を一つ一つ辿って見ても、今度の脅迫者を探し当てることは出来なかった。
「若もしやあれでは?」
と思われるものが一二ないではなかったけれど、それらの相手は皆死んでしまっているし、子孫とても残っていないことが分っていた。いくら考えても脅迫者の素性すじょうが分らぬだけに、一層不気味であった。前半生にいじめ抜いた相手が、怨霊おんりょうとなって彼の身辺にさまよっているような、何とも云えぬ恐怖を感じないではいられなかった。
川手氏は遂に堪たまらなくなって、このことを警視庁に訴え出た。だが警視庁では、所轄警察署へよく話して置くからというような返事をしたまま、一向取合ってくれないので、次には民間探偵を物色し、先ず明智小五郎の事務所へ使つかいを出したが、明智氏はある重大犯罪事件の為ために、朝鮮ちょうせんに出張中で、急に帰らないという返事であった。そこで、今度は明智探偵と並び称せられる宗像博士に犯人捜査を依頼したところ、博士の助手の木島という若い探偵が訪ねて来て、一伍一什いちぶしじゅうを聞き取った上、捜査に着手したのであった。
それから十日余りの昨夜ゆうべ、川手氏は突然中村捜査係長の訪問を受け、宗像探偵事務所の木島助手変死の次第を聞かされ、今更いまさらのように震え上った。
そして、その夜は三名の私服刑事が、徹宵てっしょう邸の内外の見張りをしてくれることになったが、しかし、この警視庁の好意はもう手おくれであった。
夕刻から友達を訪問するといって出かけた次女の雪子ゆきこさんが、十時を過ぎ十一時を過ぎ、深夜となっても帰らなかった。友達の家は元より、心当りという心当りを電話や使いで探し廻まわったが、友達の家を辞去したのが八時頃と分ったばかりで、その後の消息は杳ようとして知れなかった。
不安の一夜が明けて翌朝、麻布区の高台にある川手邸は、急を聞いて馳はせつけた親戚知己ちきの人々で、広い邸内も一方ひとかたならぬ混雑を呈していたが、その中に、第一号応接室の洋間には、中村捜査係長と宗像博士と主人川手庄太郎氏の三人が、青ざめた顔を見合せて、善後の処置を協議していた。係長と博士とは、事件の報告を受けると、取るものも取りあえず、早朝から川手邸を訪問したのである。
川手氏は半白の頭髪を五分刈りにして、半白の口髭を貯え、濃い眉まゆ、大きな目、デップリと太った、如何にも重役型の紳士であったが、いつも艶々つやつやと赤らんでいる豊頬ほうきょうも、今日は色を失っているように見えた。
同氏は、一年程前夫人に先立たれたまま、後添のちぞいも娶めとらず、二人の娘と水入らずの家庭を楽しんでいたのだが、その愛嬢の一人が、何物とも知れぬ殺人鬼の手中に奪い去られたかと思うと、流石さすがの川手氏も狼狽ろうばいしないではいられなかった。
川手氏と宗像博士は初対面であった。川手氏は、木島助手の変死の悔くやみを述べ、遺族に対して出来るだけのことをしたいと申出もうしいで、博士の方では、この重大事件を、助手任せにして置いた手落ちを詫わびた。
「承うけたまわると、犯人は妙な三重の渦巻の指紋を持った奴だということですが……」
川手氏はそれを聞き知っていた。
「そうです。三つの渦巻が上に二つ、下に一つと三角型に重なっているのです。若しや、古いお知合いに、そんな指紋を持っている人物のお心当りはないでしょうか」
博士が訊ねると、川手氏は頭かぶりを振って、
「それが全く心当りがないのです。指紋などという奴は、いくら親しくつき合っていても、気のつかぬ場合が多いものですからね」
「しかし、これ程の復讐を企てているのですから、あなたに余程深い恨みを持っている奴に違いありません。そういう点で、何かお心当りがなければならないと思うのですが」
宗像博士は、やはり少し青ざめた顔をして、じっと川手氏を見た。そこから、この資産家の旧悪を探り出そうとでもするように、鋭い目で相手の表情を見つめた。
「イヤ、そりゃ、わたしを恨んでいる人間がないとは申しません。しかし、これ程の復讐を受ける覚えはないのです。そんな相手は全く心当りがないのです」
川手氏は、博士の疑い深い質問に、少し怒りをあらわして答えた。
「ですがね、恨みという奴は、恨まれる方では左程さほどに思わなくても、恨む側には何層倍も強く感じられる場合が、往々あるものですからね」
「なる程、そういうこともあるでしょうね。さすが御商売柄、犯罪者の気持はよく御承知でいらっしゃる。しかし、わたしには、どう考えて見ても、そんな心当りはありませんね」
川手氏は益々ますます不快らしく云い放った。
「あなたの方にお心当りがないとしますと、例の指紋が、今のところ、唯一の手掛りですね。実は昨夜のうちに、警視庁の指紋原紙を十分調べさせたのですが、十五年勤続の指紋主任も、三重の渦状紋なんて見たことも聞いたこともない。指紋原紙の内には、無論そんなものはないということでした」
「化け物だ」
宗像博士が、何か意味ありげに、低い声で呟いた。それを聞くと、川手氏は脅おびえたように、キョロキョロとあたりを見廻みまわした。さりげなく装っているけれど、心の底では、何者か思い当る人物があるらしく見える。
「中村さん、宗像さんも、何とかして娘を取戻して下さる訳には行かんでしょうか。費用はいくらかかっても、すっかりわたしが負担します。懸賞をつけてもよろしい。そうだ、犯人を発見し、娘を取返して下さった方には、五千円の賞金を懸けましょう。警察の方かたでも、民間の方でも構いません。娘を安全に取戻して下さればいいのです。わたしは一秒でも早く娘の無事な顔が見たいのです」
川手氏は感情の激しい性格と見えて、喋っているうちに段々興奮して、遂には半狂乱の体ていであった。
「なる程、懸賞とはよい思いつきですが、悪くすると手遅れかも知れませんね。……僕はさっきから、あの窓の下に落ちている封筒が気になって仕方がないのだが……」
宗像博士は一方の窓の下の床を、意味ありげに見つめながら、独言ひとりごとのように云った。
その声に、何かゾッとさせるような響ひびきがこもっていたので、あとの二人は驚いて、その方へ目をやった。如何にも一通の洋封筒が落ちている。
それを一目見ると、川手氏の顔色がサッと変った。
「オヤ、おかしいぞ。つい今いまし方がたまで、あんなものは落ちていなかったのですよ。それに、わたしの家には、あんな型の封筒はなかった筈はずだ」
云いながら、ツカツカと窓の側そばへ立って行って、その封筒を拾い上げ、気味悪そうに眺めていたが、いきなり呼鈴よびりんを押して女中を呼んだ。
「お前、今朝ここを掃除したんだね。この窓の下にこんなものが落ちてたんだが」
女中が顔を出すと、川手氏は叱りつけるように聞きただした。
「イイエ、アノ、わたくし、十分注意して掃除しましたけれど、何も落ちてなんかいませんでございました」
「確かかね」
「エエ、本当に何も……」
若い女中は、いかめしい二人の客の姿におびえて、頬を赤らめながら、しかし、キッパリと答えた。
「誰かが、窓の外から投げ込んで行ったのではありませんか」
中村警部が不安らしく瞬またたきしながら云った。
「イヤ、そんな筈はありません。ごらんの通りこちら側の窓は閉め切ってあります。封筒をさし入れるような隙間もありません。それに、この外は内庭ですから、家のものしか通ることは出来ないのです」
川手氏は魔術でも見たように、脅え切っていた。
「封筒がここへ入って来た経路は兎とも角かくとして、中を改めて見ようじゃありませんか」
宗像博士は一人冷静であった。
「お調べ下さい」
川手氏は、自みずから開封する勇気がなく、封筒を博士の方へさし出した。博士は受取って、注意深く封を開き、一枚の用紙を拡げた。
「オヤ、これは何の意味でしょう」
そこには、ただ五文字、
と記しるしてあるばかり、さすがの博士も、その意味を解かいし兼かねたように見えた。
「オオ、いつもの封筒です。いつもの用紙です。犯人からの通信に違いありません」
川手氏が、やっと気附いたように叫んだ。
「犯人の手紙ですって、それじゃこれは……」
「中村君、行って見よう。これからすぐ行って見よう」
博士は何を思ったのか、中村警部の腕を取らんばかりにして、惶あわただしく促すのだ。
「行くって、どこへです」
「極っているじゃないか。衛生展覧会へですよ」
「しかし、衛生展覧会なんて、どこに開かれているんです」
「U公園の科学陳列館さ。僕は、あすこの役員になっているので、それを知っているんだが、今衛生展覧会というのが開かれている筈なんです。サア、すぐに行って見ましょう」
中村係長にも、おぼろげに博士の考えが分って来た。この素人探偵は何という恐ろしいことを考えるのだろうと、殆ほとんどあっけに取られる程であったが、兎も角愚図愚図ぐずぐずしている場合でないと思ったので、博士と共に、門前に待たせてあった警視庁の自動車に乗り込んで、U公園の科学陳列館へ走らせた。
川手氏は両人の気違いめいた出発を、あっけにとられて眺めていたが、雪子の行方不明と衛生展覧会とを、どう考えても結びつけることが出来ず、しかし、分わからなければ分らないだけに、何ともえたいの知れぬ気味悪さが、黒雲のように心中に湧き起って来て、不安と焦慮しょうりょに、居ても立ってもいられぬ心持であった。
自動車が科学陳列館へ着くと、宗像博士と中村捜査係長とは、陳列館の主任に事情を話し、その案内で、三階全体を占める衛生展覧会場へ、惶あわただしく昇って行った。
早朝のこととて、広い場内には、観覧者の姿もなく、コンクリートの柱、磨き上げたリノリューム、そこに並べられた大小様々のガラス張りの陳列台が、まるで水の底に沈んでいるように、冷えびえと静まり返っていた。
場内の一半には医療器械、一半には奇怪な解剖模型や、義手義足や、疾病しっぺい模型の蝋ろう人形などが陳列してある。三人はそれらの陳列棚の間を、グルグルと急いそがしく歩き廻った。
毒々しく赤と青で塗られた、四斗樽しとだるほどもある心臓模型、太い血管で血走ったフットボールほどの眼球模型、無数の蚕かいこが這い廻っているような脳髄模型、等身大の蝋人形を韓竹割からたけわりにした内臓模型、長く見つめていると吐き気を催すような、それらのまがまがしい蝋細工の間を、三人は傍目わきめもふらず歩いて行く。目ざすところは、疾病模型の蝋人形なのだ。
何々ドラッグ商会の例の不気味な蝋人形は、もともと衛生展覧会などの蝋人形の効果から思いついたものであった。疾病の蝋人形というものには、それ程のスリルがあるのだ。恐ろしい病毒の吹出物、ニコチンやアルコールの中毒で、黄色くふくれ上った心臓の模型などは、健康者を忽ち病人にしてしまう程の、恐ろしい心理的効果を持っている。
それらの陳列棚の中に、一際ひときわ目立つ大きなガラス箱があった。上部と四方とを全面ガラス張りとした長方形の陳列台である。
宗像博士は、遠くからそのガラス箱を見つけると、真直まっすぐにその方へ近づいて行った。そして、三人はその寝棺ねがんのようなガラス箱の前に立った。
ガラス箱の中には、等身大の若い女が、腰部ようぶを白布に蔽おおわれて、全裸の姿を曝さらしていた。遠い窓からの薄暗い光線では、十分見分けられない程であるが、しかし、何となく生きているような蝋人形である。
「どうして、こんなものを陳列するのですか。別に病気の模型らしくもないじゃありませんか。美術展覧会の彫刻室へ持って行った方が、ふさわしい位だ」
博士が主任を顧かえりみて訊ねた。すると、主任は如何にも恐縮した体で、オズオズと、
「いつの展覧会にも、こういう完全な人形が一つ位まぎれ込むものです。模型師の道楽なんですね。この人形も今朝暗い内に運び込まれたばかりで、つい今いまし方がた蔽い布を取って見て驚いた位なんです。若もしなんでしたら、別の模型と置き換えることに致しますが」
と弁解しながら、中村警部をチロチロと横目で眺めた。
「イヤ、それにも及ばないだろうが、しかし、この人形は実によく出来ているね。それに非常な美人だ。この乳のふくらみなんか、職人の仕事とは思われぬ程ですね」
博士と中村警部とは、熱心にガラス箱の中を覗き込んでいたが、やがて、何を発見したのか、警部が頓狂な声を立てた。
「オヤッ、この人形には産毛うぶげが生えている。ホラ、顎あごのところをごらんなさい。腕にも、腿ももにも」
ようやく薄暗い光線に慣れた人々は、裸体人形の全身に、銀色に光る、目に見えない程の産毛を見分けることが出来た。
三人は余りの薄気味悪さに、黙りかえって顔を見交みかわすばかりであったが、宗像博士は、ふと何かに気づいたらしく、ポケットから拡大鏡を取出して、ガラス箱の表面の或ある一点を覗のぞき込んだ。
「中村君、一寸ちょっとここを覗のぞいてごらんなさい」
云われるままに、レンズを受け取って、ガラスの表面を覗いた係長は、覗くが否いなや、はじき返されたように、その側を離れて、嗄しゃがれた声で叫んだ。
「アア、三重渦状紋だ」
如何にも、そのガラスの表面には、昨夜ゆうべ幻燈で見たのとソックリのお化け指紋が、まざまざと現われていたのである。
「君、この蓋ふたを開けて下さい」
博士が呶鳴どなるまでもなく、主任もそれに気づいて、もう真青まっさおになりながら、ポケットの鍵かぎで、ガラス箱の蓋を開いた。
「人形の肌に触ってごらんなさい」
主任はオズオズと、人差指を人形に近づけ、その腹部に触って見た。触ったかと思うと、悲鳴のような叫び声を立てて、飛びのいた。
人形の肌は、まるで腐った果物のようにブヨブヨと柔かかったからである。そして氷のように冷たかったからである。
三人は暫くの間言葉もなく茫然ぼうぜんと顔見合せていた。死体をガラス箱に入れて、衆人の目に曝さらすという、余りにも奇怪な着想に、流石さすがの犯罪専門家達もあっけにとられてしまったのだ。
「ごらんなさい。この死体には全身に化粧が施してある。唇なんかも念入りにルージュが塗ってある。蝋人形らしくするのに、こんな手数をかけたのですね」
中村係長が感に堪えたように口を切った。
如何にもそれは死体とは考えられぬ程艶なまめかしい色艶いろつやであった。犯人は死体化粧によって、そこに一つの芸術品を創造したのだ。彼が人なき部屋、ほの暗き燈火の下で、死体とたった二人のさし向い、ギラギラと目を光らせ、唇をなめずりながら、絵筆を執って、悪魔の美術品製作に余念のない有様が、まざまざと瞼の裏に浮かんで来るように感じられた。
博士も警部も、川手雪子の顔を知らなかったけれど、種々の事情を考え合せて、この艶めかしい死体こそ、捜索中の雪子さんであることは明かであった。何よりの証拠は、ガラス箱の表面に残されていた悪魔の指紋である。あの怪物の顔のように見える三重渦状紋である。こんな気違いめいた怪指紋を持った奴が、外にある筈はないからだ。
「恐ろしい犯罪だ。僕は永年犯罪を手がけて来たけれど、こんなのは初めてですよ。気違い沙汰だ。この犯人は復讐にこり固まって、精神に異状を来たしているとしか考えられませんね」
中村警部が沈痛な面持で呟いた。
「イヤ、気違いというよりも寧むしろ天才です。邪悪の天才です。これほど効果的な復讐があるでしょうか。自分の娘が惨殺されたばかりか、その死体が、しかも裸体はだかの死体が、展覧会に陳列されているのを見る父親の心持はどんなでしょう。こんなずば抜けた復讐が、並々の犯罪者なんかに思いつけるものじゃありません」
宗像博士は、犯人を讃美するような口調でさえあった。博士は今、この稀代きだいの大悪人、絶好の敵手を見出して、武者震いを禁じ得ない体ていであった。鋭い両眼は、まだ見ぬ大敵への闘志に、爛々らんらんと輝き初はじめたかと見えた。
「ところで、この死体は雪子さんに違いないと思いますが、尚なお念のために川手氏にここへ来て貰もらってはどうでしょうか。僕が電話をかけましょう。それから、僕としては直様すぐさま検死の手続きをしなければなりません。それも一緒に電話をかけましょう」
中村警部はそう云って、係員に電話の所在を訊ねた。
「それと、もう一つ大切なことがあります。この死体を出品した人形製作者を取調べることです。事務所の帳簿を調べて、すぐそこへ人をやるのですね」
博士が注意すると、警部は肯うなずいて、
「如何にもそうでした。よろしい。電話の序ついでに刑事を呼んで、すぐ調査に着手させましょう」
と云い捨て、そそくさと階下の電話室へ降りて行った。
科学陳列館は、直ちに一般観衆の入場を禁止して、現場げんじょう保存に力つとめ、博士と捜査係長と数名の係員とが、ボソボソと小声に囁ささやき交しながら待つうちに、やがて、真青になった川手氏が自家用車を飛ばして駈けつけたのを先頭に、警視庁捜査課、鑑識課の人々、裁判所の一行、所轄警察署の人々と次々に来着し、それにつづいて、耳の早い新聞記者の一団が、陳列館の玄関に押しかけるという騒ぎとなった。
川手氏は、死体を一目見ると、目をしばたたきながら、雪子さんに相違ないことを証言した。それから警察医の検死、鑑識課員の指紋検出、訊問じんもんと、取調べは型通りに進んで行ったが、雪子さんの死因が毒殺らしいこと、死後八九時間しか経過していないことなどが推定された外は、別段の発見もなかった。例の怪指紋は宗像博士が発見したものの外には一つも検出されなかった。
その取調べの最中、現場に立合っていた宗像博士のところに、惶しく一枚の名刺がとりつがれた。博士はそれをチラッと見ると、すぐさま傍らにいた中村捜査係長に囁いた。
「助手の小池君がやって来たのですよ。例のカフェ・アトランチスの件で至急に会いたいというのです。態々わざわざこんなところまで追っかけてくる程だから、恐らく何か大きな手掛りを掴んだのでしょう。別室を借りて報告を聞こうと思いますが、あなたも来ませんか」
「アトランチスというと、木島君が手紙を書いたカフェですね」
「そうです。あの手紙を白紙とすり換えた奴が分ったかも知れません」
「それは耳よりだ。是非ぜひ僕も立合わせて下さい」
警部はそこにいた係員に耳打ちして、階下の応接室を借り受けることにし、小池助手をそこに通すように頼んだ。
二人が急いで応接室に入って行くと、背広姿の小池助手が、緊張に青ざめて待ちうけていた。
「先生、又大変なことが起ったらしいですね。……川手さんのお宅ではないかと思って、電話をかけますと、川手さんは先生に呼ばれてここへ来られたという返事でしょう。それで、先生のお出先がやっと分ったのです」
「ウン、突然ここへ来るようなことになったものだからね。事務所へ知らせて置く暇ひまがなくて……ところで、用件は?」
博士が訊ねると、小池はグッと声を落して、
「犯人の風体が分ったのです」
と、得意らしく囁いた。
「ホウ、それは早かったね。で、どんな奴だね」
「昨夜あれからアトランチスへ行ったところが、ひどく客が込んでいて、ゆっくり話も出来なかったものですから、今日もう一度出掛けて見たのです。女給達がやっと目を覚ましたばかりのところへ飛び込んで行ったのです。
すると、丁度木島君のお馴染なじみの女給が居合せて、昨日のことをよく覚えていてくれました。木島君は午後三時頃あのカフェへ行って、飲物も命じないで、用箋ようせんと封筒を借りて、しきりと何か書いていたそうです。それを書き終ると、ホッとしたように女給を呼んで、好きな洋酒を命じ、それから二十分ばかりいて、プイと出て行ってしまったというのです」
「それで、その時木島君の近くに、怪しい奴はいなかったのかね」
「いたのですよ。女給はよく覚えていて、その男の風采ふうさいを教えてくれましたが、何でも年は三十五六位、小柄な華奢きゃしゃな男で、青白い顔に大きな黒眼鏡をかけていたといいます。髭はなかったそうです。服装は、黒っぽい背広で、カフェにいる間、まぶかに冠った鳥打帽とりうちぼうを一度も脱がなかったといいます。
その男が、木島君が手紙を書き終った頃、隣の席へ移って来て、何だか慣れなれしく木島君に話しかけ、別にシェリー酒を命じて、木島君に勧めたりしていたそうです。恐らくそのシェリー酒の中へ毒薬を混ぜたのではないでしょうか」
「ウン、どうやらそいつが疑わしいね。しかし女給の漠然とした話だけでは、そのまま信じる訳にも行かぬが……」
「イヤ、女給の話だけじゃありません。僕は動かすことの出来ない証拠品を手に入れたのです」
「エッ、証拠品だって?」
博士も中村警部も、思わず膝を乗り出して、相手の顔を見つめた。
「そうです。ごらん下さい。このステッキです」
小池はそう云いながら、部屋の隅に立てかけてあった黒檀こくたんのステッキを持って来て、二人の前にさし出した。見れば、その握りの部分全体に、厚紙を丸くして被かぶせてある。
「指紋だね」
「そうです。消えないように、十分用心して来ました」
丸めた厚紙をとると、下から銀の握りが現われて来た。
「ここです。ここをごらん下さい」
小池は握りの内側を指さしながら、ポケットから拡大鏡を取出して博士に渡した。博士はそれを受取って、示された部分に当てて見る。警部が無言で横からそれを覗き込む。
「オオ、三重渦状紋だ!」
木島助手が持帰った靴箆に残っていたのと、寸分違たがわぬお化けの顔が笑っていた。
「このステッキは?」
「その黒眼鏡の男が忘れて行ったのです」
「そいつはアトランチスの定連じょうれんかね」
「イイエ、全く初めての客だったそうです。木島君が帰ると、間もなくそいつも店を出て行ったそうですが、今朝になっても、ステッキを取りに来ないということです。多分永久に取りに来ないかも知れません」
アア、小柄で華奢な黒眼鏡の男。そいつこそ稀代の復讐鬼なのだ。お化けのような三重渦巻の怪指紋を持った悪魔なのだ。
「とりあえず、それだけ御報告しようと思って。それから、このステッキを先生にお調べ願いたいと思いまして、急いでやって来たのです。もう風采が分ったからには、何としてでも、そいつの足取りを調べて見ます。そして、悪魔の巣窟そうくつを突きとめないで置くものですか。では、僕、これで失礼します」
「ウン、抜け目なくやってくれ給え」
博士に励まされて、若い小池助手はいそいそと陳列館を出て行った。
それから間もなく、死体陳列事件の取調べも終り、そこに集あつまっていた人々は、それぞれ引取ることになったが、宗像博士は中村係長の承諾を得て、黒檀のステッキを研究室に持帰り、拡大鏡によって綿密な検査をしたけれど、ごくありふれた安物のステッキで、製造所のマークもなく、例の怪指紋の外にはこれという手掛りも得られなかった。
雪子さんの死体は直ちに大学に運ばれ、翌日解剖に附されたが、その結果をここに記して置くと、彼女の死因は、やはり毒物の嚥下えんかによることが明かとなった。のみならず、丁度その前日、木島助手の死体も同じ場所で解剖されたのだが、その内臓から検出された毒物と、雪子さんのそれとが、全く同じ性質のものであったことも判明した。これによって、雪子さんと木島助手の殺害犯人が同一人であることは、一層明瞭になった訳である。
なお、雪子さんの死体を蝋人形として出品した人形工場については、中村係長自身その工場に出向いて、厳重に取り調べたところ、工場主は、そういう形のガラス箱はまったく覚えがない、恐らく何者かが工場の名を騙かたって納入したのであろうと主張した。そして、それには一々確かな拠より所どころがあったので、係長もたちまち疑念をはらし、犯人の用意周到さに驚くばかりであった。
死体入りのガラス箱を陳列館に運び入れた運送店が調べられたことは云うまでもない。しかし、それも何等得る所なくして終った。やはりある運送店の名が騙られていた。それを受取った陳列館員の記憶によると、人夫は都合三人で、似たような汚らしい男であったが、中でも親分らしい送状おくりじょうに判を取って行った人夫は、左の目が悪いらしく、四角く畳んだガーゼに紐をつけて、そこに当てていたということであった。手掛りといえば、それが唯一の手掛りであった。
最愛の雪子さんを失った川手氏の悲歎が、どれほど深いものであったかは、それから四日の後、雪子さんの葬儀の日に、あのよく肥ふとっていた人が、げっそりと痩やせて、半白の髪が、更に一層白さを増していたことによっても、十分察することが出来た。
盛んな通夜が二晩、今日は午前から邸内最後の読経どきょうと焼香が行われ、正午頃には雪子さんの骸むくろを納めた金ピカの葬儀車が、川手家の門内に火葬場への出発を待ち構えていた。玄関前の広場を、モーニングや羽織袴はおりはかまの人々が右往左往する中に、宗像博士と小池助手の姿が見えた。雪子さんの保護を依頼されながらこのような結果となったお詫わび心に、二人は親戚旧知に混って、火葬場まで見送りをするつもりなのだ。
小池助手はその後、例のアトランチスの奇怪な客の捜索をつづけていたが、今日までのところ、まだその行方ゆくえをつきとめることは出来ないのだ。
宗像博士は、集っている人々に知合いもなく、手持不沙汰ぶさたなままに、金ピカ葬儀車のすぐうしろに佇たたずんで、見るともなくその観音開きの扉を眺めていたが、やがて、何を見つけたのか、博士の顔が俄にわかに緊張の色をたたえ、葬儀車の扉に顔を着けんばかりに接近して、その黒塗りの表面を凝視し始めた。
「小池君、この漆うるしの表面にハッキリ一つの指紋が現われているんだよ。見たまえ、これだ。君はどう思うね」
博士が囁くと、小池助手は、指さされた箇所をまじまじと見ていたが、見る見るその顔色が変って行った。
「先生、なんだかあれらしいじゃありませんか。渦巻きが三つあるようですぜ」
「僕にもそう見えるんだ。一つ調べて見よう」
博士はモーニングの内ポケットから、常に身辺を離さぬ探偵七つ道具の革サックを取出し、その中の小型拡大鏡を開いて、扉の表面に当てた。
艶々つやつやとした黒漆の表面に薄白く淀よどんでいる指紋が五倍程に拡大されて、覗き込む二人の目の前に浮上った。
「やっぱりそうだ。靴箆のと全く同じです」
小池助手が思わず声高に呟いた。
アア、又してもあのえたいの知れぬお化けの顔が現われたのだ。復讐鬼の執念は、どこまでも離れようとはしないのだ。
「この会葬者の中に、あいつがまぎれ込んでいるんじゃないでしょうか。なんだか、すぐ身辺にあいつがいるような気がして仕方がありません」
小池助手はキョロキョロと、あたりの人群を見廻しながら、青ざめた顔で囁いた。
「そうかも知れない。だが、あいつがこの中に混っているとしても、僕等には迚とても見分けられやしないよ。まさかあの目印になる黒眼鏡なんかかけてはいないだろうからね。それに、この指紋は、車がここへ来るまでに着いたと考える方が自然だ。そうだとすると、迚も調べはつきやしないよ。街路で信号待ちの停車をしている間に、自転車乗りの小僧が、うしろから手を触れることだって、度々たびたびあるだろうし、誰にも見とがめられぬように、ここへ指紋をつけることなど、訳はないんだからね」
「そう云えばそうですね。しかし、あいつ何の為に、こんなところへ指紋をつけたんでしょう。まさかもう一度死体を盗み出そうというんじゃないでしょうね」
「そんなことが出来るもんか。僕達がこうして見張っているじゃないか。そうじゃないよ。犯人の目的は、ただ僕への挑戦さ。僕が葬儀車の扉に目をつけるだろうと察して、僕に見せつける為に、指紋を捺おして置いたのさ。なんて芝居気たっぷりな奴だろう」
宗像博士は事もなげに笑ったが、あとになって考えて見ると、犯人の真意は必ずしもそんな単純なものではなかった。この葬儀車の指紋は、同じ日の午後に起るべき、ある奇怪事の不気味な前兆を意味していたのであった。
それはさて置き、当日の葬儀は、極めて盛大に滞とどこおりなく行われて行った。葬儀車とそれに従う見送りの人々の十数台の自動車が、川手邸を出発したのが午後一時、電気炉でんきろによる火葬、骨上こつあげと順序よく運んで、午後三時には、雪子さんの御霊みたまは、もう告別式会場のA斎場に安置されていた。
事業界に名を知られた川手氏のこと故ゆえ、告別式参拝者の数も夥おびただしく、予定の一時間では礼拝らいはいしきれない程の混雑であったが、斎場の内陣に整列して、参拝者達に挨拶あいさつを返している家族や親戚旧知の人々の中に、一際ひときわ参拝者の注意を惹ひいたのは、最愛の妹に死別して涙も止めあえぬ川手妙子たえこさんの可憐な姿であった。
妙子さんは故人とは一つ違いのお姉さん、川手氏にとって、今ではたった一人の愛嬢である。顔立ちも雪子さんにそっくりの美人、帽子から、靴下から、何から何まで黒一色の洋装で、ハンカチを目に当てながら、今にもくずおれんばかりの姿は、参拝者達の涙をそそらないではおかなかった。
予定の四時を過ぎる三十分、やっと参拝者が途切れたので、愈々いよいよ引上げようと、人々がざわめき始めた頃、妙子さんも歩き出そうとして一歩前に進んだとき、悲しみに心も乱れていたためか、ヨロヨロとよろめいたかと思うと、バッタリそこへ倒れてしまった。
それを見ると、人々は彼女が脳貧血を起したものと思い込み、我先われさきに側へ駈け寄って、介抱かいほうしようとしたが、妙子さんは、傍らにいた親戚の婦人に抱き起され、そのまま自動車に連れ込まれて、別段の事もなく自宅に帰ることができた。
自宅に帰ると、彼女は何よりも独りきりになって、思う存分泣きたいと思ったので、挨拶もそこそこに、自分の部屋に駈け込んだが、そこに備えてある大きな化粧鏡の前を通りかかる時、ふと我が姿を見ると、右の頬に黒い煤すすのようなものが着いているのに気づいた。
「アラ、こんな顔で、あたし、あの多勢の方に御挨拶していたのかしら」
と思うと、俄かに恥かしく、そんな際ながら、つい鏡の前に腰かけて見ないではいられなかった。
鏡に顔を近寄せて、よく見ると、それはただの汚れではなくて、何か人の指の痕あとらしく、細かい指紋が、まるで黒いインキで印刷でもしたように、クッキリと浮き上っていた。
「マア、こんなにハッキリと指の痕がつくなんて、妙だわ」
と思いながら、つくづくその指紋を眺め入っている内に、妙子さんの顔は、見る見る青ざめて行った。唇からは全く血の気が失せ、二重瞼ふたえまぶたの両眼が、飛び出すのではないかと見開かれた。そして「アアア……」という、訳の分らぬ甲高かんだかい悲鳴を上げたかと思うと、彼女はそのまま、椅子からくずれ落ちて、絨毯じゅうたんの上に倒れ伏してしまった。
その指紋には、三つの渦がお化けのように笑っていたのである。復讐鬼の恐るべき三重渦状紋は、遂に人の顔にまで、そのいやらしい呪いの紋を現わしたのである。
妙子さんの部屋からの、ただならぬ叫び声に、人々が駈けつけて見ると、彼女は気を失って倒れていた。そして、その頬には、まだ拭われもせず、悪魔の紋章がまざまざと浮上っていたのである。
だが、騒ぎはそればかりではなかった。丁度その頃、父の川手氏は、まだ居残っている旧知の人達と、客間で話をしていたのだが、シガレット・ケースを出そうとして、モーニングの内ポケットに手を入れると、そこに全く記憶のない封筒が入っていた。
オヤッと思って、取出して見ると、どうやら見覚えのある安封筒、封はしてあるが、表には宛名も何もない。それを見たばかりで、もう川手氏の顔色は変っていた。しかし中には手紙が入っているらしい様子、恐ろしいからと云って、見ない訳には行かぬ。
思い切って封を開けば、案の定、いつもの用紙、態と下手に書いたらしい鉛筆の筆蹟。あいつだ。あいつがまだ執念深くつき纒まとっているのだ。文面には左さのような恐ろしい文句が認したためてあった。
川手君、どうだね。復讐者の腕前思い知ったかね。だが、本当の復讐はまだこれからだぜ。序幕が開あいたばかりさ。ところで二幕目だがね、それももう舞台監督の準備はすっかり整っている。さて、二幕目は姉娘の番だ。はっきり期日を通告して置こう。本月四日の夜だ。その夜、姉娘は妹娘と同じ目に遭あうのだ。今度の背景はすばらしいぜ。指折り数えて待っているがいい。
それが済むと三幕目だ。三幕目の主役を知っているかね。云うまでもない、君自身さ。真打しんうちの出番は最後に極きまっているじゃないか。
この二つの椿事ちんじが重なり合って、川手邸は葬儀の夕べとも思われぬ、一方ひとかたならぬ騒ぎとなった。
妙子さんは、人々の介抱によって、間もなく意識を取戻したけれど、感情の激動のために発熱して、医師を呼ばなければならなかったし、それに引続いて、葬儀から帰ったばかりの宗像博士が、川手氏の急報を受けて再び駈けつける、警視庁からは中村捜査係長がやって来る。それから川手氏と三人鼎座ていざして、善後策の密議に耽ふけるという騒ぎであった。
犯人は恐らくA斎場の式場にまぎれ込んでいたものに違いない。そして、一方では妙子さんの頬に怪指紋の烙印らくいんを捺し、一方では川手氏に接近して、その内ポケットに、掏摸すりのような手早さで、あの封筒を辷すべり込ませたものに違いない。
しかし、妙子さんの頬に指型を押しつけるなんて、いくら何でも普通の場合にできる業わざではない。これはきっと、告別式が終って、妙子さんが倒れた時のどさくさまぎれに、素早く行われたものであろう。すると、その時、場内に居合せたものは、川手氏の親戚旧知の限られた人々のみではなかったか。
中村警部はそこへ気がつくと、川手氏の記憶や名簿をたよりに、忽ち四十何人の人名表を作り上げ、部下に命じて、その一人一人を訪問し、指紋を取らせることに成功した。それには主人の川手氏は勿論もちろん、同家の召使達は漏れなく入っていたし、宗像博士や小池助手の指紋まで集めたのであったが、その中には、三重渦状紋など一つもないことが確められた。
一方カフェ・アトランチスに現われた怪人物については、引きつづき宗像研究室の手で捜査が行われていたが、最初小池助手が探り出した事実の外には、何の手掛りも発見されぬままに、一日一日と日がたって行った。
そして、間もなく、復讐鬼のいわゆる第二幕目の幕開きの日がやって来た。四日の夜がすぐ目の前に近づいて来た。
川手氏の邸宅は、妖雲に包まれたように、不気味な静寂に閉されていた。妙子さんはあれ以来ベッドについたきりで、日夜底知れぬ恐怖に打震えていたし、川手氏も一切の交際を絶って、妙子さんを慰めることと、仏間にこもって、なき雪子さんの冥福めいふくを祈ることにかかり果てていた。
さて、当日の四日には、予め川手氏の依頼もあって、同邸の内外には、十二分の警戒陣が敷かれた。
先ず警視庁からは六名の私服刑事が派遣され、川手邸の表門と裏門と塀外へいそととを固めることになったし、邸内妙子さんの部屋の外そとには、宗像博士自ら、小池助手を引きつれて、徹宵見張りを続けることにした。
妙子さんの部屋は、屋敷の奥まった箇所にあり、二つの窓が庭に面して開いている外ほかには、たった一つの出入口しかなかった。博士はそのドアの外の廊下に安楽椅子を据えて夜を明かし、小池助手は二つの窓の外の庭に椅子を置いて、この方面からの侵入者を防ぐという手筈であった。
早い夕食を済ませて、一同部署についたが、川手氏はそれでもまだ安心しきれぬ体ていで、妙子さんの部屋に入ったり出たりしながら、廊下の宗像博士の前を通りかかる度に、何かと不安らしく話しかけた。
博士は笑いながら、妙子さんの安全を保証するのであった。
「御主人、決して御心配には及びませんよ。お嬢さんは、謂いわば二重の鉄の箱に包まれているのも同然ですからね。お邸のまわりには事に慣れた六人の刑事が見張っています。その目をごまかして、ここまで入って来るなんて殆んど不可能なことですよ。若もし仮りにあいつが邸内に入り得たとしてもですね、ここに第二の関門があります。たった一つのドアの外そとには、こうして僕が頑張っていますし、窓の外には、小池君が見張りをしている。しかも窓は全部内側から掛金がかけてあるのです。このドアもそのうち僕が鍵かぎをかけてしまう積りですよ」
「併しかし、若し隠れた通路があるとすれば……」
川手氏の猜疑さいぎは果てしがないのである。
「イヤ、そんなものはありやしません。さい前ぜん僕と小池君とで、お嬢さんの部屋を隅から隅まで調べましたが、壁にも天井にも床板にも、少しの異状もなかったのです。ここはあなたのお建てになった家じゃありませんか。抜穴ぬけあななんかあってたまるものですか」
「アア、それも調べて下すったのですか。流石さすがに抜目がありませんね。イヤ、あなたのお話を聞いて、いくらか気分が落ちつきましたよ。しかし、わたしは、今夜だけはどうしても娘の傍そばを離れる気になれません。この部屋の長椅子で夜を明かす積つもりです」
「それはいいお考えです。そうなされば、お嬢さんには三重の守りがつく訳ですからね。あなたがこの部屋の中にいて下されば、僕達も一層心丈夫ですよ」
そこで川手氏は、そのまま妙子さんの部屋に入って、寝室につづく控ひかえの間まの長椅子に腰をおろし、暫くの間は、ドアを開いたままにして博士と話し合っていたが、この際会話のはずむ筈もなく、やがて、川手氏は長椅子の上に横になったまま黙りこんでしまったので、博士は預って置いた鍵を取出して、ドアに締しまりをした。
夜が更ふけるに従って、邸内は墓場のように静まり返って行った。町の騒音ももう聞えては来なかった。女中達も寝静まった様子である。
宗像博士は、強い葉巻煙草たばこをふかしながら、安楽椅子に沈み込んで、ギロギロと、鋭い目を光らしていた。庭では小池助手が、これも煙草を吸いつつ、椅子にかけたり、椅子の前を歩哨ほしょうのように行きつ戻りつしたり、睡気ねむけを追っぱらうのに一生懸命であった。
十二時、一時、二時、三時、長い長い夜が更けて、そして、夜が明けて行った。
午前五時、廊下の窓に清々すがすがしい朝の光がさしはじめると、宗像博士は安楽椅子からヌッと立上って、大きな伸びをした。とうとう何事もなかったらしい。流石の復讐鬼も、二重三重の警戒陣に辟易へきえきして、第二幕目の開幕を延期したものらしい。
博士はドアに近づくと、軽くノックしながら川手氏に声をかけた。
「もう夜が明けましたよ。とうとう奴は来なかったじゃありませんか」
返事がないので、今度は少し強くノックして、川手氏を呼んだ。それでも返事がない。
「おかしいぞ」
博士は冗談のように呟きながら、手早く鍵を取出し、それでドアを開けて、室内に入って行った。
すると、アアこれはどうしたというのだ。川手氏は長椅子に横たわったまま、身体中をグルグル巻きにされて、固く長椅子に縛しばりつけられていた。その上、口には厳重な猿轡さるぐつわだ。
博士はいきなり飛びついて行って、先ず猿轡をはずし、川手氏の身体をゆすぶりながら叫んだ。
「ど、どうしたんです。いつの間に、誰が、こんな目に合せたのです。そして、お嬢さんは?」
川手氏は絶望の余り、物を云う力もなかった。ただ目で次つぎの間まをさし示すばかりだ。
博士はその方を振り返った。間のドアが開いたままになっているので、妙子さんのベッドがよく見える。だが、そのベッドの上には、誰も寝てはいないのだ。
博士は寝室へ駈け込んで行った。余程慌てていたと見え、大きな音を立てて椅子の倒れるのが聞えた。
「お嬢さん、お嬢さん…………」
だが、いない人が答える筈はない。寝室は全くの空っぽだったのである。
博士は青ざめた顔で再び控えの間に戻って来た。そして手早く川手氏の縛いましめを解くと、
「一体これはどうしたというのです」
と叱責しっせきするように訊ねた。
「何が何だか少しも分りません。ウトウトと眠ったかとおもうと、突然息苦しくなったのです。あれが麻酔剤だったのでしょう。口と鼻の上を何かで圧おさえつけられているなと思ううちに、気が遠くなってしまいました。それからあとは何も知りません。妙子は? 妙子は攫さらわれてしまったのですか」
川手氏は無論それを知っていた。だが、聞かずにはいられないのだ。
「申訳ありません。しかし、僕の持場には少しも異状はなかったのです。あいつは窓から入ったのかも知れません」
博士は云い捨てて、窓のところへ飛んで行くと、サッとカーテンを開き、掛金をはずして、すりガラスの戸を上に押し上げ、庭を覗いた。
「小池君、小池君」
「ハア、お早うございます」
何としたことだ。小池助手は別状もなく、そこにいたのである。そして何も知らぬらしく、間の抜けた挨拶をしたのである。
「君は眠りやしなかったか」
「イイエ、一睡も」
「それで、何も見なかったのか」
「何もって、何をですか」
「馬鹿ッ、妙子さんが攫われてしまったんだ」
博士はとうとう癇癪玉かんしゃくだまを破裂させた。
だが、よく考えて見ると、小池助手に落度のある筈はなかった。彼が犯人を見逃したのではない証拠には、窓は二つとも、ちゃんと内側から掛金がかけられ、少しの異状もなかったからである。
とすると、あいつは一体全体、どこから入って、どこから出て行ったのであろう。室内に抜け穴なんかないことは十分調べて確めてある。ドアには外から鍵がかかっていた。窓の締りにも別条はない。アア、愈々お化けだ。お化けか幽霊ででもない限り、密閉された部屋に忍び込んだり、抜け出したり出来る筈がないではないか。
しかし、幽霊が麻酔薬を嗅かがしたり、人を縛ったりするものであろうか。イヤ、それよりも、曲者くせもの自身は幽霊のように一分いちぶか二分の隙間から抜け出たとしても、妙子さんをどうして運び出すことが出来たのだ。妙子さんは血の通った人間だ、隙間などから抜け出せるものではない。
流石の名探偵宗像博士も、これには全く途方に暮れてしまった様子であった。だが、徒いたずらに途方に暮れている場合ではない。あらん限りの智恵を絞って、このお化じみた謎を解かなければならぬ。
博士はふと思いついたように、慌しく女中を呼んで、玄関と門とを開かせると、気違いのように門の外へ飛び出して行った。云うまでもなく、外部を固めている六人の刑事に、昨夜の様子を訊ねるためだ。
だが、その結果判明したのは、表門にも裏門にも、その外ほか邸を取りまく高塀のどの部分にも、全く何の異状もなかったということである。彼等は異口同音に、外からも内からも、門や塀を越えたものは決してなかったと確信に満ちて答えたのであった。
「おかしい。どうもおかしい。僕は何か忘れているんだ。脳髄の盲点という奴かも知れない。物理上の不可能はあくまで不可能だ」
博士は拳骨で、自分の頭をコツコツ殴なぐりつけながら、川手邸の門を入ったり出たり、そうかと思うと、モーニングの裾すそをひるがえして、コンクリート塀のまわりを、グルグル歩き廻ったりした。
明るくなるのを待って、再び屋内屋外の捜査が繰返された。博士と助手と六人の刑事とが、夫々それぞれ手分けをして、たっぷり二時間程、まるで煤掃すすはきのように、真黒になって天井裏や縁の下、庭園の隅々までも這い廻った。しかし、足跡一つ、指紋一つ発見することが出来なかった。
この事が警視庁に急報されたのは云うまでもない。忽ち全市に非常線が張られたのだが、狭い邸内でさえ、煙のように人目をくらました賊のことだ。恐らくその手配も徒労に終ることであろう。
敗軍の将宗像博士は、非常な不機嫌で、一応事務所に引上げることになった。主人の川手氏は、博士の失敗を責める力もなく、絶望と悲歎のために半病人の体ていであったし、博士は博士で、殊更ことさら詫びごとをいうでもなく、苦虫をかみつぶしたような顔で、簡単な挨拶をすると、小池助手を引きつれて、サッサと玄関を出てしまった。
自動車を拾うと、博士はクッションに凭もたれたまま、じっと目を閉じて、一言も口を利かない。まるで木彫きぼりの像のように、呼吸さえしていないかと疑われるばかりだ。小池助手は、この不機嫌な先生を、どう扱っていいのか見当もつかなかった。ただ、気拙きまずそうに、博士の横顔をチロチロと盗み見ながら、モジモジするばかりである。
ところが、自動車が事務所への道を半なかば程も来た時である。博士は突然カッと目を見開き、
「オオ、そうかも知れない」
と独言をいったかと思うと、今まで青ざめていた顔に、サッと血の気がのぼって、目の色も俄かに生々と輝いて来た。
「オイ、運転手、元の場所へ引返すんだ。大急ぎだぞ」
博士はびっくりするような声で呶鳴った。
「何かお忘れものでも……」
小池助手がドギマギして訊ねる。
「ウン、忘れものだ。僕はたった一つ探し忘れた場所があったことに、今やっと気附いたんだ」
名探偵は、そういう間ももどかしげに、再び運転手を呶鳴りつけて、車の方向を変えさせた。
「それじゃ、あの賊の秘密の出入口がおわかりになったのですか」
「イヤ、賊は出もしなければ、入りもしなかったということを気附いたのさ。あいつは、妙子さんと一緒にちゃんと僕達の目の前にいたんだ。アア、俺おれは、今までそこに気がつかないなんて、実にひどい盲点に引っかかったもんだ」
小池助手は目をパチパチとしばたたいた。博士の言葉の意味が、少しも分らなかったからである。
「目の前にいたといいますと?」
「今に分る。ひょっとしたら僕の思い違いかも知れない。しかし、どう考えてもその外に手品の種はないのだ。小池君、世の中には、すぐ目の前に在ありながら、どうしても気の附かないような場所があるものだよ。習慣の力だ。一つの道具が全く別の用途に使われると、我々は忽ち盲目になってしまうのだ」
小池助手は益々面喰めんくらった。聞けば聞く程訳が分らなくなるばかりである。しかし、彼はこれ以上訊ねても無駄なことをよく知っていた。宗像博士は、その推理が確実に確かめられるまでは、具体的な表現をしない人であった。
やがて、車が規定以上の速力で、川手邸の門前に着くや否や、博士は自らドアを開いて自動車を飛び出し、風のように玄関へ駈け込んで行った。
客間に入って見ると、川手氏は、そこの長椅子にグッタリと凭れたまま、ものを考える力もなくなったように、茫然としていた。
「御主人、ちょっと、もう一度あの部屋を見せて下さい。たった一つ見落していたものがあるんです」
博士は川手氏の手を引っぱらんばかりにして、せき立てた。
川手氏は、異議も唱えなかった代り、さして熱意も示さず、気抜けしたように立上って、博士と小池助手の後につづいた。
妙子さんの部屋の前まで来ると、博士はドアの把手ノッブを廻して見て、
「アア、やっぱりそうだったか。ここへ鍵をかけてさえ置いたらなあ」
と、落胆の溜息をついた。既に妙子さんが誘拐されてしまったあとの部屋へ、誰が鍵なぞかけるものか。博士は一体何を云っているのであろう。
部屋に入ると、博士は次の間を通り越して、寝室に飛び込み、昨夜まで妙子さんの寝ていた大きな寝台の上に、いきなりゴロリと横になった。そして、不作法にも、モーニングのまま、その上に腹這はらんばいになって、川手氏に話しかけたのである。
「御主人、このベッドはまだ新しいようですね。いつお買いになりました」
余りにも意外な博士の態度や言葉に、川手氏はますますあっけにとられて、急には答えることも出来なかった。一体この男はどうしたのだ、気でも違ったのではないかと、怪しみさえした。
「エ、いつお買入れでした」
博士は駄だ々だッ子のように繰返す。
「つい最近ですよ。以前に使っていたのが、急にいたんだものですから、四日程前に、家具屋にあり合せのものを据えつけさせたのです」
「ウン、そうでしょう。で、それを持込んで来た人夫をごらんでしたかね。たしかにその家具屋の店のものでしたか」
「サア、そいつは……。わしは丁度居合せて、据えつける場所を指図したのですが、何でも左の目にガーゼの眼帯を当てた髭面の男が、しきりと何か云っていたようです。無論見知らぬ男ですよ」
アア、左の目にガーゼを当てた男。読者は何か思い当る所がないだろうか。我々はどこかで、同じような人物に出会ったことがあるのだ。嘗かつて雪子さんの死体を入れた陳列箱を、衛生展覧会へ持込んだ人夫の頭かしらが、丁度それと同じ風体の男ではなかったか。
「オオ、やっぱりそうだったか」
博士は唸うなるように云うと、ベッドから降りて、今度はその下の僅わずかの隙間に這い込むと、自動車の修繕でもするように、仰向あおむきになって、ベッドの裏側を調べていたが、突然、恐ろしい声で呶鳴り出した。
「御主人、僕の想像した通りです。ごらんなさい。ここをごらんなさい。彼奴きゃつの手品の種が分りましたよ。アア、なんということだ。今頃になって、やっとそこへ気が附くなんて……」
川手氏と小池助手は、急いでベッドの向側に廻って見た。
「どこですか」
「ここだ、ここだ。ベッドをもっと壁から離してくれ給え。ここに仕掛けがあるんだ」
二人はいわれるままに、ベッドを押して、壁際から離したが、すると、その下から仰向きに横たわっている博士の上半身が現われ、博士はそのまま起き上って、今まで壁に接していたベッドの側面を指し示した。
「ここに隠し蓋があるんです。ホラネ、これを開けば中は広い箱のようになっています」
シーツをめくり上げて、ベッドの側面を強く圧おすと、それは巧妙な隠し戸になって、幅一尺、長さ一間程の、細長い口が開いた。つまり、ベッドのクッションの部分を、上部の三分の一程の、薄い部分にとどめて、その下部は全体が一つの頑丈な箱のように作られているのだ。無論人間が潜んでいるためだ。その広さは二人の人間を隠すに十分である。
「巧く造りやがったな。外から見たんでは、普通のベッドとちっとも違やしない」
小池助手が感心したように叫んだ。
よく見れば、普通のベッドよりは、いくらか厚味があるようであったが、しかし、その側面には複雑な襞ひだのある毛織物で、巧みに錯覚を起させるようなカムフラージュが施され、一寸ちょと見たのでは少しも分らないように出来ていた。
恐らく、復讐鬼は、家具屋から運ばれる途中で、ベッドを横取りして、予あらかじめ造らせて置いたこの偽物を持ち込んだのに違いない。
「すると、これが運び込まれた時から、あいつは、ちゃんとこの中に隠れていたのでしょうか」
川手氏が、もう驚く力も尽き果てたように、投げやりな調子で訊ねる。
「そうかも知れません。或あるいはあとから忍び込んだのかも知れません。いずれにせよ、昨夜は、早くからこの中に身を潜めていたに違いありません。お嬢さんは、それとも知らず、悪魔と板一枚を隔てて、ここへお寝やすみになったのです」
博士は無慈悲な云い方をした。
「そして、あいつは真夜中に、そこから忍び出し、あなたをあんな目にあわせた上、お嬢さんをこの箱の中へ押し込み、自分もここへ入って、逃げ出す時刻の来るのを、我慢強く待っていたのです」
「では、今朝になってから……」
「そうです。僕達は非常な失策をしました。まさか賊とお嬢さんとが、この部屋の中に隠れているとは思わないものですから、ここは開けっ放しにして、庭の捜索などやっていたのです。賊はその間に、廊下や玄関に誰もいない折を見すまして、お嬢さんを抱いて、ここから逃げ出したのに違いありません」
「しかし、逃げ出すと云って、どこへですか。一歩この邸を出れば、人通りがあります。まさか明るい町を、女を抱いて走ることは出来ますまい。それに、刑事さん達も、まだ門の外に見張りをつづけていたんだし──」
川手氏が腑に落ちぬ体で反問した。
「そうです。僕もそれを考えて安心していたのですが、賊の方では、この二重の包囲を脱出する、何か思いもよらぬ計略があったのかも知れません。イヤ、ひょっとすると、あいつは、まだ邸内のどこかに潜伏しているんじゃないか。夜を待つ為ためにですね。しかし……」
博士も確信はないらしく見えた。
「だが、妙子はどうして救いを求めなかったのだ」
川手氏はハッとそこへ気づいたらしく、真青になって、脅え切った目で宗像博士を見つめた。
「妙子はわしと同じように猿轡をはめられていたのでしょうか。それとも……」
「何とも申せません。しかし、少くとも無残な兇行が演じられなかったことは確かですよ。どこにも、血痕などは見当らないのですから。しかし、お嬢さんの生死は保証出来ません。ただ御無事を祈るばかりです」
博士は正直に云った。
川手氏の物狂わしい脳裏を、妙子さんが賊の為めに絞殺されている光景や、毒薬の注射をされている有様などが、浮かんでは消えて行った。
「若し邸の中に隠れているとすれば、もう一度捜索して下さる訳には……」
「僕もそれを考えているのです。しかし、念の為めに、門前に見張りをしている刑事に、よく訊ねて見ましょう。まだ二人だけ私服が居残っている筈です」
そういうと、博士はもう部屋の外へ走り出していた。小池助手と川手氏とが、慌しくそのあとにつづく。
門前に出て見ると、背広に鳥打帽の目の鋭い男が、煙草をふかしながら、ジロジロと町の人通りを眺めていた。
「君、その後、不審な人物は出入りしなかったでしょうね。何か大きな荷物を持った奴が、ここから出たという様なことはなかったですか」
博士がいきなり訊ねると、刑事は不意を打たれて、目をパチパチさせた。
この刑事は、早朝邸内の大捜索が終ったあと、万一犯人が邸内に潜んでいて、逃げ出すようなことがあってはと、念の為めに見張りを命ぜられていたのだから、若し不審の人物が出入りすれば、見逃す筈はなかった。
「イイエ、誰も通りませんでした。あなた方の外には誰も」
刑事は、宗像博士が彼等の上役中村捜査係長の友人であることを、よく知っていた。
「間違いないでしょうね。本当に誰も通らなかったのですか」
博士は妙に疑い深く聞き返す。
「決して間違いありません。僕はその為めに見張りをしていたのです」
刑事は少し怒気を含んで答えた。
「例えば新聞配達とか、郵便配達とかいうようなものは?」
「エ、何ですって? そういう連中まで疑わなければならないのですか。それは、郵便配達も、新聞配達も通りました。しかし、犯人がそういうものに変装して逃げ出すことは出来ませんよ。彼等は皆外から入って来て、用事をすませると、すぐ出て行ったのですからね」
「しかし、念の為めに思い出して下さい。その他に外から入ったものはなかったですか」
刑事は、何というつまらない事を訊ねるのだと云わぬばかりに、ジロジロと博士を見上げ見下していたが、やがて何事か思い出したらしく、いきなり笑い出しながら、
「オオ、そういえば、まだありましたよ。ハハハハハハハ、掃除人夫です。塵芥ごみ車を引っぱって、塵芥箱の掃除に来ましたよ。ハハハハハハハ、掃除人夫のことまで申上げなければならないのですか」
「イヤ、大変参考になります」
博士は刑事の揶揄やゆを気にもとめず、生真面目な表情で答えた。
「で、その塵芥箱というのは、ここから見えるところにあるのですか」
「イヤ、ここからは見えません。掃除人夫は門を入って右の方へ曲って行きましたから、多分勝手元の近くに置いてあるのでしょう」
「それじゃ、君は、そこで掃除人夫が何をしていたか、少しも知らない訳ですね」
「エエ、知りません。僕は掃除人夫の監督は命じられていませんからね」
刑事はひどく不機嫌であった。何をつまらないことを、クドクドと訊ねているのだと云わぬばかりである。昨夜の徹夜で、神経がいらだっているのだ。
「で、その人夫は、ここから又出て行ったのでしょうね」
博士は我慢強く、掃除人夫のことにこだわっている。一体塵芥車と昨夜の犯罪とに、どんな関係があるというのだろう。
「無論出て行きました。塵芥を運び出すのが仕事ですからね」
「その塵芥車には蓋がしてあったのですか」
「サア、どうですかね。多分蓋がしてあったと思います」
「人夫は一人でしたか」
「二人でした」
「どんな男でしたか。何か特徴はなかったですか」
そこまで問答が進むと、仏頂面ぶっちょうづらで答えていた刑事の顔に、ただならぬ不安の色が現われた。博士がなぜこんなことを、根掘り葉掘り訊ねるのか、その意味がおぼろげに分って来たのだ。彼は暫らく小首をかしげて考えていたが、やがてそれを思い出したらしく、今度は真剣な調子で答えた。
「一人は非常に小柄な、子供みたいな奴で、黒眼鏡をかけていました。もう一人は、アア、そうだ、どっちかの目に四角なガーゼの眼帯を当てた四十ぐらいの大男でした。二人とも鳥打帽を冠って、薄汚れたシャツに、カーキ色のズボンをはいていたと思います」
それを聞くと、小池助手はハッと顔色を変えて、今にも掴みかからんばかりの様子で、刑事を睨みつけたが、宗像博士は別に騒ぐ色もなく、
「君は犯人の特徴を、中村君から聞いていなかったのですか」
と穏かに訊ねた。すると、刑事の方が真青になって、俄かに慌て出した。
「そ、それは聞いていました。アトランチス・カフェへ現われた奴は、黒眼鏡をかけた小柄な男だったということは、聞いていました。しかし……」
「それから、衛生展覧会へ蝋人形を持込んだ男の風体は?」
「そ、それも、今、思い出しました。左の目に眼帯を当てた奴です」
「すると、二人の掃除人夫は、犯人と犯人の相棒とにソックリじゃありませんか」
「しかし、しかし、まさか掃除人夫が犯人だなんて、……それに、あいつらは外から入って来たのです。僕は中から逃げ出す奴ばかり見張っていたものですから。……偶然の一致じゃないでしょうか」
刑事は、ひたすら自分の落度にならないことを願うのであった。
「偶然の一致かも知れない。そうでないかも知れない。我々は急いでそれを確かめて見なければならないのです。犯人は妙子さんの自由を奪って、どこかへ隠して置いて、独りでここを逃げ出し、改めて妙子さんを運び出す為に戻って来た、と考えられないこともない。今朝あなた方が邸内を捜索している間に、犯人がひとりで逃げ出すような隙は、いくらもあったのですからね」
「隠して置いたといって、お嬢さんを塵芥箱の中へですか」
「突飛とっぴな想像です。しかし、あいつはいつも、思い切って突飛なことを考える奴です。それに、我々は今朝の捜索の時、塵芥箱の塵芥の中までは探さなかったのですからね。サア、一緒に行って、調べて見ましょう」
人々は博士のあとに従って、門内に入り、勝手口の方へ急いだ。博士と刑事のあとから、青ざめた川手氏と小池助手とがつづく。
問題の塵芥箱は、炊事場の外の、コンクリート塀の下に置いてある。黒く塗った木製の大きな箱だ。これなれば、人間一人十分隠れることが出来る。
博士はツカツカとその塵芥箱の側に近づいて、蓋を開いた。
「すっかり綺麗きれいになっている。だが、あれはなんだろう、小池君、一寸見てごらん」
云われて、小池助手も箱の中を覗き込んだが、ジメジメしたその底に、少しばかり残った塵芥に混って、四角な白いものが落ちている。
「封筒のようですね」
彼はそういいながら、手を入れて、拾い上げた。どこやら見覚えのある廉やす封筒だ。宛名も差出人もないけれど、中には手紙が入っているらしい。
「中を見てごらん」
博士の指図に従って、小池助手は封筒を開き用箋を取出した。
「オヤ、ここにインキで指紋が捺してあります」
簡単な文章の終りに、署名のかわりのように、ハッキリと一つの指紋が現われているのだ。
博士は急がしく例の拡大鏡を取り出して、その上に当てた。
「やっぱりそうだ。川手さん、僕の想像した通りでした。お嬢さんはここに隠してあったのです」
そこには、あのお化けのような三重渦状紋が、用箋の隅からニヤニヤと笑いかけていたのである。
小池助手が、気を利かして文面を読み上げた。
「川手君、俺の字引に不可能という文字はないのだ。ずいぶん厳重な警戒だったね。しかし、君のほうで二重の警戒をすれば、俺も二重の妙案をひねり出すばかりさ。
宗像大先生によろしく伝えてくれ給え。あれほど捜索をしながら、ベッドと塵芥箱に気附かなかったとは、名探偵の名折なおれですぜと伝えてくれ給え。尤もっとも俺は誰しも見逃しそうな盲点と云う奴を利用したんだがね。
君はとうとう一人ぼっちになってしまったねえ。だが、妙子にはいつか逢あえるよ。一つ探して見たまえ。そして、ある恐ろしい場所で、君が娘の無残なむくろと対面した時、どんな顔をするか。それを思うと、俺は心の底からおかしさがこみ上げて来る。川手君、これが真の復讐というものだぜ。今こそ思い知るがよい」
小池助手は途中で、幾度も朗読をやめようかと思ったが、川手氏の目が、先を先をと促うながすものだから、やっとのことで読み終った。
「川手さん、何と云ってお詫びしていいか分りません。僕は完全に敗北しました。だが、何という恐ろしい奴だ。あいつは心理学者ですよ。あいつのいう通り、僕達は盲点に引っかかったのです。それをちゃんと予知して、少しも騒がず、悠々と逃げ去った腕前は、ゾッと怖くなる程です。
しかし、僕はこの恥辱を雪すすがねばなりません。お嬢さんは恐らく、もう生きてはいらっしゃらないかも知れませんが、いずれにせよきっとその隠し場所を発見してお目にかけます。そして、僕はあいつを捉える迄は、この戦いをやめません。命をかけても、必ずあいつをやッつけます。やッつけないでおくものですか」
宗像博士は、満面に朱しゅを注そそいで、川手氏にというよりは、寧ろ我れと我が心に誓うもののように、烈しい決意を示すのであった。
宗像博士が、塵芥車のトリックを発見したのが八時三十分頃、警視庁の中村捜査係長が、おくればせに駈けつけたのが、それから又十分ほども後であった。
中村警部は、宗像博士から委細を聞き取ると、捜査手配のために、すぐさま警視庁に引返したが、あらためて全市の警察署、派出署、交番などに、犯人逮捕の指令が飛んだことは云うまでもない。
今度は犯人と共犯者の風体もよく分っているのだし、その上、塵芥車という大きなお荷物があるのだから、発見は容易である。だが、彼等が逃出してから既に一時間、何しろ魔術師のような素早い奴のことだから、まさか今頃まで、元の掃除人夫の姿で塵芥車を引っぱって、ノロノロ町を歩いている筈はない。恐らくは、邪魔な塵芥車はどこかへ捨てて、風体を変え、妙子さんを攫って、姿をくらましてしまったに違いない。とすると、折角の非常指令もあとの祭である。空っぽの塵芥車でも発見するのが関の山であろう。
案の定、それから三十分程もすると、主人を慰める為に川手邸に居残っていた宗像博士のところへ、警視庁の中村係長から電話があって、塵芥車が発見されたという知らせである。
場所は、川手邸から三町とは離れていない、神社の森のなかだという。アア、何ということだ。賊は川手邸を出たかと思うと、もう車を捨ててしまったのだ。では、妙子さんは? まさか森の中へ捨てた訳ではあるまい。一体どうして、どこへ運び去ったというのであろう。
博士と小池助手とは、兎とも角かく現場へ行って見ることにした。
車を呼ぶまでもなく、教えられた道を、走るようにして二つ三つ曲ると、もうそこが神社の森であった。その辺は、麻布区内でも、市中とも思われぬ場末めいた感じで、附近には広い空地などもあり、子供達の遊び場所になっている。
神社の森の中へ入って見ると、塵芥車はもう警察署へ運び去られたということで、そのあとに目印の小さな杭が立てられ、側に制服の若い警官が立っていた。
博士は名刺を出して、警官に話しかけた。
「警視庁の中村警部から聞いてやって来たのです。中村君もじきあとから、ここへ来ると云っていました」
「ア、そうですか。お名前はよく承知して居ります。今度の事件には御関係になっているんだそうですね」
若い警官は、有名な民間探偵の顔を、まぶしそうに見て、丁寧な口を利いた。
「で、塵芥車の外ほかに何か発見はありませんでしたか」
「さい前から、一通りこの森の中を捜索したのですが、全く何の手掛りもありません。ごらんの通りの石ころ道で、足跡は分りませんし、被害者をどこかへ隠したのではないかということですが、そういう様子も見えません。狭い境内けいだいのことですから、土を掘ったりすれば、すぐ分る筈ですし、社殿の中や縁の下なども調べたのですが、これという発見もありませんでした」
「君一人でお調べになったのですか」
「イイエ、署の者が五人程で手分けをして、調べたのです」
「イヤ、有難う。僕はこの辺を少しぶらついて見ますから、中村君が来られたら、そうお伝え下さい」
博士は警官に挨拶をして、小池助手と一緒に神社を出ると、どこという当てもなく、ブラブラと歩き出した。
「オヤ、小池君、あすこに見世物みせものが出ているようだね」
暫らく行くと、博士がそれに気附いて、助手を顧みた。
「エエ、そうのようですね。のぼりが立ってますよ。アア、お化け大会と書いてあります。例の化物屋敷の見世物でしょう」
「ホウ、妙なものが出ているね。行って見ようじゃないか。化物屋敷なんて随分ずいぶん久し振りだ。東京にもこんな見世物がかかるのかねえ」
「近頃なかなか流行しているんです。昔は化物屋敷とか八幡の藪知やぶしらずとか云ったようですが、この頃はお化け大会と改称して、色々新工夫をこらしているそうです」
話しながら歩く内に、二人は大きなテント張りの小屋掛けの前に来ていた。
小屋の前面は、張り子の岩組みと、一面の竹藪になっていて、その間から、狐格子きつねごうしの辻堂などが覗いている。さも物凄い飾りつけである。上部にはズラッと毒々しい絵看板が並び、それには、ありとあらゆる妖怪変化へんげの姿が、今にも飛びついて来そうに、物恐ろしく描いてある。
前には黒山の人だかりだ。その群衆の頭の上に、台にのった木戸番の若者の胸から上が見えている。若者は口にメガフォンを当てて、嗄声しわがれごえをふりしぼり、夢中になって客寄せの口上こうじょうを呶鳴っている。
段々近づいて見ると、木戸の上に、大きな貼紙をして、下手な字で、何かゴタゴタと書いてある。
本お化け大会入口より出口まで無事御通過なされしお客様には、入場料金を全部返却の上、賞金五円を贈呈致します。
「オヤ、変な見世物だねえ。五十銭の入場料で、五円の賞金を出していたんじゃ、興行主は損ばかりしていなけれゃなるまい」
博士が思わず独言のように云うと、群衆の中の一人の老人が、それを聞きつけて、話しかけた。
「それが、そうじゃねえんですよ。座元は丸儲まるもうけでさあ。ホラ、ごらんなさい。入口からああしてゾロゾロ見物が出て来るでしょう。みんな中途で引返すんでさあ。
あっしゃ、昨日から気をつけて見ているんだが、無事に出口まで辿りついた客は一人もねえ。よっぽどおっかない仕掛けがあるんですぜ。中途で引返ひきかえした人の話じゃ、中は八幡の藪知らずで、どこをどう歩いていいかさっぱり見当がつかない上に、全く思いもかけないところから、ヒョイヒョイとおっそろしい化物や幽霊が飛び出して来る。イヤ、化物ばかりならいいんだが、もっと気味の悪いものがあるって云いますよ。死人しびとですよ。汽車に轢ひかれて、手足がバラバラになって転がっているんだとか、胸を抉えぐられて、空くうを掴んで、口から血をタラタラと流して、今息を引取ろうとしているんだとか、怖いよりも胸が悪くなって、迚とても見ちゃいられねえっていうんです」
江戸っ子らしい老人は、ひどく話好きと見えて、聞きもしないのに、ベラベラと喋るのだ。
「で、お爺さんは中へ入って見ないんですか」
小池助手がからかい顔に訊ねると、老人は顔の前で手を振って見せた。
「御免、御免、五貫も出して胸の悪い思いをするこたあねえからね。何なら、お前さん方御見物なすっちゃどうだね」
すると、宗像博士は何を思ったのか、その言葉を引きとるように、
「どうだ、小池君、一つ入って見ようじゃないか」
と、笑いもしないで云うのである。
「エ、先生お入りになるんですか」
犯人の捜索はどこへ行ったのだ。それを捨てて置いて、子供みたいにお化けの見世物を見たがるなんて、先生はどうかしたんじゃないかしら。小池助手はあっけに取られて、博士の顔をまじまじと見つめた。
「少し思いついたことがあるんだよ。……マア、黙ってついて来たまえ」
博士はそう云ったかと思うと、群衆を押し分けて、もう木戸口の方へ歩き出していた。
小池助手は、名探偵とも云われる人の、余りの子供らしさに、呆気あっけにとられたが、ふと気がつくと、それには何か訳がありそうであった。博士は非常に実際的な規則正しい性格で、意味もなく見世物なんかへ入る人ではなかった。
「若しかすると、先生はこの化物屋敷の中で、妙子さんを探そうというのではないかしら」
この想像が、小池助手をギョッとさせた。見せびらかすことの好きな、芝居がかりの殺人鬼のことだ。或あるいはこの想像が当っているかも知れない。妙子さんを運んだ塵芥ごみ車はすぐ近所の神社の境内に、空っぽにして捨ててあったのだ。まだ薄暗い早朝とは云え、まさか若い女を抱いて遠くまで逃げることは出来まい、どちらの方角も町続きだから、やがてはげしくなる人通りの中を、怪しまれないで逃げおおせるものではない。という風に考えて来ると、いかに突飛とっぴに見えようとも、博士の想像は、どうやら当っているらしくも思われる。
博士が木戸へ近づいて入場料を払うと、木戸番の若者は妙な笑い顔で注意を与えた。
「中で紙札を二度渡しますからね。出口で返して下さい。それが無事に通り抜けたという証拠になるのですよ。二枚揃ってなくちゃいけませんよ」
二人はそれを聞き流して木戸を入って行った。テント張りとは云え、天井はすっかり厚い黒布で蔽おおってあるので、一歩場内に入ると、夜も同然の暗さであった。その薄暗い中に、見通しも利かぬ竹藪の迷路が続いているのだ。
或は右に或は左に、或は往ゆき或は戻り、やっと人一人通れる程の細道が、何町となくつづいている。全体の面積はさほどではなくても、往きつ戻りつの道の長さは驚くばかりである。
道が分れている箇所に出ると、小池助手はどちらを選ぼうかと迷った。若し間違った道に入り込んでしまったら、いつまでもどうどう廻めぐりをするばかりで、果はてしがないからである。
「君、迷路の歩き方を知っているかい。それはね、右なら右の手を、藪の垣かきから離さないで、どこまでも歩いて行くんだ。そうすると、仮令たとえ無駄な袋小路へ入っても、二度と同じ間違いを繰り返すことがない。出鱈目でたらめに歩くよりも、結局はずっと早く出られるのだよ」
博士は説明しながら、右手で竹藪を伝って、先に立って、グングンと歩いて行く。小池助手は、成程なるほどそういうものかなあと思いながら、そのあとを追うのである。
長い竹藪の間々あいだあいだには、ありとあらゆる魑魅魍魎ちみもうりょうが、ほのかな隠し電燈の光を受けて、或は横よこたわり、或は佇たたずみ、或は蹲うずくまり、或は空からぶら下っていた。あるものはからくり仕掛けで、ゆっくりと動いていた。古池になぞらえた水溜みずたまりの中から、痩せ細った手がニューッと出て、それから徐々に、お岩のように片目のつぶれた女の幽霊が現われ、見ていると、そのまんまるに飛び出した目から、タラタラと真赤な血が、とめどもなく流れ出すという、念の入った仕掛けもあった。
或時あるときはまた、見物は闇の通路で、何かしらグニャグニャした大きなものを踏んづけるのである。ギョッとして目をこらすと、何とも形容の出来ない、鼠色のいやらしいものが地上に横わっているのだ。どうやら顔らしい部分や、手足らしい部分が見えるけれど、無論人間ではない。と云って動物でもない。何かしら、ゾーッとするような、えたいの知れぬ物体なのだ。
ある場所では、真しんに迫った首吊り女が、見物の頭の上から、スーッとその肩に負ぶさって、両手でしがみつき、いやな声で笑い出す仕掛けもあった。
だが、それらの人形が、どれほど巧みに、いやらしく出来ていたとしても、屈強の男を走らせる程の恐怖は感じられなかった。よく見ていると滑稽こっけいでこそあれ、心しんから怖いというようなものではなかった。
「先生、つまらないじゃありませんか。ちっとも怖くなんかありゃしない。どうしてこんなものを見て逃げ出すんでしょうね」
「マア、終りまで見なければ分らないよ。それに僕達はただ慰みに入って来たんじゃない。大事な探しものがあるんだ。人形一つでも見逃す訳には行かないよ」
二人はそんなことを低声こごえに云い交しながら、お化けや幽霊に出くわすとは、立止り立止り、歩いている内に、やがて竹藪の迷路を抜けて、黒板塀くろいたべいのようなものに突き当った。
「オヤ、また袋小路かな。イヤイヤ、そうじゃない。ここに小さな潜くぐり戸がある。開けてお入りくださいと、貼り紙がしてある」
如何にも、黒板塀の上に、ひどく下手な字の貼り紙が見える。
「君、少し凄くなって来たじゃないか。真暗な中で戸を開けて入るというのは、何だか気味の悪いものだね」
「そうですね。一人きりだったら、一寸いやな気持がするかも知れませんね」
しかし、二人はまだ心の中ではクスクス笑っていた。なんてこけおどしな真似をするんだろうと、おかしくて仕方がなかった。
博士を先に、二人は戸を開いて中に入った。だが、そこには別に恐ろしいものがいる訳ではなく、ただ文目あやめもわかぬ闇があるばかりであった。天井も左右の壁も、板を重ねた上に黒布が張ってあるらしく、針の先程の光もささぬ如法暗夜にょほうあんやである。目の前に何かムラムラと煙のようなものが動いたり、ネオン・サインのように鮮かな青や赤の環が現われたり消えたりした。造りものの化物などよりは、この網膜のいたずらの方が、却かえって不気味な程であった。
「こりゃ暗いですね。歩けやしない」
二人は手を壁に当てて、足で地面をさぐりながらあるいて行った。
「昔パノラマという見世物があってね、そのパノラマへ入る通路が、やっぱりこんなだったよ。この闇が、つまり現実世界との縁を断つ仕掛けなんだ。そうして置いて、全く別の夢の世界を見せようというのだね。パノラマの発明者は、うまく人間の心理を掴んでいた」
手さぐりで五間ごけん程も進むと、左側の闇に、何か白いものが感じられた。やっぱり網膜のいたずらかと疑ったが、どうもそうではないらしい。何かが蹲まっているのだ。
「ナアンだ。骸骨ですよ。骸骨が胡坐あぐらをかいているんですよ」
小池はその側に近づいて、骨格に触って見た。絵ではない。人間が縫包ぬいぐるみを着ているのでもない。本物の骨格模型である。
何も見えぬ黒暗々の中に、この世のたった一つの生きもののように、白い骨が浮き上って、ポツンと胡坐をかいている有様は、怖いというよりも、異様に謎めいて不気味であった。
だが、二人が立止って見ているうちに、妙なことが起った。骸骨がスーッと立上ったのである。そして、いきなり右手を二人の方へ突き出した。その手に紙の束を持っているのが、どうやら見分けられた。
と同時に、骸骨の口がパックリと開いて、カチカチと歯を噛み合した。
妙な嗄れ声で笑っているのだ。どこかにラウド・スピーカーがあって、遠くから声を聞かせているのに違いない。
それが木戸番の云った証拠の紙札であることは、すぐに分ったが、気の弱いものは、黒暗々の中で、骸骨の手からそれを受取る勇気がなくて、逃げ出してしまうかも知れない。謂いわばこれが第一の関所であった。
博士と小池助手とは、無論怖がるようなことはなく、一枚ずつそれを受け取って、さらに前方への手さぐり足さぐりをはじめた。
それから少し行くと正面の壁に突き当った。右にも左にも道はない。行き止りになっているのだ。
「変だね、あとへ戻るのかしら」
「その辺に、又戸があるんじゃないでしょうか。やっぱり黒い板塀のようじゃありませんか」
「そうかも知れない」
博士は正面の板をしきりとなで廻していたが、間もなく、
「アア、あった、あった。ドアになっているんだよ。押せば開くんだ」
と呟きながら、そのドアを押して中へ入って行った。その拍子に、何かしらマグネシュウムでも焚たいたような、ギラギラした光線が、パッと小池助手の目をくらませたが、それも一瞬で、ドアはバネ仕掛けのように、彼の鼻先にピッタリ閉とざされてしまった。
博士を追って中へ入ろうと、押しこころみたが、どうしたことか、ドアは誰かがおさえてでもいるように、びくとも動かない。
「先生、戸が開かなくなってしまいました。そちらから開きませんか」
その声がドアを漏れて幽かすかに聞えて来たが、博士の方ではそれどころではなかった。真暗闇から突然太陽のような光の中へ放り出されて、クラクラと眩暈めまいがしそうになっていたのだ。
何かしらギラギラと目を射る、非常な明るさであった。暫らくは闇と光との転換の余りの激しさに、網膜が麻痺したようになって、何が何だか少しも分らなかったが、靄もやが薄れて行くように、目の前のギラギラした後光みたいなものが消えて行くと、その向うに、目を大きく見開いて、口を開け、だらしのない恰好かっこうで立っている一人の男が現われて来た。
「オヤッ、あれは俺おれじゃないか」
ギョッとして見直すと、その男はもう他所よそ行きの取りすました顔になっていたが、眼鏡といい、口髭といい、三角の顎髯といい、モーニングといい、宗像博士自身と一分一厘も、違わない男であった。
何だか魔法にかけられたような、それとも気でも狂ったのじゃないかと怪しまれるような、一種異様の心持であった。場所が化物屋敷の中だけに、そして、今の今まで、文字通りの闇の中を歩いて来ただけに、博士はついこの見世物の考案者を買被かいかぶったのであった。
少し落ちついて、よくよく見れば、博士の正面にあるものは、大きな鏡の壁に過ぎないことが分って来た。
「ナアンだ。鏡だったのか。しかし、それにしても、この見世物は普通の化物屋敷なんかと違って、なかなか味をやりおるわい」
だが、ナアンだ鏡かと、軽蔑するのは少し早まり過ぎた。この妙な小部屋には、まだまだ博士をびっくりさせるような仕掛けが、しつらえてあったのだから。
ヒョイと右を向くと、そこにも博士自身がいた。左を向くとそこにも同じ自分の姿があった。後を振返れば、ドアの裏側がやっぱり鏡で、そこに実物の五倍ほどもある大入道おおにゅうどうのような博士の、あっけに取られた顔が覗いていた。
イヤイヤ、こう書いたのでは本当でない。鏡は四方にあったばかりではないのだ。天井も一面の鏡であった。床も一面の鏡であった。そして、博士を取りまく壁は不規則な六角形になっていて、それが枠もなにもない鏡ばかりなのだ。つまり六角筒の内面が、少しの隙間もなくすっかり鏡で張りつめられ、その上下の隅々に電燈が取りつけてあるという、いとも不思議な魔法の部屋なのである。
しかも、それらの鏡は、必ずしも平面鏡ばかりではなかった。ある部分は先にも記したように、実物を五倍に見せる円形の凹面鏡になっていた。またある部分は、鏡の面が複雑な波形をしていて、人の姿を一丈に引き伸ばしたり、二尺に縮めたりして見せた。そして、それらの雑多の影が六角の各々おのおのの面に互に反射し合って、一人の姿が六人になり、十二人になり、二十四人になり、四十八人になり、じっと鏡の奥を覗くと、遙はるかの遙かの薄暗くなった彼方かなたまで、恐らくは何百という影を重ねて映っているのだ。それを六倍すれば何千人、更にその上に、天井と床とが、また各々に反射し合い、方々の壁に影を投げるのである。
博士はそういう鏡の部屋というものを、想像したことはあった。しかし、これ程よく出来た鏡の箱に、ただ一人とじこめられたのは、全く初めての経験なのだ。世間を知りつくし、物に動ぜぬ法医学者も、このすさまじい光景には、理窟ぬきに、赤ん坊のような驚異を感じないではいられなかった。
博士が笑えば、千の顔が同時に笑うのだ。しかも、それらの中には、五倍の大入道の顔、胡瓜きゅうりのような長っ細い顔、南瓜かぼちゃのように平べったい顔なども、幾十となく交まじっている。手を上げれば、同時に千人の手が上がり、歩けば同時に千人の足が動くのだ。
天井を見上げると、そこには逆立ちをした博士が、じっとこちらを睨みつけている。床を覗けば、そこにも足を上にしてぶら下っている博士が、下の方から見上げている。そして、それら二様の逆の姿が、無限の空にまで、奥底知れぬ六角の井戸の底まで、数限りもなく重なり合って、末は見通しも利かぬ闇となって消えているのだ。つまり、前後左右は勿論、上も下も無限の彼方に続いていて、まるで大空に投げ出されでもしたような、大地が消えてなくなったような、云うに云われぬ不安定の感じであった。
どちらを見ても、行き止りというものがなく、自分自身の姿が無限に続いているのである。この恐ろしい場所を逃れるためには、それらの何千という人々を、掻き分け押し分け、無限に走る外ほかはないという、奇怪千万な錯覚が起るのだ。
博士はふと、こんな見世物を興行させて置くのは人道問題だと思った。博士のような思慮分別のある中年者でさえ、たまらない程の不安を感じるのだから、若し女子供がこの鏡部屋にとじこめられたなら、恐怖のために泣き出すに違いない。イヤ、泣き出すばかりでなく、中には気が違ってしまう者もあるかも知れない。
博士は嘗て何かの本で、人間を鏡の部屋にとじこめて発狂させた話を読んだことがあった。そして、それと関聯して、寄席の芸人が物真似ものまねをする、蝦蟇がまの膏売あぶらうりの、滑稽なようでいて、どことなく物凄い妙な口上が、耳元に浮かんで来た。無神経な蝦蟇でさえ、鏡に取りかこまれた恐怖には、全身からタラーリタラーリと膏汗あぶらあせを流すではないか。
流石の宗像博士もこの恐怖の部屋には、そのまま佇んでいる気はしなかった。大急ぎで六角の鏡の面に触りながら、どこかに出口はないかと歩き廻った。すると、千人の同じ博士がグルグルと、大グラウンドでのマス・ゲームのように、卍巴まんじともえとなって歩き廻るのだ。
何という残酷な仕掛けだろう。入口のドアは閉まったまま開かないし、出口も見つからぬ。見物が気の違うまで閉じこめて置こうとでもいうのだろうか。
さい前ドアが素早く閉まったのには理由があったのだ。あのドアには、一人だけ中に入ると、あとから見物が入らぬよう、ある時間、押しても引いても開かなくなってしまう仕掛けがしてあるのだ。そして、一人ぼっちでこの魔の部屋の恐怖を味わせようという訳なのだ。
「小池君、こいつは気味が悪いよ。鏡の部屋なんだ。それに出口がどこにあるんだか分らない。そのドアをもう一度押してごらん」
博士は外の闇の中にいる小池助手に、大声に呼びかけた。
「どうしても開かないんです。さっきから押しつづけているんですけれど」
「小池君、君ここへ入っても驚いちゃいけないよ。僕は何も知らずに飛び込んだものだから、ひどく面喰ってしまった。どこもかも鏡ばかりなんだ。この部屋には僕と同じ奴が千人以上もウヨウヨしているんだぜ。そして、僕と同じように、今物を云っているんだ。ハハハハハハハハ、アア、僕が笑うと、奴らも口を開いて笑うんだ」
「ヘエ、気味が悪いですね。そして、出口が分らないのですか。この戸はどっか狂ったのじゃないでしょうか。入口へ戻って、人を呼んで来ましょうか」
「アッ、開いた。開いた。君、やっと鏡の壁が口を開いたよ。じゃ僕は先に出て待っているからね」
如何にも、六角形の一つの面が、機械仕掛でクルッと廻転して、人一人通り抜けられる程の隙間が出来た。その向う側は例によって、黒暗々こくあんあんの闇である。
博士はそこを出ようとして、躊躇した。若し小池助手が入って来たら、こんな不気味な部屋へ一人残して置かないで、一緒に向うへ出ようと考えたからである。
しかし、化物屋敷の考案者は、そこに抜かりがなかった。
「僕の方は開きませんよ。どうしたんだろう」
小池助手が入口のドアを、外からドンドンと叩たたく音がした。しかし、いっかな開きはしないのである。
仕方がないので、博士は先に鏡の部屋を出て、外の暗闇に入ったが、すると、今まで開いていた隙間が、カタンという音を立て、自然に塞がされてしまった。そして、殆ほとんどそれと同時に、部屋の中から幽かすかな小池助手の声が聞えて来た。
「先生、どこにいらっしゃるのです。開きましたよ。ドアが開きましたよ」
「出口はここだ。しかし、自然に開くのを待つ外はないのだ。仕方がない、暫くそこに我慢していたまえ」
博士は今出たあたりの壁をコツコツと叩いて聞かせながら、大声に呶鳴るのであった。
闇の中に佇んで暫らく待っていると、やっと目の前の壁が開いて、小池助手がフラフラと逃げ出して来た。
「驚きました。実にいやな気持ですね。僕は半分は目をつむってましたよ。そうでないと、今にも気が変になるような気がして」
「なる程。これじゃ、みんなが逃げて帰る筈だ。進めば進む程、物凄くなるんだからね」
二人はボソボソと囁き交しながら、またしても壁伝いに闇の中を歩きだした。真の闇というものは、人の声を低くするものである。そこに漂う何かしら隠微いんびな魂が高話たかばなしを抑えつけて、囁き声にしてしまうものである。
「どうです? 少し驚いたでしょう。だが、これはまだホンの序の口ですよ。本当に怖いのはこれからです。引返した方がおためですぜ。気絶なんかされちゃ困りますからね」
闇の中から低い嗄れ声が響いて来た。恐らくは骸骨の場合と同じように、どこかにラウド・スピーカーがあって、誰かが遠くから喋っているのであろうが、闇の中だけに、つい鼻の先に真黒な奴が踞うずくまってでもいるような気がして、二人は思わず立止った。
「ハハハハハハ、ひどくおどかすねえ。それに、帰れ帰れっていうのは、すこし卑怯ひきょうじゃないか」
「そうですね。人を喰ったものですね」
大多数の見物は、この辺でとどめを刺されて、愈々引返ひっかえす気になるのであろうが、博士達は引返さなかった。鏡の部屋の経験で、これが世の常の化物屋敷でないことが分ったけれど、この二人は、不気味であればある程、却って好奇心をおこす側の人々であった。それに、肝腎かんじんの死体捜索という大目的があるのだから、場内を一巡しないでは意味をなさぬ訳だ。並々の見世物でなくて、大人の二人にも、かなりのスリルを感じさせるのは、謂わば予期しなかった儲もうけものであった。
手探り足探りで歩く程に、やがて徐々にあたりがほの明るくなって来た。
「また竹藪があるようだね」
如何にも、黒布のトンネルのような通路を出ると、またしても鬱蒼うっそうたる竹藪の細道であった。そこをガサガサ云わせながら辿って行く内に、ヒョイと右側を見ると、その竹藪に切れ目があって、幅一間けん奥行二間ほどの、藪に囲まれた空地があった。その部分だけ薄青い電燈がついているので、ハッキリ見えるのだが、空地の真中に大きな十字架が建っていて、そこに一人の女が大の字にしばりつけられている。青い獄衣のようなものを着て、その胸の部分だけが、前に括り合わされ、両腋りょうわきから乳の辺まで、肌が現われている。
「磔刑はりつけ人形ですね」
その十字架の両側には、チョン髷まげに結った二人の男が、繩の襷たすきをかけて、長い鎗やりを左右から女の両腋につきつけている。そして、その鋒鋩ほさきが女の両の乳の下を、抉えぐっている。それはここに細叙さいじょすることを憚はばかるほどの、見るものはたちまち吐き気を催すほどの、無残な有様であった。
女の美しい顔は、濃い藍色あいいろであった。恨めしげに見開いた目は真赤であった。唇はドス黒く見えた。眉をしかめ、目を狐のように逆立て、口を大きく開いて、わめいている形相の物凄さ。
しかも、ここにも異様なからくり仕掛けがあった。二人の男の手が動いて、鎗の鋒鋩がグイグイとそこを抉った。すると、アア、何ということだ。磔刑女は、ゾーッと歯ぎしりが出るような、聞くも無残な声で叫ぶのである。一度聞いたら、一月も二月も耳に残るような恐ろしい声で、わめくのである。マイクロフォンとラウド・スピーカーを、何と巧みに使いこなしていることだろう。
お化ばけや幽霊を怖がらなかった二人も、流石にこの生人形には胸が悪くなった。お互の顔色が青くなっていることを認め合った。
「先生、早く通りましょう。これでは見物が逃げ戻る筈ですよ。なんてひどい見世物でしょう」
「管轄の警察の手落ちだね。こんなものを許すなんて。多分いつものお化け大会だぐらいに思って、よく調べなかったのじゃないかな」
それからの長い竹藪の細道には、或は右に或は左に、大小様々の空地があって、そこにありとあらゆる無残なもの、血腥ちなまぐさいもの、一口で云えば、解剖学教室の最も怖ろしい光景に類する恐怖が、次から次へと、ほの暗い照明の中に、毒々しい生人形の塗料を光らせて、真に迫って、並んでいたのである。或ものは断末魔のうめきを立て、十本の指に空を掴み、あるものは知死期ちしきの痙攣けいれんに震え、あの死の恐怖、大手術の恐怖を、まざまざと見物の目の底に焼きつけようとしていたのである。
その光景の悉ことごとくを描写する事は、読者の為めに避けなければならない。それらの内の、最も手軽な一例を記すだけでも、恐らく十分すぎるであろう。
そこにはやや広い空地があって、背景は暗く繁った森林、左手にトンネルが魔物のような真黒な口を開き、その中から二本の鉄路が流れ出している。レールの土台を除いて、一面の草原くさはら、今汽車が通過したばかりという心持である。
その線路と草原とのあちこちに、今轢断れきだんされたばかりの若い女の死体が、転がっている。無論それらは一つに連続した死体ではない。六つ程に分れて転がっている死体だ。
レールも、青い草も血に染まっている。夫々それぞれの切口の恐ろしさ。何かしら白いものを中心にした真赤な輪であった。
切り離された首だけが、見物に最も近い草の上に、チョコンと、切口を土につけて立っていた。藍色に青ざめているけれど、美しい顔だ。
桐の木に彫刻をして、胡粉ごふんを塗り、塗料を塗り、毛髪は一本一本植えつけ、歯は本当の琺瑯ほうろう義歯を入れるという、この生人形というものは、いつの世、何人なんびとが発明したのであろう。顔の小皺こじわの一本まで、生けるが如き生々しさ。生人形とはよくも名づけたものである。
轢死者の首は、美しい眉をしかめ、口を苦悶にゆがめて、じっと目を閉じていた。アア、何という生々しさ。今汽車が通過したばかり、そして、レールからコロコロと転がって来て、そこへ据わったばかりという心持を、どんな名画も及ばぬ巧みさで描き出していた。まだ反動が鎮しずまらないで、生首はユラユラと揺れているかとさえ疑われた。
「先生、先生」
小池助手が青ざめた顔で、乾いた唇で、強く囁きながら、博士の腕を捉えた。
「先生、僕の目がどうかしているんでしょうか。よくこの首を見て下さい。こんな人形ってあるでしょうか。若しや……」
あとは口に出すのも恐ろしいように、云い渋った。
「妙子さんではないかというのだろう。僕もそれに注意しているんだが、少しも似ていないよ。生顔いきがおと死顔しにがおとは相好そうごうが変るものだと云っても、こんなに違う筈はないよ」
「そういえば、そうですね。しかし、僕はなんだか、本当の人間の首のような気がして……」
小池助手がそこまで囁いた時であった。まるで、その言葉を裏書うらがきでもするように、生人形の首が、パッチリと目を見開いたのである。涼しい黒目勝がちの目だ。その黒目が右に左にキョロキョロと動いた。
二人はギョッとして、一歩あとにさがった。例のからくり仕掛にしては、少し出来すぎている。
呆然と立ちすくんでいる二人の前で、生首の口辺の皺がムクムクと動いて、やがて、紫色の唇が開き、白い歯がニッと現われた。そして、笑ったのである。草原の上の生首が声を立てないでニヤニヤ笑ったのである。一瞬間、流石の法医学者も、勇敢なその助手も、動悸の早まるのをどうすることも出来なかった。顔は二人とも紙のように青ざめていた。
しかし、やがて、宗像博士は笑い出した。
「これは君、生きた人間だよ。若い女が土の中へ全身を埋めて、首だけ出しているんだよ」
無論その外に考え方はなかった。恐らくそこに木の箱でも埋めて、身体が冷えぬような設備をして、そんな真似まねをしているのであろうが、それにしても、何という突飛な、人騒がせな思いつきをしたものだ。薄暗い草原の中で、人形とばかり思い込んでいた轢死女の首だけが、ニヤニヤ笑うのを見たら、大抵の見物けんぶつは腰を抜かしてしまうであろう。
「なる程考えたものだねえ。これ一つでも入場料だけの値打はありそうだぜ」
「僕はこんな気味の悪い見世物は始めてですよ。この興行主はよっぽど変り者に違いありませんね」
まだ青ざめた顔で、乾いた唇で、そんなことを話しながら、轢死の場面を立去ろうと、二三歩あるいた時である。小池助手は何かしら、うしろに異様な物の気配を感じて、ハッと振向いた。
すると、線路の上に転がっていた、血みどろの腕が、まるで爬虫類ででもあるように、スーッと草原の上を這って、こちらへ近づいて来るのが見えた。しかも、恐ろしいことには、それが見る見る柵を越して、通路の方まで這い出して来たのである。
「ワアッ!」
小池助手は思わず声を上げて、博士の肩にしがみついた。からくり仕掛けと分っていても、青白い腕ばかりが、暗い地面を這い出して来るなんて、どんな大人にも気味のよいものではない。
すると、又してもいつもの嗄れ声が、どこからともなく響いて来た。
「お客さん、これが二枚目の紙札ですよ。これを持って出ないと賞金はとれませんよ。だが、用心して下さい。死びとの腕はお客さんに咬かみつくかも知れませんぞ」
又しても、陰気な脅し文句だ。見れば、死人しびとの指には、一束の小さな紙札が握られている。
「なるほど、なるほど。よく考えたものだねえ。しかし、これを受け取れば、我々は完全に関所を通過したことになる訳だね」
博士はそんなことを呟きながら、腰をかがめて、人形の腕を掴むと、その指から二枚の紙札を抜き取った。
「なる程、大きな判が捺おしてあるね」
博士は立上って、感心したように紙札を眺めていたが、さい前のと同じように、二枚とも自分のポケットに納めた。
それからまた、幾つもの思い切って無残な場面を通りすぎて、さしもに長い竹藪も終りに近いところまで辿りついた。
「先生、とうとうおしまいのようですね。しかし、どこにも本物の死体なんて、なかったじゃありませんか」
小池助手は失望の面持である。あれだけ夥しい死びと人形の中に、一つも本物が混っていないなんて、却って不自然なような気さえした。
「だが、まだここに、何だか物々しい場面があるぜ。ここだけひどく薄暗いじゃないか」
博士はそこの柵の前に立って、じっと奥の方を見つめていた。
そこには、竹藪に囲まれ雑草の生い茂った空地に、一軒の荒屋あばらやが建っていた。六畳一間きりの屋内は、戸も障子もなくて見通しである。その部屋一杯に、色褪せた萠黄もえぎの古蚊帳ふるかやが吊ってある。光と云っては、その蚊帳の上に下っている青いカヴァーをかけた五燭の電燈ばかり。蚊帳の中は殆んど見すかせぬ程の暗さである。
「なんだろう。蚊帳の中に何かいるようじゃないか」
「いますよ。よく見えないけれど、何だか裸体はだかの女のようですぜ。アア、真裸体まっぱだかです。それでこんなに暗くしてあるんですよ」
「なにをしているんだろう」
「殺されているんですよ。顎から胸にかけて、黒いものが一杯流れています。血です。裸体はだかに剥はがれて、惨殺された女ですよ」
「五体は揃っているようだね」
「エエ、そうのようです」
「髪は断髪じゃないかい」
「断髪ですよ」
「肉づきのいい、若い女だね」
話している内に、少しずつ目が慣れて、蚊帳の中の女の姿が浮上って来た。
「調べて見ましょうか」
「ウン、調べて見よう」
二人は意味ありげな目を見交した。何かツーンと痺しびれるような感じが、小池助手の背筋を這い上った。
二人は柵を越えて、無言のまま中に入り、膝を没する雑草を踏み分けて、荒屋の上に上って行った。そして、先ず博士が古蚊帳の裾に手をかけると、それをソッとまくり上げた。
荒屋の縁側に上って、古蚊帳をまくると、天井に仕掛けた青い豆電燈の幽かな光を受けて、全裸の美女が、まるで水の底の人魚のように横わっていた。二人は這うようにして、その生々しい生人形の側へ近づいて行った。
「どうもそうらしいね」
「エエ、この顔は妙子さんにそっくりです」
小池助手の鼻の先に、ふっくらとした美女の肩がもり上っていた。彼はオズオズとその青ざめた肌に指を当てて見た。
冷い。氷のような冷さが、指の先から心臓まで伝わって来るように感じられた。それを我慢しながら、グッと押して見ると、美女の肩が、靨えくぼのように凹くぼんで行った。柔かいのだ。ゴムのように柔かいのだ。
博士は、ハンカチを取り出して、ベットリと美女の胸を染めた黒いものに押し当て、それを目の前に持って来て眺めたり、匂においを嗅いだりしていた。ハンカチには黒い液体が滲にじんでいる。
「君、懐中電燈をつけてごらん」
小池助手はポケットから、小型の懐中電燈を取り出して、スイッチを押し、その光を博士のハンカチに当てた。
今まで青い電燈の下で、黒く見えていたハンカチの汚点しみが、赤黒い血の色に変った。
博士は無言のまま、ハンカチを助手に渡すと、胸の傷痕を調べた。
「心臓を抉えぐられている。だが……」
博士は出血量が案外少いことを不審に思っているらしく、なお死体の全身を眺め廻していたが、
「アア、やっぱり絞殺されていたんだ。そして、ここへ運んで来てから、舞台効果を出すために、心臓を抉ったのに違いない」
と、独言のように呟いた。
「昨夜、寝室で絞殺されたのでしょうか」
「そうらしい。でなければ、あんなに易々やすやすとベッドの中へ隠したり、塵芥ごみ箱の中へ隠したり出来ない筈だからね。……犯人は、今朝まだ薄暗い内に、これを塵芥車にのせて、そこの神社の森の中へ引っぱって来た。それから、死体を担いで、化物屋敷のテントに忍び込み、この蚊帳の中の生人形と置き換えたのだ。心臓を抉ったのは、ここへ来てからに違いない。無論、最初からここへ死体を隠すつもりで、見当をつけて置いたのだろう。この場面を選んだのは、電燈も薄暗いし、蚊帳の中といううまい条件が揃っていたからだ。この中へ置けば、我々のように蚊帳をまくって見る見物けんぶつなんかありやしないから、急に発見される心配はないと思ったのだ」
「それに、大抵の見物は、ここまで来ないで、逃げ帰ってしまうのですからね。……でも、見世物小屋の人達に、よく見つからなかったものですね」
「犯人がここへ来た頃は、まだ夜が明けたばかりで、みんな寝ていたのだろう。それに、何も正面の入口から入らなくても、この場面のすぐうしろから、テントの裾をまくって忍び込めば、訳はないんだからね」
「早速、川手さんと中村係長に知らせなければなりませんね」
「ウン、電話をかけることにしよう。……だが、小池君、ちょっと待ち給え。さい前ぜん渡された二枚の紙札が何だか気になるんだ。懐中電燈をつけた序ついでに調べて置こう」
紙札というのは、例の暗闇のなかの骸骨と、叢くさむらを這い出して来た生腕なまうでとから受取った、化物屋敷通過証ともいうべき紙片かみきれである。
博士はその二枚の紙片を、ポケットから取り出し、小池助手のかざす電燈の光の中で、丁寧に調べて見た。
紙片は二枚とも同質同形で、その表面には、夫々「第一引換券」「第二引換券」と筆太に記され、その真中に「丸花まるはな興行部之印」という大きな赤い判が、ベッタリと捺してある。
二枚とも表面を調べ終ると、博士はそれを裏返して、懐中電燈の光に照らして見た。
「アア、やっぱりそうだ。君、これを見たまえ」
二枚とも、紙片の真中に、黒い指紋がハッキリと現われていた。偶然についたのではなくて、指の腹に墨をつけて、態と捺した指紋である。
博士は胸のポケットから、小型拡大鏡を出して、紙片の上に当てて見た。
「三重渦状紋だ、悪魔の紋章だ」
「例のいたずらですね」
「我々を嘲笑しているのだよ」
「しかし、あの骸骨や、人形の腕が、これを持っていたのは変ですね。丁度僕らの受取った札に、あいつの指紋が捺してあるというのは。……若しや、あいつ、まだこの中にウロウロしているんじゃないでしょうか」
小池助手は異様に声を低くして、じっと博士の顔を見つめた。
「そうかも知れない。君、あれは何だろう。あの藪の中にいる黒いものは……」
博士の目は、蚊帳を通して、荒屋のうしろの竹藪に注がれていた。
「エッ、黒いものですって?」
「ホラ、あすこだ。海坊主のような真黒な奴だ、まさか、こんな人の目につかぬところに、化物の人形が置いてある筈はない」
博士は、荒屋の背後うしろの竹藪の中を、目で知らせながら囁いた。殆ど光線の届かぬ闇の中だ。そう云われて見ると、何かそこに、闇よりも濃い影のようなものが、朦朧もうろうと立っているように感じられる。
博士は刺すような眼光で、それを睨みつけている。闇の中の怪物も、身動きもせず、こちらを見つめている様子だ。蚊帳を隔てて、殆んど三十秒ほども、息づまるような睨み合いがつづいた。
「君、来たまえ」
博士はそう囁くと、いきなり蚊帳をまくって、荒屋の裏の藪の中へ飛び込んで行った。
ガサガサと竹の揺れる物音。
「そこにいるのは誰だッ」
博士の叱りつけるような重々しい声に応じて、闇の中から異様な笑い声が響いて来た。クックックッと、口を押えて忍び笑いをしているような、まるで怪鳥けちょうの鳴き声のような、何とも云えぬいやな感じの音響であった。そして、又ガサガサと竹が鳴って、黒い怪物は素早く藪の中へ逃げ込んだ様子である。
「待てッ」
闇の中の盲目滅法な追跡が始まった。
小池助手も、博士のあとを追って、蚊帳を飛び出し、竹藪をかき分けながら、音のする方へ急いだ。
厚い竹藪の壁を押し分けて向うに出ると、そこは以前に通り過ぎた迷路の中で、両側に藪のある曲りくねった細道がつづいていた。
「どちらへ逃げました?」
「分らない。君はそちらを探して見てくれたまえ」
博士は云い捨てて、迷路を右へ走って行く。小池助手は左の方へ突進した。
右に折れ左に折れ、いくら走っても際限のない竹藪の細道であった。もう自分がどの辺にいるのかさえ見当がつかない。黒い怪物は影も見えず、宗像博士がどの辺を追跡しているのか、それさえ全く分らぬ。
ふと立止ると、厚い竹藪の向側に、ガサガサと人の気配がした。重なり合った竹の葉をすかして見ても、薄暗くてよく分らない。何かしら黒い人影が感じられるばかりだ。
「先生、そこにいらっしゃるのは先生ですか」
声をかけても相手は答えなかった。答える代りに、又ガサガサと身動きして、クックックッと、あの何とも云えぬ不気味な笑い声を立てた。
小池助手は、それを聞くと、ギョッと立ちすくんだが、やがて気を取りなおして、いきなり竹藪をかき分けながら、
「先生、ここです。ここです。早く来て下さい」
と叫び立て、顔や手の傷つくのも忘れて、藪の向側へくぐりぬけた。
だが、くぐりぬけて見廻すと、怪物はどこへ逃げ去ったのか、影もない。そして又、八幡の藪知らずの、際はてしもない鬼ごっこが始まるのだ。
「小池君」
ヒョイと角を曲ると、向うから宗像博士が走って来た。
「どうだった。あいつに出会わなかったか」
「一度声を聞いたばかりです。確かにこの迷路のどこかにいるには違いないのですが」
「僕も声は聞いた。竹藪のすぐ向側に立っているのも見た。しかし、こちらがそこまで行く間に、先方はどっかへ隠れてしまうんだ」
二人が立話をしている所へ、ガサガサと人の気配がして、三人の男が近づいて来た。見世物小屋の人達である。さい前の叫び声を聞きつけて、様子を見にやって来たのだ。
博士は三人のものに、事の仔細を語り、怪物逮捕の手伝いをしてくれるように頼んだ。
「小池君、じゃ、君はこの人達と一緒に、出来るだけ探して見てくれたまえ。僕は近くの電話を借りて、中村君に警官隊をよこしてくれるように頼むことにする。
外は明るいのだし、大勢の見物が集っているんだから、犯人が外へ逃げ出すことはなかろう。ナアニ、もう袋の鼠も同然だよ」
博士は云い捨てて、惶あわただしく迷路の彼方へ遠ざかって行った。
それから間もなくの出来事である。
薄暗い竹藪の、とある細道を、黒い影法師のようなものが、フラフラと歩いていた。
よく見ると、そいつは、ぴったりと身についた真黒のシャツを着、真黒のズボン下を穿はき、黒い靴下、黒い手袋、頭も顔もすっぽりと黒布で包んだ、全身黒一色の怪物であった。
ただ、黒布の目の部分だけが、細くくり抜いてあって、その奥から、鋭い両眼が要心深くあたりを見廻している。無論何者とも判断がつかぬけれど、若しこれが妙子さんを誘拐した犯人の一人とすれば、あの背の高い方の、ガーゼの眼帯を当てていた男に違いない。
黒い怪物は、宗像博士が警官隊を呼ぶために電話をかけに行ったことも、又、小池助手の指図で、十人余りの小屋の者が、迷路の要所要所に、捜索の網の目を張っていることも、よく知っているに違いない。
だが、彼は少しも慌てている様子がない。さも自信ありげに、ゆっくりと歩いている。例のクックックッという幽かな笑い声さえ立てながら。
竹藪の向うのあちこちでは、捜索の人達がガサガサと物音を立てながら、右往左往しているのが、手に取るように聞える。竹の葉をかき分ける音が、前からも後うしろからも、右からも左からも聞えて来る。黒い怪物は、今や四方から包囲された形だ。しかも、その包囲陣は徐々に彼の身辺に縮められているのだ。
怪物は、しかし、まだせせら笑っていた。冗談らしくピョイピョイと飛ぶような恰好をしたりして、暗やみの中を呑気らしく歩いていた。
角を曲ると、頭の上に白いものがぶら下っていた。例の首吊り女の幽霊である。
怪物はそれを見上げて、又クックックッとせせら笑った。黒布で包んだ顔の中から、二つの細い目が、何か陰気なけだものの目のように光っている。この黒い海坊主を見ては、幽霊の方で身震いするかも知れない。
怪物がそのまま歩き出すと、からくり仕掛けの幽霊は、そのあとを追うように、スーッと舞い下って来た。そして、普通の見物にするのと同じ恰好で、うしろから、彼の黒シャツの肩にしがみついた。
怪物は予期していたと見えて、少しも驚かなかった。又妙な笑い声を立てながら、そのか細い幽霊人形の手を払いのけようとした。
だが、どうした事か、幽霊の両手は、いくらふりほどいても、黒い怪物の肩から離れなかった。もがけばもがく程、その手はグングン彼の頸くびをしめつけて来た。
それは実に異様な光景であった。細い両眼の外は黒一色の影法師の背中に、長い髪の毛をふり乱した、白衣びゃくえの青ざめた女幽霊が、負おぶさるようにしがみついているのだ。暗闇の竹藪の中では、それが滑稽に見えるどころか、何ともえたいの知れぬ奇怪なものに感じられた。現実の出来事というよりは、悪夢の中の突拍子とっぴょうしもない光景であった。
痩せ衰えた女幽霊の余りの力強さに、流石の怪物もギョッとしたらしく、今度は本気になって、力まかせにその手をふりほどこうとあせった。
だが、幽霊の両手は、愈々力をこめて、頸をしめつけて来る。呼吸いきもとまれとしめつけて来る。
「き、貴様ッ……」
怪物は遂に悲鳴を上げた。うしろにしがみついている奴が、人形ではなくて、生きた人間であることを悟ったのだ。幽霊に化けて、彼の通りかかるのを待ち受けていた、追手の一人であることを悟ったのだ。
恐ろしい格闘が始まった。女幽霊と海坊主との、死もの狂いの組打である。
だが、戦いはあっけなく終りをつげた。頸をしめつけられて、力の弱っていた怪物は、たちまち幽霊の為に組み伏せられてしまった。
「オーイ、捕えたぞ。ここだ、ここだ、早く来てくれ」
幽霊が小池助手の声で呶鳴った。
ただ追い廻していたのでは、相手は真黒な保護色の怪物だから、急に捉える見込みはないと悟って、咄嗟とっさの機智、彼は首吊り幽霊の衣裳をつけ、長髪の鬘かつらを冠って、人形に化けて敵の虚を突いたのであった。
小池助手は得意であった。博士の留守の間に、早くも怪物を捉えてしまったのだ。残虐飽くなき復讐魔を組み敷いてしまったのだ。それにしても、見かけ程にもない弱い奴だ。一体どんな顔をしているのだろう。
彼はいきなり覆面の黒布に手をかけて、ビリビリと引き破った。顎が、口が、鼻が、そして目が、次々と現われて来た。薄闇の中とはいえ、接近しているので顔容かおかたちが分らぬ程ではない。彼は怪物の顔を見た。はっきりとその素顔を見たのだ。
一目見るや否や、小池助手の口から、何とも云えぬ恐ろしい叫び声がほとばしった。その調子には、極度の驚きと、何かしら世にも悲痛な響きが籠こもっていた。
「ウヌ、俺の顔を見たな」
黒い怪物がうめくように云って、組みしかれたまま、クネクネと身体を動かしたかと思うと、闇の中にパッと青い光が閃ひらめいて、バクッと物を裂くような音がした。
それと同時に、幽霊の胸から、真赤な血のりがポトポトと滴したたり落ちていた。彼は顔の前に垂れ下った長い髪の毛を振り乱して、ウーンとのけぞったが、そのまま縡こときれて、パッタリうしろに倒れてしまった。
組みしかれていた黒い怪物は、引裂かれた黒布を元通り顔の前に垂れると、ゆっくりと起き上った。右手には今火を吐いたばかりの小型のピストルを握っている。
「クッ、クッ、クッ……」
彼は又あの奇妙な笑い声を立てた。そして、可哀想な小池助手の死体を踏み越え、素早く竹藪の向うに姿を隠してしまった。
それと引違いに、反対の方角から、二人の小屋の者が、息せききって駈けつけて来た。小池助手の恐ろしい叫び声と銃声を聞きつけたからである。
彼等はそこに女幽霊の転がっているのを見た。不思議なことに、その幽霊の裾からは、二本の足がニューッと突き出していた。胸からは白衣びゃくえを染めて真赤な血が流れ出していた。
暫くは何が何だか分らず、呆然として立ちつくしていたが、やがて、一人がそれと気附いて、幽霊の長髪をかき分けて見た。
「オイ、これはさっきの探偵さんだぜ。幽霊に化けて曲者を待伏せしていたのかも知れない。アア、もう脈が止まっている。あいつにやられたんだ。あいつはピストルを持っているんだぜ」
二人は恐怖に耐えぬもののように、竹藪の重なり合った闇の中を見廻した。
「それは一体どうしたというのです」
見上げると、そこに宗像博士が立っていた。
「あなたのお連れの方が、曲者の為に撃たれたのです」
「エッ、小池君が?」
博士は咄嗟とっさにそれと察したのか、転がっている幽霊の側に跪ひざまずいた。
「オオ、小池君、この様子では、あいつを見つけて組みついて行ったんだね。そして、こんな目に会ってしまったんだね。
アア、もう駄目だ、心臓の真中をやられている。よしッ、小池君、この仇かたきはきっと取ってやるよ。君と木島君と二人の仇は俺が必ず討って見せるよ」
博士は両眼にキラキラと涙の玉を浮べて、小池助手の屍しかばねの前に静かに脱帽するのであった。
中村捜査係長が制服私服合せて十二名の部下を引連れ、三台の自動車を飛ばして駈けつけたのは、それから二十分程のちであった。
係長は宗像博士から委細を聞き取ると、敏速に兇賊逮捕の陣容を整えた。半数の警官は賊がテントを潜って逃走するのを防ぐ為に、小屋掛けの四方の見張りに立て、残る半数を二隊に分け、小屋の入口と出口とから、綿密な捜査をしながら中心地点に進ませることにした。
化物屋敷全体を薄暗くしている天井の黒布は、小屋の者に命じて、直ちに取りはずさせることにしたので、見る見る陰鬱な小屋の中が明るくなって行った。それにつれて、場内の魑魅魍魎は、昼間の化物となって、到る所に滑稽なむくろを曝さらしはじめた。
竹藪の迷路も、行き止りの袋小路が全部切り払われ、どこを通っても出口に達することができるようになった。警官隊と十数名の小屋の若い者とが、隊伍たいごを組んで、切り開かれた白昼の藪の間を進んで行った。
裏口から入った一隊は、無残人形の場面を、一つずつ綿密に捜索しながら、前進したが、天井の黒布が取り払われて見ると、どの場面もいたずらに毒々しく醜怪なばかりで、凄味など殆んど感じられなかった。
裏口から三つ目の舞台は、例の轢死女の場面であったが、地中に身を潜めた生ける生首は、どこへ逃げ去ったのか、影もなく、その首の生えていた部分に、ポッカリと黒い穴があいていた。
「オイ、あの奥に何だかいるようだぜ」
一人の警官が同僚を顧みて囁いた。指さすのを見ると、そこには例の模造赤煉瓦のトンネルが真黒な口を開いているのだ。
天井から光が射すとは云っても、トンネルの中は真暗だし、その辺一体は、竹藪の茂みになっていて、何となく陰気である。
三人の警官、それに小屋の若者四人、七人の同勢が、手をつながんばかりにして、オズオズと柵を乗り越え、汽車の線路を伝って、転がっている人形の手や足を蹴ちらしながら、トンネルの口に向って近よって行った。
「このトンネルは一間ばかりで行き止りになっているんですから、どこにも逃げ道はありやしませんよ」
若者が警官達に囁く。
やがて、人々はトンネルの前二間程に近づくと、暗い穴の中を覗き込んだ。
トンネルの内部は、すっかり黒い塗料で塗りつぶしてあるのだが、その行き当りの壁の中に、細い二つの目が光っていた。よく見ると、壁と同じ色をした影法師のようなものが、そこに突立っているのだ。
それを見ると、人々は思わずギョッと立止った。
「危いッ、ピストルを持っているぞッ」
人々のひるむ前に、黒い怪物は、浮き出すように前進して来た。右手には油断なくピストルを構えながら、クックックッと例の不気味な笑い声を立てながら。
トンネルを出ると、大胆不敵にも、ジリジリと警官の方へにじり寄って来る。七人の方が却って押され気味である。
怪物の足が線路を越えた。今度は柵の方へと、蟹かにのように横歩きを始める。ピストルは七人の真中に狙いを定めたままだ。
アッ、柵を越えた。越えたかと思うと、クルリとうしろ向きになった。そして、通路を人なき方かたへと、矢のように走り出した。
「ウヌ、待てッ」
「逃がすもんか、畜生」
かけ声だけは勇ましく、逃げる一人を追う七人、すさまじい追っ駈けが始まった。
「クックックッ……」
怪物は走りながらも、まだ嘲笑をやめなかった。
無残人形の幾場面を過ぎて、怪物は両側を黒布で張った細い通路へ飛び込んで行った。その正面には、例の鏡の部屋があるのだ。
その通路も、天井の蔽いが取去ってあるので、怪物の躍るような黒い姿がよく見える。彼はそこを一息に駈け抜けて、行き当りの黒板塀のドアを引きあけ、とうとう鏡の部屋に辷り込んだ。
七人の追手は忽ちドアの前に殺到したが、そこで又立ちすくんでしまった。ドアが細目に開いて、怪物の白い目がじっとこちらを睨みつけていたからだ。イヤ、目だけではない。ピストルの筒口が、今にも火を吐くぞとばかり、不気味に覗いていたからだ。
「向うの出口から廻って、はさみ撃ちにしたらどうでしょう」
一人の若者が囁き声で、妙案を持出した。
「よし、それじゃ、君は向うへ廻って、あちらにいる警官に、この事を伝えてくれ。出口の方を固めてくれるようにね」
これも惶しい囁き声の指図だ。若者は通路の壁を押し破って、鏡の部屋のうしろ側へ飛び出して行った。
愈々怪物は袋の鼠となった。彼は今、何も知らないで、戸の隙間から警官達を威嚇いかくしているけれど、やがて背後の入口から、別の警官隊が殺到するのだ。腹背ふくはいに敵を受けては、いかな兇賊も運の尽きに違いない。若し万一、どうかしてこの鏡の部屋は逃げ出すことが出来たとしても、小屋の外には六人の警官が見張りをしているばかりか、事件を聞きつけて集った弥次馬やじうまの大群が、テントのまわりをグルッと遠巻きにして見物しているのだ。その中を、どう逃げ終おわせることが出来るものか。
あとに残った六人の追手は、じっとピストルの筒口を睨みつけながら、息を殺して時の来るのを待ち構えていた。
「クックックッ……」怪物は又笑い出した。アア、何も知らないで、呑気らしく笑っている。
五秒、十秒、十五秒……追手達の腋の下から冷い汗がジリジリと流れた。突然、鏡の部屋の中に物音がした。何者かが歩き廻っているのだ。咳払せきばらいの音が聞える。
しかし、賊のピストルはこちらを狙ったまま、少しも動かない。どうしたのかしら。オオ、今にも格闘が始まるのではないか。敵も味方も鏡に映る千人の姿となって、何千人の大乱闘が演じられるのではないか。
手に汗を握って待ち構える人々の前に、鏡の部屋のドアが、静かに開き始めた。オヤッ、おかしいぞ。怪物はやっぱりピストルを構えたままだ。では、早くも計略を悟って、逆にあいつの方から打って出る積りかしら。
人々はギョッとして、思わずあとじさりを始めた。
ドアは段々大きく開いて行く。黒い怪物め、愈々いよいよ飛び出して来るんだな。逃げ腰になって、じっと見つめている一同の前に、遂にドアはすっかり開け放された。
すると、オオ、これはどうした事だ。そこに立っていたのは、敵ではなくて味方であった。味方も味方、当の怪物の発見者の宗像博士その人であった。
「オヤ、あなた方何をしているんです。あいつはどうしたのですか」
博士の言葉に、警官達は開いた口が塞ふさがらなかった。
「オオ、宗像先生、あなたはその部屋で、曲者をごらんにならなかったのですか。つい今し方まで、そのドアの隙間から、我々にピストルを突きつけていたんですぜ」
「僕もここにあいつが隠れていると聞いたものだから、はさみ撃ちにする積りで、入って来たのだが、入って見ると誰もいないのです。ただ、このピストルがドアの把手にぶら下っていたばかりでね」
博士はそういいながら、紐で結びつけたピストルを取り上げて、一同に示した。
「あなた方は、このピストルの筒口が覗いているのを見て、あいつ自身が、ここにいるのだという錯覚を起していたのですよ。あいつはピストルをここにぶら下げて、丁度あなた方の方に筒口が向くようにして置いて、素早く逃げてしまったのです」
人々は余りのことに、それに答える力もなく、呆然として博士の顔を見つめていた。
「しかし、おかしい。僕はもうさい前から、向うの戸口の外にいたんですが、誰もここから逃げ出すものを見かけなかった。ひょっとしたら、鏡の壁に何か抜け穴でも出来ているのじゃないかと思うくらいです」
怪物の奇怪な消失に、又改めて大捜索が繰返された。人の隠れそうな場所は、悉く打毀うちこわし、迷路の竹藪もすっかり倒してしまって、隅から隅まで、何度となく探し廻った。
しかし、遂に黒い怪物は、どこにも姿を現わさなかった。と云って、テントの外へ逃げ出さなかったことは、見張りの六人の警官をはじめ、まわりを囲む群集が、何よりの証人であった。
宗像博士の提案によって、鏡の部屋が取り毀され、大鏡が一枚一枚壁からはずされて行った。しかし、そのあとには、どんな抜け道も、どんな隠れ場所も発見されなかった。
あの不気味な鏡の部屋は、一人を千人にして見せるばかりでなくて、人間を全く影も形もないように吸い取ってしまう魔力を持っていたのであろうか。
人々は、六角の鏡の部屋が、奇術師の魔法の箱のように、そこへ入った人間を、先ず粉々に打ちくだき、その目にも見えぬ破片を、六方から、サーッと吸い取って行く光景を幻想して、ゾーッと肌寒くなる思いをしたのであった。
その執拗残酷な復讐鬼の正体は少しも分らなかった。不思議なことに、復讐を受けている川手氏自身さえ、全く見当がつかないと云っていた。
ただ分っているのは、そいつが世にも恐ろしい三重渦巻の指紋を持っていることであった。三つの渦巻が三角形に並んで、まるでお化けが笑っているように見える三重渦状紋。悪魔は到るところにその怪指紋を残して行った。殊に復讐行為の直前には、殺人の予告ででもあるかのように、必ず人々の前にそのお化指紋が現われるのであった。
復讐鬼は魔術師のような不思議な手段によって、川手氏の二令嬢を誘拐し、惨殺し、しかもその美しい死体を、衆人の目の前に曝しものとした。妹娘雪子さんは、衛生展覧会の人体模型陳列室に、その生けるが如きむくろを曝す憂うき目めを見、姉娘の妙子さんは、場所もあろうにお化け大会の残虐場面の生人形と置き換えられ、竹藪に囲まれた一つ家の場面に、胸を血だらけにして倒れていた。
そして、この次は、一家の最後の人、川手氏自身の番であった。復讐鬼の真の目的は、川手氏にあったことは云うまでもない。先ずその二令嬢を惨殺したのは、川手氏を思うさま苦しめ悲しませ、復讐を一層効果的にする為であったことは、復讐鬼の嘗かつての脅迫状によっても明かであった。
川手氏は愛嬢を失った悲歎と、我身に迫る死の恐怖の為、流石の実業界の英雄も、まるで思考力を失ったかのように、為なすところを知らぬのであった。殆んど人任せで妙子さんの葬儀を終ると、奥まった一間にとじこもり、人を避けて物思いに耽ふけっていた。
葬儀の翌早朝、宗像博士の来訪が取次がれた。他の来客は悉く断っているのだけれど、博士だけには会わぬ訳には行かぬ。今はこの聡明な私立探偵だけが頼りなのだ。妙子の場合は、明かに探偵の失敗であったが、忽ちに悪魔のトリックを看破し、死体のありかを探し当てたのは、宗像博士その人ではなかったか。この人をおいて、あの魔術師のような復讐鬼に対抗し得る者が、外にあろうとは考えられないのだ。
応接間に通されると、宗像博士は鄭重ていちょうに悔みを述べ、彼自身の失策を心から詫びるのであった。
「この申訳には、第三の復讐を未然に防ぐ為に、僕の全力を尽したいと思います。こうなっては、もう職業としてではありません。あなたの依頼がなくても、僕の名誉の為に戦わなければなりません。それに、僕としては、可愛い二人の助手をあいつの為に奪われているのですから、彼らの復讐の為にも、今度こそあの怪指紋の主を捉えないでは、僕自身に申訳がないのです」
「有難う、よく云って下すった。わしは二人の娘をなくし、あなたは二人の助手を奪われたのですねえ。お互に、同じ被害者だ。費用の点はいくらかかっても僕が負担しますから、思う存分にあなたの智慧ちえを働かして下さい。
二人きりの娘が二人とも、あんなことになってしまって、わしはこの世に何の楽しみもなくなったのです。もう事業にも興味はありません。今もそれを考えていたところですが、これを機会に事業界からも引退したいと思うのです。そして、二人の娘の菩提ぼだいを弔とむらって、余生を送りたいと思っています。
ですから、娘達の敵かたきを取るためには、わしの全財産を擲なげうっても惜しくはありません。君に一切をお任せしますから、警視庁の中村君とも聯絡れんらくを取って、出来るかぎりの手段をつくして下さい」
「お察しいたします。おっしゃるまでもなく、僕は当分の間、外の仕事は放って置いて、この事件に全力をつくす考えです。それについて、一つ御相談があるのですが」
宗像博士はそう云って、一膝前に乗り出すと、殆んど囁き声になって、
「川手さん。今さし当って予防しなければならないのは、第三の復讐です。つまりあなたに対する危害です。それがあいつの最終最大の目的であることは分り切っているのですからね。
こうしてお話ししている内にも、魔法使のようなあいつの魔手は、我々の身辺に迫っているかも知れません。これから僕達は、昼も夜も絶間たえまなく、あいつに監視されているものとして、行動しなければならないのです。
で、僕は第三の復讐を予防する手段について、今朝から一日頭を絞ったのですが、結局あなたに身を隠して頂く以外に、安全な方法がないという結論に達したのです。
身を隠すなんていうことは、あなたもお好みにならぬでしょうし、僕にしても採とりたくない手段ですが、この場合に限って、そうでもするより安全な道はないのです。なにしろ、相手が何者であるか、どこにいるのか、少しも分っていないのですからね。見えぬ敵と戦うためには、こちらも身を隠すほかはないのです。
そうして、あなたに安全な場所へ移って頂けば、僕は思う存分働けるというものです。あなたの保護と賊の逮捕という二重の仕事に、力をわける必要がなくなって、ただ復讐者の捜索に全力を注ぐことが出来る訳ですからね。
それについて、一つ考えていることがあるのですが」
博士はそこまで云って、ジロジロと辺りを見廻し、椅子を引き寄せて、川手氏に近づき、その耳に口をつけんばかりにして、一層声を低め、殆んど聞き取れぬ程に囁くのであった。
「あなたの替玉かえだまを作るのですよ。影武者ですね、丁度持って来いの人物があるのです。相当の報酬を出して下されば、命を的まとに引受けてもいいという男があるのです。柔道三段という豪ごうのものですよ。その男をこのお邸へ、あなたの身代りに置いて、謂わば囮おとりにする訳です。そして、近づいて来る賊を待伏せしようというのです」
「そんな男が本当にあるのですか」
川手氏は少し大人げないという面持で、気の進まぬ調子であった。
「不思議とあなたにそっくりなのです。マア一度会ってごらんなされば分ります。うまくやれば召使の方達も、替玉とは気がつかないかも知れません」
「それにしても、わしが身を隠す場所というのが、第一、問題じゃありませんか」
「イヤ、それも心当りがあるのです。山梨県の片田舎に、今丁度ちょうど売りに出ている妙な一軒家があるのです。ある守銭奴しゅせんどのような老人が、盗難を恐れる余り、そんな妙な家を建てたのですが、全体が土蔵造りで、窓にも縁側にもすっかり鉄板張りの戸がついていて、その上に城郭のような高い土塀を囲らし、土塀の外にはちょっとした堀があって、跳橋はねばしまで懸っているという、まるで戦国時代の土豪の邸とでもいった用心深い建物なのです。
僕はそこの主人がなくなる前、ある事件で知合いになって、その城のような邸に泊ったこともあるのですが、場所といい、建物といい、あなたの一時の隠れ場所には持って来いなのです。
現在は、その地方の百姓の老夫婦が留守番をしているのですが、その人達も僕はよく知っていますから、売買のことはいずれゆっくり取極とりきめるとして、今日からでもそこへ落ちつくことが出来ます。家具調度も揃っていますし、マア、宿に泊るようなつもりで、鞄かばん一つで行けばいい訳です。
実はこういうことをお勧めするのも、その城のような家があり、あなたの替玉になる男を知っていたから思いついたので、こんなお誂あつらえ向きな話は、滅多にあるものじゃないと思うのです」
「一つ、考えて見ましょう。何だかそれ程にして逃げ隠れするのも、大人げないような気もしますからねえ」
川手氏はまだ乗気にはなれない様子であった。一々記さなかったけれど、これらの会話は凡すべて、用心深く、お互の耳から耳へ囁き交されたのである。
川手氏が考え込んでいる所へ、若い女中が二度目のお茶を運んで来た。漆器しっきの蓋のついた大型の煎茶せんちゃ茶碗である。
宗像博士は、それを受取って、蓋を取ろうとしたが、何を思ったのか、ふと手を止めて、その黒い漆器の表面を、異様に見つめるのであった。それから、
「ちょっと」
と云って、川手氏の茶碗に手をのばし、その蓋を取って、窓の光線にかざしながら、つくづくと眺めた上、今度はポケットから例の拡大鏡を取出して、二つの蓋の表面を仔細に点検しはじめるのであった。
「その蓋に何かあるのですか」
川手氏は早くも恐ろしい予感に脅えて、サッと顔色を変えながら、上ずった声で訊ねた。
「あの指紋です。ごらんなさい」
恐ろしいけれど、見ぬ訳には行かぬ。川手氏は顔をよせて、レンズを覗き込んだ。アア、お化けが笑っている。まぎれもない三重渦状紋が、二つの蓋の表面に一つずつ、はっきりと浮き上っているではないか。
「態々わざわざ捺したのです。そして、我々を嘲笑っているのです」
二人はあきれた様に顔を見合せた。ア、何という素早い奴だ。妙子さんの葬儀がすむか済まぬに、もう第三の復讐の予告である。ぐずぐずしている訳には行かぬ。悪魔の触手は、既にして川手氏の身辺に迫っているのだ。
直ちにお茶を運んだ女中が、取調べられたのは云うまでもない。宗像博士は自身台所へ出向いて行って、そこにいる召使達に一人一人質問した。だが、いつの間に、誰がそんな指紋をつけたのか、まるで見当もつかなかった。念のために召使達残らずの指紋を取って見たけれど、無論三重の渦巻などは一つもなかった。
問題の茶碗は、昨夜すっかり拭き清めて茶箪笥ちゃだんすに入れて置いたのを、今取出してそのまま応接室へ運んだというのだから、賊は昨夜の内に台所へ忍び込んで、茶箪笥をあけ、指紋を捺して逃げ去ったものとしか考えられなかった。しかし戸締りには少しも異状はなく、どこからどうして忍び込んだかということは、少しも分らなかった。屋外にも賊の足跡らしいものは全く発見されなかった。
「宗像さん、やはりお勧めに従って、一時この家を去ることにしましょう。臆病のようですが、こんなものを見せつけられてはもう一刻もここにいる気がしません。それに、この家にはなくなった娘達の思い出がこもっていて、いつまでも悲しみを忘れることが出来まいと思いますから、旁かたがたあなたのおっしゃるようにする決心をしました」
川手氏は遂に我がを折った。三重渦巻のお化けの恐怖は、世間を知りつくした五十男を、まるで子供のように臆病にしてしまったのである。
「実を云いますと、無理にもこの計画を実行して頂く決心で、ちゃんとその手配をして置いたのですが、御同意下さって、僕も安堵あんどしました。あなたさえ安全な場所へお匿かくまいすれば、僕は思う存分あいつと一騎討が出来るというものです。あなたの替玉になる男も、実は用意をして、ある場所に待たせてあるのです。電話さえかければ、すぐにもやって来ることになっています」
博士はひそひそと囁いて、部屋の隅の卓上電話に近づくと、ある番号を呼出して、第三者には少しもそれと分らぬ話し方で、簡単に用件を済ませた。
それから二十分程もすると、書生の案内で、その応接間へ、異様な人物が入って来た。ソフトをまぶかく冠ったまま、インバネスを着たまま、しかもその襟えりを立てて顔を隠すようにしながら、ツカツカと部屋の中へ入って来たのだ。
予め玄関番の書生に、こういう人が来るから、怪しまないで案内するようにといいふくめてあったので、この異様な身なりのまま、無事に玄関を通過することが出来たのである。
書生がドアを閉めて出て行くと、宗像博士は、主人から渡されていた鍵で、唯一の入口へ締りをした。それから、窓という窓のブラインドをおろし、御丁寧にカーテンまで閉めてしまった。そして、薄暗くなった部屋に電燈をつけてから、異様な人物に何か合図をした。
すると、その人物が、いきなり外套がいとうを脱ぎ、帽子をとって、川手氏に向い、
「初めてお目にかかります。よろしく」
と頭を下げた。
川手氏は思わず椅子から立上って、あっけにとられたように、その人物を眺めた。アア、これはどうしたことだ。突然目の前に大きな姿見が現われたとしか考えられなかった。背恰好といい、容貌といい、髪の分け方、口髭の大きさ、着物から羽織から、羽織の紐や襦袢じゅばんの襟の色までも、川手氏とそっくりそのままの人物が、眼前一二尺のところに佇んで、ニコニコ笑いかけているのだ。
「ハハハ……、如何いかがです。これなら申分ないでしょう。僕でさえどちらが本当の川手さんだか迷うくらいですからね」
宗像博士は双生児ふたごのような二人を見比べて、得意らしく笑うのであった。
「この人は近藤こんどうという僕の知合のものです。さっきも申上げた通り、柔道三段の豪ごうのもので、こういう冒険が何よりも好きな男です。
ところで近藤君、お礼のことは僕が引受けて、十分に差上げるから、一つうまくやってくれ給え。つまり今日から君が、川手家の主人なのだ。兼ねて打合せて置いた通り奥の間にとじこもって、一切客に会わないことにするんだ。召使いもなるべく近づけないように。いくら似ていると云っても、よく見ればどこか違ったところがあるんだから、召使にはすぐ分るからね。
マア、お嬢さんがあんなことになられたので、悲しみの余り憂鬱症に罹かかったという体ていにするんだね。そして、昼間も部屋を薄暗くして、女中などにも正面から顔を見合わさないように、その都度何かで顔を隠す工夫をするんだ。
無論そんなことが永続ながつづきする筈はないから、いずれ一両日のうちに僕が来て、召使達に事情を話し、よく呑み込ませる積りだが、それまでのところを、一つうまくやってくれ給え」
博士が例のひそひそ声で注意を与えると、新しい川手氏は、呑み込んでいるよと云わぬばかりに、胸を叩いて答えた。
「マア、私の腕前を見ていて下さい。青年時代には舞台に立ったこともある男です。お芝居はお手のものですよ」
「これは不思議だ。声までわしとそっくりじゃありませんか。これなら女中共だって、なかなか見分けはつきませんよ」
川手氏はあきれたように、つくづくと相手の顔を見守るのであった。
間もなく、応接間の窓のブラインドやドアが元のように開かれ、宗像博士と、ソフト帽と外套がいとうの襟で顔を隠した異様の人物とは、偽物の川手氏をあとに残して、さりげなく川手邸を辞去した。ソフト帽と外套の男が、替玉と入れ替わった本物の川手氏であったことは云うまでもない。同氏は咄嗟に取纒めた重要書類と当座の着換えを詰めたスーツ・ケースを、外套の袖に隠すようにして下げていた。
二人は書生に送られて、玄関を出ると、門前に待たせてあった、宗像博士の自動車に乗り込んだ。
「丸の内の大平たいへいビルまで」
博士の指図に従って車は動き出した。
「近藤さん、サア、これからが大変ですよ。色々意外なこともあるでしょうが、驚いてはいけません。一切僕にお任せ下さるんですよ」
博士は川手氏を近藤さんと呼ぶのだ。
「お任せします。だが、山梨県へ行くのに、丸の内というのは、どうした訳ですか。汽車は新宿駅からでしょう」
と川手氏が不審を起して訊ねると、博士はいきなり口の前に指を立てて「シーッ」と制しながら、
「だから、お任せ下さいというのです。これから妙なことが幾つも起る筈ですから、びっくりなさらないように。みんなあなたを賊の目から完全に隠す為めの手段なのですからね。これから目的地へ着くまでに、探偵という商売がどんなものだか、あなたにもお分りになるでしょう」
と、何か意味ありげに囁くのであった。
それから二十分程のち、車は大平ビルディングの表玄関に横着けになった。博士は運転手に賃銀を支払うと、外套で顔を隠した川手氏の手を引くようにして、いきなりビルディングの中へ入って行ったが、エレヴェーターに乗ろうともせず、階段を登ろうともせず、ただ廊下をグルグル廻り歩いた末、いつの間にか建物の裏口へ出てしまった。
見ると、そこの道路に大型の自動車が一台、人待ち顔に停車している。博士は川手氏を引っぱりながら、大急ぎでその自動車の中に飛込んだ。
「怪しい奴は見なかったか」
「別にそんなものはいないようです」
運転手が振向きもせず答える。
「よし、それじゃ云いつけて置いた通りにするんだ」
車は静かに走り出した。
博士は手早く、窓のブラインドをおろし、運転席との境のガラス戸を閉め切って、さて、面喰っている川手氏の方に向き直った。
「近藤さん、これが尾行をまく、ごく初歩の手段ですよ。犯罪者が用いる籠抜かごぬけというのはこれですが、探偵も犯罪者も、時には同じ手を使うものですよ。
こうして置けば、仮令たとえお宅から我々をつけて来た者があったとしても、或は又、あの自動車の運転手が敵の廻しものであったとしても、大丈夫です。
しかし、普通一般の悪人を相手なればこれで十分ですが、なにしろあいつは神変自在の魔術師ですからね。まだまだ手段を施さなければなりません。今度は変装です。この運転手は僕の部下も同様のものですから、先ず心配はありません。この車の中で変装をするのです。探偵というものは、走っている自動車の中で、姿を変えなければならない場合が往々あるのですよ」
博士は小声に説明しながら、予め車内に置いてあった大型のスーツ・ケースを開いて、先ず髭剃そりの道具を取り出した。
「近藤さん、あなたの口髭を剃り落すのです。つまり川手さんの面影を出来るだけなくしてしまおうという訳です。構いませんか。では失礼して、お顔に手を当てますよ。サア、もっとこちらを向いて下さい」
川手氏は博士の用意周到なやり口に、感に堪えて、されるがままになっていた。あの恐ろしい復讐鬼の目を逃れる為とあれば、口髭を落すくらい、何の惜しいことがあろう。
車は予め命じられていたと見えて、徐行しながら、麹町区内の屋敷町をグルグルと廻っていた。
左右と後部の窓のブラインドがおろしてあるので、通行者から車内を覗かれる心配はない。安全至極な移動密室である。
博士はチューブから石鹸液を絞り出して、川手氏の鼻の下を泡だらけにしながら、手際よく剃刀かみそりを使って、見る見る髭を剃り落してしまい、剃りあとにメンソレータムを塗ることさえ忘れなかった。
「ウフフフ……、大変若返りましたよ。サア、これでよし、今度は僕の番です」
「エッ、あなたもその髭を剃るのですか。惜しいじゃありませんか。君まで何もそんなことをしなくっても」
川手氏はびっくりして、博士の立派な三角型の顎髯を見た。この特徴のある美髯びぜんをなくしては、宗像博士の威厳にも関するではないか。
「ところが、この髯は一目で僕という事が分りますからね。いくら変装をしても、髯があっちゃ何にもなりません。
しかし、剃り落すのじゃありません。剃らなくてもいいのです。これは僕の取って置きの秘密ですが、この際ですから、あなたにだけ明しましょう。ごらんなさい、これです」
云うかと見ると、博士は揉上もみあげのところを指でつまんで、まるで顔の皮を剥ぎでもするように、いきなりメリメリと引きむしり始めた。すると、驚くべし、あの立派な三角型の美髯が、見る見る顔を離れて行き、そのあとに滑なめらかな頬が現われた。次には口髭に爪を当てると、それも美しく剥がれてしまった。
「つけ髯とは見えなかったでしょう。これを作らせるのには随分苦心をしたものです。ある鬘師かつらしと僕との合作なんですがね。普通に註文したんでは、迚とてもこんな見事なものは出来ません。
この三角髯は、僕の謂わば迷彩なのですよ。無髯むぜんの探偵がつけ髯で変装するということは、よくありますが、こんな髯武者の男が、逆に無髯の人物に変装出来るなんて、ちょっと考え及ばないでしょう。僕はそこへ目をつけて、逆手を用いることにしたのです。数年前から、態わざと目につき易いこんな髯を貯えたと見せかけ、宗像といえばすぐに三角髯を聯想するように、世間の目を慣らして置いて、実はその逆の効果を狙った訳です。ハハハ……、探偵というものはいろいろ人知れぬ苦労をするものですよ」
川手氏は益々あっけにとられてしまった。なる程その道によっては、外部から想像も出来ない苦心のあるものだと、感嘆しないではいられなかった。
博士は十年も若返ったような、のっぺりとした顔に微笑を湛たたえながら、今度はスーツ・ケースの中から、変装用の衣服を取り出して、膝の前に拡げた。
「近藤さん、これがあなたの分です。ここで着更えをして下さい。あなたは印半纒しるしばんてんの職人になるのですよ。僕はその親分の請負師うけおいしという訳です」
川手氏の分は、古い印半纒に紺の股引ももひき、破れたソフト帽子まで揃っている。博士の分は、茶色の古い背広に、廉手やすでなニッカーボッカー、模様入りの長靴下、編上靴、ソフト帽などで、いかさま土方の親分といった服装である。
二人は車の中で、窮屈な思いをしながら、どうやら着更えを済ませた。今まで身につけていた着物や外套は、一つに纒めてスーツ・ケースの中へおし込まれた。
「サア、これでよし。近藤君、これから口の利き方もちっと乱暴になるからね。悪く思っちゃいけないぜ」
親分が云い渡すと、子分の川手氏は、急には答える言葉も見つからぬ様子で、破れソフトの下から、目をパチパチさせるばかりであった。
「もういいから、東京駅へ直行してくれ給え」
博士が境のガラス戸を開けて、運転手に声をかけた。車は忽ち方向を変えて、矢のように走り出す。
やがて、駅に着くと、二人は銘々のスーツ・ケースを下げて、車を降り、遠方へ出稼ぎに行く職人といった体で、構内へ入って行った。
博士は川手氏を待たせて置いて、三等切符売場の窓口に行き、沼津ぬまづまでの切符を二枚買った。
「オヤ、こりゃ沼津行きじゃありませんか。山梨県じゃなかったのですか」
川手氏は切符を受け取って、けげん顔に訊ねる。
「シッ、シッ、何も訊かないという約束じゃないか。サア、丁度発車するところだ。急ごうぜ」
博士は先に立って、改札口へ走り出した。
発車間際の下関しものせき行き普通列車に間に合って、二人は後部三等車の片隅に、つつましく肩を並べて腰かけた。
ゴットンゴットン各駅に停車して、横浜よこはまへついたのは、もう正午に近い頃であった。
「この次の駅で、少し危い芸当をやりますからね。足もとに気をつけて下さいよ」
博士は川手氏の耳に口を寄せて囁いた。
やがて保土ほどヶ谷や。だが停車しても博士は別に立上ろうとするでもない。
「ここですか」
川手氏が気遣わしげに訊ねると、博士は目顔で肯うなずいて、平然としている。一体どんな芸当をしようというのだろう。
車掌の呼笛ふえが鳴った。ガクンと動揺して汽車は動き始めた。
「サア、降りるんです」
矢庭に立上った博士が川手氏の手を取って、後部のブリッジへ走った。そして、もう速力を出し始めている車上から、先ずスーツ・ケースを投げ出して置いて、サッとプラット・フォームへ飛び降りた。川手氏も手を引かれたままそれに続く。二人とも足がもつれて、危あやうく転がるところであった。
「一体これはどうした訳です」
「イヤ、驚かせてすみませんでしたね。これも尾行をまく一つの手なんですよ。まさかここまであいつが尾行していようとは考えられませんが、ああいう敵に対しては、無駄と思われる程念を入れなければなりません。
こうして置いて、今度は東京の方へ逆行するんです。若しあの汽車に我々の敵が乗っていたとすれば、まんまと一駅乗り越す訳ですから、いくらくやしがっても、もう我々のあとをつけることは出来ません。オオ、丁度向うから上り列車が入って来たようです。向うへ渡りましょう。ナアニ、切符は中で車掌に云えばいいんですよ」
ガランとしたプラット・フォーム。あたりに聞く人もないので、博士は普通の口を利いた。
それから反対側のフォームに渡り、上り列車に乗って、二駅引返すと東神奈川ひがしかながわである。二人はそこで下車して、今度は八王子はちおうじへの線に乗替え、八王子で再び目的の中央線に乗替えた。つまり、東海道線に乗ったと見せかけ、桜木町八王子線の聯絡を利用して、まんまと中央線に方向転換をしたのである。その大迂回だいうかいの為めに、乗替えの度に時間をとり、甲府こうふへついた頃にはもう日が暮れかけていた。
「サア、やがてN駅です。今度こそ思い切った放れ業を演じなければなりませんよ。しかし、決して危険なことはありません。N駅の少し手前で汽車が急勾配きゅうこうばいにさしかかって、速力をウンとゆるめる場所があります。僕らはそこで土手の下へ飛び降りる予定なのです。これが最後の冒険ですよ。
何もそれ程にしなくてもとお思いでしょうが、必ずしもあいつの尾行を恐れるばかりじゃありません。いくら変装をしていても、あなたはただ口髭がなくなっただけですからね。知っている人が見れば疑います。そして、どこの駅で降りたかということを記憶していて、人に話せば、それがどんなことで敵の耳に入らないとも限りません。
当り前なれば、N駅で下車するのですが、丁度そのN駅に我々の知人が居合わさないと、どうして断言出来ましょう。中途で飛び降りるというのは、必ずしも無駄な用心ではないのですよ。それに汽車の速度が決して危険がないまでににぶることが、ちゃんと確かめてあるのですから、少しも心配は要りません」
博士は川手氏の耳に口をつけて、こまごまと説明するのであった。幸い、日もとっぷりと暮れて、窓の外は真暗になっていた。冒険にはお誂え向きの時間である。
「ボツボツ、ブリッジへ出ていましょう。今に急勾配にさしかかりますから」
二人は何気なく、鞄を下げて、後部のブリッジへ忍び出た。幸い、車掌の姿もなく、こちらを注意している乗客も見当らなかった。
やがて、トンネルを知らせる短い汽笛が鳴り響くと、汽車の速度が目に見えて減じて行った。ボッボッボッという機関の音、黒煙に混って、火の粉が美しく空を飛んで行く。
「サア、ここです」
博士の声を合図に、二つのスーツ・ケースが闇の土手下へ投げ出された。つづいて博士の手が鉄棒を離れると見るや、まん丸な肉団となって、サーッと地上へ。印半纒の川手氏もおくれず、闇の中へ身を躍らせた。
線路の土手の草の上を、二つのスーツ・ケースと、二つの肉団とが、相前後して、コロコロと転がり落ち、下の畑に折り重なって倒れた。
暫らくして闇の中に低い声が聞えた。
「大丈夫ですか」
「大丈夫です。飛び降りなんて、存外訳のないものですね」
川手氏は数十年来経験せぬ冒険に、腕白わんぱく小僧の少年時代を思い出したのか、ひどく上機嫌であった。
「すぐその向うに細い村道そんどうがあるので、そこを二三丁行って、右に折れた山裾に、例の城郭が建っているのです」
二人は闇の中に、ムクムクと起き上り、塵ちりを払って、スーツ・ケースを下げると、畑を踏んで村道に出た。
雑木林を過ぎて、右に折れ、雑草を踏み分けて、こんもりとした森の中へ入って行くと、行手の木の間に、チロチロと燈火が見えた。
「あれですよ」
「なる程、山の中の一軒家ですね」
しばらく行くと、森の切目から、夜目にも白い土蔵づくりの不思議な建物が見え始めた。なるほど城郭である。屋根のつくりにも、何かしら天守閣てんしゅかくを思い出させるようなところがある、高い土塀も見えて来た。なお近づくと、土塀の一ヶ所に、いかめしい門があって、その前に堀の跳橋はねばしが吊り上げられているのが、ぼんやりと、まるで夢の中の不思議な城門のように眺められた。
「変った建物ですね」
「お気に召しましたか」
二人はそんな冗談を云い交して、低い笑い声を立てた。
その城郭のような一軒家に到着すると、川手氏は先ず、広い邸にたった二人で留守番をしている老人夫婦に引合わされた。夫婦とも見た目こそ頑丈がんじょうな老人であったが、気だては至極淳樸じゅんぼくな田舎者、これなら身の廻りの世話をして貰うにも気が置けないし、その上護衛の役も勤まると、川手氏も大気に入りであった。
同行した宗像博士は、一晩そこに泊って、川手氏の気持の落ちつくのを見届け、老人夫婦にその世話を懇ねんごろに頼んだ上、直ちに東京に引返した。復讐鬼は東京にいるのだ。そして、今頃は影武者とも知らず、贋にせ川手氏の身辺に悪魔の触手を伸ばしているに違いない。博士は、その見えざる敵と、愈々最後の勝負を決するために、一日もぐずぐずしている訳には行かなかった。
川手氏が城郭の不思議な掛人かかりうどとなってから、四五日は何事もなく経過した。陽春の山住ずまいは憂うれいの身にも快かった。土蔵造りの白壁も明るく、それを取りまく雑木林の枝々には、黄ばんだ若芽のふくらみも暖かく、吊橋の下の小川は軽やかにせせらぎ、樹間に呼び交う鳥の声も、浮世離れてのどかであった。
三度の食膳には、老夫婦が心尽しの、新鮮な山の珍味が列べられ、退屈すれば、うらうらと日ざしの暖かい庭の散歩、夜ともなれば、老夫婦の語る山里の物珍らしい物語、忘れようとて忘れられぬ悲しみを持つ川手氏も、環境の激変に心もなごみ、時には、何か保養の旅にでも出ているような気分になることもあった。
ところが、山住いの物珍らしさに、だんだん慣れて来るにつれて、川手氏は身辺に何となく気がかりな空気を感じ始めた。あれ程の用心をしたのだから、復讐鬼がこの山中まで追駈けて来るということは、全く考えなかった。その点はすっかり安心し切っていたのだけれど、それとは別に、広い城郭住いの朝晩、何とはなしに怪談めいたゾクゾクするような雰囲気が、ひしひしと身にせまるのを覚え始めた。
最初それに気附いたのは、五日目の夜更けのことであった。ふと目を覚ますと、どこかでボソボソと人の話声はなしごえがしていた。天井の高い寒々とした十二畳の座敷、ここには電燈の設備がないので、石油の台ランプを使っているのだが、それも吹き消して寝しんについた、全くの暗闇である。
一間ひとま隔てて老夫婦の部屋があるので、彼らが老おいの寝覚めの物語でも交しているのかと想像したが、それにしては人声が遠すぎる。しかも二人ではなくて、三人四人の声が入り混っているように思われる。
何町四方人家のない山中、この城郭には自分を混ぜて三人しか人が住んではいないのに、そんな多人数の話声が聞えるというのはただ事でない。幻聴かしら、イヤイヤ、幻聴ではない。確かにどこかこの建物の中の遠くの方で、意味は少しも聞き取れぬが、ボソボソという話声がいつまでも続いている。五十男の川手氏も、それを聞いていると、ゾーッと水をあびせられたような怖れを感じないではいられなかった。
城郭には一階と二階を合せて、二十に近い部屋数がある。老人二人では迚も全部の掃除が出来ないので、入口に近い階下の五間いつま程を除いては、全く雨戸を閉め切って、誰も入らぬことにしているのだが、若しやその開あかずの部屋の奥の方に、何者かが深夜の会合をしているのではあるまいか。山賊共か。まさか今どきそんなものが、人里近いこの辺に棲んでいる筈もない。では、山の奥からさまよい出した谺こだまの精、老樹の精、沼の精、童話の国の魑魅魍魎の類たぐいであろうか。
闇と静寂と山中の一軒家という考えが、川手氏を子供のように臆病にしてしまった。しかし、頭から蒲団を被ってちぢこまるほどではない。彼は枕許の手燭てしょくに火をつけて、小用こように起き上った。
念のために廻り道して、一間隔てた老夫婦の部屋を覗いて見たが、二人は山慣れた健康者、夜半よなかに目を覚ますこともないと見え、グッスリ寝入っている。
広い冷い廊下を踏んで、ガランとした昔風の便所に入った。窓の外はすぐに大樹の茂みである。小障子を開けて空を見ると、星もない真暗闇、大樹の梢こずえがカサコソと動くのは、夜鳥やちょうか、それとも、川手氏などには馴染のない小動物が住んでいるのか。
そうしていると、心が澄んで、夜の静けさがしんしんと身にしみる。その静寂の中に、突然、実に突然、川手氏は人間の笑い声を聞いたのである。
丁度便所の壁の外の辺、女の、恐らくは若い女の忍び笑いの声であった。低いけれども、おかしくて耐らないというようにいつまで笑いつづける、まがう方かたなき女の笑い声であった。
川手氏はゾーッと背筋がしびれるように感じて、外へ出て調べて見る勇気もなく、そのまま寝室へ逃げ帰った。すると益々不気味なことには、手燭をかざして、急ぎ足に通り過ぎる廊下の闇で、スーッと何者かにすれ違ったのである。何か小さなものであった。しかし、人間には違いない。子供とすれば四つ五つの幼児である。それが、目にもとまらぬ素早さで、行手の闇から、足音も立てず、矢のように走って来て、川手氏の袖の下をくぐり、うしろの闇の中へ姿を消してしまったのだ。重ね重ねの怪異に、その夜はまんじりともせず、朝になるのを待って、老夫婦にその由よしを告げると、ひどく笑われて、山住いに慣れない人はよくそんなことを云うものだ。人の話声は、堀の小川のせせらぎを聞き誤ったのではないか。女の笑い声は、夜の鳥が鳴いたのであろう。廊下の小坊主は、気のせいでなければ、大方いたずら猿めが迷い込んでいたのであろうと、一向取合ってはくれなかった。
だが、怪異はそれで終った訳ではない。翌日は昼間から、不思議なことが起った。川手氏が老人達の部屋で暫らく話し込んで、自室に帰って見ると、床の間に置いたスーツ・ケースの位置が明かに変っていた。紫檀したんの大きな卓テーブルの上に置いてあった懐中時計が裏返しになっていた。同じ卓上の手帳が開かれていた。
一度なれば川手氏の思い違いということもあるだろうが、二度三度同じことが起った。今度は念の為めに、色々な品物の位置をよく記憶して置いて、暫らく部屋を開けて帰って見ると、ちゃんとその位置が変っている。もう思い違いではない。この城郭の奥の方には、老夫婦も知らぬ何者かが住んでいるのだ。そして、川手氏を驚かせようと、企んでいるのだ。
そんなにおっしゃるなら、御得心の行くように、邸中の雨戸をあけて家捜しをして見ましょうと、その翌日は、三人で広い邸内を二階も下もすっかり調べて見たが、別に怪しいこともなかった。どの部屋にも人の住んでいたような気配は見えぬのだ。
それごらんなさい。やっぱり猿かなんかのいたずらですよと、老夫婦は笑い話にしてしまったが、川手氏はどうも納得が行かなかった。何かしら身近に、人の匂においが感じられた。妖気とでもいうようなものが、ひしひしと身に迫るのを覚えた。
すると、その晩のことである。
川手氏は深夜また目が覚めて、どこからか漏もれて来る人の話声を聞いた。そして、前の晩と同じように、手燭をつけて小用に起きた。今夜もひょっとしたら、あの笑い声がするかも知れない。川手氏は覚悟をきめて耳を澄ましていた。今度こそ鳥の鳴き声か人間の声か聞き分けてやろう。
窓から覗いた空には、やっぱり星がなかった。そよとの風もない梢に、カサコソと不気味な音がしていた。
突然、アア、又してもあの笑い声だ、若い女が、袂たもとで口を蔽って、身体を曲げて、忍び笑いをしているような、あの笑い声だ。川手氏は目の前に、その若い女の白い顔が見えるような気がした。
今夜こそ正体を見現わさないでおくものか。かねて心に定めて置いた通り、川手氏は急いでそこを出ると、音のせぬように、廊下の端の雨戸の枢くるるをはずし、ソッと引き開けて、真暗な庭の声のしたと思われる箇所へ手燭をさしつけた。
だが、恐らくは今の間に逃げ失せてしまったのであろう。そこには一むらの南天が黒く押黙っているばかりで、人らしい物の影はなかった。
しかし、人の姿は見えなかったけれど、それよりももっと妙なものが、忽ち川手氏の注意を惹いた。というのは、その廊下の斜向うに、鈎かぎの手になった建物の大きな白壁が、夜目にも薄白く、目を圧するように浮上っているのだが、その白壁の表面にボーッと白く燐りんのような光がさしていたのである。
オヤ、何だろう。ギョッとして、よく見直すと、壁を塗り直した痕あとではない。たしかに何かの光である。直径二間にもあまる巨大な円を描いて、その部分だけが映画のように浮き上っている。
だが、怪異はそれだけではなかった。じっと見ていると、その丸い光のなかに、何かしら、無数の蛇でも這っているような、妙な黒い模様が、朦朧もうろうと見えて来るのだ。何百何千とも知れぬ蛇だ。イヤ、蛇ではない。何だか、えたいの知れぬ模様だ。どこかで見たような模様だぞ。どこで見たのかしら……。あまりに大きすぎてよく分からぬが…………
川手氏はその巨大な模様めいたものを見つめているうちに、心臓の鼓動がピッタリと止まってしまうほどの、はげしい驚きにうたれた。驚きというよりも恐れであった。ゲエッ、と吐き気を催すような深い恐怖であった。
無数の蛇の塊と見えたのは、何千何万倍に拡大された人間の指紋であることが分って来たからだ。しかも、オオ、どうしてあれを忘れよう。その巨大な指紋には、三つの渦巻があったではないか。二つは、まん丸く上部に並び、一つは、楕円形に下部に拡がっている。お化けの顔だ。一間四方のお化けが山中の一つ家の庭で、ニヤニヤと笑っているのだ。
川手氏は、訳のわからぬうめき声を立てながら、死にもの狂いに廊下を走った。
そして、老夫婦の部屋の障子を乱打しながら、狂気のようにその名を呼んだ。
それから、何事が起ったのかと、びっくりして飛び起きた二人に、事の次第を話して、庭を調べてくれるように頼んだ。
老人達は、又かというように、川手氏の幻覚を笑った。いくらなんでも、その三重渦巻の悪者とやらが、こんな山の中までやって来る筈がない。宗像先生があれ程用心に用心を重ねて、敵の目をくらましておしまいなすったのだから、決して決してその心配はない。旦那様は幻でもごらんなさったのでしょうと、相手にしないのである。
それでもと、頼むようにして、やっと庭を調べて貰ったが、二人の老人が提灯ちょうちんをつけて、例の白壁のところへ行って見た時には、もうそこには何の光りもなければ、巨大なお化け指紋など影も形もないのであった。
それではやっぱり幻を見たのかしら。怖い怖いと思っているところへ、あの笑い声を聞いたものだから、つい復讐魔を聯想れんそうして、何もない白壁の上に、あんな恐ろしい物の影を、我れと我が心に作り出したのかしら。
その晩は解き難い謎を残して、そのまま寝しんについたが、翌日はうらうらと暖かい日ざしを味方に、まさか真昼間怪しい奴が庭に隠れていることもあるまいと、川手氏は昨夜の謎を確めるために庭へ降りて行った。
太陽の光で、例の白壁の表面を調べて見たが、別に怪しい影もなく、それと見まがう亀裂ひびがある訳でもない。若しあれが幻燈の影だったとすれば、幻燈器械はあの辺に据えつけてあった筈と傍かたわらの木立の奥に目をやると、そこの小高くなった薄暗い空地に、ヒョッコリと新しい石碑が建っているのに気付いた。
オヤ、今まで度々庭を散歩したのに、ここにこんなものがあるのは、少しも知らなかった。変だなあ。あれはどうやら誰かの墓石らしいが、庭の真中に墓地があるなんて。
川手氏はいぶかしきまま、つい木立をかき分けて、そのじめじめした薄暗い中へ入って行った。近よって見ると、それはまだ磨いたばかりの真新しい墓石であることが分った。決して半月も一月も前からあるものではなく、昨日今日ここに運び込まれたものとしか見えぬのだ。
妙なことに、その墓石の表面には、戒名かいみょうのあるべき中央の部分が空白になっていて、その傍わきのところに、小さく「昭和十三年四月十三日歿ぼつ」とだけ、今鑿のみを入れたばかりのように、クッキリと鮮かに刻んであった。
待てよ。昭和十三年と云えば今年ではないか。四月といえば今月ではないか。そして、十三日といえば、アア、何ということだ。今日は十二日だから、十三日と云えば明日の日附ではないか。
川手氏は気でも狂ったのではないかと、我が目を疑った。幻覚ではない。決して読み違いではない。この通り確かに昭和十三年、四月、十三日と刻ほってある。態々わざわざ指を当てて、一字一字をさすって見たが、決して読み誤りではなかった。
一体これは何を意味するのだ。明日死ぬに違いない誰かの墓が、こうしてちゃんと用意されているのであろうか。だが、どんな重病人でも、いつ何日いくかに死ぬと予め分っているというのは変ではないか。死刑囚ででもない限り……、と考えている内に、川手氏は見る見る幽霊のように青ざめて行った。
若しかしたら、これは俺の墓じゃないのかしら。
あの深夜の笑い声といい、昨夜の白壁の怪指紋といい、幻視幻聴と思えばそうのようでもあるが、若しあれらが、何者かの計画的な悪戯いたずらであったとすれば……何者かといって、外に誰があんな妙な真似をするものか。三重渦巻の指紋の主だ! あいつが早くもこの隠れ家を探し当てて、奇怪な復讐の触手を伸ばしているのではあるまいか。そうとすれば、この墓石の謎の日附の意味も分って来る。「十三日」に「歿」する人は、外ならぬ俺自身なのだ。俺は明日中に、何らかの手段によって復讐魔の為めに惨殺されるのではないだろうか。俺は今、こうして自分自身の墓石を見せつけられているのではあるまいか。
川手氏はクラクラと眩暈めまいを感じて、今にも倒れそうになるのを、やっと我慢して、喘あえぎながら母屋に引返し、老夫婦にこの事を告げたので、二人のものは、又かと云わぬばかりに、目を見交しながら、兎も角急いで現場げんじょうへ行って見たが、案の定、そこには、いくら探しても新しい墓石なんて、影も形もないことが確められた。
まるで狐につままれたような話だけれど、川手氏自身も、あの大きな石碑が、かき消すようになくなっていることを認めない訳には行かなかった。
川手氏は我が耳我が目が恐ろしくなった。重なる心痛の為めに、視覚や聴覚に異状を来たしたのではあるまいか。イヤ、視覚聴覚ばかりではない、脳細胞そのものが病気に罹かかっているのではないだろうか。こんな山の中の独居ひとりいがいけないのかも知れぬ。このままここにいては、気が狂ってしまうような不安を感じた。
川手氏はそこで、老人に話して東京の宗像博士に、火急に相談したいことが出来たから、直ぐお出でを乞うという電報を打つことにした。そして博士の判断を求め、その結果によっては別の場所へ居を移そうと考えたのだ。
午後になって博士からの電報が到着した。明日行くという返事である。川手氏はその返電に力を得て、やっと気分を落ちつけることが出来た。そして、その晩寝しんにつくまでは別段の異変も起らなかったのだが……
しかし、川手氏は遂に宗像博士に会うことは出来なかった。博士が来なかったのではない。川手氏の方が城郭から姿を消してしまったのだ。その翌朝、老人夫婦は旦那様の蒲団ふとんが空っぽになっているのを発見した。早朝から庭でも散歩しているのかと、庭内を隈くまなく探したが、どこにも姿はなかった。座敷という座敷を見て廻ったが、川手氏は屋内にもいなかった。まるで神隠しにでも遭ったように、空気の中へ溶け込んででもしまったように、彼は、その日限り、つまり四月十三日限り、この世界から消失きえうせたのであった。
では川手氏は一体どうなったのか。その夜中やちゅう彼の身辺にどのような怪異が起ったのであるか。我々は暫らく川手氏の影身かげみに添って、世にも不思議な事の次第を観察しなければならぬ。
その夜更け、川手氏は例によって床の中でふと目を覚ました。何か人声らしいものを聞いたからである。また幻聴が起ったのかと、慄然りつぜんとして耳を澄ますと、つい障子の外の廊下の辺で、シクシクと人の泣いている声がする。さもさも悲しげに、いつまでも泣きつづけている。誰だと声をかけても、答えはなくて、ただ泣くばかりである。
川手氏はまた手燭に火をつけた。そして蒲団から起き上ると、ソッと障子を開いて、廊下の暗やみを覗いて見た。
すると、今夜は声ばかりではなくて姿があった。両手を目に当てて、啜すすり泣いている子供の姿がハッキリと眺められた。
まだ四五歳の上品な可愛らしい幼児だ。絹物らしい筒袖の着物と羽織、袖からは、明治時代に流行した、手首のところでボタンをかける白いネルのシャツが覗いている。男の癖くせに頭は少女のようなおかっぱだ。どうもこんな山里にいそうな子供ではない。それに風俗が異様に古めかしくて、現代の子供とも思われぬ。
川手氏は夢でも見ているような気持であった。変だぞ。俺はこの通りの子供を知っている。遠い遠い記憶の中に、丁度こんな服装をした子供の姿が焼きついている。誰だろう。ひょっとしたら幼年時代の遊び友達の面影おもかげではないかしら。
何か物懐かしい気持に支配されて、思わず廊下に立出でると、泣いている幼児の傍そばに近づいて行った。
「オイオイ、泣くんじゃない。いい子だ。いい子だ。お前今時分、一体どこから来たんだね」
おかっぱの頭を撫でてやると、子供は涙の一杯湛たまった目で川手氏を見上げ、廊下の奥の闇の中を指さした。
「お父ちゃんとお母ちゃんが……」
「エ、お父ちゃんとお母ちゃんが、どうかしたの?」
「あっちで、怖い小父おじちゃんに叩かれているの……」
子供はまたシクシクと泣き出しながら、川手氏の手を取って、助けでも求めるように、その方へ引っぱって行こうとする。
川手氏は夢に夢見る心地であった。真夜中、この山中の一つ家に、こんな可愛らしい子供が現われるさえあるに、その父と母とがこの邸の中で何者かに打擲ちょうちゃくされているなんて、常識を以もってしては全く信じ難い事柄であった。
アア、俺はまた幻を見ているのだ。いけない、いけない。しかし、いけないと思えば思う程、心は却かえって、いたいけな幼児の方へ引かれて行った。取られた手を振り放すことも出来ず、いつの間にか、その妖しい子供と一緒に、足は廊下の奥へ奥へと辿っていた。
子供は傍目もふらず闇の中へ進んで行く。川手氏さえ戸惑いしそうな複雑な邸内の間取りを、子供の癖にちゃんと諳そらんじているらしく、少しも躊躇しないで、廊下から座敷へ、座敷からまた別の廊下へと、グングン進んで行く。
川手氏は相手があまりに幼い子供なので、身の危険を感じはしなかった。それよりも、遠い昔、どこかで見たことのあるようなその子供が、なんとやら懐しく、可哀想にも思われて、取られた手を振り払うどころか、自ら進んで、子供の導くままにつき従って行くのであった。
「小父ちゃん、ここ」
子供が立止ったので、手燭でそこを照らして見ると、意外にも、その廊下の突当りに、井戸のような深い穴がポッカリと口を開いていた。床板が揚あげ蓋ぶたになっていて、その下にどうやら階段がついているらしい。地底の穴蔵への入口である。
不断ふだんの川手氏なれば、この不思議な地下道を見て、忽ち警戒心を起す筈であった。老人夫婦さえ知らぬ、こんな秘密の穴蔵へ、仮令たとえいたいけな子供の願いとはいえ、無謀に入って行くようなことはしなかった筈である。
だが、その時の川手氏は、この出来事を現実界のものとは考えていなかった。明治時代の風俗をした幼児と、夢の中で遊んでいるような漠然とした非現実の感じ、恐怖も恐怖とは受取れぬ無警戒な心持、謂わば空を漂っているような一種異様の朦朧とした心理状態で、つい子供のせがむままに、その穴蔵の階段を底へ底へと降りて行った。
階段を降りて狭い廊下のようなところを少し行くと、八畳敷程もある地下室に出た。床はコンクリート、四方はグルッと板壁に囲まれている。湿っぽい土の匂、押しつめられたように動かぬ空気、ジーンと耳鳴りのする死のような静けさ。手燭の蝋燭ろうそくの焔ほのおは、固体のように直立したまま、少しも揺れ動かぬ。
その手燭をかざして、あたりの様子を眺めると、何一つ道具とてもないガランとした部屋の片隅に、たった一つ妙な箱が置いてあるのが目を惹いた。
丁度寝棺ねがんほどの大きさの、長方形の白木の箱だ。近づいて見ると、その蓋の表面に、墨黒々と何か書いてある。読むまいとしても読まぬ訳には行かなかった。思いもよらぬその木箱に、川手氏自身の姓名が記されていたからである。
「俗名ぞくみょう川手庄太郎」「昭和十三年四月十三日歿」
アア、それは川手氏の死体を納める為に用意された棺桶かんおけであった。四月十三日歿という月日さえ、あの庭の石碑に刻みつけてあった日附と、ピッタリ一致しているではないか。
アア、そうだったのか。俺はこの棺かんに納められるのか。そして、庭の石碑の下へ埋められるのか。十三日といえば、明日だな。イヤ、もう十二時をすぎているから、今日という方が正しい。愈々俺はそういう事になるのかな。
川手氏は悪夢を見ているような気持で、まだ本当には驚けなかった。奥底も知れない程の恐怖ではあったが、それが何か紗しゃを通して眺めるようで、まだ身にしみて感じられなかった。
ふと気附くと、今まで側にいた子供の姿が見えぬ。一体どこへ消えてしまったのだ。四方を板で囲まれた部屋の中、どこにも身を隠す場所はないではないか。アア、これも悪夢だな。子供は魔法使の妖術で、煙のように消えてしまったのに違いない。
だが、地底の怪異はそれで終ったのではなかった。茫然と夢見るように佇んでいる川手氏の耳元に、どこからともなく、ボソボソと多勢の人の話声が聞えて来た。いつか寝室で聞いたのとは違って、板壁のすぐ向うからのように近々と響いて来る。アア、そうだったのか、山の魑魅魍魎はこんなところに隠れて、深夜の会合を催していたのか。
川手氏は声する方の壁に近づいて、どこかに秘密の出入口でもないかと、探し求めた。すると、その板壁の丁度目の高さの辺に、大きな節穴が一つ、サア覗いて下さいと云わぬばかりに開いているのが目についた。彼は中腰になってそこを覗いたが、一目覗くと、もう身動きも出来なかった。彼はそこに、全く想像もしなかった不思議なものを見たのである。
アア、これが正気の沙汰であろうか。この世に何か思いもかけぬ異変が生じたのではあるまいか。その地下室の穴蔵の板壁の向側には、夢のような一つの世界があったのである。
そこには、現代ばなれのした、ひどく古めかしい装飾の、立派な日本座敷があって、その床の間の柱に、夫婦と覚しき男女が、後手うしろでに縛りつけられていた。女の方は猿轡さるぐつわまではめられている。
男は三十四五歳の、髪の毛を房々ふさふさと分けた好男子、女は二十五六歳であろうか、友禅ゆうぜんの長襦袢ながじゅばんの襟もしどけなく、古風な丸髷まるまげの鬢びんのほつれ艶なまめかしい美女。二人とも寝入っているところを叩き起され、いきなり縛りつけられたらしく、ついその前に乱れた夜具が二つ敷いたままになっている。
縛られてうなだれた二人の前に、黒っぽい袷あわせの裾を高々とはしおり、毛むくじゃらの素足を丸出しにした四十前後と見える大男が、黒布ですっぽりと頬被ほおかぶりをして、右手にドキドキ光る九寸五分を持ち、夫婦のものを脅迫している体ていである。
その異様の光景を、高い竹筒の台のついた丸火屋まるほやの石油ランプが、薄暗く照らし出している有様は、どう見ても現代の光景ではない。室内の調度といい、人物の服装といい、明治時代の感じである。どこかへ姿を隠した、さい前の幼児が、やはり明治時代の服装をしていたことを思い合せると、一夜の内に時間が逆転して、三四十年も昔の世界が、突如として眼前に現われたとしか考えられなかった。
山の魑魅魍魎のあやかしであろうか。それとも狐狸こりの類のいたずらであろうか。だが、現代にそんな草双紙くさぞうしめいた現象があり得ようとも思われなかった。
頬被ほおかぶりをした強盗らしい男は、いきなり手にした短刀の刃で、美しい妻女の頬を、ピタピタと叩き始めた。
「強情を云わずと、金庫の鍵を渡さねえか。愚図愚図していると、ホラ、お内儀ないぎのこの美しい頬っぺたから赤い血が流れるんだぜ。ふた目と見られぬ、恐ろしい顔に早変りしてしまうんだぜ。サア、鍵を渡さねえか」
すると、縛られている男が、くやしそうに目をいからせて、盗賊の覆面を睨みつけた。
「金庫の中には書類ばかりで、現金はないって、あれ程云っているじゃないか。さっき渡した五十円で勘弁してくれ、今うちにはあれっきりしか現金がないんだから」
それを聞いた賊は、鼻の先で、フフンとせせら笑った。
「ヤイ、手前は俺がなんにも知らねえと思っているんだな。金庫の中には一万円という札束が入っているのを、ちゃんと見込んでやって来たんだ。ウフフフフ、どうだ図星だろう」
縛られている主人の顔に、サッと当惑の色が浮かんだ。
「イイエ、あれは私の金じゃない。大切な預りものだ。あれだけは、どうあっても渡すことは出来ない」
「そうら見ろ。とうとう白状してしまったじゃねえか。預りものであろうと、なかろうと、こっちの知ったことか。サア、鍵を出しねえ。俺はあれをすっかり貰って行くのだ。エ、出さねえか。出さねえというなら、どうだ、これでもか。エ、これでもか」
と同時に、ウーンと押し殺したようなうめき声が、川手氏の耳をうった。今までうなだれていた女が、顔を上げて、猿轡の中から身の気もよだつ恐怖のうめき声を立てたのだ。見ればその青ざめた白蝋はくろうのような頬に、一筋サッと真赤な糸が伸びて、そこから濡紙にインキが浸み渡りでもするように、見る見る血のりが頬を濡らして行く。
「アッ、何をするんだ。いけない。いけない。そ、それじゃ、わしの今持っているだけのお金を皆やる。ここにある。この違い棚の下の地袋じぶくろを開けてくれ。そこに手文庫が入っている。その手文庫の中の札入れに、確か三百円余りの現金があった筈だ。それを皆やるから、どうか手荒な事はよしてくれ。お願いだ。お願いだ」
主人は拝おがまんばかりの表情で懇願する。
「ホウ、そんな金があったのか。それじゃ、序ついでにそれも貰って置こう」
賊は憎々しく云いながら、直ぐさま地袋を開いて、手文庫をかき探し、札入れの中の紙幣を懐中ふところに入れた。
その間、主人は賊の一挙一動をさも無念そうに睨みつけていたが、紙幣を取り出して立上ろうとする時、賊の顔が一尺程の近さに迫って、覆面の中の素顔がはっきり見えたらしく、愕然として、
「オオ、貴様は川手庄兵衛しょうべえじゃないか」
と叫んだ。
それを聞くと、賊もギョッとした様子であったが、賊よりも節穴から覗いている川手氏の方が一層の驚きにうたれた。アア何という事だ。川手庄兵衛といえば、川手氏の亡父と同じ名前ではないか。明治時代らしいこの光景と、庄兵衛と呼ばれた男の年齢とも、ぴったり一致している。この当時には、亡父は丁度あのくらいの年輩であったに違いない。気のせいか、賊の姿や声までが、十歳の頃に死に別れた父親とそっくりのような気さえするのだ。
気でも違ったのか、夢を見ているのか、こんな不可思議な時間の逆転が起るなんて、五十近い息子が、自分よりも若い頃の父親の姿を、かくまでまざまざと見せつけられようとは。しかも、その父親は泥棒なのだ。ただの泥棒ではない、兇悪無残な持兇器じきょうき強盗なのだ。
川手氏はもう別世界の景色を眺めているような呑気な気持ではいられなかった。鼻の頭が痛くなる程、板壁に目をくッつけて、まるで、我が心の中の奇怪な秘密でも隙見するような、怖いもの見たさの、世にも異様な興奮に引入れられて行った。
川手庄兵衛と呼びかけられた賊は、一応はギョッとしたらしい様子であったが、忽ちふてぶてしく笑い出した。
「ハハハ……、そう気附かれちゃ仕様がない。如何にも俺はその川手さ。貴様の義理のお父つあんに使われた川手さ。だが何もそんなに威張いばるこたあなかろうぜ。元は貴様も俺と同じ山本やまもと商会の使用人じゃないか。それを、貴様はそののっぺりとした面で、御主人の一人娘、この満代みつよさんをうまくたらし込み、まんまと跡取り養子に入りこんだまでじゃないか。財産といったところで、元々死んだ山本の親爺さんのもの、貴様が我が物顔に振舞っているのが、無体むてい癪しゃくに触ってかなわねえのだ」
「ハハア、すると何だな、川手、貴様はこの満代が俺のものになったのを、いまだに恨んでいるんだな。その意趣返いしゅがえしにこんな無茶な真似をするんだな」
「そうともさ、俺おらあこの遺恨いこんはどうあっても忘れるこたあ出来ねえ。丁度今から八年前、貴様も知っている通り、俺はちっとばかり店の金を遣い込んで、いたたまれず逃げ出したが、それというのも、思いに思った満代さんを、貴様に取られたやけっ八ぱち。あれから朝鮮へ高飛びして、ほとぼりのさめた頃を見はからって帰って見れば、山本の親爺さんはなくなって、貴様が主人に納まり返っている。商売は益々盛んで、山本さんもよい婿むこを取り当てたともっぱら世間の噂うわさだ。
にっくい貴様達夫婦が、こうしてお蚕かいこぐるみでぬくぬくと暮らしているに引かえ、この俺は朝鮮で目論もくろんだ山仕事も散々の失敗、女房と子供を抱えて、まるで乞食同然の身の上さ。しょうことなしに、この間恥を忍んで貴様の店へ無心に行ったが、貴様はけんもほろろの挨拶、イヤそればかりじゃねえ、大勢の店員の見ている前で、よくも俺の旧悪を喋り立て、赤恥をかかせやあがったな。
若もし満代さんが、あの時俺になびいていさえすりゃ、今頃は俺が山本商会の主人となり、何十万の身代を自由にする身の上になっていたかと思うと、俺と貴様の運勢の、あんまりひどい違いに、俺アくやしくって、くやしくって、天道てんとうさまを恨まずにやいられなかった。
エエ、ままよ。どうせ天道さまに見離されたこの俺だ。まっとうにしていたんじゃ、一生乞食同然のみじめな暮しをせにゃならねえ。いっそ浮世を太く短くと思いついたのが、貴様達の運の尽きよ。
それから様子を探って見ると、丁度今日、一万円という現金が、この自宅の金庫の中へ納まるという目ぼしがついたので、それを待ち兼ねてやって来たのだ。サア、金庫の鍵を渡さねえか」
賊は時代めいたせりふを、長々と喋り終ると、又しても、血に濡れた短刀で、満代と呼ばれた美しい妻女の頬を、ペタペタと気味悪く叩くのであった。
「川手、そりゃ逆恨みというものだ。何も僕が無理やりにこの満代を、君から奪い取ったという訳ではなし、親の眼鏡に叶かなって、ちゃんと順序を踏んで結婚をした間柄だ。それを、根に持って兎や角云われる覚えはない。サア、トットと帰ってくれ。ぐずぐずしていると貴様の身の為にならぬぞ」
主人の山本は、身の自由を奪われながらも、負けてはいなかった。
「ハハハハハハ、その心配はご無用だ。女中達はみんな縛りつけて猿轡をかましてあるし、それに淋しい郊外の一軒家、貴様達がいくらわめいたって、誰が助けに来るものか。お巡りの巡回の時間まで、俺アちゃんと調べてあるんだ。サア渡せ、渡さねえと……」
「どうするんだ?」
「こうするのさ」
又しても、ウームという身震いの出るようなうめき声。満代の頬にスーッと二筋目の糸が引いて、真赤な血がボトボトと畳の上に滴った。
「待て、待ってくれ」
主人は身もだえして、ふり絞るような声で叫んだ。
「鍵を渡す。大切な預り金だけれど、満代の身には換えられぬ。鍵はこの次の間の、金庫の隣の箪笥たんすにある。上から三つ目の小抽斗こひきだしの、宝石入れの銀の小匣こばこの中だ」
「ウン、よく云った。で、組合せ文字は?」
「…………」
「オイ、組合せ文字はと聞いているんだ」
「ウーン、仕方がない。ミツヨの三字だ」
主人が歯がみをしてくやしがるのを、賊は小気味よげに眺めて、
「ウフフフフ、金庫の暗号まで満代か。馬鹿にしてやがる。よし、それじゃ、俺が次の間へ行ってる間、大人しくしているんだぞ。声でも立てたら、満代さんの命がねえぞ」
凄い口調で云い残して、賊は次の間へ消えて行ったが、ややしばらくあって、袱紗包ふくさづつみの札束らしいものを手にして、ニヤニヤ笑いながら戻って来た。
「確かに貰った。久しぶりにお目にかかる大金だ。悪くねえなあ。……ところで、これで用事もすんだから、おさらばといいたいんだが、そうはいかねえ。まだ大切な御用が残っておいで遊ばすのだ」
「エッ、まだ用事があるとは?」
主人の山本は、なぜかギョッとしたように、賊の覆面を睨みつける。
「俺ア、今夜は貴様達二人に恨みをはらしに来たんだ。その方の用事が、まだすんでいないというのさ」
「じゃあ、貴様は、金を取った上にまだ……」
「ウン、先さきに殺したんじゃ、金庫を開くことが出来ねえからね」
「エツ、殺す?」
「ウフフフフ、怖いかね」
「俺を殺すというのか」
「オオサ、貴様をよ。それから、貴様の大だいじの大じの満代さんをよ」
「なぜだ。なぜ俺達を殺さなければならないんだ。君はそうして、大金を手に入れたじゃないか。それだけで満足が出来ないのか」
「ところがね、やっぱり殺さなくちゃならないんだよ。マア考えても見るがいい。俺がこの家やを立去ったら、貴様はすぐ俺の名を云って警察へ訴えて出るだろう。そうすれば、俺は折角せっかく貰ったこの金を使うひまさえなかろうじゃないか。エ、色男、どうだね。マアそう云った理窟じゃねえか。貴様が余計なおせっかいをして、俺の正体を看破みやぶったのが運の尽きというものだ。自業自得と諦あきらめるがいいのさ。
イヤ、そればかりじゃない。仮令たとえ貴様が俺を看破らなかったとしたところが、貴様達夫婦がそうして仲よくしているところを見せつけられちゃ、俺ア黙っちゃあ帰られねえ。八年前の意趣ばらしだ。イヤ、八年前から今日きょうが日まで、片時として忘れたことのねえ恋の遺恨だ。貴様も憎いが、満代はもっと憎いんだ。恋いこがれていただけに、今の憎さがどれ程か、思い知らせてくれるのだ」
賊は憎々しく云いながら、血に濡れた九寸五分を、又しても満代の頬に当てた。それと知った満代は、恐怖の絶頂に、身を石のように固め、両眼が眼窩がんかを飛び出すかとばかり見開いて、狂気のように賊を見つめながら、猿轡の奥から、この世のものとも思われぬ凄惨なうめき声を発した。
「待ってくれ、川手、俺は決して君の名を口外しない。誓いを立てる。決して決して警察に訴えたりなんかしない。その一万円は俺の自由意志で君に贈与したことにする。だから、ねえ川手君、どうか許してくれ。命は助けてくれ。お願いだ」
云いながら山本は、ハラハラと涙をこぼした。
「川手君、君もまさか鬼ではあるまい。僕の気持ちを察してくれ。僕は果報者だ。満代はよくしてくれるし、二人の小さい子供は可愛い盛りだ。商売の方も順調に行っている。僕は幸福の真只中にいるのだ。まだこの世に未練がある。死に切れない。あの可愛い子供達や、この事業を残しては、死んでも死に切れない。川手君、察してくれ。そして、昔の朋輩ほうばい甲斐に、俺を助けてくれ。ねえ、お願いだ。その代り、君の事は悪くはしない。これからも出来るだけの援助はするつもりだ。もう一度、昔の朋輩の気持になってくれ」
「フフン、相変らず貴様は口先がうまいなあ。女を横取りして置いて、一人いい子になって置いて、昔の朋輩が聞いてあきれらあ。そんな甘口に乗る俺じゃねえ。マア、そんな無駄口を叩く暇があったら、念仏でも唱えるがいい」
「それじゃ、どうあっても許しちゃくれないのか」
「くどいよ。許すか許さねえか、論より証拠だ。これを見るがいい」
そして、賊はいきなり短刀を満代の胸へ……。
川手氏は最早もはや見るに忍びなかった。今二人の男女が殺されようとしているのだ。目を閉ふさいでも、断末魔の悲痛なうめき声が聞えて来る。しかもそれは、一寸だめし五分だめし、歌舞伎かぶき芝居の殺し場そっくりの、あのいやらしい、陰惨な、惻々そくそくとして鬼気の身に迫るものであった。
その残虐を敢あえてしている人物が我が亡き父であると思うと、川手氏は余計たまらなかった。自分よりも若い父親が、目の前に現われるなんて、理性では判断出来ない不思議だけれど、それを思いめぐらしている程、川手氏は冷静ではなかった。夢にもせよ、幻にもせよ、この残虐を黙って見ている訳には行かぬ。止めなければ、止めなければ……。
川手氏はもう気も狂わんばかりになって、いきなり拳こぶしを固めて前の板壁を乱打し始めた。地だんだを踏みながら、声を限りに訳も分らぬ事をわめき始めた。
それから十分程のち、川手氏はもうわめくことをやめて、又節穴を喰い入るように覗き込んでいた。
その間に板壁の向側で何事が行われたかは、ここに細叙することを差控えなければならぬ。川手庄兵衛なる人物は、それ程残虐であり、夫婦のものの最期は、それ程物恐ろしかったのである。
いま、節穴の向うには、最早や動くものとては何もなかった。二人の男女は、後手に縛られたまま、グッタリとうつぶせに倒れていた。青畳の上には、池のように真赤なものが流れていた。苦悶と絶叫のあとに、ただ死の静寂があった。丸火屋の台ランプが、風もないのに、さまよう魂魄こんぱくを暗示するかの如く、ジジジジと音を立てて、異様に明滅していた。
暫くすると、一方の襖ふすまが慌しく明けられて、二十五六歳程の召使らしい女が、胸に嬰児えいじを抱きしめ、四五歳の男の子の手を引いて、息せき切って駈け込んで来た。賊に縛られていた繩を、やっと解いて、主人夫婦の安否を確めに来たものに違いない。赤ん坊を抱いているのを見ると、乳母うばででもあろうか。手を引かれている男の子は、アア、これは何としたことだ。川手氏をこの地下室へ導いた、あの不思議な幼児であった。
乳母らしい女は、一目、座敷の様子を見ると、あまりの恐ろしさに、サッと顔色を変えて立ちすくんだが、やがて気を取り直すと、倒れている二人の側に駈け寄って、涙声を振りしぼった。
「旦那様、奥様、しっかりなすって下さいまし。旦那様、旦那様」
こわごわ肩に手をかけて、揺り動かすと、主人の山本は、まだことぎれていなかったと見えて、機械仕掛の人形のような、異様な動き方で、ゆっくりと顔を上げた。オオ、その顔! 目は血走り、頬はこけ、紙のような不気味な白さの中に、半ば開いた唇と舌とが、紫色に変っている。しかも、その額から頬にかけてベットリと赤いものが。
「オオ、ば、ばあやか……」
死人のような唇から、やっとかすれた声が漏れた。
「エエ、わたくしでございます。旦那様、しっかりなすって下さいまし。お水を持って参りましょうか。お水を……」
乳母は狂気のように、瀕死者ひんししゃの耳もとに口をあてて叫けぶのだ。
「ぼ、ぼうや、ぼうやを、ここへ……」
血走った目が、座敷の隅におびえている男の子に注がれる。
「坊ちゃまでございますか、サ、坊ちゃま、お父さまがお呼びでございますよ。早く、早くここへ」
乳母は幼児の手を取るようにして、瀕死の父の膝の前に坐らせ、自分は甲斐甲斐かいがいしく、主人のうしろに廻って、繩を解くのであった。
やっと自由になった山本の右手が、おぼつかなく幼児の肩にかかって、我が子を膝の上に抱き寄せた。
「ぼうや、か、かたきを、討ってくれ。……お父さんを、ころしたのは、かわて、しょうべえだ。……か、かわて、かわてだぞ。……ぼうや、かたきを、とってくれ。……あいつの、一家を、ねだやしにするのだ。……わ、わかったか。わかったか。……ばあや、たのんだぞ。……」
そして、ギリギリと歯噛みをして、すすり泣いたかと思うと、幼児の肩をつかんだ指が、もがくように痙攣けいれんして、ガックリと、そのままうっぷして、山本は遂に息が絶えてしまった。
ワーッと泣き伏す乳母、火のつくような赤ん坊の泣声、今まで余りの驚きに、泣く力さえなくおびえ切っていた男の子も、俄かに声を立てて泣き入った。
目もあてられぬ惨状だ。川手氏は又しても節穴から顔を放して、貰い泣きの涙を拭わなければならなかった。
暫くすると、乳母はやっと気を取り直して、男の子を我が前に引寄せ、決然とした様子で言い聞かせた。
「坊ちゃま。今、お父さまのおっしゃったこと、よくお分りになりまして。坊ちゃまは、まだ小さいから、お分りにならないかも知れませんが、お父さまやお母さまを、こんなむごたらしい目にあわせた奴は、元お店に使われていた川手庄兵衛でございますよ。よございますか。坊ちゃまは、お父さまの遺言を守って、仇討かたきうちをなさらなければなりません。あいつの一家を根絶やしにしてやるのです。
あいつには坊ちゃまよりは少し大きい男の子があるっていうことを聞いております。坊ちゃまは、その子供も決して見逃してはなりませんよ。そいつを、お父さまと同じような目にあわせてやるのです。いいえ、もっともっとひどい目にあわせてやるのです。そうしなければ、お父さまお母さまの魂は決して浮かばれないのです。お分りになりましたか」
乳母の恨みに燃えるまなざしが、まだ物心もつかぬ幼児の顔を、喰い入るように睨みつけた。すると、男の子は、その刹那せつな亡き父親の魂がのり移りでもしたように、幼い目をいからせ、拳を握って、廻らぬ舌で甲高く答えるのであった。
「坊や、そいつ、斬っちゃう。お父ちゃま、みたいに、斬っちゃう」
それを聞くと、節穴の川手氏は慄然として三度顔を背そむけた。アア、何という怨恨えんこん、何という執念であろう。無残の最後をとげた父母の魂は、今この幼児の心の中に移り住んだのである。でなくて、幼い子供が、あの様な恐しい目をする筈がない。あのような気違いめいた表情をする筈がない。アア、恐ろしいことだ。
再び節穴に目を当てると、いつの間にか、台ランプが消えたらしく、そこは墨を流したような闇に変っていた。人声も途絶え、物の動く気配とても感じられなかった。
だが、あれは何だろう。闇の中に直径一丈程の丸いものが、巨大な月のように、ぼんやりと白んでいた。そして、見る見るそれがはっきりと輝いて行く。
節穴から目を放していた僅かの間に、正面に白い幕のようなものが垂れ下ったらしく感じられた。その幕の表面に、一丈の月輪げつりんが輝いているのだ。
初めは、その月の中の兎のように見えていた薄黒いものが、光の度を増すにつれて、もつれ合う無数の蛇に変って行った。オオ、そこにはあの無数の蛇が蠢うごめいているのだ。蛇ではない、千倍万倍に拡大されたあの指紋が、……お化のような、あの三重渦状紋が。
「オイ、川手庄太郎、貴様の父親の旧悪を思い知ったか。そして俺の復讐の意味が分ったか」
どこからともなく、不気味な声が、まるで内しょ話のような囁き声が聞えて来た。
「俺は今、貴様の見た山本の息子、始はじめというものだ。貴様の一家を根絶やしにする事を、一生の事業として生きている山本始というものだ」
声はどこから響いて来るのか見当がつかなかった。前からのようでもあり、うしろからのようでもあり、しかし、その低い囁き声が、地下室全体に轟き渡って、まるで雷鳴のように感じられるのだ、川手氏は全身から脂汗を流しながら、金縛りにでもあったように、身動きさえ出来ない感じであった。
「貴様の父川手庄兵衛は、乳母の訴えによって、間もなく逮捕され、牢獄につながれる身となった。無論死刑だ。しかし、俺の両親の恨みはそんな手ぬるい事で霽はれるものではない。目には目を、歯には歯をだ。ところが、庄兵衛はその死刑さえ待たないで、牢獄の中で安らかに病死をしてしまった。アア、父母の恨み、俺の恨みは、一体どこへ持って行けばよいのだ。
俺はその当時、まだ幼かったので、乳母の訴えることを止めて、自分からこの手で復讐するという分別も力もなかった。あとで病死と聞いたときには、俺は泣いてお上かみを恨んだが、もうあとの祭だ。そこで俺は、父親の代りに貴様を相手にする事に決めた。子は父の為めに罪を負わなければならないのだ。これが復讐の神の掟おきてだ。
俺はその準備の為めに、四十年の年月を費した。はやる心を押え押えて、機の熟するのを待った。目には目を、歯には歯をだ。ただ貴様を殺すのはたやすい。しかし、それだけでは父母の魂が浮ばれぬ。貴様にも、父母と同じ苦しみ悲しみを与えなくてはならぬのだ。
そこで、俺は我慢に我慢を重ねて貴様の立身出世するのを待った。子供を生み、その子が立派に育つのを待った。そして貴様の出世が絶頂に達した今、俺の毒矢は遂に弦つるを離れたのだ。第一矢しは妹娘を斃たおした。第二矢は姉娘を斃した。そして、第三矢は今、この瞬間、貴様の心臓を射抜こうとしているのだ」
川手氏は父の牢死を知っていた。知って秘ひし隠しに隠していた。しかし何の罪によって入牢じゅろうしたかは、誰も教えてくれなかった。無論これ程の大罪とは知る由もなかったのだ。彼は貧苦と艱難かんなんの幼時を女親の手一つに育てられ、努力奮闘、遂に立志伝中りっしでんちゅうの人となって現在の地盤を築いたのだが、母はいまわの際まで、我子に父の恐ろしい秘密を語らなかった。何とやら腑ふに落ちぬことが多くて、屡々しばしば不審を抱くこともあったが、しかし父がそれ程の極悪非道を行っていようとは夢にも知らなかった。
「川手、何をぼんやり考えているのだ。恐ろしさに気が遠くなったのか、それとも何か腑に落ちぬことでもあるというのか」
囁き声がもどかしげに聞えて来た。
「腑に落ちぬ」
川手氏は猛然として、大勇猛心を奮い起し、いきなり怒鳴り返した。
「俺は父の罪を知らぬのだ。今聞くのが初めてだ。証拠を見せろ。俺は信じることが出来ない」
「ハハハハ、証拠か。それは、この俺が、山本始が、四十年を費して貴様に復讐を企てたことが何よりの証拠ではないか。ちっとやそっとの恨みで、人間がこれ程の辛苦に堪えられると思うのか」
「今のは、お芝居をして見せたのだな」
「そうだ。貴様に十分思い知らせる為に、多額の費用を使って地底演劇をやって見せたのだ。あの無残極まる貴様の親父の所業を目まのあたり見せたら、いくらぼんやり者の貴様にでも、俺のやり場のない無念さを、悟らせることが出来るだろうと考えたからだ。口で話した位で、あの残虐が分るものではない。
俺は子供心にも、あの父の断末魔の苦しみと、血の海にもがき廻った両親の苦悶のさまが、目の底に焼きついて、数十年後の今も、昨日のことのようにまざまざと思い出されるのだ。貴様の親父が牢死した位のことで、この恨みが、この悲しみが、消えてしまうと思うのか。俺の父は川手の一家を悉く亡ぼさなくては浮ばれないと遺言した。俺はその遺言を果したいばかりに、今日の日まで生き永らえて来たのだ。俺の生涯は父と母との復讐の為に捧げられたのだ。
川手、俺の父と母と、俺自身との怨恨がどれ程のものであったかを、今こそ思い知るがいい。俺は貴様一家を皆殺しにするまでは、死んでも死に切れないのだ」
「だが、若し俺が貴様の復讐に応じないといったら、どうするのだ」
「逃げるのか」
「逃げるのではない。立ち去るのだ。俺にはここを立ち去る自由がある」
「ハハハハハ、オイ、川手、それじゃ一つ君のうしろを振返って見たまえ」
川手氏はそれまで、節穴の向うの巨大な指紋を睨みつけて物を云っていたが、この時初めて、どうやら敵はうしろにいるらしい事に気附いた。そして、ハッと振向くと、淡い蝋燭の光に照らされて、そこに、一間とは隔たぬ目の前に、いつの間に忍び込んだのか、二人の男が立ちはだかっているのを発見して、ギョッと息を呑んだ。
オオ、あいつらだ。犯罪の行われる毎に姿を現わしたあの二人だ。一人は一方の目に大きな眼帯を当てた、無精鬚ぶしょうひげの大男、一人は黒眼鏡をかけた、痩せっぽちの小男だ。その二人が、小型ピストルを構えて、じっと川手氏に狙いを定めているのだ。
「ハハハハハ、これでも逃げられるというのか。身動きでもして見ろ、貴様の心臓に穴があくぞ」
大男の方が、今度はハッキリした声で、さも愉快らしく怒鳴った。
川手氏は、あくまで用意周到な相手に、最早や観念の眼を閉じる外はなかった。
「で、君達は俺をどうしようっていうのだ」
すると、大男は左手を上げて、静かに地下室の隅を指さした。オオ、そこには、あの薄気味悪い棺桶が、主ぬし待ち顔に置かれてあるのだ。
「君はこの中へ入るのさ。ちゃんと君の名が書いてあるじゃないか。川手、君はこれまでに、生きながらの埋葬という事を想像して見たことがあるかね。ハハハハハ、ないと見えるね。それじゃ一つ味わって見るがいい。君はこの棺かんの中に入って、生きながら土の底深く埋められるのだ」
云い放って、二人の男はお互に顔見合せ、さもおかしくて堪まらぬというように、腹を抱えて、ゲラゲラと笑い出すのであった。
川手氏は立っている力もない程の烈しい恐怖に襲われた。身体中の血液がスーッと引潮のように消えて行って、異様な寒さに、歯の根がガチガチ鳴り始めた。
「だ、誰か、誰か来てくれエ!」
土気色の顔、紫色の唇から、気違いのような絶叫がほとばしった。
「ハハハ……、駄目だ、駄目だ。君がいくら大きな声を出したって、ここは山の中の一軒家だぜ。鳥や獣物けだものがびっくりして逃げ出すくらいのものだ。アア、君は爺じいや夫婦が、その声を聞きつけて、助けに来てくれると思っているんだね。フフフ……。
ところがね、川手君、それは飛んだ当て違いというものだぜ。もうこうなったら、何もかも云ってしまうが、あの婆やというのは、外でもない、今君が見た山本家の乳母だった女なのさ。つまり俺の味方なのだ。爺やの方も、夫婦であって見れば、まさか女房を裏切って、俺の邪魔立てをする筈もなかろうじゃないか。
ハハハ……、君は不思議そうな顔をしているね。あの爺や夫婦が俺の手下だとすると、そんなところへ、宗像先生が君を連れて来たのは、変だとでもいうのかね。ハハハ……、何も変な事はないさ。宗像大先生は、この俺のためにマンマと一杯食わされたという訳だよ。俺がちゃんとお膳立てして置いたところへ、先生の方で飛び込んで来たのさ。あの三角髯の先生、見かけ倒しのボンクラ探偵だぜ。そんな探偵さんの云うままになった君の不運と諦あきらめるがいい」
眼帯の大男山本始は、得意らしく種明かしをして、さも面白そうに笑うのだが、川手氏は、その言葉さえ殆んど耳に入らなかった。ただ、あの真暗な「死」が、目の前にチラチラして、恐怖の余り魂も身に添わず、無駄とは分っていても、何かしら訳の分らぬ事を絶叫しないではいられなかった。
「ハハハ……、オイ川手、貴様も実業界では一廉ひとかどの人物じゃないか。みっともない、その態ざまは何だ。オイ黙らんか。黙れというのだ。……まだ泣いているな。往生際おうじょうぎわの悪い奴だ。……よし、それじゃ俺が黙らしてやろう」
云いながら、大男はいつの間にか川手氏のうしろに廻って、一方の手でギュッと喉のどをしめつけ、一方の手で口を蓋してしまった。川手氏は何の抵抗力もなく、まるで人形のように、されるがままになっている。
それと見ると、黒眼鏡の小男は、どこからか長い細引ほそびきを取出して、素早く川手氏の足元に走り寄り、いきなり足の先からグルグルと巻きつけ始めた。
足から腰、腰から両手と、見る見る内に、川手氏は無残な荷物のように、身動きも出来ず縛り上げられてしまった。
「よし、お前、足の方を持つんだ。そして、棺の中へ納めてしまおう」
大男の指図に、小男は無言で川手氏の膝の辺に両手を廻し、力まかせに抱き上げた。
そうして宙を運ばれながら、生きた心地もない焦慮しょうりょの中で、川手氏は不思議にはっきりと、ある異様な事柄を気附いていた。
というのは、黒眼鏡の小男が、どうも本当の男性ではないという事であった。膝に巻きついたネットリとしなやかな腕の感触、時々触れ合う胸の辺の肌触り、それに、小刻みな柔かい息遣いなどが、女としか思われないことであった。
だが、それは、慌しい心の隙間に、一瞬チラッと閃いたばかりで、やがて例の不気味な寝棺の中にドサッと抛ほうり込まれてしまうと、もうそんなことを考えつづけている余裕などある筈もなかった。
「川手、俺はとうとう目的を達したんだ。俺がどんなに嬉しがっているか、君に想像がつくかね。四十年の恨みを、俺の父と母とのあの血みどろの妄執もうしゅうを、今こそはらすことが出来たのだ。
お父さん、お母さん、これを見て下さい。あなた方の敵かたきは、今生きながら棺桶の中へとじこめられようとしているのです。あなた方のあの残酷な御最期にくらべては、これでもまだ足らないかも知れません。しかし、僕は智恵と力の限りを尽したのです。
一思いに殺すなんて、まるで相手を許してやるのも同然です。と云って、耳を削そぎ鼻を削ぐ一寸だめし五分だめしも、その苦しみの時間は知れたものです。それよりも、何が恐ろしいと云って、生きながらの埋葬ほど恐ろしいものはないと思います。無論、それ程の苦しみを与えても、お父さん、お母さん、あの時のあなた方のお苦しみには、やっと匹敵するかしないかです。でも、僕の智恵では、その上の思案も浮びません。どうかこれで思いをおはらし下さい。
ところで、川手、この生きながらの埋葬というものの恐ろしさが、君には想像が出来るかね。真暗な土の中へ入ってしまうのだ。そこで、一日も二日も三日も、空気の不足と餓えと渇きとに責められて生きていなければならないのだ。
いくら藻掻もがいたところで棺桶の蓋は開あきやしない。君の指の生爪がはがれて、血まみれになるばかりだ。フフフ……、君はその血をさえ、餓鬼のように貪むさぼり啜すすることだろうて。
藻掻きに藻掻いて、やっと息が絶えると、待ち構えていた蛆虫うじむしが、君の身体中を這い廻って、肉や臓腑を、ムチムチと啖くらい始めるのだ。……」
川手氏は棺桶の中に身動きも出来ず横わったまま、この無残な宣告を聞いていた。イヤ一語一語を聞き取る程の余裕はなかったけれど、聞かなくても、生埋めの恐ろしさは、彼自身の想像力によって、魂も消えるばかり、ひしひしと思いあたっていた。
口が自由になっても、もう叫び声さえ出なかった。ただ、自分では何か大声に叫んでいる積りで、血の気の失せた唇を、鯉こいのようにパクパク動かしているばかりであった。
「では、もう蓋をしめるぜ、観念するがいい。だが、その前に一言いちごん云って聞かせて置くことがある。……それはね、こんな目に会うのは、君が最後ではないということだよ。フフフ……、分らんかね。君は知るまいが、君には一人の妹があるんだ。君の父親があの泥棒をした金で、数ヶ月の間贅沢ぜいたくな暮らしをしていた頃、ある女の腹に出来た子供があるんだ。
俺は川手の血筋は一人残らず、この世から絶やしてしまうという誓いを立てた。だから、どっかに庄兵衛の血筋が残ってやしないかと、どれ程苦心をして探し廻ったか知れない。そして、君さえ知らぬその妹を見つけ出したのだ。
そいつも、今に君のあとを追って、地獄へ行くことだろう。地獄で目出度めでたく兄妹の対面をするがいい。イヤ、地獄といやあ、君の二人の娘も、そこで君を待っているはずだったね。ハハハハ……、久しぶりで、親子の対面も出来るというものだぜ。
それからね、序ついでにもう一つ云い聞かせて置くが、ここにいる黒眼鏡の男は、実は男じゃない。女だよ。エ、誰だと思うね。君がさい前覗き穴から見た女だぜ。と云っても、あの頃はまだ乳母に抱かれた赤ん坊だったが、あの赤ん坊がこんなに大きくなったのさ。そして、兄の手助けをして、一生を復讐の為に捧げて来たのさ。
君の二人の娘も、決して俺一人の手では料理しなかった。この妹にも存分恨みをはらさせたのだ。オイ、お前も今わの際に、こいつに顔を見せてやれ。あのときの赤ん坊が、両親ふたおやの断末魔の血を啜って、どんな女に生長せいちょうしたか、よく顔を拝ませてやれ」
山本始の指図に従って、男装の女は川手氏の上に顔を近よせ、大きな黒眼鏡を取って見せた。
川手氏は、蝋燭の光の陰に、眼界一杯にひろがった中年の女の顔を見た。気違いのように上ずった、二つの恐ろしい目を見た。
女はじっと川手氏の顔を睨みつけて、キリキリと歯噛みをした。そして、いきなり川手氏の顔に唾つばを吐きかけた。
「ホホ……、泣いているわ。顔の色ったらありゃしない。兄さん、あたしこれで胸がせいせいしたわ。サ、早く蓋をして、釘を打ちつけましょうよ」
妹は兄に輪をかけた狂人であった。この無残な言葉を、まるで日常茶飯事のように、子供の無邪気さで云い放った。亡き山本夫妻の怨霊のさせる業か、この復讐鬼兄妹は、揃いも揃って、精神的不具者としか考えられなかった。その所業の残忍、その計画の奇矯ききょう、到底常人の想像し得る所ではなかった。
やがて、鬼気漂う地底の窖あなぐらに、一打ち毎に人の心を凍らせるような金槌かなづちの音が響き渡った。その金槌の音につれて、赤茶けた蝋燭の火が明滅し、ニヤニヤと不気味に笑う男女二匹の鬼の顔が、闇の中に消えたり浮上ったりした。
釘を打ち終ると、二人は棺桶を吊って窖の外に出た。真暗な廊下を幾曲りして、雨戸を開き、そのまま庭の木立の中へ入って行く。
大樹の茂みに囲まれた闇の空地、昨日川手氏が自分自身の墓石を見たあの同じ場所に、何時いつの間に誰が掘ったのか、深い墓穴が地獄への口を開いていた。
二人は小さな蝋燭の光をたよりに、棺桶をその穴の底に落し入れると、その辺に投げ捨ててあった鍬くわとシャベルを取って、棺の上に土をかけた。そして、穴を埋め終ると、その柔かい土の上で、足を揃えて地均じならしを始めた。
足拍子も面白く、やがて、男女二いろの物狂わしい笑い声さえ加わって、地上に立てたほの暗い蝋燭の光の中に、二つの影法師は、まるで楽しい舞踏ででもあるように、いつまでもいつまでも、地均しの踊りを踊り続けるのであった。
お話は一転して東京に移る。
あの無残な川手氏の生体埋葬が行われた翌日の夜、隅田川にボート遊びをしていた若い男女が、世にも不思議な拾いものをした。
男は丸の内のある会社に勤めている平凡な下級社員、女は浅草のあるカフェーの女給であったが、丁度土曜日のこと、まだ季節には早いけれど、川風が寒いという程ではなく、闇の中で、たった二人で話をするのには、これに限るという思いつきから、もう店開きをした貸ボートを借りて、人目離れた川の真中を漕ぎ廻っていた。
やがて十時であった。
季節でもないこの夜更けに、ボート遊びをしているような物好きもなく、暗い川面かわもには、彼らの外ほかに貸ボートの赤い行燈あんどんは、一つも見当らなかった。
彼らはその淋しさを、却ってよい事にして、楽しい語らいの種も尽きず、ゆっくりと櫂かいを操あやつりながら、今吾妻橋あづまばしの下を抜けようとした時であった。夢中に話し込んでいる二人の間へ、ヒューッと空から何かしら落ちて来て、女の膝をかすめ、ボートの底に転がった。
「アラッ!」
女は思わず声を立てて、橋を見上げた。空から物が降る筈はない、橋の上を通りかかった人が、投げ落したものに違いないのだ。
男は櫂を一掻きして、ボートを橋の下から出し、それと覚しい辺りを見上げたが、その辺に川を覗いているような人影もなかった。怒鳴りつけようにも、相手はもう立去ってしまっていたのだ。
「痛い? ひどく痛むかい」
女が渋面じゅうめんを作りながら膝をさすっているので、男は心配そうに訊ねた。
「それ程でもないわ。でも、ひどいことをするわね。あたし、まだ胸がドキドキしている。誰かがいたずらしたんじゃないかしら」
「まさか。それに、あの時、ボートは橋の下から半分も出ていなかったから、きっと、こんな所に舟なんかないと思って投げたんだよ。川の中へ捨てたつもりで行ってしまったんだよ」
「そうかしら、でも危いわねえ。軽いものなら構わないけど、これ随分重そうなものよ。アラ、ごらんなさい。何だかいやに御丁寧に縛ってあるようよ」
男は櫂を離して、ボートの底に転がっている一物を拾い上げ、行燈の火にかざして見た。
それは石鹸箱程の大きさのもので、新聞紙で丁寧に包み、上から十文字に細い紐で括ってあった。
「あけて見ようか」
男は女の顔を眺めて、冗談らしく云った。
「汚いわ、捨てておしまいなさい」
女が顔をしかめるのを、意地悪くニヤニヤして、
「だが、若しこの中に貴重なものが入っていたら、勿体もったいないからね。何だかいやに重いぜ。金属の箱らしいぜ。宝石入れじゃないかな。誰かが盗んだけれど、持っているのが恐ろしくなって、川の中へ捨てたというようなことかも知れないぜ。よくある奴だ」
男は多分に猟奇の趣味を持っていた。
「慾ばっている! そんなお話みたいなことがあるもんですか」
「だが、つまらないものを、こんなに丁寧に包んだり縛ったりする奴はないぜ。兎も角開けて見よう。まさか爆弾じゃあるまい。君、この行燈を持っていてくれよ」
男の酔狂すいきょうを笑いながら、しかし、女も満更まんざら好奇心がない訳でなく、蝋燭のついた行燈を取って、男の手の上にさしつけてやるのであった。
男はその新聞包をボートの真中の腰かけ板の上にのせ、その上にかがみ込んで、注意深く紐を解き始めた。
「いやに沢山結び玉を拵こさえやがったな」
小言を云いながら、でも辛抱強く、丹念に結び玉を解いて、やっと紐をはずすと、幾重にも重ねた新聞包を、ビクビクしながら開いて行った。
「ホーラごらん。やっぱり捨てたもんじゃないぜ。錫の小函だ。重い筈だよ。ウン、分った。この函は重しに使ったんだ。中のものが浮いたり流れたりしないように、こんな重い函の中へ入れて捨てたんだ。して見ると、この中には、ひょっとしたら、ラヴ・レターかなんか入っているのかも知れないぜ。こりゃ面白くなって来た」
「およしなさいよ。何だか気味が悪いわ。いやなものが入っているんじゃない? こんなにまでして捨てるくらいだから、よっぽど人に見られては困るものに違いないわ」
「だから、面白いというんだよ。マア、見ててごらん」
男はまるで爆弾でもいじるような風ふうにおどけながら、勿体らしく小函の蓋に手をかけ、ソロソロと開いて行った。
「ハンカチらしいね」
小函の中にはハンカチを丸めたようなものが入っていた。男は拇指おやゆびと人差指で、ソッとそれの端をつまみ上げ、函の外へ取出した。
「ア、いけない。捨てておしまいなさい。血だわ。血がついているわ」
如何にもそのハンカチには、ドス黒い血のようなものがベットリと染み込んでいた。
それを見ると、女が顔色を変えたのに引かえ、男の好奇心は一入ひとしお激しくなりまさった。
彼はもう無言であった。何かしら重大な事件の中にまき込まれたという興奮のために、目の色が変っていた。彼は咄嗟の間に、嘗て愛読した探偵小説の中の、それに似た場面をあれこれと思い浮べていた。
ほの暗い行燈の下で、血染のハンカチが注意深く開かれて行った。
「何だか包んである」
男の声は、囁くように低かった。顔をくっつけ合った二人には、お互の鼻息が、異様に耳についた。
「怖いわ。よしましょう。捨てておしまいなさいな。でなければお巡りさんに渡した方がいいわ」
だが、男はもうハンカチを拡げてしまっていた。真赤に染まったハンカチの上に、何かしら細長いものが、鈎かぎなりに曲って横わっていた。
「指だよ」
男が鼻息の間から喉のつまった声で囁いた。
「マア!」
女はもうお喋りをする元気もなく、行燈をそこに置いたまま、顔をそむけてしまった。
「女の指だよ。……根元から切取ってある」
男が憑つかれた人のように、不気味な囁きをつづけた。
「指を切取って、川の中へ捨てなければならないなんて、これは一体どうした訳だろう。……犯罪だ! 君、これは犯罪だよ。……悪くすると殺人事件だよ」
隅田川の夜更け、ボート遊びの男女が、吾妻橋の上から投げ捨てられた奇怪な錫の小函の中から、今斬り取ったばかりのような生々しい人間の指を発見して、色を失った、その翌朝よくあさのことである。
警視庁の中村捜査係長は、出勤の途中、ふと宗像博士を訪ねて見る気になり、丸の内の宗像探偵事務所に立寄った。
中村係長は、民間探偵とはいえ、宗像博士の学識と手腕に、日頃から深く傾倒しているので、何かというと、博士を相談相手のようにしていたのだが、殊に今度の三重渦巻の怪指紋の犯人の事件では、博士は被害者川手氏の依頼を受けて、その捜査に当っていることでもあり、何か新しい手掛りの発見でもないかと、時々宗像探偵事務所を訪問して見るのであった。
宗像博士は中村警部の顔を見ると、
「や、いいところへお出で下すった。実は僕の方からあなたのところへ出向こうかと思っていたところです」
といいながら、先に立って、警部を奥まった化学実験室へ案内した。
「ホウ、そうでしたか。じゃ、何か新しい手掛りでも……」
「そうですよ。マアお掛け下さい。色々重大な御報告があるのです。無論例の三重渦状紋の怪物についてですよ」
中村警部はそれを聞くと、早朝の訪問が無駄でなかったことを喜びながら、目を輝かして博士の顔を見つめた。
「そいつは耳よりですね、一体どんなことです」
「サア、どちらからお話していいか。実は御報告しなければならない重大な事柄が二つ重なって来たので、僕も面喰らっているのですが、マア、順序を追ってお話しましょう。
その一つは、川手庄太郎氏が行方不明になってしまった事です」
「エッ、行方不明に?」
「そうです。これは僕に全責任がある訳で、全く申訳ないと思っているのです。川手氏を甲府こうふの近くの山中の一軒家へ匿かくまったことは、先日お話した通りですが、あれ程用心に用心を重ねて連れて行ったのに、どうしてこんなことになったのか、殆んど想像もつきません。
一昨日おとといでした。川手氏から至急来てくれという電報を受取ったのです。用件は書いてありませんでしたが、あの不便な山の中から電報を打つくらいですから、よくよくの事に違いないのです。
ところが、その日僕は別の事件で、どうしても手の放せないことがあったものですから、一日延ばして、昨日の午後やっと川手氏のところへ行ったのです。
行って見ると、留守番の爺さん夫婦のものが、オロオロしながら、今朝から川手氏の姿が見えないというのです。昨夜お寝みになったまま、蒲団がもぬけの殻になっていて、いつまで待っても食事にもいらっしゃらないので、家うちの中は勿論、庭から附近の山までも探し廻ったのだけれど、どこにも姿が見えぬというのです。
調べて見ると、川手氏の衣類はちゃんと揃っている。寝間着のままで行方不明になってしまったのです。まさか寝間着のまま汽車に乗る筈もなく、自分の意志で家出をしたとは考えられない。てっきり何者かに攫さらわれたのです。イヤ、何者かではない、あの三重渦巻の怪物に連れ去られたのに違いありません。
僕は余程あなたにお電話しようかと思ったのですが、東京からお出でになるのじゃ夜中になってしまいます。で、やむを得ず、僕自身で出来るだけのことをしました。
あちらの警察と青年団の手を借りて、一寸した山狩りのようなこともやって見ました。その捜索はまだ今でも続けられている筈ですが、昨夜ゆうべ僕の帰るまでには、何の発見もありませんでした。
一方僕は自身で、附近の三つの駅に電話をかけて、怪しい人物が下車しなかったか、何か大きな荷物を持った人物が乗車しなかったかと、訊ねて見たのですが、どの駅にもそういう怪しい人物の乗降はなかったのです。イヤ、あったとしても、駅員には少しも気附かれなかったのです。
で僕は一先ず東京へ帰ることにしました。例の怪指紋の犯人の仕業とすれば、その本拠は東京にあるのですし、いずれは川手氏の死体を東京の真中で、衆人に見せびらかす計画に違いないと考えたからです。それと、この事をあなたにも報告して、今後の処置について、よくお打合せしたかったのです。その上、都合によってはまたNへ引返すつもりでした。
ところが、今朝夜明けに新宿に着いて、一応自宅に帰り、今し方事務所へ来て見ますと、ここにも亦また、実に驚くべき事件が待ち構えていたのです」
「エッ、ここにもですって?」
中村警部は、川手氏の行方不明について、もっと詳しく聞き糺ただそうとしていたのだが、今はそれも忘れて、膝を乗り出さないではいられなかった。
「そうです。僕が来る少し前、この事務所へ妙な品物が届けられたのですが、それを見て、僕は川手氏の行方を急いで探す必要はないと思いました。あの人はもう生きてはいないのです。その品物が川手氏の死をはっきりと語っているのです」
「それは一体何です。どうして、そんな事がお分りになるのです」
「これですよ」
宗像博士は、化学実験台の上に置いてある、小さな錫の小函を指し示して、
「今朝、三十歳位の会社員風の男が僕を訪ねて来て、助手が不在だというと、手帳の紙をちぎって、こんなことを書きつけて、これと一緒に僕に渡してくれといって、逃げるように立去ったというのです。その男はひどく青ざめて、震えていたといいます」
云いながら、博士はポケットからその手帳の紙を取出して、中村警部に渡したが、それには鉛筆の走り書きで、左さのように記してあった。
昨夜午後十時頃、ボートを漕いでいて、吾妻橋の下で、この品を拾いました。包んであった新聞紙も紐もそのままお届けします。なぜこの品を先生のところへ持って来たかは、小函の中のものをよくごらん下されば分ります。今出勤を急ぎますので、後刻改めてお邪魔します。
「フーム、吾妻橋の下で拾ったというのですね。すると、誰かがこの品を隅田川へ投げ捨てたという訳ですか。綺麗な小函じゃありませんか。中に一体何が入っているのです」
「実に驚くべきものが入っているのです。マア開けてごらんなさい」
博士は錫の小函を中村警部の方へ押しやった。
「錫の函を、こんなに沢山の新聞で包んで、その上をこの紐で括ってあったのですね。ひどく用心深いじゃありませんか」
警部はそんな事を云いながら、拇指と人差指で、小函の蓋をソッとつまみ、静かにそれを持ち上げた。
「オヤ、血のようですね」
小函の中には、読者は既に御存知の血染めのハンカチが丸めて押し込んである。中村氏はそのハンカチを、実験台の上に取出して、恐る恐る開いて行った。開くに随したがって、何か不気味な細長いものが現われて来た。指だ。人間の指だ。鋭利な刃物で根元からプッツリ切断した、まだ生々しい血染めの指だ。
「女の指のようじゃありませんか」
警部は職掌柄、はしたなく驚くようなことはなかったが、その顔には流石に緊張の色を隠すことが出来なかった。
「僕もそう思うのですが、しかし女と極めてしまう訳にも行きますまい。華奢きゃしゃな男の指かもしれません」
「しかし、この指が川手氏の死を語っているというのは? これが川手氏の指だとでもおっしゃるのですか」
警部は血に染まった女のように細い指と、宗像博士の顔を見比べるようにして、不審らしく訊ねた。
「イヤイヤ、そうではありません。ここに拡大鏡がありますから、その指をもっとよく調べて下さい」
博士が差出す拡大鏡を受取ると、警部はポケットから鼻紙を取出して、それで指をつまみ上げ、拡大鏡の下に持って来て、熱心に覗き込んだ。
「オヤッ、この指紋は……」
流石の警部も、今度こそは顔色を変えないではいられなかった。
「見覚えがありましょう」
「見覚えがあるどころか。渦巻が三つ重なっているじゃありませんか。三重渦状紋だ。例の奴とそっくりです。これは一体……」
「僕は今、その隆線の数も算かぞえて見ましたが、例の殺人鬼の指紋と寸分違いません」
「すると……」
「すると、この指は犯人の手から斬り取られたのです。恐らく犯人自身が斬り取って、隅田川の底へ沈めようとしたのでしょう。重い錫の小函を使ったのも、その目的に違いありません」
「なぜです。あいつは、なぜ自分の指を斬り取ったりしたのです」
「それは容易に想像がつくじゃありませんか。考えてごらんなさい。犯人はこの指さえなくしてしまえば全く安全なのです。我々が犯人について知っているのは、ただこの三重渦状紋だけです。これさえ抹殺してしまえば、犯人を捉える手掛りが皆無になる訳ですからね。
犯人は川手氏を脅かし苦しめる為めに、この怪指紋を実に巧みに利用しましたが、その大切な武器を惜しげもなく切り捨てたところを見ると、もう指紋そのものが不要になった、つまり復讐の目的を完全に果したとしか考えられないじゃありませんか。僕が川手氏はもう生きていないだろうというのは、そういう論理からですよ」
「なる程、目的を果してしまったら、俄かに逮捕されることが恐ろしくなったという訳ですね。よくある奴です。僕もあなたの想像が当っているような気がします。それにしても、その小函が、どういう経路で佐藤という男の手に入ったか、又この手帳の切れっぱしに書いてある事が事実かどうかを、先ず取調べて見なければなりません。変な奴ですね、警察へ届けもしないで、いきなり先生のところへ持って来るなんて、この男を疑えば疑えない事もないじゃありませんか」
中村警部は警察が無視された点を、何より不服に思っているらしく見えた。
「ハハハ……、イヤ別に深い考えがあった訳じゃないでしょう。世間では三重渦巻の事件といえば、すぐ僕の名を思い出すような具合になっているのです。新聞があんなに書き立てるのですからね。佐藤という男も、それを知っていて、態と僕の所へ持って来たのでしょう。これを拾って指紋に気附いたところなどは、なかなか隅に置けない。例の街の探偵といった型の男ですね」
「それにしても、その男がもう一度ここへやって来るのを待って、詳しく聞き糺ただして見る外はありませんね。この指や小函だけでは、犯人が何者だか、どこに隠れているか、全く見当もつかないのですから」
「イヤ、僕の想像では、佐藤という男も多くを知ってはいまいと思うのです。ただ橋の上から投げ込まれたのが、偶然ボートの中へ落ちたというような事でしょうからね。それよりも、我々は手に入ったこれらの品を、綿密に研究して見なければなりません。一本の紐も、一枚の古新聞も、ましてハンカチなどというものは、証拠品として非常に重大な意味を持っていることがあるものです」
「しかし、見たところ、別にこれという手掛りもなさそうじゃありませんか。手掛りといえば、この指紋そのものが何より重大な手掛りですが、こうして犯人の身体から切り放されてしまっては、全く意味がない訳だし、この錫の小函にしても、どこにでも売っているような、ありふれた品ですからね」
「如何にも、指と小函に関しては、おっしゃる通りです。しかし、ここにはまだ紐と新聞紙とハンカチがあるじゃありませんか」
宗像博士は、何なぜか意味ありげに云って、相手の顔を見つめた。中村警部はそれを聞くと、脇に落ちぬ体で、改めて血染のハンカチを拡げて見たり、包装の古新聞を裏返して見たりした。
「僕には分りませんが、これらの品に、何か手掛りになるような点があるとおっしゃるのですか」
「もっと念を入れて調べてごらんなさい。僕はこの品々によって、犯人の所在を突きとめることが出来るとさえ考えているのですよ」
「エッ、犯人の所在を?」
警部はびっくりしたように、博士の顔を見た。博士はさも自信ありげに微笑んでいる。学者めいた三角型の顎髯に、何かしら奥底の知れぬ威厳のようなものが感じられた。
「先ずこの血染めのハンカチです。血まみれていて、ちょっと気がつかぬけれど、この隅をよくごらんなさい。赤い絹糸でイニシアルが縫いつけてある。光にかざして見ないと分らないが」
警部はハンカチを手に取って、窓の光線にかざして見た。
「なる程、RとKのようですね」
「そうです。犯人はR・Kという人物ですよ。偽名かも知れないが、いずれにしても、これは犯人のハンカチでしょう。川の底へ沈めてしまうものに、まさか作為をこらす筈もありませんからね」
「しかし、広い東京には、R・Kという頭字かしらじの人間が、無数にいるでしょうから、この持主を探し出すのは容易のことではありませんね」
「ところが、よくしたもので、その無数の中からたった一人を探し出す別の手掛りが、ちゃんと揃っているのですよ。この頭字をクロスワードの縦の鍵とすれば、もう一つ横の鍵に当るものを、我々は手に入れているのです」
中村警部はそれを聞くと、面羞おもはゆげに瞬きをした。博士の考えていることが、少しも分らなかったからである。
「その鍵というのは小函の包んであった新聞紙の中に隠されているのですよ。御丁寧に五枚も新聞を使っていますが、その内四枚は『東京朝日』です。ところが、ごらんなさい。一枚だけ地方新聞が混っている。『静岡日々にちにち新聞』です。これは一体何を意味するのでしょうか」
だが、情ないことに、中村氏にはまだ博士の真意が理解出来なかった。ただ先生の前の生徒のように、じっと相手の顔を見つめている外はないのだ。
「犯人が往来や外出先で指を切るなどということは考えられない。無論自宅でやったのに違いありません。そうすれば、この新聞も、その場にあり合せた、犯人自身の購読している新聞を使用したと考えても、先ず間違いはないでしょう。『東京朝日』は皆昨日の朝刊です。『静岡日々』だけが一昨日おとといの日附になっている。これによっても、犯人がその日読み捨てた新聞を、何気なく使ったことが、よく分るではありませんか。
ところで、この『静岡日々』ですが、これは犯人が街頭の地方新聞売子から買ったものか、それとも、直接本社から毎日郵便で犯人のところへ送っているものか、二つの場合のどちらかです。
そこで、僕は若しやこの新聞に郵送の帯封の痕が残っていないかと、拡大鏡で調べて見たのですが、ごらんなさい、ここにちゃんとその痕跡がある。極く僅かだけれど、ハトロン紙を剥がした痕が残っている。
サア、これがあいつの致命傷ですよ。無論犯人は川に沈める積りだったのだから、ハンカチのイニシアルもそのままにして置いたし、ハトロン紙の痕跡など、まるで注意もしなかったのでしょうが、それが偶然ボートの中へ落ちて、僕の手に入るなんて、恐ろしいことです。どんな賢い犯罪者でも、いつかは尻尾しっぽを掴まれるものですね」
「アア、なる程、やっと分りました。その静岡日々新聞社の直接読者名簿を調べればいい訳ですね」
中村警部は疑問がとけて、ホッとした面持である。
「そうですよ。東京でこんな田舎新聞を取っている人は、そんなに沢山ある筈はない。精々百人か二百人でしょう。その中からR・Kの頭字の人物を探せばいいのですから、何の面倒もありません。あなた方警察の手でやれば、数時間の間に、このR・Kの住所をつきとめることが出来るでしょう」
「有難う。何だか目の前がパッと明るくなったような気がします。では、僕はすぐ捜査課に帰って手配をします。ナアニ、電話で静岡警察署に依頼すれば、R・Kの住所姓名はすぐ分りますよ」
中村警部は面おもてを輝かして、もう椅子から立上っていた。
「じゃ、この証拠品はあなたの方へ保管して置いて下さい。そして、犯人の住所が分ったら、僕の方へも一寸お知らせ願えれば有難いのだが」
「無論お知らせしますよ。では、急ぎますからこれで……」
中村捜査係長は、博士がハトロン包みにしてくれた証拠品を受取ると、いそいそと事務所を立去るのであった。
その日の午後三時頃、待ち兼ねている宗像博士のところへ、中村警部から電話がかかって来た。
「大変おくれまして。例の人物の住所が判明したのです。若しお差支さしつかえなければ、これからすぐ青山高樹町たかきちょう十七番地の北園竜子きたぞのりゅうこという家を訪ねて、お出で下さいませんか。高樹町の電車停留場から一町もない場所ですから、じき分ります。僕も今そこへ来ているのです」
警部の声は犯人を突き留めたにしては、何となく元気がなかった。
「北園竜子、キタゾノ、リュウコ、アアやっぱり女でしたね。それがあのR・K本人ですね」
「そうです。今まで調べた所では、そうとしか考えられません。しかし、残念なことに、その家は、昨日引越しをしてしまって、空家になっているのです。……イヤ、詳しいことはお会いしてからお話しましょう。ではなるべく早くお出でをお待ちします」
という訳で、博士は直ちに自動車を青山高樹町に飛ばした。運転手に尋ねさせると、北園竜子の住んでいた空家はじき分ったが、それは大邸宅と大邸宅に挟まれた、ごく手狭な建物であった。
「ヤア、お待ちしていました。汚いですが、こちらへお入り下さい。今丁度ちょうど昨日まで北園に使われていた婆さんを見つけて、調べを始めようとしている所です」
空家の中から中村捜査係長が飛び出して来て、博士を屋内に導いた。階下が三間、二階が二間程の、ひどく古めかしい建物である。
その階下の八畳の座敷に、中村氏の部下の刑事が胡坐あぐらをかいていて、その前に六十歳程の小柄な老婆がかしこまっていた。博士が入って行くと、刑事は丁寧に目礼して、有名な民間探偵に敬意を表した。
「この人が北園竜子に使われていたお里さとさんというのです」
中村警部が紹介すると、老婆は博士をえらいお役人とでも思ったのか、オドオドしながら行儀のよいお辞儀をした。
さて、それから宗像博士の面前で、老婆の取調べが始められたが、その結果判明した点を略記すると、老婆は一年程この家に使われていた事、北園竜子は三十九歳だといっていたが、見たところ三十前後と云ってもいい程若々しい美人であったこと、彼女は数年前ぜん夫に死別し、子供もなく、両親も兄弟もなく、ひどく淋しい身の上であったこと、少しは貯金もあったらしい様子だが、職業としては生華いけばなの師匠ししょうをしていたこと、弟子の娘さん達の外に、友達といっては生華の仲間の婦人数名が出入りするだけで、全く孤独な生活をしていたこと、今度の引越しは郷里の三島みしま在へ帰るのだと云っていたが、そこにどんな親戚があるのか、老婆は少しも知らぬこと、引越しを思い立ったのは一週間程前で、それから不要の品を売払ったり、女手ばかりでボツボツ荷造りをしたりして、荷物を送り出したのは、昨日のお昼頃であったこと、運送屋が荷物を運び出してしまうと、老婆は暇ひまを出され、主人を見送るからといっても聞き入れられず、そのまま同じ区内の身寄りの者の所へ立去ったこと(若し北園竜子が犯人とすれば、指を切ったのは、無論その後のちに違いない)だから、主人の竜子が何時の汽車に乗って、どこへ行ったかは少しも知らぬことなどであった。
「で、あんたの主人には、特別に親しくしている男の友達というようなものはなかったのかね。くだいて云えば、マア情夫といったようなものだね」
中村警部が訊ねると、老婆は暫くもじもじと躊躇していたが、やがて思い切ったように語り出した。
「それがあったのでございますよ。こんなことをお喋りしてしまっては、御主人様に申訳ございませんが、お上かみのお訊ねですから、何もかも申上げてしまいます。
どこのお方か、何というお名前か、わたしは少しも存じませんが、何でも四十五六のデップリと肥ふとった背の高い男の方でございますよ。その方がいらっしゃる時分には、奥様が必ずわたしを遠方へお使いにお出しになるものですから、妙な話ですが、まるでお顔を見たこともなければ、お声を……アア、そうそう、たった一度、ある晩のことでした。奥様に云いつけられたお使いを、思いの外ほか早くすませて帰って見ますと、丁度そのお方も格子を開けてお帰りになるところで、出会いがしらに、電燈の光で、たった一度お顔を見たことがございます。それは立派な好男子の方でございましたよ」
「フーム、それで、あんたは、今でもその男に出会えば、これがそうだったと顔を見分けることが出来るかね」
「ハイ、きっと見分けられるでございましょう。たった一度でしたが、奥様があんなに隠していらっしゃる方かと思うと、いくら年寄りでも、やっぱり気を附けて、胸に刻み込んで置くものでございますよ」
老婆は歯の抜けた口をすぼめて、ホホホと笑うのであった。
「で、その男は泊って行くこともあったのかね」
「イイエ、一度もそんなことはございません。わたしがお使いから戻るまでには、きっとお帰りになりました。ですが、その代り、奥様の方が……」
「エ、奥様の方が、どうしたというの?」
「イイエね、奥様の方がよく外そとでお泊りになったのでございますよ」
「ホウ、そいつは変っているね。で、どんな口実で留守にしたの?」
「遠方のお友達の所へ遊びにいらっしゃるのだと申してね。一晩も二晩もお留守になることが、ちょくちょくございました。どんなお友達だか知れたものじゃございませんよ」
それを聞くと、捜査係長と私立探偵とは、思わず目を見合せた。若しその竜子の外泊の日が、これまでの殺人事件の日と一致すれば、愈々いよいよこの女を疑わなければならないのだ。
そこで、中村警部は川手氏の二人の令嬢が殺害されたと覚しき日附、その死体が陳列館やお化け大会へ運ばれた日附、それから川手氏自身が行方不明になった日附などを思い出して、それらの事件の当夜、竜子が外泊したかどうかを確めて見ることにした。
老婆の記憶を呼び起すのに、ひどく手数と時間がかかったけれど、月々の行事などに結びつけて、結局それらの事件の日と竜子の外泊の日とがピッタリ一致していたことを確め得たのである。
中村警部はこれに勢いを得て、更に質問をつづけた。
「で、奥さんの様子に、近頃、何か変ったところはなかったかね。どうして突然引越しをする気になったか、どうもそこの所が少しはっきりしないようだが」
「サア、わたしもそれを不思議に思っているのでございますよ。変った様子といえば、引越しの十日余り前から、奥様は何か深い心配事でもおありの様子で、いつもの奥様とはまるで人が変ったように、ソワソワしていらっしゃいました。
わたしなんかには何もお話しにならないので、事情はちっとも存じませんが、なんでもよっぽどの御心配事のようで、それから間もなく引越しの話が持上ったのでございます」
老婆との問答の、後々のちのちに関係のある重要な点は、以上に尽きていた。
老婆の取調べが終った頃、引越しの荷物を運んだ運送屋の若い者が、一人の刑事に連れられて入って来た。そこで又問答が行われたのだが、その結果、北園竜子の大小十三箇の引越し荷物は、運賃前払、東海道三島駅前運送店留置とめおきという指図で、昨日の夕方貨車に積み込んだことが判明した。
運送屋が帰るのと入れ違いに、待ち兼ねていた鑑識課の指紋係が、指紋検出の道具を携えて入って来た。窓のガラスだとか、襖の框かまちや引手だとか、家の中のあらゆる滑かな箇所が、次々と検査されて行った。その結果を簡単に記すと、不思議なことに、屋内の滑かな物の表面は、悉く布様のもので拭き取った形跡があり、指紋らしいものはどこにも発見されなかったが、ただ一つ、流石にここだけは拭き忘れたのか、便所の中の白い陶器の表面に、幾つかの指紋が検出された。そして、その一つに、問題の三重渦状紋がはっきりと残っていたのである。
刑事達は歓声をあげんばかりであった。愈々三重渦巻の怪犯人は北園竜子と決ったのだ。老婆が云った四十五六の情夫というのが相棒かも知れない。噂うわさによれば竜子は非常に若々しく見える、風にも堪えぬ風情ふぜいの、なよなよとした美人だという。ただ、いくら尋ね廻っても写真が手に入らぬのが残念だが、附近の人々は口を揃えて、その美貌を説き聞かせてくれる。妖魔だ。今の世の妲己のお百ひゃくは、逞たくましい情夫と力を合せて、残虐の数々を演じ、忽然として大都会の唯中に消え失せたのだ。
やがて、中村係長の命めいを受けて、四方に散っていた刑事達が、次々と帰って来た。附近の住宅や、その近くに住む竜子の生華の弟子を訪ねて、聞込みの報告を持ち寄るもの、夜番よばんの爺さんを叩き起し、出入商人の御用聞きを引きつれて来るもの、一々を記していては際限がないが、それらの聞込みや問答からは、読者に伝えて置かなければならぬ程の、重大な事柄は殆んど発見されなかった。
だが、その中にただ一つ、ここに書き漏らすことの出来ないのは、一人の刑事に連れられて来た食料品店の御用聞きの陳述である。
「そういえば妙なことがあるんですよ。一昨日の夕方、こちらへ御用を聞きに来ますと、奥さん自身で勝手口へ出ていらしって、今夜中に届けてくれって、妙な註文をなすったのです」
「フム、妙な註文とは」
「それがね、実に妙なんです。店で売っている牛肉の罐詰と、福神漬の罐詰の大きい奴を五つずつと、それから、パン屋さんで食パンを十斤きん買って、一緒に届けてくれっておっしゃるのです。
そんなに沢山どうなさるんですって、聞いたら、奥さんは怖い目で睨みつけて、何でもいいから持ってお出で、その代りにこれを上げるといって、一円下すったのです。それはもう使ってしまいましたがね。そして、お前の店には内しょに出来ないだろうけれど、パン屋さんにも、その外の人にも、あたしがこんな註文をしたことは、決して云うんじゃないよって、口止めされたんです。しかし、警察の旦那には白状しない訳に行きませんや」
「で、君はそれを届けたのか」
「エエ、夜になってからお届けしました。すると、婆やさんはいないと見えて、やっぱり奥さん自身で受取りに出ていらっしゃいました」
中村警部はそれを聞くと、何だかえたいの知れぬ不気味な謎にぶッつかったような気がした。一体これは何を意味するのだ。その翌日引越しをする矢先になって、十斤のパンと十個の罐詰を註文するなんて、狂気の沙汰ではないか。まさか罐詰やパンを国への土産みやげにする奴もなかろう。それとも彼女は逮捕を恐れる余り、人里離れた山の中へ、たて籠こもる積りででもあったのだろうか。
美しい殺人鬼とパンと罐詰。この妙な取り合せは何となく滑稽な感じであった。だが、そのおかしさの裏には、ゾッとするような不気味なものが隠れていた。中村警部は、ふとそれに気附くと、心の底からこみ上げて来る、一種異様の戦慄を感じないではいられなかった。
その日の取調べは、この御用聞きの不思議な陳述を以て一段落を告げた。宗像博士は、終始これという意見を挟むこともなく、中村警部の活動を傍観していた。
やがて、捜査係長と民間探偵とは、刑事達と別れて、同じ自動車で帰途についた。
「僕が今考えているのは、無論偽名だとは思いますが、兎も角あいつの戸籍簿を調べて見ること、一枚でもあいつの写真を探し出すこと、それから荷物の送り先の三島駅の運送店に張込みをすることなどですが、そういう正攻法では、うまく行きそうもないような気がします。何だか今日の取調べには、不気味な気ちがいめいた匂いがつき纒っていたじゃありませんか」
中村警部が半ば独言のように呟いた。
「気違いめいているのは最初からですよ。殺人犯人が死体を衆人に見せびらかすなんて、正気の沙汰じゃありません。恐るべき狂人の犯罪です。狂気の分子は到る処ところにちらついています。しかし、犯罪にかけては天才のように正確無比な奴です」
博士は殺人鬼を讃嘆するように溜息をついた。
「今日のパンと罐詰の一件なんか、僕は何だかゾーッとしましたよ。ナンセンスのようでいて、実はその奥にえたいの知れない怪物の着想が隠されているような気がするのです」
「怪物の着想、そうです。僕もそんな風のものを感じます。例えばですね。君は三重渦巻の指紋の持主が女性、しかも美しい女性であったことを、どう考えますか。
この事件には最初から女性がいたのでしょうか、しかし、我々は眼帯の大男と、黒眼鏡の小男しか見ていないではありませんか。
僕は今こんなことを考えているのですよ。あの少年のように小柄で、素敏すばしっこい黒眼鏡の男こそ、外ならぬ北園竜子その人ではなかったかとね」
中村警部はそれを聞くと、ハッとしたように顔を上げて博士を見た。そして、そのまま二人は、お互の目の中を覗き合うようにして、いつまでも黙り込んでいた。
翌日の各新聞には、この意外な犯人発覚の径路が、夜更けの隅田川、ボート遊びの男から説き起して、事細ことこまかに報道され、全読者に思いもかけぬ激情を味わせた。血染めのハンカチ、切断された生指、美貌の生華師匠、その不思議な失踪、分けても十箇の罐詰と十斤の食パンの謎は、二人以上の人の集るところ、必ず好奇の話題となって、さも気味悪げに囁き交されるのであった。
北園竜子の写真を手に入れる事、彼女の戸籍簿を調べる事、三島駅前の運送店に張り込みをする事という、中村捜査係長の三つの捜査方針は、戸籍簿を除いては全く失敗に終った。
刑事を八方に走らせ、竜子の知人という知人を訪ねて、写真を探し求めたけれど、流石に殺人鬼は用心深く、どの知人の手元にも一葉の古写真さえ保存されていなかった。
また三島駅前の張り込みは、少しの抜かりもなく行われたが、運賃前払いの十数箇の荷物は、運送店の倉庫に積み上げられたまま、受取人の姿はいつまでたっても現われず、三島駅にそれらしい人物の下車した様子もなかった。
ただ一つ、戸籍簿だけは満足な結果が得られた。犯人は意外にも偽名もせず、寄留届もちゃんとしていたので、戸籍は何の苦もなく判明したが、それによると、北園竜子は原籍静岡県三島町の北園弓子ゆみこというものの私生児で、母は竜子の十三歳の時病死しており、竜子には兄弟もなく、近い身寄りは悉く死亡しているという孤独な身の上であることが分ったが、それ以上戸籍簿からは何の得うるところもなかった。原籍の番地を調べても、北園の家は遠い昔に跡方もなくなって、母の弓子を記憶している人さえない有様であった。
そして、竜子失踪の翌々日の夜となった。宗像博士の事務所へは、中村警部から、その都度つど電話の報告があったので、博士は捜査の行き悩んでいることを知り、博士自身、警察とは別に、どんな捜査方針を採るべきかを苦慮していた。
いつもなれば、午後五時には事務所を閉めて帰宅する博士が、その夜は八時になっても、例の実験室にとじこもって、しきりと考えごとをしている。その様子を、次の間から新しく傭い入れられた助手の林はやしという青年が、心配そうに窺っていた。
林は去年ある私立大学の法科を出たばかりの、まだ二十五歳の青年であったが、探偵小説を愛読した余り、未来のシャーロック・ホームズを夢見ている男で、小池、木島の二人の先任助手が、殺人鬼の毒手に斃たおれたことも承知の上、志願して博士の助手となったのである。
謂わば、この事件を目当てに傭やとわれたようなものであったから、三重渦巻の指紋の主が、意外にも美しい女性と分り、その女性が不思議な失踪をしたことを知ると、林はもう夢中であった。飛んでもない見当はずれの想像説を組み立てては、博士に笑われて、頭を掻きながら引下る事も度々であった。
彼は、宗像博士を現代随一の名探偵として畏敬いけいしていた。実験室にとじこもっている博士の頭の中に、どんなすばらしい論理が組立てられているのかと、咳払いの聞える度に、影法師の動く度に、ただその事ばかり考えていた。
「林君、ちょっとここへ来てくれ給え」
突然ガラス戸の向うから博士の声が洩れて来た。林は待ち兼ねていたように「ハア」と答えて、勢いよく実験室へ飛び込んで行ったが、見れば、博士の顔に明るい微笑が漂っている。さては、何か妙案が浮かんだのに違いないと、林も思わずニコニコと笑った。
「林君、君は幽霊とかお化けとかいうものを怖がる質たちかね」
博士の藪から棒の質問に先ず面喰った。
「それはどういう意味でしょうか。まさか、先生が幽霊なんかを信じていらっしゃる訳ではないでしょうが……」
「ハハハ……、幽霊そのものは存在しないにしても、幽霊を怖がる恐怖心だけは、不思議と誰にもあるものだよ。君はそういう恐怖心が強いかどうかと訊ねるのさ」
「アア、そうですか。それなら、僕は怖がらない方です。真夜中に墓地を歩き廻ったりするのは大好きな方です」
「ホウ、そいつは頼もしいね。それじゃ、これから一つ僕と一緒に、夜の冒険に出かけるのだ。うまく行けば、すばらしい手柄が立てられるぜ」
「夜の冒険といって、一体どこへ行くのでしょうか」
「北園竜子の住んでいた空家へ、これから二人で忍び込むのだ。そして、空家の中で夜明かしをするのだ」
「では、あの空家に何か怪しいことでもあるとおっしゃるのですか」
「怪しいことがあるかも知れない。ないかも知れない。それを二人で試して見るのだ」
林助手には博士が何を考えているのか、まだよく分らなかった。しかし、無論北園竜子捜査に関する、何かの手掛りを得るためには違いない。
「まさか、あの空家に幽霊が出るという訳ではありますまいね」
林が冗談らしく笑うと、博士は案外真面目な顔で、
「ウン、幽霊が出てくれるといいんだがね。わしは、それを念じているくらいなんだよ」
と訳の分らぬ事を云った。
林助手は就職間まもなかったけれど、博士の奇矯ききょうな言動には、もう慣れっこになっていた。一日中実験室にとじこもって一言も口を利かないで、哲学者みたいに瞑想めいそうに耽っているかと思うと、突然車にも乗らないで、異様なモーニングの裾を飜ひるがえしながら、鉄砲玉のようにどこかへ飛び出して行く。そして、そのまま二日も三日も帰らないことさえ珍らしくはなかった。名人肌ともいうべき奇行家なのだ。
その調子を呑み込んでいるので、突如として「化物退治」のお供を命じられても、今更驚くことではない。イヤ、そういう突飛な企ての裏に、博士のどんな深い智慧が隠されているのかと思うと、未来のシャーロック・ホームズは、嬉しさに身内がゾクゾクするのであった。
それから、二人が葡萄酒とサンドイッチを詰めた小鞄こかばんをさげて、自動車に乗り込み、青山高樹町の問題の空家の一町ほど手前で下車したのは、もう九時半頃であった。
前にも記した通り、その辺は物淋しい屋敷町なので、さして夜も更けていないのに、殆んど人通りもなく、まばらな街燈の光も薄暗く、商店街に比べてはまるで別世界のように、ひっそりと静まり返っていた。
「僕らは無断であの空家へ忍び込むのだからね。そのつもりで、通行人などに怪しまれないように」
博士は小声に注意を与えながら、足音も盗むようにして、空家の裏側の路地へ忍び込んで行く。細い路地には電燈もなく、全くの暗闇である。その闇の中を、手探りで、二人の洋服男が影のように忍んで行く有様は、若し第三者が見たならば、探偵どころか、恐るべき夜盗の類と早合点したことであろう。
空家の勝手口に辿りつくと、先に立った博士は、ポケットから鍵束のようなものを取出して、それをあれこれと戸の錠前に当てがっていたが、忽ち易々と錠をはずし、ソッと板戸を押し開いて、真暗な土間へ入って行った。
いよいよ夜盗である。博士は錠前破り専門の盗賊も及ばぬ巧みさで、空家の戸締りを開いたのだ。
「林君、ここで靴を脱ぐんだ。声を立ててはいけないよ。わしがいいというまでは、無言の行ぎょうだ。いいかね、忘れても音を立てたり、声を出したりするんじゃないよ」
博士は暗闇の土間に立って、林助手の耳に口を寄せ、やっと聞える程の囁き声で命じた。
靴を脱いで、板の間に上り、手探りで、博士のあとについて行くと、博士は中の間と覚しき部屋で立止り、林助手の肩を押えて坐れという合図をして、自分も、その暗闇の中に胡坐をかいた。
声を出すなと云われているので、これからどうするのかと質問する訳にも行かず、林は博士の隣に坐ったまま、息を殺すようにして、真暗なあたりを見廻すばかりであった。
電車通りからは遠く、自動車も滅多に通らぬ横町なので、滅入めいるように静かだ。その上にこの暗闇、山奥の一軒家にでもいるような心細さである。
やがて、暗闇に目が慣れるにつれて、あたりの様子が、ほのかに見分けられるようになって来た。階下は三間みまほどの狭い借家、それが荷物を運び出したまま、どの部屋も開けっぱなしになっているので、階下全体が一つの大きな暗室のような感じである。初めは白い襖がポーッと浮かび出し、それから障子、黄色い壁、床の間と段々物の形が見え始め、やがて、障子の桟さんが算えられる程にはっきりして来た。
そうして、十分、二十分と無言の行をつづけているうちに、林助手は喋るなと云われていても、何だか口がムズムズして、もう我慢が出来なくなった。彼は博士の耳の側へ口を持って行って、まるで蚊かの鳴くような低い声で、ソッと囁いた。
「先生、僕らは一体何を待っているのですか。こんな空家の中で、こうしていたって、別に何事も起りそうもないじゃありませんか」
すると、博士は幽かすかに舌打ちをして、林の耳に口を寄せ、押し殺した声で囁き返した。
「幽霊が出るのを待っているんだよ。喋っちゃいけない。少しでも物音を立てたら、出なくなってしまうんだからね」
そう云って、叱りつけるように、肩の所をグッと押えられたので、林はもう囁き声で質問する事も出来なくなった。
変だな、先生気でも違ったのじゃないかしら、この家で人殺しがあった訳じゃなし、お化けや幽霊の出る因縁がないじゃないか。
だが、先生程の人が、こんなに真剣になっているんだから、ひょっとしたら本当に幽霊が出るのかな。一体その幽霊というのは、何者であろう。待てよ、幽霊といったって、無論昔の怪談にあるような奴が現われる筈はない。先生がそんなものを信じているとは考えられない。すると……アア、そうだ。若しかしたら……。
林助手は、何だか博士の待っているものの正体が、おぼろげに分って来たような気がした。そして、その想像が、彼をゾーッとさせた。若しそんなことがあり得るとしたら、そいつは幽霊なんかより、幾層倍も気味悪く、恐ろしい代物に違いなかった。博士がお化けとか幽霊とか形容したのも尤もっともである。
彼は何だか背筋がゾクゾク寒くなって来た。じっと目を凝らしていると、ポーッと白い襖の蔭から、黒い朦朧としたものが、ヒョイとこちらを覗いては引込んで行くような気がした。
何かソッと腕に触さわるものがあるので、びっくりして振り向くと、博士がサンドイッチを摘んで彼に渡そうとしているのだ。どうやら博士自身もそれを頬張って、ムシャムシャやっている様子だ。
無言でそのサンドイッチを受取って、口に入れたことは入れたが、博士の所謂いわゆる幽霊が気になって、今にもそいつが、向うの真暗闇から、バアッと飛び出して来るのではないかと思うと、食慾どころではなかった。
あとになって考えて見ると、そうして坐っていたのは一時間余りに過ぎなかったのだが、その一時間の長かったこと。林助手にはそれがたっぷり十時間にも感じられたのであった。
じっと我慢をして坐りつづけている彼の網膜には、あらゆる奇怪なるものの姿が、走馬燈のように去来し、耳には、彼自身の動悸の音が、種々様々の意味を持って、悪魔の言葉を囁きつづけた。
目を閉じれば瞼の裏の眼花となり、目を開けば暗闇の部屋に蠢く怪しい影となって、幻想の魑魅魍魎が目まぐるしく跳梁ちょうりょうするのだ。
無言の行が永引くにつれて、彼の全身には、ジットリと脂汗が浮かび、息遣いさえ異様にはずんで来るのを、どうすることもできなかった。
ふと気がつくと、頭の上に、人でも歩いているような気配が感じられた。二階の闇の中を、誰か歩いているのかしら。ハッとして、耳をすましたが、その物音は二三度ミシミシと幽に鳴ったばかりでやんでしまった。
気のせいかしら、今のは耳鳴りの音だったのかしらと怪しんでいると、今度は、すぐ次の間の梯子はしご段がミシミシと鳴りはじめた。
足音を忍ばせて、何者かが階下したへ降りて来る様子だ。
すると、闇の中から、誰かの手がニューッと伸びて、林助手の肩先をグッと押えつけた。宗像博士の手だ。博士が身動きしてはいけないと、無言の指図をしたのだ。そんな指図を受けなくても、林助手はもう金縛りにでもあったように身がすくんで、足音の主に立向って行くような勇気は少しもなかった。
まさかお化けや幽霊ではあるまい。幽霊が足音を立てる筈はない。では一体何者であろう。林助手にはそれがおぼろげに分っていた。分っているからこそ、一入ひとしお恐ろしいのだ。
やっと階段の軋きしみがやむと、次の間の闇の中に、朦朧として黒い人影が浮び出した。やっぱり人間だ。
息を殺して見ていると、そのものは、二人がそこに坐っているとも知らず、スーッと中の間を通り抜けて、奥座敷の縁側の方へ消えて行った。そして、ギイーと開き戸の軋む音。
あんな音のする開き戸がほかにある筈はない。縁側の隅の手洗い場だ。オヤ、すると、あの怪しい人影は、手洗い場へ入る為めに、二階から降りて来たのであろうか。
「先生、あれは何者です」
博士の耳に囁くと、博士も囁き返す。
「分らないかね」
「何だか、分っているような気がします。でも、今の奴は黒い洋服を着ているように見えましたぜ。男のようでしたぜ」
「それでいいのだよ。あれがあいつのもう一つの姿なのだ」
「捉えるのですか」
「イヤ、もう少し様子を見よう。相手をびっくりさせてはいけない。もう袋の鼠も同じことだからね」
そして、二人はまた押黙ってしまったが、すると、再び開き戸の軋む音がして、黒い影が戻って来た。
暗闇とは云え、相手も闇に慣れている筈だ。見つけられてはいけないと、二人は中の間の隅に身を縮めて、息を殺した。
黒い影は、足音も立てず、スーッと中の間へ入って来たが、ふと何かの気配を感じたように、そこに立止ってしまった。どうやら、闇をすかして、こちらを見つめているらしい様子だ。匂いを気附いたのかしら。それとも幽な呼吸の音が相手の耳に入ったのかしら。
闇の中の、息もつまるような、脂汗のにじみ出すような、恐ろしい睨み合いであった。そして、黒い影の口から「アッ」という幽な叫び声が洩れたかと思うと、怪物は風のように次の間へ逃げ込み、大きな音を立てて階段を駈け上って行った。
「見附けられたね。だが、大丈夫だ。逃げ路はないのだ。サア来たまえ」
博士はそう云って、鞄の中から二箇の懐中電燈を取り出すと、一つを林助手に手渡し、パッとそれを点じて、先に立った。
階段を上って見ると、二階は、僅か二間しかない上に、家具も何もないガランとした部屋なので、一目で見渡すことが出来る。
「オヤ、変ですね。誰もいないじゃありませんか」
博士の振り照らす懐中電燈の光が、二つの部屋をグルッと一巡したのに、その光の中へは何者の姿も現われなかった。
調べて見ると、両側の窓の雨戸は閉まったまま、中からちゃんと枢くるるがかかっている。二つの押入れも開いて見たが、中は何もないがらんどうだ。
「外ほかに隠れる場所もないし、どこへ消えてしまったのでしょう」
林助手はけげんらしく呟いたが、呟いているうちにゾーッと背筋が寒くなって来た。やっぱり幽霊だったのかしら。それともあいつは、幽霊よりも不気味な魔法使なのかしら。
「シッ、静かにしたまえ。あいつが聞いているじゃないか」
博士の囁き声を聞くと、「ソレ、そこに!」と云われでもしたように、又ドキンとした。
「どこに隠れているのでしょう」
怖々こわごわ訊ねると、博士は闇の中でニヤニヤと笑っているらしく、懐中電燈の光で、ソッと天井を指し示した。
「エッ、では、この上に?」
囁き声で聞き返す。
「そうだよ。外に逃げ場所はないじゃないか」
博士は囁いておいて、一方の押入れを覗き込み、懐中電燈でその天井板を調べていたが、オズオズと近よる林助手の腕を掴んで、耳に口をつけ、
「ここだよ。この天井板がはずれるようになっているのだ。……君、勇気があるかね」
と、からかい気味に訊ねた。
林助手は、勇気がないとは答え兼ねた。相手はお化でも幽霊でもない、生きた人間、しかも一人ぼっちで逃げ隠れている奴だ。それを怖がって尻ごみするようでは、探偵助手の恥辱である。
「僕この上へ上あがって、確かめて見ましょう。先生はここにいて下さい。若し相手が手強てごわいようでしたら、声をかけますから、加勢に来て下さい」
「じゃ、捉えなくてもいいから、ただあいつがいるかいないかだけを確かめてくれ給え。あとは警察の方に任せてしまえばいいのだから」
ヒソヒソと囁き交して、林助手は上衣を脱ぎ、なるべく物音を立てないように注意しながら、押入れの中段によじのぼり、天井板をソッと横にずらせて、埃ほこりっぽい屋根裏へ這い上って行った。
彼は嘗て、猟奇の心から、電燈工夫のあとについて、自宅の天井へ上って見た事があるので、屋根裏というものがどんな構造になっているかを、大体知っていた。天井のどの辺を足場にして這えばいいかというような事も心得ていた。
態と懐中電燈は消したまま、蜘蛛くもの巣と埃の中を、四ん這いになって、ジリジリと進んで行った。
博士に軽蔑されまいと、痩我慢を出しては見たものの、そうして何の隔てるものもなく、真の闇の中で、えたいの知れぬ怪物に相対しているかと思うと、不気味さは一入であった。
広くもない屋根裏のこととて、脅えながらも、ジリジリと進んで行くうちに、もうその中央の辺に達していた。
息を殺し、耳をすまして、じっとしていると、どこからか「ハッハッ」と小刻みの呼吸いきの音が聞えて来る。
「オヤ、それじゃ、相手も怖がっているのだな。あの烈しい息遣いはどうだ」
それと悟ると、林助手は俄かに勇気が出て来た。
「よしッ、思い切って、懐中電燈で照らしてやれ」
彼はいきなりそれを点じて、人の気配のする方角を、パッと照らして見た。
すると、その丸い光の中に、案の定、一人の異様な人物が蹲まっていた。
古ぼけた黒の背広服の襟を立て、黒のソフト帽の鍔つばをグッとさげて冠っている。そのソフト帽の下から、大きな眼鏡がギラギラと光って見える。ひどく小柄な弱そうな奴だ。その姿を見て、林はまた一段と勇気をました。
パッとさし向けられたまぶしい光に、その人物は思わず顔を上げて、こちらを見たが、それはまるで追いつめられた小兎のようにオドオドした、見るも哀れな表情であった。
細面ほそおもての女のように優しい顔が、恐怖に青ざめ歪んで、目には涙さえ光っている。「どうか見逃して下さい。お願いです、お願いです」と手を合せて拝まんばかりの様子である。
「ナアンダ、こんな弱々しい奴だったのか。よしッ、それじゃ一つ引っとらえて、手柄を立ててやろう」
林はますます大胆になって、無言のまま、ノソノソとその方へ這い寄って行った。だが、相手は猫の前の鼠のように、もう身動きさえ出来ないらしく、ただ泣き出しそうな顔で、じっとこちらを見つめているばかりだ。
やがて、二人の顔と顔とが、一尺程の間近に接近した。相手の心臓の鼓動が聞えるかと思われるほどであった。それでも、相手はまだじっとしていた。
林はなぜか妙な躊躇を感じた。相手が可哀想になって来た。そのやつれ果てた、哀願しているような表情は、一生忘れられないだろうと思った。
しかし、躊躇している場合ではない。屋根裏に逃げ隠れているような奴を憐れむことはないのだ。彼は思い切って、サッと腕を伸ばすと、相手の手首を掴んだ。想像していた通り、非常にしなやかな細い手首であった。
すると、相手の目がキラッと光った。「これ程頼んでも許してくれないのか」と叫んでいるように感じられた。そして、その態度が突然一変した。こんな弱々しい奴に、どうしてこれ程の力があるのかと、びっくりするような烈しい勢いで、掴まれている手首を振り放した。
アッと思う間に、相手は本当に小兎のような素早さで、向うの闇の中に飛び退すさっていた。
ウヌ、逃がすものか。林はもう懐中電燈で照らしている余裕もなく、その方へ飛びかかって行った。天井板が今にも破れそうに、メリメリと鳴った。
だが、飛びかかって行った場所には、どうしたのか相手の身体がなかった。身体はなかったけれど、頭の上の屋根の方から、二本の足がブラブラと下っているような気がした。
オヤッ、変だなと思ったけれど、ゆっくり考えている暇はない。無我夢中で、その二本の足のようなものにしがみついて行った。
すると、その足が、スーッと屋根の方へ引込んで行くような感じがしたが、次の瞬間には、それが恐ろしい勢で、グーンと下へ伸びて来た。
アッと思う間に、林助手は天井板をメリメリ云わせて、そこに転がっていた。
何が何だか分らなかった。懐中電燈は点火したまま転がっていたけれど、その異変の起った場所には直接の光が射さぬので、はっきり見定めることが出来ないのだ。
だが、忽ち事の次第が分って来た。ほのかな反射光の中に、屋根の裏側の薄い板張が見えている。その板張の一部分に、ポッカリと二尺四方程の穴があいているのだ。穴の上には何の目を遮さえぎるものもなく、遥かの彼方に、キラキラと星が光っている。
アア、何ということだ。こんなところに屋上への抜け穴が用意してあったのだ。
ガタガタと瓦を踏む音が聞える。怪物は林を蹴飛ばして置いて、屋根の上へ逃げ出したのだ。
「先生、外へ廻って下さい。大屋根の上へ逃げました。屋根を伝って、下へ降りる積りかも知れません」
押入れの外に待っていた宗像博士の耳に、屋根裏の闇の中から、林助手の声が聞えて来た。
それでなくても、天井の恐ろしい物音に、もう身構えをしていた博士は、この声を聞くと、矢庭やにわに身を躍らして、疾風のように階段を駈け降り、裏口から闇の道路へと飛び出し、空家の表側に廻って、相手に悟られぬよう、物蔭から、じっと屋根の上を注視した。
怪物は二階の大屋根から、雨樋を伝わって、非常な危険を冒しながら、やっと一階の屋根まで降りたところであった。遠くの街燈のほのかな光線が、守宮やもりのように二階の窓の雨戸にへばりついた黒い背広に黒いソフト帽の人物を、朦朧と映し出している。
その者は、雨戸にへばりついた姿勢のまま、ソッと首を伸ばして、下の道路を眺め、耳をすまして様子を窺うかがっている。
博士は一層注意して、物蔭に身を隠し、僅かに一方の目だけで、屋根の上を見つめていた。
もう十一時に近い時刻、淋しい屋敷町には、全く人通りも途絶えている。遠くを走る電車の響きの外は、何の物音も聞えない。その死に絶えたような静寂の中で、黒い怪物は、屋根の上を、四よつん這いになって、ソロソロと庇ひさしの端の方へ乗り出して来る。不気味な無声映画でも見ているような感じであった。
するとその時、怪物の頭の上の大屋根に、瓦の軋む音がして黒い人の姿が現われた。林助手が抜け穴から這い出して、その辺を探し廻っている姿である。
怪物はハッとしたように、大屋根を見上げた。そして、瓦の音に追手の迫るのを察したのであろう。何か非常な決心をした様子で、いきなり庇の端に乗り出すと、パッと闇の地上へと身を躍らせた。大きな黒い塊が、博士の目の前の道路へ、スーッと墜落して、コロコロと転がったが、忽ち起き上って、非常な早さで走り出した。
宗像博士がそのあとを追ったのは云うまでもない。追い縋すがって捉えようと思えば、捉えられぬ筈はないのだが、博士はなぜかそれをせず、あくまで相手の跡を追って、どこへ逃げるのか、その行先をつきとめようとするらしく、適当の距離を保ちながら、執拗な追跡をつづけた。
怪物はこの辺の地理をよく知っていると見え、淋しい方へ淋しい方へと町角を曲りながら、十丁近くも走ったが、息切れがするらしく、段々速度が鈍くなった頃には、行手に何かの神社のこんもりとした森が見えて来た。そして、その森の中が逃走者の目ざす場所であった。
破れた生垣の間から、森の下闇へ踏み込み、ジメジメとした落葉の上を、奥の社殿へと辿って、その裏側の高い床下へ隠れる姿が、辛うじて認められた。
博士は相手に悟られぬよう、足音を忍ばせながら、社殿の裏に近づき、床下の闇の中に、幽に蠢く人影をつきとめると、突然、パッと懐中電燈を点火して、相手の顔にさしつけた。
背をかがめて歩ける程の高い床下、柱と柱の間に身を縮めて蹲まっている怪物、その胸から上の半身像が、電燈の丸い光の中に、クッキリと浮き上った。
黒ソフトをまぶかく冠り、大きな眼鏡で顔を隠しているけれど、その眼鏡の中から、恐怖の為めに一杯に見開かれた両眼が、追いつめられたけだもののように、こちらを見つめ、青ざめた頬、激動の為めに白っぽく色を失った唇が、半ば開いたままになって、ゾッとするような烈しい息遣いをしている。確かに女だ。しかも美しい女だ。
「ハハハハハハ、とうとう追いつめられてしまったね、北園竜子。そうだろう、君は北園竜子だね」
博士は物柔かに云って、じっと相手の表情を注視した。
「誰です。あなたは誰です」
竜子の顔がキューッと歪んで、今にも泣き出しそうな渋面になった。あの兇悪な殺人鬼が、どうしてこんな弱々しい表情をするのか、不思議と云えば不思議であった。だが、油断は出来ない。女というものは、ましてこれ程の悪人となれば、悲しくもないのに涙を流し、怖くもないのに恐怖の表情を作るなどは朝飯前の芸当に違いない。
「わしかね、わしは三重渦巻の指紋を持つ殺人犯人を捉えるために、永い間苦労している宗像というものだ。無論君はわしをよく知っている筈だね」
相手は答えなかった。答える代りに一層恐怖の表情を強めて、身をすくめた。
「わしは実を云うと、君の腕前には全く感心しているのだよ。君は悪魔の智恵を持っている。そんな悄しおらしい顔をしていて、実は人殺しの天才なのだ。川手氏の妹娘の死骸を博物館の陳列箱の中へ飾ったり、姉娘の死骸をお化け大会の破れ蚊帳の中へ寝かした腕前には、流石のわしも兜を脱いだ。永年の間にはずいぶん毛色の変った犯罪事件も取扱ったが、君のような魔法使を相手にしたのは初めてだよ」
博士がそこまで云うと、男装の竜子が突然両手を前にさし出して、博士の口を塞ぎたいとでもいう様な恰好をした。そしてまるで気でも狂ったように叫び出した。
「違います。違います。わたしはそんな恐ろしい罪を犯した覚えはありません。わたしは何も知らないのです。川手という方にも、その二人のお嬢さんにも、会ったことさえありません。これには何か深い訳があるのです。何者かが私を罪に落そうと、恐ろしい企らみをしているのです」
「ハハハハハハ、つまらんお芝居はよしたまえ。このわしをそんな手で欺だまそうとするのは、浅墓あさはかだよ。わしは何もかも知っているのだ。若し罪がないものなら、なぜ逃げ隠れをするのだ。それも普通の逃げ方ではない。引越しをして、空家と見せかけて、そこの天井裏に隠れているなんて、悪魔でなくては考えつけないことだよ。この一事いちじからでも、君があの恐ろしい殺人者であることは、立派に証拠立てられている。現に警察の人達は、君の行方を探しあぐねて、途方に暮れているじゃないか。若しわしが君のトリックに気づかなかったら、君はまんまと世間を欺あざむきおおせたかも知れぬ。そして、あれだけの大罪を犯しながら、永久に法網を脱のがれてしまったかも知れぬ。
君はどうして、わしが天井裏の隠れ場所を察したか知るまいね。まぐれ当りではないのだよ。食料品屋の小僧から聞き出したのだ。そして、あの不思議な十箇の罐詰と十斤の食パンの謎を解いたのだ。引越しにそんなものの必要はない。これは君が、数日の間、世間と全く交通を断って、どこかに隠れる積りに違いないと考えた。では、どこに隠れるか。鬼熊のように人里離れた山の中に隠れるか。イヤ、君がそんな間抜けな真似をする筈がない。これまでのやり方でも分っているように、君という人は巧みに人の意表を突く手品使なのだからね。
わしはそういう手品使の気持になって、君の計画を想像して見た。すると、どうも君の突然の引越しそのものが臭いのだ。殊更あの家を空家にして見せたところに、何かカラクリがあり相そうな気がするのだ。わしはつい数時間前に、やっとそこへ気がついた。そこで、助手を連れて、空家の探検に出かけて来たのだが、そのわしの想像がまんまと的中した。これでわしも、君と同じくらいの智恵を持っているという自信を得た訳だよ。ハハハハハハ」
「イイエ、違います。それはあの家を引越したと見せかけて、屋根裏へ隠れたのは本当ですけれど、それにはどうにも出来ない恐ろしい訳があったのです。逃げ隠れをしたからといって、決してわたしは罪を犯した訳ではありません。人殺しなんて、全く身に覚えのないことです」
男装の女性は、さもさもくやしげに、ハラハラと涙を流してかき口説くのだ。
「ハハハ……、そんな筋の通らない理窟では駄目だよ。罪も犯さぬのに逃げ隠れする奴があるものか。だが、そのどうにも出来ない恐ろしい訳というのは、一体どんな事だね」
博士は半ば揶揄やゆするように、嘲笑を浮べて訊ねる。
「アア、もう駄目です。どんなに弁解して見ても、あなた方が納得して下さる筈はありません。わたしは呪われているのです。あんないまわしい指を持って生れて来たのが、わたしの業ごうだったのです」
「フフン、実にうまいもんだ。流石に君は名優だよ。そういうと、何だか、君は例の三重渦巻の指紋の持主ではあるけれど、殺人罪は犯さない。真犯人は外にあるのだとでもいうように聞えるね」
博士は懐中電燈の丸い光を、近々と相手の顔にさしつけ、どんな細かい表情の変化も見落すまいとするかのように、つくづくとその顔を見つめるのであった。
丸い光の中の女性は、一入悲しげな、絶望の表情になって、なおもかき口説く。
「そうなのです、犯人は決してわたしではありません。でも、その無実を云い解くすべが、全くないのです。ごらん下さい。ここにあの恐ろしい指紋の指が着いていたのです」
彼女は云いながら、丸い光の中へソッと左手をさし出した。手首全体に繃帯ほうたいが巻いてあるので、切口は見えぬけれど、人差指のあるべき場所が異様にくぼんで、歯の抜けたような感じを与えている。
「わたしは、三重渦巻の指紋を持った殺人鬼の話は聞いておりましたけれど、つい十日余り前まで、迂濶うかつにも、わたしの人差指の妙な指紋が、その恐ろしい三重渦状紋とやらだとは、まるで、気もつかないでいました。
ところが、ふと新聞に出ている、犯人の指紋の拡大写真を見たのです。そして、ハッとして、自分の左手の人差指と比べて見ますと、アア、何という恐ろしい事でしょう。形は勿論、筋の数まで、一分一厘違わぬ事が分りました。その時のわたしの気持をお察し下さいませ。いきなり、地獄の底へ突き落されたとでも申しましょうか、スーッと目の前が真暗になって、気を失わぬのがやっとでございました。私は広い世界に、全く同じ指紋が二つとあるものではないと云う事を、ハッキリ知っていたのでございます」
長々しい繰くり言に、博士はもどかしげに足踏みをした。
「それで、疑いを逃れるために、思い切って人差指を切り落し、隅田川へ投げ込んだというのだね。だが、おかしいじゃないか。身に覚えのないことなら、何も指など切らなくても、殺人事件のあった日には、どこそこにいましたと、アリバイという奴を申立てればいいのだからね」
それを聞くと、丸い光の中の女性の顔が、またしてもキューッと引き歪んで、青白い頬にハラハラと涙がこぼれた。
「アア、それが出来ましたら。それが出来さえしましたら。……わたしは呪われているのです。本当に引くことも進むことも出来ない地獄の呪いにかかっているのです。
アリバイという言葉は本で読んでよく知っております。わたしもそれに気がついて、一まず安心したのです。そして、念の為めに、古い新聞を探して、あの殺人事件の最初からの日附を確めて見ました。
すると、どうでしょう。わたしは又息もつけない程の驚きにうたれました。アリバイが全くないことが分ったのです。どの殺人事件の日にも、わたしは家をあけて外出していました。それも一時間や二時間ではなく、半日以上、ある時は一晩中帰らない日さえありました。そして、何という恐ろしい運命でしょう。そのわたしの外出していた日に限って、必ずあの殺人事件が起っているではありませんか。イイエ、外出と申しましても、よそのお家を訪ねたわけではありません。ただ何となく歩き廻ったのです。郊外だとか、時には鎌倉かまくら江えの島しまなど……」
「ハハハ……、益々辻褄つじつまが合わなくなって来た。そんな永い時間、一人で歩き廻る奴もないものだ」
「イイエ、一人ではありません。あの、お友達と……」
「エ、お友達? それじゃちゃんとアリバイがあるじゃないか。その友達を証人にすればいい筈じゃないか」
「でも、それが、……」
「それが?」
「それが、普通のお友達ではなかったのです」
「ウン、分った。君の家の婆やが云っていたが、君には男の友達があったそうだね。だが、そんな事を恥しがって、殺人の嫌疑を甘んじて受ける奴もないものだ。その男の友達に証言させればいいじゃないか」
「でも……」
「でも、どうしたんだね」
竜子はもう口が利けなくなった様子で、ワナワナと唇を震わせながら、烈しく泣きじゃくり始めた。泣き声を噛み殺そうとするのだが、そうすればする程、胸の奥から嗚咽おえつがこみ上げ、涙はとめどもなく流れ落ちる。これをお芝居とすれば、実に驚くべき名優である。
宗像博士も流石に憫あわれみを催したらしく、無言のまま、相手の激情の静まるのを待っていた。すると、ややあって、彼女は漸ようやく泣きじゃくりをやめ、さも悲しげな細い声で、幽に呟くのであった。
「その人には、もう二度と逢うことが出来ないのです」
「どうしてだね」
「こんなことを申し上げても、あなたは信じて下さらないでしょうが、わたしはそれ程親しくしていた、その人の職業も住所さえも知らないのです。
名前は須藤すどうと申していましたが、それさえ本当の名かどうか分りません。その人は、所も名も明かさないで、こうして夢のようにつき合っている方が、童話の国の交わりみたいで、面白いではないかと申すのです。
三月程前、ふと汽車の中で御一緒になったのが、最初でしたが、その人は、大変身分のある人のように感じられました。きっと奥さんも、お子さんもおありなのでしょう。でも、その人の何とも知れぬ不思議な、夢のようなお話に、いつとはなく引きつけられて、お恥しいことですけれど、わたしは小娘のように夢中になってしまったのです。
丁度四日程以前、この指を切る前の晩のことでした。わたしは、その人と約束した時間に、このお社やしろの森の中へ来たのです。エエ、ここなのです。その人と外そとで出逢う時はいつもこの森の中だったのです。そして、この間からの、わたしの恐ろしい境遇を、よく相談しようと思ったのです。
ところが、その晩は、どうしたことか、その人の姿が見えません。丁度ここです。このお社の床下に、わたしはあの人を待って待って、明け方まで待ち暮らしました。まさかとお思いでしょうね。でも、わたしは何かに魅入られていたのです。本当に夢のように、一夜をここで過したのです。
そして、夜の白々あけに、ふと見ますと、そうです、丁度この柱でした。この柱に小さな紙切れが貼りつけてあるのに気がつきました。その紙切れに、何と書いてあったとお思いです。
縁切り状でしたの。もうこれっきり、あなたと逢うことはないでしょう。楽しかった夢を忘れませんと、そう書いてあったのです」
語り終って、男装の竜子は、又込み上げる悲しさに、今は恥も外聞も忘れたように、声を立てて泣き伏すのであった。
思わぬ長話に、さい前から三十分余りも時がたっていた。人なき深夜の社殿の床下で、男装の女と、モーニング姿の私立探偵とが、光と云えば懐中電燈ただ一つをたよりに、ヒソヒソと語り合う。その二人が恋人でもあることか、一人は稀代の殺人魔、一人はそれを追いつめた名探偵。何という不思議な取合せ、常規じょうきを逸した光景であったろう。
宗像博士は泣き伏す女怪を、あきれ果てた面持で眺めていたが、やがて感に堪えたように、しきりと肯きながら、
「うまい。実にうまいもんだ。君は名優なばかりでなくて、すばらしい小説家だ。よくもそこまで考えたもんだねえ。すっかり辻褄が合っている。
だがね、それは君が創つくり出したお話に過ぎないと云われても、何の反証も上げられないじゃないか。男の友達があったということは、証人もある事だから、本当に違いない。しかし、それは、君を捨てた夢のような恋人ではなくて、君の人殺しの相棒だったと考える事も出来るのだからね。
この殺人事件には、君とそっくりの男装の女が、度々顔を出しているのだが、その女にはいつでも左の目に眼帯を当てた大男がついている。君の今云った男の友達にそのままあてはまるじゃないか。
エ、どうだね。そう考えた方が、少くとも実際的ではないかね。君の今の話は、なかなかロマンチックで面白いことは面白いが、まさか、そんな夢のような話を信じる裁判官はあるまいぜ。
君は既に指を切っている。その指を御丁寧に錫の函に入れて、態々隅田川に投げ捨てている。そして、引越しをしたと見せかけて、空家の屋根裏に身を潜め、発見されたと知ると、いつの間にか屋根を打ち抜いて、女の身には想像もできない危い芸当を演じて逃走している。犯人でもないものが、こんな馬鹿な真似ができると思うかね。誰に聞かせたって、君が犯人だという事を疑うものは、一人だってある筈がないよ」
女は顔を上げなかった。泣き伏したままの姿勢で、絶望的に呟くばかりであった。
「アア、もう駄目です。……わたしは呪われているのです。……あなたはきっと、そうおっしゃるだろうと思いました」
「気の毒だが、君のお芝居は無駄骨折りばかりだったよ。サア、それではわしと一緒に出かけようか」
宗像博士がそう云って、懐中電燈を持ち変えた時であった。泣き伏していた女が、突然、物に驚いたように、ヒョイと顔を上げた。
「アラ、あなたは誰ですの?」
博士はこの突飛な言葉を聞くと、相手が気でも狂ったのかと怪しんだのであろう、ギョッとしたように、身動きをやめて、鋭く答えた。
「何を云っているのだ。わしは宗像だよ。私立探偵の宗像だよ」
「本当ですの? でも、何だか……、ねえ、すみませんが、その懐中電燈で、あなたの顔を照らして見て下さいませんか」
真実気が違ったのかも知れない。男装の女は、何か異常な熱心さで、床下から這い出して、博士の前に立ちはだかった。
「ハハハ……、妙な註文だね。よろしい。サア、よく見るがいい。君を捉えた男がどんな顔をしているか、よく見覚えて置くがいい」
博士は電燈の丸い光を、我れと我が顔にさし向けて、朗かに笑って見せた。
女は闇の中から、大きな眼鏡を光らせて、異様に執念深く博士を見つめた。いつまでも、いつまでも、獲物を狙う牝豹めひょうのような感じで、名探偵を凝視しつづけた。真暗な中から、ひどく弾んだ息遣いが、ハッハッと薄気味悪く聞えた。
二人とも身動きもしないで、永い間立ちつくしていた。それは実に不思議な、息づまるような光景であった。両人の身辺から、何とも名状の出来ない殺気のようなものが立ち昇るのが感じられた。
神社の森の中で、宗像博士と北園竜子との不思議な問答が行われている頃、警視庁の中村捜査係長は、麻布区龍土町にある、私立探偵明智小五郎の事務所を訪ねていた。
明智小五郎は、年こそ若かったけれど、私立探偵としては、宗像博士の先輩であり、随ってその手腕も、博士をしのぐものがあった。現に川手庄太郎氏も、この物語の初めにも記した通り、この事件をまず明智探偵に依頼しようとしたが、丁度旅行中で、いつ帰京するとも判らなかったので、それではと新進の宗像博士を選んだのであった。
明智は三重渦巻指紋の事件が起る少し前、政府からある国事犯捜査の依頼を受けて、朝鮮に出張し、京城を中心として半島の各地を飛び廻っていた。そして、首尾よくその目的を果し、今日帰京したばかりのところであった。
中村捜査係長は、明智から帰京の通知を受けると、何はおいても、今度の奇怪な殺人事件について、彼の意見を聞いて見たいと思った。係長は明智とは宗像博士よりもずっと早くからの知合で、ごくうちとけた交りを結んでいた。
予め電話があったので、明智は事務所の応接室に、久し振りの友達を待ち受けていた。
「あちらの仕事は大変うまく行ったそうだね。お目出度う」
中村警部は明智の顔を見ると、先ずその喜びを述べるのであった。
「有難う。つい今し方まで陸軍関係の晩餐会ばんさんかいに呼ばれていたんだが、恐ろしく歓待してくれてね、なんだか英雄にでもなったような気持がしているんだよ。しかしああいう種類の仕事は、随分敏捷に立廻らなければならないし、冒険味もたっぷりなんだが、実を云うと、僕なんかには、例えば今君がやっている、三重渦巻指紋の事件などの方が、ずっと魅力があるね」
明智は大仕事を済ませたばかりの、のびやかな気持から、いつもよりは多弁であった。
「君はあの事件を注意していたのかい」
「ウン、京城の新聞の簡単な記事で初めて見たんだが、それでも僕はすっかり惹きつけられてしまったよ。何とも云えない一種の匂いがあるんだ。僕の鼻は猟犬のように鋭敏だからね。ハハハ……、だから帰る途中大阪おおさかで、事件の最初からの新聞をすっかり揃えて貰って、汽車の中で読み耽って来たのさ」
「ハハ……、君らしいね。だが、そいつは都合がいい。実は今夜こんなに遅くやって来たのも、あれについて君の意見が聞きたかったからだよ。明日まで待っていられなかった程、僕は弱っているんだ。何だか壁のようなものにぶッつかってしまってね。白状すると全く途方に暮れているんだ。あんなに新聞が騒ぐものだから、世間がうるさくってね。僕がまあこの事件の担当者みたいになっているので、やり切れないのだよ。
で、君はあの事件の大体の輪郭は分っている訳だね」
「ウン、新聞に出ただけは分っている。だが、君の口から詳しい話が聞きたいもんだね」
「無論話すがね。それよりも、ここにいいものがあるんだ。僕個人の捜査日記だよ。君に読んで貰おうと思って持って来たのだ。口で云うよりも、これを一読してくれれば、一切がよく分ると思う」
警部はポケットから大型の手帳を取出して、そのある頁を開き、明智に手渡した。
明智はそれを受取ると、早速読み始めた。ソファに深く凭もたれ込んで、長い脚を組んで、その膝の上に手帳をのせ、丁寧に頁ページを繰って行った。
疑問の箇所にぶつかると、読むのをやめて、警部に質問する。警部は一々詳細に答える。そんなことを繰返して、たっぷり三十分程も費すうちに、明智は事件の経過をすっかり呑み込んでしまったように見えた。
「遠慮なく感想を聞かせてくれたまえ。僕は渦中にあるので、冷静な判断がむずかしいのだ。全く白紙でこの事件を見渡して、君はどう考えるね」
警部が促すと、明智はソファに凭れ込んで、腕組みをして静かに目をつむったまま、暫らく黙り込んでいたが、やがて落ちついた口調で話しはじめた。
「僕は宗像君とは二三度会ったばかりだが、彼の一種の才能には、深く敬意を表している。恐ろしい男だ。だが、今度の事件は流石の彼も、少なからず手古摺てこずっているようだね。いつも犯人に先手をうたれて、後へ後へと廻っている。被害者は予め分っているのに、一人だって助けることは出来なかった。宗像君にしては珍らしい不成績だね。エ、そうは思わないかね」
明智はそこで言葉を切って、じっと中村警部の顔を見た。なぜかその唇の辺に幽な微笑が浮かんでいる。警部にはその微笑の意味が分らなかった。商売敵がたきに対して非難めいた口を利いた事を、はにかんでいるのだと考える外はなかった。
「恐ろしい事件だ。この犯人は、あの俊敏な宗像博士よりも、更に一枚上手の役者らしいね。新聞は魔術師だなんて書き立てているが、全く魔術師だ。その上に、この犯人は露出狂だね。殺人その事よりも、その結果をできるだけ飾り立てて、世間に見せびらかしたいのだ。一種の狂人だね。狂人の癖に、恐ろしく賢い奴だ。名探偵と云われる宗像君を、思うままに飜弄するほど賢くて抜目のない奴だ。
しかし、宗像君も、なかなか味をやっているね。殊に隅田川に投げ込まれた小函の包装から、犯人の住所をつきとめたあたりは、流石に水際立っている」
「だが、それも後手ごてだったよ」
警部は投げ出すように云って、唇を噛んだ。
「この北園竜子という女のやり口が、又実に面白い。引越しの前晩に、沢山の罐詰とパンを買入れた点など、興味津々としてつきないものがあるよ。君の手帳には、その記事の横に赤い線が引いてあるが、これはどういう意味だね」
「僕には全く見当がつかない。多分犯人は人里離れた山奥へでも身を隠す用意をしたのだと思うが、何だかそれも信じられないような気がする。ただ、僕はその事実を聞いた時に、ゾーッとしたのだよ。なぜか分らないが、胸の中を冷い風が吹き過ぎたような、変てこな気持がしたんだ。それで赤線など引いたのだろう」
「ハハハ……、なる程渦中にあると盲目になるもんだね。だが、君の潜在意識はちゃんと真相を感づいていたのだよ。君がゾーッとしたというのは、その口の利けない潜在意識が、非常信号を発したのさ。ハハ……、僕には犯人の隠れ場所は大方想像がついているよ」
「エッ、隠れ場所が? 冗談じゃあるまいね。ど、どこだい? それは」
警部は思わず椅子から立上って、頓狂な声を立てた。
「なにも慌てることはない。お望みとあれば、君をその場所へ御案内してもいいよ。だが、宗像君程のものが、そこへ気のつかぬ筈はない。ひょっとしたら、今晩あたり、宗像君単独で、その場所へ犯人を捉えに行っているかも知れないよ」
「そんな近い所なのか」
「ウン、北園というのはなかなか利口な女だよ。君達を錯覚に陥れようとしたのだ。引越しをして、家を空家にしてしまえば、その家はもう捜査網から除外されるわけだからね。その日から、一番安全な隠れ場所に一変する」
「エッ、するとあいつは、あの空家に隠れているというのか」
「若しその女が、僕の想像しているような賢い奴だったらね」
「ウーン、そうか。成程、あの手品使いの考えつきそうな事だ。よしッ、兎も角も確めて見なくっちゃ。明智君、僕はこれで失敬するよ」
「まア、待ち給え。君が構わなければ、僕も一緒に行ってもいい。……ア、電話だ。一寸待って呉れ給え」
明智は急がしく卓上電話の受話器を取って、一こと二こと話したかと思うと、その受話器を中村警部の方へ差し出しながら、
「君だよ。捜査課の徳永とくなが君からだ。何だかひどく慌てているぜ。重大な用件らしい」
警部はすぐさま受話器を耳に当てた。
「エッ、宗像博士が? 発見したって?……ウン、青山の……明神の境内だね。……エ、社殿の床下?……ウン、分った、分った。よし、僕はここから直ぐ行くから、君達も手配をして、駈けつけてくれ給え」
中村係長は興奮のため、顔を真赤にして、ガチャンと受話器を置くと、明智に事の次第を告げた。
「やっぱり君の推察の通りだった。あの女は空家の屋根裏に隠れていたんだって。そこから屋根を破って逃げ出したのを、宗像博士が追いつめて、近くの神社の境内で捉えたらしい。博士から今電話で知らせて来たというのだ。僕はすぐ出かけるが、君は……」
「無論お供するよ。北園という女の顔も見たいし、久し振ぶりで宗像君にも会いたいからね」
明智は云いながら、呼鈴ベルを押して、助手の小林少年を呼び、電話で車を命じさせて置いて、手早く外出の用意をするのであった。
それから十分余りの後、例の神社の鳥居の前で車を捨てた二人は、暗闇の森の中へ入って行った。
向うにチラチラする幽かなる光を目当てに社殿の裏へ近づくと、そこに三人の黒い人影が、手に手に懐中電燈をかざして佇んでいた。モーニング姿の宗像博士と制服の二人の警官である。あとで聞けば、それは博士の知らせによって、附近の交番から駈けつけた警官達であった。
「宗像さんですか。中村です。丁度明智君を訪ねていましてね、捜査課から電話の知らせを受けたものですから、明智君と一緒に駈けつけたのですよ。警視庁からも間もなくやって来るでしょう」
闇の中で、中村警部が挨拶すると、宗像博士は、明智と聞いて一歩前に進み出でた。
「オオ、明智さん、お帰りになった事は新聞で承知していました。あなたのお留守中に、僕は途方もない難事件を引受けさせられてしまいましてね。やっと犯人を追いつめたかと思えば、ごらん下さい、この始末です」
博士は弁解でもするような調子で云いながら、社殿の床下へ懐中電燈の光を向けた。
「アッ、これは……」
中村警部が、驚きの余り、思わず叫び声を立てた。
それも無理ではない。社殿の床下、懐中電燈の丸い光の中に、まざまざと浮き出していたのは、無残な生人形のような、血みどろの死骸であった。
黒い背広の胸が開いて、その白いシャツが真赤に染まり、血の塊が電光を受けて、ギラギラと毒々しく光っていた。ソフト帽が脱げて、長い黒髪が乱れ、土気色つちけいろになった女の唇から顎にかけて、一筋二筋、赤い毛糸のような血が流れていた。女の右手には五寸程の白鞘しらざやの短刀が握られ、その刃先にベットリ血のりがついている。
「自殺ですね。しかし、どうしてこんなことに……」
警部の言葉を受けて、宗像博士が申訳なさそうに説明した。
「僕の手抜かりでした。あなたに報告して、警察の手で、あの空家の捜索をして頂けばよかったのです。しかし、決して抜けがけの功名をしようとした訳ではありません。確信がなかったのです。若しやという想像ぐらいで、警察を煩わずらわす気になれなかったのです。兎も角、その想像が当っているかどうか、僕自身で確めて見ようとしたのです。
すると、僕のその想像は当りすぎる程当っていました。そして、この女をここまで追跡して、なんなく捉えてしまったのです。ところが、何を云うにも僕一人だったものですからね。自動車を探すのに、この女を引きつれて歩く訳にも行かず、それよりは、電話でお知らせして、あなた方に来て貰った方がと考えたのです。
で、僕はこの女を、ここの床下の柱に縛りつけて置いて、近所の商家まで電話を借りに走ったのです。その商家の人に頼んで、交番にも知らせて貰ったのです。ホンの五分間程ここを留守にしたばかりです。
ところが、帰って見ると、この始末じゃありませんか。どうして解いたのか繩目を解いて、見事に心臓を突いて自殺していました。まさか短刀など隠していようとは思いも及ばなかったのです」
宗像博士は大切な犯人を殺してしまった失望に、説明もしどろもどろであった。
成程、死人の身体には、解けた細紐が幾重にも纒いつき、その端が側そばの柱に括りつけてあった。宗像博士が、常に身辺を離さぬ、絹糸製の丈夫な細紐である。
「どうしてこれを解くことが出来たんだろう。まさか縛り方が悪かったのではないでしょうね」
明智は柱の側にしゃがんで、その細紐を調べながら、半ば独言のように呟いた。
「僕もそれを不思議に思っているのです。捕繩ほじょうのかけ方ぐらいは心得ているつもりですが」
博士も不審に耐えぬ面持だ。
「宗像さん、この女は自殺したのではないかも知れませんね」
明智がふと何かに気附いたらしく、妙なことを云い出した。
「エッ、自殺でないというと?」
宗像博士も中村警部も、意外な言葉に、明智の顔を覗くようにして、聞き返す。
「他殺ではないかと思うのです。誰かがこの女の心臓を抉って、その短刀を死人の手に握らせた上、自殺と見せかける為めに、あとから繩を解いて置いたとも考えられますからね」
「しかし、誰が何の為めにそんな真似をしたのでしょう。犯人に恨みを含むものが、この森の中に忍んでいたとでもいうのですか」
宗像博士は腑に落ちぬ様子で、明智の軽率な判断をなじるように云った。
「イヤ、必ずしも恨みを含む者とは限りません。宗像さん、僕はさい前、中村君から、事件の経過を詳しく聞いたのですが、この事件には、男装の女らしい小柄な犯人の外に、もう一人、一方の目に眼帯をあてた大男がいるというではありませんか。
犯罪者が一身の安全を計る為めに、仲間を殺すというのは、例のないことではありません。僕は何だか、その辺の闇の中に、まだ眼帯の大男が身を潜めて、僕らの話を聞いているような気がするのですよ。つい身近にそいつの気配を感じるのですよ」
明智は闇の中の宗像博士の側に近よって、そのモーニングの腕を、指先で注意を促すように軽く叩きながら、声を低めて云うのであった。
「なぜです。仮令共犯者がここへ来たとしても、何もこの女を殺すことはないじゃありませんか。単に繩を解いて連れ去ればすむことではありませんか」
博士は彼の優れた商売敵を、嘲笑うかのような口吻くちぶりであった。
「しかし、彼としては、我々の常識では判断の出来ない深い事情があったのかも知れませんよ。宗像さん、僕はこの事件の全体の経過を、静かに考えて見て、どうもそんな気がするのです。なぜ眼帯の男は、共犯者を救わないで、その命を絶たなければならなかったか。そこにこの事件の恐ろしい謎があるのじゃないかと、そんな風に感じているのです」
「感じですか?」
宗像博士は一層皮肉な調子になった。だが、明智は少しもひるまない。
「そうです。僕はまだ明確に云うことは出来ないのです。しかし、この事件は最初から、理論を超越して、狂気と魔術に満ちていたではありませんか。犯人は、あらゆる不合理と不可能を易々と為なしとげているのです。救うべき共犯者を殺すなども、彼の狂気と魔術の一つの現われでないと誰が断言出来ましょう。眼帯の男は、なぜ北園竜子を殺さなければならなかったか。実に面白い謎々ですね。この難題が解けさえすれば、事件の全貌は自ら明かになって来るのじゃないでしょうか」
明智は言葉以上に、事件の奥にあるものを見通してでもいるように、静かに云うのであった。
「あなたは共犯者がこの女を殺したものと決めていられるようですが、僕にはどうも信じられませんね。しかし、それは兎も角として、眼帯の男を捉えなければならぬのは、云うまでもありません。僕は最初からこの事件に関係している責任上、あいつは必ず捉えてお目にかけます。そうすれば凡てが明かになるでしょう。魔術師の正体があばかれるでしょう」
博士は明智の言葉に反撥はんぱつを感じたのか、やや切口上になって云った。
「オオ、あなたは眼帯の男を捉えるとおっしゃるのですか。何か確信がおありなのですか」
明智はなぜかびっくりしたような、烈しい口調で聞き返した。皮肉ではなく、真実驚いているらしい様子だ。宗像博士ともあろうものが、もう一人の共犯者を捉えて見せると云ったからとて、何をそれほど驚くことがあるのだろう。まるで「そんなことは不可能ですよ」と言わぬばかりの口吻であった。
今夜の、明智の態度口吻こうふんには何となく解かいし難い所があった。日頃の明智なれば、他人の手がけている犯罪事件に口出しをするさえ好まぬ筈だ。それに、今夜はノコノコ犯人逮捕の現場へ出かけて来たばかりか、同業者の宗像博士を揶揄するかのような態度を示しているのだ。明智らしくないやり方である。これには何か深い訳があるのではないだろうか。
「あの男を捉える確信があるかとおっしゃるのですか。ハハハ……、マア、見ていて下さい」
博士は何を失敬なと云わぬばかりに、挑戦的な口調で、闇の中の明智の顔のあたりを、グッと睨みつけた。
明智はたじろがなかった。彼も亦、博士の顔を異様に見つめている。長い間妙な睨み合いがつづいた。中村警部は、後日その折の有様を形容して、二人の目から青白い火花が散るかと怪しまれたと語った程である。
そうしているところへ、鳥居の前に自動車の停車する物音が聞え、捜査課長を初め警視庁の人々が来着し、順序を踏んで、物慣れた現場調査が行われた。暫くすると、検事の一行も駈けつけて来た。そして一応の取調べが終ると、身柄引取人とてもない北園竜子の死体は、一先ず警視庁の死体置場へと運ばれたのであった。
明智小五郎は、調査の終るのを待たないで、先に帰宅したのだが、その帰りがけに、中村警部を人目のない場所に招いて、こんなことを囁いた。
「僕はこの事件にすっかり惹きつけられてしまった。一つ僕は僕で、宗像君の邪魔をしないように、調査をして見ようかと思うのだよ」
「調べると云って、もう主犯が死んでしまって、あとは共犯の眼帯の男を探すばかりだが、君は何か心当りでもあるのかい」
中村警部は、いぶかしげに聞き返す。
「イヤ、共犯者を探すことは、宗像君に任せて置けばいい。宗像君が、どんな風にしてあの眼帯の男を捉えるか、僕は非常に興味を感じている」
明智は意味ありげに答えた。闇の中でニヤニヤ笑っているらしい様子だ。
「それじゃ、後には何も調べることがないじゃないか。犯人は川手氏一家への復讐の目的を完全に果してしまったのだから、これ以上事件の起りようはないし、その犯人の一人は自殺か他殺か、兎も角死んでしまった。残っているのは眼帯の男ただ一人だ。あの男を探さないで、君は何を調べようというんだい」
「君は忘れているよ。川手氏一家がみなごろしになったといっても、川手庄太郎氏だけは、山梨県の例の山の家で行方不明になったことが分っているばかりで、まだその死骸も現われないじゃないか」
「ウン、それはそうだ。しかし、今まで行方が分らないところを見ると、川手氏も無論殺されているに違いない。でなくて、犯人があの怪指紋の指を切ったりする筈がない。あの指を切って、隅田川へ捨てたのは、奴らの復讐事業が全く終ったことを意味すると考える外はないじゃないか」
「そうも考えられるがね。しかし、川手氏に限って、犯人が例の死体を見せびらかす手を用いなかったのはなぜだろう。一番怨みの深い筈の川手氏を、安らかに眠らせて置くというのは、この犯罪の動機から考えても変じゃないか。これには何か、死体陳列の出来ないような特別の事情があったとしか考えられない。僕はそこに一縷いちるの望みをつないでいるんだよ。
いずれにしても確めて見なければならない。僕は明日N駅へ行って、あの一軒家を調べて見るつもりだ。そして、川手氏がどんな最期をとげたか、探り出して見るつもりだ。
だが、それは宗像君には云わないでくれ給え、警視庁の人達にも内密にして置いて貰いたい。僕は全く陰の人として、僕自身の好奇心を満足させれば、それでいいのだからね。分ったかい。じゃ、いずれ調査の結果は、君だけに報告するからね」
そう云い捨てて、明智は境内けいだいの闇を、鳥居の方へ立ち去って行くのであった。
それから数日は何事もなく過ぎ去ったが、丁度北園竜子変死から七日目の夕方、日本橋のK大百貨店に、飛降り自殺の騒ぎが起った。
百貨店閉館の間際に、その側面の道路を歩いていた人々は、空から大きな黄色いものが、爆弾のように落下して来て、目の前の鋪道に恐ろしい地響じひびきを立てて叩きつけられるのを見た。
飛降り自殺者であった。
一瞬間ギョッと立ちすくんだ人々が、やがて、それと知って駈けよって見ると、そこの敷石道の上に、カーキ色の労働服を着た男が、血にまみれて、押しつぶされたようになって息絶えていた。
附近の交番から警官が駈けつけて、調べて見ると、覚悟の自殺らしく、死体の胸のポケットから、一通の書置き様ようの紙切れが発見された。
警官は何気なくその紙切れを読み始めたが、見る見る顔色が変った。その飛降り自殺者こそ、外ならぬ川手氏一家鏖殺みなごろしの共犯人、例の眼帯の男であることが分ったからだ。
遺書には、
「自分は生涯をかけての大復讐の目的を果して、ここに自決する。この自殺は必ずしも予定の行動ではないのだが、私立探偵宗像博士の為に、素性すじょうを看破みやぶられ、数日に亙わたる執拗な追跡に、最早もはや逃亡の気力も失せたので、博士に手柄を立てさせるよりは、自ら一命を絶つ決心をしたのだ。自分は復讐の為に、川手の娘達を群衆の前に晒さらし物にした。今こうして賑かな人通りにむくろを晒すのも、その罪亡ほろぼしの積りである。
川手一家は自分の父母の仇敵である。父母は川手庄太郎の父の為に、自分が川手一家に加えたよりも、もっと残虐なやり方で殺害されたのだ。自分は父の今わの際きわの遺言に基いて、川手の子孫の根絶やしを思い立ち、生涯をその復讐事業の為に捧げたのである。
北園竜子は本名を山本京子きょうこといい、自分の肉親の妹だが、三重渦巻の異様な指紋を持っていたので、それを利用して川手一家のものを脅おびやかす手段とした。この目論見もくろみは、意外の効果を収め、自分達は三重渦巻の賊とまで呼ばれるに至った。その妹京子も宗像博士の為に捉えられ、遂に隙を見て自殺してしまった。自分はもうこの世に何の思い残すところもない。一刻も早く冥途めいどに行って、可愛い京子に会い、二人の生涯をかけての大事業の完成を喜び合いたいばかりだ」
という意味のことが、拙つたない鉛筆文字で細々こまごまと認められ、その終りに「山本始」と署名がしてあった。これで明智小五郎の竜子他殺説は全く誤解であったことが判明した。流石の明智も、この事件では、いらざる差出口さしでぐちをして、却って新進宗像博士の引立て役を勤めたかの観があった。彼の推察が見当違いであったのに反して、博士の口約は見事に果された。眼帯の男山本始を殺してしまったのは残念だけれど、博士の手が犯人の直後に迫っていたことは、彼の遺書によっても明かであった。
かくして、あれ程世間を騒がせた三重渦巻の怪殺人事件も、ここに全く終焉しゅうえんをつげたのである。被害者一家はみなごろしになってしまった。加害者は二人とも自殺をしてしまった。恨むもの、恨まれるもの、共に亡び去ったのだから、事件がこれ以上続きよう筈はなかった。さしもの大事件も、山本始の自殺を境として、もう過去の語草かたりぐさとなってしまったのだ。世人は勿論、警視庁自身さえ、そう考えていた。ただ一人、モジャモジャ頭の私立探偵明智小五郎を除いては、誰一人事件の終焉を信じないものはなかった。
殺人鬼山本始が自殺してから数日後のある夜、警視庁の刑事部長は、捜査課長や中村係長の進言を容いれて、この大犯罪事件の終焉を祝し、並々ならぬ労苦を嘗なめた民間探偵宗像博士を犒ねぎらう意味の小宴を催した。別段手柄を立てたわけではないが、捜査課長や中村係長の友人である明智小五郎も、席を賑わすためか、博士と共に招待を受け、主客五人、京橋区のF──レストラントの別室に、食卓を囲んで雑談の花を咲かせていた。
「宗像さんは、二人まで助手の命をとられているんだから、今度は一生懸命だったでしょうね。しかし、あなたのお蔭で、案外早く犯人達の自決を見て、何よりでした」
刑事部長が宗像博士を慰めるように云うと、博士は鼈甲縁の眼鏡を直しながら、恐縮の面持で答えた。
「イヤ、今度は最初から失策つづきで、実に申訳ないと思っております。いつも一歩の差で犯人にしてやられたのです。私の助手はともかくとして、折角依頼を受けた川手家の人達を、遂に救うことが出来なかったのは、実に残念でした。
私としては全力を尽したのですが、今度の奴だけは、明智さんも云われたように、どこか人間放れのした、気違いめいた智慧を持っている奴で、常識では想像もつかない手を打つので、非常な苦労をして、しかも苦労甲斐がなかったのです」
「明智さん、中村君に聞けば、あなたも今度の事件には非常に興味を持っていられたということですが、何か御感想は?……あなたは、北園竜子は自殺でないという御意見だったそうですね」
刑事部長は、なぜか明智の痛いところへ触れるような云い方をした。すると、明智はそれを待ち兼ねてでもいたように、
「そうですよ。僕はそう考えているのです」
とキッパリ云い切るのであった。
「エ、あなたは今でもあれを他殺だとお考えなのですか」
捜査課長がびっくりしたような表情で、横合よこあいから口を出した。
「他殺としか考えられませんね」
明智は極り切ったことのように、動ずる色もなく答えた。
それを聞くと、宗像博士の目が異様に光った。博士は明智の挑戦を感じたのだ。もう黙っているわけには行かぬ。
「ハハハ……、明智君、大人げないじゃありませんか。いくら名探偵の君でも、時に失策がないとはいえぬ。それを、一度口にしたことは、あくまで押し通そうというのは、つまらない意地というものですよ。飛降り自殺をした山本始は、竜子の実の兄だったじゃありませんか。いくら我身を守る為だといって、真実の妹を殺すなんて、考えられないことです。現に山本の遺書にも、妹は自殺したのだと、はっきり記してあったではありませんか。……それとも、あなたはあの山本の遺書を認めないとでもいうのですか」
博士はまるで後輩にでも云い聞かせるような態度で、明智をたしなめた。
「認めませんね。あんな都合のいい遺書なんてあるもんじゃない。あれはまるで出鱈目ですよ」
アア、何を云い出すのだ。明智は気でも違ったのではないか。彼は宗像博士との手柄争いに敗れて、まるで駄々ッ子のようにやけくそになっているのかとさえ怪しまれた。
「明智君、君は本気でそんな無茶を云っているのですか。酔っているのじゃありませんか、仮令悪人にもせよ、死の間際まぎわに書き残したあの告白が、出鱈目だなんてあり得ないことです。君こそ出鱈目を云っているとしか考えられませんね。それとも何か、あの遺書を認めない、はっきりした理由があるのですか」
一座の人々も、この口論では、宗像博士に味方しないわけには行かなかった。明智は今日はどうかしているのだ。博士が云ったように、酔っぱらっているのかも知れない。刑事部長と捜査課長とは、非難をこめた眼差まなざしで、無言のまま明智の顔を見つめるばかりであった。
ところが、博士の詰問に答えた明智の言葉は、ますます意外な、殆んど健康人の論理を無視したようなものであった。アア、明智は本当に気が違ってしまったのではあるまいか。人々はもう、あっけに取られて、急には言葉も出ない有様であった。
「無論、遺書を認めない理由ははっきりしていますよ。あの自殺した男が、果して犯人の一人であったかどうかを疑うからです」
「エッ、なんですって? 君は、犯人でもない男が、あんな遺書を書いて飛降り自殺をしたというのですか」
宗像博士は開いた口が塞がらぬという体ていで、殆んど笑い出さんばかりの表情であった。
「眼帯の男の顔をはっきり見届けたものは、誰もないのです。ただ無精髭を生やした労働者風の大男ということが分っているばかりです。それがあの飛降り自殺をした男と同一人であったと、どうして保証出来ましょう。無論、眼帯の男の筆蹟も分っていないのですから、あんな遺書など誰にでも偽造出来るじゃありませんか」
明智の止とめ度どもない放言に、宗像博士は激怒のために真赤になってしまった。
「それじゃ君は、あの自殺した男が、偽物だったというのですか。馬鹿馬鹿しい、犯人でもないものが、態々遺書まで用意して自殺するなんて、君は一体何を考えているのです。酒の上の戯談じょうだんでないとすれば、君は気でも違ったのではありませんか」
「ハハハ……、そうかも知れませんね。相手が気違い犯人ですから、僕もおつき合いをして気が狂ってしまったのかも知れません。
僕自身でさえ、今僕の考えていることが、余り並はずれな奇怪な事柄なので、本当に頭がどうかしたのではないかと、不安になるくらいです。例えば、僕はまだこんなことも考えているんですよ。
飛降り自殺をした男が犯人でなかったばかりでなく、あの北園竜子さえ、犯人かどうかよく分らないということです。僕は確証がほしいのです。あの二人があなたの信じているように、真犯人であってくれればいいと、僕は随分その確証を掴むために悩んだのですが、遺憾ながら確証は全くないことが分ったのです」
ここまで来ると、一座の人々はもう黙っているわけには行かなかった。明智は実に驚くべき妄想を描いているらしいことが分って来たからだ。彼は眼帯の男を否定し、北園竜子をすら否定せんとしている。すると、この殺人事件の犯人は、まだ一人も捕まっていないことになるではないか。事件が落着した心祝いの集つどいに招かれて、彼は事件の落着そのものを、頭から否定しているのだ。アア、これは一体どうしたことであろう。
刑事部長も捜査課長も、何か口々に驚きの叫び声を発したが、当の宗像博士の憤慨はもう極点に達していた。博士は例の三角型の顎髯を、ピリピリ震わせて、思わず椅子から腰を浮かし、明智の前に握り拳を振廻しながら、わめくのであった。
「明智君、黙りなさい。君は僕に何か私怨しえんでもあるのですか。僕が解決した事件を、なぜぶち毀こわそうとするのです。しかし、お気の毒だが、君の云い草は支離滅裂、まるで気違いのたわごとじゃないか。そんな出鱈目な論理で、僕の仕事にけちをつけようなんて、君も余りに子供らしいというものだ。
北園竜子が犯人でないなんて、一体どこからそんな結論が出て来るのです。君は三重渦巻の指紋を忘れたのですか。犯人でもないものが態々指を切断して、屋根裏に身を隠すなんて、そんな馬鹿馬鹿しいことが出来ると思うのですか」
「ところが、僕は北園竜子があの怪指紋の持主だったからこそ、真犯人ではないと考えるのですよ。エ、宗像君、この意味がお分りですか」
明智は落ちつき払って、ニコニコ笑ってさえいるのだ。
「分りませんね。そんな気違いのたわごとは、僕には少しも分らない。……皆さん、あなた方には大変失礼ですが、私はもう一刻もこんな気違いと同席するのは御免です。中座させて頂きます」
宗像博士は椅子から立上って、今にも食堂を立去ろうとする気組みを見せた。
「マア、待って下さい。主賓しゅひんのあなたに帰られては、今夜の集りの意味がなくなってしまいます。……明智さん、あなたは今夜はどうかしていらっしゃるようですね。折角我々が宗像さんの慰労の宴を催したのですから、この席で論争をなさることは差控えて頂きたいと思います。兎に角、事件は落着して、世間でもホッとしているのですから、この際、根拠のない否定論は慎んで下さらないと困りますね」
捜査課長が仲裁するように云って、取ってつけたように笑って見せた。
「イヤ、皆さんが、僕が無茶を云っているようにお思いなさるのは、無理もありません。しかし、僕の考えには、決して根拠がない訳ではありませんよ。僕の悪い癖でしてね、筋路すじみちを話さないで、突然結論から始めるものですから、僕の頭の中の論理を御存じない皆さんは、まったく感情的な暴言のように感じられるのです。
では、順序を立てて、なぜ僕が二人の犯人を偽物だなどと云い出したか、その訳をお話しましょう。宗像君も、そんなに立腹しないで、マア一応、僕の話を聞いて下さい」
明智は、両手を上げて制するようにしながら、いつに変らぬニコニコ顔で一同をなだめるのであった。
酔っぱらったのでもなければ、頭が変になったのでもない。明智は何かしら、一座の人々には想像も出来ないような、奇怪な推理を組立てているらしい。ひょっとしたら、彼の犯人自殺否定論には、深い根拠があるのかも知れない。人々はそう考えると、半信半疑ながら、兎も角、明智の説明を聞いて見る外はなかった。宗像博士も不承不精ふしょうぶしょうに着席した。
そこで、明智が話しはじめる。
「僕は中村君からこの事件の経過を聞いた時に、殺人鬼の行動に、一つの心理的な矛盾むじゅんがあることを気附いたのです。そして、その角度から、宗像君とは全く別の見方で、この事件を眺めて見ようと思い立ったのです。
その矛盾というのは外でもありません。犯人はなぜ川手氏の死体を衆人の前に陳列して見せなかったかということです。
川手氏の二人の娘さんは、実に残酷なやり方で、見世物のように衆人の眼の前に晒されている。娘さん達でさえそんなひどい目にあわせた復讐者が、当の川手氏に限って、その挙に出なかったのには、何か特別の理由がなくてはならない。若しかしたら、犯人は川手氏を、死体の陳列は出来ないけれども、しかし、死体の陳列などよりももっと残酷な方法で殺害したのではないか。例えば長い時間かかって、徐々に死んで行くような、極度に残虐な方法を案出したのではないかと考えたのです。
そこで僕は竜子が自殺をした翌日、川手氏が行方不明になったというN駅の近くの、山中の一軒家へ出かけて行きました。ある理由の為に、このことは、ここにいる中村君以外には、誰にも知らせず、こっそり出発したのです。
あの一軒家は、今では留守番もない全くの空家になっているので、門を開くことも出来ず、僕は非常な苦心をして、堀を渡り、高い塀をよじ登って、邸内へ忍び込んだのです。そして、たっぷり一日かかって、屋内、屋外を残るところなく捜索しました。
しかし、その捜索の模様などを、ここで詳しくお話しする必要はありません。すぐに結果を申上げますと、結局、僕の推察が当っていたのです。つまり、僕は川手庄太郎氏を発見したのです」
そこまで聞くと、刑事部長はもう黙っていられなくなった。
「川手氏の死骸をですか。一体どこに隠してあったのです。当時あの地方の警察が、山狩りまでして捜索しても、とうとう発見出来なかったのですが」
「イヤ、死骸ではありません。僕は生きている川手さんを発見したのです」
明智の意外千万な言葉に、人々は色めき立った。
「エッ、生きていた? それは本当ですか。じゃあ犯人は肝腎かんじんの川手氏に復讐をとげなかったわけですか」
「イヤ、そうではありません。犯人は犯罪史上に前例もないような、残酷極まる方法で、川手氏に復讐したのです。若し僕の発見が、もう一日おくれたならば、恐らくこの世の人ではなかったでしょう」
「一体、それはどんな方法です」
捜査課長が、ひどく興奮して、思わず口をはさんだ。
「生き埋めです。川手氏は棺桶ようの木箱の中へ入れられて、あの家の庭の林の中に埋められていたのです」
「で、あなたはそれを救い出したのですか。一体どうして今日まで生き永らえていたのです」
「今日ではありません。僕がそれを発見したのは、今から十日も前なのです。川手氏が行方不明になってから丁度五日目でした。五日の間、土の中にいたばかりです。
多分川手氏をいやが上に苦しめるためでしょう、その棺桶ようの箱には、ところどころに隙間が作ってあったのです。つまり、あっけなく窒息ちっそくしてしまわないように、出来るだけ長く闇の地中で苦しみもがくように、息の通う場所を作って置いたのです。それに、埋められた位置も割合に浅く、土と落葉の混ったようなもので蔽われていたのですから、川手氏は棺の中でも、辛うじて呼吸いきをつづけることが出来たのです。
しかし、ただ息が出来るというだけで、食いものは無論なく、厳重に釘づけにされた厚い板の中で、殆んど身動きも出来ず、飢餓と迫って来る死の恐怖とのために、可哀想に川手氏は髪の毛がすっかり白くなっていた程です。
僕がどうして川手さんの埋められている場所を発見したかというと、若しやそんなことではないかと、予め想像していたので、庭の林の中なども念入りに歩き廻って見たからです。警察の人達が、あれを発見出来なかったのは、まさか邸内の土の中に埋められていようなどと、考えても見なかったためでしょう。
そこで、僕は川手さんを助け出して、僕が乗って行った自動車にかつぎ込み、そのまま甲府市のある病院へ入院させたのです。そして、数日後、川手氏の元気が回復するのを待って、コッソリ東京に連れ帰り、実は、今僕の家にかくまってあるのです。
勝手な真似をしたとお叱りを受けるかも知れません。しかしこれには止むを得ない訳があったのです。甲府市の病院でも、態と川手さんの名を隠して置きましたし、無論警察へも届けませんでした。
なぜかといいますと、僕は川手さんの口から、この事件の裏に潜む、あらゆる秘密を探り出そうとしたからです。それには、瀕死の病人も同然のあの人の記憶が、完全に甦よみがえるのを待たなければならなかったのです」
「で、川手氏はすっかり元気を回復しましたか。元々通りの健康体になりましたか」
宗像博士が初めて口を開いた。博士の顔には、何は兎ともあれ、事件依頼者の無事を喜ぶ色が浮かんでいた。
「イヤ、まだ健康体とは云えません。僕の家の一間にとじこもったきり、寝たり起きたりという状態です」
「そうですか。何としてもお手柄でした。それを聞いて僕も心が軽くなりましたよ」
博士は他意もなく明智の手柄を称たたえたが、ふと何事か思い出した様子で、
「アア、話に夢中になっていて、うっかり忘れるところだった。皆さんちょっと失礼します。ある事件依頼人に、電話をかける約束があったのです。じき戻りますから明智君、話の続きは暫らく待っていて下さい」
と慌しく電話室へと立って行った。
「明智さん、そんなに、私立探偵の権能を揮ふるわれては困りますね。川手氏を発見しながら、無断で自宅にかくまって置くなんて、事を荒立てれば、何かの犯罪を構成しますぜ」
刑事部長は半ば戯談のように、明智の勝手な振舞を責めた。
「イヤ、その説明は、今に詳しく申上げますが、決してお叱りは受けないだろうと信じています。犯人が魔法使みたいな恐ろしい奴ですから、こちらも少し変則な手段をとらなければならなかったのです」
明智は弁解しながら、なおも川手氏発見の模様を何かと話しつづけるうちに、やがて、電話室から宗像博士も席に戻って来た。
「御用はすみましたか」
明智は非常に愛想よく、ニコニコ笑いながら声をかけた。
「すみましたよ。どうもお待たせしました。では、今のお話をつづけて頂きましょうか」
博士も妙に丁寧な口調で答え、何かひどく嬉しい事でもあるようにロイド眼鏡の中の目を細め、三角髯をゆるがせながら、ニタニタと笑って見せるのであった。
博士が電話室から帰って来ると、その間中絶していた話題が、刑事部長の質問でまた元に戻った。「で、あなたは、その川手氏の口から何か聞き出されたのですか。北園竜子が真犯人でないというようなことを」
「イヤ、川手氏は別に何も知ってはいないのです。ただ今度の犯人の親達が川手氏のお父さんのために無残な最期をとげた、その復讐のために川手氏一家の鏖みなごろしを企てたということ、犯人の一人の眼帯の男は本名を山本始といい、男装の女はその実の妹であることなどが分ったばかりで、二人とも変装をしていたので、犯人達の顔さえはっきりは覚えていないという仕末しまつです」
明智が答えると、刑事部長は畳みかけるようにして、質問の二の矢を放った。
「それじゃ、百貨店の屋上から飛降り自殺をした男の遺言と全く一致しているじゃありませんか。あなたが、北園竜子や、あの自殺をした男が真犯人でないとおっしゃる論拠は?」
「それは論理の問題です。中村君から詳しいことを聞いて見ますと、この事件は初めから終りまで、あらゆる不可能の連続と云ってもいいくらいです。彼等が魔術師と云われた所以ゆえんもそこにありました。僕はそれらの不可能について静かに考えて見たのです。真実の不可能事が行われ得る筈はありません。それが行われたように見えたのは、何かその裏に、何人なんびとも気附かぬ手品の種が隠されていたと考える外はないのです。その秘密さえ解き得たならば、この事件はこれ迄までとは全く違った相貌そうぼうを呈して来るかも知れませんからね」
「で、君はその秘密を解いたというのですか」
横合から宗像博士が堪り兼ねたように口を出した。
「解き得たつもりですよ」
明智は、博士の方に向き直ってニッコリ笑って見せた。博士も嘲あざけるように笑い返したが、二人とも目だけは異様に光っていた。そして、その四つの目の間に、何かしら烈しい稲妻のようなものが閃き合うのが感じられた。
「では、参考のためにその論理とやらを聞きたいものですね。事件の最初から、二人の部下まで犠牲にして、目と耳と足と頭を働かせて来た僕の解釈が正しいか、事件が殆んど終ってしまってから、机上きじょうに組み立てた君の空想が正しいか、一つ比べて見ようじゃありませんか。ハハハ……」
博士は無遠慮な笑い声を立てて、腕組みをしながら椅子の背に反り返って見せた。
「イヤ、そういう感情の問題はともかくとして、我々としても一応明智さんの論理を承わらなければなりません。若し北園が真犯人でないとすると、この事件は最初からやり直しですからね」
捜査課長も真剣な表情で、明智を促すのであった。
「僕はこの事件の最初からの、常識では判断の出来ないような不思議な出来事を、すっかり、ここに書き出して見たのですがね」
明智はポケットから手帳を取出して、その頁を繰りながら、落ちつき払って語りはじめた。
「この事件に最も異様な色彩を与えたのは、申すまでもなく、例の怪指紋です。犯人はあの指紋を実に巧みに使用して、川手一家の人々に、どれほどの恐怖を与えたか知れません。あの指紋をじっと見ていると、何かこう悪魔の呪いとでも云ったようなものが、ひしひしと感じられますからね。
しかし、あの指紋は、非常に奇怪ではありますが、別に不可能が行われたわけではありません。北園竜子が偶然あんな恐ろしい指紋を持って生れたのだとすれば、指紋そのものには何の不思議もありません。ただ異様なのは、その指紋の現われ方です。たとえば、川手雪子さんの葬儀の日に、告別式に列した妙子さんの頬に、どうしてあの指紋が捺されたか。また、お化け大会の中で、骸骨や人形の生首が持っていた通行証明の紙片かみきれに、どうしてあの指紋がついていたか、それから川手氏の話によりますと、あの人が、宗像君に連れられて自邸を逃げ出す直前に、女中の持って来た煎茶茶碗の蓋にまで、例の指紋がついていたそうですが、事件の最中で見張りの厳重な川手家の台所へ、どうして犯人は忍びこむことができたか。これらは殆んど不可能に近い奇怪事と云わねばなりません。
その他、川手雪子さんの殺害の通告状が、どこからともなく川手家の応接室に現われた不思議、雪子さんの葬儀の日に、川手氏のモーニングのポケットに復讐者の脅迫状が忍び込ませてあったことなど、そういう小さな出来事まで拾い上げれば、殆んど際限もない程ですが、僕はこれらの不思議を、あらゆる角度から眺めて、そのすべてを満足させるような一つの仮説を組み立てて見ました。
僕は正面から解決することのできない、非常に難解な事件にぶッつかった場合は、いつもこの論理学上の方法を用いることにしているのです。その仮説が、事件のあらゆる細目にぴったり当てはまって、少しも無理がないことが確められたならば、それは最早や仮説ではなくて真実なのです。今度の事件が丁度それでした。そして、僕の組み立てた仮説は、あらゆる細目を満足させたのです。
ここで、その僕の推理の過程を一々説明するのは、少し煩雑はんざつすぎると思いますから、今度の事件の様々の不思議の中から、最も重大な、また異様な三つの出来事を拾い出して、僕の仮説がどんなものであるかをお察し願うことにしますが、その第一は例のお化け大会のテントの中から、黒覆面の犯人がどうして逃げ去ることができたかという点です。
あのテントの外には沢山の見物人が群むらがっていました。テントの中には警官や興行者側の人達が四方から犯人を取り巻いていました。その真中の鏡の部屋の中で、犯人はただ一挺のピストルを残したまま、消え失せてしまったのです。直ちに鏡の部屋は打毀うちこわされ、地中に抜け穴でもあるのではないかと、十二分に調べたと云いますが、そういう手品の種は何一つ発見されなかったのです。
この魔法めいた不思議を、どう解釈すればよいのでしょう。鏡の部屋に何の仕掛けもなく、十数人の追手の目に間違いがなかったとすれば、犯人は絶対に逃げ出す術すべはなかったのではありますまいか。つまり犯人はそこにいたのではないでしょうか。僕はこういう仮説を立てて見たのです。犯人は決して逃げなかった。最後まで追手の真中に踏みとどまっていたのだ。しかも、追手達はそれが犯人だとはどうしても考え得ないような、一種不可思議の手段によって、ちゃんとその場にいたのだという仮説です」
明智はそこで言葉を切って、謎のような微笑を浮べながら一座を見廻したが、誰も物を云うものはなかった。人々は酔えるが如く押黙って、ただ話手の顔を凝視するばかりであった。
「第二は山梨県の山中の川手氏の隠れ家を、犯人はどうしてあんなに易々と発見することが出来たかという点です。川手氏の話によりますと、宗像君は犯人の尾行を防ぐために、実に驚くべき努力をしておられます。宗像君と川手氏とは、念入りな変装をした上に、市内のビルディングで籠抜けをしたり、態々別の方角へ汽車に乗ったり、目的地へ達しても駅へは降りないで、危険を冒して進行中の汽車から飛降りたり、実にここには云い尽せない程の苦心をしているのです。
ところが、それ程までにして、川手氏を匿まった場所が、忽ち犯人によって発見されたというのは、犯人が千里眼せんりがんの怪物でもない限り殆んど不可能なことではありませんか。これをどう解釈すればよいのでしょう。僕の仮説によれば、この場合もまた、犯人はそこにいたのです。絶対にそれと分らぬ一種不可思議の手段によって、絶えず川手氏を尾行していたのです。
お分りになりますか」
明智はまた言葉を切って、一同を見廻したが、一座の沈黙は深まるばかり、誰一人口を利くものもなかった。
「第三は北園竜子がなぜ自殺をしたかという点です。縲紲るいせつの恥かしめを逃れるために自決したと云えば、一応筋道が通っているようですが、実はそこに非常な矛盾があります。一種の心理的不可能と云ってもよいのです。
彼女は決して縲紲の恥しめを受けることはなかった。なぜと云って、短剣で自殺するためには、先ず床下の柱に縛りつけられていた繩を解かなければならなかったからです。ところが、繩を解いた以上は、最早や自殺する必要はどこにもない。闇にまぎれて逃げ去ってしまえばよかったのです。屋根裏に隠れてまで逃亡を計った女が、繩を解いて自由の身になりながら、突然自殺する気持になるなんて、全く考えられないことではありませんか。
一方また、彼女は自殺したのではなくて、神社の森の中に隠れていた同類に殺されたのだという考え方もありますが、それは一層不合理です。同類が我が身の安全を計るために相棒を殺したのだとすれば、何もわざわざ繩を解くことはないのです。縛られているのを幸さいわい、闇にまぎれてこっそり刺し殺してしまえばよい訳ですからね。
自殺の場合は繩が解ければ死ぬ必要はなくなるのだし、他殺の場合は殺すために繩を解く必要はないのですから、残る可能な解釈はただ一つ、何者かが彼女を殺害して、後から自殺と見せかけて置いたという考え方です。これは同類の仕業ではありません。同類なれば既に幾人もの殺人罪を犯しているのですから、今更苦心をして自殺を装わせる必要は少しもないのです。
僕が今度の事件の裏には、何か非常な秘密が伏在しているのではないかと、ふと気附いたのは、実はこの事実からでした。繩を解きながら、しかも自殺していたというこの事実からでした。僕はひどく難解な謎にぶッつかったのです。
先程申上げた仮説は、無論これにも当てはまります。前後の事情は悉くその仮説の犯人を指しているのです。しかし、何かしら一つ足りないものがありました。僕の推理の環に一寸した切れ目が残っていたのです。
それを川手氏が埋めてくれました。川手氏を生埋めにする直前、犯人はまだもう一人復讐しなければならぬ人物が残っていると告白したといいます。それは、川手氏自身は少しも知らなかったのですが、妾腹しょうふくに出来た妹さんがどこかにいて、犯人はその妾腹の子まで根絶やしにするのだと豪語していたというのです。
皆さん、これを聞いて、僕がどんなにハッとしたかお分りですか。まるで、闇の中に突然太陽の光が射した感じでした。僕の推理の環は完全につながったのです。何もかも白昼のように明かになったのです。
川手氏のお父さんが獄中で病死したのは、川手氏の十歳の時だと云いますから、そのまだ見ぬ妹さんというのは、いくら若くても、川手氏と十以上は違わない訳です。川手氏は今四十七歳だそうですから、妹さんは四十歳近くの年配です。これは北園竜子の年齢とピッタリ一致するではありませんか」
宗像博士はさい前から何かいらだたしそうに頻しきりに身動きしていたが、明智の言葉がちょっと途切れると、もう堪らなくなったように、いきなり取って着けたような笑い声を立てた。
「ワハハハ……、明智君、夢物語はいい加減にして貰いたいね。黙って聞いていれば、君の空想はどこまで突走るか、分りやしない。だが、いくら何でも、君はまさか、北園竜子がその川手氏の妹だなんて云い出すのではあるまいね」
「ところが僕はそれを云おうとしていたのですよ。北園は犯人ではなくて被害者だったということをね」
明智の調子はいよいよ皮肉になって行くのだ。
「ハハハ……、これはおかしい。君は、犯人でもないものが変装して屋根裏に隠れたり、女の身で、屋根から飛び降りて逃げ出したりするというのかね。それに、何よりの証拠は、北園竜子のあの指紋だ。君は、あの怪指紋のことを、すっかり忘れてしまっているじゃないか」
「イヤ、決して忘れてやしない。北園竜子は怪指紋の持主だったからこそ、本当の犯人でないと考えるのです。宗像君、僕達は常識的な出来事を論じているのではない。常識を超越した恐るべき犯罪者を相手にしているのですよ。僕の想像力なんか、今度の犯人のずば抜けた空想に比べたら、取るにも足らぬものです。アア、何というすばらしい手品だ。僕は犯人のこの空想力を考えると、余りの見事さにうっとりしてしまう程ですよ。
犯人は事件の初めから終りまで、これでもかこれでもかと、実に執拗にあの怪指紋を見せつけましたね。俺はこういう特徴のある指紋を持っているのだぞ、この指紋の持主こそ真犯人だぞと、凡あらゆる機会を捉えて広告している。そして、それが同時に川手氏をこの上もなく脅えさせる手段ともなったのですから、犯人の狡智こうちには全く驚く外ありません。
しかし、これは無論逆を考えなくてはならないのです。犯人が広告している事実には、いつもその裏があるのです。あの怪指紋は決して犯人のものではない。イヤ、それどころか、あの指紋は逆に被害者の指についていたのです。
皆さん、犯人の智慧の恐ろしさは、この一事いちじによっても、はっきりと分るではありませんか。三重渦巻の怪指紋は、その紋様が象徴している通り、実に三重の大きな役割を勤めたのです。第一はそのお化けめいた隆線模様によって、被害者を極度に脅えさせ、復讐をいやが上にも効果的ならしめた事、第二は世人にこの怪指紋の持主こそ犯人だという錯覚を与えて、犯人自身の安全に資しした事、そして第三は、その怪指紋を当の復讐の相手である川手氏の妹さんの指から盗んで来たこと、つまりそうして最後には殺人罪の嫌疑を悉く被害者自身に転嫁てんかしようと、深くも企らんだ訳です。
犯人はどうかして、当の仇敵である川手氏の妹さんの指に、偶然あの奇妙な指紋のある事を発見したのです。そして、そこからこの復讐事業の筋書が仕組まれたのです。犯人はある手段によって(この手段がまた非常に面白いのですが)川手氏の妹さんに接近しました。恐らくそうして妹さんの指紋を盗み、精巧な写真製版技術によって、怪指紋のゴム印を造ったのだと思います。そのゴム印は絶えず犯人のポケットに忍ばされていました。
皆さん、あれは巧みに出来たゴム印に過ぎなかったのです。それが魔術師の手品の種だったのです。ゴム印なればこそ、あらゆる不可能を超越して、どんな場合にでも、例えば被害者の妙子さんの美しい頬にさえ、混雑にまぎれて、ソッと押しつけることも出来たのです。
しかし、犯人のこの奇妙な手品が、その指紋の持主である川手氏の妹さんには、全く想像も出来ない程のひどい打撃となって帰って行きました。彼女は最初の間は気もつかないでいたかも知れませんが、新聞に殺人鬼の怪指紋として、その拡大写真が掲載されたときには、ハッとばかり、自分自身の指先を見つめないではいられなかったことでしょう。アア、その時の彼女の驚きと恐れがどれ程であったか、想像するさえ身の毛もよだつ程ではありませんか。
彼女はもう絶対に殺人の嫌疑を免まぬかれることは出来ないと信じ込んでしまったのに違いありません。そこで、呪わしい指を切断して隅田川に捨てるようなことにもなり、転宅と見せかけて屋根裏に潜み、捜査の手がゆるんでから、どこかへ逃亡しようと企らむにも至ったのです。まるで犯罪者のような奇矯な行動ではありましたが、相談相手とてもない、独り身の女としては、恐ろしさに気も顛倒てんとうして、そんな気違いめいた考えになったのも、少しも無理とは思われません。
しかし、彼女はそうして、結局真犯人の思う壺つぼにはまったのです。それ程彼女を苦しめたというだけでも、犯人の目的は半ば達せられたのですが、彼は更にこの哀れな女をあくまで追いつめて、無残にも刺し殺してしまいました。そして、自殺のように見せかけて、何喰わぬ顔をしていたのです。
イヤ、それだけではありません。犯人の悪企みには殆んど奥底がないのです。皆さんは北園竜子の召使の老婆の証言によって、竜子がどこの誰とも知れぬ四十歳余りの男と、ひそかに逢曳あいびきを続けていたことを御存知でしょう。僕の仮説は、その相手の男というのが、外ならぬ真犯人自身であったことを教えてくれます。彼はそうして、仇敵の娘を弄もてあそび、復讐事業の材料として指紋を盗み、その上に、竜子のアリバイを悉く抹殺することに成功したのです。つまり、今度の事件で数々の殺人罪が犯された当日は、竜子は必ずこの男の為に呼び出され、家を留守にしていたという事実があるのです。
若しアリバイさえ成立すれば、いくら気の弱い竜子でも、まさか指を切るような事はしなかったでしょうが、それが全く見込みがないと分ったものですから、ああいう気違いめいた行動に出たのでしょう。真犯人はあらゆる点にいささかの抜かりもなかったのです」
人々は、今は石のように身動きもせず、ジットリと汗ばむ手を握りしめて、微びに入いり細さいを穿うがって鮮かな、名探偵の推理に聴き入っていた。だが、ただ一人宗像博士だけは、彼の打立てた推理が、見る見る片っ端からくずされて行くのを見て、焦躁しょうそうの色蔽おおうべくもなく、顔色さえ青ざめて、追いつめられた獣けだもののように、隙もあらば反撃せんと、血走る目をみはっていた。
「中村君が調べた戸籍簿によりますと、竜子は北園弓子というものの私生児ですが、すると、川手氏のお父さんの妾であった女はこの弓子でなければなりません。僕は川手氏に、北園弓子という名前に記憶はないかと訊ねて見ました。すると、川手氏は、その名をちゃんと記憶していたのです。幼い時分二三度家へ来た事のある知合しりあいの美しい女に、確かそういう名前のものがあったという答えでした。最早や何の疑う所もありません。竜子こそ川手氏のお父さんの妾腹の娘だったのです。犯人ではなくて、被害者の一人だったのです」
この時テーブルの一方に、ガタガタという音がしたので、一同その方を眺めると、真青になった宗像博士が、果し合いでもするような顔で突立っていた。立上る時、興奮の余り、つい椅子を倒したのである。
「明智君、実に名論です。しかし、それはあくまで名論であって、事実ではない。論理と空想の外には、現実の証拠というものが一つもないじゃないか。証拠を得ようにも、残念ながら竜子が死んでしまっているので、今更どうすることも出来やしない。
これで君の竜子が犯人でなかったという空想はよく分ったが、それじゃもう一人の犯人、あの眼帯の男の方は一体何者だね。これも犯人ではなくて被害者だったとでもいうのですか」
明智は少しも騒がず、にこやかに答えた。
「一種の被害者です。しかし、川手氏の一族だという意味ではありません。彼はこの事件とは何の関係もない、恐らくは一人のルンペンなのでしょう。
犯人は眼帯の男によく似た大男を探して、甘言を以て眼帯の男の服装を与え、多分は御馳走もしたことでしょう。或は金銭を与えもしたでしょう。そして、閉店間際の百貨店の、人影もない屋上に誘い出し、例の偽の遺書をポケットに突込んで、隙を見て地上へ突き落したのです。これは僕の想像ですが、恐らく間違ってはいないと思います」
明智は強い語調で云って、じっと博士の目の中を見つめたが、博士はややまぶしそうに、その視線を避けながら、しぼり出すように、空ろな笑い声を立てた。
「ハハハ……、またしても想像ですか。僕は君の空想を訊ねているのじゃない。確証のある事実が聞きたいのだ」
「その答は簡単ですよ。僕は真犯人の眼帯の男が、まだ生きてピンピンしていることを、よく知っているからです」
「ナニ、生きている? それじゃ君は、その犯人がどこにいるかも知っているのだね」
「無論知っていますよ」
「では、なぜ捉えないのだ。犯人のありかを知りながら、こんな所で無駄なお喋舌しゃべりをしていることはないじゃないか」
「なぜ捉えないというのですか」
「そうだよ」
「それは、もう捉えてしまったからです」
明智の意外な言葉に、一座は俄に色めき立った。刑事部長も、捜査課長も、中村警部も、思わず椅子から腰を浮かして、口々に何か云いながら、明智につめよる気配を見せた。
宗像博士の血走った両眼は、異様にギラギラと輝きはじめた。
「犯人を捉えたって? オイオイ、冗談はよしたまえ。一体いつどこで捉えたというのだ」
「犯人はいつもそこにいたのです」
明智は平然として答えた。
「お化け大会の中でも、川手氏が山梨県の山中に身を隠す途中でも、北園竜子が一命を失った刹那せつなも、犯人は常にそこにいたと同じように、今も犯人はここにいるのです。犯人は全く気附かれぬ保護色に包まれて、我々の目の前に隠れているのです」
それを聞くと、刑事部長はもう打捨てては置けぬという面持で、鋭く質問した。
「明智君、君は何を云っているのです。ここには我々五人の外に誰もいないじゃありませんか。それとも、我々の中に犯人がいるとでもいうのですか」
「そうです。我々の中に犯人がいるのです」
「エ、エ、それは一体誰です」
「この事件での数々の不可能事が起った時、いつもその現場に居合わせた人物です。被害者川手氏を除くと、そういう条件にあてはまる人物は、たった一人しかありません。……それは宗像隆一郎氏です」
明智は別に語調を強めるでもなく、ゆっくり云いながら、静かに宗像博士の顔を指さすのであった。
「ワハハハ……、これはおかしい。こいつは傑作だ。明智君、君は探偵小説を読み過ぎたんだよ。小説家の幻想に慣れすぎたんだよ。如何にも探偵小説にありそうな結論だね。ワハハハ……、実に傑作だ。こいつは愉快だ。ワハハハ……」
宗像博士は腹を抱えんばかりに笑いつづけたが、悲しいかな、その笑い声の終りは、泣いているのかと疑われる程、弱々しい音調に変って行った。
「宗像さん、明智君は冗談を云っているのではないようです。今までの明智君の推理を聞いていますと、我々としても、何となくあなたがその手品遣いの本人ではなかったかと考えないではいられません。あなたはこの際、是非弁明をなさる必要があります」
刑事部長が宗像博士をキッと見つめながら、厳然たる警察官の口調で云った。
「弁明せよとおっしゃるのですか。ハハハ……、夢物語を真面目に反駁はんばくせよとおっしゃるのですか。僕はそういう大人げない真似は不得手ですが、強いてとおっしゃるならば申しましょう。……確証がほしいのです。明智君、確かな証拠を見せて貰おう。君もこれ程僕を侮辱したからには、まさか証拠がない筈はなかろう。それを見せたまえ、サア、それを見せたまえ」
「証拠ですか。よろしい、今お目にかけましょう」
明智はチョッキのポケットから時計を出して、眺めながら、
「話に夢中になっている間まに、もう一時間半もたっています。宗像君、君が電話をかける為にこの部屋を出てから、もう一時間半もたってしまったのですよ。ハハハ……、一時間半の間には、随分色々なことが起っているかも知れませんね。……オオ、ボーイがやって来た。手に紙片かみきれを持っている。多分僕の所へ来たのでしょう。証拠が車に乗って駈けつけて来たのかも知れませんよ」
明智は冗談のように笑いながら、その白服のボーイの手から小さな紙片を受取って、そこに書いてある鉛筆の文字を読み下した。
「やっぱりそうでした。丁度うまい所へ証拠がやって来たのです。ではすぐここへ通してくれ給え」
ボーイが立去ると間もなく、明智の言葉の意味を解し兼ねて、不審げに入口を見つめる人々の視線の中へ、先ず現われたのは明智の助手の小林少年であった。詰襟金釦つめえりきんぼたんの服を着て、林檎りんごのような可愛い頬に、利口そうな目を輝かせながら、人々に一礼すると、ツカツカと明智の側そばに進みより、何か二言三言ささやいたが、明智の肯くのを見ると、入口に向って「お入り」と声をかけた。
すると、ドヤドヤと足音がして、二人の屈強な青年に、両方から抱えられるようにして、後手うしろでに縛られた小柄な真黒な人の姿が、部屋の中によろめき込んで来た。
それを一目見るや、宗像博士はギョッとしたように立上り、キョロキョロとあたりを見廻していたが、何を思ったのか、いきなり表の道路に面する窓の方へ走り寄った。
「宗像君、その窓を開けて、下を覗いてごらん。中村君の部下の私服刑事が十人ばかり、今にも君がそこから飛降りるかと、手ぐすね引いて待ち構えているんだよ」
刑事部長も捜査課長も知らなかったけれども、中村警部は明智の依頼によって、予め部下のものを、このレストラントの周囲に張りこませて置いたのである。
博士はそれと聞くと、素早く窓の下を一瞥いちべつして、明智の言葉が嘘でないことを確かめたが、何かきまり悪げに、しかし、なおも虚勢をはりながらノロノロと元の席に戻るのであった。
「皆さん、御紹介します。この黒い覆面の人物は、世間体は宗像君の奥さん。その実は宗像君の血を分けた妹さんです。宗像君の本名は、もう御想像になったでしょうが、山本始と云い、この妹さんは山本京子というのです。偽物の山本始と京子は殺されてしまいましたが、本物はこうしてちゃんと生きていたのです。
僕はさっき申上げた仮説を組み立ててから、それを確めるために宗像君の自宅に捜査の手を入れました。そして、宗像君の夫人が、極度の人嫌いで、事務所の助手達にも一度も顔を見せたことがないというのを知って、いよいよ僕の仮説が間違っていないという自信を得たのです。そして、この夫人にはそれ以来絶えず見張りの者をつけて置きました。
宗像君は、さい前僕が川手氏を匿っているということを話した直後、口実を設けて電話室へ行き、どこかへ電話をかけましたが、それはこの妹の京子を呼び出して、邪魔の入らぬうちに一刻も早く仕損じた敵討ちを完成するように云いつけたのです。つまり、僕の留守の間に、即刻僕の家へ忍び込んで川手氏を殺害することを命じたのです。宗像君、僕の推察が間違っていますか。ハハハ……、僕は君の心の奥底までも見通しているのですよ。
ところが、そうしてこの女が僕の家へ忍び込んでくれるのを、僕は待っていたのです。その為に態と川手氏が僕の家に寝ていることを、ハッキリ口外したのです。それを聞いて宗像君が顔色を変え、電話室へ行った時には、実を云うと僕は心の中でしめたと叫んだくらいですよ。
では山本京子の素顔をお見せしましょう」
明智は云いながらツカツカと黒衣の人物の前に進んで、いきなり覆面の黒布こくふをかなぐり捨てた。するとその下から、極度の激情に紙のように青ざめ、細い目のつり上った、四十女の痩せた顔が現われた。
「サア、小林君、この女が僕の家で何をしようとしたのか、君から簡単に皆さんに御報告するがいい」
云われて小林少年は一歩前に進み、ハッキリした口調で、ごく手短に事の次第を語った。
「先生の命令によって、僕達三人は、川手さんの泊っていらっしゃる寝室の中に、待ち伏せしていたのです。
天井の電燈は消して、スタンドだけの薄暗い光にして置いたのですが、その光の中で、川手さんは何も知らず眠っていました。僕達はてんでに物蔭に身を隠して、じっと待っていたのです。
すると、今から三十分程前、庭に面したガラス窓が(それは態と掛金をはずして置いたのですが)ソーッと音もなく開いて、そこからこの黒覆面の人が忍び込んで来ました。
息を殺して見ていますと、この人は寝台に寝ている川手さんの顔を、確めるように眺めていましたが、どこからか西洋の短剣を取出して、それを右手に握り、川手さんの上にのしかかるようにして、その胸を目がけて、いきなり刺し通そうと身構えました。
僕達三人は、それを見て、隠れ場所から鉄砲玉のように飛び出して行きました。そして、三方からこの人に組みついて、何の苦もなく取りおさえてしまったのです。
川手さんは物音に驚いて目を覚ましましたが、かすり傷一つ受けてはいませんでした」
小林少年が報告を終るのを待って、明智はとどめを刺すようにつけ加えた。
「宗像君、僕の証拠がどんなものであったか、これで君にもハッキリ分っただろうね。だが、この君の妹さんは、僕の予想がうまく的中して、幸いに捉えることが出来たが、僕の握っていた証拠はこれだけではないのだ。君は気附いていないかも知れぬが、北園竜子に雇われていたお里という婆やが、竜子の恋人に化けた君の素顔を、よく見覚えているのだよ。
小林君、あの婆やも連れて来たのだろうね」
「エエ、廊下に待たせてあります」
「じゃ、ここへ呼んで来たまえ」
やがて、小林少年につれられて、お里婆やがオズオズと入って来た。
「お里さん、君はこの人に見覚えがないかね」
明智が指さす宗像博士の顔を、老婆はつくづく眺めていたが、一向記憶がないらしく、かぶりを振って、
「イイエ、少しも存じませんですが……」
と恭うやうやしく答えた。
「アア、そうだった。君が知っているのはこの顔ではなかったね。宗像君、この婆やの為に、面倒だけれど、一つそのつけひげと眼鏡を取ってやってくれたまえ。イヤ、とぼけたって駄目だよ。僕は何もかも知っているのだ。
君は川手氏と一緒に山梨県の山中へ行く途中で、変装をする為に、その三角ひげを取って見せたっていうじゃないか。いずれは殺してしまう川手氏のことだからと、つい油断をしたのだろうが、その川手氏が生返って見れば、あれは君の大失策だったよ。川手氏の外には、君のその精巧なつけひげの秘密を知っているものは、一人もないのだからね。
ハハハ……、宗像君、今更ら躊躇するのは未練というものだよ。それじゃ、一つ僕がそのつけ髯をはがして上げるか」
明智は云いながら、素早く宗像博士の前に近より、いきなり猿臂えんぴを延ばして眼鏡を叩き落し、口鬚と顎髯とをむしり取ってしまった。するとその下から、今までのしかつめらしい博士とは似てもつかぬ、のっぺりとした無髯むぜんの悪相が現れて来た。
「オオ、そのお方なら存じて居ります。おなくなりになった御主人様の所へよく訪ねていらしった方でございます。お名前は存じませんが、御主人様と二人づれで、時々どこかへお出かけになった方でございますよ」
お里婆さんが、やっきとなって喋べり立てる。
「つまり、いつか君が云っていた、北園竜子の情夫というのが、この男なんだね」
中村警部が横合から質問すると、老婆は肯いて、
「エエ、マアそういう御関係のお方と、お察し申していたのでございますよ」
と答えながら、口に手を当てて、羞はにかみ笑いを隠すような仕草をした。
「宗像君、これでも君はまだ弁明をする勇気があるかね。若しこの二人の証人で足りなければ、僕の方には外にも証人があるんだよ。例えば山梨県の例の一軒家の留守番をしていた老夫婦だ。川手氏の話で、あの老婆の方が君達兄妹の昔の乳母だったことも分っている。その老夫婦は僕の部下が今捜索しているのだが、所在をつきとめて裁判所に引渡す日も遠くはあるまい。
それから、君が川手氏に地下室でお芝居を見せた時の役者連中だ。この方にも、もう捜索の手が伸びている。君は一人も証人などはあるまいと安心していたようだが、川手氏が生返ったばかりに、こういう証人があり余る程出て来たのだ。
宗像君、君がいくら魔法使いでも、もう逃れる道はない。見苦しい真似はしないでくれたまえ。僕は君の犯罪者としての才能と狡智には驚嘆に近い感じを持っている。僕がこれまで取扱った犯罪者には、君程の天才は一人もなかったと云ってもいい。
復讐事業の為に、先ず民間探偵に化けて、様々の事件で手柄を立てて見せた遠大の計画といい、怪指紋を巧みに利用して、被害者を逆に犯人と見せかけた着想といい、イヤ、そればかりではない、犯人からの脅迫状を、塵芥ごみ箱の中や、当の被害者のポケットに入れて置いて、さも不思議そうに驚いてみせたり、怪指紋のゴム印を、色々な器物や人間の頬にまで捺して、自分自身で捺した指紋を怪しんで見せたり、たとえ正体を見破られた苦しまぎれとはいえ、助手を二人まで我が手にかけて、嫌疑の転嫁を計ったり、その機敏と大胆不敵には、流石の僕も舌を捲かないではいられなかった。
君の五つの殺人のうちで、最も手の込んでいたのは、妙子さんの場合だが、あの記録を読んだ時にも、僕は君のすさまじい虚栄心に目を見はった。ただ予告の殺人を成しとげたいばっかりに、君は実に手数のかかるトリックを考え出している。
あんなにまで苦労しなくても、予告をやめて、不意を襲いさえすれば、易々と目的を達することが出来るのに、態々そのたやすい道を避けて、不可能に近い困難な方法を選んでいる。
君はその為に、クッションの下に空洞のある特別のベッドを、非常な苦心をして、予め妙子さんの寝室に持込まなければならなかった。しかし、それは人目を欺く手品の種、犯人も被害者も決してその空洞の中に隠れていたのじゃない。あの夜、廊下の見張り番を勤めていた君は、探偵という保護色によって、誰に疑われることもなく、妙子さんの寝室に忍び込み、そこにいた川手氏を縛り上げ、妙子さんを絞め殺して、その死体をすぐ表庭に運んで、塵芥箱の底へ隠して置いたのだ。
それから夜が明けて、邸内の大捜索が始まってから、君は捜索に参加しているように見せかけて、その実は、コッソリ邸を抜け出し、眼帯の男に化けて、京子と一緒に塵芥車を挽ひき込んで、死体運び出しの大芝居を演じたという訳だ。
態々註文して作らせた、仕掛けのあるあのベッドは、ただ見せかけの手品の種で、犯罪には全く使用されなかったという点を、僕は非常に面白く思った。気違いでなくては考えつけないような、ずば抜けた着想だ。ただ殺人を見せびらかすという、『殺人芸人』のみのよくするところだ。
お化け大会の中では、君は黒い衣裳と黒覆面を、予めどこかへ隠して置いて、探偵と犯人との一人二役を演じて見せた。君の賢い助手は、犯人が宗像博士と知らないで、巧みな手段によって、見事に黒衣の人物を捕えたが、そうして君の素顔を一目見たばっかりに、その場で撃ち殺されてしまった。
鏡の部屋では、扉の隙間からピストルの筒口を覗かせて置いて、人々の躊躇する間に、洋服の上に着ていた黒衣を手早く脱ぎ捨て、元の宗像博士の姿になって追手の前に立ち現われたのだ。つまり君はいつも人々の目の前にいたのだ。しかし、名探偵その人が稀代の殺人犯人だなんて誰が想像し得ただろう。君は実に驚くべき保護色に包まれて、易々と世人をあざむきおおせたのだ。
それ程の悪智慧を犯罪捜査に使ったのだから、君が名探偵と謳われたのも無理ではない。犯罪者でなくては、犯罪者の心は分らないのだからね。盗賊上りのヴィドックが稀代の名探偵となり上ったのも、君の場合と全く同じだったといっていいのだ」
明智は思わず犯人を讃美するかの如き口吻こうふんを漏らしたが、そこで何に気附いたのか、ふと言葉をとめて、鋭く宗像博士を睨みつけた。
眼鏡と髯のなくなった宗像博士は、狂えるけだものの相好を呈していた。彼は今こそ彼等兄妹の運の尽きであることを、はっきり悟ったのだ。如何なる魔術師も、この重囲の中を逃げ出す工夫は全くなかった。ただ追いつめられた野獣の最後の一戦を試みるばかりだ。
彼は部屋の隅に突立ったまま、腰のポケットから一挺の小型ピストルを取出して、先ず仇敵明智の胸に狙いを定めた。
「明智君、問答無用だ。俺は負けたのだ。俺の犯罪力は君の探偵力に及ばなかったのだ。しかし、このままおめおめと捉えられる俺ではないぞ。君を道連れにするのだ。俺の罪をあばいてくれた君の胸板に、この鉛玉を進上するのだ。覚悟するがいい」
宗像博士の山本始はピストルの引金に指をかけて、じっと狙いを定めた。そして、彼の気違いめいた目が、糸のように細められたかと思うと、その指にグッと力が入った。
人々はハッと息を呑んだ。ピストルは発射されたのだ。しかも銃口は、一直線に明智の心臓部を指していた。この近距離で玉のそれる気遣きづかいはない。では、明智はもろくも撃ち倒されたのか?
だが、不思議なことに、明智は何の異状もなく、元の場所に突立ったまま、ニコニコと笑っていた。
「ハハハ……、そのピストルからは、鉛の玉は飛び出さないようだね。どうしたんだね。サア、もう一度やって見給え」
山本始は、それを聞くと、あせってまた狙いを定め、引金を引いた。しかし、今度も弾丸たまは飛び出さないのだ。
「ハハハ……、よし給え、いくらやったって、引金の音がするばかりだ。君は今夜はひどく興奮していたので、僕の小手先の早業に気づかなかったのだよ。そのピストルの弾丸は、さい前僕がすっかり抜いて置いたのだ。見給え、これだ」
明智はそう云って、ポケットから取出した幾つかのピストルの弾丸を手の平の上で、コロコロと転がして見せた。兇悪な犯人を捉える際には、常に用いる彼の常套手段である。
「兄さん、いよいよ最期です。早く、あれを、あれを……」
突如として劈つんざくような金切声が響き渡ったかと思うと、黒衣の京子が、二青年の手を振り払い、後手に縛られたまま、髪振り乱して、兄の側へ駈け寄った。
兄はその華奢な妹の身体を抱きしめて、
「よしッ、それじゃ今から、お父さんお母さんのお側へ行こう。そして俺達が復讐の為にどんなに骨折ったかを御報告しよう。サア、京子、今が最期だよ」
その言葉が終るか終らぬに、妹の色を失った唇から「ウーム」という細い鋭いうめき声が漏れて、彼女はクナクナと床の上にくずおれてしまった。
兄はうめき声さえ立てなかった。ただ青ざめた顔に、見る見る玉の汗を浮べて、苦痛を堪こらえる様子であったが、遂にその力も尽きたのか、彼の大きな身体は、妹をかばうように、折重なってその上に倒れ、兄も妹もそのまま動かなくなってしまった。
人々は何が何やら訳が分らず、あっけにとられて、ただこの有様を眺めるばかりであった。
やがて、明智小五郎が、何に気附いたのか、二人の死体の側に身をかがめ、その唇を開いて、口中を調べていたが、しきりと肯きながら立上ると、低い声で呟いた。
「アア、何という用心深い悪魔だ。二人とも奥歯に金の義歯を篏はめていたのですよ。その義歯の中が虚うつろになっていて、強い毒薬が仕込んであったのでしょう。いざという場合には、たとえ手足を縛られていても、その義歯の仕掛けを噛み破って、中の粉薬を飲み込みさえすればよかったのです。
皆さん、悪魔の狡智は、考え得るあらゆる場合を計算に入れていました。そして、今その最悪の場合に際会さいかいしたのです。
それにしても、何という執念だったでしょう。この兄妹の心理は常識では全く判断が出来ません。恐らく幼時の類例のない印象が、二人の魂に固着したのです。残虐な殺人現場で、両親の流した血の海を這い廻った、あの記憶が彼等を悪魔にしたのです。
仇敵の子孫を根絶やしにする為に、生涯を捧げるなどという心理は、寧ろ精神病理学の領分に属するもので、我々には全く理解し難い所です。
この二人は気違いでした。しかし、復讐という固着観念の遂行の為には、天才のように聡明な気違いでした」
いつもにこやかな名探偵の顔から、微笑の影が全く消え失せていた。そして、その青白い額に、これまで誰も見たことのないような、悲痛な皺が刻まれていたのである。
底本:「江戸川乱歩全集 第12巻 悪魔の紋章」光文社文庫、光文社
2003(平成15)年12月20日初版1刷発行
底本の親本:「江戸川乱歩選集 第二巻」新潮社
1938(昭和13)年10月
底本の親本:「日の出」新潮社
1937(昭和12)年10月~1938(昭和13)年10月
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
入力:門田裕志
校正:北川松生
2017年1月12日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
超人ニコラ
江戸川乱歩
東京の銀座に大きな店をもち、宝石王といわれている玉村たまむら宝石店の主人、玉村銀之助ぎんのすけさんのすまいは、渋谷しぶや区のしずかなやしき町にありました。
玉村さんの家庭には、奥さんと、ふたりの子どもがあります。ねえさんは光子みつこといって高校一年生、弟は銀一ぎんいちといって中学一年生です。
あるとき、その玉村銀一君の身の上に、じつにふしぎなことがおこりました。それがこのお話の出発点になるのです。
その夜、玉村君は、松井まつい君、吉田よしだ君という、ふたりの友だちと、渋谷の大東だいとう映画館で、日本もののスリラー映画を見ていました。
それは大東映画会社の東京撮影所で作られたもので、映画の中に、ときどき、東京の町があらわれるのです。
「あっ、渋谷駅だっ。ハチ公がいる。」
松井君が、おもわず口に出していいました。それはおっかけの場面で、にげる悪者、追跡する刑事、カメラがそれをズーッとおっていくのですが、そこへ駅前の人通りがうつり、ハチ公の銅像も、画面にはいったのです。
「あらっ、玉村君、きみがいるよ。ほら、ハチ公のむこうに、やあ、へんな顔して、笑ってらあ。」
吉田君が、とんきょうな声をたてたので、まわりの観客が、みんなこちらをむいて、「シーッ。」といいました。
玉村君は、スクリーンの上の自分の姿を見て、へんな気がしました。ハチ公の銅像のうしろから、こちらをのぞいて、にやにや笑っている自分の顔、それが一メートルほどに、大きくうつっているのです。
それがうつったのは、たった十秒ぐらいですが、たしかに自分の顔にちがいありません。玉村君は、ここにうつっているのは、いつのことだろうと考えてみました。
「おやっ、へんだな。ぼくは渋谷駅で、映画のロケーションなんか見たことは、一度もないぞ。」
いくら考えても、おもいだせません。知らないうちに、うつされてしまったのでしょうか。まさか、ロケーションに気づかないはずはありません。
そのばんは、うちにかえって、ベッドにはいってからも、それが気になって、なかなかねむれませんでした。
あれは、自分によくにた少年かもしれないとおもいましたが、しかし、あんなにそっくりの少年が、ほかにあろうとは考えられないではありませんか。
玉村君は、なんだか心配になってきました。自分とそっくりの人間が、どこかにいるとしたら、これはおそろしいことです。
それから一週間ほどたった、ある日のこと、玉村君の心配したことが、じつに気味のわるい形で、あらわれてきました。
玉村君と松井君とは、明智あけち探偵事務所の小林こばやし少年を団長とする、少年探偵団の団員でした。ですから、ふたりはたいへんなかよしで、どこかへいくときは、たいてい、いっしょでした。
その松井君が、ある日、学校がおわってから、玉村君をひきとめて、校庭のすみの土手にもたれて、へんなことをいいだしました。
「玉村君、ぼく、すっかり見ちゃったよ。きみは秘密をもっているだろう。」
「秘密なんかないよ。どうしてさ。」
玉村君は、ふしんらしく、聞きかえしました。
「きみのうちは、お金持ちだろう。お金持ちのくせに、スリなんかはたらくことはないじゃないか。」
ますます、みょうなことをいいます。
「えっ、スリだって?」
「そうだよ。ぼくはすっかり見ちゃったんだよ。」
「ぼくがかい? ぼくがスリをやったって?」
玉村君はびっくりしてしまいました。
「ほら、八幡はちまんさまの石がき……。あの石がきの石が、一つだけ、ぬけるようになっているんだ。きみはその石のうしろに、からの紙入れを、たくさん、かくしたじゃないか。」
「なにをいっているんだ。ぼくにはちっともわからないね。もっとくわしく話してごらん。」
玉村君は、あまりのいいがかりに、腹がたって、おもわず、つよい声でいいました。
「じゃあ、くわしく話すよ。」
松井君は、ゆうべのできごとを、はなしはじめました。
きのうは八幡さまのお祭りでした。
こんもりした林にかこまれた、その八幡さまは、玉村君のうちからも、松井君のうちからも、そんなに遠くないところにありました。
ゆうべ、松井君は、ただひとりで、その八幡さまの中をブラブラしていたのです。
五千平方メートルほどの、八幡さまの境内けいだいには、テントばりの見世物が二つと、オモチャ屋の店や、たべものの店が、いっぱいならんで、そのあいだを、おおぜいの人が、ゾロゾロ歩いていました。テントばりの見世物の一つは、おそろしく古めかしい「クマむすめ」という、かたわものを十円で見せているのです。
「クマむすめ」というのは、二十歳ぐらいのむすめの、肩のへんいちめんに、まっ黒な、クマのような毛がはえているのです。まるで、人間とクマのあいの子みたいなので、「クマむすめ」とよんでいるのです。
いまどきめずらしい見世物なので、おおぜいの見物人が、十円はらって、中へはいっていきます。
入口はテントの右のほう、出口は左のほうですが、松井君が見ていますと、その出口からゾロゾロと出てくる見物人の中に、玉村銀一君がまじっていたではありませんか。
「おやっ、玉村君は、こんなつまらない見世物を見たんだな。」
とおかしくなって、声をかけて、ひやかしてやろうと、そのほうへ、ちかづいていきました。そして、こちらへやってくる玉村君と、バッタリ、であったのです。ふたりは二メートルほどの近さで、顔を見あわせたのです。
ところが、ふしぎなことに、玉村少年は、松井君を見ても、ニッコリともせず、知らん顔をして、すれちがって、いってしまうではありませんか。
「ははん。あいつ、はずかしがっているんだな。わざと、知らん顔をして、にげだしたんだな。よしっ、そんならこっちは、どこまでも尾行びこうしてやるぞ。」
少年探偵団で練習していますから、尾行はお手のものです。松井君は、玉村君にさとられぬように、あとをつけはじめました。
玉村君は、いつまでも八幡さまから出ないで、人ごみの中を、あちこちしています。わざと人だかりの中へ、もぐりこんでいくのです。そこを出ると、また、つぎの人だかりへもぐりこみます。玉村君は、よっぽど人ごみがすきらしいのです。
一時間ほども、そんなことをくりかえしていましたが、やっと人ごみにもあきたのか、玉村君は八幡さまを出て、外のくらい道をかえっていきます。
松井君は、あくまで尾行をつづけました。
玉村君は、八幡さまの外がわの長い石がきの半分ぐらいのところまでくると、そこで立ちどまって、キョロキョロと、あたりを見まわしました。だれか見ていやしないかと、気をくばっているらしいのです。
松井君は、すばやく電柱のかげに、身をかくしました。ほかに人通りもありませんので、玉村君は安心したように、石がきのそばによって、そこにしゃがんでしまいました。
そして、石がきの一つの石に手をかけると、グーッとひっぱりだしました。その石だけが、ぬけるようになっていたのです。
玉村君は石をぬきとったあとの穴に、手をいれて、なにかやっていましたが、また石をもとのとおりにはめこむと、そのまま、立ちあがって、むこうへ歩いていきます。
松井君は、あの石のおくに、なにかかくしたにちがいないとおもいました。そこで、玉村君の尾行をあきらめて石のおくをしらべてみることにしました。
松井君は、あたりを見まわして、人通りがないのをたしかめると、石がきのそばによって、さっきの石に両手をかけ、グッとひっぱりました。石はなんの苦もなく、ズルズルとぬけてきます。
石をぬきとると、そのあとの穴に、手をいれて、さぐってみました。
ある、ある。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、それはみんな紙入れや、がまぐちでした。あけてみると、どれも中はからっぽです。
松井君は、あきれかえってしまいました。玉村少年は、人ごみの中で、これらの紙入れや、がまぐちを、スリとったのです。そして、中のお金をとりだして、からの紙入れなんかを、この石がきにかくしたのです。
ふつうなら、紙入れなんかは、どこかへすててしまうのですが、用心ぶかく、からの紙入れまでかくすというのは、よっぽどなれたやつです。スリの名人といってもいいでしょう。
ああ、親友の玉村銀一君が、スリの名人だったなんて。あまりのことに、松井君は、あいた口がふさがりません。
あのお金持ちの玉村君が、わずかのお金のために、スリをはたらくなんてまったく考えられないことです。これにはなにか、わけがあるにちがいない。おもいきって、玉村君にきいてみよう。
松井君は、そう決心をしたので、校庭のすみで、さっきのように、玉村君を、といつめたのでした。
玉村君は、すこしもおぼえのないことでした。
「ねえ、松井君、ぼくとまったくおなじ顔のやつが、どっかにいるんだよ。あの映画のハチ公のそばに立っていたのも、けっしてぼくじゃない。また、きみの見たスリの少年も、むろん、ぼくじゃない。きみでさえ、まちがえるほど、ぼくとそっくりのやつが、いるのにちがいない。ぼくはなんだか、心配だよ。いまのところは、そいつは、ぼくとなんのかんけいもないけれども、そいつがなにかわるいことをして、その罪を、ぼくにきせようとすれば、きせられるんだからね。」
玉村君はそういって、考えこんでしまいました。
「まさか……。」
松井君は、玉村君をげんきづけるようにいいました。が、心の中では、玉村君の心配は、むりではないとおもっているのでした。
それから、しばらく話したあとで、ふたりはわかれて、それぞれのうちへかえりましたが、それは、学校がひけて、一時間もたったころでした。
玉村君がうちにかえってみますと、そこにはじつにおそろしいことが、まちかまえていたのです。
「ただいま。」といって、玄関げんかんにはいると、ちょうどそこに、ねえさんの光子さんが立っていました。
「あらっ、またかえってきたの?」
「えっ、またって?」
「だって、もうさっき学校からかえって、お部屋でおやつをたべたじゃありませんか。わたしがコーヒーとお菓子をもってってあげたら、うまいうまいって、たべたじゃないの。いつのまに、外へ出ていったのよ。そして、学校の道具なんかもって、またかえってくるなんて、どうかしてるわ。」
それをきくと、玉村銀一君は、ゾーッとしました。
「ねえさん、ぼくをかつぐんじゃないだろうね。」
銀一君は、しんけんな顔で、ねえさんをにらみつけました。
「おおこわい。なんてこわい顔するの? 銀ちゃんをかついだって、しょうがないわ。たしかに、さっきかえったから、かえったっていうのよ。」
銀一君は、それにはこたえず、くつをぬぐのももどかしく、おそろしいいきおいで、自分の勉強部屋へ、かけていきました。
ドアをあけて、とびこんでみると、ああ、やっぱり、そこには、机の上にからになった菓子ざらとコーヒーの茶わんがのっていたではありませんか。
「あいつがきたのだ。そして、ぼくがかえったのを知ると、大いそぎで、窓からにげだしたのだ。」
ここからにげたといわぬばかりに、窓のガラス戸が、あけはなしになっていました。銀一君は、いそいで、窓の外をのぞきますと、そこの地面に、大きな足あとが、いくつものこっているではありませんか。
しらべてみると、本箱の本のおきかたが、かわっています。あいつが本を動かしたのでしょう。机のひきだしをあけてみると、どのひきだしも、みんな、あいつがいじったらしく、紙などのかさねかたが、ちがっています。
じぶんとそっくりのやつが、うちへはいってきて、おやつをたべたり、本箱や、机のひきだしを、かきまわしたかとおもうと、なんともいえない、いやあな気がしました。
すぐに茶の間へとんでいって、おかあさんに、このことを知らせましたが、あんまりへんなことなので、おかあさんも、どうしていいかわかりません。おとうさんが、お店からおかえりになったら、よく相談しましょうと、おっしゃるばかりでした。
しばらくして、銀一君は、勉強部屋にかえって本を読んでいました。もう夕ぐれで、庭はうすぐらくなっています。おやっ、あれはなんでしょう。
本を読んでいる目のすみに、チラッと、動いたものがあります。窓の外でなにかが動いたのです。ハッとして、そのほうを見ると、さっきしめた窓ガラスに、自分の顔がうつっていました。
しかし、なんだか角度がへんです。あんなところに、ぼくの顔がうつるかしら……あっ、もしかしたら! 銀一君はギョッとして立ちあがると、窓ガラスへ近づいていきました。
やっぱりそうでした。ガラスにうつっているのではなくて、ガラスのむこうがわに、自分の顔があるのです。自分の顔ではない、自分とそっくりのやつが、ガラスの外から、のぞいていたのです。
十秒ほど、ガラスをへだてて、まったくおなじ二つの顔が、じっとにらみあっていました。じつに、なんともいえない、へんてこな光景でした。
十秒ほどにらみあったあとで、窓のむこうの顔は、パッとガラスをはなれて、庭の立ち木のあいだに、にげこんでしまいました。
銀一君は、少年探偵団員だけあって、こういうときには勇かんです。うちの人に知らせるひまもないので、そのまま、窓からとびだすと、くつもはかないで、自分とそっくりの少年のあとを、おいました。
あいては、うらのコンクリートべいを、よじのぼって、外の道路へ、とびおりたようです。銀一君も、そのへいをのりこえました。
見ると、二十メートルほどさきを、あいつが大いそぎで、あるいていきます。うしろ姿は、銀一君と、まったくおなじ服装です。
こちらは、しずかに、へいからすべりおちて、追跡をはじめました。ほとんどくらくなっているので、あいてにさとられる心配はありません。
それにしても、なんというふしぎな追跡でしょう。まったくおなじ顔の、おなじ服装の、ふたりの少年が、二─三十メートルをへだてて、トット、トットと、いそぎ足に、歩いているのです。
さびしい町から、さびしい町と、あるいているうちに、いつのまにか、あの八幡さまの石がきのところにきていました。
あいての少年は、石がきをとおりすぎて、八幡さまの林の中へはいっていきます。ゆうべでお祭りはすんだので、林の中はまっくらで、人っ子ひとりいません。
銀一君も、すこしおくれて、八幡さまの中へ、はいっていきましたが、くらいので、なにがなんだかわかりません。あの少年はどこへいったのか、いくらさがしても姿が見えないのです。
むこうにボーッとひかったものがあります。八幡さまの社殿しゃでんの前に、うすぐらい常夜灯じょうやとうが立っているのです。
その社殿のえんがわのようなところに、みょうな人間が、こしかけていました。はでなしまの背広をきた老人です。
老人は白いかみの毛をモジャモジャにして、長い白ひげを胸の前にたらしています。大きなめがねをかけていて、それが常夜灯の光を反射して、キラキラひかっているのです。
こんなまっくらな中で、社殿にこしかけているなんて、あやしい老人です。銀一君は、気味がわるくなって、にげだそうかと思いましたが、にげるのもざんねんです。勇気をだして、ぎゃくに、こちらからちかづいていきました。
「おじいさん、ぼくとおんなじ服をきた、おんなじ顔の子どもが、ここをとおらなかったですか。」
おもいきって、はなしかけてみました。すると、老人は、こしかけたまま、身動きもしないで、にやりと笑いました。
「おお、かんしん、かんしん、きみはなかなか勇気がある。きみとおんなじ顔をした子ども、あれはきみの分身じゃよ。」
地の底から、ひびいてくるような、いんきな声です。
「分身って、なんですか?」
「きみが、ふたりになったのじゃ。ひとりの子どもが、ふたりにわかれたんじゃよ。」
「どうして、そんなことができるのですか。」
「わしがそうしたのじゃよ。ハハハハハハ。」
老人はぶきみに笑いました。やっぱり、あやしいやつです。
「おじいさんはだれですか。」
「わしはニコラ博士というものじゃ。」
「ニコラ博士? じゃあ、日本人ではないのですか。」
「わしは十九世紀のなかごろに、ドイツで生まれた。だが、わしはドイツ人ではない。世界人じゃ。イギリスにも、フランスにも、ロシアにも、中国にも、アメリカにもいたことがある。そして、いたるところで、ふしぎをあらわして歩くのじゃ。わしは大魔術師じゃ、スーパーマンじゃ。わしにできないことはなにもない。神通力じんつうりきをもっているのじゃ。わしひとりの力で、この世界を、まったくちがったものにすることができる。そういう神通力をな。ウフフフフフ。」
老人はそういって、またしても、地の底からのような、いんきな声で、笑うのでした。
「十九世紀のなかばというと、一八五〇年ごろですね。」
銀一君は、びっくりして、聞きかえしました。
「そうじゃ。わしが生まれたのは一八四八年だよ。」
銀一君は、しばらく、指をおって、かぞえていましたが、あっとおどろいて、おもわず大きな声を出しました。
「じゃあ、おじいさんは、百十四歳ですね。」
「ウフフフフフ、おどろくことはない。わしは、これからまだ、百年も二百年も生きるつもりじゃよ。わしは、あたりまえの人間ではない。スーパーマンだ。魔法つかいだ。
さて、玉村銀一君。これから、わしがおもしろいところに、つれていってやる。そこにいけば、どうして、きみとそっくりの少年が、あらわれたか、その秘密が、わかるのじゃよ。さあ、わしといっしょに、くるがいい。」
怪老人ニコラ博士は、ちゃんと銀一君の名まえを知っていました。玉村家にたいして、なにかおそろしいことを、たくらんでいるのかもしれません。
ニコラ博士は、社殿のえんがわからおりると、銀一君の手をとって神社のうらてのほうへ、歩いていきました。
森を出はずれると、さびしい、広い道があって、そこに、りっぱな自動車がとまっていました。
銀一君は、こんな自動車で、どこへつれていかれるかわからないと思うと、こわくなってきました。
「ぼく、うちにかえります。」
そういうと、いきなり、にぎられていた手を、ふりはなして、にげだそうとしました。
「どっこい、そうはいかないぞ。きみはもう、わしのとりこなのじゃ。」
白ひげのニコラ博士は、すばやく銀一君をつかまえて、自動車の中におしこもうとしました。
そこで百十四歳の老人と、十三歳の少年との、ふしぎなとっくみあいが、はじまったのです。ふつうならば、百歳をこえた老人のほうが、まけてしまうはずですが、超人ちょうじんニコラ博士は、おそろしくつよくて、銀一君は、とても勝てないのです。
ニコラ博士は、銀一君を、身動きもできないように、だきしめて、ポケットから、大きなハンカチをとりだし、それをまるめて、銀一君の口の中におしこみました。
もう声をたてることもできません。そのまま自動車の中に、おしこまれてしまいました。すると、ハンドルをにぎって、まちかまえていた運転手が、すぐに車を出発させるのでした。
二十分ほど走ると、さびしい町の、石のへいにかこまれた洋館の前につきました。
ニコラ博士は、銀一君の手をひっぱって、その門の中にはいっていきます。まるで鉄のようにつよい手です。とてもにげることはできません。
洋館にはいると、広い廊下をとおって、地下室への階段をおりていきました。
地下室は、三十平方メートルほどの物置部屋です。ふるいいすやテーブルや、いろいろな木の箱などが、ゴタゴタとつみかさねてあります。
「ここは、あたりまえの物置きじゃ。地下室は、これでおしまいのように見えるじゃろう。ところが、このおくに、秘密の部屋があるのじゃ。まさか地下室のおくに、もうひとつ地下室があるなんて、だれも考えないからね。たとえ、家やさがしをされても、だいじょうぶなのだ。ほら、ここに秘密のドアがある。」
ニコラ博士は、そういって、コンクリートの壁かべの、かくしボタンをおしました。すると、目の前の壁が、スーッと、音もなく、むこうにひらいていって、そこに、四角な穴ができました。
その穴をくぐって、廊下のようなところをすこしいきますと、両がわに、鉄棒のはまった、動物園のおりのような部屋がならんでいました。
ニコラ博士は銀一君の口から、ハンカチのさるぐつわを、とりだしてから、そのおりのような部屋のドアをかぎでひらいて、銀一君を中におしこみ、ドアをしめて、またかぎをかけてしまいました。
「ここで、ゆっくりしているがいい。ベッドもあるし、便器もおいてある。食事も、なるべくおいしいものを三度三度、はこばせるよ。じゃあ、またくるからね。」
ニコラ博士は、そういいのこして、どこかへたちさってしまいました。
地底の牢獄です。銀一君は、おそろしいとりこになってしまったのです。いつになったら、ここを出られるのでしょう。ひょっとしたら、一生がい、出られないのではないでしょうか。
「おい、きみ、おい、きみ。」
どこからか、人の声がきこえてきました。前の廊下の、むこうからのようです。
銀一君は、おりの鉄棒につかまって、そのほうを見ました。廊下のてんじょうに、うすぐらい電灯がついているだけですから、おりの中は、ぼんやりとしか見えません。むこうがわのおりの中に、なにか動いているものがあります。
じっと見つめていますと、だんだん目がなれて、その姿が、はっきりしてきました。それは、銀一君よりは二つ三つ年上らしい少年でした。
「おい、きみ、わかるかい。ぼくだよ。きみもぼくと、おんなじめに、あったらしいね。きみのかえ玉が、きみのうちにはいり、ほんもののきみは、ここにとじこめられたんだろう。」
「そうですよ。きみもそうなんですか。」
「うん、ぼくのうちには、いま、ぼくのかえ玉がいるんだ。おとうさんも、おかあさんも、かえ玉とは気がつかない。それほど、ぼくとそっくりなんだ。ニコラ博士は、おそろしいスーパーマンだよ。人間の顔を、どんなにでも、かえることができるんだ。ぼくとそっくりの人間をつくることもできるし、また、ぼくを、まるでちがった顔に、かえてしまうことだってできるんだ。で、きみは、なんていうの? きみのうちは、なにをやってるの?」
「ぼく、玉村銀一。おとうさんは玉村宝石店をやっているのです。」
「あっ、そうか。あの有名な宝石王だね。ぼくは白井保しらいたもつ。ぼくのうちは、銀座の白井美術店だよ。」
「知ってます。あの大きな美術店でしょう、仏像やなんか、たくさんおいてある。」
「そうだよ。きみ、わかるかい。ニコラ博士は、宝石や美術品をねらっているんだぜ。そして、まず、ぼくたちのかえ玉をつくって、人間の入れかえをやったんだ。このつぎに、あいつがなにをやるか、ぼくには、わかっているよ。ああ、おそろしいことだ。はやくだれかに知らせなければ、とりかえしのつかないことになる。」
白井保少年は、おりの鉄棒にしがみついて、じだんだをふまんばかりでした。
それから二日ほどのちの午後、玉村さんのうちでは、おとうさんの銀之助さんは銀座のお店へ、おかあさんは麹町こうじまちの親類へおでかけになって、高校一年の光子さんと、銀一君のふたりが、書生さんや、女中さんたちといっしょに、おるす番をしていました。
光子さんと銀一君は光子さんの部屋で、おやつのお菓子をたべおわったところです。
「おねえさん、それじゃあ、ぼく、じぶんの部屋で、宿題をやるからね。」
銀一君は、そういって、部屋を出ていきました。なんだか、へんですね。銀一君は、あの地底の牢獄から、にげだしてきたのでしょうか。そんなにやすやすと、にげられるはずはありません。
ひょっとしたら、いまうちにいる銀一君は、にせもののほうではないのでしょうか。まったくおなじ顔をしているので、おとうさんも、おかあさんも、おねえさんも、すっかりだまされてしまって、にせものを、ほんとうの銀一君と、しんじているのではないでしょうか。
銀一君がいってしまうと、光子さんは、机の前のいすにかけたまま、窓のほうをむいて、広い庭を、ながめていました。
すると、庭の木のしげみのおくから、みょうな人間が、あらわれてきたではありませんか。
女のこじきです。年は光子さんとおなじ十六ぐらいに見えます。かみの毛はモジャモジャになって、ひたいにかぶさり、服はボロボロにやぶけて、肩から、腰から、たくさんのひもがぶらさがっているように見えます。それに、くつ下も、くつもはかない、どろまみれの足です。
そのこじきむすめが、じっと光子さんを見つめて、こちらにちかづいてくるのです。
ふつうのむすめさんなら、こんなものを見たら、おくへにげこんでしまったでしょうが、光子さんは、にげません。光子さんは、たいへん、なさけぶかいたちで、かわいそうな人を見ると、だまってはいられないのです。
あるとき、道ばたにすわっている、おばあさんのこじきを見ると、つくったばかりの外とうをぬいで、そのこじきにきせかけたまま、さっさとかえってきたことがあります。
また、あるときは、子どものこじきを、自動車の中にひろいあげて、うちにつれてかえり、おかあさんに、そのこじきの子を、うちにおいてくださいと、たのんだこともあります。
光子さんは、そんなふうに、なみはずれた、なさけぶかい心をもったおじょうさんでした。
ですから、庭にあらわれた、こじきむすめを見ても、にげだすどころか、ちかづいてきたら、なにかしんせつなことばをかけてやろうと、じっとまちかまえているのでした。
こじきは、やがて、窓の下までくると、そこに立ったまま、ジロジロと光子さんをながめながら、みかけによらぬ、きれいな声でいいました。
「おじょうさん、なぜにげないの? あたしがこわくないの?」
光子さんは、それをきくと、この子はひがんでいるのだ、だから、こんな、ひにくなことをいうのだと、かなしく思いました。そこで、できるだけ、やさしい声で、たずねてみました。
「あんた、どこから、はいってきたの?」
「門からよ。だって、ねるところがなければ、どこにだって、はいるわ。ゆうべは、お庭のすみの物置小屋でねたの。」
あんがい、ちゃんとしたことばをつかっている。このむすめは、生まれつきのこじきではないらしいと、光子さんは考えました。
「おなかがすいているんでしょう。あんた、おとうさんや、おかあさんは?」
「なんにもないの。みなし子よ。そして、おなかのほうは、おさっしのとおり、ペコペコだわ。」
「じゃあね。人に知れるといけないから、この窓から、はいっていらっしゃい。いま、わたしが、なにか、たべるもの、さがしてきてあげるわ。」
「だれも、きやしない?」
「だいじょうぶよ。このうちには、いま、わたしと弟きりで、あとは書生や女中さんばかりよ。この部屋には、だれもこないわ。」
それをきくと、こじきむすめは、窓をのりこえて、はいってきました。光子さんは、こじきをいすにかけさせておいて、部屋を出ていきましたが、やがて、クッキーのカンと、牛乳のびんを二つと、コップをもって、かえってくると、それをこじきの前のテーブルにおき、
「さあ、おあがりなさい。」
とすすめるのでした。
こじきは、よっぽど、おなかがすいていたとみえて、クッキーをわしづかみにして、口にほおばりましたが、そのとき、ひたいにたれていたかみの毛を、うるさそうにかきあげたので、はじめて、こじきの顔が、はっきり見えました。
ああ、なんて美しいこじきでしょう。きたない服にひきかえて、顔だけは、すこしもよごれていないのです。色白のふっくらとしたほお、パッチリとした、美しい目、赤いくちびる。
「まあ、あんた……。」
光子さんは、さけぶようにいって、思わず立ちあがると、ドアのほうへ、にげだしそうにしました。
光子さんは、ひどくおどろいたのです。こじきが、美しい顔をしていたためばかりではありません。もっと、びっくりすることがあったのです。
すると、こじきむすめは、ニッコリ笑って、
「ああ、うれしい。おじょうさんにも、やっぱり、そう見えるの? あたし、ほんとうにうれしいわ。こんなきたないこじきの子が、このりっぱなおやしきのおじょうさんと、そっくりだなんて。」
ほんとうに、そっくりでした。一方は、ちゃんとといたかみの毛、きれいな服、一方はモジャモジャ頭、ボロボロの服、そのちがいをべつにすると、ふたりは、背の高さから、肉づきから、顔かたちまで、まるでふたごのように、おそろしいほど、よくにているのです。
「あたし、もうずっと前から、おじょうさんと、あたしと、ふたごのように、よくにていることを知っていました。もし、あのおじょうさんと、ひとことでも、お話ができたらと、もうそれが、あたしの、一生ののぞみだったのです。いま、そののぞみがかなって、あたし、こんなうれしいことはありませんわ。」
こじきむすめは涙ぐんでいました。
「まあ、こんなふしぎなことって、あるもんでしょうか。」
光子さんは、それまでよりも、十倍も、なさけぶかい心になって、ため息をつきながらいうのでした。
まるでたちばのちがう、このふたりのむすめは、たちまち、きょうだいのように、なかよしになってしまいました。
光子さんがたずねますと、こじきむすめは、あわれな身のうえ話をしました。光子さんは、涙をこぼして、それをきいていましたが、話しているうちに、ふたりは、顔ばかりでなく、気質きしつまで、よくにていることが、わかってきました。
しめっぽい身のうえ話がすむと、ふたりは、だんだん快活かいかつになって、笑い声をたてながら、話しあっていましたが、やがて、光子さんは、こんなことをいいだすのでした。
「ああ、いいことを思いついたわ。まあ、すてきだわ。ねえ、あんた、わたし、いま、それはおもしろい遊びを考えついたのよ。」
「あら、おじょうさんと、あたしとが、なにかしてあそぶんですの?」
こじきむすめは、びっくりして、ききかえします。
「ええ、そうよ。わたしね。子どものとき『乞食王子』って本を、よんだことがあるの。それで思いついたのよ。あのね、わたしがあんたになるの。そして、あんたがわたしになるの。わかって? つまりね、あんたとわたしが、服やなんか、すっかり、とりかえてしまうのよ。ふたりは、顔がおんなじでしょう。だから、服をかえて、かみの毛のくせをかえれば、あんたがわたしになり、わたしがあんたになれるのよ。」
この思いつきも、半分は光子さんのなさけぶかい心から出ているのでした。かわいそうなこじきむすめに、ひとときでも、宝石王の令嬢になった夢を見せてやりたいと思ったのです。
「まあ、あたしと、おじょうさんと、いれかわるの? ワー、すてき。あたしに、そのきれいな服をきせてくださるのね。」
こじきむすめは、もうむちゅうになっていました。
光子さんは、洗面器にお湯をいれて、てぬぐいと、足ふきをもってきて、まず、こじきの顔や手を、それから足を、きれいにふいてやりました。そして、かみの毛を、ていねいになでつけてやり、服をとりかえました。
きたないこじきむすめが、たちまち、美しいおじょうさんにかわってしまいました。
光子さんは、こじきを三面鏡の前に、つれていきました。
「どう、さっきまでのわたしと、そっくりでしょう。」
「ワーッ、これがあたし? ほんとかしら……。」
こじきむすめは、そういって、じぶんのほおをつねってみるのでした。
つぎは光子さんの番でした。きたないボロボロの服をきて、かみの毛を、指でかきまわして、モジャモジャにして、鏡をのぞきこみました。
「あら、そんな美しいこじきって、ないわ。顔に、まゆずみを、うすくぬってあげましょうか。そうすれば、ほんとうのこじきに見えるわ。」
こじきむすめは、ちょうしにのって、そんなことまでいいだしましたが、光子さんは、かえっておもしろがって、学校の仮装会かそうかいのことを思いだしながら、こじきむすめのいうままに、顔いちめんに、まゆずみをぬらせるのでした。
「こっちへいらっしゃい。ふたりならんで、鏡の前に立ってみるのよ。」
こじき姿の光子さんが、光子さんの服をきたこじきむすめの手をとって、鏡の前につれていきました。
「あらっ、あんた、あたしとそっくりだわ。そして、あたしは、あんたとそっくりね。だれにも見わけられないわ。」
「わたし、うれしいですわ。こんなきれいなおじょうさんになれたんですもの。でも、いけませんわ。だれかに見られるとたいへんですわ。はやく服をとりかえましょうよ。」
「なあに、いいのよ。みんなをびっくりさせてやりたいわ。ね、あんた、もっとぐっとおすまししてね、あちらへいって、書生や女中に、なにかいってごらん。お紅茶をもってくるようにいいつけてもいいわ。そして、だれにもうたがわれないで、ここにかえってきたら、そうね、なにかごほうびをあげるわ。おこづかいをあげてもいいわ。」
光子さんは、このいたずらが、たのしくてたまらないという、顔つきです。
「だって、わたし、こわいわ。きっとみつかりますわ。」
光子さんとそっくりのこじきむすめは、なかなか決心がつかないらしいのです。
「みつかるもんですか。ほら、鏡をごらんなさい。ね、あんた、あたしとそっくりだわ。だいじょうぶよ。さあ、いっていらっしゃい!」
光子さんは、そういって、こじきむすめを、ドアのところにつれていくと、グッと、廊下に、おしだしてしまいました。にせものの光子さんは、しかたなく、廊下を歩いていきます。
一つかどをまがると、むこうから書生がやってくるのに、パッタリであいました。こじきむすめは、びっくりして、にげだしたでしょうか。
いや、いや、そのとき、じつにおそろしいことがおこったのです。ほんとうの光子さんが、まるで考えてもいなかったことが、おこったのです。こじきむすめは、いきなり、書生のそばにかけよりました。そして、こんなことをさけんだのです。
「はやくきて! たいへんなのよ。あたしの部屋に、こじきの子が、はいっているのよ。はやく、あれをおいだしておくれ。」
光子さんになりすましたこじきむすめが、とほうもないことを、いいだしたのです。
書生は、すこしもうたがわず、このことばをまにうけてしまいました。
「えっ、こじきが? おじょうさんのお部屋に? とんでもないやつだ。ここにまっていらっしゃい。すぐにつかみだしてやりますから。」
書生は、いきなり、かけだして、光子さんの部屋に行ってみますと、黒い顔をした、きたないこじきが、鏡の前にこしかけて、じぶんの顔をうつしながら、にやにや笑っているではありませんか。
「こらっ、きさま、どうしてここにはいってきたんだ。はやく出ていけ。ぐずぐずしていると、警察にひきわたすぞっ。」
いくらどなっても、あいては、へいきな顔をして、こんなことをいうのです。
「あらっ、なにをそんなにおこっているの? ちょっといたずらをしてみたのよ。おこることはないわ。」
書生は、光子さんのことばのいみを、とりちがえました。
「ばかっ、ちょっといたずらに、部屋の中にはいられてたまるかっ。さあ出ろ。出なければ、こうしてやるぞっ。」
書生は、こじきむすめ(ほんとうの光子さん)の首すじをつかんで、窓のそばにつれていき、いきなり、窓の外に、つきおとしてしまいました。
こじきむすめは、窓の下にころがって、からだじゅう、砂まみれになりました。
「青木あおきっ、なにをするの。あたしをだれだと思っているの。」
光子さんは、やっとおきあがると、窓からのぞいている書生に、せいいっぱいの声で、どなりつけました。青木というのは、書生の名です。
「なまいきいうなっ。だれとも思っていない。こじきだと思っているよ。さっさと出ていけ。出ていかないと、もっと、いたいめをみせてやるぞっ。」
書生は、いまにも、窓からとびだしてきそうないきおいです。
光子さんは、ただどなっていたってしかたがない、わけをはなそうと思いました。
「ねえ、青木さん。あんたが思いちがいをするのも、むりはないわ。でもあたしは光子なのよ。庭からはいってきた、こじきむすめと、服のとりかえっこをしたのよ。」
それをきくと、書生は、声をたてて笑いました。
「アハハハハハハ、なにをつまらないことをいっている。あっ、ちょうどいい、光子さんがこられた。ねえ、おじょうさん、こいつ、あなたと服をとりかえたんだといってますよ。」
すると、窓に、二つの顔があらわれました。にせの光子さんと、それから、弟の銀一君です。
「あっ、あんた、そこにいたの。はやく、あたしをたすけてちょうだい。あんたがあたしの服をきて、あたしがあんたの服をきているんだわね。」
それをきくと、光子さんにばけたこじきむすめは、目をまんまるにして、わざとおどろいてみせるのです。
「まあ、おそろしい。なんといういいがかりをつけるのでしょう。そんなばかなことを、だれが信用するものですか。青木さん、はやくこのこじきを、門の外へ、ほうりだして。」
こじき姿の光子さんは、びっくりしてしまいました。
「あらっ、なにをいうの。あんたこそ、おそろしい人だわ。ねえ、銀ちゃん、あんたはわかってくれるわね。ほら、おねえさんの光子よ。」
弟の銀一君によびかけて、顔を窓のほうへつきだしましたが、銀一君も、とりあってくれません。
「光子ねえさんはここにいるよ。そんなきたないねえさんなんてあるもんか。おまえなんか、はやく、どっかへいっちまえっ。」
たのみの綱つなが、きれはてました。
ああ、とんだことをしてしまった。あんな気まぐれをおこして、服のとりかえっこをしたばっかりに、おそろしいめにあわなければならない。光子さんは後悔しましたが、いまさらおっつきません。
あっ、書生がえんがわからまわって、庭に出てきました。おそろしい顔をしています。
「さあ、門の外にでるんだ。そして、おまえのこじき小屋にかえるんだ。」
そういって光子さんのえり首をつかむと、グングン門のほうへおしていくのです。
おとうさんは銀座のお店です。おかあさんは麹町の親戚におでかけです。もうたすけをもとめる人もありません。
それにしても、弟の銀一が、どうして、あたしを見わけてくれなかったのだろうと、光子さんはふしぎに思いました。
しかし、読者諸君はごぞんじです。これは銀一君とそっくりの顔をした、にせものです。ほんとうの銀一君は、ニコラ博士という白ひげのじいさんにつれていかれ、地下室にとじこめられているのです。
ああ、これはどうしたことでしょう。怪人ニコラ博士は、いったい、なにをたくらんでいるのでしょう。まず銀一君をにせものといれかえ、いまはまた、光子さんをいれかえたのです。おそろしい計画は、つぎつぎと、なしとげられていくようにみえます。
「さあ、はやく、あっちへいけっ。」
書生は、門の鉄のとびらをひらいて、光子さんを外につきとばし、そのまま、パタンととびらをしめて、うちにはいってしまいました。
光子さんは、書生につきとばされたとき、ひざを強くうったので、いたさに、そこにうつぶしたまま、シクシクと泣いていました。
ああ、「乞食王子」のまねなんかしなければよかった。あんな小説をおぼえていたばっかりに、とんだことになってしまった。あたしは、どうすればいいんだろう。
くよくよと、おなじことを、くりかえし、考えているうちに、ふと気がつくと、なにかおしりをつっつくものがあります。
おどろいて、うつむいていた顔をあげてみますと、いつのまにか、六人ほどの子どもたちにとりかこまれていました。
近くのいたずら小僧どもが、きたないこじきむすめがたおれているのを見て、あつまってきたのです。その中のひとりが棒きれをもって、光子さんのおしりをつっついたのです。
光子さんは、その子をにらみつけて、おきあがりました。すると、子どもたちは、ワーッといって、むこうへにげていきます。
もうこんなところに、たおれているわけにはいきません。子どもたちが、またいたずらをするにきまっているからです。
光子さんは、ひざのいたみをこらえて、たちあがり、トボトボと、歩きだしました。
「ワーイ、ワーイ、ばっちいおねえちゃんよう。どこへいくんだよう。」
あとから、子どもたちがゾロゾロついてきます。
ふりむいて、こわい顔で、にらみつけますと、子どもたちは、ワーッといって、にげますが、しばらくすると、また、ちかづいてきて、下品なことばで、からかうのです。
光子さんは、ワーッと声をあげて、泣きだしたくなりました。しかし、じっとこらえて、くちびるをかみしめて、トットと、急ぎ足に歩きました。
町かどを、まがりまがり、四百メートルも歩くと、いつのまにか、子どもたちは、あとをつけてこなくなりました。
ああ、たすかったと思いながら、バスの停留所のほうへ歩いていきます。いまから銀座のお店にいこう。そして、おとうさんにわけを話して、たすけてもらおう。そのほかにてだてはない。光子さんは、そう考えて、バスに乗るつもりでいたのですが、ふと気がつくと、一円もお金がないのです。といって、歩いて銀座までいくのは、たいへんです。どうしたらいいだろうと、思案しあんにくれるのでした。
光子さんは、すこしも気がつきませんでしたが、さっきから、いたずら小僧たちとはべつに、光子さんのあとをつけてくる、ひとりのあやしい男がありました。ネズミ色の背広に、ネズミ色のオーバーをきて、おなじ色の鳥打帽とりうちぼうをかぶっています。ひげのないツルッとした顔に、まんまるなめがねをかけているのですが、その顔が、なんだかへんなのです。
顔色がよくって、しわがなく、スベスベしていて、洋服屋のショーウインドーにかざってあるマネキンのような顔なのです。人形のような紳士です。
光子さんが、お金がなくて、バスに乗れないので、思案にくれて、たちどまっていますと、その人形紳士は、なにげなく、光子さんをおいこして、歩いていきましたが、そのとき、ポケットから銀貨をとりだして、そっと地面におとし、そのまま、むこうのかどをまがりました。
かどをまがったかとおもうと、そこにたちどまって、へいのかどから、目ばかり出して、そっと光子さんのほうを、のぞいているのです。
光子さんは、立ちどまっていても、しかたがないので、うなだれたまま、歩きだしましたが、目が地面にそそがれているので、すこし歩くと、さっき人形紳士がおとしていった銀貨をみつけました。ひろいあげてみると、百円銀貨です。これがあればバスにのれます。だれがおとしたのかしらないが、しばらくおかりしておこうと、心をきめました。それからは、急ぎ足になって、停留所につくと、銀座を通るバスをまって、乗りこみました。
さいわい、立っている人が多いので、車内のみんなに、きたない姿を見られることはありませんでしたが、車のすみに、ソッと立っていても、すぐ近くの人からは、ジロジロながめられました。車掌しゃしょうさんまでが、顔をしかめて、じっと、こちらを見ているのです。
光子さんは、そのはずかしさがいっぱいで、すこしも気づきませんでしたが、あのマネキンのような顔をした人形紳士も、このバスに乗っていました。
光子さんのあとから、乗りこんで、光子さんから、できるだけはなれて、そっぽをむいて、そしらぬ顔で、つりかわにぶらさがっているのです。ときどき、チラッ、チラッと、光子さんのほうを、ぬすみ見るのですが、光子さんは、銀座でおりるまで、気づかないでいました。
バスをおりると、光子さんは、すぐそこの玉村宝石店へいそぎましたが、人形紳士もそこでおりて、光子さんのあとをおいました。にぎやかな銀座通りのことですから、もう光子さんにかんづかれる心配はありません。
光子さんは、玉村宝石店のきらびやかなショーウインドーのあいだから、店にはいっていきました。
「おいおい、きみ、こんなとこにはいってきちゃいけない。おもらいなら、うらへまわりなさい。」
わかい店員が、光子さんのこじき姿を見て、どなりつけました。
光子さんは、その店員をよく知っていました。しかし、あいてには、こちらがわからないのです。
「ねえ、あたし、わけがあって、こんななりをしているけど、玉村光子よ。おとうさん、おくにいらっしゃるでしょう。通ってもいいわね。」
店員はびっくりして、まゆずみでよごれた光子さんの顔を、ジロジロとながめました。
「なんだって? 光子さんだって? おじょうさんが、そんなきたない服をきられるわけがないじゃないか。おどかさないでくれよ。さあ、出ていった、出ていった。」
「いいえ、どうしても、おとうさんにあいます。じゃましないで、おくにとおしておくれ。」
「いけない。いけないったら。こいつ気ちがいだな。さあ、出ていけ。出ていかないと、なぐるぞっ。」
そのさわぎをききつけたのか、そのとき、おくとのさかいのガラスのドアが、サッとひらいて、おとうさんの玉村銀之助さんの姿があらわれました。
「かまわないから、表おもてにほうりだしてしまいな。そいつはおそろしいかたりだ。顔がにているのをさいわい、光子だといって、わしをゆするつもりなんだ。はやく、ほうりだしてしまえ。」
ああ、おとうさんまでが、と思うと、光子さんは泣きだしたくなりました。
「おとうさん、わけをはなしますから、きくだけきいてください。こんななりをしていますが、あたしは光子にちがいないのです。」
死にものぐるいで、すがりつくようにたのみましたが、玉村さんは、とりあってくれませんでした。
「そのわけは、もうちゃんと知っている。ほんとうの光子からきいている。光子、あいつに顔を見せてやりなさい。」
その声におうじて、光子さんになりすました、あのこじきむすめが、玉村さんのうしろから、美しい顔を出しました。
ああ、なんというすばやさ! にせ光子は、ほんとうの光子が、おとうさんのたすけをもとめて、ここにくることをさっして、自動車でさきまわりをしたのでしょう。そして、おとうさんをときつけて、いつほんものがあらわれても、だいじょうぶなようにしておいたのです。
それにしても、玉村さんまでが、にせものを信じるというのは、にせものが、ほんものと、すこしもちがわないからです。どうして、こんなにもよくにた人間がいたのでしょう。考えられないことです。おそろしい夢でも見ているようです。これにはなにか、ふかいわけがあるのでしょう。いままでの科学では、とけないような、おそろしい秘密があるのでしょう。
しかし、光子さんは、そこまでは考えませんでした。ただ、くやしくて、かなしくて、はらわたがにえくりかえるようです。
「ちがいます。そいつが、にせものです。服をとりかえたのです。あたしの服を、そいつがきているのです。あたしがほんとうの光子です。」
気ちがいのように、泣きわめく、こじきむすめを、玉村さんは、おそろしい顔で、にらみつけました。
「わかっている。おまえのいいぐさは、もうちゃんとわかっているのだ。おい、みんな、かまわないから、そいつを、表にほうりだしてしまえ。」
もう、どうすることもできません。光子さんのこじきむすめは、おおぜいの店員に、こづきまわされて、表につきだされてしまいました。
光子さんは、しばらく店の前に、うずくまっていましたが、やがて、あきらめはてたように、トボトボと、歩きはじめました。
すると、さっきの仮面のような顔の人形紳士が、どこからかあらわれて、光子さんに声をかけました。
「光子さん、きみが光子さんだということは、わしがよく知っている。きっとあかしをたててあげる。しかし、いまはいけない。ひとまず、わしのうちにきなさい。そして、計画をたてて、出なおすのだ。わかったね。さあ、わしのうちにいこう。」
ボソボソと、耳のそばで、ささやくようにいうのです。
「あなた、どなたですか。」
光子さんはびっくりして、ききかえしました。
「きみをよく知っているものです。あんしんしてついておいでなさい。さ、いきましょう。」
人形紳士は、そういったまま、しずかに歩きだしました。光子さんは、目に見えぬ糸でひっぱられでもするように、フラフラと、怪紳士のあとから、ついていくのでした。
銀一君のときは、白ひげのじいさんがあらわれ、光子さんのときは、人形みたいな顔の紳士があらわれて、どことも知れぬあやしい家へつれていき、そこの地下室に、とじこめてしまったのです。
玉村さんのうちには、にせの光子さんと銀一君が、ちゃんといるのですから、だれも、人間がいれかわったとは気がつきません。光子さんのにせものも、銀一君のにせものも、じつにうまく、ほんもののまねをしていたのです。
ところが、たったひとり、にせの銀一君をうたがっている少年がありました。
それは、いつか銀一君がスリをはたらくところをみつけた、松井少年です。銀一君の同級生の松井君です。
松井君は、玉村銀一君とそっくりの少年が、もうひとりいることを、知っていました。もしその少年が、銀一君といれかわったら、どうなるだろうと思うと、なんだかおそろしくなってきました。
ある日、松井君は、休みの時間に、学校の運動場を、玉村銀一君と、肩をならべて歩いていました。
「ねえ、玉村君、きみ、ほんとうに玉村君だろうね。」
松井君がみょうなことをいいました。
「なにをいってるんだ。ぼくは玉村だよ。どうして、そんなことをきくんだい。」
銀一君は、おこったような顔をしました。
「きみ、それじゃあ、少年探偵団のバッジをもってるかい?」
「きょうはもってないよ。うちにあるよ。」
松井君も玉村君も、少年探偵団員でした。団員はB・Dバッジを二十個以上、いつもポケットに入れていなければならない規則です。悪者につれていかれるようなとき、道にばらまいて、いくさきを知らせるためです。玉村君はその規則を知らないのでしょうか。
「じゃあ、七つ道具は?」
「えっ、七つ道具って?」
少年探偵団の七つ道具は、①B・Dバッジ ②万年筆型の懐中電灯 ③呼よび子この笛 ④虫めがね ⑤小型望遠鏡 ⑥磁石 ⑦手帳と鉛筆です。
「それももってないんだね。」
「うん。きょうはもってないよ。」
「じゃあ、なにとなにだかいってごらん。」
玉村君は、きゅうには答えられないで、しばらく考えていましたが、やがて、どもりながら、こんなことをいうのです。
「B・Dバッジ、それから懐中電灯、えーと、それから、オモチャのピストル、とびだしナイフ、えーとそれから……。」
そこで、いきづまってしまいました。玉村君は、七つ道具を知らないのです。松井君はさらに聞きました。
「じゃあね、七つ道具のほかに、団長と中学生の団員だけがもっている道具があるんだよ。なんだか知ってる?」
玉村君は、口をもぐもぐさせていますが、答えることができません。知らないらしいのです。
「縄なわばしごだよ。」
松井君がおしえますと、玉村君は、いかにも知ったかぶりに、
「そうだよ。縄ばしごだよ。二本の縄に、足をかける木の棒が、たくさんくくりつけてある。」
「ちがうよ。黒いきぬ糸を、よりあわせたひもだよ。二本じゃない。一本きりだよ。そのきぬひもに、三十センチおきに、足の指をかける、むすび玉がついているんだよ。」
「あっ、そうだ。ぼく、うっかりしてたよ。黒いきぬ糸だったねえ。」
玉村君はそういって、ごまかそうとしましたが、ほんとうは、なにも知らないことが、わかりました。
松井君は、いよいよ、こいつはにせものにちがいないと思いました。その場は、なにげなくわかれて、その日、学校がひけてから、明智探偵事務所の小林少年をたずねました。
明智先生は北海道に事件があって、旅行中でした。小林少年は、少女助手のマユミさんとふたりで、るす番をしていました。
小林君は、少年探偵団長です。すぐに松井君を応接室にとおして、話をききました。
松井君は、お祭りの日に、玉村銀一君とそっくりの少年を見たことから、きょう学校でのできごとまで、すっかり話しました。
「だから、ひょっとすると、玉村君は、にせものといれかわっているんじゃないかと思うのです。そんなによくにた人間がいるなんて、ふしぎでしょうがないけれど、ほんとうなんです。ぼくは、そいつがスリをはたらいているところを、ちゃんと見たんですからね。」
「へんな話だねえ。ふたごでもないのに、そっくりの人間が、ふたりいるなんて、ちょっと、考えられないことだねえ。」
さすがの小林少年も、こんな話をきくのは、はじめてでした。
「だから、ふしぎなんですよ。しかし、たしかに、ふたご以上に、よくにたやつがいるんです。そいつが、玉村君のまわりに、ウロウロしていたんですからね。ぼくはどうもあやしいと思うんです。バッジももっていないし、七つ道具のことも知らないのは、ほんとうの玉村君でないしょうこですよ。」
「なにか、たくらんでいるのかもしれないね。」
「玉村君のおとうさんは、宝石王でしょう。宝石を手に入れるための陰謀いんぼうかもしれません。玉村君のおとうさんに、このことを知らせてあげなくてもいいでしょうか。」
「うん、そうだね。明智先生がいらっしゃるといいんだが、一週間ぐらいはお帰りにならない。しかし、きみの話だと、ほってもおけないようだから、ぼくが玉村君のおとうさんにあって、このことをお話ししておいたほうがいいかもしれないね。」
「ええ、ぼくもそう思うんです。にせものといれかわった玉村君が、どこかで、ひどいめにあっていると、たいへんですからね。」
「じゃあ、電話をかけて、玉村さんのつごうを聞いてみよう。いまは銀座の店におられるだろうね。店をたずねるのがいい。すまいのほうにはにせの銀一君がいるんだからね。」
そこで、小林君が電話をかけますと、玉村銀之助さんは、ちょうど店にいて、電話口に出ました。
玉村さんは小林君をよく知っていました。名探偵明智小五郎あけちこごろうの少年助手として、たびたびてがらをたてて、新聞にのるものですから、小林少年の名を知らない人はありません。ことに玉村銀一君は少年探偵団員なので、その団長の小林君には、おとうさんも、したしみをかんじていたのです。
「うちの銀一が、いつもおせわになります。」
玉村さんは、電話口で、そんなあいさつをするのでした。
「その銀一君のことで、至急にお話ししたいことがあるのです。これからお店のほうに、おじゃましていいでしょうか。」
といいますと、それでは、お待ちしていますから、どうかおいでください、という返事でした。
それから三十分ほどたって、銀座の玉村宝石店の社長室には、社長の玉村銀之助さんと、小林少年と、松井少年とが、テーブルにむかいあっていました。
小林君が、松井君から聞いたことを、くわしく話しますと、玉村さんは、はじめは、そんなばかなことがと、とりあげようともしませんでしたが、小林君が、うたがわしいわけを、だんだん、話していきますと、玉村さんは腕をくんで、考えこんでしまいました。
そして、しばらくすると、ひとりごとのように、つぶやくのでした。
「そうすると、あのこじきむすめも、ほんとうの光子だったかもしれないぞ。」
「えっ、こじきむすめですって?」
小林君が、おどろいて聞きかえします。
「二─三日前に、こじきむすめが、この店にやってきましてね。わたしがほんとうの光子だ。おとうさんのそばにいるのは、にせものだといいはるのです。
光子というのは銀一の姉ですが、その光子が、じぶんとよくにたこじきむすめと、服のとりかえっこをしたというのです。だが、そんなばかなことは、しんじられないので、こじきむすめを、店からつきだしてしまいましたが、思いだしてみると、そのこじきは、光子とそっくりの顔をしていました。銀一がにせものだとすると、光子もにせものと、いれかわっているかもしれない。
だが、まさかそんなことが……いや、いや、そうかもしれない。ああ、おそろしいことだ。このふしぎなできごとのうらには、なにかの、ふかいたくらみがあるのかもしれない。
しかし、そんなによくにた人間がいるものかしら。小林さん、きみはどう思います?」
「わかりません。なにか、とほうもない魔術がおこなわれているのです。この事件のうらには、おそろしい悪人がかくれているのかもしれません。
ぼくはこの事件を、探偵してみたいと思います。明智先生がおるすなので、ざんねんですが、ぼくにできるだけのことを、やってみたいと思います。」
「ああ、それは、わたしからおねがいしたいところです。わたしも、それとなく、光子と銀一のようすを注意しますが、あなたも外から、さぐってください。もし、にせものとすれば、どこかにかくれている、このたくらみのなかまと連絡をとるでしょうからね。」
それから、いろいろ、うちあわせをしたうえ、小林、松井の二少年は、玉村さんにいとまをつげて、それぞれの家に帰りました。
小林君は、そのばんから、きたないこじき少年にばけて、渋谷の玉村さんのうちの見はりをつづけました。
はじめの夜は、なにごともありませんでしたが、ふたばんめに、おそろしいことがおこりました。
月もない、まっくらな夜です。八時ごろでした。
玉村さんのやしきの、うらてのコンクリートべいの下に、一枚のむしろがすててあります。とおくの街灯の光で、それがぼんやりと見えています。
あっ、そのむしろが、モゾモゾと動きました。よく見ると、むしろの下に人間がいるのです。こじきが、むしろをかぶって、寝ているのかもしれません。そのへんは、さびしいやしき町ですから、なんのもの音もなく、死んだように、しずまりかえっています。
しばらくすると、町のむこうから、まっくろな大きなものが、スーッと、こちらへ近づいてきました。
ヘッドライトをけした自動車です。
そのあやしい自動車は、こじきの寝ているむしろのそばに、とまりました。
自動車のドアが、音もなくひらいて、へんてこな大きなものが、とびだしてきました。
金色に光っています。それは人間ではなくて、四つ足で歩く猛獣もうじゅうでした。トラです。黄金のトラです。
東京の町の中にトラがあらわれたのです。しかも、そいつは自動車に乗ってやってきたのです。
金色に光るトラは、そのへんをノソノソと歩いていましたが、グッと首を低くして、ねらいをさだめたかと思うと、パッと、ひととびで、コンクリートべいの上にかけあがり、まるで綱わたりのように、せまいへいのてっぺんを歩いていきます。
地面のむしろの下の人間は、首をもたげて、じっと、それを見つめていました。
へいの上を十メートルほど歩くと、黄金のトラは、玉村さんのやしきの中に、ピョイととびおりて、姿をけしてしまいました。
地面のむしろが、パッとはねのけられ、その下に寝ていた人間が、立ちあがりました。少年です。ボロボロの服をきた、こじき少年です。
少年は、すぐそばにとまっている自動車の中をのぞきました。そして、思わず、「おやっ。」と声をたてました。
自動車にはだれもいないのです。運転手もいないのです。では、あの金色のトラが、自動車を自分で運転してきたのでしょうか。そんな器用な猛獣がいるのでしょうか。
こじき少年は、だれもいないことをたしかめると、車のうしろにまわって、そこのトランクのふたに手をかけて、もちあげてみました。
すると、かぎがかけてないとみえて、ふたはスーッとひらきました。中をのぞくと、荷物もなく、からっぽです。こじき少年は、トランクにはいりこんで、その中に身をかくし、ふたをしめてしまいました。尾行するつもりなのです。
いまに黄金のトラがもどってくるでしょう。そして、自動車を運転して、どこかへいくでしょう。こじき少年は、そのいくさきを、つきとめるつもりなのです。
それから十分ほど、なにごともおこりませんでした。すこしのもの音もなく、すこしの動くものもありません。
やがて、コンクリートべいの上から、金色のものが、ヒョイとのぞきました。トラの顔です。らんらんと光る目で、じっとへいの外をながめています。
それから、へいの上にのぼって、ノソノソと歩きはじめ、自動車の近くまでくると、ピョイと地面にとびおりて、車の運転席にはいりこみました。
やっぱり、この猛獣は、自動車の運転ができるのです。
自動車は、さびしい町から、さびしい町へと走っていきます。
二十分もたったころ、大きな洋館の門の中にはいって、そこでとまりました。
黄金のトラは、自動車からおりて、四つんばいになって、玄関のドアの前までいくと、あと足で立ちあがり、まるで人間のように、ドアをひらくと、その中に姿をけしてしまいました。
こじき少年は、トランクのふたを、ほそめにひらいて、そのようすを見ていましたが、トラが中にはいってしまうと、ふたをぜんぶひらいて、トランクからはいだし、玄関のドアのそばまでいって、中のようすに、耳をすましました。
しばらくまって、そっとドアをひらいて、のぞいてみますと、どこかに、うすぐらい電灯がついていて、そのへんがボンヤリと見えています。
玄関のホールから、廊下がおくへつづいていますが、そこには人影もありません。いやトラの影もありません。
こじき少年は、だいたんにも、ドアの中にしのびこみ、足音をしのばせながら、廊下を、おくのほうへすすんでいきました。
二十メートルもいくと、むこうにキラッと光るものが見えました。黄金のトラの背中です。そいつは、やっぱり、あと足で立って歩いているのです。
「ウフフフフ……。」
どこからか、みょうな笑い声が聞こえてきます。
こじき少年は、びっくりして、たちどまりました。
ああ、やっぱりそうです。トラが笑ったのです。
「ウフフフフ……。」
そして、ヒョイと、こちらをふりむきました。らんらんと光る目が、ほそくなって、口は三日月みかづき形に笑っているのです。
「おい小林君。きみは、こじきにばけているが、明智の助手の小林だろう。うまく、おれの計略にかかったな。きみはきっと、おれを尾行するだろうと思った。それで、さそいをかけたのだよ。」
トラが人間のことばをしゃべったのです。
こじき少年は、やっぱり小林君でした。小林君は、まんまと敵のわなにかかってしまったのです。
これはいけないと思い、いそいで、にげだそうとしました。
「おっと、にげようたって、にげられやしないよ。ほらね。ワハハハ……。」
黄金のトラが、おそろしい声で笑いだしました。
その笑い声といっしょに、ダーッという音がして、てんじょうから大きな鉄ごうしがおちてきました。
廊下いっぱいの鉄ごうしです。もう、うしろへはいけません。
しかたがないので、前へつきすすもうとすると、またしても、ダダーッという地ひびきがして、前にも鉄ごうしがおちてきました。
前とうしろに鉄ごうしがおちたのですから、おりの中にとじこめられたのとおなじことです。
「ワハハハハ……、どうだ、このしかけには、おどろいたか。さすがの小林少年探偵も、きょうから、おれのとりこだ。いまに、べつの部屋にいれてやるから、ゆっくり、滞在していくがいい。」
鉄ごうしのむこうから、トラがしゃべっているのです。ものをいうたびに、口がガッとさけて、赤い舌したがペロペロと動くのです。
「きみは、いったい何者だっ。」
小林君は、せいいっぱいの声で、どなりつけました。
「おれは人間だよ。しかし、きまった顔をもたない人間だ。だれにでもばけることができる。このとおり、猛獣にだってばけられる。トラにはかぎらない。シシにだって、ヒョウにだって、大蛇だいじゃにだって、ばけられるのだ。
おれの名をおしえてやろう。おれは百十四歳になるニコラ博士という魔術師だ。スーパーマンだ。」
「玉村銀一君とそっくりの少年をつれてきて、人間の入れかえをやったのは、きみだなっ。いったい玉村君をどこへかくしたのだ。」
「銀一君はここのうちにいるよ。いや、銀一君だけじゃない。いろいろな人間が、とりこにしてある。銀一君のねえさんもいるし、そのほかにも、きみの知らない人間がたくさんいる。」
「みんな、かえだまと、いれかえたんだな。」
「アハハハハ……、だんだんわかってきたようだな。おどろいたか。おれはどんな人間のかえだまでも、つくることができるのだ。
たとえば、きみとそっくりのかえだまだって、わけなくできる。魔法博士の神通力だよ。アハハハハ……。」
黄金のトラは、あと足で立ちあがって、自由自在に、人間のことばをしゃべっているのです。じつに、なんともいえない、ふしぎなありさまです。聞いているうちに、小林君は、ゾーッとおそろしくなってきました。
この金色のトラのいうことが、ほんとうだとすると、小林少年は、ここにとじこめられたまま、小林少年とそっくりのかえだまが、明智事務所に帰っていくことになるかもしれません。すると、どんなことがおこるでしょう。考えれば考えるほど、おそろしくなってくるではありませんか。
宝石王の玉村銀之助さんは、じぶんのやしきのまわりを見はっていた小林少年が怪人につれさられたことは、すこしも知りません。あのトラが自動車を運転するという奇妙な事件のあった翌日、午前十時ごろ、玉村さんはいつものように、自動車にのって、銀座の店へ出かけるのでした。
道路は自動車でいっぱいです。とある交差点で、何十台というトラックや、バスや、乗用車が、三列にならんでとまっていました。そうして、十分もじっとまっていなければならないのです。玉村さんは、車のこんざつには、なれていましたから、イライラしてもしかたがないと、じっと目をつぶって、クッションにもたれていました。
右の窓のガラスが、半分ひらいてあります。そのガラスをコツコツとたたくものがありました。
おやっとおもって、目をひらきますと、右がわすれすれに、一台の乗用車がとまっていて、その窓が、こちらの窓のすぐそばにあるのです。
玉村さんが、そこを見たときには、窓は、なにかボール紙のようなものでふさがれていて、中は見えませんでした。
しかし、さっき、コツコツと、こちらのガラスをたたいたのは、たしかに、その窓の中にいる人です。たたいておいて、ボール紙で窓にふたをして、かくれてしまったのでしょうか。
「へんだな。」とおもって、じっと見ていますと、ボール紙がすこしずつ下のほうへさがっていって、そのうしろから、黄色くひかったものが、のぞきました。
まだボール紙が、半分しかひらいていないので、そのものの姿は、はっきりわかりませんが、なんだか、とてつもない、へんてこなものです。
ボール紙は、またジリジリと下のほうへさがっていきます。そして、窓の中が、すっかり見えるようになりました。
玉村さんはギョッとして、おもわず、車の中で立ちあがりそうになりました。
半分ひらいたガラスの中に、おそろしいトラの顔があったのです。
ランランとかがやく、大きな目で、じっとこちらをにらんでいます。
玉村さんは、だれかが、でっかいトラのオモチャをひざの上にのせているのではないかとおもいました。
しかし、そのトラの顔は、人間の顔の倍もあるのです。そんなでっかいオモチャがあるのでしょうか。
いや、オモチャではありません。
トラの目が動きました。口がひらきました。口の中で、まっかな舌がヘラヘラと動きました。
「ウヘヘヘヘ……。」
なんともいえないへんな声で、トラが笑ったのです。まるで人間の老人のような、しわがれた声で、うすきみわるく笑ったのです。
笑えるのは人間だけで、ほかの動物は笑えないはずです。
しかも、トラのような猛獣が笑うなんて、おもいもよらないことです。
玉村さんは、あまりのふしぎさに、あっけにとられて、こわさもわすれて、ぼんやりしていました。
すると、こんどは、もっとへんなことがおこりました。トラがものをいったのです。
「用心するがいい。いまに、おそろしいことがおこる。」
たしかに、猛獣が人間のことばを、しゃべったのです。
玉村さんは、夢を見ているような気持で、まだぼんやりしていましたが、ふと気がつくと、ここは自動車の行列のまんなかです。大きな声をたてれば、みんなが、力をかしてくれるでしょう。いくら猛獣でも、このこんざつのなかを、うまくにげられるものではありません。
玉村さんは、前にいる運転手の肩をつついて、ささやきました。
「見たか。」
「ええ、見ました。」
ふたりで、もう一度、そのほうをふりむくと、むこうの窓は、またボール紙でふたをされて、トラの姿は見えませんでした。
「みんなに知らせよう。大きな声でさけぶんだ。」
はんたいがわのドアをひらいて、からだをのりだし、
「オーイ、たいへんだあ。ここの車の中にトラがいるぞう……。」
と、なんどもくりかえして、さけびました。
自動車にトラがのっているなんて、あんまりとっぴなことなので、はじめは、だれも信じませんでしたが、こちらが、しんけんにさけぶものですから、勇気のある運転手たちが、自動車からとびおりて、あつまってきました。
その人数がだんだんふえ、やがて、交通整理のおまわりさんまで、ピストルをにぎって、かけつけてきました。
みんなが、あやしい自動車のまわりをとりかこみました。
そのときには、窓のボール紙はなくなって、中が見とおせるようになっていましたが、そこにはひとりの紳士がこしかけているばかりで、トラなど、どこにも見えません。おまわりさんが、その紳士に声をかけて、ドアをひらき、中をのぞきこみました。
「この窓からトラの顔が見えたというんですが、まさか、トラといっしょにのっていたのではないでしょうね。」
「ハハハハ……、なにをおっしゃる。そんなばかなことが、あるはずはないじゃありませんか。だれが、そんなことをいったのですか。」
「この人ですよ。」
おまわりさんが、そこに立っている玉村さんを指さしました。
「ハハハハ……、あなた、夢でも見たんでしょう。車の中でうたたねしていたんじゃありませんか。」
「いや、たしかに、金色のトラが……。」
玉村さんはいいかえしましたが、見たところ、トラのかげも形もないのですから、けんかになりません。
「なあんだ、夢か。いくらなんでも、トラが自動車にのっているなんて、おかしいとおもったよ。」
みんな、チェッと舌うちをして、じぶんたちの自動車へかえっていきます。
おまわりさんは、ぐずぐずしていると、自動車がたまるばかりですから、どの車も、そのまますすむように、あいずをしました。
玉村さんも、あわてて車にのりこみ、出発しましたが、車の列は、交差点で三方にわかれ、いつのまにか、あのあやしい自動車を見うしなってしまいました。
玉村さんは銀座の店につくと、すぐに明智探偵事務所に電話をかけて、小林少年に店のほうへきてくれるようにたのみました。
それから三十分もすると、小林少年が、玉村宝石店の社長室へはいってきました。
読者のみなさん、なんだかへんですね。小林少年は、ゆうべ怪人のために、あやしい洋館の地下室に、とじこめられたはずではありませんか。小林君は、はやくも、そこからぬけだしてきたのでしょうか。いやいや、そうではなさそうです。そのことは、みなさんがよくごぞんじです。
しかし、玉村さんはなにも知りません。そこへやってきたのは、ほんとうの小林少年だと思いこんでいます。
玉村さんは小林君に、さっきの事件をくわしく話してきかせました。
「そのトラがね、わたしの顔を見て、用心するがいい、いまに、おそろしいことがおこる、といったのだよ。」
「えっ、トラがですか。」
小林君は、びっくりしたように、ききかえしました。ほんとうの小林少年なら、じぶんも、ゆうべ、金色のトラがしゃべるのをきいたはずではありませんか。
「そうだよ。トラがしゃべるなんて、信じられないことだ。しかし、ほんとうにしゃべったんだよ。」
「人間がトラにばけていたのでしょうか。」
「うん、わたしもそう思う。超人ニコラ博士だ。ニコラ博士は、なんにでも、ばけられるというじゃないか。
まずトラにばけて、わたしをおどかしておいて、それから、みんなにかこまれたときには紳士にばけかわって、すましていたのかもしれない。」
「でも、おそろしいことがおこるぞと、予告をしたのですから、ゆだんはできませんね。」
「うん、それで、きみにきてもらったのだよ。この店には、たくさんの店員がいるけれども、あいてはおばけみたいなやつだからね。やっぱり名探偵のきみの知恵をかりたほうがいいとおもってね。」
「ありがとうございます。なによりも渋谷のおうちのほうが心配ですね。警察の力をかりるほかないでしょう。ぼくから警視庁の中村警部に電話でたのみましょう。そして、おうちのまわりを、まもってもらうようにしましょう。」
玉村さんもそれがいいというので、小林君は警視庁に電話をかけましたが、中村警部はすぐにしょうちして、その手配をしてくれました。中村警部は明智探偵の親友ですから、小林君をよく知っていて、少年だからといって、けいべつするようなことはないのです。
「ぼくはここにいて、あなたをまもります。なんだか、きょうは、あなたがあぶないような気がするんです。」
小林君は、そんなことをいって、部屋の中をコツコツと、歩きまわるのでした。
しばらくすると、若い店員が社長室へはいってきました。
「れいの大時計をトラックではこんできましたが、ごらんになりますか。」
「うん、ここにはこんで、ここでひらいてもらおう。なにしろ、いまではめったに手にはいらない美術品だからね。」
店員はそれをきくと、店のほうへもどっていきましたが、まもなく、ドカドカと足音がして、二メートルもある長方形の木箱きばこを、ふたりの運送屋の男が、はこびこんできました。
この木箱の中には、西洋では「おじいちゃん時計」といわれている、人間よりも背のたかい、ふりこ時計がはいっているはずです。
玉村商店は宝石商ですが、西洋の時計などもあつかっているので、ときどき、みょうな注文をうけることがあります。
あるお金持ちのおとくいが、明治時代にはやった「おじいちゃん時計」がほしいというので、さがしていたところが、りっぱな大時計がみつかったので、きょう、それを見せにきたというわけです。
その時計をみつけたブローカーの男が、ふたりの運送屋にはこばれる木箱につきそって、はいってきました。
「やあ、橋本はしもとさん、ごくろうさま。これがこのあいだお話しの時計ですね。」
玉村さんは、この橋本というブローカーとは、ついこのあいだ、はじめてあったのです。
「はい、じつにりっぱな美術品でございますよ。」
「機械もくるっていないですね。」
「ふしぎと、くるっておりません。ただしい時を知らせてくれますよ。」
「それはめずらしい。じゃあ、店のものもここによぶことにしましょうか。」
「いや、まず社長おひとりで、ごらんください。もったいぶるわけではありませんが、ひじょうにめずらしい品ですから。」
「わたしひとりでね。それもいいでしょう。しかし、この小林君は、ここにいてもかまいませんね。こんな小さいからだをしているが、じつは、わたしのボディーガードなんですよ。」
「かまいませんとも。そのかたがボディーガードですか。」
ブローカーはけげんそうな顔つきです。
「民間探偵明智小五郎さんの助手の小林君です。」
「ああ、あの有名な小林少年ですか。そういえば新聞の写真で、よくお目にかかってますよ。なるほど小林さんなら、たのもしいガードですね。」
そういうわけで、小林少年は、このめずらしい「おじいちゃん時計」を、玉村さんといっしょに見ることになったのですが、そうときまると、小林君はなにを思ったのか、玉村さんのそばによって、
「ドアのかぎを。」
と、ささやいて、手をだしました。
玉村さんは、ボディーガードにかぎをわたしておくのはあたりまえだとおもい、べつにうたがいもせず、ポケットからかぎを出してわたしました。
「では、箱をひらくことにします。」
ブローカーが、ふたりの運送屋の男に目くばせすると、ふたりは、くぎぬきをもって、ギイギイと、木箱のくぎをぬきはじめました。
そのとき、玉村さんが箱に気をとられているすきに、小林少年が、みょうなことをしました。
小林君は、玉村さんのほうをむいたまま、横いざりに、ドアの前までいって、手をうしろにまわして、なにくわぬ顔で、ドアにかぎをかけてしまったのです。
もっとへんなことがあります。小林君は、こちらをむいたまま、おしりのポケットから、大きなハンカチをまるめたようなものを、とりだして、ギュッと右手ににぎっているではありませんか。いったい、なにをしようというのでしょう。
「さあ、よくごらんください。」
ブローカーが、もったいぶったちょうしでいいました。
ふたりの男が、くぎをぬいてしまった木箱のふたを、横にのけますと、白い布ぬのでつつんだものが、箱いっぱいによこたわっています。
そのとき、部屋の中が、おそろしく、しんけんな空気で、みたされました。
ブローカーは、両手を、にぎりこぶしにして、おそろしい顔つきで、玉村さんをにらみつけています。
小林少年は、ドアの前から、ジリジリと、玉村さんのうしろへと、ちかづいていきます。手には、あの白いきれをまるめたものを、いつでもつかえるように、用意していました。
ふたりの男は、箱の中の白布しらぬのの、両はしをもって、一、二、三で、パッとはねのけようと、身がまえしています。
一、二、三の号令ごうれいがかかったわけではありません。しかし、ブローカーのぶきみな目が、それとおなじはたらきをしました。
パッと、白布が、めくりとられました。
「あっ!」
玉村さんは、おもわずさけんだまま、身動きもできなくなってしまいました。
木箱の中には、大時計ではなくて、ひとりの人間がよこたわっていたのです。
死人でしょうか。いやいや、生きています。しかも、それは、じつにおどろくべき人間だったのです。
その男は、箱の中でゆっくりと上半身をおこし、それからヒョイと立ちあがると、箱の外へでました。
ああ、ごらんなさい。玉村さんが、ふたりになったではありませんか。
いま箱からでた男は、玉村さんとそっくりの顔をしています。背広やネクタイまで、玉村さんのとおなじです。ふたりの玉村さんが、むかいあって、一メートルのちかさで、顔をにらみあって、立ちはだかっているのです。
じつにふしぎなありさまでした。じっと見ていますと、どちらがほんもので、どちらがにせものだか、わからなくなってきます。
こんなにもよくにた人間が、この世にあるものでしょうか。超人ニコラ博士の魔術にちがいありません。しかし、このおそろしい魔術は、いったい、どんな種があるのでしょうか。
玉村さんも、そこに気がつきました。このまま、じっとしていたら、箱からでてきた男が、じぶんになりすまし、じぶんは箱づめになって、どこかへ、つれさられるのにちがいないと、気がついたのです。
店にはおおぜいの店員がいます。大声でたすけをもとめたら、すぐにかけつけてくるはずです。
玉村さんは、口をいっぱいにひらいてわめき声をたてようとしました。
しかし、そのときはもうおそかったのです。いっぱいにひらいた口に、パッと、白いハンカチのようなものが、とびついて、ふたをしてしまいました。小林少年が、うしろから手をまわして、麻酔薬をしませたきれを、玉村さんの口と鼻に、おしつけたのです。
それからあとは、手ばやくパタパタとことがはこばれてしまいました。
麻酔薬で気をうしなった玉村さんは、木箱の中にねかされ、箱のふたがくぎづけになりました。
にせの玉村さんは、ゆったりと安楽あんらくいすにこしかけて、さも社長さんらしい口ぶりで、さしずをしました。
「小林君、ドアをあけて、店のものをよんでくださらんか。」
小林少年は、いうまでもなく、これもにせものですが、さっきのかぎをポケットからだして、ドアをひらき、
「店のかた、ちょっときてください。」
と、声をかけました。
ひとりの若い店員が、いそいではいってきました。
「じつにけしからん。きみ、これをすぐに、もってかえってください。こんなにせものに、ごまかされるわしじゃあない。」
といって、いまはいってきた店員のほうにむきなおり、
「この人をおくりだしてくれたまえ。この人は、とんだごまかしものを、もちこんできたのだ。」
ブローカーの男は、首うなだれて、ふたりの運送屋に木箱をはこばせ、しおしおと店をでていきました。
外にはトラックがまたせてあったので、木箱をそれにのせ、ブローカーもそのわきにのって、トラックは、どことも知れず、走りさってしまいました。
さて、銀座の店で、玉村銀之助さんが、にせものといれかえられたあくる日の夕方、渋谷区の玉村さんの家に、またしても、おそろしいことがおこったのです。
にせものの光子さんと、銀一君は、一階の子ども部屋の窓から、庭をながめていました。あたりはもううす暗くなっていて、木のしげった中は、まっくらです。
そのまっくらな中で、チラッと、金色のものが動いたのです。ふたりは、それを見つめていました。
「なにを見ているんだね。庭になにかいるのかね。」
ふりむくと、そこにおとうさんの銀之助さんが立っていて、にこにこ笑っていました。いうまでもなく、このおとうさんも、にせものなのです。
「木の下に金色のものが見えたんです。」
銀一君がこたえました。
「えっ、金色のものだって?」
「ええ、きっとあいつですよ。ね、あの金色のトラですよ。」
そのとき、家の横から、人の姿があらわれ、庭のむこうのほうへ、歩いていくのが見えました。洋服をきた女の姿です。
「あっ、おかあさんだわ。どうして庭へ出ていらっしゃったのでしょう。」
光子さんが、ふしぎそうに、つぶやきました。
「あっ、庭のへいの戸がひらいた。だれかはいってくる。おかあさんはきっと、あの人にあいにいったんだよ。」
銀一君が大きな声でいいました。
おかあさんのあき子さんは、夕やみの中を、いそぎ足で、裏口のほうへ、すすんでいきます。そこから、はいってきた男に、約束でもしてあったのでしょう。
あき子さんの歩いていく左がわに、大きな木のしげったところがあり、その中はまっくらです。
「あっ!」
光子さんも、銀一君も、おとうさんも、おなじように、おどろきの声をたてました。
木のしげみの中に、ピカッと光ったものがあるからです。
やがて、そのものが全身をあらわしたのを見ると、やっぱりあのおそろしい金色のトラでした。
そいつは、ノソノソと木のしげみから、はいだしてきて、ウオーッと、ものすごいうなり声をたてるのでした。
おかあさんのあき子さんは、ハッとして、そのほうを見ましたが、見たかと思うと、クナクナと、くずれるように、その場にたおれてしまいました。
それを窓からながめた、おとうさんも、光子、銀一のきょうだいも、ふつうならば、なんとかしておかあさんをたすけようと、とびだしていったのでしょうが、三人ともにせものですから、おかあさんがたおれたって、へいきです。
おとうさんと、ふたりの子どもは顔を見あわせて、ニンマリと笑いました。ああ、なんという、無慈悲むじひな笑い顔だったでしょう。
庭のむこうでは、裏口から、さっきの男のほかに、もうひとり、はいってくるのが見えました。
男たちは、たおれているあき子さんのそばによると、そのからだをふたりでかかえて、裏口の外へ出ていきます。
あの金色のトラは、あき子さんをきぜつさせてしまえば、もう用事はないのでしょう。また、木のしげみのくらやみの中に、姿をかくしてしまいました。
窓の三人は、もう一度、顔を見あわせて、ニンマリと笑いました。三人とも、あき子さんが、どんなめにあうのか、ちゃんと知っているらしいのです。
裏口のへいの外には、一台の自動車がとまっていました。ふたりの男は、その車のドアをひらいて、はこびだしてきたあき子さんのからだを、中にいれました。
すると、それといれちがいに、車の中から、あき子さんが、とびだしてきました。気をうしなっていたあき子さんが、きゅうに、正気しょうきづいて、いれられたばかりの車から、出てきたのでしょうか。
いや、そうではありません。車の中をのぞいてみますと、そこのシートに、あき子さんが目をつむって、たおれているではありませんか。
車から出てきたのは、あき子さんとそっくりの顔をした、べつの女なのです。ニコラ博士の魔法が、またしても、にせものをつくりだしたのです。
ふたりの男が、車の中にはいると、自動車はしずかに、すべりだし、どこともしれず、走りさってしまいました。
あき子さんとおなじ顔をして、おなじ服をきた女は、裏口をはいると、そこの戸をしめて、ゆっくり、こちらへちかづいてきました。
じつによくにています。男たちに、かつぎだされたあき子さんが、そのまま、もどってきたとしか思われません。
あき子さんは、窓の下までくると、そこからのぞいている三人を見あげて、ニッコリと笑いました。
「あき子、話があるから、あがっていらっしゃい。」
玉村さんが、声をかけました。これで玉村家の家族はぜんぶにせものにかわってしまったのです。
しかし、四人とも、おたがいにそれを知りながら、まるでほんもののように、はなしあっているのでした。
それからしばらくすると、玉村さんと、あき子夫人と、光子さんと、銀一君の四人は、玉村さんの書斎にあつまっていました。
その部屋の一方の壁に、大きな金庫がはめこんであります。にせの玉村さんは、ダイヤルの暗号を、ちゃんと知っていて、それをまわして、金庫をひらきました。
金庫の中には、たくさんのひきだしがついていて、それに宝石がいっぱいはいっているのです。
銀座の店においてあるのは、ありふれた宝石ばかりで、ほんとうにたいせつな宝石は、みんなこの金庫にしまってあるのです。店にある宝石でも、ひとつ百万円以上のものは、まい日かばんにいれてもちかえり、この金庫にしまっておくことになっていました。
「このひきだしには、何百という宝石がはいっている。十億円をこすわしの財産だ。どこへもっていこうと、わしの自由な財産だ。わかったかね。
この宝石のために、われわれは、こうしてはたらいているのだ。いや、ここにある宝石だけではない。宝石王玉村銀之助の信用を利用して、日本全国のめぼしい宝石を、すっかりあつめてしまおうというのが、ニコラ博士の計画だ。」
「どうして、あつめるのでしょうか。」
にせのあき子夫人が、ききかえしました。
「それには、こういう方法がある。まず、わしが主催者になって、全国の宝石商や、有名な宝石をもっているお金持ちによびかけて、宝石展覧会をひらくのだ。そして、日本のめぼしい宝石を、一ヵ所にあつめてしまうのだ。
展覧会をひらいているあいだに、出品されたぜんぶの宝石のにせものをつくるのだ。人間のにせものさえこしらえるニコラ博士のことだ、宝石のにせものぐらい、朝めし前だよ。そのにせものと、ほんものと、すりかえてしまう。わしは展覧会の主催者だから、すりかえるのは、わけもないことだからね。」
「ふーん、うまい考えですね。そうして展覧会の宝石をすりかえたあとは、わたしたちは、この世から消えうせてしまうのでしょうね。」
「そうだよ。そこで、われわれにせものの役目は、おわるのだ。」
にせの玉村さんは、金庫のとびらをしめると、ベルをおして、女中さんをよび、ばんごはんの用意をするように、いいつけました。玉村家にはコックのおばさんがいて、毎日おいしいごちそうをつくっているのです。
しばらくすると、四人は食堂のテーブルにむかって、食事をしていました。おいしい洋食のおさらが、つぎつぎとはこばれます。
玉村家の書生さんも、女中さんも、コックのおばさんも、玉村さんたち四人が、ぜんぶにせものとは、すこしも気がつきません。いつものご主人たちと信じきって、いいつけに、そむかないようにしていました。
「もうこれで、すっかり安心ですね。そのせいか、こんやのごちそうは、たいへん、おいしゅうございますわ。」
あき子夫人が、フォークで肉を口にはこびながら、たのしそうにいいました。
「うん、そうだね。わしも、このブドウ酒が、いつもよりもうまいようだ。それにしても宝石展覧会を、はやくひらきたいものだね。」
「ぼくたちも、その展覧会が、はやく見たいよ。ねえ、ねえさん。」
「ええ、日本中の有名な宝石が、ぜんぶあつまったら、どんなにきれいでしょうね。」
そのとき、女中さんがはいってきて、明智探偵の助手の小林少年が、たずねてきたことを知らせました。
「ああ、それはちょうどいい。ここにおとおししなさい。」
小林少年のにこにこ顔があらわれ、テーブルにすわりますと、そこに新しい料理のさらがはこばれ、小林君も食事のなかまにくわわりました。
「玉村さん、銀一君の友だちの松井君が、へんなことをいってきたので、ぼくも一度は光子さんや銀一君をうたがいましたが、みんな松井君のひとりがてんだとわかりました。同じ顔の人間が、この世にふたりいるなんて考えられないことですからね。」
「そうですよ、小林さん。そんなばかなこと、あるはずがないやね。おかげで、わしもすっかり安心しましたよ。」
玉村さんはそういって、さっきの宝石展覧会の話をしました。
「そりゃすばらしいですね。日本中の名だかい宝石を、ぜんぶあつめる展覧会なんて、これまで一度もなかったでしょう。ぼくも見にいきますよ。どんなに美しいことでしょうね。」
もちろん、この小林少年もにせものです。五人のにせものが、同じテーブルをかこんで、さもほんものらしく、たのしげに語りあっているのです。
お話かわって、やはりそのころの、ある夜のことでした。
少年探偵団のおもな少年たち十人が、芝公園の森の中にあつまっていました。
その十人のなかには、小林団長と、中学二年の白井保君もまじっていました。白井君は銀座の白井美術店の子どもなのです。読者諸君はこの白井保君の名を、どこかで読まれたでしょう。ひとつ思いだしてみてください。
少年たちは小林団長のまわりを、まるくとりかこんでいました。空には満月にちかい月がさえて、みんなの顔を青白くてらしています。
「こんやここにあつまったのは、この森の中におこる、ふしぎなできごとを見るためです。きみたちは、映画やテレビで、アメリカのスーパーマンが空を飛ぶのを見たことがあるでしょう。あれとよくにたスーパーマンが、日本にもあらわれたのです。
ここにいる白井保君が、そのスーパーマンの空を飛ぶところを見たのです。そして、その人と話をしました。その人は、超人ニコラ博士と名のったそうです。」
「あ、超人ニコラ……。」
「ニコラ博士……。」
少年たちが、口々に、つぶやきました。超人ニコラ博士の名は、いつとはなく、少年探偵団員たちに知れわたっていたのです。
「ニコラ博士は白井君に約束しました。こんや八時に、芝公園のこの森の中に飛んでくるから、少年探偵団の友だちをさそって見にくるがいいといったそうです。
ぼくも、べつのときに、ニコラ博士にあったことがあります。そのとき、博士は長い白ひげを胸にたれた老人でした。しかし、博士のほんとうの姿はわかりません。自由に顔かたちをかえることができるからです。あるときは人形のような顔をしていたといいます。白井君があったときには、どんな顔をしていたのですか。」
「まっかな顔をしていました。かみの毛も、まゆ毛も白くて白いひげをはやしていました。むかしの絵にあるテングにそっくりでした。」
「そうだ、日本のテングも空を飛ぶことができた。だから、博士はテングの姿になって、飛んでみせるのだよ。」
ニコラ博士が、どういう悪事をはたらいているか、少年たちには、まだよくわかりません。ですから、これを警察に知らせて、博士をつかまえるということは、考えてもみないのでした。それよりも、スーパーマンが空を飛ぶのを、見たくてたまらなかったのです。
「いま七時五十分だ。森の中にはいって、まつことにしよう。月の光であかるいから、空飛ぶ博士が、よく見えるだろう。」
十人の少年たちは、ゾロゾロと森の中にはいっていきました。高い木が立ちならんでいるあいだに、まるい空地があります。
「約束の場所は、ここだよ。」
白井君がそういって、みんなの歩くのをとめました。
十人は空地の一方のすみに、ひとかたまりになって、ボソボソと、ささやきあっています。
「八時五分前だよ。」
小林団長が、腕時計を月の光にすかして見ながら、いいました。
もうあと四分、……三分、……二分、……一分。八時はまたたくまに、ちかづいてきました。
「あっ、飛んでくる。ほら……。」
ひとりの少年が、空を指さして、さけびました。
ああ、ごらんなさい。むこうの空から、一直線に飛んでくるのです。黒いマントを、コウモリの羽のようにひるがえし、フサフサとした白ひげを風になびかせながら、両手をまっすぐ前につきだして、水の中をおよぐように、こちらへ、ちかづいてくるのです。
「あっ、赤い顔してる。でっかい鼻がついている。テングさまそっくりだ。」
もう、そこまで見わけられるのです。
空飛ぶ超人は、一本の高いスギの木のてっぺんにちかづくと、そのこずえの枝に、こしかけました。
「あなたは、ニコラ博士ですか。」
白井君が、大きな声でたずねました。
「そうだよ。きみたちは少年探偵団だね。」
「そうです。ここへおりてきませんか。」
こんどは、小林団長がさけびました。
「きみは、小林君だね。」
「そうです。」
「じゃあ、そこへいくよ。」
ニコラ博士は、サルのように、木の枝をつたいながら、少年たちのそばにおりてきました。
ほんとうに、まっかなテングさまの顔です。頭には、針金のような白いかみの毛が、モジャモジャとみだれています。
肩から黒いマントをヒラヒラさせて、その下には、ピッタリ身についた黒いシャツとズボンをはいているようです。
少年たちは、そのぶきみな姿に、思わず、あとじさりをしました。
「わしは、きみたちのような少年がすきだ。なにもしないから、こわがることはない。さあ、わしについて、こちらへくるがいい。きみたちに、おもしろいものを見せてやるよ。」
こわい顔をしていますが、いうことはやさしいので、少年たちは、だんだんニコラ博士のほうへ、ちかよっていきました。
すると、博士は、
「さあ、わしについてくるのだ。」
といいながら、森のおくへと、はいっていきます。
十人の少年たちは、あとにつづきました。枝がしげりあっているので、月の光もささず、そのへんはもうまっくらです。
ニコラ博士は、フワフワと、宙ちゅうにうくように、歩いていきます。やみのなかでも、博士の姿だけは、クッキリと見えるのです。
「あっ。」
びっくりするようなさけび声が、ひびきわたりました。ひとりや、ふたりの声ではありません。十人の少年が、一度にさけんだような、おそろしい声でした。
少年たちの足の下の地面が、消えてしまったのです。あっというまに、十人のからだが、下へおちていきました。
ドシンと、しりもちをついたところは、木の葉がいっぱいたまっていて、それほどいたくはありませんでした。
しかし、それはふかい穴の底で、とても、はいあがることはできません。
「ワハハハハ……、ざまあみろ。少年探偵団は、なまいきにも、わしの正体を探偵しようとした。わしにはそれがちゃんとわかっていたので、ちょっと、おかえしをしたんだよ。ワハハハハ……、いいきみだ。いつまでも、その穴の中でくるしむがいい。」
ニコラ博士の笑い声は、だんだん、上のほうへ、とおざかっていきました。さっきのスギの木にのぼっていったのでしょう。
それからしばらくすると、スギの木のてっぺんから、大きなコウモリのようなものが、月夜の空へ飛びたっていくのが、ながめられました。むろん超人ニコラ博士の飛行姿です。
十人の少年がおちこんだのは、ニコラ博士が、まえもってこしらえておいた、おとし穴でした。大きな穴の上にかれ枝をならべ、その上に木の葉をつみかさねて、穴とわからないようにしてあったのです。
少年たちは、なかまの背中にのって、やっと穴の外にはいだし、こんどは、その上から手をのばして、なかまの少年たちを、ひっぱりあげるというやりかたで、とうとう、みんなが穴の外に出ることができました。
それにしても、少年たちを、ここにつれだしたのは小林団長と白井保君でした。このふたりが、とっくににせものにかわっていることは、読者諸君がよくごぞんじですね。にせものは、つまり博士の手下ですから、少年たちをくるしめる手びきをしたのは、あたりまえです。
ところで、ほんとうの小林君は、ニコラ博士の手下の、ふたりの男につれられて、地下室の牢屋の中へいれられてしまいました。
そのおなじ地下室には、玉村銀一君や、白井美術店の子どもの白井保君なども、とじこめられていたのですが、小林君のいれられた牢屋は、銀一君たちの牢屋とは、すこしはなれていましたので、小林君は、まだなにも知りません。
ふたりの男が、小林君を牢屋にいれて、鉄ごうしにかぎをかけて、いってしまいますと、それといれかわるように、鉄ごうしの外へ、白ひげの老人が、あらわれました。さっきまでトラにばけていたニコラ博士が、こんどは老人に姿をかえているのです。
「小林君、少年名探偵も、いくじがないねえ。まんまと、つかまってしまったじゃないか。しばらく、ここにいてもらうよ。ひもじいおもいなんかさせないから、ゆっくり、とまっていくがいい。」
「なぜ、ぼくをとじこめたのですか。」
小林君は、鉄ごうしに顔をくっつけるようにして、ききただしました。
「きみが、じゃまだからさ。わしが、おもうぞんぶんのことをやるのには、きみはじゃまものだ。いや、きみばかりじゃない。きみの先生の明智小五郎も、むろん、じゃまものだ。だから明智が北海道から、かえってきたら、やっぱり、ここに、とじこめてしまうつもりだよ。」
「えっ、明智先生を?」
小林君は、おもわず、大きな声をたてました。
「そうとも、わしは日本にきて、まもないが、明智小五郎のことは、よく知っている。日本で、なにかわるいことをするためには、まず、明智をやっつけなければならない。そうしなければ、こっちが、あいつにやられてしまうのだからね。ウフフフフ……。」
「明智先生が、きみなんかに、つかまるもんか。」
小林君は、顔をまっかにして、どなりました。
「ハハハハハ……、きみにとっちゃあ、神さまみたいな明智先生だからね。オールマイティーだからね。だが、このニコラ博士はそれ以上の力をもっているのだ。スーパーマンだ。ワハハハハ……、スーパーマンとオールマイティーの戦いだ。ゆかい、ゆかい、かんがえただけでも、胸がおどるよ。」
「ハハハハハ……。」
小林君も、まけないで、笑いとばしました。
「きみは明智先生を知らないのだ。きみみたいなおいぼれに、まけるような先生じゃない。いまに、びっくりするときがくるよ。」
「ウフフフフ……、小林君、なかなか、いせいがいいね。なあに、どちらが、びっくりするか、そのときになってみれば、わかることだ。それよりも、小林君、きみがここにとじこめられているあいだに、もうひとりのきみが、なにをしているか、知っているかね。」
「えっ、もうひとりのぼくだって?」
「そうとも、顔もからだも、きみとそっくりのやつが、もうひとりいるんだ。そして、きみのかわりに、だいじなしごとをやっているのだ。」
それをきくと、小林君は「しまった」とおもいました。小林君がこの事件にかかりあったのは、玉村銀一君が、にせものといれかわっているらしいことからでした。ニコラ博士は、なんかの魔力によって、ほんものと、全然ちがわない、にせの人間を、つくりだすことができるのかもしれません。そして、こんどは、小林君が、その魔力にかかったのです。小林君とそっくりの少年が、どこかに、もうひとり、いるらしいのです。
「ウフフフフ……、顔色がかわったね。おどろいたか。ニコラ博士の魔法が、こわくなったか。もうひとりのきみは、いま、あるところで、わしの命令のままに、はたらいているのだ。
え、わかるかね。きみがよびだせば、少年探偵団員は、みんな、あつまってくる。そして、きみのいうことには、なんでも、したがうのだ。
にせの小林は、なにを命令するかわからない。だから、少年探偵団員は、どんなひどいめにあうかも、わからない。いや、そんなことよりも、にせの小林は、もっともっと、おそろしい悪事をはたらいているかもしれないよ。
オールマイティーの明智先生だって、きみとそっくりの少年のいうことなら、信用するにちがいない。そうすると、どんなことがおこるだろうね。……え、小林君。にせの小林という武器をつかえば、オールマイティーが、オールマイティーでなくなってしまうのだよ。ハハハハハ……。」
ニコラ博士は、その笑い声をのこして、鉄ごうしの前から、むこうへ立ちさっていきました。
小林君は、すっかり、まいってしまいました。
じぶんとそっくりのにせものが、どっかで悪事をはたらいているのかとおもうと、気が気ではありません。しかも、その悪事が、どんなことだかわからないのですから、いよいよ心配です。
明智先生が北海道からかえられる日も、ちかづいています。もし、にせものが先生を出むかえて、うそをついたら、どんな危険なことがおこるかしれません。
考えれば、考えるほど、心配でしかたがありません。
いっこくも早く、ここからにげだし、にせもののばけのかわをはいで、わるいことのおこるのを、ふせがなければなりません。
どうしたら、ここをにげだすことができるでしょう。小林君は、しばらくのあいだ、しんけんな顔で、かんがえていましたが、やがて、なにをおもいついたのか、ニッコリと笑いました。
「あっ、そうだ。こういうときに、あれをつかうのだ。」
そんなひとりごとをいいながら、ポケットから、筒つつのようにまるめた、レザーのシースをとりだし、鉄ごうしの外から、のぞかれやしないかと、注意しながら、そのシースをひらきました。
それは電気工事をやる人が、腰にさげている皮のシースを小さくしたようなもので、小型のナイフ、ペンチ、ヤットコなどがさしてあり、また、ふといのや、ほそいのや、十センチあまりの針金が、何本もいれてあるのでした。少年探偵団の七つ道具のほかに、小林団長だけは、いつもこのシースを、用意しているのです。
小林君は、鉄ごうしのとびらの外がわの錠前じょうまえの穴をしらべて、それに合うふとさの針金をえらびだし、ヤットコを片手に、針金ざいくをはじめました。
針金を、錠前の穴にいれて、なにかコチコチやっていたかとおもうと、それをとりだして、さきのところを、ヤットコでキュッとまげ、また穴にはめて、コチコチやってから、とりだして、キュッとまげ、それをなんども、くりかえして、針金を、ふくざつな、かぎのような形に、まげてしまいました。
こうして、とっさのあいかぎができあがったのです。もとは、錠前やぶりのどろぼうが、かんがえだしたのですが、明智探偵はそれのつくりかたを知っていて、助手の小林少年におしえておいたのです。
この針金のあいかぎをつくるのには、いろいろなコツがあって、ひじょうにむずかしいのですが、小林君は、練習をかさねて、いまでは、それができるようになっていました。
玉村さんのへいの外で、金色のトラにであったのは午後八時ごろでしたから、いまはもう、真夜中です。ニコラ博士や、その手下のやつらは、もうねてしまったのでしょう。耳をすますと、シーンとしずまりかえっていて、なんのもの音もありません。小林君は、にげるのは、いまだとおもいました。
かぎのようになった針金を、錠前の穴にいれて、しずかにまわしますと、カチッと音がして、錠がはずれました。
そっと鉄ごうしのとびらをひらいて、外に出ると、もとのとおりにしめて、針金で、かぎをかけました。
あとで、小林君がいないことがわかっても、錠前はもとのとおりに、しまっているのですから、どうして出ていったかわからないので、びっくりするにちがいありません。こんどは、小林君のほうが魔法つかいになったわけです。
廊下のところどころに、小さな電灯がついているばかりなので、ひどくうすぐらいのです。どちらへいけば、外に出られるのか、まるで、けんとうもつきません。
小林君は、まず右のほうへいってみることにして、壁をつたうようにして、しずかに歩いていきました。
もしこのとき、小林君が右ではなくて左のほうへいったならば、そこに、じぶんがいれられていたのとおなじような、鉄ごうしの牢屋が、いくつもならんでいて、その中に、玉村銀一君などが、とじこめられているのを、みつけだしたでしょうが、そのときは、はんたいの方角へ、歩いていったのです。そして、そのかわりに、もっともっとおそろしいことに、ぶつかってしまったのです。
そこは、秘密の地下室ですから、コンクリートをながしこんだばかりの、ザラザラの灰色の壁がつづいています。
小林君は、足音をしのばせながら、その壁をつたって、おくへおくへと、すすんでいきました。うすぐらい廊下には、ところどころに、ドアがしまっています。ドアにでくわすたびに、そこに耳をつけるようにして、中のもの音をきこうとしましたが、人がいるのか、いないのか、なにもきこえません。
音のしないドアを三つすぎて、四つめにちかづきますと、ボソボソと、だれかの話し声がもれてくるではありませんか。
かぎ穴に目をあててみると、中には、あかあかと電灯がついていて、いすにかけた人の、うしろ姿が見えます。ひとりではありません。二─三人の人間が、テーブルにむかいあって、話をしているらしいのです。
「ぼくたちは、みょうなことから、先生の弟子になりましたが、先生の魔法の力には、まったくおどろいてしまいました。そっくりおなじ人間を、いくらでも、こしらえることができるなんて、人間の知恵ではありません。神さまか、悪魔の知恵です。あの三重の秘密室の中には、いったい、どんなしかけがあるのですか。」
手下の男の声です。「三重の秘密室」とは、なにをさすのでしょう。
読者諸君は、この地下の牢屋が、二重の秘密室であることを、ごぞんじでしょう。玉村銀一君がニコラ博士にかどわかされたとき、まず地下室の物置きにはいり、そこの壁のボタンをおして、二重の秘密室にはいったのでした。そこまではわかっています。しかし、「三重の秘密室」が、どこにあるかは、まだわかりません。たぶん、二重の秘密室の、もうひとつおくの、秘密室なのでしょう。
その「三重の秘密室」には、手下の男たちも、はいったことがないらしく、その中に、どんな秘密があるのかと、きいているのです。
「それは、まだいえない。いつかは、きみたちにもおしえるときがくるだろうが、いまはいえない。そこには、わしの魔法の種が、かくしてあるのだ。
ともかく、そこからは、ほんものとそっくりのにせものが、うまれてくる。いくらでも、うまれてくるのだ。」
「では、先生は、ほんものと、にせものと、人間のいれかえをやって、なにをしようというのですか。」
「それは、きみたちも、知っているじゃないか。まず宝石展覧会をひらくのだよ。にせの玉村銀之助にひらかせるのだ。玉村の信用で、日本全国の宝石があつまってくる。それをひとばんのうちに、にせ宝石といれかえて、ほんものはぜんぶ、わしがちょうだいするのだよ。」
ニコラ博士の声です。この宝石展覧会のたくらみも、読者諸君は、とっくに、ごぞんじのはずですね。
「宝石を手にいれたら、そのつぎには美術品ですか。」
また、べつの声がたずねます。
「そのとおり。だが、これは宝石みたいに、ぜんぶ一ヵ所にあつめるというわけにはいかん。まず美術商のもっているものからはじめて、それから、各地の博物館や、お寺の宝物ほうもつなどに手をのばしていく。
美術商の主人を、わしのつくったにせものといれかえ、博物館の館長や館員を、にせものといれかえ、お寺の坊さんを、にせものといれかえれば、美術品をぬすみだすなどわけもないことだよ。ウフフフフ……。」
ニコラ博士が、うすきみわるく笑いました。
「それでおしまいですか。先生の魔法でなら、どんなことだって、できないことはないようにおもわれますが。」
「たとえば?」
ニコラ博士は、弟子たちの知恵をためしでもするかのように、ききかえしました。
「たとえば、ある国を、のっとることも、かんたんにできるでしょうし、また、ある国をほろぼすこともできるでしょう。」
「ふーん、きみは大きなことを、かんがえているね。では、ある国をのっとるには、どうすればいいんだね。」
ニコラ博士は、自分はよく知っているけれども、あいてに、しゃべらせてみようというようなちょうしで、たずねます。
「それは、その国の総理大臣や、政党の首領などを、にせものといれかえればいいのです。そうすれば、その国のことは、いっさい、にせものの、おもうままになるじゃありませんか。
ある国をほろぼすのも、おなじことです。にせものの総理大臣や、政党の首領や、軍隊の長官が、めちゃくちゃをやれば、その国は、たちまち、ほろんでしまいます。」
「なるほど、だれでもかんがえることだね。わしの魔法の力によれば、どんな大きなことだって、できないことはない。わしは世界をかえてしまうことができる。世界をてんぷくさせることができる。また、ナポレオンのように、世界を征服することもできる。
もっとおそろしいことをいうならば、にせものの力で、原水爆の秘密をぬすむこともできるし、また、にせものによって、ふいに原水爆を爆発させることだってできるのだ。
人間のにせものを、自由に、うみだす力をもっているわしの字引きには、〝できない〟ということばはないのだ。
わしはいま、日本の宝石と美術品をわがものとするために、この魔力をつかおうとしているが、そのつぎには、日本そのものを、ぬすむかもしれない。いや、世界をてんぷくし、世界をぬすむかもしれない。もっとちがったいいかたをすれば、地球全体を、わしのものにしてしまうかもしれない。」
ニコラ博士は、うちょうてんになって、じぶんの魔力をじまんするのでした。
小林君は、この会話を立ちぎきして、心の底からおどろいてしまいました。
いかにも、だれのにせものでも、自由につくりだす力があれば、全世界をぬすむことだって、できないことはありません。ああ、なんというおそろしいことでしょう。
それにしても、その魔法の種のかくされている「三重の秘密室」というのは、いったい、どこにあるのでしょうか。
小林君は、なんとかして、その「三重の秘密室」にはいりたいとおもいました。
こんきよく、ニコラ博士をつけまわしていれば、いつかは、その秘密室にはいるにちがいありません。小林君は、あいてにさとられぬように、ニコラ博士を見はってやろうと考えました。
それには、ゆっくりことをはこぶほかはありません。このまま牢屋をからっぽにしておいては、にげだしたことを気づかれ、あいてを用心させてしまいますから、ひとまず、牢屋にもどらなければなりません。小林君は、針金のかぎで錠をひらいて、もとの牢屋の中にはいりました。
地下室には、夜も昼もありませんが、ニコラ博士の手下が食事をはこんでくるので、だいたいの時間がわかります。三度の食事がすめば、夜になり、見まわりも、とだえますので、それをまって、こっそり牢屋をぬけだし、ニコラ博士をみはることにしました。
小林君は、ニコラ博士の寝室をみつけたいとおもいました。なんとなく、寝室のどこかに、「三重の秘密室」への通路が、かくされているようにおもわれたからです。
やっと博士の寝室がみつかりました。おなじ地下室の一方のすみにある、小さな部屋で、ベッドと、つくえと、たんすがおいてあり、ニコラ博士は、その部屋で、ひとりで寝ることがわかりました。
ところが、この寝室に、ふしぎなことがおこったのです。
小林君がとらえられてから三日めの夜のことでした。ニコラ博士の寝室がわかったので、廊下のまがりかどにかくれて、そのほうを見はっていますと、ニコラ博士が寝室へはいっていくのが見えました。
あとから、だれかくるといけないので、しばらく、ようすを見てから、寝室の前にいき、ドアのかぎ穴から、そっとのぞいてみますと、寝室の中には、人のけはいもありません。
ベッドの半分と、机と、いすが見えていますが、そこにはだれもいないのです。かぎ穴から、部屋のぜんぶが見えるわけではありませんけれど、なんとなく、からっぽのかんじがするのです。
小林君は、おもいきって、そっとドアをひらいてみました。だれもいません。部屋の中へはいって、ベッドの下、机の下、たんすのうしろなどを、のぞいてみました。やっぱり、だれもいません。
ふしぎです。ニコラ博士が、この寝室にはいって、ドアをしめてから、ずっとドアを見ていました。博士が出ていけば、気がつかぬはずはありません。
壁か床に、秘密のぬけ穴でもあるのではないかと、さがしまわっていますと、どこからか、ドドドド……と、地ひびきのような音がきこえ、寝室ぜんたいが、かすかに、ふるえているようなかんじがします。
地震かとおもいましたが、どうもそうではなさそうです。
そのうちに、ギョッとするようなことに気がつきました。
しまっている入口のドアが、グングン下へさがっていくのです。というのは、つまり、部屋の床が、上へ上へと、あがっていくことなのです。
そのうちに、下へさがっていったドアが、すっかり見えなくなったかとおもうと、こんどは、上のほうから、べつのドアがさがってくるではありませんか。ドアだけではなく、壁もいっしょに、さがってくるのです。
ああ、わかりました。このニコラ博士の寝室は、部屋ぜんたいが、エレベーターのしかけになっているのです。ドアがさがったのではなくて、部屋そのものが上にあがり、一階上のドアと、ピッタリ合うところで、とまったのです。
この寝室は、まったくおなじ部屋が、上と下に二重にくっついているのです。
ニコラ博士がはいったのは、下の部屋でした。それがエレベーターのしかけで、下へおりていって、小林君がしのびこんだときには、いつのまにか、上の部屋とかわっていたのです。
ですから、そこに博士の姿が見えなかったのは、なんのふしぎもありません。そのとき博士のいる寝室は、地下室のもう一つ下の地下室、つまり地下二階へおりていって、小林君がしのびこんだのは、それとそっくりおなじにできている、上のほうの部屋だったのです。
ニコラ博士は、寝室全体のエレベーターを、下におろして、地下二階へおりていったのにちがいありません。しかし、そこには、いったい、なにがかくされているのでしょうか。
これほど大じかけな、秘密の出入り口をつくって、だれもはいれないようにしてあるところをみると、この地下二階には、よほどの秘密が、かくされているのにちがいありません。
小林君は、それを考えると、なんだか、からだじゅうの、うぶ毛が、ゾーッとさかだってくるような、いうにいわれないおそろしさをかんじました。
小林君のはいった部屋は、地下一階から、一つ上にあがったのですから、いまいるところは、一階にちがいありません。
小林君は気がつきました。この部屋は、エレベーターじかけで、下におりても、地下一階までしかおりないのですから、いつまでこの部屋にいても、地下二階の秘密をさぐることはできないと、気がついたのです。
ですから、いま、この部屋のドアをひらいて、一階に出て、ふつうの地下室におり、あの壁のボタンをおして、秘密の出入り口から、地下一階におり、ニコラ博士の寝室にしのびこむほかはありません。つまり、この部屋の真下にある、そっくりおなじ、もう一つの部屋にいくのには、そうするほかはないのです。
そのみちで、ニコラ博士の部下にみつかってはたいへんです。小林君は用心のうえにも用心をして、廊下から、廊下へと、しのび歩き、地下室の入口をみつけて、そこにおり、がらくたものがおいてある、つきあたりの部屋の壁のボタンをおして、地下一階におり、ニコラ博士の寝室へ、たどりつきました。
上下に二つつながっている、おなじ部屋の上のほうを出て、大まわりをして、下のほうの部屋まできたわけです。
かぎ穴からのぞいてみますと、だれもいません。ニコラ博士は、地下二階におりて、用事をすませ、地下一階にもどって、部屋を出ていったのでしょう。ドアにはかぎがかかっていました。
小林君は、また、針金をいろいろにまげて、錠前やぶりをしなければなりませんでした。
五分ほどかかって、やっとドアがひらきました。部屋にはいってドアをしめ、ベッドの下や、たんすのうしろなどを、よくしらべましたが、どこにも人間がかくれているようすはありません。
小林君は、もう一度、この部屋を地下二階におろして、そこの秘密をさぐりたいと思いましたが、どうすれば、下におりるのかわかりません。どこかに、スイッチか、おしボタンがあるのでしょうが、それをさがすのがたいへんです。
しかし少年探偵の小林君は、こういうことになれていました。かくしボタンなどは、どういう場所をさがせばいいか、いままでのたくさんの経験で、だいたいわかっているのです。
それでも、かくしボタンをみつけるのに、八分ほどかかりました。入口のドアには、中から針金で、かぎをかけておいて、さがしまわったのですが、ふいに、だれかがやってきやしないかと、気が気ではありません。
でも、うまいぐあいに、かくしボタンがみつかりました。ベッドの下のジュウタンの一ヵ所が、プクッと小さくふくれているのに気づいて、足でふんでみますと、それがかくしボタンでした。やにわに、部屋全体が、ブルブルふるえだしたのです。つまり、エレベーターがおりはじめたのです。
やがて、エレベーターがとまるのをまって、小林君は、針金のかぎで、ドアをひらき、そっと地下二階の廊下へふみだしました。
どこかに電灯はついているのですが、ひじょうにうすぐらくて、あたりのようすが、よくわかりません。
どこからか、つめたい風が、スーッとふいてきました。幽霊の手で顔をなでられたような気持です。小林君は、ブルブルッと、身ぶるいして、そこに立ちすくんでしまいました。
なんともいえないぶきみさです。人間界をはなれて死の国にはいってきたような、ふしぎなおそろしさです。
ここには、いったい、どんな秘密が、かくされているのでしょう。それを考えただけでも、心臓がドキドキしてきます。
そのうちに、目がなれてきて、あたりが見えるようになりました。
コンクリートの壁、コンクリートの床、なんのかざりもない灰色の廊下が、つづいています。おっかなびっくりで、その廊下を、たどっていきますと、やがて、両がわに、たてにながいロッカーが、ズラッとならんでいるところにきました。
ロッカーににているけれども、ふつうのロッカーよりは、幅が広く、人間ひとり、じゅうぶんはいれるほどの大きさで、なんだか、気味のわるいかっこうをしています。まるで、かんおけをたてにして、ならべたようなかんじです。
このふしぎなロッカーは、両がわに、あわせて三十個ほどならんでいましたが、そのとびらには、小さいネーム・プレートがついていて、エナメルで、ローマ字と数字とが、T1、T2、S1、S2、A1、A2などと書いてあるのです。
小林君は、すぐ目の前のT1のとびらをひっぱってみましたが、かぎがかかっているとみえて、ひらきません。かぎがかけてあるからには、中になにかだいじなものがいれてあるのでしょう。
それはなんでしょうか。こんなところに、ふつうのロッカーがあるはずはありません。その中にオーバーなんかがはいっているとは考えられないのです。
では、なにがはいっているのでしょうか?
小林君は、なぜか、ゾーッと、からだがさむくなるような気がしました。針金を使えば、とびらをひらくのは、わけはありません。しかし、とびらをひらくのが、なんだかこわいのです。
でも、とうとう決心をして針金のかぎで、そのT1と書いてある、ロッカーのような箱のふたをひらきました。ひらいたかと思うと、
「あっ!」
とさけんで、まっさおになって、ピシャンとふたをしめてしまいました。
そこには、なんだか、へんなものがいたのです。気味のわるいものが立っていたのです。
それは人間でした。しかも小林君のよく知っている少年でした。
玉村銀一。そうです。少年探偵団員の玉村銀一君とそっくりの少年が立っていたのです。
銀一君が、どうして、こんな箱の中にとじこめられているのでしょう。こうして立たされていては、足がつかれてしまうでしょうし、ピッタリふたがしめてあるので、息もできないでしょう。じつにおそろしいごうもんです。
しかし、どうもへんです。小林君と顔を見あわせたとき、銀一君は、なにもいわないで、じっと立っていました。「小林さん」とさけんで、とびだしてくるはずではありませんか。それとも、銀一君は、立ったまま、気をうしなっているのでしょうか。
小林君は、勇気をだして、もう一度箱のふたをあけてみました。
やっぱり、玉村銀一君です。いつも着ている服を着て、正面をむいたまま、まばたきもしないで、立っています。
「玉村君、きみは、玉村銀一君だね。」
声をかけても返事もしません。こちらの顔を見ようともしません。
小林君は、銀一君の腕に手をかけてゆすぶってみました。すると、銀一君のからだが、ユラユラとゆれたのですが、そのゆれかたがへんでした。
それは人間ではなくて、人形だったのです。プラスチックでできた人形だったのです。じつによくできていました。銀一君にそっくりです。
気がつくと、人形の立っている足の下にひきだしが一つついていました。
それをあけてみますと、中に写真がたくさんはいっているのです。
みんな玉村銀一君の写真です。顔と全身を、前から、うしろから、横からと、あらゆる角度からとったものです。
ああ、わかりました。これらの写真をもとにして、この人形をつくったのです。これだけたくさんの写真があれば、銀一君とそっくりの人形をつくることもできるでしょう。
だが、なんのために、こんな人形をつくったのでしょうか。そこがどうもよくわかりません。
小林君は、ふと、みょうなことを考えました。超人ニコラ博士はにせものをつくったあとで、ほんもののほうは、人形にしてしまったのではないかということです。魔法つかいのニコラ博士にとっては、人間を人形にかえてしまうぐらいはわけのないことでしょう。
この、ロッカーみたいな箱の中には、ほかにも、たくさんの人形がはいっているのかもしれません。小林君は、いよいよ、気味がわるくなってきましたが、勇気を出して、針金のかぎで、つぎのT2のふたをひらいてみました。
その中には、美しい女の子が立っていました。まだあったことはないけれども、銀一君のねえさんの光子さんかもしれません。光子さんもにせものにかわっているらしいことは、玉村銀之助さんからきいていました。
そのつぎには、T3というふたをひらいてみました。
「おやっ、銀一君のおとうさんまで!」
そこに立っているのは、たしかに宝石王の玉村銀之助さんでした。
「すると、このあいだ銀座の店であったのは、にせものだったのかしら。」
小林君は、小首こくびをかしげました。あれがにせものだったとは、どうにも考えられないのです。
そうです。あのときの玉村さんは、まだほんものでした。読者諸君は、よく知っています。玉村さんが、にせの小林少年のために、大時計の箱にとじこめられたのは、あれよりあとのことでした。
小林君が、このロッカーのような箱の中を見ているときには、まだにせものとのいれかえは、すんでいませんでしたが、人形のほうは、もうちゃんとできていたのです。
小林君は、こうなったら、みんな見てやろうと、どきょうをきめました。
そして、つぎにひらいたのは、T4のふたです。そこには、三十五─六歳の女の人が立っていました。小林君はあったことがありませんが、これは銀一君のおかあさんらしいのです。
「おやおや、おかあさんまで、にせものといれかえるつもりだな。」
小林君は、思わず、つぶやきました。これで玉村さんの家族はぜんぶです。ニコラ博士は、玉村家の人をみんなにせものといれかえて、玉村家をのっとってしまうのでしょうか。それを考えると、怪博士の、あまりの悪だくみに、小林君は、心の底から、ふるえあがってしまいました。
こんどはS1のふたです。それをひらくと、銀一君よりはすこし大きい少年が立っていました。むろん人形です。小林君は知りませんでしたが、これは白井美術店の子どもの白井保君です。
つぎのS2の箱には、保君のにいさんの人形が、S3、S4と、ひらくにつれて、保君のおとうさんをはじめ、白井家の人たちが、ズラッとならんでいるのです。小林君はその人たちを、ひとりも知りませんが、じつは、白井美術店の主人の家族ぜんぶが、そこに人形にされていたのです。
ニコラ博士は、こうして、玉村宝石店をのっとったのとおなじように、白井美術店ものっとろうとしているのにちがいありません。
そのつぎにはA1のふたをあけてみました。針金をカチカチやって、なんの気なしに、そのふたをひらいたのですが、ひらくと同時に、小林君は、目をまんまるにして、立ちすくんでしまいました。
ああ、なんということでしょう。その箱の中には、もうひとり小林少年が立っていたではありませんか。顔もおなじ、服もおなじ、まるで鏡にでもうつったように、ふたりの小林君が、むかいあって立っているのです。
小林君は、おどろいてしまいました。じぶんとそっくりのやつが、こっちをにらみつけているのです。小林君は、こわい目をして、相手をにらんでやりました。しかし、人形は、いっこうにへいきです。そしてながいあいだ、小林君と小林君との、ふしぎなにらみあいがつづきました。
小林君が牢屋にいれられたとき、ニコラ博士がやってきて、
「きみのにせものが、外ではたらいている。そのあいだ、ほんもののきみは、ここにとじこめておくのだ。」
といいました。では、この人形が、そのにせものなのでしょうか。
いや、そうではありますまい。にせものは、どこかで、生きて動いているはずです。すると、この人形は、なんのために、つくられたのでしょうか。
小林君は、しばらく考えていましたが、やがて、そのわけがわかりかけてきました。
「ああ、そうだ。まずぼくの写真をあつめたにちがいない。ぼくの知らないまに、だれかがとったのだ。」
ねんのために、人形の足の下のひきだしをあけてみますと、小林君の写真が何十枚もはいっていました。顔だけのもの、全身のもの、前から、うしろから、横からと、あらゆる方角からとった写真がたくさん出てきたのです。
「この写真をもとにして、プラスチックの人形をつくったのだ。この人形が、いわば原型なんだ。そして、なにかの魔法で、原型のとおりの、生きた人間をつくりだすのだ。
つまり、ほんとうのぼくと、人形とにせもののぼくと、三人のぼくがいるわけだな。」
小林君は、そう考えて、ひとり、うなずくのでした。
「じゃあ、つぎのA2の箱には、だれがはいっているのだろう。」
やっぱり、あけてみないではいられません。
小林君は針金でかぎ穴をカチカチいわせて、そのふたをひらきました。
「あっ、先生!」
とんきょうな声をたてたのも、むりはありません。そこには、名探偵明智小五郎が、にこやかにほほえみながら立っていたのです。
むろん人形です。足の下のひきだしをひらいてみると、やっぱり、明智先生のいろいろな写真が、どっさり、そろっていました。
「すると、あいつは、明智先生のにせものも、つくる気なんだな。」
小林君は、なんだかこわくなってきました。明智先生は、まだ北海道からおかえりにならないが、ひょっとしたら、旅さきで、とっくに、にせものとかわっているのではないだろうかと思うと、ゾーッとしないではいられませんでした。
小林君は、それからも、つぎつぎと、箱をひらいてみましたが、あとには、見知らぬ人形が五つほど、はいっていたばかりで、そのほかの箱は、ぜんぶからっぽでした。これから、べつの人形をいれるために、のこしてあるのでしょう。
小林君は、人形箱を見てしまうと、つぎの秘密が、知りたくなりました。これらの人形をもとにして、どうして、にせの人間をつくるのか、その秘密が、やっぱり、この第三の地下室の中に、かくされているにちがいないのです。
ロッカーのような人形箱のならんだ、せまい廊下を、まっすぐにいきますと、そのつきあたりに、がんじょうなドアが、しまっていました。
ドアに耳をつけてみましたが、なんのもの音もせず、シーンと、しずまりかえっています。
かぎ穴からのぞいてみました。
あっ、なんというあかるさ! まるで、まっぴるまの原っぱのようです。しかし、そこは地下二階ですから、太陽の光がさしているはずはありません。やっぱり電灯でしょう。おそろしくあかるい電灯が、部屋じゅういっぱいに、かがやいているのです。
小林君は、また針金のかぎを、使いました。すこしてまどりましたが、とうとうドアがひらき、小林君は、広い部屋の中に、ふみこみました。
そして、おどろきのあまり、あっと、たちすくんでしまいました。
そこは、絵でも写真でも、一度も見たことのないような、ふしぎな機械の部屋でした。あらゆる形の機械が、部屋じゅうに、みちあふれているのです。
いっぽうには、手術台のようなものがあり、そのそばのガラス戸だなには、キラキラひかるメスやハサミや、そのほかさまざまのおそろしい道具が、いっぱいにならんでいました。
いっぽうには、歯科医の治療台のようなものが、いくつもならび、また、べつのすみには、大きな化学の実験台があって、その上に、あらゆる形のガラスの道具がならび、ガスの炎ほのおの上の、まるいガラスビンの中には、血のような液体が、フツフツとあわだっているのです。
小林君は、びっくりして、たちすくんでいましたが、すると、むこうの機械のあいだから、みょうな人間が、あらわれてきました。
頭は、かみそりできれいにそった、まるぼうずです。顔はしわだらけで、ひろいひたいの下に、まんまるな目がギョロッと、ひかっています。
まゆ毛は、ひどくうすいので、あるのかないのかわかりません。ひらべったくて、ペシャンコの鼻、その下に、大きな赤いくちびるが、まるで虫のように、モグモグうごいています。
服は青いもめんの労働服で、その上にまっ白な手術着のようなものを、はおっています。
子どものように背がひくくて、その胴体の上に、じいさんの首がのっているという、ふしぎな人間です。一寸法師いっすんぼうしという、かたわものなのでしょう。
そいつは、ニヤニヤわらいながら、こちらへちかづいてきました。そして、まっかなくちびるを、大きくひらいて、こんなことをいいました。
「おお、よくきた。おまえは、わしのつくったA1号だな。」
そして、つくづく小林君の顔を、ながめながら、
「うん、よくできた。A1号の写真とそっくりじゃ。だれも、おまえを見やぶるものはあるまいて。ウフフフフフ、おまえは、わしの傑作じゃよ。」
小林君は、しばらくかんがえていましたが、やがて、一寸法師のいっていることが、わかってきました。A1号というのは、あの小林君とそっくりの人形が、はいっていたロッカーの番号です。
まず小林君のいろいろな写真をあつめ、それによってあの人形をつくり、その原型から、小林君とそっくりの生きた人間を、つくりだしたのに、ちがいありません。
しかし、どうして、そんなことができるのでしょう。このぶきみな一寸法師は、魔法つかいなのでしょうか。
超人ニコラ博士は、どんな人間にも、ばけることができます。では、この一寸法師も、やはりニコラ博士の、べつの姿ではないのでしょうか。
「あなたはニコラ博士ですか。」
小林君は、そうたずねてみました。
「わしはニコラではない。」
一寸法師がこたえました。
「では、あなたはだれです。」
「さあ、だれじゃったか。わしはわすれたよ。」
なんだかへんです。この一寸法師は、自分がだれだったか、忘れてしまったといっているのです。
「あなたは、ぼくをつくったといいましたね。どうして、そっくりおなじ人間が、つくれるのですか。あなたは魔法つかいですか。」
小林君は、そんなことをたずねないではいられませんでした。すると、一寸法師は、大きな口をあいて、歯のない歯ぐきを見せて、うすきみわるく、わらいました。
「ウフフフフフ、魔法つかいか。そうじゃ、魔法つかいといってもいい。だが、わしは医者だよ。魔法のような医術をつかうのじゃ。医術によって人間をつくりかえるのじゃ。つまり、わしは世界にたったひとりしかいない魔法医者なのじゃ。」
小林君は、そんなばかなことができるものかとおもいました。この一寸法師は、とんでもないホラふきか、気ちがいか、どちらかにちがいありません。
「ウフフフフ、みょうな顔をしているね。きみは、わしの手術をうけたことを、わすれてしまったのか。よろしい。それじゃあ、きみにあわせる人がある。きみはたしか、名探偵明智小五郎の助手じゃったね。ちょうどいい。まあ、こちらへきて見るがいい。」
一寸法師のみじかい手が、小林君の手をにぎって、グングンむこうへ、ひっぱっていくのです。ゴチャゴチャした機械のあいだをとおっていきますと、白い手術台のならんだところへ出ました。
一つの手術台に、だれかがよこたわっています。モジャモジャにみだれた髪の毛が見えています。
「もう麻酔がさめたころだ。きみ、気分はどうだね。」
一寸法師が、ねている人の顔を、のぞきこんで、はなしかけました。
すると、その人はパッチリ目をひらいて、ふしぎそうに、あたりを見まわしています。
「あっ、先生!」
小林少年は、とんきょうな声をたてて、手術台にかけよりました。
そこにねていたのは、名探偵明智小五郎だったのです。いや、明智探偵とそっくりの人間だったのです。
ほんとうの明智探偵は、まだ北海道からかえりません。こんなところにねているはずはないのです。
これは、A2という番号のロッカーの中にあった、明智とそっくりの人形をもとにして、一寸法師の魔法医者が、つくりだした人間にちがいありません。
そこにねている明智探偵は、小林君が「先生っ」とさけんで、ちかづいても、べつにおどろくようすもなく、知らん顔をしています。にせものですから、まだ小林君を知らないのです。
「A2号ですね。」
小林君が、ニヤッとわらっていいました。すると一寸法師は、
「そうじゃよ。つまり、明智探偵がふたりになったというわけさ。」
とこたえました。
「人形もいれると三人ですね。」
「ウフフフフ、そうじゃ、そうじゃ。おまえ、なかなか、かしこいのう。」
そういって、一寸法師は、みじかい手で、背のびをしながら、小林君の頭をなでるのでした。
一寸法師は、からだのかっこうが、へんなばかりでなく、いうことも、なんだかおかしいのです。気ちがいかもしれません。しかし、気ちがいに、どうして、こんな人間製造ができるのでしょう。じつに、ふしぎというほかはありません。
小林君が、なおも質問しようとしていますと、そのとき、部屋の入口のほうに、人の足音がして、だれかが、こちらへやってくるようです。
小林君はびっくりして、機械のかげに身をかくして、そのほうをながめますと、白ひげのニコラ博士が、こちらへやってくるのが見えました。
みつかっては、たいへんです。小林君は、あわてて、機械と機械のすきまを、おくふかく、にげこむのでした。
さて、それから、どんなことがあったか。小林君は、ニコラ博士にみつかることもなく、ながいあいだ、その機械室にいて、一寸法師の魔法医者の秘密を、すっかりききだしてしまいました。
それから三日のあいだに、小林君は、ニコラ博士の洋館のすみずみまで、のこるところなく、しらべあげました。
地下一階の牢屋のような鉄ごうしの中にとじこめられた、玉村宝石王一家、白井美術店一家の人たちとも、こっそり話をして、すべての事情を知ることができました。
それだけでなく、小林君は、いかにも明智探偵の弟子らしい、おもしろいトリックを考えついて、それをやってみることにしました。
そのトリックとは、いったい、どんなことだったのでしょうか。
いや、それよりも、一寸法師の魔法医者は、どのような方法によって、同じ人間をつくりだすことができたのでしょうか。
お話かわって、こちらはほんものの明智探偵です。小林君がニコラ博士にとらえられてから一週間ほどのち、明智探偵は北海道の事件をしゅびよく解決して、その日の午後、羽田はねだ空港につきました。
電報がうってあったので、小林君が自動車でむかえにきていました。そして、小林君と、もうひとり、三十歳ぐらいの見知らぬ男が、探偵のそばへよってきました。
「先生、おかえりなさい。事件がうまくかたづいたそうで、おめでとうございます。」
小林君があいさつをしますと、明智もニコニコして、
「うん、ありがとう。……で、その人は?」
と、見知らぬ男を目でさししめして、たずねました。
「こんどたのんだ先生のボディーガードです。くわしいことは、あとでおはなしします。先生、こちらにも、ふしぎな事件がおこっているのです。先生のおかえりをまちかねていました。」
「そうだってね。おもしろい事件らしいじゃないか。」
「ええ、これまで一度も手がけたことのない、ふしぎな事件です。事務所へかえってから、ご報告します。」
そして、三人はまたせてあった自動車にのりこみました。小林君が右がわに、見知らぬ男が左がわに、明智探偵を中にはさんで、こしかけたのです。
運転手も見かけたことのない男です。明智はちょっと、へんに思いましたが、車は事務所専用の「アケチ一号」ですし、小林君がついているので、べつに、ふかくもうたがいませんでした。
車は京浜けいひん国道を三十分もはしったかとおもうと、さびしい横町へまがりました。
「道がちがうじゃないか。」
明智探偵が、そういって、思わず腰をうかそうとしました。ハッと危険をかんじたからです。でも、小林君がいるのに、こんなみょうなことがおこるのはなぜだろうと、ふしぎに思いました。
ところが、明智が腰をうかしたときには、右手は小林君に、左手は見知らぬ男に、かたくにぎられて、うごきがとれなくなっていました。
「ぼくをどうしようというのだ。小林君、きみまでが……。」
とさけんで、小林少年の顔をにらみつけますと、おどろいたことには、その小林君が、ふてぶてしくわらいながら、こんなことをいうではありませんか。
「ウフフフフ、よくにているだろう。だが、おれは小林じゃないのさ。小林とそっくりの別の人間なのさ。ほんとうのことをいうとね、おれたちはみんな、超人ニコラ博士の手下なのさ。おっと、明智先生が、いくらつよくってもだめだよ。こちらには、これがあるんだからね。」
と、いったかと思うと、小林君によくにた少年と、見知らぬ男とが、左右からピストルをつきつけ、運転手も車をとめて、うしろをふりむくと、右手をグッとこちらに出して、やっぱりピストルを、さしむけるのでした。
こうして明智探偵は、目かくしをされ、さるぐつわをはめられ、両手をうしろにしばられて、もう、身動きもできなくなってしまいました。
それから、また四─五十分もはしって、車がついたのはニコラ博士の怪洋館でした。
明智探偵は三人につれられて、地下室から、第二の秘密室へ、そして鉄ごうしの牢屋の中へ、ほうりこまれてしまいました。
明智探偵が牢屋へいれられて、しばらくすると、白ひげのニコラ博士が、ゆうぜんと、地下室の見まわりにやってきました。そのうしろから、さっきの小林君によくにた少年がしたがっています。
玉村宝石店の親子四人がとじこめられている鉄ごうしのまえを、とおりすぎました。かわいそうに、四人のものは、部屋のすみにうずくまって、だまって、うなだれています。
そのむかいがわには、白井美術店の家族が、とじこめられ、おなじようにうなだれていました。
それから十メートルほどむこうに、小林少年のいる牢屋があります。ニコラ博士とにせの小林君が、そのまえをとおりかかると、鉄ごうしの中から、おそろしい声がひびいてきました。
「ニコラ先生、おれをここから出してください。おれはにせもののほうだ。そこにいるのが、ほんものの小林だ。小林がおれをここへとじこめて、じぶんはにげだしてしまったのだ。そして、にせものになりすましているのだ。」
ニコラ博士は、それをきいても、べつにおどろきません。小林君から、わけを知らされているからです。
「ね、そうでしょう。さすがは小林の知恵です。うまいことを考えました。ほんとうの小林が、どうかして鉄ごうしをあけて、にせものを引きいれ、替え玉の入れかえをやったというのです。だから、じぶんを牢から出して、かわりに、ぼくを入れようというのですよ。しかし、あいつはうそをついているにきまってます。なぜといって、ほんものの小林は、あいかぎを持っていないので、牢から出られっこないのですからね。かぎは、このにせの小林が、ちゃんとこうして、もっているのですからね。」
牢屋の外の小林は、そういって、ポケットからかぎたばをとりだし、チャラチャラと音をさせてみせました。
へんなことになってきました。ニコラ博士は知りませんが、読者諸君は知っています。小林君は、針金をつかって、じゆうじざいに、鉄ごうしの錠をあけることができるのです。それを、牢屋の外にいる小林君は、あいかぎがなければ、あけられないなどと、うそをついているではありませんか。
牢屋の中にいる小林よりも、外にいる小林のほうが、あやしいのではないでしょうか。つまり、中の小林が、じつはにせもので、外の小林がほんものではないのでしょうか。なんだかややこしいことになってきました。
しかし、もし、外にいる小林がほんものだとすると、明智探偵を自動車にのせて、とりこにし、この地下室の牢屋へ入れたのは、どういうわけでしょうか。ほんものの小林君なら、あくまで明智探偵のみかたをするはずではありませんか。
なんだかわけがわからなくなってきました。もうすこし、ようすを見ることにしましょう。そうすれば、やがてハッキリしたことがわかるでしょう。
さて、ニコラ博士と小林君とは、牢屋の見まわりをすませて、一階へあがっていきましたが、しばらくすると、こんどは、小林君だけが、こっそり地下室へおりてきました。そして、あの小林の牢屋の前をとおりかかると、またしても、中から、どなり声がきこえてきました。
「やい、そこへいくほんものの小林。うまく博士をごまかしたな。だが、きさまのうそが、いつまでもつづくはずはない。きっとそのうちに、見やぶられる。そのときは、どんなひどいめにあうか、かくごしているがいい。おれはきっと、きさまといれかわってみせるぞっ。」
中の小林は、鉄ごうしにすがりついて、ガタガタいわせながら、しきりに、どくぜつをたたいています。
外の小林君は、それをあいてにしないで、牢屋の前を通りすぎ、ニコラ博士の寝室へしのびこみました。ここのかぎだけは、ニコラ博士がはなしませんので、小林君は、やっぱり、針金をつかってドアをひらかなければなりませんでした。
小林君は、エレベーターのかくしボタンをおして、地下二階へおり、A2のロッカーから、明智探偵とそっくりの人形をとりだし、それをこわきにかかえて、もとの地下一階にもどり、さっき明智探偵をとじこめた牢屋へといそぎました。
エレベーターから、明智の牢屋へ行くのには、ほかの牢屋のまえをとおらなくてもよいので、人形をだいているのを、気づかれる心配はありません。
その鉄ごうしのまえへいくと、明智探偵は部屋のまんなかにすわって、おそろしい顔で、こちらをにらみつけていました。
小林君は、鉄ごうしに顔をくっつけて、ささやきました。
「先生、ぼくはほんとうの小林です。ぼくは一度牢屋へいれられたのですが、そこをぬけだし、うまくだまして、にせものと入れかわったのです。そして、ぼくは、ニコラ博士のみかたのにせものになりすましたのです。つまり替え玉の替え玉になったわけです。
さっきは、先生にピストルなどむけて、ごめんなさい。ああして、にせもののように見せておかないと先生をおたすけすることができないからです。
ニコラ博士は、ぼくをにせものと信じていますから、ぼくに牢屋のかぎをあずけました。ですから、この鉄ごうしをひらくのは、わけもないのです。」
小林君は、そういいながら、かぎたばをとりだして、鉄ごうしのドアをひらき、中へはいって、部屋のおくにしいてあるござの上に、いまもってきた明智探偵とそっくりの人形をよこたえ、もう一枚のござを、胸のへんまでかけました。こうしておけば、外から見たのでは、明智探偵がねているとしか思えませんから、ほんとうの明智がにげだしてしまっても、しばらくはだいじょうぶです。
「さあ、先生、にげましょう。とちゅうで、だれかに見つかるとたいへんですから、そういうときには、いそいで、廊下のくらいところへ、かくれなければなりません。しかし、ぼくは、じゅうぶん、にげ道をしらべておきましたから、まず、だいじょうぶだと思います。」
明智探偵といっしょに、外に出ると、小林君は、鉄ごうしのドアをしめて、かぎをかけました。そして、うすぐらい廊下の、壁をつたうようにして、秘密の地下室から、ふつうの地下室へ、それから一階へと、足音をしのばせて、いそぐのでした。
さいわい、だれにも見つからず、洋館の外に出ることができました。それから、さびしいやしき町を、はしるようにして大通りに出ると、タクシーをひろって、こういうときに、いつもつかう、渋谷駅ちかくの目だたない旅館へといそぎました。
旅館の一部屋へおちつくと、小林君は、これまでの、いっさいのことを、明智先生に話しました。
「いま午後四時半ですね。じつは今夜、おそろしいことがおこるのです。まだじゅうぶんまにあいます。それをふせがなければなりません。一寸法師の魔法医者は、先生とそっくりの人間をつくりました。そいつが明智探偵としてはたらくのです。
ぼくはニコラ博士のみかたの、にせ小林だとおもわれていたので、かれらの秘密のたくらみは、みんなきいてしまいました。ですから、今夜のことも知っているのです。」
そして、小林君は、そのおそろしいたくらみというのを、くわしく話してきかせるのでした。
小林少年が、ニコラ博士のとりことなった明智探偵をたすけだして、ニコラ博士のおそろしいたくらみを話してきかせた、あの日の夕方のことです。
お話かわって、世田谷せたがや区のやしき町に、広い邸宅をもっている、園田大造そのだだいぞうというお金持ちから、明智探偵事務所へ電話がかかってきました。
「明智先生ですか、ひじょうに重大な事件で、ご相談したいのですが、すぐ、わたしのうちまでおいでねがえませんでしょうか。」
園田さん自身が電話口に出て、声をふるわせてたのんでいるのです。
「重大な事件というのは、いったい、どんなふうな事件でしょうか。」
明智がたずねますと、
「いや、電話では話せません。ぜひ、お目にかかってお話したいのです。おそろしい事件です。先生のお力をかりなくては、どうにもならないのです。先生のことは、友人の菅原すがわら君の宝石事件で、よくぞんじております。どうか、わたしを助けてください。」
そうまでいわれては、たのみをきかないわけにはいきません。明智探偵は、すぐおうかがいするといって、電話をきりました。
それから一時間ほどして、園田さんの大きなやしきの洋風応接間に、主人の園田さんと、明智探偵と、助手の小林少年がテーブルをはさんで話しあっていました。
「すると、あいては、ニコラ博士ですね。」
明智が、しんけんな顔で、ききかえしました。
「そうです。わたしは毎朝、五時におきて、庭を散歩するのですが、けさ、庭を歩いていますと、木の間にあいつが立っていたのです。長いひげをはやした、七十歳ぐらいのじいさんです。そいつのからだは、青く光っていました。まだうすぐらい木のしげみの中ですから、幽霊のように、青く光っているのが、よくわかるのです。わたしは、びっくりして、にげだそうとしましたが、催眠術でもかけられたように、足が動かなくなって、にげることができません。
そいつは、じっと、わたしの顔を見つめながら、地の底からひびくような、気味のわるい声で、こんなことをいいました。
『わしは、おまえのだいじにしているダイヤモンド『青い炎』がほしいのだ。こん夜、かならずもらいにくるから、用心するがいい。だが、おまえがどんなに用心しても、わしは魔法つかいだから、かならず、とってみせるよ。』
そういって、ウフフフと笑ったかとおもうと、そこのヒノキのみきにつかまって、まるでサルのように、スルスルとのぼっていき、木の葉の間に、姿が見えなくなってしまいました。先生、それから、おそろしいことがおこったのです。」
園田さんは、そこでちょっとことばをきって、おびえたような目で、窓の外の空をながめました。
「ヒノキのてっぺんから、あいつが、空へとびたったのです。そして、朝やけの空を、アメリカのスーパーマンのように、両手を前につきだして、マントをヒラヒラさせて、ひじょうな速さで空中をとびさってしまったのです。」
園田さんは、まっさおな顔になっていました。
「ニコラ博士が空をとぶことは、ぼくもきいております。それについて、ぼくはある考えをもっているのですが……。ところで、そのあなたのダイヤモンドというのは、どこにおいてあるのですか。」
明智がたずねますと、園田さんは、なぜかニヤリと笑って、
「それはだれも知りません。わたしのほかには、だれも知らないのです。しかし、あいつはスーパーマンみたいなやつですから、宝石のかくし場所を知っているかもしれません。
このダイヤモンドには『青い炎』という名がついているのです。インドの仏像のひたいに、はめこんであったのを、あるイギリス人が手にいれて、それがまわりまわって、わたしのものになったのです。青い炎がもえるように、かがやいているので、そういう名がついたのです。二十五カラットもある大きなもので、日本では最大、最高のダイヤです。
ですから、わたしは、これを、ぜったいにわからないある場所にかくし、うちのものにも見せないようにしているのです。まして、他人には一度も見せたことがありません。
じつは、二─三日前に、ある有名な宝石商が、日本じゅうの宝石をあつめて、宝石展覧会をひらきたいから『青い炎』を出品してくれないかといってきたのですが、わたしは、ぜったいに人に見せるつもりはないといって、かたくことわったほどです。」
「そうですか。それほどの宝物でしたら、ぼくも、全力をつくして、おまもりしますが、そのダイヤモンドは、いったい、どこにかくしてあるのでしょうか。それをうかがっておかないと、まもるにもまもれないのですが。」
明智のことばに、園田さんはうなずいて、
「ごもっともです。先生にだけは、かくし場所を、おおしえするほかありません。いま、そこへごあんないしますから、どうかこちらへおいでください。」
といって、いすから立ちあがり、園田さんは、女中さんをよんで、明智探偵と小林少年のくつを、庭のほうへ、まわすようにいいつけておいて、廊下を、さきに立ってあるいていきました。
廊下を二つほどまがると、庭へおりるドアがひらいていて、三人はそこからおりていきました。
池や林のある、広い庭です。林の中を通りすぎると、ちょっとした広っぱがあり、そこにお寺のお堂のようなものが立っていました。
「わたしの持仏堂じぶつどうですよ。この中に、平安朝へいあんちょう時代の黄金仏が安置してあるのです。」
園田さんはそういって、お堂のとびらをひらき、ふたりを中にあんないしました。
うすぐらいお堂の中には、まんなかに大きな台があって、その上に、人間の倍もあるような、金色の仏像が立っていました。その台のまわりはグルッと石だたみでかこまれ、仏像を横からでも、うしろからでも見られるようになっているのです。
「うまいかくし場所でしょう。この仏像は国宝です。だれも国宝に傷をつけるなんて、考えもしないでしょう。ところが、わたしは傷をつけたのです。この仏像の背中に、十センチ四方ほどの、小さなきりくわせをつくって、それを宝石箱にしたのです。外から見たのでは、ちっともわかりません。こちらへきてごらんなさい。」
園田さんは仏像のうしろへまわりました。明智探偵と小林少年も、そのあとについていきましたが、仏像の背中のどこに、秘密のかくし場所があるのか、すこしもわかりません。
「このボタンをおせばいいのです。」
園田さんは、仏像の右のももにある、ちょっと見たのでは、わからないほどの、イボのようなものを、グッとおしました。すると、カタンと音がして、仏像の背中の四角いふたがひらいて十センチ四方ほどの穴があきました。
「この中に宝石がはいっているのです。だが、まってください。むやみに手をいれてはあぶない。どろぼうの用心がしてあるのです。宝石をとろうとして、手をいれると、穴の四方から、するどい鉄のツメが、サッととびだして、手にささり、どろぼうは動けなくなってしまうのです。
それをふせぐのには、もうひとつのかくしボタンをおせばよろしい。」
園田さんは、こんどは仏像の左のももの、やはり小さなイボのようなものをおしました。
「さあ、これで、もうだいじょうぶ。」
といいながら、穴の中へ手をいれて、ダイヤモンド「青い炎」をとりだし、明智探偵に見せるのでした。
ああ、なんというみごとな宝石でしょう。虹にじのように七色にかがやいているのですが、青の色がいちばんつよく、ほんとうに、青い炎がもえているようです。
「ぼくも、いろいろな宝石を見ましたが、こんなりっぱなのは、はじめてです。なるほど日本一のダイヤモンドですね。」
明智探偵も、思わず、ほめたたえないではいられませんでした。
「だから、ニコラ博士が目をつけたのですよ。だいじょうぶでしょうか。あいてはおそろしい魔法つかいですからね。」
園田さんは、心配そうです。
「ぼくがおひきうけしたら、だいじょうぶです。ぼくは魔法つかいというやつには、たびたび出あったことがありますが、一度も、やぶれたことはありません。あいてが魔法をつかえば、こちらも、それ以上の魔法をつかうからです。」
明智探偵の力づよい返事に、園田さんは、安心したようすで、宝石を穴の中にもどし、ボタンをおして、そのふたをしめました。
「ぼくは、いまから、夜にかけて、ずっと見はりをつづけましょう。しかし、このお堂の中にいたのでは、ダイヤはここにかくしてありますと、敵に知らせるようなものですから、ぼくと小林はお堂のそばの庭にかくれて、見はりをつづけます。もしニコラ博士がやってきたら、かならず、つかまえてお目にかけます。ここはぼくたちにまかせて、あなたは、うちにおもどりになっているほうがよろしいでしょう。」
園田さんが、うちの中へもどるのをまって、小林少年は、明智探偵になにかささやいたうえ、電話をかけるために、おもやへはいっていきましたが、それは、少年探偵団のおもな団員を、よびあつめるためでした。それから一時間もしますと、十人の団員が、園田さんの庭へ、つぎつぎと、あつまってきて、あちらこちらの木かげに身をかくして、ニコラ博士のやってくるのをまちうけました。この少年たちは、このあいだ芝公園で、ニコラ博士にひどいめにあっているので、きょうは、そのしかえしをしてやろうと、はりきっているのです。
そして、日がくれ、だんだん夜がふけていきました。
夜の十時に、園田さんに電話がかかってきました。
「わしがだれだか、いわなくても、わかっているじゃろう。うん、そのとおり、わしはニコラ博士じゃ。きみのダイヤモンドは、明智小五郎が見はりをしているね。いい人をたのんだものじゃ。なにしろ日本一の名探偵じゃからなあ。
だが、だいじょうぶかね。わしは魔法つかいじゃよ。もうとっくにダイヤモンドを、ぬすんでしまったかもしれないぜ。え、どうだね、心配ではないかね。ウフフフフ、ほうら、見たまえ、きみは声がふるえている。心配になってきた。
ダイヤモンドは、かくし場所にあるだろうか。いや、ないのだ。あのかくし場所は、からっぽだ。うそだと思うなら、いますぐ、あそこへいって、しらべてみるがいい。ウフフフフ……。」
そして、ガチャンと電話がきれました。
園田さんは、受話器をおいたまま、まっさおになって、その場に立ちすくんでいましたが、庭の持仏堂へいってみないでは、どうにも安心ができません。
懐中電灯をもって、えんがわから庭げたをはいて、あの黄金仏のお堂の前にかけつけました。
「明智先生、明智先生はいませんか。」
大きな声でよびますと、お堂のそばのしげみの中から明智探偵と小林少年が出てきました。ちょうど月夜で、そのへんは昼のように明るいのです。
「どうなすったのです。なにかあったのですか。こちらは、べつにかわったこともありませんが。」
明智ののんきなことばに、園田さんははらだたしげに、どなりつけました。
「ニコラ博士が電話をかけてきたのです。そして、ダイヤは、とっくにぬすんでしまったというのです。明智さん、しらべてください。ダイヤがかくし場所にあるかないか、しらべてみてください。」
「そんなばかなことがあるものですか。ぼくはお堂の入口をずっと見はっていました。お堂のとびらは、一度もひらかなかったのです。だから、ダイヤをぬすみだせるはずがありません。」
「ともかく、しらべてみましょう。いっしょにきてください。」
園田さんは、いいすてて、お堂のとびらをひらくと、その中へとびこんでいきます。しかたがないので、明智探偵と小林少年も、そのあとからついていきました。
園田さんは仏像のうしろへまわると、かくしボタンをおして、秘密のふたをひらき、もうひとつのボタンをおして、鉄のツメがとびださないようにしておいて、穴の中へ手をいれました。
「あっ、ない。なくなっている。明智さん、この中はからっぽですよ。」
明智探偵をしかりつけるように、さけびました。
「おかしいですね。ニコラ博士は、このかくし場所を、知らないはずじゃありませんか。それをどうして……。」
「だから、はじめから、もうしあげておきました。あいつは魔法つかいです。どんなことだってできるのです。それをふせいでくださるのが、あなたの役目ではありませんか。しかも、あんなにかたく、おひきうけになったではありませんか。」
園田さんに、つめよられて、明智探偵はタジタジとあとじさりをしていました。
そのときです。じつにふしぎなことがおこりました。とびらをひらいたままになっているお堂の入口に、みょうな人間が立っていたのです。
銀色の月の光が、横のほうから、その人の顔の半分を、てらしていました。
園田さんも、明智探偵も、その顔を見ると、あっとさけんだまま、立ちすくんでしまいました。
その人は懐中電灯を持っていました。その光をこちらにむけながら、ゆっくりとお堂の中へはいってきます。
こちらの三人は、思わずあとじさりをしながら、園田さんの懐中電灯は、しぜんに、そのふしぎな人間の顔をてらしました。
あいての懐中電灯は、明智探偵の顔をてらしています。
人間の倍もある金色の仏像の前に、おたがいに懐中電灯でてらされた二つの顔が、まっ正面にむきあっていました。
おお、ごらんなさい。その二つの顔は、まるで鏡にうつしたように、そっくりおなじではありませんか。
そうです。明智探偵がふたりになったのです。どちらかが、ほんもので、どちらかが、にせものにちがいありませんが、その見わけが、まったくつかないのです。
「ワハハハハ……、にせものの明智君、うまくばけたね。しかし、きみはニコラ博士の手下だ。ダイヤモンドをまもるのではなくて、それをぬすむためにやってきたのだ。そして、きみはもうぬすんでしまったのだ。」
あとからきたほうの明智が、そういって、カラカラと笑いました。
しかし、前からいる明智も、けっしてまけてはいません。
「なにをばかな。きみこそにせものだ。いまごろになって、ノコノコやってきたのが、にせもののしょうこじゃないか。
だが、うたがうなら、ぼくのからだをさがしてみるがいい。あんな大きなダイヤだから、ぼくが持っていれば、すぐにわかるはずだ。」
それをきくと、小林少年が、お堂の入口へかけていって、用意していた、呼び子の笛をとりだすと、ピリピリピリリリリリリ……と、はげしくふきならしました。
この小林少年は、ほんものなのでしょうか、それとも、にせものなのでしょうか。読者諸君は、もうおわかりになっているでしょうね。
それはともかく、呼び子の音に、庭のあちこちにかくれていた十人の少年探偵団員が、大いそぎでかけつけてきました。
少年たちはお堂の入口にむらがって、中をのぞきこみましたが、明智先生がふたりいるのを見ると、ギョッとして、ものもいえなくなってしまいました。
「やあ、少年探偵団の諸君だね。ここにいるぼくとそっくりのやつは、にせものだ。こいつは大きなダイヤモンドをぬすんだのだ。きみたちみんなで、こいつのからだをしらべてくれたまえ。どこかにかくしているにちがいないのだから。」
あとからきた明智がいいますと、さきにきていた明智もまけないで、少年たちに声をかけました。
「やあ、きみたち、ゆだんをしてはいけないぞ。いましゃべったやつが、にせもので、ニコラ博士の手下だよ。
しかし、ぼくのからだをさがすなら、さがしてもよろしい。ぼくはぬすみなんか、ぜったいにしていないのだから。」
すると、小林少年が、さきにたって、その明智のポケットなどを、さがしはじめましたので、少年たちも、四方から明智のからだにとりついて、上着とズボンをさがしたあとで、その上着とズボンを、よってたかって、ぬがせたうえ、シャツとズボン下だけになった明智を、とうとうその場にころがしてしまいました。
いくら子どもでも、小林君をまぜて十一人ですから、どんな力のつよいおとなだって、どうすることもできません。十一人にとりつかれては、まるでアリにたかられたコオロギのようなもので、されるままになっているほかはないのです。
「ないねえ。」
「ないよ。」
「先生、どこにもダイヤなんて、かくしていません。」
あらゆる場所をさがしたあげく、少年たちは、とうとう、かくしていないときめてしまいました。
「そうらみろ。ぼくがぬすみなんかするはずはない。なぜといって、ぼくこそほんとうの明智小五郎だからだ。そこにいるやつが、にせものだよ。」
シャツ一枚にされた明智が、それみろといわぬばかりに、とくいらしくいいました。
それをきくと、小林君が、ハッとなにかを、思いだしたようすで、大声にどなりました。
「そうじゃない。まださがさないところが、一ヵ所だけある。きみたち、そいつの顔を、動かないように、つよくおさえていてくれたまえ。ぼくは、そいつの左の目をえぐってやるのだ。」
小林君が、おそろしいことをいいました。
しかし、少年たちは、小林団長の命令にしたがって、みんなで、たおれた明智の上にのしかかり、頭を地面におさえつけて、顔を動かさないようにしました。
「懐中電灯で顔をてらしてください。」
小林君はそういいながら、人さしゆびをグッとのばして、いきなり、明智の左の目にちかづけました。
ああ、なんというざんこく! 小林君の指は、あいての左の目の中へ、グーッと、つきささっていきました。そして、目の玉をくりぬいてしまったではありませんか。
「みなさん、こいつの左の目は義眼なのです。義眼がもののかくし場所になっているのです。ごらんなさい、これが園田さんのダイヤです。」
小林君はそういって、大きな宝石を、高くかざして見せました。懐中電灯の光をうけて、それは青い炎のようにもえています。
「やっ、さては、きさま、ほんとうの小林だな。いつのまに、いれかわったのだ。」
にせ明智は、おさえつけられたまま、わめきました。
「ハハハハハ、はじめから、いれかわっていたのさ。にせの小林は、ぼくのかわりに、地下室の牢屋にはいっているよ。ぼくが、ほんとうの明智先生をとらえる手だすけをしたのは、きみたちを、ゆだんさせるためだったのさ。」
小林君は、笑いながら、種あかしをしました。
「ちくしょうめ、こわっぱめに、はかられたのかっ。」
にせ明智は、さもくやしそうに、つぶやきましたが、そのあとから、かれの顔に、うすきみのわるい笑いがうかんできました。
「ウフフフフ、きみたち、それで、勝ったつもりでいるのかね。ウフフフフ、そうはいくまいぜ。こっちには、おくの手があるんだからね。
おい、おれのはらを、おさえているぼうや、右のポケットにさわってごらん。写真機みたいなものが、はいっているだろう。
それを、なんだと思うね。世界でいちばん小さい無電機だよ。さっきからスイッチはいれたままになっているから、ここで、みんなのしゃべったことは、すっかりニコラ博士の無電機にはいっている。
さあ、そうすると、どういうことになるだろうね。いまに、おそろしいことがおこるだろうから、用心するがいいぜ。」
ただのおどかしではなさそうです。小林君は、にせ明智のポケットから、写真機のようなものを、とりだしました。たしかに小型無線機のようです。スイッチをはずして、音がつたわらないようにして、じぶんのポケットにいれました。
「きみたち、そいつの手と足を、グルグルまきにしばって、身動きできないようにするんだ。みんな、ほそびきを、腰にまいているだろう。それでしばるんだ。」
小林君の命令で、十人の少年のうちの三人が、腰のほそびきをといて、にせ明智を、げんじゅうに、しばりあげてしまいました。
そのとき、持仏堂の入口から、ほんものの明智探偵が、はいってきました。いつのまにか、外へ出て、どこかへ行ってきたらしいのです。
「いや、感心、感心、さすがに小林君だ。よくやった。」
明智探偵はニコニコしながら、小林少年をほめたたえるのでした。
「ウフフフフ……。」
しばられて、お堂の入口にころがっている、にせの明智が、また、うすきみわるく笑いました。
「ニコラ博士は、あんがい、近くにいるのだ。もうやってくるじぶんだぜ。どんな姿で、やってくるか、きもをつぶさぬ用心をするがいい、ウフフフフ……。」
そのときです。お堂の外から「ウオーッ。」という、ものすごいうなり声が、ひびいてきました。明智探偵と小林少年は、お堂の外に、とびだしてみました。
月がてりかがやいて、そのへんは、昼のように明るいのです。それに、広い庭には、森のように木のしげったところがあります。
その中は、月がさしこまないので、まっくらです。
そのときです。チカッと金色に光るものが見えました。
そしてまた、「ウオーッ。」という、おそろしい、うなり声です。
「先生、さっき、お話した金色のトラです……。今夜は、きっと、あらわれるだろうと、思っていました。」
小林君が、そういっているうちに、黄金のトラは全身をあらわして、こちらへノソノソ歩いてきます。
人間が四つんばいになったほどの、でっかいトラです。そして、そのからだは、金色にピカピカ光っているのです。
「ウオーッ。」
こちらをむいて、大きな口をガッとひらきました。白いするどい牙きばがニュッとつきだし、口の中はもえるように、まっかです。二つのまんまるな目はリンのように青く光っています。
さすがの明智探偵も、小林少年も、それを見ると、思わず、たちすくんでしまいました。
すると、黄金のトラは、ゆうゆうと、森の外に出てきました。月の光をあびて、全身が美しく光りかがやいています。
小林君のうしろにいた十人の少年たちは、「ワーッ。」といって、にげだしました。
トラは少年たちには目もくれず、パッとひととびで、お堂の入口にちかづきました。その速さ! まるで金色のにじが立ったように見えました。
トラはお堂の中にはいると、そこにころがされている、にせ明智のそばによって口とまえ足をつかって、ほそびきを、ほどこうとしました。
それを見ると、明智探偵が、小林君の耳に、なにかささやきました。
小林君は、うなずいて、ポケットからピストルをとりだしました。にせ小林になりすまして、自動車の中で、明智にさしむけた、あのピストルが、まだポケットにはいっていたのです。
「こらっ、やめろっ。でないと、ピストルをぶっぱなすぞ。」
小林君は、まるで、あいてが人間ででもあるように、どなりつけました。
すると、ふしぎなことが、おこったのです。トラが、人間のように、まえ足を上にあげて、「かんべんしてください。」といわぬばかりに、あとじさりをはじめたではありませんか。
「あっ、そいつもにせものだ。ほんとうのトラでなくて、人間がトラの皮をかぶっているのだ。みんな、こいつをやっつけてしまえ。皮をはいでしまえっ。」
小林君がさけびますと、にげだしていた少年たちが、もどってきました。
「それっ、やっつけるんだ。」
小林君が、まっさきに、トラにとびついていきました。十人の少年たちも、四方からトラのからだに、くみつき、「エイ、エイ。」とかけ声をして、とうとう、トラをそこにたおしてしまいました。
「あっ、やっぱりそうだっ。ここにチャックがある。」
小林君が、それをグーッとひっぱりますと、トラのはらがさけて、中に人間がはいっていることがわかりました。黒いシャツをきた大きな男です。
「みんな、こいつもしばってしまえ。」
十人の少年たちは、すっかりトラの皮をはいで、黒シャツの男を、グルグルまきに、しばってしまいました。
トラ男は、小林君のさしむけるピストルを見て、うっかり手をあげたのが、しっぱいでした。それで人間だということがわかってしまったのです。
そのときです。またしても、むこうの木のしげみの中から、「ウオーッ、ウオーッ。」という、おそろしいうなり声が、ひびいてきました。そして、チラッ、チラッと金色のものが、見えたりかくれたりしています。
トラは一ぴきではなかったのです。
木の間から、二ひきの大トラが、ノソノソとあらわれてきました。
こんどは、ほんもののトラかもしれません。ピストルをさしむけても、いっこうに、ひるむようすがないのです。
「先生、足を撃ちますよっ。」
小林君は、明智探偵に、そうさけんでおいて、ピストルを撃ちました。致命傷をあたえないように、足をねらったのです。
みごとに命中しました。明智探偵事務所では、ピストルなんか、めったに使いませんが、明智探偵はピストルの名手ですし、小林君も、まんいちの場合のために、ひごろ射撃の練習をしていますので、それが、こういうときに、役に立つのです。
あと足をうたれたトラは、そこにころがって、まえ足で傷口をおさえています。ほんとうのトラならば、口で傷口をなめるはずではありませんか。
「あっ、やっぱり人間だっ。そいつもしばってしまえ。」
小林君の命令に、少年たちはゆうかんに、二ひきのトラに、とびかかっていきました。
傷つかないほうのトラも、一ぴきが撃たれたので、にげだそうか、どうしようかと、まよっていましたが、少年たちが、とびかかってきたので、もうにげることはできません。死にものぐるいの戦いがはじまりました。
傷ついたトラも、こうなっては、じっとしているわけにいきません。いたさをこらえて、おきあがり、少年たちにむかってきました。
こんどは、あいてが二ひきですから、少年たちは、二組にわかれなければならないので、なかなかの苦戦です。
二ひきの黄金の怪獣が、あちらにとび、こちらにとび、少年たちをけちらして、あばれまわり、月光にてらされた黄金のにじが、縦横じゅうおうにいりみだれました。
しかし、こちらは小林少年をいれて十一人の少年探偵団員です。それに、明智探偵と園田さんも、てつだってくれるのです。いくら強くても、ほんとうのトラではないのですから、とてもかなうものではありません。二十分ほどもかかった大格闘のすえ、トラは二ひきとも、その場に、くみふせられてしまいました。
まだあとから、べつのトラが出てくるのではないかと、しばらくまっていましたが、そのようすもありません、トラはぜんぶで三びきしかいなかったのです。
そのときです。少年のひとりが、大きな声でさけびました。
「あっ、スーパーマンだっ!」
ああ、ごらんなさい。はれわたった月光の空を、黒いマントをひるがえした、スーパーマンが、とんでくるのです。
これこそニコラ博士にちがいありません。博士のほかに、空をとべるやつがあろうとは思えないからです。
両手をグッと前につきだして、風をきってとぶスーパーマンは、お堂の上までくると、その屋根のまわりを、グルグルと、まわりはじめました。地上五十メートルほどの高さです。ニコラ博士は、そこから、下界のようすを、見とどけようとしているのです。
敵は、高い空中にいるのですから、どうすることもできません。ピストルを撃とうにも、あまり高いので、もしあいてを、ころしてしまうようなことがあっては、たいへんですから、それもできないのです。
ニコラ博士は、こちらをばかにしたように、いつまでも、お堂の上を、グルグル、グルグル、まわっていましたが、やがて、むこうの森のような木立ちの上へとんでいって、姿が、見えなくなってしまいました。
「森の中におりたのかもしれないぞ。」
少年のひとりが、大きな声でいいました。
いまに、こちらに出てくるだろうと、みんな、ゆだんなく、まちうけました。小林君はピストルをかまえることをわすれませんでした。
しかし、いくらまっても、ニコラ博士は出てくるようすがありません。どこかへ、とびさってしまったのでしょうか。それとも、森の中におりて、なにかたくらんでいるのではないでしょうか。
みんなはもう、まちきれなくなりました。
「森の中にはいって、ようすを見ることにしよう。」
小林君は、とうとう、しびれをきらして、森の中にはいってみる決心をしました。明智探偵もいっしょにいってくれることになりました。
少年探偵団員たちは、みんな小型の懐中電灯をもっていますので、てんでに、それをふりてらしながら、まっくらな森の中にはいっていくのです。小林団長はピストルをにぎって、先に立っています。
ひとかかえも、ふたかかえもあるような、大きなヒノキなどが、たちならんでいます。
懐中電灯はたくさんあっても、みんな万年筆型の小さいのですから、たいして明るくはありません。いやにチロチロして、なんだか、そのへんに、あやしいやつがかくれているような気がします。
木のみきから、木のみきを、グルグルまわって、すすんでいきましたが、森のまんなかへんにきたとき、とつぜん、ガサガサという音がしたかと思うと、先に立っていた小林君の頭の上から、なにか大きなものが、サーッとおちてきました。
アッというまに、小林君は、そこにたおれていました。
「だれだっ。きさま、ニコラ博士だなっ。」
小林君は、大声にさけびましたが、ふと気がつくと、右手ににぎっていたピストルが、ありません。
「ワハハハハハ、いかにも、おれはニコラ博士だ。小林君、きみのピストルは、いまもらったよ。こっちのは、おれのピストルだ。つまり二梃ちょう拳銃さ。きみたちは、だれももうピストルはもっていない。こうなったら、おれの命令にしたがうほかはないね。さあ、そこをのくんだ。ニコラさまのお通りだ。」
少年たちは、みんな、あとじさりをして、道をあけました。コウモリのようなマントをきた、白ひげのニコラ博士は、ゆうゆうとその間をとおって、森の外に出ていきました。
だれもてむかうものはありません。少年たちがおそれをなしたのは、むりがないとしても、名探偵明智小五郎は、いったい、どうしたのでしょう。ふしぎなことに、そのへんに、姿が見えません。まさかにげだしてしまったわけではないでしょう。いや、にげだすどころか、そのとき、明智探偵は、ニコラ博士に気づかれぬよう、ある場所で、ひじょうにだいじな仕事をしていたのです。
森を出たニコラ博士は、お堂の前に立っていた園田さんのそばへ、両手にピストルをかまえながら、近づいていきました。
「おい、さっき小林からうけとった、ダイヤモンドを、おれにわたせ。おれはニコラ博士だ。いうことをきかなければ、きみの命がないぞ。」
地の底からひびいてくるような、いやな声です。二梃のピストルをつきつけられては、命令にしたがうほかはありません。園田さんは、ポケットから「青い炎」をとりだして、博士の前に、さしだしました。博士はそれをうけとって、
「よし、よし、これでおれも、約束をはたしたわけだね。ワハハハハハ、じゃあ、あばよ。」
といいすてて、また森の中へはいっていきました。
少年たちは、まだ森の中にいましたが、だれもこの怪人にてむかうものはありません。
やがて、さっき小林君の上から、とびおりた、大きなヒノキのそばへくると、二梃のピストルを、両方のポケットにいれ、いきなり、そのみきにすがりついて、木のぼりをはじめました。まるでサルのように、木のぼりがうまいのです。たちまち、枝や葉のしげった中に、姿が見えなくなってしまいました。
小林少年は、べつの木のみきにかくれて、そっとそのようすを見ていました。懐中電灯はつけなくても、やみに目がなれて、ぼんやりと、そのへんが見えるのです。
小林君は、いまに木の上で、どんなことがおこるかを、あらかたさっしていましたので、それをたのしみにして、まちかまえているのです。
ここで、お話は、そのヒノキの上の枝葉えだはのしげった中にうつります。
ニコラ博士は、二梃のピストルをポケットにいれ、両手で木のみきをかかえながら、第一の横枝から、第二の横枝へと、だんだん上のほうへ、のぼっていきました。
そして、第三の横枝にのぼりついたときです。ハッと気がつくと、両方のポケットが、かるくなっていました。
びっくりして、足でからだをささえ、両手でポケットをさぐってみますと、ピストルがありません。二梃ともなくなっているのです。
ふしぎです。おとしたはずはありません。ひょっとしたら、この木にはサルかなんかがいて、ピストルを、よこどりしたのではないでしょうか。
「ウフフフフ、ニコラ博士、びっくりしているね。ぼくだよ、明智小五郎だよ。ピストルは、ぼくがちょうだいして、下へなげおとしてしまったのだよ。これで、きみもぼくも、武器がなくなったのだから、ごかくの戦いができるというものだ。」
ああ、名探偵はここにかくれて、ニコラ博士のかえってくるのを、まっていたのです。博士はスーパーマンのように、空をとぶためには、どうしても、この木のてっぺんに、かえってこなければならないわけがあったのです。明智探偵は、そのことを、ちゃんと知っていました。
明智は、さらに、ことばをつづけます。
「ぼくがどうしてこんなところにいるか、そのわけは、きみももう、さっしているだろうね。
いうまでもなく、きみの空とぶ羽根を、こわしてしまうためさ。きみがどうして、スーパーマンのように、空をとぶか、その秘密を、ぼくは知っているのだ。数年前、あるフランス人が、人間が背中につけてとべる、ヘリコプターを小さくしたような機械を発明した。日本にたったひとり、その機械を買いいれたやつがいる。きみはそれを使ってスーパーマンのまねをしていたのだ。夜や、うすぐらい日には、プロペラが見えないので、いかにもスーパーマンがとんでいるように思うのだ。
きみは、その機械を、この木のてっぺんにかくしておいて、ダイヤモンドをうばうために、おりていったが、それが手にはいったので、またプロペラを背中につけて、空へとびたつために、ここにもどってきた。だが、もうだめだよ。あの機械は、きみが下におりているうちに、ぼくがこわしてしまった。きみはもうとべないのだ。スーパーマンが飛行の術をうしなってしまったのだ。」
そのとき、パッと、二つのまるい光がいれちがって、まっくらな木の葉の中に、二つの人間の顔が、明るくてらしだされました。
明智探偵と、ニコラ博士とが、それぞれ懐中電灯をとりだして、あいての顔をてらしたのです。
名探偵とニコラ博士は、ヒノキの枝の上で、にらみあいました。
「きみは、この木のてっぺんから、スーパーマンのように、とびたつつもりだったろうが、そのとび道具のプロペラは、ぼくがこわしてしまった。きみはもう超人の力をうしなったのだ。」
明智が一段上の木の枝から、ニコラ博士を見おろして、とどめをさすように、いいました。
ニコラ博士は、ポケットにいれていた二梃のピストルも、さっき明智にとりあげられてしまったので、もうどうすることもできません。上の枝には明智がいるのですから、にげるなら、下におりるほかはないのです。
博士は、いきなり、木をすべりおちるように、下へにげます。明智はそのあとをおいながら、大声にさけびました。
「おーい、小林君、少年探偵団の諸君。ニコラ博士は、木をおりていく。ピストルはぼくがとりあげてしまったから、だいじょうぶだ。みんなで、つかまえてくれたまえ。」
すると、下にまちかまえていた小林少年が、ポケットから、呼び子の笛をとりだして、ピリピリピリ……と、ふきならしました。
それをきくと、四方ににげちっていた少年たちが、小林君のそばに、かけもどってきました。
「ニコラ博士は、もうピストルを持っていない。みんなで、つかまえるんだっ。」
そうさけんでいるところに、すぐ目の前のヒノキのみきを、サーッとすべりおりてくるニコラ博士の姿が見えました。
「それっ。」というので、少年たちはとびかかっていきます。
おそろしい格闘がはじまりました。ニコラ博士は、若者のような力があります。くみついていく少年たちは、かたっぱしから、投げとばされました。
しかし、投げられても、投げられても、またくみついていく少年たち。こちらは小林少年をいれて十一人です。いくら博士が強くても、だんだん、旗色はたいろがわるくなってきました。
しかし、ニコラ博士にはおくの手があったのです。
博士は、少年たちのうちで、いちばんよわそうなひとりを、いきなり、うしろから、だきかかえると、少年の首に、腕をまきつけて、のどをしめました。
「やい、こわっぱども。おれにてむかいすると、この子どもを、しめ殺してしまうぞっ。さあ、どうだ。これでもか。」
小林君の懐中電灯が、そのありさまをてらしだしました。
つかまっている少年は、息がつまって、まっかな顔をして、目を白黒させています。このまま、ほうっておいたら殺されてしまうかもしれません。
小林君はポケットをさぐりました。そこには二梃のピストルがはいっています。さっき、木の上から、明智探偵が投げおとしたニコラ博士のピストルを、ひろっておいたのです。
「ニコラ博士、その手をはなせっ。でないと、これだぞっ。」
小林君は、右手で一梃のピストルをかまえて、左手の懐中電灯の光を、それにあててみせました。
そのとき、くらやみの中から、明智探偵の力強い声がひびいてきました。探偵もヒノキからおりて、さっきから、格闘のようすをながめていたのです。
「二十面相君、きみは人殺しはしないはずだったね。」
ふいをつかれて、ニコラ博士は、おもわず、少年をつかまえていた手をはなしました。そして、おどろきのために、とびだすほど、見ひらいた目で、やみの中をみつめました。ニコラ博士の顔は、明智の懐中電灯でてらされていましたが、明智の姿は、やみにかくれて、すこしも見えないのです。
「ハハハハハ……、とうとう白状したな。いまのようすで、きみが二十面相であることは、もうまちがいない。背中につけて、空をとぶ豆ヘリコプターを持っているのは、二十面相のほかにはない。ぼくはそれを、まえに見たことがあるので、よく知っているのだ。このヒノキのてっぺんに、かくしてあったのは、それとおなじものだった。
ぼくはさいしょから、ニコラ博士は二十面相にちがいないと思っていた。宝石や美術品ばかりねらうのは、いかにも二十面相らしいし、小林君や少年探偵団員を、ひどいめにあわせて、よろこんでいるのは、二十面相の復讐としか考えられないからね。そこへもってきて、小林君が、にせ小林になりすまして、きみの秘密を、みんなきいてしまったのだよ。ハハハハ……、二十面相君、しばらくだったねえ。」
「ワハハハハ……。」
ニコラ博士は、明智よりも、もっと大きな声で笑いとばしました。
「明智君、きみももうろくしたな。てごわいあいてにでくわすと、みんな二十面相にしてしまう。わしはドイツ生まれの百十四歳のニコラ博士だ。人ちがいをしてもらってはこまるよ。」
そのとき、やみの中から、パッととびだしてきたものがあります。明智探偵です。探偵は、いきなり、ニコラ博士にちかづくと、博士の長い白ひげと、しらがのかつらを、力まかせに、はぎとってしまいました。その下からあらわれたのは、黒いかみの毛の、わかわかしい顔でした。
こうなっては、もう百十四歳の老人などといいはることはできません。
「ハハハハ……、さすがは明智君だ。とうとうニコラ博士の魔法をやぶってしまったねえ。だが、おれはまだまけたわけではないぜ。いつもいうように、おれはどんなときでも、さいごのおくの手が、のこしてあるのだ。」
そういったかと思うと、ポケットから小さな写真機のようなものをとりだして、口の前に持っていきました。
「こちらニコラ。こちらニコラ。さいごの手段だっ。わかったか。よしよし、わかったね。」
それは小型の無線電話機でした。はなしかけたあいては、ニコラ博士の、れいのすみかに、るす番をしている部下のものにちがいありません。
二十面相は、にくにくしげな笑い顔で、明智探偵にむきなおりました。
「わかるかね。さいごの手段とは、なんだと思う。爆発だっ。なにもかも、こなみじんになって、ふっとんでしまうのだ。おれの地下室の牢屋には、宝石王玉村一家のものと、白井美術店の人たちが、とじこめてある。おれに自由をあたえなければ、それらの人たちが、みな殺しになってしまうのだ。おれは人殺しは大きらいだ。しかし、おれの自由にはかえられない。おれに人殺しをさせるのも、明智君、みんなきみのせいだぞっ。」
「アハハハハ……。」
とつぜん、べつの方角から、笑い声がひびきました。小林少年です。小林君が、さもおかしそうに、笑っているのです。
「アハハハハ……、二十面相君、きみは地下室においてある爆薬のたるのことをいっているのだろう。あのたるの導火線に火をつけて、みんながにげだすという、ふるくさいやりかただろう。ところが、あの爆薬は、ぼくがだめにしておいたよ。たるの中は水びたしだし、導火線は外から見たのではわからぬように、きりはなしてあるのだ。それに火をつけたって、爆発などおこりっこないよ。アハハハハハ……。」
それをきくと、二十面相は、無電機を地上に投げつけて、じだんだをふみました。
「ちくしょうめ、小林のやつ、よくもそこまで、手をまわしたなっ。おぼえていろ。このしかえしは、きっとしてやるからな。」
そのとき、くらやみのかなたから、懐中電灯の強い光が三つ、グングンこちらへちかづいてきました。
「明智君、中村だ。」
それは警視庁の中村警部が、数名の刑事たちをつれてやってきたのでした。
「中村君、ここだ。二十面相はここにいる。つかまえてくれたまえ。」
刑事たちが、二十面相にかけよって、たちまち手錠をはめてしまいました。
さっき持仏堂の中で、小林君がにせ明智の義眼をくりぬいて、ダイヤモンドをとりかえしたとき、ほんものの明智探偵が、しばらく、どこかに姿を消していましたが、そのとき、探偵は、中村警部に電話をかけて、いそいでここにきてくれるようにと、たのんだのでした。
「中村君、これからすぐに、こいつのすみかにのりこもう。二十面相もいっしょにつれていく。ぼくは警視庁の留置場にとじこめるまで、こいつのそばをはなれないつもりだ。でないと、こいつ、どんなおくの手を用意しているか、わからないからね。」
二十面相の両手に手錠をはめ、右左にひとりずつ刑事がつきそい、手錠の片方を刑事の手にもはめて、ぜったいににげられないようにして、自動車にのりこみました。
二十面相は、もうかんねんしたのか、にが笑いをうかべて、だまりこんでいます。
警視庁の自動車のほかに数台のハイヤーをよんで、中村警部、その部下たち、明智探偵、手錠をはめられたにせ明智、小林少年、それから、今夜のとりものの功労者である十人の少年探偵団員もみんな自動車にのりこんで、怪人のすみかへといそぐのでした。
ニコラ博士のすみかにつくと、中村警部とその部下たちは、うらおもてから建物にふみこみ、そこにいた賊の手下どもを、すっかりとらえてしまいました。
それから、二十面相を、地下室の牢屋の一つにとじこめ、見はりの刑事をつけておいて、べつの牢屋にいれられていた、玉村家と白井家の人たちをたすけだし、牢屋にのこっていた、にせの小林少年は、ひきだして、手錠をはめてしまいました。
「これで、二十面相とその部下のしまつはついたが、まだ一つだけ、のこっていることがある。それは、この地下室のいちばんおくにかくれている、一寸法師の医学者の尋問じんもんだ。まったくおなじ人間を、いくらでもつくりだす、あの医学者の秘密を、あきらかにしなければならない。小林君、そこに案内してくれたまえ。」
みんなは、小林少年のあとについて、部屋ぜんたいのエレベーターで地下二階におり、ロッカーのような人形箱のならんでいる廊下をとおりすぎて、あの、まぶしいほどあかるい機械室にはいっていきました。
すると、たちならぶ、めずらしい機械のおくから、まるでビックリ箱をとびだすように、あの頭をまるぼうずにした一寸法師が、ピョコンと、姿をあらわしました。
小林少年は、ツカツカとそのそばにちかづいて、
「先生、ぼくをおぼえていらっしゃるでしょう?」
と、声をかけました。
「おお、おぼえているとも、わしのかわいいむすこじゃもんなあ。」
一寸法師はニヤニヤ笑っています。
「えっ、むすこですって?」
「おお、むすこじゃとも、わしのつくった人間は、千人、万人、十万人、みんなわしのかわいいむすこじゃよ。
ところで、きみたち、おおぜいで、きょうは、なにかあるのかね。あっ、そうだ。お祝いのパーティーだったね。シャンパンをぬくんだね。おーい、ボーイども、シャンパンだ。十本、二十本、いや、まだたりない。五十本、百本、いくらでも持ってこい。そして、けいきよくポンポンぬくんだ。おーい、ボーイどもはいないのか。ボーイ、ボーイ……。」
こんなところにボーイなどいるはずがありません。シャンパンなどあるはずがないのです。一寸法師は、このまえ、小林君があったときから、気ちがいめいていましたが、今夜はもっとひどいようです。
「先生、そんなことよりも、このあいだ、ぼくにおしえてくださったように、そっくりおなじ人間をつくり出す方法を、みなさんに話してあげてください。このかたは警視庁捜査課の中村警部さんです。それから、こちらは、ぼくの先生の明智探偵です。今夜はみんなで、あなたのお話をききにきたのですよ。」
「おお、きみが名探偵明智小五郎君か。わしは、一度あいたいと思っていたよ。ちょうどいい。さあ、シャンパンをぬいて乾杯しよう。そして、きみとおどろう。バンド・マスター、うまくたのむぜ。」
そういったかと思うと、おどろいたことには、一寸法師は、いきなり、ひとりでダンスをはじめて、機械のあいだを、あちらこちらと、はねまわるのでした。
それを見て、明智探偵は、みんなに話しかけました。
「この人は、とうとう気がちがったようです。この人には、まえに小林君があったことがあるのです。そのときから、すこしおかしかったそうですが、それでも、人間改造術について、ながながと、小林君に演説してきかせたそうです。
ぼくはそれを、小林君からくわしくきいていますから、ここで、ごくかんたんに、その術についてお話しすることにしましょう。人間の顔をかえることは、眼科や耳鼻科で、今でも、あるていどは、やっているのです。
眼科では、ひとえまぶたを、ふたえまぶたにする手術は、てがるにできます。顔を美しくしたい若い女の人などが、よくその手術をうけています。
耳鼻科では、ゾウゲやそのほかの材料を、鼻の中に入れる手術で、鼻を高くすることができます。これも、おしゃれの男や女が、さかんにやってもらっているのです。
いまはやっているのは、目と鼻の手術ぐらいですが、やろうと思えば、人間のからだは、どこでも、そういう整形手術をほどこすことができるはずです。たとえば肩のはった人を、なで肩にするのには、肩の骨をけずればいいのだし、あごの形をかえるのにも、やはりあごの骨をけずればいいのです。そういう手術は、わけなくできるけれども、だれもそんなものずきなまねをしないだけのことです。それから、歯を総いれ歯にすれば、そのいれ歯のつくりかたで、口やほおの形を、どんなにでもかえることができます。また、やせたほおをふっくらさせるのには、薬品をほおに注射するというやりかたもあります。かみの毛のはえぎわや、まゆの形をかえるのには、脱毛術、植毛術があり、毛の色をかえるのも、ぞうさないことです。
それから、コンタクトレンズを、すこし大きくつくって、義眼のように黒目の絵をかけば、黒目を大きくも小さくもできるし、目の色をかえることだってわけはないのです。
この一寸法師の医学者は、医科大学にいるころに、人間改造術ということを考えつき、だれもやらないその術のために、一生をささげようと決心したのだそうです。
そして、眼科、歯科、耳鼻科、整形外科、皮膚科、美容術と、あらゆる方面にわたって研究をつづけ、ついに人間改造術というものをつくりあげてしまったのです。ところが、ふつうの人間は、顔かたちをかえることなど、考えるものではありません。もしそういうことを考えるものがあるとすれば、それは犯罪者です。警察に追われている犯罪者ならば、じぶんの顔を、まったくちがった顔にかえたくなるでしょう。
ですから、この一寸法師のお医者さんは、しぜんと悪人とつきあうようになり、さいごには、怪人二十面相の手下になってしまったのです。めざす宝石や美術品をもっている人の一家を、みんな、にせものにかえてしまうという思いきったやりかたは、おそらく二十面相が考えついたのでしょう。
まず、その人によくにた人間をさがしだして、人間改造術のふしぎを見せて、ときつけるのです。有名な宝石商や美術店の主人や家族になれるのですから、すこしでも悪い心のあるやつなら、だれもいやとはいわないでしょう。手術にとりかかるまえに、まず、あらゆる角度からとった、ほんものの人間の写真をあつめ、それによってロウ人形をつくり、ほんものをよく知っている人に見てもらって、なおすところはなおしたうえ、いよいよ人間改造術にとりかかるのです。もともと、からだや顔のにた人間に手術をほどこすのですから、できあがった人が、そっくりおなじに見えるのも、ふしぎではありません。
二十面相は美術愛好家です。ですから、さいわいにも、宝石や美術品をぬすむためだけに、人間改造術を使ったので、ひじょうに大きな害はなかったのですが、この術は、使いかたによっては、世界を一大動乱にみちびき、核戦争をおっぱじめさせることだって、できないことはないのです。たとえば、ある国の最高の地位の人や、大臣高官たちを、人間改造術によって、悪人の手下と入れかえてしまったら、どんなことになるでしょうか。
それを一つの国だけでなく、いくつもの大国にほどこしたら、どんなことになるでしょうか。世界を一大動乱にまきこむことは、わけはないのです。核戦争は、その持ち場についている、たったひとりの人間の、ちょっとした思いちがいや、ボタンのおしまちがいからでも、おこりうるといいます。そうだとすれば、たったひとりの改造人間をつくれば、核戦争をおこし、地球上の人類を滅亡させることだってできないことではありません。考えただけでも、身ぶるいが出ます。
二十面相が、そこまでの悪人でなかったことは、なによりのことでした。さいわいなことに、この一寸法師は気がくるったようです。もう手術をする力もないかもしれません。天ばつです。天が人間改造術などという、おそろしい罪をゆるさなかったのです。この男は気ちがいです。しかし、ねんのために、一生がい牢獄にとじこめておかなければなりません。」
明智探偵は長い話をおわって、中村警部に目であいずをしました。すると、警部はそばにいたふたりの刑事に、なにかささやきました。
ふたりの刑事はツカツカと、前にすすみました。そして、まだニヤニヤ笑っている一寸法師にちかづくと、いきなりカチンと手錠をはめてしまいました。一寸法師はそれでも、べつにおどろくようすはありません。
「わしをどこへつれていくのだ。ああ、わかった。王様の御殿につれていくのだな。そして、王様はわしに勲章くんしょうをくださるのだ。ありがたい、ありがたい。」
と、みょうなたわごとを口ばしるのでした。これで超人ニコラ博士の事件はめでたくおわりました。
ニコラ博士にばけていた怪人二十面相と、その手下たちはとらえられ、一寸法師の気ちがい医師も刑務所に送られ、宝石王玉村さん一家、美術店白井さん一家は、ぶじすくいだされ、盗まれた宝石などは、みんな持ち主の手にかえりました。
「こんどの事件で、いちばんの働きをしたのは、小林君だな。そして、それをたすけたのは、少年探偵団の諸君だ。」
中村警部が笑いながらいいました。
「いや、日ごろの明智先生の教えがなければ、なにもできなかったでしょう。やっぱり先生のおかげですよ。」
小林少年が、けんそんしていいました。それをきくと、十人の少年探偵団員が、口をそろえてさけびました。
「明智先生、ばんざあい……。」
「小林団長、ばんざあい……。」
そして、
「少年探偵団、ばんざあい……。」
底本:「超人ニコラ/大金塊」江戸川乱歩推理文庫、講談社
1988(昭和63)年10月8日第1刷発行
初出:「少年」光文社
1962(昭和37)年1月~12月
入力:sogo
校正:茅宮君子
2018年2月25日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
大金塊
江戸川乱歩
小学校六年生の宮瀬不二夫みやせふじお君は、たったひとり、広いおうちにるす番をしていました。
宮瀬君のおうちは、東京の西北のはずれにあたる荻窪おぎくぼの、さびしい丘の上に立っていました。このおうちは不二夫君のおじさんが建てられたのですが、そのおじさんが亡くなって、おばさんも子どももなかったものですから、不二夫君のおとうさまのものとなり、一年ほどまえから、不二夫君一家がそこに住んでいたのでした。
このおうちを建てたおじさんというのは、ひどくふうがわりな人で、一生お嫁さんももらわないですごし、そのうえ人づきあいもあまりしないで、自分で建てた大きな家にとじこもって、こっとういじりばかりして暮らしていたのですが、このおうちも、そのおじさんが建てただけあって、いかにもふうがわりな、古めかしい建て方でした。
全体で十二間まほどの二階建てコンクリートづくりの洋館なのですが、赤がわらの屋根の形がみょうなかっこうに入りくんでいて、まるでお城かなんかのような感じでしたし、その屋根の上に、いまどきめずらしい、石炭をたく暖炉だんろの、四角なえんとつがニューッとつきでていて、おうちのかっこうをいっそう奇妙に見せているのでした。
おうちの中もみょうな間まどりになっていて、廊下がいやにまがりくねっているような建て方でしたが、この部屋部屋のかざりつけは、さすがにこっとうずきのおじさんがえらばれただけあって、みな美術的なりっぱなものばかりでした。
なかにも階下にある広い客間なんかは、まるで美術陳列室といってもよいくらい、高価な美しい品物でいっぱいになっていました。壁かべにかかっている西洋の名画、外国からわざわざ取りよせた、名人のこしらえたイスやテーブル、ほりものの美しいかざりだな、ペルシャ製のじゅうたんなど、こりにこった、とびきり高価なものばかりでした。
宮瀬不二夫君は、そのりっぱなおうちの寝室で、今ベッドにはいったばかりのところなのです。
おとうさまは会社のご用で、どうしても一晩、家をるすにされねばならなかったものですから、不二夫君は、広いおうちに、ひとりでるす番をしていたのです。もっとも書生や女中たちが、遠くの部屋にいることはいたのですが、それはみな雇やとい人なのですから、おとうさまがいられたときのように、心じょうぶではありません。
では、おかあさまはといいますと、そのやさしいおかあさまは、四年ほどまえに亡くなられて、今では、宮瀬家の家族は、おとうさまと不二夫君のただふたりだけなのでした。
春の夜もふけて、ベッドのまくらもとの置き時計は、もう十時をすぎていました。不二夫君は、いつもならば、もうとっくにねむっている時刻なのに、今夜はどうしたわけか、みょうに寝つかれないのです。寒くもないのに、なんだか背中がぞくぞくするようで、さびしくて、こわくてしかたがないのです。六年生にもなっていて、こんなおくびょうなことではだめだと、いくら元気をだそうとしても、なぜかすぐに気がくじけて、びくびくしながら、窓の外の物音に、耳をすますというありさまです。
ベッドにはいるまえに、本を読んだのがいけなかったのです。それはおそろしい盗賊とうぞくの出てくる、西洋の物語だったのですが、さし絵にあった盗賊のものすごい姿が、わすれようとしてもわすれられないのです。今にもそのおそろしい賊が、あの窓からしのびこんでくるのじゃないかしらと考えると、もうこわくてこわくてしかたがありません。
窓には厚い織り物のカーテンがしめきってあって、外を見ることはできませんが、そのカーテンのむこうのガラス窓の外は、広い庭になっていて、大きな木がこんもりとしげっているのです。もしかしたら、その木の下を、あやしげな黒い影が、しのび足で、こちらに近よっているのじゃないだろうか。不二夫君はそんなことまで考えて、毛布の中で身をちぢめているのでした。
広いおうちの中は、あき家のように、しいんと静まりかえっています。ただ、まくらもとの置き時計の秒をきざむ音が、コチコチ、コチコチ鳴っているばかりです。それをじっと聞いていますと、みょうな節ふしをつけて、だれかがものをいっているように感じられ、時計の音さえきみ悪くなってくるのです。
不二夫君は、どうかしてねむろうと、目をかたくとじてみました。でも、いくら目をとじても、心はねむらないのですから、いろいろな考えがうかんできます。
「ああ、そうだ。あの本のお話には賊のおそろしい手紙が、しめきった部屋の中へ、どこからともなくまいこんでくるところがあったっけ。お話の中のおじょうさんも、やっぱりぼくみたいにベッドに寝ていたんだ。すると、ちょうどその顔のあたりへ、ひらひらと白い紙が落ちてきたんだ。」
そう考えますと、不二夫君は、今、自分の顔の上にも、同じようなことが起こっているのではあるまいかと、ゾウッとしました。気のせいか、天井の方から、何かひらひらとまいおりてくるような、空気のかすかな動きが感じられます。
「ばかな、そんなばかなことがあるもんか。」
不二夫君は、自分のおくびょうを笑ってやりたいような気持ちになって、パッと目をひらきました。そして、
「ほうら、どうだ、なんにも落ちてきやしないじゃないか。」
と、自分自身にいい聞かせてやろうと思ったのです。
ところが、そうして目をひらいて、天井のほうを見あげたせつな、不二夫君は、あまりのおそろしさに、アッとさけびそうになりました。
ごらんなさい。本のお話に書いてあったとおりのことが、いま、目の前に起こっているのです。天井から、寝ている不二夫君の顔の上へ、ひらひらと、一枚の白い紙がまいおりてくるのです。
不二夫君は夢ではないかと思いました。心の中で思っていたことが、そっくりそのまま、じっさいに起こるなんて、こんなふしぎな、きみの悪いことがあるものでしょうか。
しかし、夢でもまぼろしでもありません。白い紙はかすかな風を起こして、スウッと顔の上を通りすぎたかと思うと、ベッドの毛布の上に、ふわっと落ちたのです。
不二夫君は、しばらくのあいだは、身をすくめて、じっとその紙を見つめていましたが、きみが悪ければ悪いほど、それがどういう紙だか、たしかめてみないでは安心ができません。
「もしやお話のように、おそろしい賊の脅迫状ではあるまいか。」
と考えますと、もうからだじゅうが、じっとりとつめたく汗あせばんできて、こわくてしかたがないのですが、でも、あらためて見なければ、なお気持ちが悪いものですから、思いきって毛布の中から手をのばして、その紙を取ってまくらもとの卓上電灯の光にかざしてみました。
すると、その紙には字が書いてあることがわかりました。鉛筆でなんだか書いてあるのです。
不二夫君は読みたくないと思いました。読むのがこわかったのです。でも、読むまいとしても、目はかってに文字の上を走っていました。そして、またたくまにその文章をすっかり読んでしまったのです。そして、不二夫君は、まっさおな顔になってしまいました。
それもむりではありません。そこには、こんなおそろしいことが書いてあったのです。
不二夫君
どんなことが起こっても、きみは朝までけっしてベッドをはなれてはいけない。声をたててはいけない。ただ目をつむって寝ていればいいのだ。もし、さわいだりすると、きみはどんなめにあうかもしれないよ。それがこわかったら、ただじっとしているのだ。じっとしてさえいれば、きみは安全なのだ。いいかね、命がおしかったら、そのままじっとしているのだよ。
読みおわっても、あまりのこわさに、しばらくはものを考える力もなく、ただぼんやりしていましたが、やがて心が静まるにつれて、なんともいえぬきみの悪いうたがいが起こってきました。
「いったい、これはどういうわけなんだろう。なぜ、じっとしていなければならないのだろう。きっと、じっとしていられないほど、みょうなことが起こるのにちがいない。ああ、どんなおそろしいことが起こるのかしら。……それにしても、この手紙は、どこから落ちてきたんだろう。天井には、そんなすきなんかないのだし、窓はしめきってあるのだし……。」
考えながら、ふと気がつきますと、どこからか、部屋の中へ、つめたい風がスウッと吹きこんでくるような感じがしました。
「おや、窓があいていたのかしら。」
思わずその窓のほうへ目をむけましたが、そして、あの庭に面した窓の、厚いカーテンをひと目見たかと思うと、不二夫君のかわいらしい目が、とびだすばかり、いっぱいにみひらかれ、顔が今にも泣きだしそうにゆがみました。
おお、ごらんなさい。その窓のカーテンの合わせめから、ピストルのつつ口が、じっとこちらをねらって、つきだされているではありませんか。長いカーテンの下からは、二本の長ぐつがのぞいているではありませんか。
悪者です。悪者が窓からしのびこんで、カーテンのうしろにかくれながら、さわげばうつぞと、不二夫君をおどかしているのです。手紙を投げこんだのも、この悪者のしわざにちがいありません。
悪者は息をころし、身動きもしないで、だまりこんでいます。顔も見えなければ、姿も見えません。ただ、ピストルと、カーテンのふくらみと、下から見えている長ぐつで、それと、わかるばかりです。
でも顔形が見えないだけに、いっそうぶきみな感じがします。相手が、どんなやつとわかっていれば、まだいいのです。それがまったくわからないものですから、なんだかお化けにでも出あったような、いうにいわれない、心の底から寒くなるようなおそろしさです。
お話の本には、悪漢におそわれたおじょうさんが、歯の根も合わぬほどふるえていたと書いてありました。それを読んだときには、「歯の根が合わぬって、どんなことかしら。」と、ふしぎに思ったのですが、今こそ、その気持ちがはっきりわかりました。ほんとうに上下の歯が、しっかりと、合わないのです。からだじゅうが小きざみにぶるぶるふるえ、歯がガチガチ鳴って、いくらとめようとしてもとまらないのです。
不二夫君は、ざんねんながら、そうしてふるえながら、毛布の中に身をちぢめて、かたくなっているほかはありませんでした。賊のいいつけにそむいて、たすけを呼んだり、部屋から逃げだしたりすることは思いもよりません。そんなことをすれば、むろん命がないのです。あのカーテンのあいだから出ているピストルが火を吹くのです。
その部屋は、おとうさまといっしょの寝室でしたから、すぐむこうがわに、おとうさまのからっぽのベッドが見えているのです。そのベッドのまくらもとの壁には、書生や女中を呼ぶベルのボタンがあるのです。ただ二メートルか三メートル走れば、それをおして人を呼ぶことができるのです。
でも、不二夫君は、そのベルのボタンのところまでさえ行けません。そこへ行くのには、どうしても自分のベッドをおりて、床の上を歩かなければならないからです。歩けば、賊のピストルが火をふくにきまっているからです。
不二夫君がそうして、生きたここちもなく、目をふさいで、わなわなふるえていますと、やがて、どこからか、みょうな物音が聞こえてきました。
ゴトゴト、ゴトゴト、テーブルだとかイスだとかを動かしている音です。壁をたたくような音も聞こえます。人の歩きまわるけはいもします。
「おや、あれは客間じゃないかしら。客間へ賊がしのびこんで、あのたいせつな油絵や道具などをぬすみだしているんじゃないかしら。」
寝室の壁ひとえとなりが、あの広いりっぱな広間なのです。そこには、まえにしるしたとおり、いろいろな美しいかざりものや道具などが、たくさんおいてあるのです。このおうちで、賊が目ぼしをつけるものといっては、さしずめ、あの高価な絵や道具類のほかにはありません。
壁のむこうがわの物音は、だんだんひどくなってくるばかりでした。まるで大掃除か引っ越しのようなさわぎです。書生や女中の部屋は遠いのですし、不二夫君はピストルでおどしつけているから、だいじょうぶと思ったのでしょう。賊たちは、人の住んでいないあき家をでも荒らすように、かってほうだいにあばれまわっています。物音のようすでは賊はひとりではありません。ふたりも三人もいるらしいのです。
あんな大きな物音をたてているほどですから、絵や置き物ばかりでなく、イスもテーブルも、じゅうたんも、金目かねめのものは、いっさいがっさい、ほんとうに引っ越しのようにぬすんでいくつもりにちがいありません。門の外には、賊の大きなトラックが待っているのかもしれません。
不二夫君は、それを思うと、おとうさまに申しわけないようで、気が気ではないのですが、ざんねんながら、どうすることもできません。カーテンのあいだからは、あのピストルが執念しゅうねんぶかく、ねらいをさだめていて、いつまでたっても、立ちさろうとはしないからです。うすきみ悪くだまりこんだ怪人物が、カーテンのむこうから、じっと不二夫君をにらみつけているからです。
ああ、それはどんなに長い長い一夜だったでしょう。不二夫君は、まるでひと月もたったように感じました。あまりのことに、こわさを通りこして、心がしびれたようになって、ボウッとなってしまって、今にも気をうしなうのではないかとあやぶまれたほどでした。
ピストルをかまえた怪人物は、一晩中カーテンのかげから動かなかったのです。ですから、かわいそうな不二夫君は、朝までまんじりともせず、カーテンとにらめっこしていなければならなかったのです。
しかし、その長い長い一夜がすぎて、やっと、夜が明けはじめました。部屋の中がなんとなく、ボウッとうす白くなって、表の道路を牛乳屋さんの車が走る音、なっとう売りの呼び声などが聞こえてきました。
「ああ、うれしい。とうとう朝になった。でも、賊は客間のものを、根こそぎ持っていったにちがいないが、ああ、ほんとうに、ぼくが子どもで、どうにもできなかったのがざんねんだ。」
不二夫君は、ざんねんはざんねんでしたけれど、それでも、ホッとした気持ちで、れいのカーテンのほうを見ますと、ああ、なんという執念ぶかい、ずうずうしいやつでしょう。あいつは、まだじっと立っているのです。ピストルをかまえて、カーテンの下から長ぐつの足を見せて、だまりこくって、立っているのです。
それを見ますと、不二夫君はぞっとして、また首を毛布の中へちぢめてしまいました。
いったい、この怪人物は何をしようとしているのでしょう。となりの客間をガタガタいわせていた同類たちは、とっくに立ちさってしまったのに、こいつだけが、なんのためにいつまでも居残っているのでしょう。
外はだんだん明かるくなってきたらしく、カーテンの上のすきまから、ほの白い光がさしこんできました。でも、カーテンの織り物が厚いのと窓の外に木がしげっていますので、賊の影がすいて見えるほどではありません。カーテンのひだのふくらみで、それとわかるばかりです。
まくらもとの置き時計がもう六時十分まえをしめしています。やがて、書生の喜多村きたむらが、不二夫君を起こしにやってくるころです。
おお、廊下にそれらしい足音が聞こえてきました。喜多村です。喜多村らしい、かっぱつな歩き方です。
不二夫君は、その足音を聞きつけて、あんどするよりも、かえってドキドキしました。
「もし喜多村がふいにはいってきたなら、カーテンのかげのやつは、まさか、じっとしていやしない。逃げだしてくれればいいけれど、もし、いきなり喜多村めがけてピストルをうつようなことがあれば、それこそ、たいへんだ。」
そう思うと気が気ではありません。
しかし、何も知らぬ書生は、もう部屋の入り口まで来て、コツコツとドアをたたいておいて、いきなり寝室の中へはいってきました。
「喜多村、いけない。はいってきちゃいけない。」
不二夫君は、書生に、もしものことがあってはいけないと、何もかもわすれて、するどくさけびました。
「え、ぼっちゃん、なんです。」
喜多村は、びっくりしたように、戸口に立ちどまりましたが、目早いかれは、その瞬間、カーテンのうしろの人影を見つけてしまいました。
「あ、そこにいるのは、だれだ。」
逃げるどころか、喜多村は、いきなり賊のほうへかけよったではありませんか。不二夫君が喜多村を気づかうように、喜多村のほうでも、ぼっちゃんの一大事とばかり、われをわすれてしまったのです。
「喜多村、いけない。」
不二夫君は思わずベッドをとびおりて、書生のうしろから、その手を取って、引きとめようとしました。
でも、喜多村は、もうむちゅうです。ピストルのつつ先も目にとまらぬかのように、カーテンのほうへつめよっていきました。喜多村は勇敢な青年でした。それに柔道初段の免状を持っているほどで、腕におぼえがあるのです。
「やい、返事をしないか。……さては、きさま、どろぼうだな。うぬ、逃がすものか。」
喜多村は、まるで土佐犬とさいぬのような勇ましいかっこうで、まっかな顔をしてどなりながら、パッとカーテンに組みついていきました。
「あ、あぶない、賊がピストルを……。」
不二夫君は、今にもパンというピストルの音が聞こえ、喜多村が血を流してたおれやしないかと、息もできないほどでした。
ところが、ピストルの音ではなくて、バリバリというおそろしい音がしたかと思うと、おや、これはどうしたというのでしょう。書生はカーテンにとびついた勢いで、そのむこうの窓ガラスをやぶってしまったのです。そして、その場にころがってしまいました。
しばらくは、何がなんだかわけがわからず、喜多村も不二夫君も、キョロキョロそのへんを見まわすばかりでしたが、やがて気がつきますと、今のさわぎでめくれたカーテンのはしに、一ちょうのピストルが、ひもでくくって、ぶらんぶらんとゆれながらさがっていました。カーテンの下には、二つの長ぐつが、横だおしになってころがっていました。
不二夫君はそれを見て、思わず顔をまっかにしてしまいました。ひもでぶらさげたピストルと、長ぐつにおびえて、一晩中、息もたえだえの思いをしたのかと考えると、はずかしくてしかたがなかったのです。
「なあんだ。人かと思ったら、長ぐつばっかりか。まんまといっぱいくわされてしまった。……これ、ぼっちゃんのいたずらですか。」
喜多村は、指をけがしたらしく、それをチュウチュウ口ですいながら、顔をしかめて、不二夫君をにらみつけました。
「そうじゃないよ。やっぱり、どろぼうなんだよ。」
不二夫君は、まだ赤い顔をしたまま、気のどくそうに書生をながめて、ゆうべからのできごとを、手みじかに話して聞かせました。
「え、なんですって。じゃ、客間の家具を──。」
「そうだよ。あんなひどい音をたてていたんだから、きっと、何もかも持っていったにきまっているよ。」
「じゃ、行ってしらべてみましょう。ぼっちゃんもいらっしゃい。」
大学生服の喜多村と、パジャマ姿の不二夫少年とは、まだうすぐらい廊下をまわって、客間へ急ぎました。
客間の入り口には、左右に開く彫刻のある大きなドアがしまっているのですが、ふたりはそれを開くのがこわいような気がして、しばらくは、顔見あわせてつっ立っていました。やがて、喜多村は思いきったように、静かにドアを開いて、そのすきまから、そっと室内をのぞきこみました。ところが、どうしたのか、ちょっとのぞいたかと思うと、喜多村はびっくりしたような顔で、不二夫君を見かえりました。
「おや、ぼっちゃん、へんですよ、あなた夢をみたんじゃないの?」
「エッ、なんだって? 夢なもんか。あんなにはっきり聞いたんだもの。でも、どうかしたの、へんな顔して。」
「へんですとも、見てごらんなさい。客間のものは、なんにも、なくなってやしないじゃありませんか。」
「おや、そうかい。」
そこでふたりは、急いで客間にはいり、窓のカーテンを開いて、あたりを見まわしました。
じつにふしぎです。壁の油絵も、暖炉のかざりだなの上の銀のかびんも、銀製の置き時計も、何もかもすっかりそろっているのです。イスやテーブルも、いつものとおりにならんでいますし、じゅうたんをめくったあともなければ、だいいち、窓を開いたらしい形跡けいせきさえないのです。
不二夫君は、あっけにとられてしまいました。あんな引っ越しのようなさわぎだったのに、客間の中のものが、何一つ動かされたらしいようすもないとは、まるで、キツネにでもばかされたような気持ちです。
もしかすると、客間でなくて、ほかの部屋だったかもしれないというので、ふたりは部屋部屋を一つ一つまわり歩いてみましたが、どこにも異状はないのです。ふたりはまたもとの客間にもどって、ひじかけイスにぐったりともたれこんで、何がなんだかわからないというように、あきれかえった顔を見あわせるばかりでした。
「だって、きみ、夢のはずはないよ。これごらん。こんな手紙がぼくのベッドの上へまいこんできたんだもの。これが夢でないしょうこだよ。たしかに悪者が大ぜいしのびこんだのだよ。」
不二夫君は、後日ごじつのしょうこにと、たいせつにパジャマのポケットに入れていた、ゆうべの脅迫状を取りだして喜多村にしめすのでした。
「そうですよ。だから、ぼくもふしぎでしようがないのですよ。ぼっちゃん、こりゃなんだかへんな事件ですね。探偵小説にでもありそうな、えたいのしれない怪事件ですね。」
「ぼく、さっきから考えているんだけど、これは名探偵の明智小五郎あけちこごろうさんにでもたのまなくちゃ、解決できないような事件だね。」
不二夫君は、ちゃんと名探偵の名を知っていて、さも、しさいらしく、パジャマの腕をくみながらつぶやくのでした。
さて、読者諸君、このなんとも説明のできない、怪談のようなできごとは、いったい何を意味するのでしょうか。大ぜいのどろぼうがはいったことはあきらかなのです。しかも家の中の品物は、何一つなくなっていないのです。まさか、そんな、ばかばかしいことがあろうとは考えられません。では、不二夫君や喜多村は、何かたいせつなものが、うばいさられたのを、見おとしているのでしょうか。もしかしたら、それは客間の額がくや装飾品などとは、くらべものにならない、びっくりするほど重大な品物ではないのでしょうか。
そうしているところへ、おりよく表に自動車の音がして、不二夫君のおとうさまが、帰ってこられました。朝早く東京駅につく汽車で、旅からお帰りになったのです。
不二夫君と喜多村とは、玄関へとびだしていって、おとうさまをむかえましたが、不二夫君はお帰りなさいというあいさつもろくろくしないで、息を切らしながら、ゆうべのみょうなできごとを、おとうさまにお知らせしました。
おとうさまの宮瀬鉱造みやせこうぞう氏は、ことし四十歳、でっぷりふとったあから顔に、かっこうのいい口ひげをはやした、いかにもはたらきざかりの実業家といった感じの方でした。ある大きな貿易会社の支配人をつとめておいでになるのです。
宮瀬氏は不二夫君の話を聞くと、なぜか、ひどくびっくりされたようすで、すぐさま客間にはいって、そこにおいてある品物を念入りにおしらべになりましたが、やっぱり何一つ紛失していないことがわかりました。
「ね、おとうさま、いったいどうしたっていうんでしょう。ぼく、ふしぎでしようがないんです。」
「うん、わしにもわけがわからないよ。だがね、ひょっとすると……。」
宮瀬氏は、不二夫君がめったに見たことのないような、心配そうな顔をして、何かしきりと考えておいでになるのです。
「え、ひょっとするとって?」
「わしの家にとっては、何よりもたいせつなものをぬすまれたかもしれないのだよ。」
「たいせつなものって、なんです。」
「ある書類なのだ。」
「じゃ、その書類をしらべてみたらいいじゃありませんか。なくなっているかどうか。」
「ところがね、おとうさまも、その書類が、どこにしまってあったか知らないのだよ。」
「え、おとうさまも知らないんですって? おわすれになったのですか?」
不二夫君は、なんだかへんだというような顔をして、じっと、おとうさまの顔を見つめました。
「いや、わすれたんじゃない。はじめから知らないのだよ。しかし、この家のどこかに、その書類がかくしてあることはわかっていたのだ。この家を建てたおじさんが、そのかくし場所をわしにいわないで亡くなってしまわれたのでね。あんなふうに急な病気で、遺言をするひまがなかったものだからね。」
「じゃ、そんなたいせつなものが、この客間のどこかにかくしてあったのですね。それを、どろぼうがさぐりだしてぬすんでいったのでしょうか。」
「どうもそうとしか考えられない。そんな大さわぎをして、何もぬすんでいかなかったはずはないからね。」
それ以上は、いくらたずねても、おとうさまは、何もおっしゃいませんでした。何か秘密があるのです。子どもの不二夫君などには、うっかり話せないほどの、大きな秘密があるのに、ちがいありません。
宮瀬氏はさも心配そうなようすで、しきりと考えごとをしながら、客間の中を、あちこちと歩きまわっておられましたが、やがて、何か妙案みょうあんがうかんだらしく、大きな両手をパチンとたたいて、そこにいた書生に話しかけられました。
「おい、喜多村君、きみは明智小五郎っていう名探偵を知っているだろうね。」
「ええ、名まえは聞いています。さっきぼっちゃんと、その明智探偵のことを話していたのです。」
喜多村は明智と聞いて、何かうれしそうに答えました。
「うん、不二夫も知っていたのか。不二夫、おまえはどう考えるね。おとうさまは、このわけのわからない事件を、あの明智探偵にたのんだらと思うのだが。」
「ええ、ぼくもそう思っていたのです。明智さんならきっと、なぞをといてくださると思います。」
不二夫君もうれしそうに、目をかがやかせて、おとうさまを見あげました。
「ふん、ひどく信用したもんだね。小学生のおまえにまで、そんなに信用されているとすると、よほどえらい男にちがいない。よし、たのむことにしよう。おい、喜多村君、明智探偵事務所の電話番号をしらべるんだ。そして、明智さんに電話に出てもらえ。用件はわしが直接お話するからね。」
そして、電話がかけられ、明智小五郎は、宮瀬氏のていちょうな依頼を承諾しょうだくして、すぐ不二夫君のおうちへやってくることになったのでした。
一時間ほどのち、明智探偵の西洋人のように背の高い洋服姿が、客間にあらわれました。よく光る目、高い鼻、引きしまったかしこそうな顔が、今、不二夫君たちの前にあらわれたのです。頭はもじゃもじゃにみだれています。ちょうど絵にある古代ギリシアの勇士のような頭なのです。
宮瀬氏は明智探偵をイスに招しょうじて、ていねいにあいさつをしたうえ、昨夜のできごとをくわしくものがたりました。
「よくわかりました。それだけの手数をかけて、何もぬすまないで帰ったとは考えられません。わたしもこの部屋の中に、かならずなくなったものがあると思います。では、さっそく、この部屋をしらべてみたいと思いますから、しばらくのあいだ、わたしをひとりきりにしておいてくださいませんでしょうか。」
明智はにこにこ笑いながら、歯ぎれのよい口調でいいました。
そこで、宮瀬氏は不二夫君や書生の喜多村をつれて、別の部屋にしりぞきましたが、三十分もたったころ、客間の呼びリンが鳴って、しらべがすんだという知らせがありました。
宮瀬氏と不二夫君とが、急いで客間へはいっていきますと、明智は手に小さな紙きれを持って、部屋のまん中につっ立っていました。
「これをごぞんじですか。むこうの長イスの下にこんな紙きれが落ちていたのです。わたしは部屋のすみからすみまで、一センチも残さずしらべたのですが、賊はよほどかしこいやつとみえて、なんの手がかりも発見することができませんでした。ただ、こんな小さな、みょうな紙きれのほかには。」
宮瀬氏はそれを受けとってしらべてみましたが、いっこう見おぼえのないものでした。
それは長さ五センチ、はば一センチほどの、小さな紙きれで、それに左のようなみょうな数字が書いてあるのです。
5+3・13-2
「不二夫、おまえじゃないか、こんなものを落としておいたのは。」
「いいえ、ぼくじゃありません。ぼくの字とまるでちがいます。」
書生も知らぬといいますし、女中たちを呼んでたずねても、だれもおぼえがないという答えでした。
「みなさんが、だれもごぞんじないとすると、これはゆうべの賊が、うっかり落としていったものと考えるほかはありませんね。」
「そうかもしれません。しかし、そんな紙きれなんか、べつに賊の手がかりになりそうもないじゃありませんか。」
宮瀬氏がつまらなそうにいいますと、明智は長い指で、もじゃもじゃの髪の毛をいじくりながら、意味ありげに、にっこり笑いました。
「いや、わたしはそう思いません。もし賊が落としていったものとすると、ここに書いてある数字に何か意味があるのかもしれません。」
「数字といっても、小学生の一年生にでもわかるような、つまらない、たし算とひき算じゃありませんか。そんな数字にどんな意味があるとおっしゃるのです。」
「まあ、待ってください。ええと、五に三たす八ですね。十三から二ひく十一ですね。八と十一と……アッ、そうかもしれない。」
何を思いついたのか、明智はそういいながら、つかつかと部屋のいっぽうの壁に近づきました。
その壁には、旧式な、石炭をたく大きな暖炉が切ってあって、暖炉の上の大理石のたなに、金の彫刻のあるりっぱな置き時計がおいてあります。
明智はその暖炉の前にあゆみよって、両手で置き時計を持ちあげ、その裏がわや底をねっしんにしらべていましたが、べつになんの発見もなかったとみえて、がっかりしたように、それをもとの場所におきました。
「そうじゃない。もっとほかのものだ。八と十一、八と十一……。」
明智はきちがいのように、わけのわからぬことをつぶやきながら、また部屋のまん中にもどって、くわしくあたりを見まわしています。
不二夫君は、おとうさまのうしろに立って、明智のようすをねっしんに見まもっていました。あの有名な探偵が知恵をしぼっているありさまを、まのあたり見ているのかと思うと、なんだかぞくぞくするほどうれしくなってくるのです。
しばらく部屋の中をぐるぐる見まわしていた明智の目が、また、暖炉のたなにもどって、そのまま動かなくなってしまいました。
「うん、あれだ。あれにちがいない。」
明智はもう、そばに人のいるのもわすれたように、むちゅうになってつぶやくと、暖炉の前にかけより、そこにしゃがんで、みょうなことをはじめました。
れいの大理石のたなは、額ぶちのように暖炉をかこんだ、木製のりっぱなわくの上に乗っているのですが、そのわくの大理石の板を受けている部分に、横に長く、まるいうきぼりの彫刻が、いくつもいくつも、ずっとならんでいるのです。
不二夫君は、いつかかぞえたことがあって、そのまるい彫刻が十三あることを知っていました。ちょうど小さな茶わんを十三ならべて伏ふせたような形で、横にずっとならんでいるのです。
明智は、そのまるいうきぼりを右からかぞえたり左からかぞえたり、一つ一つ、ねじでもまわすようにいじくりまわしたり、まるで、子どものいたずらのようなまねをはじめたのです。
でも、なかなか思うようにならぬとみえて、しばらく手を休めて、小首こくびをかたむけ、ひたいに手をあてて考えてみたり、れいの紙きれを見つめて、口の中で何かブツブツつぶやいたりしていましたが、とつぜん、「アッ、そうだ。」と、ひとりごとをいったかと思うと、また、まるい彫刻をねっしんにいじりはじめました。そして、とうとう何か秘密のしかけを見つけたらしく、やっと立ちあがって、こちらをむき、にこにこ笑いながらいうのでした。
「わかりました。ここにしかけがあったのです。今、どこかしらこの部屋の中に、みょうなことが起こりますから、注意していてください。」
そして、もう一度、暖炉の前にしゃがんで、左から五番めのまるい彫刻を、ぐいぐいと右にねじまわし、つぎに十三番めのを左にまわしたかと思いますと、どこかべつの方角でカタンとみょうな音がしました。
「アッ、獅子が口をひらいた。おとうさま、ごらんなさい。あの柱の獅子が口をひらきましたよ。」
いち早くそれを発見して、とんきょうな声でさけんだのは不二夫君でした。
その声に一同が不二夫君の指さすところをながめますと、いかにも獅子が口をひらいているのです。
暖炉と同じがわの壁に、はば三十センチほど、柱のように出っぱった部分があって、その上のほうに青銅せいどうの獅子の頭がつくりつけてあるのです。部屋のかざりなのです。その青銅の獅子が、今までかたくとじていた口を、とつぜん大きくひらいたのです。
「アッ、それじゃ、あの獅子のあごにしかけがあったのか。」
宮瀬氏は、あきれたようにつぶやきました。
「そうです。この暖炉のまるい彫刻を、この紙きれの数字のとおりにまわしますと、壁のうしろにしかけがあって、獅子が口をひらくようになっていたのです。むろん、あの獅子の口の奥が秘密のかくし場所になっていて、賊はそこから、何かたいせつなものをぬすんでいったのにちがいありません。こうしてあれをひらく暗号の紙きれを、ちゃんと用意していたくらいですからね。」
明智は説明しながら、つかつかとその獅子の前に近づき、背のびをして、ひらいた口の中へ右手をさし入れました。
「からっぽです。何もありません。」
「おお、それじゃ、やっぱり賊は、その中のものをぬすんでいったのですね。」
宮瀬氏は、青ざめた顔で、がっかりしたようにためいきをつくのでした。
ややあって、宮瀬氏は何を思ったのか、明智探偵に内密の話があるからといって、不二夫君と喜多村とを立ちさらせ、ぴったりドアをしめて、探偵とただふたり、テーブルをはさんで、さしむかいとなりました。
「さいぜんも、ちょっとお話したように、わたしは、そのかくし場所を少しも知らなかったのです。しかし、どこかしらこの家の中に、あるたいせつな書きものが、かくしてあることは、よく知っておりました。亡くなったわたしの兄がかくしておいたのです。
わたしは、それを手をつくしてさがしました。兄がこの家をわたしにゆずって、亡くなってから一年ほどになるのですが、そのあいだ、わたしは毎日のように、この家のすみからすみまでさがしまわったのです。しかし、秘密のかくし場所は、どうしても見つかりませんでした。
それを、あなたは、たった一時間のあいだに、見つけてしまわれた。いったい、どうしてこの秘密がわかったのですか。」
宮瀬氏は、ほとほと感じいったように、明智の顔を見つめるのでした。
「いや、何もわたしのてがらではありませんよ。この紙きれです。この紙きれが、教えてくれたのです。」
明智はやっぱり、にこやかに笑いながら、少しも高ぶらないで答えました。
「それはわかっています。むろんその紙きれが手がかりになったことはわかっていますが、どうして暖炉の彫刻にお気づきになったのか、まるで手品のようで、わたしなどには、さっぱりわけがわかりません。」
「いや、なんでもないことなのですよ。」
明智は、むぞうさに説明しました。
「ぼくもはじめは、たいへんな思いちがいをしていたのです。五に三たす八、十三から二ひく十一というふうに、たし算とひき算をするのだとばかり思っていたのです。
それで、この部屋の中に八とか十一とかいう数のものが、何かないかと、そのへんを見まわしていますと、あの置き時計が目につきました。時計の文字盤には、一から十二までの数字がきざんであるのですからね。
わたしは、ふと、あの時計の針を、八時のところへまわしたり、十一時のところへまわしたりすれば、秘密のかくし場所がひらくようなしかけになっているのではないかと考えました。
しかし、あの時計をよくしらべてみますと、どうもそんなしかけがあるらしくも思えません。そこで、わたしはまた部屋のまん中に立って、心をしずめて、四方を見まわしたのです。すると、こんどはあのたなの下の彫刻が目にはいりました。
そこで、あのまるい彫刻の左から八番めと十一番めを動かしてみたり、右から八番めと十一番めを動かしてみたりしましたが、これも失敗でした。少しも動かないのです。
わたしは、とほうにくれて、紙きれをもう一度ながめました。そして数字を見ているうちに、ふとべつの考えがうかんできたのです。
この+や-の印しるしは、たしたりひいたりするのでなく、もっとほかのことを教えているのじゃないかしら、ためしにたしたりひいたりしないで、もとの数でやってみようと考えたのです。もとの数というのは、つまり五と十三ですね。
そこで、まず左からかぞえて五番めのまるい彫刻を、動かしてみました。すると、なんだか少し動くような気がするのです。ためしに右へねじってみますと、ぐるぐるまわるじゃありませんか。
ひょっとしたら、五にたす三は、三回まわせという意味かもしれない。そう考えて右へ三回まわしますと、何か、かすかな手ごたえがあって、そこでぴたりととまって、動かなくなりました。
こんどは左からかぞえて十三番めの彫刻です。動かしてみますと、やっぱりまわるのです。右へではなくて、左へまわるのです。
そこで、わたしは、すっかり、紙きれの数字のわけがわかりました。+のほうは右へまわせという印で、-のほうはその反対の左へまわせという印なのです。13-2ですから、十三番めの彫刻を左へ二回まわせばいいのです。
そのとおりにしますと、あんのじょう、あの獅子の口がひらいたというわけですよ。」
「ああ、そうでしたか。その紙きれの数字は、金庫をひらく暗号と同じものだったのですね。それにしても、あの暖炉のかざりの彫刻にお気づきになるとは、やっぱり専門家はちがったものです。われわれには思いもおよばぬことですよ。」
宮瀬氏は感じいって、探偵の知恵をほめたたえたのでした。
「しかし、わたしはまだ、あの獅子の口の中に、何がはいっていたかということを知らないのですが、それほどにして、賊がぬすんでいったところをみますと、よほどたいせつなものだったのでしょうね。」
「そうです。ばくだいな金額のものです。今のねうちにすれば、おそらく一億円をくだるまいと思います。」
宮瀬氏は、人に聞かれるのをおそれるように、さも一大事らしく、ささやき声になって、いいました。
「エッ、一億円? それは、たいへんな金額ですね。いったいどういう書類なのです。」
さすがの明智探偵も、金額があまりに大きいのに、びっくりしたおももちでした。
「暗号文書なのです。一億円の金塊のかくし場所をしるした暗号なのです。とつぜんこんなことをいったのでは、おわかりにならないでしょうが、これには深いわけがあるのです。あなたには、その暗号文書を賊の手から、取りもどしていただかねばなりませんから、だれにも打ちあけたことのない秘密を、お話するのですが、それはこういうわけなのです。
わたしの祖父にあたる宮瀬重右衛門じゅうえもんというのは、明治維新めいじいしんまえまで、江戸でも五本の指にかぞえられる大富豪だったのです。
その重右衛門という人が、まあおくびょう者とでもいうのでしょうね。維新のさわぎで、江戸に大戦争が起こるといううわさを聞きますと、そうなれば自分のような商人なぞは、どんなめにあうかしれないというので、たくわえていた百万両以上の金銀のほかに、家いえ蔵くらまで売りはらってしまって、それをすっかり大判小判にかえ、何百という千両箱につめて、どこか遠い山の中へ、うめかくしてしまったのです。
さっき金塊と申しましたが、じつは大判小判のかたまりなのです。いや、大判小判の山なのです。それをわたしの兄は、『大金塊、大金塊』と申していたのです。
それから重右衛門は、一家のものを引きつれて、山梨県の片いなかにひっこみ、そこで亡くなったのですが、亡くなるときに、その子ども──というのは、つまりわたしには父なのですが──そのわたしの父に宮瀬家の宝もののかくし場所をしるした、暗号文書をのこしていったのです。
重右衛門も、わたしの兄と同じように、急病で亡くなったので、くわしいことをいいつたえるひまがなかったのだと申します。
ですから、わたしの父は暗号文書を持っていても、それをとくことができなかったのです。なんでも、ひどくむずかしい暗号で、一生涯いっしょうがいかかっても、どうしても、そこに書いてある意味を知ることができなかったのです。ただ暗号文書を、命から二番めにたいせつにして、じっと持っているばかりでした。
父が亡くなりますと、その暗号は兄につたわりました。兄とわたしとは東京に出て、いろいろ苦労をしまして、ふたりとも、まあ人なみの暮らしをするようになったのですが、その兄というのが、また、かわりものでした。少し財産ができますと、こんな、みょうな洋館を建てて、世間づきあいをいっさいやめて、こっとういじりをはじめたものです。
かわりものの兄は、たいせつな暗号文書をぬすまれてはたいへんだというので、知恵をしぼって、みょうなことを考えつきました。それは、暗号の紙を二つにさいて、兄とわたしとがその半分ずつを、めいめいに、どこか秘密のかくし場所へかくしておくという、きばつな考えなのです。
それと申すのも、宮瀬家の大金塊といううわさが、いつとなく世間に知れて、暗号文書を高価にゆずってくれというものがあったり、あるときには、兄の家にどろぼうまではいったものですから、なんとなく危険を感じだしたのですね。
兄はその暗号の半分を、ひじょうな苦心をして、兄が建てたこの家の中の、だれにもわからぬ場所へかくしたと申しておりました。そして、
『わしが生きているあいだは、おまえにもそのかくし場所をいわない。死ぬときに遺言としておまえにうちあける。』というのです。
ところが、一年ほどまえ、その兄が急病で亡くなりましたが、わたしがかけつけたときには、もう息を引きとっていて、遺言をするひまもなく、とうとうそのかくし場所を聞かずにしまったのです。
それから、なんどもこの建物の中だということを聞いていたものですから、わたしはすぐさま、兄のこの家へ引っ越しをして、一年のあいだというもの、すみからすみまでさがしまわったのですが、どうしても、その暗号の半分を発見することができませんでした。まさか、獅子の口の中とは気がつかないものですからね。」
「すると、賊は暗号をぬすんでも、なんの役にもたたないわけですね。」
明智はそれに気づいて、ことばをはさみました。
宮瀬氏は、にわかに、さもおかしそうに笑いだすのでした。
「ははは……、そうですよ。せっかくぬすんでいっても、なんにもならないのですよ。その半分の暗号というのはね、ほら、こうして、たえずわたしが身につけているのですよ。」
宮瀬氏はそういいながら、右手のくすり指にはめていた、大きな指輪をぬきとって、明智の前へさしだしました。
「暗号の半分はこの指輪の中にしこんであるのですよ。わたしが考えたわけじゃありません。それも兄の知恵なのです。この指輪の石は、ねこめ石という宝石ですが、その石がはずれるようになっているのです。」
そのねこめ石を、よりをもどすように、ぐるぐるまわしますと、石は台座をはなれて、その下にもう一つ、直径三ミリほどの、水晶のような透明な、小さな石がはめこんであるのが、あらわれてきました。
「これですよ。このけし粒つぶみたいなガラス玉にしかけがあるのですよ。指輪を目の前に持っていって窓のほうをむいて、そのガラス玉をのぞいてごらんなさい。そこに暗号の半分がはいっているのです。よく考えたものじゃありませんか。兄は暗号の半分を、そのままわたしにわたさないで、けし粒ほどの写真にしたのですよ。そして、その写真を二枚の小さなレンズのあいだにはさんだのが、そのガラス玉です。豆まめ写真は、とても肉眼では見えないのですけれど、ガラス玉がレンズになって、大きく見えるのですよ。外国製のはさみの柄えなどに、よくそういうガラス玉をはめこんだのがありますね。それをのぞいてみると、女優の写真なんかが見えるのです。これはあのやりかたをまねたのですよ。兄は、これさえあればいいのだといって、もとの暗号の半分の紙は焼きすててしまいましたがね。」
明智はいわれるままに、その指輪のガラス玉のところを目にあてて、窓の光にかざして見ました。すると、これはどうでしょう。まるで顕微鏡でものぞくように、そのわずか三ミリのガラス玉の中にはっきりと左のような文字が読めたではありませんか。
「かなばかりですね。なんだか意味がよくわかりませんが……。」
「わたしは何度も見ているので、文句は読めますよ。『獅子が烏帽子えぼしをかぶる時』でしょう。それから『カラスの頭の』でしょう。まあ、そうでも読むよりほかに読み方がないのです。しかし、むろんなんのことだかわけがわかりません。それに、これは暗号の半分なのですから、ぜんぶ合わせてみないことには、どうにも、ときようがないのです。」
「ふうん、なるほど、『獅子が烏帽子をかぶる時』ですか。みょうな文句ですね。」
明智はひごろから暗号には、ひじょうに興味をもっているものですから、むちゅうになって、けし粒のようなガラス玉をのぞきつづけるのでした。
「獅子が烏帽子をかぶる」とはいったい何を意味するのでしょう。烏帽子をかぶった獅子なんて、絵にかかれたのも見たことがないではありませんか。そのうえ、あとの文句が「カラスの頭の」です。なんという、ぶきみな暗号でしょう。どこかしら深い山の奥にうずめられた、一億円の金貨のそばには、烏帽子をかぶった獅子や、おばけカラスが、じっと見はり番をつとめている、とでも、いうのでしょうか。
宮瀬氏と明智探偵とが、そのふしぎな暗号文のことについて、話しあっているところへ、あわただしく書生がはいってきて、主人に電話がかかってきたことを知らせました。
「だれからだね。」
鉱造氏は書生のほうをふりかえって、めんどうくさそうにたずねました。
「名まえはいわないでも、わかっているとおっしゃるのです。ご用をうかがっても、ひじょうに重大な用件だから、ご主人でなければ話せないとおっしゃるのです。」
「へんだねえ。ともかく、この卓上電話へつないでごらん。わしが聞いてみるから。」
そして、鉱造氏は、その応接室の片すみにある、小さい机の前へ行って、そこにおいてある受話器を取りました。
「もしもし、わたし宮瀬ですが、あなたは?」
なにげなく話しかけますと、電話のむこうからは、なんだかひどくうすきみの悪い、しわがれ声がひびいてきました。
「ほんとうに宮瀬さんでしょうね。まちがいありますまいね。」
「宮瀬ですよ。早く用件をおっしゃってください。いったいあなたはだれです。」
鉱造氏はかんしゃくを起こして、少し強い声でたずねました。
「あ、そうですか。では申しますがね。わたしは、昨晩、あなたのおるすちゅうに、お宅へおじゃましたものです。ウフフ……、こういえば、べつに名を名のらなくても、よくおわかりでしょうな。」
電話の声は、おそろしいことをいって、きみ悪く笑いました。ああ、なんということでしょう。どろぼうから電話がかかってきたのです。ゆうべ暗号の半分をぬすみだしていった悪者が、大胆不敵だいたんふてきにも、電話をかけてきたのです。
宮瀬氏は、あまりのことに、なんと答えてよいのか考えもうかばず、ちょっとためらっていますと、先方はあわてたように、またしゃべりだしました。
「もしもし、電話を切ってはいけませんよ。たいせつな相談があるのだから。……あなたは、びっくりしているようですね。フフフ……、ごもっともです。どろぼうが電話をかけるなんて、あまり世間にためしのないことですからね。しかし、まあ聞いてください。きょうはあなたと商売上の取り引きをしようというのです。けっしてらんぼうな話ではないのです。聞いてくれますか。」
名探偵明智小五郎は、宮瀬氏の顔色がかわったのを見て、すぐ、卓上電話のそばへ近づいてきました。そして、宮瀬氏の持っている受話器に耳をよせて、そこからかすかにもれてくる、先方の話し声を聞きとってしまったのです。
宮瀬氏は明智の顔を見て、「どうしたものでしょう。」と、目でたずねました。探偵は「かまわないから先方のいうことを聞いてごらんなさい。」という意味を目で答えました。
「ともかく、その用件をいってみたまえ。」
宮瀬氏が、しかたなく返事をしますと、きみの悪いしわがれ声は、さっそく、用件にとりかかりました。
「もうお気づきでしょうが、わたしは、ゆうべあなたの家につたわっている、暗号文をちょうだいするために参上したのです。そして、暗号文の半分だけは、しゅびよく手に入れましたが、どうも半分ではしかたがありません。あとの半分は、あなたがどこかへかくしているにちがいないと思いますが、わたしは、そのあなたの持っている半分の暗号を買いたいのです。
どうです。売る気はありませんか。わたしは金持ちですよ。百万円で買いましょう。あの小さな紙きれが百万円なら、いいねだんじゃありませんか。
暗号文の半分は、わたしが手に入れたのです。だから、あなたの手もとにのこっている半分は、紙くずも同様になってしまったのです。半分では暗号がとけっこありませんからね。どうです。その紙くず同様のものを百万円で買おうというのです。売りませんか。」
なんという虫のよいいいぐさでしょう。半分はぬすんでおいて、あとの半分が紙くず同然になったからといって、一億円のねうちのものを、たった百万円でゆずり受けようというのです。
宮瀬氏は、明智探偵と目で話しあって、売ることはできないと答えました。
「じゃ、もう百万円ふんぱつしましょう。二百万円出します。それでゆずってください。
二百万円では安いというのですか。一億円の金塊のかくし場所をしるした暗号だから、二百万円ぐらいではゆずれないというのですか。しかし、よく考えてごらんなさい。あの暗号はあなたのおじいさんが書いたものですよ。それからきょうまで、何十年という月日がたっています。そんな長いあいだ、あなた方は、あの暗号文をとくことができなかったじゃありませんか。たとえ、暗号の紙がぜんぶそろっていても、あなた方の知恵ではきゅうにとけるはずはありません。
とけない暗号なんか、だいじそうに持っていたって、なんにもならないじゃありませんか。まして、今ではそれが半分になってしまったのですから、あなたにとっては、まったく、なんのねうちもないのです。
その紙くず同然のものを、わたしは二百万円で買おうというのです。お売りなさい。お売りになったほうが、あなたのためですよ。」
賊が、あまりばかばかしい相談を持ちかけてきますので、宮瀬氏は少しおかしくなってきました。こちらも、相手をからかってやりたいような、気持ちになってきました。
「ハハハ……、だめだめ、そんなねだんで売れるものか。それよりも、きみのぬすんでいった半分を買いもどしたいくらいだ。どうだね、きみのほうこそ、暗号文の半分をわしに売る気はないかね。」
「フフフ、おいでなすったな。よろしい。売ってあげましょう。そのかわり、わたしのほうのは少し高いですよ。一千万円です。一千万円がびた一文かけてもだめです。どうです。買う気がありますか。フフフ……、買えますまい。だいいち、あなたの家には一千万円なんてお金はありゃしない。それよりも、悪いことはいわない。わたしにお売りなさい。二百万円でいやなら、三百万円出しましょう。え、まだ安いというのですか。じゃ、もうひとふんぱつしましょう。五百万円だ。さあ、五百万円で売りますか、売りませんか。」
賊はまるで、じょうだんのように、だんだんねだんをせり上げてきました。
「つまらない話はよしたまえ。五百万円であろうと八百万円であろうと、わしがどろぼうなんかと取り引きをするような人間だと思っているのか。それよりも、きみはつかまらない用心をするがいい。わしも、たいせつな暗号をぬすまれて、だまっているつもりはないからね。」
宮瀬氏は、きっぱりと賊の申し出をはねつけました。
「フフン、それがあなたの最後の返事ですか。せっかくしんせつにいってやっているのに、それじゃあなたは、元も子もなくなってしまいますよ。売らないといえば買わぬまでです。そのかわりに、こんどは少し手荒らいことをはじめるかもしれませんよ。あなたこそ用心するがいいのだ。わたしは、どんなことをしても、あなたの持っている暗号の半分を手に入れてみせますからね。」
「とれるものなら、とってみるがいい。わしのほうには、きみたち盗賊が鬼のようにおそれている名探偵がついているのだからね。」
「フフン、名探偵ですって? 明智小五郎ですか。相手にとって不足はありませんよ。ひとつ明智探偵と知恵くらべをやりますかね。
じゃ、せいぜいご用心なさいよ。今にどんなことが起こるか、そのときになって泣きっつらをしないようにね。念のためにいっておきますがね。電話を切ったあとで、交換局へぼくの住所をたずねてもむだですよ。ぼくは公衆電話で話しているのですからね。」
そして、ぷっつり電話は切れてしまいました。
さあ、いよいよ戦いです。
どろぼうはまだ何者ともわかりませんが、ぬすみをはたらいた家へ、ずうずうしく電話をかけてくるほどのやつですから、よほどきものすわった悪漢にちがいありません。
賊は宮瀬氏に「今にどんなことが起こるか、そのときになって泣きっつらをしないように。」と、さも自信ありげにいいましたが、いったい、どんなおそろしいてだてを考えているのでしょう。
賊は暗号の半分が、宮瀬氏の指輪の中にかくしてあることは、まだ、少しも気づいていないはずです。では、どうしてそのありかを見つけだすつもりなのでしょう。賊のほうには何か、暗号そのものを見つけだすよりも、もっと別のうまいてだてがあるのではないでしょうか。
賊がしゅびよく目的をはたすか、名探偵明智小五郎が勝利を得るか、いよいよ死にものぐるいの知恵くらべがはじまろうとするのです。
「明智さん、だいじょうぶでしょうか。わたしはあんな強いことをいったものの、なんだか心配でしかたがありません。あいつは長いあいだ暗号をつけねらっていたらしいようすです。おそろしく執念ぶかいやつです。このつぎには、いったいどんなたくらみをするかと思うと、気が気ではありません。明智さん、何かうまいお考えはないでしょうか。」
宮瀬氏は、青ざめた顔で、名探偵の知恵にすがるようにいうのでした。
「ぼくも今、それを考えているのです。あいつはもう一度、ここへやってくると思います。この家へ近づかなくては、暗号の半分を、手に入れることはできないのですからね。
われわれはそれを待っていればいいのです。そして、ぎゃくにあいつのかくれ家をつきとめて、ぬすまれた暗号を取りもどせばいいのです。しかし、あいつもなかなか悪がしこいやつですから、たとえこの家へやってくるにしても、われわれのゆだんを見すまして、何か思いもよらないやりかたで、不意うちをするつもりにちがいありません。
われわれは、それをふせぐことを考えなければなりません。相手のてだてにのらない用心をしなければなりません。」
明智はもじゃもじゃの頭に、指をつっこみながら、しきりと考えていましたが、やがて何か思いついたらしく、にこにこしていいだしました。
「ああ、こいつは妙案だ。宮瀬さん、ぼくはうまいことを思いつきましたよ。これならばだいじょうぶ、相手にさとられる気づかいはありません。ちょっと電話を拝借します。ぼくの助手の小林という子どもを、ここへ呼びよせたいのです。」
宮瀬氏があっけにとられて、ながめているあいだに、明智はもう卓上電話機をとって、明智探偵事務所を呼びだしていました。
「ああ、きみ、小林君だね。すぐここへ来てもらいたいんだ。宮瀬さんのお宅、わかっているね。あ、それから、れいの化粧箱を持ってきてくれたまえ。自動車で、急いでね。じゃ、待っているよ。」
その電話が切れるのを待って、宮瀬氏はいぶかしげにたずねました。
「明智さん、その妙案というのは、どんなことなんです。わたしには、聞かせてくださってもいいでしょう。」
「それは、こういうわけなのです。」
明智はあいかわらず、にこにこしながら説明をはじめました。
「賊が何かたくらみをするために、もう一度ここへやってくるとすれば、それをふせがなければなりません。いちばんいいのは、ぼくがお宅へとまりこんで、見はりをつとめることですが、それでは相手が用心をして近づかないかもしれません。
たとえ変装するにしても、家族がひとりふえたとなると、あんな悪がしこいやつですから、きっとあやしむにちがいありません。それにしても、さいぜんあなたが、ぼくの名を賊におっしゃったのはまずかったですよ。ぼくが、この事件に関係しているとわかっては、賊はいよいよ用心ぶかくなりますからね。
それで、ぼくのかわりにだれかと考えたのですが、けっきょく、ぼくの助手の小林に、この役をつとめさせることを思いついたのです。
小林を使うというのには、わけがあります。じつはお宅へうかがったときから、気づいていたのですが、こちらのぼっちゃん、不二夫君といいましたね。あのぼっちゃんがからだのかっこうから、顔のまるいところなんか、ぼくの助手の小林と、ひじょうによく似ているのです。年は小林のほうが上でしょうが、ぼっちゃんは大がらなので、せいの高さなども同じぐらいなのです。
そこで、ぼくはへんなことを考えついたのですよ。少しとっぴな考えですから、おおどろきになるかもしれませんが、助手の小林を不二夫君のかえ玉にして、しばらくここへ、とまらせていただくことにしたいと思うのです。」
それを聞きますと、あんのじょう、宮瀬氏は目をまるくしました。
「へえ、うちの不二夫のかえ玉ですって? で、いったいそれは、どういうお考えなのです。」
「小林を不二夫君に変装させて、不二夫君の部屋に住まわせるのです。夜も不二夫君のベッドに寝させるのです。まさか、そのかえ玉を学校へ通わせることはできませんが、かぜをひいたていにして、休ませておけばいいのです。そして、賊のやってくるのを待つのです。小林はまだ子どもですが、探偵の仕事にかけては、じゅうぶん、ぼくのかわりがつとまるほどの腕まえを持っています。けっしてへまをやるようなことはありません。」
「なるほど、そういうわけですか。しかし、それじゃほんとうの不二夫のほうはどうするのです。不二夫がふたりもいては、おかしいじゃありませんか。」
「ほんとうの不二夫君は、しばらくぼくがおあずかりしたいのです。助手の小林に変装させて、ぼくの家にいていただくことにしたいのです。学校のほうは、少しのあいだ休ませなければなりませんが、そのかわりに、ぼくなり、ぼくの家内なりが先生になって、みっちり勉強させますよ。
なぜ、そんな手数のかかるまねをするかといいますとね、これにはもう一つ別のわけがあるのですよ。というのは、ぼくは不二夫君の身のうえに、何か危険なことが起こりはしないかと、心配するからです。
賊は、あなたの指輪の秘密を知りませんから、暗号そのものをぬすみだすことはできません。何か、あなたにひどい苦しみをあたえて、あなたががまんしきれなくなるように、しむけるにちがいありません。
それには、さしあたって、不二夫君がいちばん目をつけられやすいと思うのです。子どもをかどわかして、その身のしろとして、暗号の半分をよこせという、よくある手です。ぼくは、賊がそれを考えているんじゃないかとおそれるのです。さっきの電話の口ぶりが、なんだかそんなふうに感じられましたからね。」
「ふうん、なるほど、おもしろい考えですね。そうすれば不二夫も安全だし、あなたの少年助手も、だれにもうたがわれないで、わたしの家にとまりこめるというわけですね。なるほど、こいつは名案ですね。」
宮瀬氏はしきりに感心するのでした。目の中へ入れてもいたくないほどかわいがっている不二夫君を、賊にかどわかされでもしたら、それこそたいへんです。それを、明智探偵が、あらかじめふせいでくれるというのですから、これほど安心なことはありません。宮瀬氏は、喜んで明智の考えにしたがうことになりました。
それからまもなく、表おもてに自動車のとまる音がして、小林少年が、手に小型のトランクをさげて、書生に案内されてはいってきました。
明智探偵は、小林君を宮瀬氏にひきあわせてから、小型トランクを受けとって、その中をちょっとしらべていましたが、何かうなずきながら、パタンとふたをしめて、
「宮瀬さん、これはぼくの変装用の化粧箱ですよ。この中にいろいろな絵の具やはけなどがはいっているのです。」
と説明しました。
それから、明智は、別の部屋にいた不二夫君を呼んでもらい、小林少年とふたりをつれて、化粧室へはいりました。
不二夫君は、小林少年に変装するのだと聞かされて、いやがるどころか、うちょうてんになって喜んでしまいました。あの有名な少年助手にばけて、日本一の名探偵の事務所で暮らせるのだと思うと、もう、うれしくてしようがないのです。
それから三十分ほどしますと、明智探偵は、変装させたふたりの少年を左右にしたがえて、もとの応接間へもどってきました。
「ほう、これはどうだ。おまえが不二夫かい。すっかり少年探偵になってしまったね。それに、小林君も、そうして小学生服を着ると、不二夫とそっくりですよ。明智さん、あなたのお手なみが、これほどとは思いませんでした。じつにおどろきましたよ。」
宮瀬氏はすっかり感心して、ふたりの少年を見くらべるのでした。
それから、いろいろなうちあわせがすみますと、明智探偵は、不二夫君になりすました小林助手をあとにのこし、少年助手にばけた不二夫君をつれて、宮瀬邸を立ちさりましたが、探偵のそばによりそって、玄関の石段をおりていく不二夫君は、中学生のように長いズボンをはいて、りんごのようにつやつやした顔を、さもうれしそうにほころばせ、どこからながめても、名探偵の少年助手としか見えないのでした。
さて、読者諸君、こうして世にもふしぎな取りかえっこの計略は、しゅびよくなしとげられたのですが、それにしても、明智探偵の考えは、はたしてあたったでしょうか。賊はもう一度、宮瀬邸へやってくるのでしょうか。来るとすれば、いったいどんなふうにして、何をしに来るのでしょう。
その夜のことです。不二夫君にばけた小林少年は、かりのおとうさまの宮瀬氏に「おやすみなさい。」をいって、さきにベッドにはいったのですが、なれぬ部屋、なれぬベッドのことですから、なんとなく目がさえて、きゅうには寝つかれないのです。
寝つかれぬままに、まじまじと窓のほうをながめていますと、ひるま明智先生から聞かされた、ゆうべのできごとが思いだされます。
ああ、あのカーテンのあいだから、ピストルのつつ口がのぞいていたんだな。そして、この天井から、賊の脅迫状がひらひらとまいおりてきたんだな。そのときの不二夫君の気持ちはどんなだったろう、などと考えると、いよいよ目がさえるばかりです。
ゆうべとはちがって、そのカーテンが少しひらいているので、窓のガラス戸が見えています。そしてその外は墨すみを流したようなまっ暗やみです。
ハッと気がつくと、そのやみの中に、何か白いものが動いていました。人の顔です。鳥打ち帽をまぶかにかぶった、あやしげな人の顔です。
小林君は、思わずベッドをとびおりました。そして、窓とは反対の入り口のほうへかけより、ドアをひらくと、いきなり「喜多村さあん。」と、書生の名を呼びたてました。
それから家中の大さわぎになって、宮瀬氏はもちろん、書生も、小林君も、手に懐中電灯を持って庭におり、あやしい人影の見えたあたりを、あちこちとさがしまわりましたが、いち早く逃げさったものとみえて、どこにも人のけはいさえないのでした。
やっぱり明智探偵の心配はあたっていたのです。賊は案にたがわず、不二夫少年をねらいはじめたのです。その夜はさいわい、なにごともなく終わりましたが、このぶんでは、いつどんな手段で、賊は不二夫君を、いや不二夫君にばけた小林少年を、かどわかさないともかぎりません。
そして、その心配は、まもなくじっさいとなってあらわれました。賊は、じつにふしぎな手段によって、小林君をかどわかしたのです。まるで考えもおよばないような、奇想天外きそうてんがいの手段によって、目的をはたしたのです。
ああ、それはいったいどのような手段だったのでしょう。そして賊のために、まんまとかどわかされた小林君は、どこへつれさられ、どんなめにあうのでしょうか。
それから二日のあいだは、なにごともなくすぎましたが、さて、三日めの午後のことです。宮瀬家の門のそとに、一台のトラックがとまって、ふたりの職人みたいな男が、大きな荷物をかつぎこんできました。
書生の喜多村が、玄関へ出てみますと、職人みたいな男のひとりが、何か書きつけを見ながら、
「大門だいもん洋家具店のものですが、ご注文の長イスを、おとどけにまいりました。」
というのです。書生はそんな長イスが注文してあるということを、ご主人から聞いていませんでしたが、大門という店の名は、まえにイスや机を注文したことがあるので、よく知っていました。
「今、ご主人がおるすだし、ぼくは何も聞いていないので、わからないが、たしかにうちから注文したのでしょうね。」
と、たしかめますと、男はにこにこ笑って、
「まちがいありませんよ。こちらのだんなが、わざわざ店へおいでになって、おあつらえになったのですからね。ぼっちゃんの部屋へおかれるというので、すこし小型につくったのです。」
といいながら、長イスの上にかぶせてあった白い布を取りのけて見せましたが、なかなかりっぱな長イスです。
「それじゃ、ともかくおいていってください。しかし、玄関へおきっぱなしにされてもこまるが……。」
といいますと、職人は、またなれなれしい笑顔になって、
「ぼっちゃんの部屋へはこんでおきましょうか。ぼっちゃんにも一度見ていただくほうがいいでしょうからね。」
というのです。書生は深い考えもなく、それもよかろうと思いましたので、さきに立って不二夫君の勉強部屋へ案内しました。ふたりの男は、そのあとから、おもい長イスを、えっちらおっちらと、はこぶのでした。
不二夫君にばけた小林少年は、ふいに大きな長イスがはこびこまれましたので、めんくらってしまいました。きっと、ほんものの不二夫君が、おとうさまに、こんな長イスをおねだりしたんだろうと考えましたが、かえ玉のことですから、そういう事情が少しもわかりません。ですから、小林少年としては、不二夫君ならきっとこんな顔をするだろうというような、うれしそうな顔をしてみせるほかはないのでした。
「ぼっちゃん、お気に入りましたか。この上でいくらあばれてもいいように、うんとじょうぶにこしらえておきましたよ。へへへ……さて、どのへんにおきましょうかね。」
職人は顔に似あわず、なかなかおせじがうまいのです。
そこで、小林君は、書生の喜多村君と、ここがいいだろう、あすこがいいだろうと、長イスのおき場所の相談をはじめたのですが、すると、ちょうどそのとき、玄関のほうで、何かわめくような大声がしたかと思いますと、女中が顔色をかえて走ってきて、
「喜多村さん、みょうなよっぱらいがはいってきて、動かないのよ。早く来てください。」
と知らせました。泣きだしそうな女中の顔を見ては、ほうっておくわけにいきません。柔道初段の喜多村君は「ようし。」と答えながら、肩をいからせて、女中といっしょに玄関へ出ていきました。
イスをはこんできた男たちは、それを見おくって、なぜか顔を見あわせて、にやりと笑いました。そして、ひとりがすばやくドアをしめて通せんぼうをするように、そこに立ちふさがったかと思うと、もうひとりの男が、ゆだんをしている小林君のうしろからとびかかってきました。
小林君はおどろいて、声をたてようとしましたが、アッと思うまに、手ぬぐいをまるめたようなものを、口の中へおしこまれ、声をたてるどころか、息もできなくなってしまったのです。
「さあ、おれがつかまえているから、早くしばってしまえ。」
うしろから小林君をだきかかえて、ささやき声でいいますと、ドアの前に立っていた男が、ポケットから長いなわをとりだして、サッとかけより、もがきまわる小林君の手足を、たちまち、ぐるぐるまきにしばりあげてしまいました。
いうまでもなく、このふたりの男は、暗号の半分をぬすんでいったあの悪者の手下だったのです。家具屋にばけて、まんまと不二夫君の部屋へはいったのです。そして、まさかかえ玉とは知らないものですから、小林少年を不二夫君と思いこんで、かどわかそうとしているのです。
しかし、男たちは、小林君を、いったいどうしてこの部屋からつれだそうというのでしょう。玄関には書生や女中がいますし、うらのほうから逃げるにしても、昼間のことですから、町にはたくさんの人が通っています。交番にはおまわりさんも見はりをしているのです。その中を、手足をしばった子どもをかついで通りぬけるなんて、思いもよらぬことではありませんか。
ところが、賊は、じつにおそろしい悪知恵を持っていたのです。まるで奇術のような、ふしぎなことを考えていたのです。
ふたりの男は、小林少年にさるぐつわをはめ、ぐるぐるまきにしばってしまいますと、その部屋にはこんであった、れいの長イスに近よって、みょうなことをはじめました。
男たちは、その長イスのクッション(腰かけるところ)に両手をかけて、うんと持ちあげますと、おどろいたことには、そのクッションだけが、すっぽりとはずれて、その下に、人間ひとり横になれるほどの、すきまがこしらえてあったのです。それが賊の手品の種だったのです。
ふたりの男は、しばりあげた小林少年を、わけもなくそのすきまの中へとじこめ、上から、またクッションをはめこみました。すると、長イスはもとのとおりになって、その中に人間がかくされているなんて、外からは少しもわからなくなってしまったのです。
仕事をすませたふたりは、にやにやと笑いかわして、そのまま、長イスを部屋の外へはこびだし、えっちらおっちら、玄関のほうへ歩いていきました。
書生の喜多村は、やっとよっぱらいの男を追いかえして、もとの不二夫君の部屋へ引っかえそうとしていたのですが、見ると、ふたりの男が、せっかく持ちこんだ長イスを、また、そとへはこびだしてくるようすなので、びっくりして声をかけました。
「おや、どうしたんです。なぜ、それを持ちだすのです。」
すると、さきに立った男が、きまりわるそうに笑いながら、こんなことをいうのです。
「へへへ……、どうも申しわけのないことをしちまいました。書きつけの読みちがいですよ。念のために、今よくしらべてみましたら、書きつけには宮田みやたと書いてあるじゃありませんか。町も番地も同じだったので、ついまちがえたんですよ。宮田と宮瀬のまちがいだったのですよ。へへへ……。」
ああ、なんといううまいいいぬけでしょう。相手がさも、まことしやかに、わびるものですから、喜多村は、すっかりごまかされてしまいました。
「なあんだ、宮田さんだったのか。道理でどうもへんだと思ったよ。ご主人がイスを注文しておいて、ぼくにだまっていられるはずはないんだからね。宮田さんなら、きみ、この裏手のほうだよ。」
「そうですか。へへへ……、とんだおさわがせをして、どうもすみません。」
ふたりの男はペコペコおじぎをしながら、長イスをはこびだし、門の前にとめてあったトラックにつみこんで、そのまま大いそぎで出発しました。
そして、百メートルも走ったかと思うと、なぜかトラックをとめて、そこに待ちうけていたひとりの男を、車の上に乗せて、また全速力で、走りさってしまいました。
その道ばたに待ちうけていた男というのは、さいぜん宮瀬家の玄関をさわがせた、あのよっぱらいだったのです。おどろいたことには、あのよっぱらいも、やっぱり賊の手下だったのです。
つまり、その男が、よっぱらいのまねをして、書生や女中を玄関へ引きよせているあいだに、小林少年をしばって、長イスの中へとじこめようという、最初からのたくらみなのでした。
ああ、なんということでしょう。昼日なか、女中や書生の目の前で、賊はまんまと小林少年をかどわかしてしまったのです。
それにしても、長イスにとじこめられた小林少年は、いったい、どこへつれていかれるのでしょうか。そして、どんなおそろしいめにあうのでしょうか。
さすがの名探偵助手小林少年も、賊の手下が家具屋にばけてくるなどとは、少しも考えていなかったものですから、ついゆだんして、思わぬ失敗をしてしまいました。
長イスにとじこめられて、さけぼうにも、さるぐつわのために、息もできないほどですし、あばれようにも、手足にくい入るなわのいたさに、身動きさえできないのです。
みすみす、書生や女中の前を、はこびだされながら、「ここにぼくがいるんだ。」ということを、外へ知らせることができません。小林君は、まっくらなイスのなかで、どんなに、ざんねんがったことでしょう。
長イスが邸やしきをはこびだされたのも、それからトラックにつまれて、どこかへ走りだしたのも、小林君にはよくわかっていました。
「いよいよぼくは、賊のかくれがへつれていかれるのだ。賊は、ぼくを不二夫君だと思いこんでいるので、ぼくを人質にして、宮瀬さんにあとの半分の暗号をよこせと、談判だんぱんするつもりにちがいない。」
小林君は明智探偵から、そういう事情を、すっかり聞かされて、よく知っていたのです。いや、そればかりか、もし賊にかどわかされるようなことがあったら、あくまで不二夫君になりすまして、あべこべに賊の秘密をさぐり、あわよくば、ぬすまれた半分の暗号を取りもどすようにと、教えられていたのです。
「フフン、おもしろくなってきたぞ。こんなときこそ、うんと頭をはたらかせて、先生にほめられるようなてがらをたてなくっちゃ。さあ、小林助手、心をおちつけるんだ。びくびくするんじゃないぞ。賊の手下が何人いようとも、ちっともこわいことなんかありゃしない。ぼくには明智先生が、ちゃんとついていてくださるんだから。いざといえば、きっと先生がたすけにきてくださるんだから。」
小林君は、はげしくゆれるトラックの上でそんなことを考えながら、賊のかくれがにつくのを、今やおそしと待ちかまえていました。こんなひどいめにあっても、少しも気をおとさないのは、さすがに名助手といわれる小林少年です。
トラックは、三十分あまりも、全速力で、どこかへ走っていましたが、やがて、ぴったりとまったかと思うと、長イスがおろされて、どこかの家の中へはこびこまれるようすでした。
「いよいよ来たんだな。」
と思いながら、目をふさいで、じっと考えていますと、長イスはゴトゴトと階段をはこばれているらしいのですが、みょうなことに、それが上へのぼるのでなくて、下へ下へとくだっているのです。
「おや、地下室へおりていくんだな。」
地底の穴ぐらへつれこまれるのかと思うと、いくらかくごしていても、なんだか、うすきみ悪くなってきます。
階段をおりて、少し行ったところで、ガタンと長イスがおろされ、やっとクッションが取りのけられ、小林君は手あらくイスの中から引きだされました。
長いあいだくらいところに入れられていたので、パッと目をいる光が、まぶしいほどでしたが、よく見れば、昼間だというのに、それは電灯の光なのです。やっぱり、どこともしれぬ地の底の、陰気な部屋だったのです。
「さあ、小僧、少しらくにしてやるぞ。ここなら、いくら泣いたって、わめいたって、人に聞かれる心配はないからな。」
ふたりの荒らくれ男は、そんなことをいいながら、小林君のさるぐつわを取り、からだじゅうのなわをといて、ただ、うしろ手にしばるだけにしてくれました。そして、そのなわじりをとって、
「こっちへくるんだ。首領が、おまえのかわいらしい顔が見たいといって、お待ちかねだからね。」
と、地下室の廊下のようなところを、ぐんぐん奥へ引っぱっていくのです。
いよいよ悪者の首領にあうのかと思うと、小林君はさすがに胸がドキドキしてきましたが、ぐっと心をおちつけて、敵に弱みを見せないように、わざと肩をいからせながら、平気な顔をして歩いていきました。
「さあ、こっちへはいるんだ。」
がんじょうなドアをひらいて、つれこまれたのは、二十畳じきほどの広い地下室で、壁も床もねずみ色のコンクリートでしたが、そこにおいてある机やイスなどは、目をおどろかすばかり、りっぱなものです。さすがに首領の居間だとうなずかれるのでした。
部屋の正面には、大きな安楽あんらくイスがあって、そこにきみょうな人物が、ゆったりと腰かけていました。黒ビロードのルパシカというロシア人の着るような上着を着て、黒いズボンをはいて、黒ビロードの袋のようなものを、頭からあごの下まですっぽりとかぶって、顔をかくしているのです。
その黒ビロードの袋の、両方の目のところに、三角の小さな穴があいていて、その奥からするどい目が、ぎろぎろと光っているのですが、ちょっと見るとまっ黒な顔のおばけみたいな感じです。
あとでわかったのですが、この悪者の首領は、ひじょうに用心ぶかいやつで、自分の部下のものにさえ、一度も顔を見せたことがないのだそうです。人にあうときは、かならずそのみょうな黒ビロードの覆面ふくめんをつけることにしているのだそうです。
ふたりのあらくれ男は、まずその首領にていねいにおじぎをして、
「宮瀬不二夫をつれてきました。」
といいながら、小林君をそこへすわらせました。
「うん、ごくろうだった。長イスの手品が、うまくいったとみえるね。ははは……。」
黒覆面の首領は、さもゆかいらしく、若々しい元気な声で笑いましたが、こんどは小林少年を見おろしながら、思ったよりやさしい口調で、
「不二夫君、気のどくだったね。おどろいただろう。だが心配しなくてもいい。べつに、きみをどうしようというのじゃない。ただ、しばらくこの地下室にいてもらえばいいんだ。きみのおとうさんに少し相談があるのでね。おとうさんが『うん』といってくだされば、いつでもきみは家へ帰れるんだ。わかったかね。ははは……、きみはきょうから、ぼくのだいじなお客さまというわけだよ。ハハハハ……。」
首領はビロードの覆面の中で、さもここちよげに笑うのでした。
小林君は、あまり平気な顔をしていて、かえってうたがわれてはいけないと考え、不二夫君なら、きっとこんな顔をするだろうと思われるような、こわくて心配でたまらないという顔をして、じっとうつむいていました。
「わかったかね。よしよし、わかったら、きみの部屋が、あちらにちゃんと用意してある。部屋へいってゆっくり休むがいい。」
首領はそういって、ふたりの男になにかあいずしました。すると、男のひとりが、小林君のなわじりを取って、どこかへつれていくのです。
首領の部屋を出て、くらい廊下を少し行きますと、むこうに、動物園のおりのような鉄ごうしが、見えてきました。おや、この地下室には猛獣もうじゅうでもかってあるのかしら、と思っていますと、男は、
「さあ、小僧、ここがおまえの部屋だ。どうだ気にいったかね。へへへ……、居ごこちのよさそうな部屋じゃねえか。」
と、にくにくしくいいながら、小林君のなわをとって、その鉄ごうしのすみにある開き戸から、中へおしこんでしまいました。
それは、おりではなくて、地底の牢獄だったのです。小林君のための客間というのは、つまりこの鉄ごうしの牢だったのです。
男は小林君をそこに入れますと、ポケットからかぎを出して、開き戸についている錠じょうまえに、ピチンとかぎをかけました。
「へへへ……、まあ、そこでゆっくり休むがいい。すみにはわらぶとんもおいてあるからね。それから、食いものは、三度三度ちゃんと持ってきてやるから、心配しないがいいよ。おまえをうえ死にさせちゃいけないって、首領のいいつけだからね。」
男は鉄ごうしの外から、牢の中をのぞきこみながら、さもおもしろそうにいうのです。
見ると、牢というのは、三畳じきほどのコンクリートの部屋で、くさくて、きたないわらぶとんのベッドがおいてあるほかは、ライオンやトラのおりと少しもかわりがありません。小林君は、つめたいコンクリートの床の上にすわったまま、こんなところに、しばらく住まなければならないのかと思うと、うんざりしてしまいました。
「へへへ……、いやにだまりこんでいるね。あんまり、部屋がりっぱなので、びっくりしているのかい。へへへ……、だが、おまえ小さいくせになかなか感心だねえ、ちっとも泣かないねえ。いい子だよ。ごほうびに、何か持ってきてやろうか。え、腹はへらないかね。それとも水でものむかね。」
男はいつまでも、小林君をからかっているのです。鉄ごうしに顔をくっつけるようにして、目をむいたり、口をゆがめたり、へんな顔を見せて、おもしろがっているのです。
小林君は腹がたちましたが、心の中で、
「今にみろ、ひどいめにあわせてやるから。」とつぶやきながら、じっとこらえていました。それにしても、いわれてみると、おなかは、それほどでもありませんが、のどがかわいてしかたがないのです。そこで、
「ぼく、のどがかわいたから、牛乳をください。」
と、ぶっきらぼうにいいますと、男は笑いだして、
「へへへ……、はじめて口をきいたね。牛乳をくださいか。なかなかぜいたくなことをいうねえ。よしよし、それじゃ、牛乳を持ってきてやるよ。」
といいすてたまま、どこかへ立ちさりましたが、やがて、牛乳を入れたコップを持って、もどってきました。
「さあ、ご注文の牛乳だ。毒なんかはいっていないよ。安心してのむがいい。おまえは、だいじな人質なんだからね。」
そして、小林君が牛乳をのんでいるあいだ、男はまたみょうな顔をしたり、へんなしゃれをいったりして、さんざんからかっていましたが、やがて、それにもあきたのか、開き戸の錠まえをねんいりにしらべたうえ、どこかへ行ってしまいました。
腕時計を見ますと、さいわい、こわれもせず動いていましたが、時間はもう午後の六時でした。
「よし、今のうちにねむっておこう。そして、夜中になったら、ひとはたらきするんだ。見ているがいい。きっと悪者たちの秘密をあばいてやるから。」
小林君はこんなことを考えながら、すみのわらぶとんのベッドの上に、ごろりと横になりました。春のことですから、そんなに寒いというほどでもないのです。
大胆な小林君は、やがてそのかたいわらぶとんの上で、ぐっすりねむってしまいました。しばられたり、長イスの中にとじこめられたりして、つかれていたものですから、八時間ほどもぶっとおしにねむって、目をさましたのは、もう夜中の二時でした。
「ああ、よくねむった。これなら仕事ができそうだぞ。賊のやつら、今に見るがいい。」
小林君はそんなことをつぶやいて、にっこり笑いながら、きたないわらのベッドから、起きあがりました。
そして、ポケットから、なにか銀色の針金のようなものを取りだして、牢の鉄ごうしの開き戸に近づいていきました。
その開き戸には大きな錠がついていて、かぎがなくては開くことができないようになっています。
「ふふん、こんな錠なんか、なんでもないや。ぼくは明智先生の発明された、万能ばんのうかぎを持っているんだからね。」
小林君は、こうしのあいだから手を出して、銀色の針金のようなものを、錠のかぎ穴に入れて、しばらくコチコチやっていました。すると、これはどうでしょう。あのがんじょうな錠まえがカチンと音をたててあいてしまったではありませんか。
万能かぎというのは、その針金のようなものが一本あれば、どんなかぎ穴にでもあてはまるというおそろしい力を持っているのです。
明智探偵は、いつのまにか、こんなふしぎな道具を発明していました。でも、もし、どろぼうなどが、この万能かぎの作り方を知ってはたいへんだというので、そのかぎは、どんなしたしい人にも見せない、明智探偵と小林君だけの秘密になっているのでした。
さて、なんなく、牢をぬけだした小林君は、開き戸をもとのとおりにしめておいて、うすぐらい廊下を、賊の部屋と思われるほうへ、足音をしのばせて、進んでいきました。
「覆面の首領がいた部屋は、たしかこっちのほうだった。」
と考え考え、廊下を歩いていきますと、一つのドアの前に出ました。立ちどまって、耳をすませていますと、中から大きないびきの音が聞こえてきました。
「ああ、この部屋には、手下のやつらが寝ているんだな。」
昼間、あんなにいばっていたやつが、正体もなく寝こんでいるかと思うと、おかしくなって、ちょっと、その寝顔をのぞいてやりたくなりました。
ドアのとってをそっとねじってみると、かぎをかけてないとみえて、わけもなく開きましたので、そこから顔を出してのぞいてみますと、部屋の中には五つのベッドがならんでいて、五人の大男が、前後もしらず寝こんでいました。
いちばん大きないびきをかいているのは、昼間、小林君を牢にとじこめて、外からみょうな顔をして見せてからかった男でした。口をとんがらかして、息をするたびに、ふうふうとほおをふくらましています。
小林君はそれを見て、思わずふきだしそうになりました。
ねむっている手下の男などを、いくら見ていてもしかたがありません。めざすのは賊の首領の部屋です。ぐずぐずしているときではないと、ドアをしめようとしましたが、ふと見ますと、入り口に近いたなの上に、丸型の懐中電灯がおいてあります。
「ああ、いいものがあった。これをしばらく借りていこう。」
小林君は、そっとその懐中電灯を取って、ドアをしめました。探偵七つ道具の一つの、万年筆型の懐中電灯は、ちゃんと、ポケットに用意していたのですが、それよりも大型の懐中電灯が手にはいれば、いっそう、つごうがよいからです。
それからまた、廊下を進んでいきますと、二つのあき部屋を通りすぎて、そのむこうに、見おぼえのある首領の部屋がありました。
ここもドアにかぎがかかっていないで、やすやすと中にはいることができましたが、ここは電灯が消してあって、まっくらなのです。
入り口にうずくまって、息をころして、じっとようすをうかがっていましたが、広い部屋の中はひっそりとして、まるで死んだように、なんの物音もありません。
人がいれば、たとえ寝ていても、息づかいの音が、するはずですが、それも聞こえないところをみますと、ここはだれもいないのかもしれません。
小林君は思いきって、パッと懐中電灯をつけて、大急ぎでグルッと部屋中をてらしてみました。
やっぱり、部屋はからっぽです。賊の首領はいったいどこへ行ったのでしょう。しかし、考えてみますと、この部屋にはベッドもないのですから、ここで寝るわけにはいきません。きっと首領の寝室は、もっと別のところにあるのでしょう。
だれもいないとわかると、小林君は大胆になって、懐中電灯をてらしながら、部屋中を歩きまわって、れいの暗号文のしまってあるような場所はないかと、じゅうぶんしらべましたが、そういう場所はどこにもないのです。引きだしのないテーブルとイスのほかには、なにもないのです。
ところが、そうして、部屋の中をぐるぐるまわり歩いているうちに、とつぜん、みょうなことが起こりました。小林君はびっくりして、もう少しで、アッと大きな声をたてるところでした。
そのとき、小林君は右手で懐中電灯を持ち、左手で壁をなでながら歩いていたのですが、その壁の一部分がゆらゆらと動きだして、アッと思うまに、そこに大きな穴があいてしまったのです。
小林君は、はずみをくって、その穴の中へよろけこみましたが、グッとふみこたえて、よくしらべてみますと、それはとなりの部屋へ通じるかくし戸だったのです。壁と同じ色にぬって、少しも見わけがつかないようになっているドアだったのです。
どこかに、その秘密のドアをあける、しかけのボタンがあって、小林君の左手が、そのボタンにあたったのかもしれません。思いもよらず秘密の入り口を発見してしまったのです。
しかし、もしその秘密の部屋に、人がいたらたいへんですから、小林君はびくびくして、懐中電灯をさしつけてみましたが、さいわい、そこにはだれもいないことがわかりました。
そこは五メートル四方ぐらいの小さな部屋で、一方のすみに、りっぱなベッドがおいてあるところからみますと、ここが賊の首領の寝室にちがいありません。でも、そのベッドの上は、からっぽなのです。
やっぱり、首領はどこかへ出かけてるすなのでしょうか。でも、るすとすればちょうどさいわいです。そのあいだに、この部屋の中もしらべることができるからです。ここには大きな西洋だんすなどもあって、暗号文がかくしてありそうな気がします。
ベッドの反対の壁ぎわに、りっぱなほりもののある西洋だんすが立っています。小林君は、まずその引きだしをかたっぱしから、しらべました。かぎのかかっている引きだしは、れいの万能かぎで、苦もなく開いて、のこらず中のものをしらべましたが、暗号文らしいものは、どこにも見あたりませんでした。
その大だんすのいちばん下は、高さ八十センチほどの、左右に開くとびらになっているのですが、小林君は最後に、そのとびらを開いて中をのぞいてみました。
すると、ふしぎなことに、その中には何もはいっていないのです。その中は人間ひとり、らくにはいれるほど広いのですが、それが、まったくからっぽなのです。
「へんだぞ。ほかの引きだしには、みな何かしらはいっているのに、この広い場所に何も入れないなんて、おかしいぞ。」
小林君は思わず小首をかしげました。さすがに名探偵の助手だけあって、少しでもへんだと思えばあくまでしらべてみないでは、気がすまないのです。
そこで、その開き戸の中へはいこんで、懐中電灯で奥のほうをしらべましたが、よく見ますと、その奥の板が、しっかりたんすについていないで、少し動くような気がするのです。
「いよいよへんだぞ。もしかしたら、ここからまた、どっかへ秘密の通路がこしらえてあるのかもしれないぞ。」
小林君は胸をドキドキさせながら、なおもそのへんをよくしらべますと、右がわの板のすみに、小さなボタンのようなものが、出ばっているのに気づきました。
「あ、これかもしれない。これをおせば、うしろの板が開くのかもしれない。」
思いきって、そのボタンをギュッとおしてみました。
すると、ああ、やっぱりそうだったのです。うしろの板がスウッと下へさがっていって、そのむこうに、広いすきまができました。外から見たのでは、たんすのうしろは、すぐ壁になっているのですが、その壁をくりぬいて、せまい通路がこしらえてあったのです。
見ると、そのせまいすきまに、鉄のはしごのようなものが立っています。
「おやおや、それじゃこの通路は上へのぼるようになっているんだな。きっと地下室から、この上にある建物の中へ、行けるようになっているんだ。よし、ひとつこのはしごをのぼってみよう。」
小林君は、せまい、まっくらなすきまへ身を入れて、まっすぐに立っている鉄ばしごをのぼりはじめました。
用心のために、懐中電灯は消してしまいましたので、まるで鉱山の穴の中にいるような気持ちです。
ああ、このはしごの上には、いったい何があるのでしょう。小林君はもしかしたら、思いもよらぬおそろしいめにあうのではないでしょうか。
まっくらな、せまいはしごを十二、三段ものぼりますと、頭が板のようなものにさわりました。そのまま、行きどまりになっているのです。
「おや、へんだな。こんなところで、行きどまりになるはずはないんだが。」
と思って、手をあげてさぐってみると、そこは、上の部屋の入り口らしく、厚い板でふたがしてあることがわかりました。
小林君は、力をこめて、その板をおしあげました。すると、板はちょうつがいになっているらしく、スウッと上へ開いていくのです。
あとでわかったのですが、それは、ちょうど、道路にあるマンホールのふたぐらいの大きさの、まるい板でした。つまり、上の部屋の床に、そんな穴があいていて、それに板のふたがしてあったわけです。
板を持ちあげてのぞいて見ますと、その上の部屋もまっくらで、べつに人のいるようすもありませんので、小林君はかまわず穴の上によじのぼって、板のふたをもとのとおりにしめてしまいました。
さあ、これからが、いよいよ危険です。もし賊に見つかろうものなら、どんなことになるか、わかったものではありません。
まず、そのまっくらな部屋を手さぐりでしらべてみますと、そこは畳一畳じきぐらいの、まるで押し入れみたいな、ごくごくせまい部屋であることがわかりました。むろん、人はいないのです。
そこで、やっと安心して、懐中電灯をつけて、あたりを見まわしましたが、四方とも板ばりのへんな部屋です。部屋というよりも、やっぱり押し入れか物置きのような感じです。
そこには、べつに何もおいてないのですが、ただ一方の板壁に、みょうなものが、ぶらさがっています。まっ黒な洋服のようなものです。手に取ってみますと、やっぱり、それはおとなの洋服でした。
「おや、これはルパシカではないか。それに、これはいったいなんだろう。」
ルパシカというのは、ロシア人の着る上着なのです。ルパシカといえば、何か思いだすではありませんか。小林君がここへつれられてきて、賊の首領の前に引きだされたとき、首領は何を着ていたでしょう。やっぱりこのルパシカという、へんな洋服ではありませんでしたか。
いや、そればかりではないのです。ルパシカのほかに、まだたしかなしょうこがありました。それは黒ビロードの覆面です。あの覆面が、やはり同じくぎにかけてあったのです。頭からすっぽりとかぶるようになっていて、目のところだけ三角の穴があいている、あのぶきみな覆面です。
「ふふん、あいつはここまであがってきて、はじめて覆面をぬぐんだな。そして、ふだんの着物に着かえるんだな。
してみると、あいつが手下にも顔を見せたことがないというのは、ほんとうらしいぞ。手下のものにはこの下のベッドのある部屋で、寝るように見せかけて、ほんとうは、毎晩ここへあがってきて、どこかほかの部屋で寝るのかもしれない。
なんて用心ぶかいやつだろう。手下にさえ顔も見せなければ、寝る場所も知らせないんだ。この秘密のはしごだって、きっと手下には教えてないのにちがいない。
そうとすれば、むろん暗号文も地下室においてあるはずはない。ここへ持ってあがって、だれも知らない部屋にかくしてあるのだ。」
小林君はそんなふうに考えをめぐらしましたが、賊の首領のあまりの用心ぶかさに、少しうすきみが悪くなってきました。
いったい賊は何者だろう。なぜこんなにまで用心をして、顔をかくしているのだろうと思うと、なんだかゾウッとこわくなるような気持ちでした。
「それにしても、この部屋にはどこか出口があるにちがいない。やっぱり、かくし戸になっているのかもしれないぞ。」
そう考えて、懐中電灯で、四方の板壁をてらして見ますと、一方のすみに、どうやらかくし戸らしいものが見つかりました。その部分をおしてみると、少し動くような気がするのです。
しかし、ただおしただけでは、とても開きそうにもありません。きっとまた、どこかに、戸を開くしかけのボタンがあるのでしょう。
小林君はいっしょうけんめいにそれをさがしましたが、やがて頭の上のほうの高いところに、ちょっと気のつかぬような小さなボタンがあるのを見つけました。
でも、こんどこそ、うっかり、それをおすわけにはいきません。もし、戸のむこうにだれかがいて、小林君に気づいたら、もうとりかえしがつかないのです。
おそうか、おすまいかと、長いあいだ、ためらっていました。そして、板壁に耳をつけるようにして、そのむこうがわのようすをうかがいましたが、ひっそりとして、なんの物音もありません。もう夜中の三時です。たとえ、むこうがわに人がいるとしても、まさか今ごろまで起きているはずはないのです。
「よし、思いきっておしてみよう。もし見つかったら、すばやく逃げだせばいいのだ。そして、もとの牢へはいって、知らん顔をしていればいいのだ。」
小林君は、とうとう決心しました。
まず指さきをボタンにあてておいて、用心のために懐中電灯を消してから、その指にぐっと力をこめて、ボタンをおしたのです。
すると、あんのじょう、板壁の一部が、ドアのように、グウッと、こちらへ開いてきたではありませんか。
大急ぎで、そのすきまから、むこうをのぞいてみますと、やっぱりうすぐらくて、何も見えないのです。なんだかすぐ目の前に幕がさがっているような感じで、見とおしがきかないのです。
音をたてないように気をつけて、そっとその部屋へはいっていきましたが、はいったかと思うと、何かやわらかいものに行きあたりました。手でさぐってみると、そこに厚いカーテンがさがっていることがわかりました。
カーテンのむこうには電灯がついているらしく、織り物の目から、ちかちかと光がもれています。
小林君は、カーテンのあわせめをさがして、それをほんの一センチほど開いて、部屋の中をそっとのぞきました。
それはびっくりするほど、りっぱな部屋でした。そんなに広くはないのですが、おいてある家具がみな、りっぱで、きらびやかなのです。一方には大きな化粧台があって、鏡がきらきら光っていますし、その前の台の上には、いろいろな形の美しい化粧品のびんがならんでいます。
りっぱな長イスや、ひじかけイスは、目のさめるような美しいもようのきれではってあります。床には、まっかなじゅうたんがしいてあります。
いや、それよりも、もっとりっぱなのは、正面に見えるベッドです。あたりまえのベッドよりは、ずっと大きくて、美しいかざりがあって、その上の天井からは、ぴかぴか光るまっ白な絹が、ちょうど富士山のような影で、ベッドの三方にすそをひろげているのです。
そのりっぱなベッドの上には、ひとりの美しい女の人が、顔をこちらにむけて、すやすやとねむっていました。
小林君にはよくわかりませんでしたが、その女の人は、三十歳ぐらいでしょうか。娘さんではなくて、奥さんという感じでした。
小林君は、明智先生の奥さんほどきれいな人は、ほかにないように思っていたのですが、いま目の前にねむっている女の人は、もっときれいなのです。すごいほど美しいのです。
まるでキツネにつままれたような気持ちでした。これはいったい、どうしたというのでしょう。賊の首領がいるとばかり思っていた部屋に、こんな美しい女の人がねむっているなんて、なんだか夢でも見ているようではありませんか。
覆面とルパシカをぬいだ男は、どこへ行ってしまったのでしょう。
小林君は女の人の寝顔をみつめて、長いあいだ考えていました。なんとなく、ふにおちないことがあるのです。どこやら、つじつまの合わないような気がするのです。
そうしているうちに、小林君の頭に、ひょいとみょうな考えがうかびました。
「おや、そうかしら。そんなことがあるのだろうか。」
それは、なんだか、ゾウッと身ぶるいするようなおそろしい考えでした。
「やっぱり、そうかもしれない。ああ、きっとそうだ。もしそうでないとしたら、ここに秘密の通路があるわけがない。
この女の人は、あんな美しい顔をしているけれど、秘密の出入り口をちゃんと知っているのだ。この部屋に住んでいて、それを知らぬはずがない。
それから、賊の首領は、なぜ手下の前でも、顔をかくしているのだろう。それには何か深いわけがあるのだ。
そうだ。賊の首領というのは、この女の人なんだ。女だものだから、あんなに用心をして、顔をかくしているのだ。
そういえば、きのう首領の声を聞いていて、なんだかつくり声のような気がした。ほそい声をむりに太くしているような気がした。
そうだ。あすこにねむっている、あの美しい女の人が賊の首領なのだ。」
小林君は、そこまで考えますと、お化けでも見ているような、なんともいえぬおそろしさに、背中がぞくぞく寒くなってきました。
ひげむじゃの大男なんかなら、かえってこわくないのですが、あのおそろしい大悪人が、こんな美しい女の人だったかと思うと、心の底からゾウッとしないではいられませんでした。
そう思って見ますと、女の人の顔は、美しいことは美しいけれど、けっしてやさしい顔ではないのです。なにか男もおよばないようなおそろしいたくらみをしそうな、すごみのある美しさなのです。
小林君はふと、西洋のある女どろぼうの写真を思いだしました。その女どろぼうは、美しい顔をしているくせに、男の人を何人も毒薬で殺したり、変装をしたり、宝石をぬすんだり、いろいろなおそろしいことをして、しまいには、とうとう死刑にされたのですが、ベッドに寝ている女の人の顔は、その女どろぼうと、どこかしら似ているのです。
じっとながめていればいるほど、女の人の寝顔が、おそろしく見えてきました。美しいからこわいのです。美しい顔が、こんなにこわく見えるものだということを、小林君は今の今まで知りませんでした。
ところが、そんなことを、むちゅうになって考えているうちに、小林君は、たいへんなしくじりをやってしまいました。カーテンを持っていた手が、知らず知らず動いたのです。そして、カーテンをつってある金の輪が、チーンと鳴ったのです。
ハッとして、身をすくめましたが、もうまにあいませんでした。その小さな物音に、ベッドの女の人は、たちまち目をさまして、びっくりしたように顔をあげてこちらを見ました。
小林君は逃げ腰になって、胸をドキドキさせながら、カーテンのすきまをできるだけほそくして、なおものぞいていますと、女の人は、ベッドの上に起きなおり、ヒョウのようにきらきら光る目で、部屋の中を見まわしていましたが、
「おや、今のは夢だったのかしら、なんだかみょうな音がしたように思ったけれど……。」
と、ひとりごとをつぶやきました。
小林君は石のようにからだをかたくして、息の音もたてないようにしていましたので、カーテンのうしろに人がかくれているとは気づかないようです。
でも、なんとなく心配になるとみえて、女はベッドをおりて、むこうの入り口のところへ行き、ドアのとってに手をかけて、動かしてみましたが、そこには、うらがわからかぎがかかっているらしく、開くようすもありません。
女はそれをたしかめて、安心したようにうなずいていましたが、こんどは急いで、部屋の一方の壁ぎわにあるりっぱな鏡台の前に近づいて、その上にならんでいるいろいろな化粧品の中から、大型のクリームのつぼを手に取って、そのふたを開きました。
小林君は、この真夜中にお化粧をはじめるのかしらと、びっくりして見ていますと、女はべつにお化粧をするのでもなく、クリームのつぼに、もとのとおりふたをして、鏡台の上におきました。そしてこんどは、小林君のかくれているカーテンのほうにむきなおって、そろそろと近づいてくるのです。
まさか秘密の通路から人がくるはずはないけれど、ねんのためにしらべておこうというような顔つきです。
小林君は、ハッとして身がまえました。もうぐずぐずしてはいられません。ここで見つかったら、せっかくの苦心が何もかもだめになってしまうのです。
そこで、音をたてないように、すばやく、もとの小部屋にはいり、さかいの戸をそっとしめて、れいのマンホールのような板を持ちあげると、鉄ばしごをつたって穴の中へ逃げこんでしまいました。
そして、しばらく聞き耳をたてていましたが、女はカーテンを開いてみただけで安心したのでしょう、小部屋の中へはいってくるようすはありません。
うまいぐあいに、相手にさとられないで、逃げだすことができたのです。
「これだけ見とどけておけば、今夜はもうじゅうぶんだ。ぐずぐずしていて、部屋のやつらが起きてきてはたいへんだから、早く牢へ帰ることにしよう。」
小林君はそう思って、急いで鉄ばしごをおり、地下室の首領の部屋にもどりました。そのとちゅうの秘密戸は、みな、もとのとおりにしめておいたのです。
それから、懐中電灯を、部下の寝ている部屋に返しておいて、急いで牢に帰り、鉄ごうしの戸にももとのようにかぎをかけて、そのまま、わらのベッドに横になりました。
「ふふん、うまくいったぞ。ぼくが、あれだけ歩きまわっているのに、だれも気がつかないなんて、賊のやつらものんきなもんだなあ。でも、首領が女だなんて、ほんとうに思いもよらなかった。あんなきれいなおばさんが大どろぼうとは、おどろいたなあ。」
小林君はあおむけに寝ころんだまま、しばらくは、いま見てきた女首領のことばかり思いだしていましたが、そのうちに考えが、だんだんかんじんな点にむいていきました。
「だが、暗号文のかくし場所が見つからなかったのはざんねんだなあ。きっとあの女首領の寝室の中にかくしてあるにちがいないんだが……。」
小林君はくらい天井を見つめて、しばらくのあいだ、じっとしていました。すると、とつぜん、頭の中にピカッといなずまでもさしたように、すばらしい考えがひらめいたのです。
「ああ、そうだ。そうにちがいない。わかったぞ。暗号文のかくし場所がわかったぞ、ああ、なんてきばつなかくし場所なんだろう。ぼくはあのとき、それに気がつかないなんて、よっぽどどうかしていたんだ。」
小林君はうれしまぎれに、思わずわらのベッドの上にすわってしまいました。そして、胸をわくわくさせながら、その暗号文を取りかえすことを考えました。
「首領のるすのときを考えて、もう一度あの部屋にしのびこめばいいんだ。そして、暗号文を手に入れて、この地下室を逃げだせばいいんだ。暗号文を持ってぶじに明智先生のところへもどったら、先生、どんなにほめてくださるだろうなあ。きっとにこにこして、さすがに小林君だって、おっしゃるにちがいない。」
それを思うと、もう、うれしくてしかたがないのでした。
「だが、待てよ。暗号文は手に入れても、この地下室を逃げだせなかったら、なんにもならないぞ。夜中に、みんなの寝ているすきに逃げるにしても、きっと、ひとりぐらいは寝ずの番がいるにちがいない。だれかが地下室の入り口にがんばって、外からしのびこむものや、中から逃げだすものを、見はっているにちがいない。
それに、きょうはみんなぐっすり寝ていて、うまくいったけれど、どんなことで、ほかの部下のやつらが目をさまさないとはかぎらないし、ここをぬけだすのは、なかなかめんどうだぞ。」
小林君はすわったまま、腕ぐみをして、また考えこみました。そして、しばらくじっとしていましたが、やがて、何か名案がうかんだものとみえて、思わずひとりごとをいいました。
「うまいっ。すばらしい思いつきがあるぞ。少しぼくのほうが背がひくいかもしれないが、なあに、だいじょうぶだ。きっとうまくいく。部下のやつらの見ている前で、大手をふって逃げだせるんだ。それがうまくいったら、あいつら、あとでどんなにおどろくだろう。ああ、おもしろくなってきたぞ。」
小林君はそんなことをつぶやいて、ひとりにやにや笑っていましたが、やがて、また、ごろっと横になったかと思うと、いつのまにかすやすやと寝いってしまいました。暗号のありかもわかったし、逃げだすてだてもきまったものですから、すっかり安心したのです。
さて、読者諸君、小林君は、どうして暗号のかくし場所を気づくことができたのでしょう。いったい、それはどこにかくしてあるのでしょう。また、見はり番のいる前を、やすやすと逃げだすてだてとは、どんなことでしょう。
諸君も小林君の見ただけのものは、ちゃんと見ているのですから、よく考えればおわかりになるはずです。さきを読みつづけるまえに、ひとつそれをあててごらんになりませんか。
その翌日の夕方までは、なにごともなくすぎさりました。三度の食事は、きのう小林君を牢に入れた、あのおしゃべりの部下の男が、はこんでくれましたが、そのたびに、じょうだんをいってからかうので、小林君のほうでも、相手になってものをいうようになり、だんだん心やすくなっていくのでした。
夕方、六時ごろになりますと、やっぱり同じ男が、夕ごはんのおぼんを持って、鉄ごうしの外へやってきました。
「さあ、ぼうや、ごちそうだ。ゆっくりたべるがいい。」
男は持っているかぎで、鉄ごうしの戸を開き、おぼんを中に入れると、またすぐ戸をしめて、かぎをかけてしまいました。
「ははは、へんな顔しているね。たいくつかい。童話の本でもあるといいんだが、ここには、あいにく、そんなものがおいてないんでね。まあ、ごちそうだけで、がまんするんだね。」
男はあいかわらず、おしゃべりです。
小林君は、ゆうべ牢をぬけだしたとも知らないで、いばっている男の顔を見るたびに、おかしくてしかたがありませんでした。それに、ゆうべ、この男は五人の部下の中で、いちばん大きないびきをかいて正体もなくねむっていたのです。それを思いだすと、小林君はふきだしそうになるのでした。
でも、賊は小林君が明智探偵の少年助手だなんて、夢にも知らず、宮瀬不二夫君だとばかり思いこんでいるものですから、うっかり笑顔なんかできません。こわくてしかたがないというようなふうをして、おどおどしていなければならないのです。
「ねえ、おじさん。」
小林君は、おずおずと男に声をかけました。
けさから、きこうきこうと思いながら、あまりなれなれしく見えてもいけないと思って、今までがまんしていたのですが、もうよい時分と、それをいいだすつもりなのです。
「え、なんだい。何かほしいものでもあるのかい。それならえんりょなくいうがいいぜ。おまえは、だいじなお客さまだから、なんでもいうままにしてやれって、首領のいいつけだからね。」
男は、にやにや笑いながら、ひげむじゃの顔を鉄ごうしにくっつけるようにして、いうのです。
「あのね、おじさん、首領って、いったいだれなの? どんな人なの?」
小林君は、なにげなくたずねました。
「こわいおじさんさ。ははは、じつをいうとね、おれたちも、首領がどんな人だか、よくは知らないのだよ。一度も顔を見たことがないんだからね。だが、いい首領だ。おこるとこわいけれど、仕事をすれば、ちゃんとそれだけのことはしてくださるんだからね。それでなけりゃ、こんな穴ぐらずまいなんか、一日だってがまんできるもんじゃないよ。」
小林君が、たった一日で見やぶってしまった首領の正体を、この男はまだ知らないようすです。悪人でも、人の手下になっているようなやつは、力は強くても、頭のはたらきがにぶいのでしょう。
「あのね、おじさん、この地下室の入り口は一つしかないんだろう。」
小林君は、だんだん大胆になって、また別のことをたずねてみました。
「うん、一つしかない。おまえのつれられてきた入り口一つきりだよ。」
「そこには番人がいるんだろうね。」
「ハハハ、こいつへんなことをききだしたな。おまえ、牢やぶりをして、逃げだすつもりかい。ハハハ、だめだめ、むろん番人がいるよ。地下室の入り口には、昼でも夜でも、こわいおじさんが大きな目をむいてがんばっているんだ。おまえが逃げだそうとでもしたら、その番人にひどいめにあうぜ。そんなつまらないことは考えるんじゃない。だいいち、逃げだそうといったって、その鉄ごうしが、おまえなんかの力でやぶれるものかね。ハハハ。」
男は何も知らないで、さもおかしそうに笑いました。
小林君は、ゆうべこの鉄ごうしを開いて、ちゃんとぬけだしているのです。明智先生の発明された万能かぎを持っているので、どんな錠まえだってやすやすと開くことができるのです。それを知らないで男が安心しきって笑っているのを見ると、こちらこそ、ふきだしたくなるのでした。
「おじさん、首領っていう人、いつでも、ここにいるのかい。ときどき外へ出かけることもあるの?」
小林君は、こんどは、さもなにげないふうで、いちばんききたいことをたずねました。
「そりゃお出かけになるさ。首領はここに一日いることなんて、めったにないんだよ。いろいろな仕事があってね、とてもいそがしいからだなんだ。今夜もだいじな用件があって、あるところへ出かけるんだよ。」
「やっぱり、あんな覆面のまま出かけるのかい。」
「ハハハ、おまえ、いろんなことをきくんだねえ。いくら夜だって、覆面のまま外へ出ては、かえって人にあやしまれるじゃないか。むろん、あたりまえの身なりにかえて出かけるんだよ。」
「じゃ、そのとき、おじさんたち、首領の顔が見られるじゃないか。どうして、首領の顔を知らないなんていうの?」
「ところが、見られないんだよ。首領は魔法使いなんだ。おれたちのちっとも知らないうちに、どこかへ出かけたと思うと、いつのまにか、また、ちゃんと帰っているんだ。首領は変装の名人でね、いつもまるでちがった身なりをして出かけるということだが、おれたちは、その姿を一度も見たことがないんだ。」
「へんだねえ、じゃ、どっかに秘密の出入り口があるんじゃないの? 首領は、そこからこっそり出入りしているんじゃないの?」
小林君は、その秘密の出入り口もちゃんと知っているのに、わざとそしらぬふりをして、ききかえしました。
「うん、おれたちも、そうじゃないかと思っているんだ。だが、それがどこにあるのか、すこしもわからないのだ。どう考えても、首領は魔法使いだよ。おれたちはまた、首領のそういうふしぎな力に、すっかりまいっているんだがね。」
男は相手を子どもとあなどって、ひごろおもっていることを、なにもかも、うちあけてしまうのでした。
「じゃ、首領は今夜は、るすなんだね。」
小林君は何よりも、それがたしかめたいのです。
「うん、るすだ。お帰りは夜中になるだろう。いつもそうだからね。」
小林君はそれを聞いて「うまいぞ。」と思いました。暗号文を取りかえすのには、首領のるすのときを待つほかはないが、それには二、三日牢ずまいをしなければなるまいとかくごしていたのに、その機会がこんなに早くやってこようとは、なんというしあわせでしょう。いよいよ今夜逃げだせるのかと思うと、もう、うれしくてしかたがありません。
男は、なおもいろいろじょうだんをいって、小林君をからかっていましたが、小林君がだまりこんでしまったので、つまらなそうに、おしゃべりをやめて、どこかへ立ちさってしまいました。
「さあ、いよいよ今夜は大仕事だぞ、うんとおなかをこしらえておかなくっちゃ。」
小林君は男のはこんでくれた夕ごはんを、おいしそうにたべはじめました。なかなかごちそうです。大きなチキンのフライに、トマトがどっさりついていて、ごはんがおさらに山もり、それに紅茶までそえてあるのです。小林君は、そのごちそうを、またたくまにすっかりたいらげてしまいました。
「首領の帰りは夜中だといっていたから、たぶん十二時ごろなんだろう。それまでに仕事をすまさなければならない。しかし、あまり早くても、部下のやつらが、そのへんを、うろうろしているだろうから、十時半ごろまで待つことにしよう。」
小林君はそう考えて、腕時計を見ますと、まだ七時まえでした。三時間半も待たなければならないのです。
ああ、そのあいだの待ちどおしさ。何度時計を見ても、針がおなじところにあるような気がするのです。
でも、やっと、その長い長い三時間半がすぎさって、十時半がきました。
「さあ、いよいよはじめるんだ。小林! しっかりやるんだぞ。へまをやって明智先生のお名まえをけがすんじゃないぞ。」
小林君は、われとわが名を呼びかけて、心をはげますのでした。
牢の鉄ごうしの戸を開くのは、もうゆうべ経験ずみですから、わけはありません。れいの針金をまげたような形の万能かぎを取りだして、錠まえをはずし、なんなく、牢の外へ出ました。
それから、うすぐらい廊下を耳をすまして、足音をしのばせながら、首領の部屋のほうへたどっていきました。
そのとちゅうには、れいの部下たちの寝室があるのですから、その前はことに気をつけて、通らなければなりません。ぬき足さし足、その寝室のドアに近づいていきますと、中では部下のやつらが、何か大声に話しあって笑っているのが、もれ聞こえてきました。
このぶんならだいじょうぶと、胸をなでおろして、そのドアの前を通りすぎ、いよいよ首領の部屋へはいっていきました。
それからの秘密の通路は、前にしるしたとおりですから、ここにはくりかえしませんが、小林君はやはり、ゆうべとそっくりの順序で、地上の建物の、あの美しい女首領の寝室へしのびこみました。
思ったとおり、その寝室はからっぽでした。あのりっぱなベッドの上には、まっ白な絹のきれがかぶせてあって、しわ一つよっていませんし、部屋ぜんたいがきちんとかたづいていて、ただ、ほのかに香水のにおいがただよっているばかりです。
小林君はその部屋にはいると、わき目もふらず、つかつかと、れいの鏡台の前に近づき、その上に乗せてあるたくさんの化粧品のびんの中から、ゆうべ女首領が手に取ったあのクリームのつぼをさがしだして、そのふたを開くと、いっぱいつまっている白いクリームの中へ、いきなり、指をつっこみました。
おやおや、小林君は気でもちがったのでしょうか。真夜中、賊の寝室にしのびこんで、男のくせにお化粧をするつもりなのでしょうか。
いや、そうではありません。ごらんなさい。小林君は、クリームの中から、何か小さなパラフィン紙の包みをつまみだしたではありませんか。
そのパラフィン紙をていねいに開きますと、中から、一枚の古びた日本紙が出てきました。
「あ、これだ──。」
小林君は、うれしさに顔を赤くしました。その日本紙の切れっぱしこそ、だいじなだいじな宮瀬家の暗号文だったのです。一億円の大金塊のかくし場所をしるした暗号文だったのです。
ああ、なんというきばつなかくし場所でしょう。あのたいせつな暗号を、化粧品のつぼの中へ、むぞうさにつっこんでおくなんて、じつにうまい思いつきではありませんか。
小林君はポケットから手帳を出して、暗号文をだいじそうにその中にはさみ、それから、手帳の紙を一枚やぶって、それに鉛筆で何か手紙のようなものを書き、手帳は内ポケットへ、手紙の紙は外のポケットへ入れました。
そして、クリームの表面をもとのように平らにして、ふたをしめ、もとの場所において、そのままカーテンのうしろの、暗い小部屋へもどりました。
読者諸君もごぞんじのとおり、この小部屋には、賊の首領の覆面と、ルパシカという洋服がかけてあるのです。小林君は何を思ったのか、それを一まとめにしてこわきにかかえ、そのまま、あのマンホールのような板をあげて、鉄ばしごをくだりました。
鉄ばしごをおりきると、れいの大きな西洋だんすの中ですが、小林君は、そのたんすからはいだして、その前でみょうなことをはじめました。
首領の寝室のつぎの間から持ちだしてきた、ルパシカとズボンとを、洋服の上に着はじめたのです。それを着てしまうと、こんどはビロードの覆面を、頭からすっぽりとかぶりましたが、すると、今までかわいらしい少年であった小林君が、たちまち、あのおそろしい首領の姿にかわってしまいました。
小林君は年にしては背の高いほうでしたし、賊の首領は女のことですから、ふつうの男よりも背がひくかったので、ルパシカもズボンも、だぶだぶしてこまるというようなこともなく、うまいぐあいに、身についています。
これが、小林君の妙案だったのです。こうして首領に変装して、番人の前を大手をふって通りすぎようという、思いつきなのです。
覆面の怪物になりますと、手には、さっき手帳をちぎった紙を持って、そのまま首領の部屋を出ました。そして、うすぐらい廊下を、地下室の出口のほうへ、のこのこと歩きだしたのです。
出口がどこにあるか、はっきりわからないものですから、廊下をぐるぐるまわっているうちに、むこうからひとりの部下のやつがやってくるのに出あいましたが、小林君は平気な顔で、そりかえって歩いていきますと、部下のやつは、小林君を首領がいつのまにか帰ってきたものと思いこんで、ぺこぺことおじぎをするのでした。
「うまいうまい、これならだいじょうぶだぞ。」
小林君はすっかりとくいになって、いよいよ肩をいからせながら、のしのしと歩いていきました。
まもなく、地下室の出口が見つかりました。そこには厚い板戸がしめてあって、その前の小部屋に、ひとりの大男がイスにかけて見はり番をしています。いかにも強そうなやつです。
しかし、小林君は平気で、その男の前へ近づいていきました。そして、だまってつっ立ったまま、男の鼻の先に、手帳の紙のたたんだのをさしだし、「外出するから戸を開け。」という身ぶりをしてみせました。
番人はるすだと思っていた首領が、とつぜんあらわれたので、ちょっとびっくりしたように見えましたが、いつもどこから帰ってくるかわからない首領のことですから、べつに深くうたがうようすもなく、ぺこぺこおじぎをしながら、厚い板戸をギーッと開いてくれました。
小林君は、しめたと思いながら、そのまま、ゆうゆうと外のくらやみへ出て、そこにあるコンクリートの階段を、地上へとのぼっていきます。
番人は、そのあとを見送って、板戸をしめると、もとのイスにもどって、いま手わたされた紙きれを開いてみました。首領の命令書だとばかり思いこんでいたのです。
ところが、その紙きれを、うすぐらい電灯のそばに近づけて、読みくだしたかと思うと、番人は、「アッ。」というおどろきのさけび声をたてました。目をまんまるにみひらいて、口をぽかんとあけて何がなんだかわからないという顔つきです。
その紙きれには、つぎのような痛快つうかいな文句がしたためてありました。
暗号文はもらって帰ります。そして、正しい持ち主に返します。いろいろごちそうしてくださってありがとう。では、さようなら。
まんまと賊をあざむき、首領をびっくりさせるような手紙までのこして、地下室をぬけだした小林少年は、何よりもまず、その地下室の上には、どんな建物が建っているのか、また、そこはなんという町なのかということを、たしかめなければなりませんでした。
なぜといって、小林君が賊のために、この地下室へつれられてきたときには、長イスの中にとじこめられていて、まったく外を見ることができなかったからです。
地下室の階段をかけあがって、あたりを見まわしますと、そこはコンクリートのヘイにかこまれた庭の中で、地下の真上にあたるところには、古い木造の洋館が建っていました。
コンクリートのヘイにそって走っていきますと、まもなく門のところに出ました。正面の門のとびらはぴったりしまっていましたが、そのわきのくぐり戸があいていたので、小林君は、なんなく門の外に出ることができました。
外に出て、門灯の光で、門の柱を見あげますと、そこに出ている表札には「目黒めぐろ区上目黒かみめぐろ六丁目一一〇〇、今井いまいきよ」という女の名まえが書いてありました。
今井きよというのは、あの美しい女首領の偽名にちがいありません。こんなやさしそうな名まえで世間の目をごまかして、地下室では、覆面をして男になりすまし、おおぜいの手下を自由に追い使っているのです。
じつにうまく考えたものです。あの美しい女の人が大どろぼうだなんて、だれだって夢にも思わないでしょうからね。
でも、小林君は、そんなことを、考えているひまもありません。ぐずぐずしていれば、賊の手下が追っかけてくるのですから、ただ表札の町名番地と名まえとを、すばやく暗記して、そのままかけだしました。
少し行きますと、道のわきに、まっくらな原っぱみたいなところがありましたので、小林君はそこへかけこんで、くらやみの中で、変装の覆面を取り、ルパシカをぬいで、もとの服の少年姿になりました。
そして、覆面とルパシカとは小さくまるめて、こわきにかかえ、にぎやかな表通りのほうへ急ぎました。
「なんにしても、早くこのことを、明智先生にお知らせしなければならない。先生きっと心配していらっしゃるだろうからなあ。ああ、ちょうどいい。あすこに公衆電話があるから、帰るまえに電話でお知らせしておこう。」
小林君はとっさに思いついて、その町かどにあった公衆電話へとびこみました。
「ああ、小林君か。どこからかけているんだ。え、うまく逃げだしたって? 暗号も手に入れた? それはえらい。さすがにきみだ。きみなら、きっとうまくやるだろうと思ったが、しかし心配していたよ。よかった。よかった。」
電話のむこうから、明智先生の声があわただしく聞こえてきました。
小林君は賊の首領が女であること、今井きよという名まえで上目黒の洋館に住んでいることなどを、てみじかに知らせたあとで、女首領にあてて、手紙をのこしてきたことをいいますと、明智探偵は心配そうな声で、
「きみ、その手紙に自分の名を書きやしなかったかい。」
とたずねました。
「ええ、書きました。明智探偵の助手の小林って書きました。あいつらが、ぼくを不二夫君と思いこんでいるので、びっくりさせてやろうと思ったのです。」
「しまった。そいつはまずかったね。きみにも似あわない、つまらないまねをしたじゃないか。」
「どうしてですか。」
小林君は不服らしく聞きかえしました。
「どうしてって、わかりきっているじゃないか。きみがぼくの助手とわかれば、賊は用心をするにきまっている。逃げだしてしまうかもしれない。せっかくかくれ家がわかったのに、逃がしてしまっちゃ、なんにもならないじゃないか。」
小林君はそれを聞いて、ハッとしました。
いかにも大失策でした。暗号を取りもどしたことだって、賊に知らせる必要は少しもなかったのです。ただこっそり逃げだしさえすればよかったのです。なんだか賊にいばってやりたいような気がして、手紙なんか書いたのは、たいへんな失敗でした。
「先生、ぼく、うっかりしていました。どうしたらいいでしょう。」
小林君は、先生に申しわけない気持ちがいっぱいで、もう泣きだしそうな声になっていました。
「その女首領は、きみが逃げだすときには、まだ帰っていなかったんだね。」
「ええ、そうです。」
「じゃ、まだ、まにあうかもしれない。ぼくはこれからすぐ、警視庁へ電話をかけて、中村君に犯人逮捕の手はずをしてもらっておくから、きみは急いで帰ってくれたまえ。」
中村君というのは、警視庁の捜査係長で、明智探偵とは、ごくしたしいあいだがらなのです。
小林君は先生にしかられて、がっかりしてしまいましたが、でも、自分の不注意ですから、しかたがありません。二度とこんな失敗はくりかえさないようにしようと、かたく心にちかって、公衆電話を出ました。
もう十一時半でしたが、大通りにはまだ人通りがあり、タクシーも通っていましたので、それを呼びとめて、明智探偵事務所へ急ぎました。
「先生、とんだ失策をしてしまって申しわけありません。」
小林君は明智先生の書斎にはいると、まっさきにおわびをしました。
「なあに、そんなにあやまることはないよ。たとえ賊に逃げられたとしても、きみは暗号を手に入れたという大てがらをたてているんだからね。さっきは、ぼくのいい方が、少し強すぎたようだね。気にしないでもいいんだよ。」
やっぱりいつものやさしい先生でした。小林君は先生のにこにこ顔を見て、ほっとしましたが、そんなにやさしくいわれますと、いよいよ自分の失策がはずかしくなるのでした。
「これが暗号です。化粧台のクリームのつぼの中にかくしてあったのです。」
小林君は内ポケットの手帳の中から、暗号の紙きれを出して、先生に手渡し、それを手に入れた順序を報告しました。
「うん、よくやったね。たった一晩で、秘密の通路を見つけだし、賊の正体を見やぶり、クリームつぼのかくし場所まで気がつくなんて、きみでなければできないげいとうだよ。ありがとう、ありがとう。」
明智探偵は小林君の肩に両手を乗せて、さもしたしげにお礼をいうのでした。小林君はそれを聞いて、なんだか目の奥があつくなるような気がしました。そして、心のなかで、この先生のためなら、命をすてたってかまわないと思うのでした。
「暗号の研究は、あとでゆっくりとすることにしよう。」
明智探偵は、暗号文の紙を書斎の秘密の金庫の中にしまいました。
「きみが、暗号を取りもどしたことは、いま宮瀬さんに電話で報告しておいたよ。宮瀬さんもたいへん喜んでおられた。それから中村警部に電話したが、夜中だけれども、そういう大事件ならば、すぐに部下のものをつれて、賊の逮捕にむかうからということだった。ちょうど、ここは上目黒への通り道だから、中村君たちはここへ立ちよることになっている。」
「じゃ、ぼくがご案内しましょうか。」
「うん、そうしてくれたまえ。むろん、ぼくもいっしょに行くよ。だが、賊が逃げだしたあとでなければいいがなあ。」
そうしているところへ、表に自動車のとまる音がして、中村捜査係長の一行が到着しました。係長のほかに七名の刑事が、二台の自動車に乗ってやってきたのです。ものものしい捕り物陣です。
明智探偵と小林少年とは、前のほうの自動車に乗って、案内役をつとめることになり、二台の自動車は、そのまま深夜の町を、上目黒めざして、おそろしいスピードで走りだしました。
上目黒につきますと、一同は賊のすみかの百メートルほどてまえで自動車をおり、くらい町を、はなればなれになって、れいの洋館へと近づいていきました。
あらかじめ、自動車の中でうちあわせをして、中村捜査係長と明智探偵とは表玄関から、小林少年は五名の刑事の案内をして、地下室から賊のすみかにふみこむことになり、のこりの二名の刑事は、洋館の表門と裏門に見はり番をつとめる手はずになっていました。
小林君は刑事たちのさきに立って、用心しながら、れいの階段から地下室へおりていきましたが、入り口の大戸はあけっぱなしになっていて、どこへいったのか、番人の姿も見えません。
「へんだな。」と思いながら、だんだん奥へはいっていき、五人の部下の寝室の前までたどりつきました。すると、その部屋のドアもあけっぱなしになっていて、ベッドはみなからっぽなのです。なんだか引っ越しでもしたあとのように、がらんとした感じです。
「だれもいないようですね。」
刑事のひとりが、小林君をせめるようにささやきました。
「ええ、逃げてしまったのかもしれません。でも、ともかく首領の部屋までいってみましょう。首領は外出していたのだから、ひょっとしたら、まだ帰っていないかもしれません。そうすれば、待ちかまえていて、とらえることができるのですから。」
小林君は、刑事たちをなだめるようにささやきかえして、いよいよれいの秘密の通路のある部屋へはいっていきました。
まっくらなぬけ穴の鉄ごうしを、小林君を先頭に、五人の刑事がそろそろよじのぼって、やがて、れいのマンホールのような穴から、地上の建物にぬけだしました。
いよいよ首領の寝室です。さかいの厚いカーテンを細目にあけて、そっとのぞいて見ますと、アッ、いる! いる! あの美しい女首領は、なにも知らないで、ベッドの上にねむっているではありませんか。
すると、ちょうどそのとき、むこうがわのドアが静かにあいて、だれかが首領の寝室へしのびこんでくるのが見えました。
「おやっ!」と思って見つめていますと、ドアがすっかりあいて、そこにあらわれたのは、ほかでもない、明智探偵と中村係長の姿でした。
ふたりは部屋にはいると、すぐベッドの女の人を見つけて、ハッとしたように立ちどまりましたが、とっさに「これが女首領だな。」とさとったようすで、おたがいに目であいずをして、つかつかとベッドのほうへ進みよりました。
それとみた小林君は、もうかくれているときでないと思いましたので、やにわにカーテンを開いて、部屋の中にとびこんでいきました。
つまり、むこうの入り口からはいった中村係長と明智探偵、こちらのカーテンからとびだしていった小林君と五人の刑事とが、両方からベッドに近づいていったのです。
さすがの女賊も、もう運のつきです。両方の出口をふさがれてしまったうえに、こちらは総勢八人、相手はかよわい女ひとりなのですから、どうしたってのがれることはできません。
係長が目くばせしますと、ひとりの刑事が、いきおいこんでベッドにつき進んでいきました。女はまだ身動きもしません。起きているのかねむっているのか、目をふさいだままです。
刑事はいきなり女賊にくみついていきました。そして、ねまき姿の女をだきあげたかと思うと、
「おや。」
といって、いきなりそれを床の上へほうりだしてしまいました。
女賊はカタンというみょうな音をたてて、そこに横たわったまま、まるで死人のように身動きもしません。
「人形です。これはろう人形です。」
人々は刑事の声に、おどろいて、女の形をしたものに近づいて、その顔をのぞきこみました。
それは生きた人間ではなくて、女首領のねまきを着せられたろう人形でした。そのさいくがあまりよくできているので、だれも人形とは気づかなかったのです。
やっぱり、賊は小林君の手紙によって、何もかもさとってしまったのです。そして、明智探偵がここへくることを察して、こんな人形を身がわりに寝かせておき、名探偵をアッといわせるつもりだったのです。なんというすばやい、悪がしこいやつでしょう。
「おや、人形が、なんだか紙きれをにぎっていますよ。」
刑事が人形の手にはさんであった、一枚の紙を取って、明智探偵に手渡しました。それは女首領から明智にあてた手紙だったのです。小林君がしたように、女賊もまけないで、置き手紙をのこしていったのです。
それは、つぎのようなうすきみの悪い手紙でした。
明智さん
こんどはわたしのまけです。あなたはいい少年助手をお持ちですね。わたしは一時この家をすてて立ちのきますが、けっして、宮瀬家の金塊をあきらめるわけではありません。かならず手に入れてお目にかけます。わたしには最後の手段がのこっているのです。それがどんな手段だか、ひとつ、あなたの知恵であててごらんなさいませんか。
その翌朝、明智探偵は、あずかっていた不二夫君をつれて、宮瀬家をたずねました。
主人の宮瀬鉱造氏は、暗号文の半分が手にはいったという知らせを受けていましたので、待ちかねていて、明智を応接室に通しました。
明智は小林君が不二夫少年の身がわりとなって、賊のすみかにつれられていってからのちのできごとを、くわしく報告しました。
「そういうわけで、小林が不二夫君のかえ玉だということも、賊のほうへわかってしまいましたので、いつまでもわたしの家におあずかりしておくのもなんですから、きょうは不二夫君をおつれしてきたのです。
これからは、警察のほうで、じゅうぶん不二夫君のことも気をつけてくれるはずです。とうぶん、おたくの付近に刑事の見はりをつけるということでした。」
「いや、いろいろお手数でした。不二夫のことはわたしのほうでも、書生の人数をまして、気をつけることにします。で、暗号はお持ちくださいましたでしょうか。」
宮瀬氏は、何よりも暗号の半分が気にかかるのでした。
「持ってきました。これです。」
明智は、ポケットからその紙きれを取りだして、テーブルの上におきました。
宮瀬氏は、急いでそれを手に取り、二、三度読みかえしましたが、さっぱり、わけがわからないらしく、小首をかしげて、
「どうも、わかりませんなあ、これはいったい、なんのことでしょう。」
と、明智の顔を見るのでした。
「わたしもまだよくはわかりません。ひとつそれを、あなたの指輪の中にはめてある半分の暗号とつづけてここへ書いてみましょう。」
明智はそういって、テーブルの上の白紙に、筆でつぎのような形に暗号文をかきとりました。
ぎざぎざの線からまえの部分が、宮瀬氏の指輪の中にかくしてある半分、ぎざぎざからあとの部分が、こんど小林君が取りもどした半分です。
「やっぱりわかりませんなあ。いったいどう読むのでしょう。」
宮瀬氏が、それをのぞきこんで、いぶかしげにいいました。
「たぶん、このはじめのほうは、このあいだもいったように『獅子が烏帽子をかぶる時、カラスの頭の』でしょうね。そのあとは、『ウサギは三十ネズミは六十岩戸いわとの奥をさぐるべし』とでも読むのでしょう。
つづけて読めば、獅子が烏帽子をかぶる時、カラスの頭のウサギは三十、ネズミは六十、岩戸の奥をさぐるべし、となります。」
「なんだか動物園へでもいったようですね。それに、カラスの頭のウサギっていうのは、いったいどんな動物でしょう。ウサギの胴にカラスの首がついている化けものでもいるのでしょうか。」
「なんだか、魔術師のじゅ文みたいな感じがしますね。しかし、これを何度も何度もくりかえして読んでいると、少しずつ意味がわかってくるようです。
まず、いちばんおしまいの『岩戸の奥』というのは、どこかに、岩が戸のように入り口をふさいでいるほら穴かなんかが、あるのではないでしょうか。そのほら穴の奥をさがせ、という意味じゃないでしょうか。」
「なるほど、そうでしょうね。しかし、この動物どもは、さっぱりわかりませんなあ。ウサギが三十ぴきに、ネズミが六十ぴきなんて。」
「いや、それもよく考えれば、わかるのです。ウサギとネズミには特別の意味があるのですよ。ウサギという字は、ちがう字で書くと『卯う』でしょう。それからネズミは『子ね』でしょう。つまり両方とも十二支のうちの一つなのです。
十二支というのは、子、丑うし、寅とら、卯、辰たつ、巳み、午うま、未ひつじ、申さる、酉とり、戌いぬ、亥いの十二で、午の年とか酉の年とかいうあの呼び方なのです。」
「うん、なるほど、そうですね。すると……。」
「すると、この二つの動物は、方角をしめしているのじゃないかと思うのです。」
「アッ、そうだ。いかにもおっしゃるとおり、これは方角です。」
宮瀬氏は何か大発見でもしたように、うれしそうな顔になって、明智の顔を見るのでした。
「ウサギ(卯)は東でしょう。ネズミ(子)は北でしょう。すると、これは東のほうへ三十、北のほうへ六十ということになります。」
読者諸君の家に古い磁石がありましたら、その目もりをごらんになるとわかります。古い磁石には、東西南北のほかに、十二支の名で方角が書いてあるはずです。それを見ますと、東は卯、西は酉、南は午、北は子となっています。
「では、この三十と六十は長さのことですね。」
「そうです。昔のことですから、むろんメートルではなく、尺しゃくか間けんですが、間にすると、六十間は百メートル以上ですから、これは少し遠すぎるような気がします。やはり尺でしょう。つまり卯の方角の東のほうへ三十尺(九・一メートル)へだたり、そこからまた子の方角の北のほうへ六十尺(十八・二メートル)へだたったところに、この岩の戸があるという意味じゃないかと思います。」
明智が、わけのわからない暗号をすらすらとといていきますので、宮瀬氏はすっかり感心してしまいました。
「それじゃ、このまえのほうの獅子やカラスはどういう意味でしょうか。これもあなたはおわかりになっているのですか。」
「ええ、だいたい見当がついています。」
明智は、にこにこして答えました。
「これは、少しめんどうなのです。ただ考えたのではわかりません。ぼくはこの意味をたしかめるために、登山家の名簿をくって、ほうぼうの有名な登山家に電話をかけたり、手紙をだしたりして、知恵をかりたのですよ。」
宮瀬氏は登山家と聞いても、なんのことか少しもわかりませんでした。登山家が「烏帽子をかぶった獅子」や「カラスの頭」を知っているとでもいうのでしょうか。
宮瀬氏は、明智がこの暗号をどんなふうにといてみせるかと、待ちどおしくてたまらないように、じっと探偵の顔を見つめていました。
名探偵は、いつものように、にこにこして説明をはじめます。
「ここには動物では獅子とカラスとがあります。それから烏帽子です。この三つのものが何を意味しているかということを、ぼくはいろいろと考えてみました。
暗号のあとのほうには、さっきもいったように、東へ三十尺だとか北へ六十尺だとか、方角が書いてあるのですから、この獅子やカラスは、何かその方角のもとになる場所をしめすものにちがいないのです。
ぼくは、たぶんその場所は、山の中だろうと思いました。山の中で、獅子だとか、カラスだとかいうようなものが何かないかと考えてみました。むろん、生きた獅子は日本の山にはいませんし、カラスにしても、生きたカラスでは、ほうぼうへ飛んでいきますから、目じるしにはなりません。ほんとうの獅子やほんとうのカラスではないのです。
いろいろと考えているうちに、ぼくは、ふとこんなことを思いつきました。
山のなかを流れている深い谷川の両がわなどには、よく大きな岩が、そびえているものです。そして、そういう大きな岩には、土地の人が、いろいろな名をつけていますが、この暗号の烏帽子や獅子は、その大岩の名まえではないかと考えたのです。烏帽子岩とか獅子岩とかいう名はよく聞くじゃありませんか。
きっとその山の中には、烏帽子のような形をした大岩や、獅子の頭のような形をした大岩があるのだろうと思います。
そう考えてきますと、このカラスの頭というのも、やっぱりカラスの頭に似た形をした岩の名かもしれません。カラス岩なんてあまり聞いたことがありませんが、でも、日本中をさがせば、どこかにないとはかぎりません。
つまり、どこかの山の中に、烏帽子岩と獅子岩とカラス岩とが、一つところにかたまっているような場所をさがせばいいのです。烏帽子岩とか獅子岩とかが、ただ一つだけある場所は、ほうぼうにあるでしょうが、烏帽子と獅子とカラスと三つひとかたまりになっているような山が、二つも三つもあろうとは考えられません。
ですから、この三つの岩のあるところを見つけさえすれば、あなたのご先祖が金塊をかくされた山の名がわかるわけです。」
明智がここまで説明しますと、宮瀬氏は感じいったように、しきりにうなずいてみせて、
「なるほど、なるほど、いかにもあなたのおっしゃるとおりかもしれません。おもしろくなってきましたね。で、それから。」
と、さきをうながすのでした。
「そこでぼくは、山岳会員の名簿をくって、有名な登山家十人ほどに、そういう岩のある山をごぞんじないかと、電話や手紙で問いあわせてみたのです。」
「うん、すると。」
宮瀬氏はイスをガタンといわせて、前にのりだしました。
「ところが、ふしぎなことに、そういう三つの岩のかたまっているような山を、だれも知らないのですよ。」
「それじゃ、だめだったのですか。」
「いや、山の中にはありませんでしたが、ひとりの登山家が、そういう名の三つの岩のある島を知っているといって、教えてくれたのです。その人は山登りばかりでなく、ひじょうな旅行家で、日本のすみからすみまで知っている人です。」
「島ですって?」
「そうです。ところで、宮瀬さん、金塊をかくされた、あなたのおじいさんが東京のかたということはわかっていますが、それよりもっとまえのご先祖はどこのかたですか、もしや三重県のかたではありませんか。」
明智がたずねますと、宮瀬氏はびっくりしたような顔をして、答えました。
「ええ、そうですよ。わたしの先祖は三重県の南のほうから出ているのですよ。どうしてそれがわかりました。」
「それじゃ、いよいよあの島にちがいない。三重県の南のほうの海に、岩屋島いわやしま(仮名)という小さな島があって、その島には烏帽子岩、獅子岩、カラス岩という三つの大きな岩があるのだそうです。
大神宮さまのある宇治山田うじやまだ市などよりも、ずっと南のほうに、長島ながしまという町があるのですが、そこから船で八キロばかりの荒海あらうみの中に、その岩屋島があるのです。まわり四キロあまりの、人も住んでいない小さな島だそうです。
岩の多い島で、遠くからながめると、ちょうど鬼の面を上むきにして、海にうかべたような形をしているので、その近所の人は、鬼ガ島と呼んでいるようです。そして、その島には、むかし鬼がすんでいたんだといって、こわがって、漁師などでも、船を近づけないようにしているということです。
あなたのおじいさんは、ご先祖のすんでいた三重県に、そういう人の近づかない島のあることをごぞんじだったので、東京から船で、そこへ金塊をはこんで、かくされたのではないでしょうか。山の中だなんて思わせておいて、じつは海の中にかくされたのではないでしょうか。」
「なるほど、先祖の土地へ宝ものをかくすというのは、ありそうなことですね。」
「あなたはごぞんじなくても、あなたのおとうさんなどは、ときどきは故郷へ行かれたこともあるでしょうし、岩屋島にそういう三つの岩のあることも知っておられたかもしれません。ですから、おじいさんは、この暗号は、ほかの者にはわからなくても、あなたのご一家のかたにはよくわかるだろうと、お考えになったのではないでしょうか。」
「ああ、そうです。そうにちがいありません。明智さん、ありがとう。このむずかしい暗号が、そんなにやすやすと、とけようとは、夢にも思いませんでした。とにかく、わたしは、きゅうにその島へいってみたくなりました。もしおさしつかえなければ、明智さん、あなたもいっしょに行ってくださいませんか。」
宮瀬氏は何十年というあいだ、だれにもとけなかったなぞが、明智探偵のおかげで、みごとにとけたものですから、もう大よろこびです。
「ええ、ぼくもごいっしょに行きたいと思います。岩屋島にかくしてあることは、だいたいわかったとしても、まだ暗号がすっかりとけているわけではありませんからね。やはり、島へ行ってしらべてみなければ、ほんとうのことはわからないのです。」
宮瀬氏はそれを聞いて、やっと気づいたように、まゆをしかめました。
「おお、そうでした。わたしは、それをおききしたいと思っていたのです。獅子と烏帽子とカラスが岩の名だということはわかりましたが、その獅子岩が烏帽子をかぶるということは、いったいなんのことでしょう。それに、三つの岩はわかっていても、そのどこから、東へ三十尺(九・一メートル)はかるのだが、まるでけんとうがつかないじゃありませんか。」
「そうですよ。そこがぼくにもまだ、よくわからないのです。獅子が烏帽子をかぶった時に、カラス岩の頭から、東のほうへ三十尺はかるというのでしょうが、その獅子が烏帽子をかぶるというわけが、ぼくにもわかりません。どうしても島へ行って、三つの岩を見なければ、わからないのです。」
さすがの名探偵も、烏帽子をかぶった獅子というのが、どんなものだか、まるでけんとうがつきませんでした。
ああ、烏帽子をかぶった獅子、なんだかまんがにでもありそうな形ではありませんか。しかし、このとっぴな組みあわせには、なんとなくきみの悪いようなところがあります。
大きな獅子が、烏帽子をかぶって、荒海の中の無人島にじっとうずくまっていることを考えると、なんだかゾウッとするではありませんか。
そして、いよいよふたりは岩屋島へ出かけることに話がきまりましたが、宮瀬氏は、気がかりらしくこんなことをいいました。
「わたしたちのるすちゅうに、賊のやつがまた、不二夫をひどいめにあわすことはないでしょうか。小林君が身がわりになって、暗号をぬすみだしたり、警察が賊のすみかをおそったりしたのですから、賊は、そのしかえしをしようと、待ちかまえているにちがいありません。そこへ、わたしたちが旅行してしまったら、あいつらは、また不二夫をどうかするのじゃないでしょうか。」
「そうですね。そういうことが起こらないとはいえませんね。どうでしょう。不二夫君も岩屋島へつれていってあげては。そして、ぼくも小林をつれていくことにしたら、お友だちもあるわけですし。」
と、明智がうまいことを思いつきました。
そこで、宮瀬氏は不二夫君を応接室によび入れて、そのことを話して聞かせますと、不二夫君はすっかり喜んでしまいました。
「ええ、ぼくだいじょうぶです。小林君といっしょに、きっとおとうさんの手助けをします。鬼ガ島探検隊っていうんでしょう。ぼく、そういう旅行はだいすきですよ。」
「ハハハ……、鬼ガ島探検隊はよかったねえ。すると、おまえと小林君とが、桃太郎っていうわけかい、ハハハ……、よし、それじゃ、つれていってあげるとしよう。」
宮瀬氏も上きげんで、不二夫君をつれていくことにきめました。不二夫君はずっと学校を休んでいたのに、またつづけて休まなければなりませんが、賊にさらわれることを思えば、学校を休むのもしかたがないわけです。
そうして、鬼ガ島探検隊員は、明智と宮瀬氏と小林少年と不二夫君の四人づれということになったのです。
出発は、その翌日の夜ときまりました。
明智と宮瀬氏は登山服にゲートルをつけ、ステッキを持ち、小林少年と不二夫君は、洋服に、やはり、ゲートルをまいて、四人ともリュックサックを背おい、わざと品川しながわ駅から、人目につかぬように、汽車に乗りこみました。
汽車の中でねむって、そのあくる日の昼ごろには、三重県の南のはしの長島町についていました。それは海岸の漁師町でした。町じゅうに、磯くさいにおいがただよって、近くの海岸から、ドドンドドンという波の音が聞こえていました。
四人は、町にたった一軒の、いなかめいた宿屋にはいって、昼の食事をしたのですが、明智探偵は、その宿の主人を呼んで、いろいろ岩屋島のことをたずねてみました。
「はあ、あの島は鬼ガ島と申しまして、ここの名所になっております。お客さんがたは、よく船で見物においでになります。」
「その鬼ガ島に、烏帽子岩と、獅子岩と、カラス岩という三つの大きな岩があるそうだね。」
「ええ、ございます。みょうな岩でね、一つは烏帽子にそっくりだし、もう一つは獅子の頭にそっくりだし、それから、カラス岩と申しますのは、まるでカラスがくちばしを開いて、カァカァと鳴いているようなかっこうをしております。いかがでございます。船をやとって、見物なされては。ぼっちゃんがたは、きっとお喜びでございますよ。」
「それじゃ、ひとつ船をやとってください。ことによったら、島へあがってしばらく遊ぶかもしれないから、晩がたまでかかるつもりで、来てくれるようにいってください。」
明智がいいますと、主人はびっくりしたように、目をまるくしました。
「え、島へおあがりなさる? それはおやめになったほうがようございましょう。獅子岩やカラス岩は船からでもよく見えます。おあがりになったところで、岩ばっかりの島で、べつに見るものもありませんし、それに漁師たちはあの島へ船をつけることを、いやがりますので……。」
と、しきりにとめるのです。
「漁師がいやがるというのは、何かわけがあるのですか。」
「なあに、つまらない迷信でございますがね。あの島には、むかし鬼が住んでいたので、その鬼のたましいが今でも島の中にのこっていて、あの島へあがったものは、おそろしいめにあうというのでございます。ハハハ……、このへんの漁師なんて、まるで子どもみたいなもので、それをすっかりほんきにしているものですから……。」
そういうわけで、船をやとうのは、なかなかめんどうでしたが、きまりの船賃の三倍のお礼をするからといって、やっとひとりの年よりの漁師をしょうちさせて、その漁師の持っている発動機のついた和船わせんで、岩屋島へわたしてもらうことにしました。
海岸に石をつみかさねた小さなさん橋のようなものがあって、四人はそこから船に乗りました。
船のまん中のしきりに、むしろがしいてあって、四人がそこへすわるといっぱいになってしまうような、小さな船でしたが、でも船のうしろのほうに、ちゃんと発動機がついていて、漁師のじいさんはろをこぐのではなくて、まるで自動車の運転手のように、その発動機を運転するのでした。
ポンポンポンポンとはげしい音をたてて、船はみるみる海岸をはなれていきました。風のない静かな日でしたが、それでも、波がないわけではなく、船がブランコに乗ったように、気持ちよくゆれるのです。
うしろを見ますと、長島の町が、だんだん小さくなっていきます。そして前のほうは、見わたすかぎり、はてしもない大海原です。
はるかむこうの水平線が、右のはしから左のはしへ、グウッと弓のように、丸くなって見えています。その水平線を見わたしていますと、地球がまるいものだということが、はっきりわかるような気がします。
「やあ、すてきだなあ。鎌倉かまくらの海なんかよりずっといいや。あ、見たまえ、小林君、あんな遠くを汽船が走っている、まるでおもちゃみたいだねえ。」
「不二夫君、ほら、下を見てごらん。底まで見えるようだよ。ぼく、こんなきれいな海、見たことがないよ。あら、なんだか大きな魚がおよいでいった。サメかしら。」
不二夫君と小林少年とは、長い汽車の旅で、すっかりなかよしになっていました。ふたりは船べりにもたれて、青々としたきれいな水に、手を入れて、手の先から白い波が立つのを、おもしろがってながめるのでした。
二十分ほども走りますと、船は一つのみさきをまわって、すっかり入り海の外へ出てしまいました。
「あ、あれだ、あれだ、ねえ、きみ、あの島が鬼ガ島なんだろう。」
不二夫君がまっさきに見つけて、漁師のじいさんにたずねました。
「そうじゃ、ぼっちゃん。あれが鬼ガ島だよ。」
「やあ、そっくりだね。鬼の面を海にうかしたようだって、ほんとうだね。あれが角つの、あれが鼻、あれが口、あ、口からきばが出てらあ。」
不二夫君は、むちゅうになってさけぶのでした。
「なるほど鬼の面だね。こりゃふしぎだ。」
宮瀬氏も、手をひたいにあてて、はるかの島をながめながら、感じいったようにいいました。
いかにも、それはきみょうな、ものすごい形の島でした。島の上には少し青い森も見えますが、大部分は、かどばった灰色の岩でできていて、その岩がさまざまの形をして、にょきにょきとそばだっていますので、全体がなんとなく鬼の面のように見えるのです。鬼の面を空にむけて、海にうかべたように見えるのです。
「やあ、波がひどくなってきた。」
不二夫君が、船の中に立って、ふらふらしながらさけびました。入り海を出たものですから、にわかに波が高くなったのです。見れば、岩屋島のまわりにも、まっ白な波が、鬼の面をかみくだこうとでもするように、たえまなく、おそいかかっています。
船は、波がくるたびに、へさきをあげたりさげたりしながら、ポンポンポンポンと発動機の音をたてて、勇ましく進んでいきます。船が進むにつれて、鬼の面の岩屋島は、みるみる形を大きくしながら、こちらへ近づいてくるのです。
「きみ、獅子岩って、どれなの。」
不二夫君がたずねますと、漁師は、もう百メートルほどに近づいた島の上を指さして、答えました。
「獅子岩はまだじゃが、烏帽子岩が見える。ほら、あの鬼の角みたいな、たけの高い岩が、烏帽子岩じゃ。」
いわれてみますと、いかにも、その岩は烏帽子という昔のかんむりとそっくりの形をしています。
「それから、烏帽子岩のとなりに立っている、みじかいほうの角が、カラス岩。のう、カラスがくちばしを、あーんとあいているじゃろうが。」
なるほど、その岩は、カラスの頭の形をしています。くちばしのようにつき出た岩が、二つにわかれて、さもカラスが鳴いているように見えるのです。
船と島とのあいだは、五十メートル、三十メートル、二十メートルとせばまっていきます。それにつれて、おそろしい岩のかたまりが、おっかぶさるように、目の前に近づいてきました。
「お客さん、やっぱり、この島へあがりなさるのかね。」
漁師のじいさんは、明智探偵と宮瀬氏の顔を見くらべながら、なるべくならば、このまま帰ってもらいたいものだ、といわぬばかりに、声をかけました。
「むろん、あがるよ。そのために来たんじゃないか。」
明智が答えました。
「悪いことはいわぬ。やめたらどうですかね。何年というもの、この島へは、ひとりもあがった者はないのだからね。この島には鬼のたましいがこもっておりますのじゃ。ぼっちゃんなんぞつれてあがっては、どんなことが起こるかもわからんでのう。」
漁師は島へつくのを一分でもおくらせたいらしく、船の速力をぐっとひくめて、まじめな顔で意見をするのでした。
「なあに、だいじょうぶだよ。この子どもたちは、からだは小さいけれど、きもったまは大きいのだからね。化けものなんかにびくびくしやしないよ。とにかく、約束したとおり、島へつけてくれたまえ。」
明智がきびしい調子でいいますと、じいさんはしかたなく、船を島の岸に進めました。
岸といっても、砂浜なんかがあるわけでなく、トンネルみたいな岩の穴の下をくぐって、岩でかこまれた池のような、小さな湾の中へはいりますと、一方に、岩が段々になっているところがあって、船はその前につきました。
「ぼくたちは、この島でしばらく遊ぶつもりだから、きみはここで待っていてくれてもいいし、ここにいるのがいやだったら、一度かえって、二時間ほどしてから、ぼくたちを、むかえに来てくれてもいい、どちらでもいいようにしたまえ。」
明智がいいますと、漁師のじいさんは、
「それじゃ、一度かえって、あとからおむかえに来ますでのう。こんなとこに、ひとりぼっちでおられるもんじゃない。」
と、つぶやきながら、大急ぎで、船のむきをかえて、もと来たほうへ帰っていきました。年よりのくせに鬼のたましいとやらが、よくよくこわいのでしょう。
「あのじいさん、おくびょうものだね。今にもそのへんから、化けものでも出るように、びくびくしていたよ。」
不二夫君が、おかしそうにいいました。
「ぼくたちは鬼ガ島たいじの桃太郎なんだから、鬼が出てくれたほうがおもしろいと思っているのにねえ。」
小林君も、あいづちをうつのでした。
それから、四人の探検隊は岩の段々をのぼって、いよいよ鬼ガ島に上陸しました。
岩の切り岸をのぼると平地に出ました。そこは岩ではなくて土になっていて、森のように、木がはえしげっていましたが、一行は、何年という長いあいだ、人の通ったあともない、森の中の落ち葉をふんで、ぐんぐん、烏帽子岩の方角へ進んでいきました。
森を出はなれますと、そのむこうは、ごつごつした岩ばかりです。小林少年と不二夫君は、手を引きあって、その岩のあいだをかけだしていきましたが、壁のようになった岩の切れめのところで、びっくりしたように、立ちどまってしまいました。
「あ、あれだ、あれが獅子岩だ。」
「そうだね、神社においてある石の獅子とそっくりだね。」
それは五メートルほどもある、獅子の顔でした。さかだったたてがみのようなものもあります。耳らしいものもあります。目のところが大きくくぼんで、その下に、ガッとひらいた口があります。
ふつうの岩が何千年というあいだ、雨風にさらされて、いつのまにかこんな形になったのでしょうが、それにしても、なんというふしぎな岩でしょう。ほんとうに獅子の顔です。まるで生きているようです。そばへよったら、その大きな口で、がぶっと食いつきそうに見えるではありませんか。
さて、読者諸君、四人の探検隊は、いよいよ目的の場所についたのです。むこうには烏帽子岩とカラス岩とがそびえています。ここには獅子岩がおそろしい顔をもたげています。一目で三つの岩が見えるのです。
しかし、いったいこの三つの岩のどこから、「東へ三十尺」はかるのでしょう。どの岩もあまり大きくて、そのもとになるところが、どこなのか、まるでけんとうもつかぬではありませんか。明智探偵は、このなぞをどんなふうにとくのでしょう。
四人はしばらくのあいだ、三つの岩のみごとさに、金塊のことなどすっかりわすれてしまって、ただ見とれているばかりでしたが、やがて、宮瀬氏がやっと暗号のことを思いだして、明智に話しかけました。
「見たところ、烏帽子岩と獅子岩とは五十メートルもはなれているようですが、この獅子がどうして、あの烏帽子をかぶることができるのでしょう。暗号には『獅子が烏帽子をかぶる時』とありますが、大地震でも起こらないかぎり、この二つの岩がかさなりあうことなんて、思いもおよばないじゃありませんか。明智さん。あの暗号をどうお考えになります。」
「ぼくも今それを考えていたところです。あの暗号は、この獅子岩がほんとうにあの烏帽子岩をかぶるという意味じゃなく、何かもっと別のことだと思うのです。もう少ししらべてみましょう。」
さすがの明智探偵にも、それだけがまだわからないのでした。
それから、四人はごつごつした岩の道を歩いて、獅子岩、烏帽子岩、カラス岩の順に、一つずつそばへよってしらべてまわりました。近よって見ますと、三つとも見あげるような大岩で、なんだかおそろしくなるようでしたが、不二夫君は大喜びで、小林少年をさそって、岩の上へよじのぼって、下にいるふたりのおとなに「ばんざい。」などとさけんでみせたりするのでした。
明智探偵はそれらの岩を、一つ一つたんねんにしらべているようすでしたが、べつにこれという発見もないらしく、四人はまた、もとの獅子岩のそばへもどってきました。
島へ上陸したのは午後三時ごろでしたが、岩を見まわっているうちに、いつのまにか時間がたって、もう五時をすぎていました。太陽は西のほうの海面に近づいて、だんだん形が大きくなり、赤い色にそまっていくのでした。
不二夫少年は、またしても獅子岩の上によじのぼって、ひとりではしゃいでいましたが、とつぜん大きな声でさけびました。
「やあ、すてきすてき、獅子の形があんなにのびちゃった。小林君、ごらん、獅子の頭がもう少しでむこうの烏帽子岩にとどきそうだよ。ぼくの影もあんなに長くなっちゃった。ほらほら……。」
さけびながら、不二夫君は獅子岩の上で手をふってみせましたが、その手の影が、ずうっとむこうの岩のはだにうつって、ひらひらと動いているのです。
不二夫君のいうとおり、獅子岩の影は、今にも烏帽子岩にとどきそうになっています。下に立っている三人は、不二夫君に教えられてその影をじっと見つめていましたが、やがて、明智探偵がハッと何ごとかを気づいて、うれしそうな声で宮瀬氏に話しかけました。
「宮瀬さん、わかりました。暗号のなぞがとけたのです。不二夫君のおかげですよ。今の不二夫君のことばで、すっかりなぞがとけたのです。」
「エッ、不二夫のことばで? わたしにはさっぱりわかりませんが……。」
宮瀬氏はびっくりしたように、名探偵の顔を見つめました。
「ごらんなさい。不二夫君に教えられて気がついたのですが、獅子岩の影があんなにのびて、今にも烏帽子岩に、とどきそうになっているじゃありませんか。もう少し太陽がさがれば、影はもっとのびて、ちょうど獅子の頭が烏帽子岩の下のほうにうつるでしょう。すると、獅子が烏帽子をかぶるわけじゃあありませんか。暗号の意味は、獅子の頭の影が、烏帽子岩にうつって、ちょうど、烏帽子をかぶったように見える時ということだったのですよ。」
「ああ、なるほど、そうだ、そうだ、そうにちがいありません。やっぱりその場へ来てみなければわからないものですね。まさか影とは気がつかなかった。
不二夫、おまえは、たいへんなてがらをたてたんだよ。おまえがなにげなくいったことばから、明智先生が暗号をといてくださったのだよ。」
宮瀬氏はうれしまぎれに、岩の上の不二夫君に、大声に呼びかけるのでした。
「もう少しです。もう少し待てば、獅子が烏帽子をかぶった形になります。ちょうどそのときに、あのカラス岩の頭の影がどのへんにさしているか、それを見さだめなければなりません。その頭の影の頂上から、東へ三十尺はかり、それから北へ六十尺はかればいいのです。そこに戸のようになった岩があるわけです。」
いっているうちに、太陽はみるみる西の水平線にちかづいて、獅子岩の影は、だんだんのびていきます。
「さあ、みんな、あの烏帽子岩の前へ行って、獅子が烏帽子をかぶるのを見ていてください。ぼくはカラス岩のむこうへ行って、カラスの頭の影がどこにさすか見さだめます。」
明智のさしずで、宮瀬氏と不二夫君と小林少年の三人は、烏帽子岩のほうへかけだしました。明智はただひとり、カラス岩のむこうへ走っていきます。
しばらくすると、烏帽子岩の前から小林少年のかんだかい声がひびきました。
「先生、今です。ちょうど、獅子が烏帽子をかぶった形になりました。」
すると、カラス岩のずっとむこうから、明智の声が答えました。
「ようし、それじゃあ、みんなこっちへ来てくださあーい。」
三人が大急ぎでかけつけますと、明智はカラス岩の頭の影をふんで、にこにこ笑いながら立っていました。
「さあ、小林君、きみのリュックサックから、巻尺をだしたまえ。いま、ぼくの立っているところから、東へ三十尺はかるのだ。」
小林君が手ばやく巻尺を取りだしますと、明智は、その巻尺のはしを、くつでふんで動かないようにして、それから、時計のくさりについている磁石を見ながら、右手を上げて、東の方角をさししめしました。
小林君はその指のさししめす方角へ、巻尺をのばして歩いていき、ちょうど、三十尺(九・一メートル)のところで立ちどまりました。
「ここが三十尺です。」
「よし。それじゃ、そこに動かないで立っているんだよ。」
明智がそういって、はしをふんでいた足をのけますと、小林君は巻尺のハンドルをまわして、もとのように巻きました。
明智は大急ぎで小林君の立っているところへ行き、また巻尺のはしをふんで、こんどは、北の方角をさししめします。すると、小林君は巻尺をのばしながら北へ北へと歩いていきましたが、そのへんも、やはり、でこぼこになった岩ばかりの道で、それが急な坂になって、谷のようなくぼ地へくだっているのです。
「ここがちょうど六十尺(十八・二メートル)です。」
やがて、そのくぼ地の底から、小林君の声が聞こえてきました。
「何かあるかい?」
明智がたずねますと、
「ええ、みょうなほら穴みたいなものがあります。」
という答えです。
そこで、三人は急いで、小林君の立っているところへ行ってみましたが、いかにも、その谷底のようになった一方の岩はだに、大きなほら穴の口があいているのです。
明智をさきに立てて、一同がそのほら穴の中へはいってみますと、五メートルほどで行きどまりになっていることがわかりました。
あさい穴ですけれど、それでも、奥のほうはよく日がささないので、うすぐらくなっていて、目がなれるまでは、何があるのかよくわかりませんでした。
明智はそのほら穴の中を、あちこちとしらべましたが、やがて、何か発見したらしく、
「あ、これだ、これだ、宮瀬さん、岩の戸を見つけましたよ。」
とさけびました。
みなは、ハッとして、いきなりそこへかけよりました。
「ごらんなさい。この大きな岩がふたのようになって、穴の奥へ行く道をふさいでいるのです。ちょっと見たのではわからないけれど、この岩はここへはめこんであるのですよ。
たしかに穴をかくすために、岩でふたをしたのです。暗号にある『岩戸』というのは、この岩のことにちがいありません。」
「なるほど、そうらしいですね。すると、この岩の奥に深い穴があるのでしょうか。」
「たぶんそうだと思います。ひとりではとても動かせませんが、みんなで力を合わせたら、この岩を取りのけることができるかもしれません。ひとつやってみようじゃありませんか。」
そこで、四人は力を合わせて、エンヤエンヤとその大岩をゆり動かしはじめました。
十分ほどもかかって、やっと大岩を取りのけてみますと、あんのじょう、その奥に深いほら穴があることがわかりました。明智探偵はリュックサックから懐中電灯を取りだして、穴の中をてらしてみましたが、人間ひとりやっと通れるほどのせまい穴が、ずっと奥のほうまでつづいていて、行きどまりを見とどけることはできませんでした。
「おそろしく深い穴ですよ。むろん人間がほった穴じゃない。岩の中の石灰分がとけて、自然にできた穴ですよ。それだけに、奥がどんなふうになっているか、けんとうもつかないわけです。
小林君、きみのリュックサックにろうそくが入れてあったね。そいつをだして火をつけてくれたまえ。穴の中に悪いガスがたまっているといけないから、ろうそくを先に立ててはいってみることにしよう。酸素がすくなくなれば火が消えるわけだからね。地の底の深い穴を探検するときは、かならず、ろうそくを持っているものだよ。」
明智はふたりの少年のために説明しながら、小林君の火をつけたろうそくを受けとって、さきに立って、まっくらな穴の中へふみこんでいきました。二番めには小林君が、先生からわたされた懐中電灯を持って、そのつぎに不二夫君、いちばんうしろが宮瀬氏という順で、おずおず明智のあとにつづきました。
穴はうねうねとまがって、だんだんくだり坂になりながら、どこまでもつづいていましたが、やがて二十メートルほども進んだころ、道が二つにわかれているところへ出ました。
明智は三人をそこへ待たせておいて、両方の穴の奥のほうをしらべて帰ってきましたが、こまったような顔をして宮瀬氏にいうのでした。
「このままはいっていくのは、危険ですよ。このほら穴は枝道がいくつもあって、迷路のようになっているのです。あまり奥へ進んで、帰れなくなってはたいへんです。それに、もう日も暮れるでしょうし、だいいちみんな、おなかがすいてきたでしょう。一度、宿へ帰って、あしたゆっくり出なおしてくるほうがいいでしょう。こんどはおべんとうなんかも、じゅうぶん用意してくるんですね。」
「ええ、わたしもそのほうがいいと思います。それにあの漁師のじいさんも、海岸で待ちかねているでしょうからね。しかし、わたしの先祖は、じつに用心ぶかいかくし方をしたものですね。岩の戸を開けば、すぐにも金塊が手にはいるのかと思ったら、まだその奥があるんですからね。しかもそれが地の底の迷路というのでは、これからがたいへんですよ。」
宮瀬氏は、先祖の用心ぶかさに感じいったようにいいました。
「そうでしょう。そのころにしても百万両に近い大金ですからね。ご先祖が、用心のうえにも用心なさったのも、むりはありませんよ。」
明智は、宝さがしがむずかしくなったのを、かえって喜ぶようなおももちで答えました。
それから、また四人がかりで、大岩をもとのところへもどして、穴の入り口がわからないようにしておいて、そのまま、島の船つき場へ引きかえしましたが、漁師のじいさんは、もうちゃんと、そこに待ちかまえて、ぶじに一同を長島の町に送りとどけました。
さて、そのあくる朝です。四人は宿屋でぐっすりねむって、ひじょうな元気で目をさましました。きょうこそ、いよいよ大金塊を手に入れることができるのかと思うと、宮瀬氏はもちろん、明智探偵も、ふたりの少年も、心がおどるような気持ちです。
土地の人のこわがる鬼ガ島へ、二日もつづけて遊びに行くのを、みょうにうたがわれてはいけませんので、宿屋へは、あの島のめずらしい鉱物を見つけたから、それを採集に行くのだといって、きのうの漁師のじいさんを、むりにたのんでもらって、午前九時ごろ、長島町の海岸を出発しました。
きょうは、にぎりめしだとか、パンだとか、うんとおべんとうを用意して、みんなのリュックサックにつめてあるのです。地の底の迷路の中で、道にまよって、二日ぐらいはだいじょうぶおなかがすかないように、できるだけ食糧品をしいれたのです。それに、みんなの水筒にはお湯がいっぱいはいっています。
島につきますと、夕方、またむかえにくるようにといって、じいさんを帰し、四人は大急ぎできのうのほら穴にたどりつきました。大岩を取りのけて、東京からリュックサックに入れて持ってきた、長い細引ほそびきのはしを、ほら穴の入り口の岩かどにくくりつけ、その細引きをつたって中へはいることにしました。まんいち迷路にまよったときの用心です。
きのうのように、明智がろうそくを持って先に立ち、小林君と不二夫少年とは懐中電灯をてらし、宮瀬氏は登山用のピッケルをにぎりしめて、あたりに気をくばり、用心しながらほら穴の中へはいっていきました。
そのとき、四人がもう少し注意ぶかく、島ぜんたいをしらべておけばよかったのです。そうすれば、あんなおそろしいめにあわなくてすんだかもしれません。
でも、岩屋島はまったく無人島かと思いこんでいたものですから、さすがの明智探偵も、ついゆだんをして、そこまでは気がつかなかったのです。
ごらんなさい。何も知らないで四人がほら穴へはいっていくのを、あのカラス岩の岩かげから、そっとのぞいているやつがあるではありませんか。
せびろの洋服を着てゲートルをつけて、鳥打ち帽をまぶかくかぶって顔をかくすようにして、じっとほら穴の入り口を見つめています。
むろんこのへんの人ではありません。都会から来た旅人です。その男は、いったいどこからこの島へ上陸したのでしょう。もし、けさ、長島町から島へわたったのだとすれば、せまい町のことですから、漁師のじいさんが知っているはずです。ところが、じいさんはそんな客があったということを、一度もしゃべらなかったではありませんか。
なんにしても、あやしい人物です。この島のどこかに、人知れずそんな人物が住んでいたのでしょうか。それとも、もしかしたら、土地の人がこわがっている、あの鬼のたましいとやらが、人間の姿にばけて、島をあらしにやってきた四人のものに、あだをしようとしているのではないでしょうか。
四人の探検隊の行くてには、何かしら、おそろしい運命が待ちうけているような気がします。
地の底で、大金塊を見つけるまえに、思いもよらぬ大事件が起こるのではないでしょうか。
ほら穴の入り口から五、六メートルのあいだは、ひじょうに道がせまくて、四人は腹ばいになって、やっとくぐりぬけましたが、そこを出はなれますと、ちょっと広くなったところがあって、道が二つにわかれていました。
「まず右のほうへはいってみよう。こちらのほうが広いようだから。」
明智はそういって、右のほうのほら穴へぐんぐんはいっていきました。そのへんはもう、はわなくてもじゅうぶん立って歩けるのです。
しばらく行きますと、また枝道に出くわしましたが、明智はやはり右の道をとって進みました。行っても行っても、ほら穴はくねくねとまがりながら、はてしもなくつづいていました。五、六メートルごとに枝道があるうえに急な坂になって、地の底へ地の底へとくだっていくかと思うと、またのぼり道になっているというふうで、五、六十メートルも進みますと、いま自分たちがどのへんにいるんだか、まるでけんとうもつかなくなってしまいました。
「おそろしく深い穴ですね。いったいどこに行きどまりがあるのでしょう。この島の地の下ぜんたいが、こんなほら穴になっているのじゃないでしょうか。それにしても、わたしの先祖は、じつにむずかしい場所へ宝ものをかくしたもんですね。これほどにしなくてもよさそうに思われますが。」
宮瀬氏が、あきれはてたようにつぶやきました。
「いや、なにしろ、ばくだいな宝ものですからね。ご先祖がここまで用心ぶかくなさったのも、もっともですよ。一生はたらきづめにはたらいても、ふつうのものには、とても手にはいらないほどの大きな金額です。それをさがすのに、これぐらいの苦労をするのはあたりまえですよ。」
明智は笑いながら、そんなことをいって、みんなをはげますのでした。
それから、また、すこし行きますと、肩にすれすれであった両がわの岩が見えなくなって、地の底の広っぱのようなところへ出ました。懐中電灯でてらしてみても、むこうがわの岩がはっきり見えないほど、がらんとした大きなほら穴なのです。
明智はやはり右のほうへ、岩の壁をつたうようにして、進んでいきましたが、しばらくすると、とつぜん、いちばんあとから歩いていた宮瀬氏が、アッとおそろしいさけび声をたてました。すると、その声が四方の岩壁にこだまして、あちらからも、こちらからも、アッ、アッ、アッと、同じさけび声が、つづけざまに聞こえてきました。
「どうなさったのです。宮瀬さんですか。」
いちばんさきの明智が大きな声でたずねますと、その声もやはりこだまになって、同じことばが、やみの中から、つづけざまに聞こえてきました。
小林少年はまえに、ある事件で、こんな経験がありますから、べつにおどろきませんでしたが、不二夫君は、こだまというものをはじめて聞いたものですから、きみ悪そうに、まっさおになってふるえあがってしまいました。
広いほら穴のほうぼうに、あやしいやつがかくれていて、人のまねをしているのではないかと思うと、こわくてしかたがないのです。それにしても、不二夫君のおとうさんは、いったいどうなったのでしょう。なぜ、あんなおそろしいさけび声をおたてになったのでしょう。不二夫君は大急ぎで、懐中電灯でおとうさんのほうをてらしてみました。
宮瀬氏は、もうよほど小さくなった、れいの細引きの玉を、両手で持って、地面にはっている細引きを、しきりと引っぱっているのです。すると、引くにつれて、細引きはいくらでもこちらへもどってきて、まもなく、すっかり宮瀬氏の手もとに、たぐりよせられてしまいました。
岩かどにむすびつけてあったのがとれたのでしょうか。それとも、どこかとちゅうで切れたのでしょうか。たぐりよせられた細引きの分量があまり多くないのを見ますと、どうやらとちゅうで切れてしまったらしいのです。
さあ、たいへんです。たった一つの道しるべのひもがなくなったのです。悪くすると、四人はもう入り口へも出られないかもしれません。地の底の迷路の中を、まい子のように、いつまでもぐるぐる歩きまわっていなければならないかもしれません。
四人はそこに立ちどまったまま、しばらくだれも口をきくものもありませんでした。何かしら行く手におそろしい運命が待ちかまえているような気がして、ひどくきみ悪く思われたのです。
しばらくして、明智が、しずかに口を切りました。
「こういうときにあわててはいけない。これからどうすればいいか、ゆっくり考えるのです。むろん、われわれはこれより奥へはいることは、一時中止しなければなりません。どうにかして、その細引きの切れた場所までもどるのです。どこで切れているかをさがすのです。それさえ見つければ、そこにのこっている細引きをつたって、入り口へ出ることができるのですからね。
さあ、みんなで地面をさがしながら、もと来た道を帰りましょう。小林君も不二夫さんも、よく地面を見て歩くんだよ。」
それから、四人は心おぼえの道を、もとのほうへもどりながら、熱心に地面をさがしました。みんな腰をかがめて、地面に顔を近づけて、何か小さいおとしものでもさがすようなかっこうです。
宮瀬氏は不二夫君の持っていた懐中電灯を取って、さきに立って進みます。つづいて、ろうそくを持つ明智探偵、少しはなれて、小林少年と不二夫君とが手をつないで、小林君の懐中電灯で地面をてらしながら、ゆっくり歩いていきました。
広いほら穴から、もとのせまい道にはいって、だんだん進んでいきましたが、みな仲間のことはわすれて、むちゅうになって地面ばかり見つめて歩いているものですから、いつのまにか、ふたりの少年は、宮瀬氏と明智探偵から、ひどくはなれてしまいました。
「おや、おとうさんや明智先生はどこだろう。へんだね、むこうのほうがまっくらになってしまったぜ。」
不二夫君がびっくりしたようにさけびました。見ると、さいぜんまで、むこうのほうにちらちらしていた、宮瀬氏の懐中電灯も、明智探偵のろうそくも、いつのまにか見えなくなって、前もうしろも、ただ墨を流したようなやみばかりなのです。
「おとうさあん!」
不二夫君は、今にも泣きだしそうな声で、さけびました。すると、その声がワーンというような音をたてて、ほら穴のむこうのほうへひびいていきましたが、耳をすましますと、どこか遠くのほうから、
「おうい、不二夫! どこにいるんだあ。早くこちらへおいで!」
という宮瀬氏の声が、かすかに聞こえてきました。
「あ、あっちのほうだ。」
ふたりはその声の聞こえてきた方角へ、大急ぎでかけだしました。ところが、行っても、行っても、懐中電灯の光も、ろうそくの火も見えないのです。
むちゅうになって走っているうちに、いくつも枝道になったところを通りすぎましたが、あわてているので、つい反対のほうへ、反対のほうへとまがってきたのかもしれません。
「おとうさあん!」
「明智せんせえい!」
ふたりは声をそろえて、呼ばわりました。しかし、もうどこからも返事がないのです。返ってくるのは、自分たちの声のこだまばかりです。
「へんだね、道をとりちがえたのかしら。うしろへもどってみようか。」
「うん、そうしよう。」
ふたりはもう声の調子がかわっていました。なんだか口の中がひどくかわいてしまって、胸がおそろしい早さで波うっています。このままおとなたちにあえなかったら、どうしようかと思うと、おそろしさに気もくるいそうです。
ふたりは手を取りあったまま、また、うしろのほうへかけだしました。しかし、いくら行っても、光は見えないのです。いくらさけんでも、宮瀬氏の声も、明智探偵の声も聞こえてはこないのです。
あわてればあわてるほど、みょうな枝道へはいりこんでしまって、しまいには、どちらが前なのか、どちらがあとなのか、けんとうもつかなくなってしまいました。
「おとうさあん!」
「せんせえい!」
のどがいたくなるほどさけんでは走り、またさけんでは走っていましたが、そのうちに、小林君は岩かどにつまずいて、アッと思うまに、地面にたおれてしまいました。そのいきおいに、手を引きあっていた不二夫君も、小林君にかさなるようにたおれました。
「だいじょうぶかい。けがしなかった?」
上になった不二夫君が、まず起きあがって、小林君を助けおこしながら、心配そうにたずねました。
「うん、だいじょうぶ、少し、ひざをすりむいたくらいのもんだよ。」
小林君はいたさをこらえて、やっと立ちあがりましたが、さて前へ進もうとしますと、急にめくらにでもなってしまったように、道が少しも見えないのです。今まで道をてらしていた懐中電灯の光が消えてしまっているのです。
おやっ、と思いながら、たおれてもしっかりにぎりしめていた、懐中電灯をふり動かしてみましたが、どうしたのか少しも光が出ないのです。スイッチをカチカチやったり、ねじをしめつけたりしてみても、どうしてもつかないのです。
「懐中電灯をおっことしちゃったの。」
不二夫君の声が、心ぼそそうにたずねました。
「いや、ちゃんと持っているんだけど、つかないんだよ。今、岩かどにぶつけたから、豆電球がだめになったのかもしれない。」
小林君も泣きだしそうなようすです。
「かしてごらん、ぼくがやってみるから。」
不二夫君はそういって、手さぐりで、懐中電灯を受けとって、いろいろやってみましたが、やっぱりだめでした。まだ電池がつきるはずがありませんから、電球のなかの線が切れたのにちがいありません。
「ああ、いいことがある。ぼくのリュックサックの中に、まだろうそくがはいっているんだよ。」
小林君はそれを思いだして、すくわれたようにさけびました。
そして、あわててろうそくを取りだし、マッチをすって火をつけました。すると、赤ちゃけた光が、ちろちろとまたたきながら、両がわのおそろしい岩はだを照らしだすのでした。
ろうそくの光で、小林少年と不二夫君の顔が、やみの中にボウッとうきあがりましたが、赤い光があごの下のほうをてらしているので、なんだか見たこともないようなきみの悪い顔に見えるのでした。
「きみ、おばけみたいな顔だよ。」
「きみだって、そうだよ。」
ふたりはそんなことをいって、むりに笑おうとしましたが、笑っている下から、ゾウッとおそろしさがこみあげてくるのでした。
二少年はとうとう、地の底のはても知れぬ迷路の中で、まい子になってしまいました。宮瀬氏と明智探偵のほうでも、きっとふたりをさがしているのでしょうが、うまく出あうことができるでしょうか。もしかしたら、四人が出あわないさきに、何かしら、もっともっとおそろしいことが起こるのではないでしょうか。
ふたりは、もう、どちらへ進んでいいのだか、さっぱり、けんとうがつかなくなってしまいましたが、じっと立ちどまっていては、なお、おそろしい気がしますので、手を引きあって、ともかく歩きだすことにしました。
そして、「せんせえい。」「おとうさあん。」と声をかぎりにさけびながら、無我夢中で、枝道から枝道へとさまよい歩きました。
しかし、歩いても歩いても、入り口には出られないのです。入り口とは反対の奥のほうへ奥のほうへと歩いていたのかもしれません。それとも、迷路のことですから、同じ道をいくたびとなく、ぐるぐるまわり歩いていたのかもしれません。
そのうちに、はじめは走るようにしていたふたりの足が、だんだんのろくなってきました。ことに不二夫君のほうは、ひどくつかれているらしく、なんどとなく岩かどにつまずいて、ふらふらところびそうになるのです。
「きみ、こんなにむやみに歩いていたって、なんにもなりゃしないよ。すこし休んで、よく考えてみようじゃないか。」
さすがに年上の小林君は、そこへ気がついて、不二夫君を引きとめました。
見まわしますと、ちょうどそこは、小部屋のように広くなった場所で、一方のすみに出っぱった岩がありましたので、ふたりは、地面にろうそくを立てておいて、その岩の上に、肩をならべて腰かけました。
「ぼく、すっかりのどがかわいちゃった。そして、おなかもぺこぺこなんだよ。ここでおべんとうをたべようじゃないか。こんなときにはあわてたってしかたがない。おちつかなくっちゃだめだよ。」
小林君は明智探偵の口まねをして、わざとなんでもないという顔をして、年下の不二夫君の気分を引きたてようとしました。
「ぼく、おなかなんかすかないや。それより、早くおとうさんにあいたいなあ。」
不二夫君は、おそろしさに、おべんとうどころではないのでした。
「なあに、おちついて考えれば、うまく出口が見つかるかもしれないよ。びくびくすることはないよ。さあ、きみもたべたまえ。ほら穴の中で、べんとうをたべるなんておもしろいじゃないか。あとでみんなに話したら、きっとぼくたちの勇気におどろくよ。」
小林君は、そんなことをいいながら、水筒の水をのみ、リュックサックから竹の皮づつみを取りだして、大きなにぎりめしを、おいしそうにたべはじめました。
さすがは明智探偵の名助手といわれるだけあって、小林君の大胆不敵には感心のほかありません。人は、ひじょうに苦しいめや、おそろしいめにあったとき、ほんとうのねうちがわかるものです。小林君のえらさが、地の底のくらやみの中で、はっきりあらわれてきました。
不二夫君も小林少年にはげまされて、少しずつ元気をとりもどしました。そして、小林君がおいしそうに、にぎりめしをたべているのを見ると、なんだか、にわかにおなかがすいてきましたので、不二夫君もまねをして、リュックサックから、竹の皮づつみを取りだす気になりました。
ふたりは、その岩の上に腰かけたまま、たちまちおべんとうをたいらげてしまいました。
そして、水筒の水をおいしそうに、ゴクゴクとのむのでした。
ところが、ちょうどふたりが水筒の水をのんでいるときに、なんだかみょうな音が聞こえてきました。ゴボゴボと泉がわき出すような音です。水筒の水の音ではありません。もっとずっと大きな音で、遠くから聞こえてくるのです。
「きみ、あれ聞こえる? なんだろう。へんな音だね。」
ふたりは顔を見あわせて、耳をすましました。
すると、ゴボゴボという音はだんだん大きくなって、しまいにドーッという地ひびきさえくわわってきました。
「地震じゃないかしら?」
「いや、地震なら、ぼくたちのからだがゆれるはずだよ。地震じゃないよ。」
「それじゃ、なんだろう。あ、だんだんひどくなってくる。ぼくこわい!」
不二夫君は、思わず小林少年にしがみつきました。
するとそのとき、地ひびきの音が、とつぜんかみなりのようなすさまじい音にかわったかと思うと、そのほら穴の両方の入り口から、ドドドドドドと、まっ黒な怪物がころがりこんできました。いや、怪物ではありません。それは水だったのです。おそろしい分量の水が、ドッと一時にほら穴の中へおしよせてきたのです。ろうそくのぼんやりした光では、それがなんだかべらぼうに大きな、黒い怪物のように見えたのです。
しかし、それが目に見えたのも一瞬間でした。アッと思うまに、ひとかたまりの黒い怪物は、たちまちくずれて、サアッとほら穴じゅうにひろがり、地面に立ててあったろうそくの火を消してしまいました。そして腰かけていたふたりの足へ、はげしいいきおいで、おそいかかってきたのです。
何を考えるひまもなく、ふたりは岩の上にとびあがって、身をさけましたが、水はあとからあとからおそろしい物音をたてて、ほら穴の中へ流れこんでくるらしく、岩にぶっつかる音が、だんだん上のほうへのぼってくるような気がします。
ろうそくの火が消えてしまったので、まったくのやみです。やみの中に水のドドドド、ドドドドと流れこむつめたいしぶきが、足や手や顔にまで、はねかかるのが感じられるだけです。
ふたりは岩の上に立って、いつのまにか、しっかりだきあっていました。あまりのおそろしさに、ものをいうどころではありません。ただ両手に力をこめて、おたがいのからだを強く強くだきしめて、生きたここちもなく立ちつくすばかりでした。
水はぐんぐんいきおいをまして、みるみる水面を高めてきました。そして、一段高い岩の上に立っているふたりの足のところまで、おしよせてきました。
もう足が水の中につかっています。その氷のようにつめたい感じが、くつ下を通して、一センチずつ一センチずつ、上へ上へとのぼってくるのです。
そして、今はもう、ふたりのひざのあたりまで、水面が高くなってきました。その早さはおどろくばかりです。
「不二夫君、わかったよ。わかったよ。これは海の水なんだ。海が満みち潮しおになって、岩のすきまから流れこんできたのだよ。」
そんな中でも、小林君は頭をはたらかせていたのです。そして、このおびただしい水が、どこからはいってきたかということを、さとったのです。
小林君の考えたとおり、それは海の水でした。海には潮の満ちひきということがあって、満ち潮のときには、水面がずっと高くなるのです。その高くなった海の水が、どこか遠くの岩のすきまから、ドッと流れこんできたのです。
こんなにはげしく流れこんでくるのですから、ここはほら穴の中でも海面よりはずっと低い場所にちがいありません。低いといっても、いったいどのくらい低いのでしょう。もし二メートル、三メートルもひくいのだとしますと、いまに、水は、このほら穴の天井まで、いっぱいになってしまうはずです。
今はまだ、ひざまでしかありませんけれど、やがてその水面が、ももから腰、腰から腹、腹から胸と、だんだん高くなって、しまいには立っているわけにはいかず、この墨のようなくらやみの中で、ふたりは泳がなければならなくなるのではありますまいか。
でも、いくら泳いでも、このほら穴をぬけだすことはできません。両方の入り口は、水面よりはずっと低いところにあるのですし、たとえそこまでもぐってみたところで、とても水のない場所までおよぎつづけることはできません。
ああ、ふたりはいったいどうなるのでしょう。このおそろしいやみのほら穴の中で、おぼれ死んでしまう運命なのでしょうか。わたしたちは、あの勇敢な小林君や、かわいらしい不二夫君に、もう二度とあうことはできないのでしょうか。
聞こえるものは、ゴウゴウとうずまきかえす水の音ばかり。もうふたりは身動きすることさえできず、おたがいのからだをひしとだきあって、そこに立ちすくんでいるほかはありませんでした。
足の先におしよせた水が、たちまちのうちに、ひざの高さになり、やがて、パンツをぬらして腰のほうへのぼってくるのです。
もうそのころには、両方の穴からあふれ出る水の音は聞こえなくなっていましたが、そのほうがかえってぶきみです。音がしなくなったのは、水かさがまして、水面が流れこむ水よりも高くなったためで、けっして水がとまったのではありません。
やみの中の水面は、音もなく、刻一刻高くなって、だきあっているふたりにはいのぼってきました。腰はもうすっかり、水につかり、それからおなかがつめたくなり、はては、胸のへんまでも、ジャブジャブとまっ黒な水がのぼってきたのです。
からだがふらふらして、もう立っていることもできません。
「きみ、泳げる?」
小林少年が、のどのつまったような声で、不二夫君にたずねました。
「うん、およげるけど……だって、この穴の天井まで、水がいっぱいになったらどうするの? ぼくたち息ができなくなるじゃないか。」
それはもっともな心配でした。この小部屋のような場所は、天井の岩もかなり高いようでしたが、いくら高くても、もしそこが、ほかの海面よりも低いとすると、その穴は水でいっぱいになってしまうかもしれません。そうすれば、ふたりは息もできなくなって、おぼれ死ぬほかはないのです。
「不二夫君、明智先生はね、いつもぼくにこういって教えてくださるんだよ。もし、いのちがあぶないというようなめにあったら、たとえ助かるみこみがないと思っても、最後の一秒までがんばらなけりゃならないって。けっしてあきらめてしまわないで、なんでもいいから、少しでも助かるように、できるだけの力をふりしぼって、はたらくんだって。
そのことを、運命と戦うっていうんだよ。戦わないで、まけてしまっちゃ、だめなんだよ。だからね、きみ、失望しちゃいけないよ。最後までがんばるんだ、さあ、泳ごう。泳いで、泳いで、この水のやつと根こんくらべをしてやろうじゃないか。」
さすが明智探偵の名助手といわれるだけあって、小林君は、けなげな決心をして、自分より小さい不二夫君をはげますのでした。
不二夫君も、この力づよいことばに、少し元気をとりもどしました。そして、ふたりは手をつないだまま、まっくらなつめたい水の中で、立ち泳ぎをはじめました。
ただ浮いてさえいればいいのですから、べつにつかれるようなことはありませんでしたが、たださえ寒い地の底で水の中につかっているのですから、そのつめたさはひととおりではありません。さいわい春のおわりのあたたかい気候でしたから、海の水もそれほどつめたくはなかったのですが、もしこれが冬のさなかのできごとでしたら、ふたりは、たちまちこごえ死にをしてしまったにちがいありません。
「不二夫君、しっかりしたまえ。下っ腹に力を入れておちついているんだよ。こうして泳いでいるうちには海が引き潮になるよ。そうすれば、水が流れこまなくなるし、ここにたまった水も、岩のすきまから外へ流れだしてしまうにきまっているからね。ぼくらはただ、がんばっていればいいんだよ。」
小林君はやみの中で、しきりに不二夫君をはげましました。
「ぼく、めくらになったんじゃないかしら。ほんとうに、なんにも見えないんだもの。きみは何か見える?」
不二夫君は泳ぎながら、心ぼそそうにたずねました。
「ぼくだって、見えないよ。めくらって、こんなもんだろうね。」
ほんとうに、目というものがなくなってしまったのも同じことでした。ただ声が聞こえるのと、水のつめたさと、にぎりあっている、おたがいの手ざわりがあるばかりなのです。
みなさん、ちょっと目をつむって、このふたりのありさまを考えてごらんなさい。こんなさびしい、心ぼそい、おそろしい心持ちがまたとあるものでしょうか。
しばらくして、不二夫君が泣きだしそうな声でいいました。
「ねえ、まだ水がふえているんだろうか。」
「うん、まだ引き潮にはならないだろうね。ぼく、もぐって、しらべてみようか。」
小林君はあくまで元気でした。
「よしてよ、手をはなしちゃいやだよ。」
不二夫君は、このやみの中で、一度手をはなしたら、それっきり、小林君とはぐれてしまうような気がしたのです。
「だいじょうぶだよ。ちょっともぐってみるよ。」
小林君は、そういったかと思うと、にぎりあっていた手をはなして、ぐうんと水の底へしずんでいきました。
不二夫君は、その水音を聞いて、もう気が気ではありません。名を呼んだところで、水の中の小林君に聞こえるはずはありませんから、呼びたいのを、じっとがまんして、耳をすまして待っていました。わずか三、四十秒のあいだでしたが、それが不二夫君には、とても長く感じられたのです。
すると、ややしてから、ガバガバと水が動いて、ブルッと手で顔の水をふく音が聞こえました。そして、小林君の声がさけびました。
「わあ、深い。とてもふかいよ。だいじょうぶ二メートル以上あるよ。まだぐんぐん水が流れこんでいる。」
「え、まだ流れこんでいる?」
不二夫君はがっかりしてしまいました。いや、がっかりしたばかりではありません。さっきのことが、また心配になりはじめたのです。このほら穴の天井まで、水でいっぱいになって、息ができなくなるのではないかという、あのおそろしい考えが、ひしひしとよみがえってきたのです。
不二夫君が、そのことをいおうかいうまいかと、ためらっていますと、またしても、小林君が、びっくりするようなさけび声をたてました。
「あ、へんだな。ねえ、不二夫君、水が流れはじめたよ。ぼくらはどっかへ流されているんだよ。わからない? ほら、ぐんぐん流れているじゃないか。」
そういわれて、気をつけてみますと、いかにも、急に水が動きだしていることがわかりました。
「あ、ほんとだ、それじゃ、いよいよ引き潮になったのかしら。」
不二夫君も、大きな声でさけびました。
「そうじゃないよ。今ぼくがもぐって、しらべてきたばかりだもの。まだ水はおそろしいいきおいで流れこんでいるんだよ。へんだなあ。いったいどうしたんだろう。」
さすがの小林君も、このきみょうな水の動き方を、どう考えてよいのか、すこしもわかりませんでした。
なんとなく、うすきみが悪いのです。またしても、何か思いもよらぬおそろしいことが起こるのではないかと、心臓がドキドキするばかりです。
水の動き方はだんだんはげしくなってきました。たしかに一方にむかって流れているのです。おそろしいいきおいで流れているのです。ふたりはまた手を取りあって、流されまいと、ぎゃくに泳いでみましたが、だめでした。急流のような早い流れにさからうことはできません。
それは流れているというよりも、どこかへすいよせられているような感じでした。ほら穴の中の水が、四方から、ある一ヵ所にむかって、うずまきのようになって、すいよせられているのです。
いったいこれはどうしたというのでしょう。何物が、こんなおそろしい力で、水をすいよせているのでしょう。ふたりの少年は、べらぼうに大きなまっ黒な怪物を想像しないではいられませんでした。その怪物が大きな口を開いて、ほら穴の中の水を、ひとのみにしようとしている姿を思いうかべて、ほんとうにふるえあがってしまいました。
流れるといっても、わずか五メートル四方ぐらいのほら穴の中ですから、そこを一方にむかって流れていけば、たちまち岩の壁につきあたるはずです。
ところが、ふしぎなことに、ふたりはくらやみの中を、ぐんぐんとおし流されているのに、どうしたわけか、少しも岩にぶつからないのです。ほら穴がきゅうに広くなるはずはありませんし、じつにみょうなことが起こったものです。
ふたりはむがむちゅうでもがいていましたが、すると、手足が水の中で、何かかたいものにさわっているのに気がつきました。
小林君は、思わず水の中でよつんばいになって、それから、力をこめて立ちあがってみました。すると、これはどうでしょう。水の深さは、もものへんまでしかないことがわかりました。ちゃんと立っていられるのです。
「不二夫君、浅いよ。浅いよ。だいじょうぶだから立ってごらん。立てるんだから。」
その声にはげまされて、不二夫君も立ちあがりました。水はぐんぐん一方に流れていますけれど、足をさらわれるほどではありません。
立ったひょうしに、思わずそのへんを手さぐりしますと、両がわとも、手のとどくところに、岩の壁があることがわかりました。
「あ、わかった。これはぬけ穴なんだよ。こんな高いところに、岩のさけめができていたんだ。そこへ水が流れこんでいるんだよ。」
小林君がさけびました。
「そうだ。じゃ、ぼくらはたすかったんだね。」
不二夫君も、うれしそうな声をたてました。
ほら穴の天井に近いところに、思いもよらぬぬけ穴があって、ほら穴にあふれた水が、そこへ流れていたのです。水は、ふたりの少年をおぼれ死にさせないで、かえって、そのいのちをすくったのです。
しかし、まだ安心はできません。もしこのぬけ穴が、すぐ行きどまりになっているとすれば、やっぱり、そのうちには、水でいっぱいになってしまうかもしれないからです。
「あ、そうだ。こういうときの用意に、ぼくはマッチをだいじにとっておいたんだ、ねえ、不二夫君、ぼくはマッチをぬらさないように、ドロップのあきかんに入れて、腹巻きの中へしまっておいたのだよ。」
小林少年は、じまんそうにいって、ぬれた腹巻きからあきかんを取りだし、ポンと音をさせてそのふたを開きました。
シュッという音といっしょに、たちまち、目の前が昼のようにあかるくなりました。やみになれた目には一本のマッチの光が、おそろしく明かるく感じられたのです。
いそいで、あたりを見まわしますと、そのぬけ穴は、むこうのほうほどせまくなってはいますが、行きどまりではないことがわかりました。
「きみ、あっちへ行ってみよう。」
小林君は、もえきったマッチをすてて、穴の奥へ進んでいきます。不二夫君も、そのあとにしたがいました。
五メートルも、水の中をジャブジャブ進みますと、穴はずっとせまくなって、腰をかがめてやっと通れるほどでしたが、そのせまいところを、手さぐりで、また二メートルもはいっていきますと、とつぜん両がわの岩がなくなって、広い場所に出ました。
小林少年はそこで立ちどまって、もう一度マッチをすってみましたが、さいぜんのほら穴の倍もある、広い洞くつであることがわかりました。
「不二夫君、ぼくらは助かったよ。いくら海水がおしよせたって、この広いほら穴をいっぱいにすることはできないからね。」
見れば、水はやっと足首をかくすくらいに浅くなって、流れかたもずっとおそくなっているのです。
「やっぱり、泳いでいてよかったねえ。きみがはげましてくれたからだよ。」
不二夫君はうれしさに、ギュッと小林少年の手をにぎりしめるのでした。
そして、ふたりは広いほら穴の中を見まわしていましたが、小林君のかざしていたマッチが、いま消えようとするとき、不二夫君が、びっくりするような声でさけびました。
「あ、なんだかあるよ。きみ、あすこにへんなものがあるよ。」
「え、どこに?」
ききかえしたときには、もうマッチが消えてしまったので、小林君は、また一本新しくマッチをすって、不二夫君の指さすほうをてらして見ました。
遠いので、よくわかりませんが、どうも岩ではなさそうです。なんだか四角なものが、うじゃうじゃとかたまっているのです。
ふたりはいそいで、そのみょうなものに近づいていきました。とちゅうでまたマッチが消えたので、小林君は、もう一度それをすらなければなりませんでした。
まぢかに近よって、マッチの光でよく見ますと、それは、やっぱり岩ではなくて、何十何百ともしれぬ木の箱が、山のようにつみあげてあることがわかりました。
みかん箱を平べったくしたような形の、じょうぶそうな木の箱で、板の合わせめには、黒い鉄板が帯おびのようにうちつけてあります。
「あ、これ、昔の千両箱じゃない?」
不二夫君が、とんきょうな声でさけびました。
「うん、そうだ。千両箱とそっくりだ。あ、これだよ! これだよ! きみの先祖がかくしておいた金のかたまりっていうのは、これなんだよ。」
小林君も、思いもよらぬ大発見に、われをわすれてさけびました。
ほんとうをいいますと、その箱は昔の千両箱よりもずっと大きく作ってあったのですが、ふたりの少年は、そこまでは気がつかないのです。
それから、ふたりは何本もマッチをすって、むちゅうになって、このおびただしい箱の山を見まわしていました。やがて、またしても、不二夫君がとんきょうなさけび声をたてました。
「きみ、見たまえ。ここだよ。ほら、箱がやぶけて、ほら、こんなに、ぴかぴか光ったものが……。」
小林君がマッチを近づけてみますと、一方のすみの箱のふたに、さけめができて、そのすきまから、中のものが、きらきらと見えているのでした。
「あ、小判だ。昔の金貨だよ。」
小林君は、そのせまいすきまから、やっと指を入れて、四、五枚の小判を取りだしました。そして、またマッチをすって、ふたりが顔をくっつけるようにして、それをながめました。
「きれいだね。金だから、ちっともさびないんだね。」
「そうだよ。明治維新といえば、今から七十何年も昔のことだろう。こんなにたくさんの金が、七十年のあいだ、だれにも知られないで、ここにかくしてあったんだね。」
「この箱の中に、小判が何枚はいっているんだろう。千両箱だから、千枚かしら。」
「もっと多いよ。見たまえ、こんなにいっぱいつまっているんだもの、二千枚だってはいるよ。それから、小判ばかりじゃなくて、ほかの箱には、きっと、もっと大きい形のもはいっているんだよ。金の棒やかたまりもはいっているんだよ。」
「いったい、この箱いくつあるんだろう。」
「かぞえてみようか。」
ふたりの少年は、もうむちゅうになって、また、何本もマッチをすって、箱の数をかぞえはじめましたが、めちゃくちゃにつみかさねてあるのですから、とてもほんとうの数はわかりません。
「よそう。こんなことをしていたらマッチがなくなってしまうよ。それよりぼくらは、このほら穴を出ることを考えなけりゃいけないんだ。いくら金貨を見つけても、そとに出られなかったら、なんにもなりゃしない。」
小林君は、ふとそれに気づいて、マッチをすることをやめてしまいました。ほんとうにそうです。せっかく宝ものを見つけても、宝ものといっしょに、うえ死にをしてしまうのでは、なんのかいもありません。
「そうだね。おとうさんや明智さん、どこにいるんだろうなあ。」
不二夫君も、がっかりしたような声で、さびしそうにいいました。
また、もとの墨を流したようなくらやみでした。ふたりはそのやみの中に、立ちすくんだまま、もう口をきく元気もなく、だまりこんでいました。「もしこの地の底の迷路から、いつまでも出ることができないとしたら……。」それを考えますと、金貨を見つけた喜びも、どこかへふっとんでしまうのです。
ところが、ふたりがそうして、だまりこんで立ちつくしていたときに、とつぜんどこからか、チラッとまるでいなびかりのような強い光が、むこうの岩壁をてらしたのです。
ふたりは、ハッとして、思わずからだをすりよせ、手をにぎりあいました。あまりの不意うちに、ものをいうこともできないほど、びっくりしたのです。
すると、またしても、ちらちらと、青白い光ものが、岩壁をつたって走りました。
「アッ。わかった。あれは懐中電灯の光だよ。」
小林少年が、不二夫君の手をぐっと引きよせて、ささやきました。
「あ、そうだ。懐中電灯だ。じゃ、もしかしたら……。」
不二夫君も胸をわくわくさせながら、ささやきかえしました。
それはふたりが考えたとおり懐中電灯の光だったのです。その広いほら穴のむこうがわの入り口から、何者かが懐中電灯をてらしながら、近づいてきたのです。
不二夫君は、とっさに、その懐中電灯の主が、おとうさんの宮瀬氏と明智探偵ではないかと考えました。小林少年も同じ思いです。「おりもおり、ちょうど、宝ものを見つけたところへ、ふたりのおとなが来あわせるなんて、なんというしあわせだろう。」と、うれしさに胸をドキドキさせて、そのほうへかけだそうとしました。
ところが、今、かけだそうと身がまえした二少年の耳に、みょうな声が聞こえてきました。まったく思いもよらぬ、聞きなれない声なのです。
「へへへへへへ、うまくいったね。四人のやつら、今ごろは道にまよって、べそをかいているだろうぜ。」
「そうよ。運の悪いやつらだ。宝ものが、こんな手ぢかなところに、かくしてあるとは知らないで、別の穴へまよいこんでしまったんだからね。さすがの名探偵も、こんどこそは運のつきだろうぜ。道しるべのひもを切られてしまっちゃ、とてもあの穴を出られっこはないんだからね。フフフフフフ、ざまあ見るがいい。」
「だが、こんなにうまくいこうとは思わなかったね。やつらのあとをつけて、このほら穴へしのびこんで、ひょいと別の枝道へはいってみると、たちまち千両箱の山にぶつかったんだからねえ。神さまが、おれたちのほうに味方していてくださるんだね。」
「ハハハハハハハ、神さまでなくって、この岩屋島に住んでいる鬼のご利益りやくかもしれない。なんにしても首領の運のつよいのにはおどろくよ。」
そんなことを、ガヤガヤしゃべりながら、近づいてきたのは、ひとりやふたりではなくて、どうやら四、五人のあらくれ男らしいのです。
二少年はこの会話を聞いて、ハッと身をすくめました。味方とばかり思っていたのが、そうではなくて、おそろしい敵とわかったからです。
話のようすでは、大金塊を横どりしようとして、四人の探検隊のあとをつけてきたらしく、道しるべのひもを切ったのも、こいつらのしわざだったのです。四人がちがう枝道へまよいこんでいるあいだに、こいつらは悪運つよくも、正しい道をさがしあてて、とっくに宝ものを見つけていたのです。そして千両箱を外へはこびだすために、人数をそろえてもどってきたのにちがいありません。
なんにしても、こいつらに見つかってはたいへんです。明智探偵のなかまと知れたら、どんなひどいめにあわされるか、知れたものではないからです。
小林少年は、ものをもいわず、不二夫君の手をひっぱって、もとのせまい穴へ逃げこみました。そのせまい穴には海の水が流れこんでいて、奥へ行くほど深くなるのですが、そんなことにかまってはいられません。ふたりは、またしても、ひざのへんまであるつめたい水の中へ、はいっていかなければなりませんでした。
そして、その穴の奥から、そっとのぞいて見ますと、あらくれ男たちは、もう千両箱の山の前にひとかたまりになっていて、これから、それをはこびだそうとしているところでした。
かぞえてみれば、男たちは五人づれであることがわかりました。みな、力の強そうなおそろしい顔つきの大男の中に、ひとりだけ少し小がらな、みょうなまっ黒な服装をした人物がまじっていました。どうやらそれが悪者どもの首領らしいのです。
やがて、ひとりの男が身動きするひょうしに、その男の手にしていた懐中電灯が、首領らしい小男の顔をてらしました。
すると、その光の中へ、人間の顔ではなくて、なんともえたいの知れないみょうなものがあらわれたのです。まっ黒な化け物です。目と口のところだけが、三つの穴のように白くなって、そのほかは、耳も鼻もなにもないまっ黒な顔をしているのです。
小林君はそれを見て、ギョッとしましたが、しばらくすると、その小男が、お化けよりも、もっとおそろしいやつであることがわかりました。
そいつは、まっ黒な顔ではなくて、黒布で覆面していたのです。黒布の目と口のところだけがくりぬいてあったのです。
読者諸君も、もうおわかりでしょう。それは女だったのです。このお話のはじめのほうで、小林君を地下室にとじこめた悪者たちの女首領だったのです。ロシア人の着るルパシカに似た黒服といい、覆面のかっこうといい、あの地下室の女首領とそっくりだったのです。
ああ、なんという執念ぶかい悪者でしょう。大金塊のかくし場所をしるした暗号がぬすみだせなかったものですから、こんどは手をかえて、はるばる東京から、四人の探検隊のあとをつけてきたのです。そして、明智探偵がかくし場所を見つけるのを待ちかまえていて、大金塊を横どりしようとたくらんだのです。
小林君はそれと気づくと、賊のあまりの執念ぶかさにゾウッとしないではいられませんでした。なんだかおそろしい夢でもみているようで、目の前のできごとが、ほんとうとは思えないほどでした。
「よっこらしょっと、こりゃあ重いや。あの船では、これだけの箱を、とても一度には、運べませんね。」
ひとりの男が、千両箱を肩にかついで、首領に話しかけました。
「うん、まあ三分の一だろうね。船で、れいのところまで運んでおいて、また引っかえしてくるんだ。なにしろ一億円なんだからね。どんなに骨をおったって、骨おりがいがあるというものだ。おまえたちもみんな、きょうから大金持ちになれるんだぜ。」
覆面の首領が男の声で、部下の男たちをはげましました。首領が女だということは、部下のものは、まだ知らないようです。その秘密を知っているのは、広い世界で、小林少年たったひとりなのかもしれません。
「フフフフフフ、おれたちが、みんな百万長者か。なんだか夢みたいだね。」
「夢ならばさめてくれるな。フフ、世の中がおもしろくなってきたぞ。ねえ、首領、おれたちはずいぶん悪いこともはたらいてきたが、こんなでかい仕事は、あとにもさきにもはじめてですね。」
「おいおい、喜んでいないで、早く運ぶんだ。これをすっかりかたづけてしまうまでは、安心ができない。どんなじゃまがはいらないともかぎらないからね。」
むだ口をききながら、男たちは一つずつ千両箱をかついで、ほら穴を出ていきました。覆面の首領は、懐中電灯を持って部下のものを見はるようにしながら、いちばんうしろから歩いていきます。
やがて、賊の話し声や足音も聞こえなくなり、懐中電灯の光も消えてしまうと、ほら穴の中は、またもとの、めくらになったかと思うような暗さでした。
話のようすでは、悪者たちは、岩屋島のどこかへ船をつけて、こっそり上陸したものにちがいありません。今の千両箱をその船へ運んで、また引きかえしてくるのでしょう。そうして、ほら穴と船とのあいだを、なんども行ったり来たりして、つめるだけつみこもうというのでしょう。
小林少年は、賊が立ちさるのを見すまして、不二夫君に、ことのしさいを話して聞かせました。そして、手を引きあって、かくれ場所を出ましたが、苦心に苦心をかさねて、やっと目的の宝ものを見つけたと思ったら、たちまち賊のために横どりされてしまうなんて、じつになんともいえないくやしさでした。
といって、相手はおおぜいなのですから、ふたりの子どもの力では、どう手むかうことができましょう。ああ、こんなときに明智先生がいてくださったら、と思うと、小林君も不二夫君もざんねんでたまりません。どうしてこんなに運が悪いのかと、泣きだしたくなるほどでした。
「でも、ここにじっとしていたってしかたがないよ。あいつらのあとをつけて、ようすを見てやろうじゃないか。そうすれば、何かいい知恵がうかぶかもしれないよ。」
「うん、そうしよう。さっきの話では、ほら穴の入り口は、じき近くにあるらしいね。」
ふたりはそんなことをささやきあって、マッチをすって、方角を見さだめておいて、用心ぶかく、賊のあとを追いました。
ほら穴は、右や左にまがりながら、進むにしたがってせまくなり、しまいには立って歩けないほどになりましたが、そのせまいところをはうようにして、ぬけだしますと、少し広い道になり、どこからか、かすかに光がさして、あたりが、ほの明かるくなっているのに気づきました。
「あ、きみ、もう入り口が近いんだよ。ほら穴の入り口から光がさしているんだよ。」
外はまだ、昼間なのですから、これからさきへはうっかり進めません。もし賊に見つかったら、それこそどんなめにあうかもしれないからです。
「きみ、見たまえ、ここで道が二つにわかれている。ここが最初の枝道なんだよ。ぼくたちは、あっちのほうの広い道へはいっていったものだから、あんなめにあったんだよ。あのときもし、こちらのせまい道へ進んでいたら、賊よりもさきに、ぼくたちが金貨を発見したんだぜ。ざんねんなことをしたなあ。」
「あ、そうだ。それじゃ、ぼくたちは、ぐるっとひとまわりして、もとにもどったんだね。」
ふたりは、そこの岩の形に見おぼえがありました。考えてみれば、この枝道を右へ行くか左へ行くかの、ほんのちょっとしたちがいから、とんでもないことになってしまったのでした。
「もう少し入り口のほうへ行ってみようよ。」
不二夫君はそういって、うすい光のさしてくるほうへ歩きはじめました。小林君もそのあとにつづきます。地上の明るい世界がなつかしくてたまらなかったのです。
ところが、そうしてふたりが五、六歩歩いたときでした。とつぜんうしろのくらやみから、パッと青白い光がさしてきました。みょうな光が両がわの岩にちらちらと動くのを見て、ふたりはびっくりして、うしろをふりむきました。
すると、まっくらなほら穴の奥のほうから、怪物の目のように、ぎらぎら光ったものが、こちらへ近づいてくるではありませんか。懐中電灯なのです。何者かが懐中電灯をてらして、広いほうの枝道の中から出てくるのです。
二少年は、それを見ますと、ギョッとしてそこに立ちすくんだまま、もう身動きもできなくなってしまいました。
賊の部下にちがいありません。あの覆面の首領はぬかりなく、こんなところに見はり番をのこしておいたのでしょう。それを知らず、のこのこと近づくまで出てきたのは、じつに不覚ふかくでした。もうかくれる場所も逃げる道もありません。
ああ、ふたりは、とうとう悪者のためにつかまってしまうのでしょうか。やっと水の難なんをのがれたと思ったら、またしてもこんなおそろしいめにあうなんて、なんという運の悪さでしょう。それにしても、神さまは正しいものを見すてて、悪人の味方についておしまいなすったのでしょうか。そんなことがあってもいいものでしょうか。それでは小林君や不二夫少年が、あんまりかわいそうではありませんか。
二少年は、たがいに身をすりよせて、手をにぎりあって、胸をドキドキさせながら、立ちすくんでいました。まるでへびにみこまれたかえるのように、逃げだす力さえなくなってしまったのです。そういえば、くらやみの中に光っている懐中電灯は、とほうもなく大きな毒へびの目のようにさえ感じられるのでした。
そのぎらぎら光るへびの目は、刻一刻こちらへ近づいてきました。ああ、もう運のつきです。とうとうつかまってしまったのです。
小林君も不二夫君も、いよいよ覚悟をきめました。そして、口をきくかわりに、にぎりあっていた手に、ぎゅっと力をこめて、最後のわかれをつげるのでした。
すると、そのとき、じつに思いもよらぬことが起こりました。
「おお、不二夫、不二夫じゃないか。」
「あ、やっぱりそうだ。小林君だね。」
とつぜん、ぎらぎら光るへびの目のうしろから、そんなさけび声が聞こえてきたのです。
意外も意外、ふたりの少年にとっては、たましいもしびれるほどうれしい意外でした。それは賊ではなかったのです。賊どころか、味方も味方、さがしてさがしぬいていた明智探偵と宮瀬氏だったのです。
二少年の口から、なんともいえない喜びのさけび声がほとばしりました。そして、小林君は明智先生の胸をめがけて、不二夫君はおとうさんの宮瀬氏の胸をめがけて、おそろしいいきおいで飛びついていきました。
先生と弟子と、父と子とは、そのくらやみの中で、ひしとだきあったまま、しばらくは口をきくこともできませんでした。やがて、はげしいすすり泣きの声が聞こえてきました。不二夫君が、あまりのうれしさに、とうとう泣きだしてしまったのです。
あとで聞きますと、明智探偵と宮瀬氏は、二少年のゆくえをさがして、長いあいだ、地底の迷路をさまよったあげく、知らず知らずほら穴の入り口にたどりついたのです。すると、ちょうどそこへ、小林君たちも来あわせていたというわけでした。なんという幸運でしょう。やっぱり神さまは正しいものをお見すてにはならなかったのです。悪いやつは、いつかはほろび、正しい者は、いつかは、しあわせにめぐりあうのです。
しかし、うれしさにむちゅうになっているばあいではありません。いつ賊がもどってくるかもしれないからです。小林君はそこへ気がつきましたので、明智探偵と宮瀬氏に、てみじかに、ことのしだいを語りました。
それを聞いたふたりのおどろきは申すまでもありません。
「ああ、また、きみたちにてがらをたてられてしまったねえ。金貨が見つかったというのも、そんなおそろしい水ぜめにあいながら、少しもくじけなかった、きみたちの勇気のたまものだよ。えらかったねえ。ことに不二夫君は、よくがまんしましたね。」
明智が、年下の不二夫君をほめれば、宮瀬氏は、それもまったく小林君のおかげです、小林君は不二夫のいのちの親ですと、明智探偵の名助手をほめたたえるのでした。
「でも、その金貨は賊が横どりしようとしているのです。船でどっかへはこぼうとしているのです。先生、どうかして、あいつらをとらえるわけにはいかないでしょうか。」
小林君は何よりも、それが気がかりでした。
「それならば安心したまえ。ぼくは今、うまいことを考えついたんだ。たとえ相手が何人いようとも、きっととらえてみせるよ。宮瀬さん、ご先祖の小判一枚だって、賊の手に渡すようなことはしませんから、ご安心ください。さあ、それじゃ、賊がもどってこないうちに、急いで外へ出よう。」
明智探偵は何か考えがあるらしく、たのもしげにいって、さきに立ってほら穴の入り口へと進むのでした。
それから、四人はせまい入り口をはいだして、なつかしい太陽のかがやく地上の世界へ、もどりました。もう夕方です。考えてみれば、おひるまえから六、七時間の長いあいだ、地底のくらやみをさまよっていたわけです。
明智探偵は、しばらくあたりを見まわしていましたが、ほら穴の入り口から二十メートルほどのところに、大きな岩が立っているのを見つけて、一同をつれてその岩かげに身をかくしました。
そして、四人のものは、賊が千両箱をはこびだすために、もどってくるのを、待ちかまえていたのです。
岩かどから、そっとのぞいていますと、それとも知らぬ賊の一団は、覆面の首領を先頭に、どこからか姿をあらわし、岩穴の中へはいって行くのが見えました。
明智探偵は、賊の最後のひとりがその中へ消えるのを見とどけて「さあ、今だ。」と、人々をうながし、大急ぎでほら穴の入り口へかけつけました。
読者諸君は、四人が最初その場所を発見したとき、ほら穴の入り口が大きな岩でふさいであったことをご記憶でしょう。あの大岩はそのまま入り口のそばにころがっていたのですが、明智探偵は、いきなりそれに近づいて、大岩に両手をかけ、
「さあ、みんな、力を合わせておしてください。もとのように穴をふたしてしまうんです。」
と、ささやき声でさしずしました。
ひとりやふたりの力では、とても動かないのですが、四人がいっしょうけんめいにおしたものですから、さすがの大岩もやっと動きだし、まもなく、ほら穴の入り口をぴったりとふさいでしまうことができました。
ああ、なんといううまい考えでしょう。これでいっさいすんでしまったのです。賊と格闘したり、なわでしばったり、そんなめんどうな手数をかけないで、大岩一つで、五人のものを完全にとりこにしてしまったのです。さすがに名探偵ではありませんか。
「小林君、わかるかい。これは理科の問題だよ。こうしておけば、中からはどうしても、この岩をおしのけることができないのだ。なぜかというとね、穴の入り口のところは、立って歩けないほどせまいので、中からこの岩をおすにしても、たったひとりしか手をかけることができないからだよ。いくら力の強いやつでも、ひとりでこの岩を動かすなんて、思いもよらんことだからね。」
明智探偵が説明しました。なるほど、穴のそとでは、四人が力を合わせることができたので、さしもの大岩も動いたのですが、せまい穴の中からでは、いくらおおぜいいても、岩をおすことのできるのはひとりだけですから、とても動かせるものではありません。
「こうしておいて、ぼくたちは賊の船で長島の町へ帰るんだよ。そして賊の捕縛は、町の警察へお願いするんだ。なあに、見はり番なんかのこしておくことはないよ。たとえこの岩が動かせたとしても、船がなくては、どうすることもできゃしない。まさか、あの遠くの海岸まで泳ぐわけにもいくまいからね。」
何から何まで、じつにうまくできていました。四人は、れいの漁師のじいさんの小船を待つまでもなく、賊の船をうばって町へ帰ることができるのです。しかも、そうすれば、賊はこの島から一歩も逃げだせなくなるのですからね。
賊の船はわけもなく見つけることができました。四人の探検隊が上陸したのと反対がわの、島の切り岸に、一そうのりっぱなランチがつないであったのです。まっ白にぬった、窓の多い客室がついていて、へさきには美しいローマ字で「カモメマル」としるしてありました。
船の中に賊の部下がのこっているかもしれないと、用心しながら近づいてみますと、客室も機関室も、まったくからっぽで、人っ子ひとりいないことがわかりました。賊は一刻も早く千両箱をつみこもうと、総動員でほら穴へ出かけたのです。
四人は美しい「カモメマル」に乗りこみました。明智探偵が機関をしらべて、すぐさま運転をはじめました。名探偵はそういう技術も、ちゃんとこころえていたのです。
ランチは岸をはなれ、青海原を、はるかの長島町にむかって、すばらしい速力で走りだしました。
晴れわたった青空のかなたに、まっかにもえた夕やけ雲が、たなびいています。そよそよと吹く潮風、音楽のようにこころよい機関のひびき、白波を二つにわけて、矢のように走る「カモメマル」のへさきには、小林、宮瀬の二少年が、肩をくみあって、はるかの海岸をながめながら、立っていました。声をあわせて唱歌を歌ったり、口笛を吹いたり、そのほおは夕焼け雲にてりはえて、つやつやと希望の色にかがやいていました。
覆面の首領をはじめ、五人の賊が、その日のうちに、長島町の警察署の手で捕縛せられたことは申すまでもありません。そして、覆面の首領が美しい女であることもたしかめられたのですが、しらべてみますと、この女賊は、数年のあいだ、東京、大阪をまたにかけて、数かぎりない悪事をはたらいていたことがわかりました。
日本全国の新聞が、この大事件を社会面いっぱいに書きたてました。無人島の地底にうずまっていた時価一億円の大金塊、これに希代きだいの女賊がからみ、名探偵明智小五郎とかれんな二少年の冒険談がつけくわわっているのですから、新聞記事としては、じつに申しぶんのない大事件でした。
宮瀬氏が手に入れた金貨や金のかたまりを、ことごとく大蔵省におさめたことはいうまでもありませんが、一どきに一億円という大金塊が、国の金庫へおさまったのですから、政府の感謝、国民の喜びはことばにつくせぬほどでした。大蔵大臣は、わざわざ宮瀬氏を官邸に呼んで、ていちょうな感謝の意を表したほどでありました。
宮瀬氏は、金塊と引きかえに、政府からさげわたされた、ばくだいなお金も、けっして自分のものにしようとはせず、学校を建てたり、病院を建てたりして、あくまで世間のためにつくす考えでした。
名探偵明智小五郎は、この事件によって、いっそう、その名声を高めましたが、宮瀬氏のひょうばんは明智探偵以上でした。
しかし、そのふたりのおとなのりっぱな行ないよりも、もっともっと世間の人を喜ばせたのは、小林君と不二夫君の、手に汗にぎる冒険談でした。大金塊を見つけたのも、賊をとらえたのも、つまりは二少年のいのちがけの冒険のおかげなのですから、そのひょうばんは、たいしたもので、小林、宮瀬二少年の名は、日本全国津々浦々つつうらうらにまでひびきわたったのでした。
底本:「超人ニコラ/大金塊」江戸川乱歩推理文庫、講談社
1988(昭和63)年10月8日第1刷発行
初出:「少年倶楽部 第二十六巻第一号─第二十七巻第二号」大日本雄弁会講談社
1939(昭和14)年1月~1940(昭和15)年2月
※図は、「大金塊」大日本雄弁会講談社、1940(昭和15)年6月第2版を底本とした「江戸川乱歩全集 第13巻 地獄の道化師」光文社からとりました。
入力:sogo
校正:茅宮君子
2018年3月26日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
電人M
江戸川乱歩
少年探偵団員で、中学一年の中村なかむら君と、有田ありた君と、長島ながしま君の三人は、大のなかよしでした。
ある午後のこと、有田君と長島君が、中村君の家に、遊びにきていました。
中村君の家は港みなと区のやしき町にある、広い洋館で、その二階の屋根の上に、三メートル四方ほどの、塔のような部屋がついていました。その部屋だけが三階になっているわけです。
中村君は星を見るのがすきで、その塔の部屋に、そうとう倍率ばいりつの高い天体地上望遠鏡がそなえてありました。
三人はその部屋にのぼって、話をしていましたが、やがて話にもあきて、望遠鏡をのぞきはじめました。
ひるまですから、星は見えませんが、地上のけしきが、大きく見えるのです。ずっと向こうの家が、まるでとなりのように、近く見えますし、町を歩いている人なども、恐ろしいほど、すぐ目の前に見えるのです。
こんどは長島君の番で、望遠鏡の向きをかえながら、一心にのぞいていましたが、やがて、東京タワーの鉄塔が、レンズの中にはいってきました。
ここからは五百メートルも離はなれているのに、まるで目の前にあるように、大きく見えるのです。展望台のガラスごしに、見物の人たちの顔も、はっきりわかります。
長島君は、むきをかえて、タワーのてっぺんに、ねらいをさだめ、だんだん下の方へ、望遠鏡のさきを、さげていきました。
組み合わせた鉄骨が、びょうの一つ一つまで、はっきりと見えます。
だんだん、下にさがるほど、鉄骨の幅はばが広くなって、展望台のすぐ上まできたとき、長島君は、思わず「あっ。」と、声をたてました。
「おい、どうしたんだ。なにが見えるんだ。」
中村君と有田君が、声をそろえて、たずねました。しかし、長島君は返事もしません。息をはずませて、くいいるように、望遠鏡に見いっています。
それもむりはありません。望遠鏡の中には、じつにふしぎな光景がうつっていたのです。
タワーの鉄骨に、なにか黄色っぽい、グニャグニャしたものが、まきついていたのです。はじめは、はだかの人間かと思いましたが、そうではありません。なんだか、えたいのしれない、へんてこなものです。しかも、そいつが、生き物であるしょうこには、ゆっくりゆっくり、動いているのです。