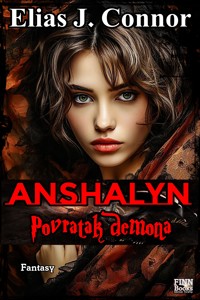3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Meyra
- Sprache: Deutsch
メイラは、暗黒の時代に生死を選ばざるを得ない、古の吸血鬼王朝という自身の家族の影から逃れようとしていた。嵐の夜、建築を学ぶ学生キーランを死の淵から救った時、メイラは渇望と義務を超越する感情に目覚める。しかし、兄が真実を暴き、メイラを家族の秘密の城の地下牢へと誘拐したことで、二人の秘密の愛は恐ろしい脅威へと変わる。キーランは選択を迫られる。メイラを忘れるか、命を危険にさらして王朝の魔の手から彼女を救い出すか? 忠誠心と情熱の間で劇的な戦いが繰り広げられる。そして、二人の愛を救えるのはただ一つの犠牲だけ… 禁じられた感情、抑えきれない想い、そして生と不死の選択を描いた、魅惑的な小説。
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 16
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elias J. Connor
Meyra - A vampire fairytale (japanese edition)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
献身
第1章 夜の静寂
第2章 秘密の王朝
第3章 最初の出会い
第4章 メイラの裏側
第5章 隠された翼
第6章 姉妹
第7章 芽生えた感情
第8章 禁じられた愛
第9章 - 彼女の目の中の閃光
第10章 家族の陰謀
第11章 思い出
第12章 黙示録
第13章 疑い
第14章 探索
第15章 一族の絆
第16章 キーランの脱出
第17章 最後通牒
第18章 撤退
第19章 避難所
第20章 狩猟
第21章 グールの教訓
第22章 王朝の闘争
第23章 儀式
第24章 - 私の血はあなたの血管に流れている
第25章 無限
用語集
著者について エリアス・J・コナー
Impressum neobooks
献身
彼女へ。
ミューズ、夢の解釈者、真実の愛。
いつもそこにいてくれて、私のそばにいてくれてありがとう。
エリアス。
第1章 夜の静寂
聖歌隊の声が夜空に静かに響き渡る。どこから歌声が聞こえたのか、正確には特定できない。いずれにせよ、この夜は湿っぽく寒いので、この歌声はどこか物足りない。人通りの少ない脇道は、みぞれと濃い霧に包まれ、不快な氷のような風が吹いている。
今何時でしょうか?午後11時、あるいは真夜中過ぎでしょうか?
しばらくすると、どこから聞こえてきたにせよ合唱の音は静まり、この奇妙で人里離れた場所は完全に静まり返ります。
彼女はちらりと顔を上げ、再び厚手のウールセーターの襟の下に頭を埋めた。彼女は震えている。脚はリズミカルに痙攣し、息が顔の前で小さな雲のように立ち上る。
一瞬、彼女は何かを言ったように見えますが、それはおそらく彼女の唇に浮かんだ影でしょう。
彼女が座っている橋はそれほど大きくも高くもないが、少なくともここは乾いている。
少女は再び顔を上げた。ダークブロンドの髪が顔にかかり、髪型は乱れ、何度も目にかかった髪を拭おうとしていた。唇はまだ寒さで震えていた。
足音が近づいてきた。彼女は足音を聞いて顔を上げ、素早く柱の後ろに隠れた。ウールのセーターにさらに深く頭を突っ込み、半開きのジャケットの紐をきつく締め、誰にも見られないようにした。
ゆっくりとした足音。一つ一つが聞こえる。体が震えるのは寒さのせいか、それとも恐怖のせいか。
彼女は橋脚に寄り添い、両腕でしっかりと掴みかかる。まるで橋脚と一体になり、姿が見えなくなることを望んでいるかのようだ。
しかし、もう遅かった。年配の男は既に彼女に気付いていた。彼はゆっくりと近づいてくる。彼の足音が橋の下にこだまする。
彼女は柱に体を押し付け、目を閉じた。突然、肩に手が触れた。男は強くはないが、毅然とした態度で彼女を振り向かせ、彼女の目を見つめた。
「ここに誰かが隠れているのは分かっていた」老人は彼女にぶつぶつ言った。「こんな夜遅くに、一人で何をしているんだ?」
少女は震え続けた。ほとんど閉じた目で用心深く彼を見つめ、ついに何も言わずに顔を横に向けた。
「君くらいの年頃の女の子が夜一人で歩き回るべきじゃないよ」男は朗々とした声で言った。
少女は風に揺れる薄くなった白髪を見つめている。
「19歳よ」と彼女はついに、ほとんどささやくような声で言った。「夜に何をするかは私の勝手よ」
「君は14歳か15歳に見えるよ」老人は信じられないといった様子で言った。
「私は19歳です」と少女は静かに繰り返した。
その時になってようやく彼女は橋脚から手を離し、縁に腰を下ろした。年配の男性は彼女の隣に座り、タバコに火をつけた。
少女はほとんど嫌悪感を覚えながら、顔から煙を払いのけるように手を振り、年上の男性を軽蔑の眼差しで見つめた。
「しばらく一緒に座ってもよろしいでしょうか?」と彼は尋ねます。
少女は首を横に振った。
「もうあまり動けないんです」と男性は言う。「それに家まではまだ遠い。だから時々休憩を取らないと」
少女はうなずいた。
「君はあまり口数が少ないな」男は訝しげな視線を向けた。「名前はあるか?」
彼女の吐く息の雲が彼女の青白い顔をほぼ完全に包み込んでいる。
「メイラ」彼女はそっとささやいた。
「大丈夫だ、メイラ」老人は言った。「怖がる必要はない。俺は君を傷つけない。しばらくここに座っているだけだ。足が動き次第、移動する」
メイラは老人を横目で見る。彼女の目は同情に満ちているようだが、よく見ると、その視線には全く異なる何かが見える。
それが何であろうと、老人はそれを認識できない。
「あなたは一人暮らしですか?」若い女性は男性に尋ねた。
彼は深く息を吐き出し、彼女の方を向いた。「妻はとっくに亡くなっているんです」と彼は言った。「子供もいなかったし、もう家族もいない。そう、僕は一人で暮らしているんです」
メイラの瞳は、まるで風が歌を奏でているかのようにきらめき、心臓の鼓動が激しく鼓動した。
「他に誰も残っていないの?」メイラは確かめたいようだ。
男はうなずいた。
「誰もあなたがいなくて寂しがらないの?」メイラは彼に直接質問した。
「なぜそんなことを聞くんだ?」男は答えた。「私を殺すつもりか? いいぞ。もう人生に何も期待できない。」
メイラは息を荒くした。内心が震えた。体が震える。彼女はそれがどれほど嫌なのかを知っている。そうせざるを得ないこと、さもなくば死ぬことを知っている。そして、メイラが自分の人生を憎んでいるのと同じくらい――老人が自分の人生を憎んでいるのと同じくらい――彼女は死にたくない。生き延びるための生来の本能こそが、彼女を生き続けさせ、普段なら決してしないようなことをさせるのだ。
最後にもう一度。彼の瞳から放たれた最後の閃光は、メイラの心を射貫くようだった。
そして次の瞬間、老人は地面に倒れて死んでいた。
メイラは彼の傍らにしゃがみ込んでいる。彼女の視線は深く悲しげで、目には涙が溢れ、唇は赤く、おそらく血で染まっているのだろう。
彼女はもう一度彼を見つめた。そして静かに立ち上がり、橋の下の薄暗く不気味な場所から数歩離れた。十分に離れると、彼女は走り始めた。
高速道路に入ると、メイラはさらにスピードを上げた。まるで稲妻のように、通り過ぎる車よりも速く、彼女は闇夜を駆け抜ける。時折、車のヘッドライトがかすめてくるが、気にしない。自分のせいじゃない、と自分に言い聞かせる。誰かに聞かれても、自分のせいじゃない。
ええ、彼女はそれを嫌っています。ずっとそうでした。でも、他に選択肢はありません。彼女はそれを知っています。それが現実であり、これからもずっとそうなのです。
しばらくして到着したメイラ地区は、市内中心部から約20キロ離れた場所にあります。それほど広くはなく、実際には数軒の家が建っているだけで、かなり裕福な人々が住んでいるようです。どうやら良い地域らしいです。
メイラが村を歩いていると、辺りはすでに静まり返っていた。通りには誰もいない。メイラは歩みを緩め、街灯に目を向ける。霧が街灯の向こうを静かに流れていくのを眺め、光の中に小さな雨粒が浮かんでいるのに気づく。
メイラは額の汗を拭う。暑かったので、またジャケットを開ける。
彼女は幹線道路をゆっくりと歩き、町の端までたどり着いた。そして最後の信号で右折し、近くの森の小道に入った。
街の明かりが徐々に消えていく。メイラは最後にもう一度振り返る。再び前を見ると、彼女は小さな隠れた路地の前に立っていた。その光はまるで夜の闇に完全に飲み込まれてしまったかのようだった。
陰鬱で落ち着いた丘陵地帯に、知られざる村がひっそりと佇んでいる。陰鬱で暗い。木骨造りの家々がひっそりと佇み、そのファサードは苔のような緑色に輝き、板葺きの屋根は周囲のオークの密林にほとんど映えない。道を示す標識はなく、地図にも場所が記されていない。静かな小道を知る者だけが、二本の古木の間にあるブドウ畑の入り口を見つけることができるだろう。
名もなきこの秘密の場所の中心には、家々の列の間に細い路地が曲がりくねって伸びている。根っこでひび割れた石畳は、まるで木々が地面に指を突き刺したかのように、あちこちでぽっかりと開いている。黒ずんだ鉄のランタンが木の梁から曲がって垂れ下がり、不規則なリズムで揺らめき、風化した壁に踊るような影を落としている。
路地の中には、錆びたボルトと色褪せたルーン文字がちりばめられた巨大なオーク材の落とし戸で唐突に途切れているものもある。耳を澄ませば、遠くから水が滴る音や、その向こうからかすかに聞こえる足音が聞こえる。こうした隠れ家の急な階段の下には、地下迷宮が広がっている。湿った通路、古代のカタコンベ、そして高い地下室が張り巡らされたこの迷宮では、上空の街の息吹がかすかに響くのみである。
日中、ここを散策する旅人はほとんどいない。しかし、木々の間から霧が立ち込める夕暮れ時、最奥の掩蔽壕で忘れられた秘密を研究した学者や、路地裏で誘うように微笑みかけた旅人たちが、落とし戸の影へと消えていったという話がささやかれる。この道を選ぶ者は、ただ隠された村を見つけるだけでなく、地下の広大な世界を発見する。その通路は果てしなく深淵へと続く。
メイラは苔むしたブドウ畑の門を静かにくぐり、薄暗い夜明けの静かな村へと足を踏み入れる。木骨造りの家々は、過ぎ去った時代を静かに見守る証人のようにそびえ立ち、重々しい柾板屋根の下には露が漂っている。メイラの視線は、村を迷路のように曲がりくねって貫く狭い路地へと移っていく。まるで侵入者を永遠に閉じ込めようとしているかのようだ。
彼女は路地を選び、石畳がブーツの下で静かに軋む音を聞きながら、木の壁の間の奥へと続く緩やかな坂道を進む。ランタンの炎が静かな風に揺らめき、舗道の割れ目に影が踊る。頭上では、古いオークの枝がアーチを描き、路地に緑がかった夕暮れの光を投げかけている。
メイラはある地点で立ち止まった。錆びたボルトで固定された、年代物のオーク材でできた巨大な落とし戸には、色褪せた刻印が刻まれていた。心臓が高鳴る。ここから深淵への道が始まるのだ。慣れた手つきでボルトを回し、扉を少し持ち上げると、下の階段から冷たく湿った空気が立ち上ってくるのを感じた。
彼女は慎重に降りていく。一歩一歩が祈りのように石壁に反響する。苔と根が崩れかけた壁に絡みつき、遠くでは水滴の音が反響する。メイラは天井が低くなる狭い通路を進み、広い交差点に着く。矢印は左に忘れられた井戸、右に囁く夜の墓所を指している。しかし、正面にはかすかな松明の光が灯っている。
彼女は中道を選び、囁きを後にし、木の門に辿り着いた。二体の石のガーゴイルが静かに見張り、門自体も精巧な彫刻で飾られていた。それは、地上の街よりも古い力の証だった。メイラは金属製の取っ手を握り、最初の引き金を引いた。きしむ音と、古代の魔法の輝き――そして、目の前に、夜警たちの地下城への門が開いた。
敷居の向こうには黒大理石の広間が広がり、その表面は松明の光を冷たく反射している。巨大な柱が影の中に突き出ており、天井には血と名誉の物語を物語る風化したフレスコ画が描かれている。メイラはフードを脱ぎ、苔と古代の石の香りを吸い込む。そして、闇へと続く道、運命へと続く唯一の道を見つけたことを悟った。
第2章 秘密の王朝
ロンドンの狭い路地には、霧がまるで透き通らない覆いのように、古びた石畳を覆い隠している。ランタンの淡い光が雨に濡れた壁を照らし、小川が下水道へと流れ込んでいる。遠くで真夜中を告げる鐘の音が響き、何世紀にもわたってこの大都市の影に君臨してきた古の吸血鬼一族が目覚める。彼らの存在は人間には隠されているが、あらゆる暗い片隅、煙の立ち込めるパブ、そして重厚な木の扉の向こうで、彼らの囁きが脈打っている。
メイラはひっくり返った木箱の陰に隠れていた場所から静かに姿を現した。ブロンドの三つ編みが肩に垂れ下がり、黒い革のコートとは対照的だった。彼女は19歳。彼女が狩る者たちの多くとほとんど変わらない年齢だが、それでも人間が知る限りでは年上だった。青白い顔は完璧に見えたが、青い瞳の緊張は、彼女の内に渦巻く苦悶を物語っていた。一滴一滴の血が、彼女の運命の闇へと深く刻み込まれていく。メイラは、一口一口を渇望する自分の渇望を憎んだ。
今夜、イーストエンドの路地は彼女のもの。夜明けの光が街路を照らす前に、一家は二手に分かれ、できるだけ多くの犠牲者を出し抜こうとしている。メイラは女狩人グループに属している。それは名誉であると同時に重荷でもある。メイラの隣には、一族の姉であるアヴェリンとルシンダがいて、二人はメイラを敬愛すると同時に軽蔑している。赤い唇と艶めかしく揺れる腰を持つアヴェリン。氷のように白い瞳と、常にどこか冷淡な笑みを浮かべるルシンダ。二人とも、誘惑と恐怖の術を誰にも劣らず熟知している。
かすかな光が脇道から漏れる。メイラは脈が速くなるのを感じた。これほど多くの生命が一度に、これほど多くの温もりと、これほど多くの人間の匂いが漂ってきた。建設作業員の汗、若い女性の香水、小さなパブのビールの匂いがする。この空気中の血の一滴一滴が、前のものより甘く感じられる。人間の血管の中で、渇望が解放を求めて叫び声をあげる。それでも、メイラは沈黙を強いる。
アヴェリンがかすかに聞こえる合図を送ると、三人の吸血鬼は散り散りになった。メイラは、作業員たちが木箱を運んでいる、警備の甘い倉庫の窓辺に忍び寄る。くぐもった笑い声が響き、メイラは男の一人が口の端からタバコを抜くのを見守る。彼女は深く息を吸い込み、嫌悪感とともに喉の渇きを血管に引き寄せると、まるで捕食者のような軽やかさで部屋に入っていく。男たちは、彼女が目の前に立つまで彼女に気づかない。その笑みは、誘いというよりは死刑宣告のようだった。
「さて、娘よ、ここは場違いか?」誰かがよどみながら、コートに手を伸ばした。メイラは首を振り、ゆっくりと向きを変え、コートを後ろに引いた。指先の薄い皮膚が湿った木に触れ、流れるような動きで彼女は立ち去った。
瞬きする間もなく、彼女は飛びかかる。彼女の手の爪が彼の手首を掴むと、作業員は凍りつく。心臓が高鳴り、目を見開く。メイラの歯が光り、暗闇の中で真珠のようにきらめく。一瞬、彼女はためらう。聞こえる心臓の鼓動の一つ一つが、音楽であると同時に悪意に満ちている。そして、彼女が噛みつくと、周囲の世界がぼやける。血が口の中に流れ込み、感覚が麻痺し、肺は陶酔するような熱で満たされる。他の男たちの叫び声は、くぐもった声として彼女に届くだけだった。彼女は一口ずつ飲み、周囲の全てが滅びるまで飲み続ける。
ついに彼女が手を離すと、死体は地面に沈んだ。メイラの目はぼやけ、感覚は陶酔と後悔の間で揺れ動いていた。もし人生が違っていたら守れたはずの人々を殺してしまうほどの渇望を、彼女は憎んでいた。食事のたびに良心が苛まれ、それでも彼女はそれを止めることができなかった。血こそが彼女の運命であり、家族の悪意に満ちた網の一部となる祝祭なのだ。
ルシンダはすでに路地裏で待っています。彼女の視線は冷たく、しかしその目には燃えるような好奇心が宿っています。
「また我慢できなかったの?」と彼女は囁いた。年老いた吸血鬼の唇は、非難と好奇心が入り混じった笑みを浮かべた。「あなたは自分が古い人間だと証明したいのかと思ったわ」
メイラは袖で口角を拭う。コートには血痕がついているが、ほとんど気にしていない。
「空腹の方が強かった」彼女は視線を落とし、羞恥の波を感じた。こんな時、彼女は自分が殺した相手よりも年上であるはずなのに、罪を犯した子供のように感じてしまう。
アヴェリンは静かに近づき、メイラの肩に手を置いた。
「そんなに弱気にならないで、姉さん。弱気は私たちには許されない贅沢よ」彼女の声は柔らかかったが、その一音一音がメイラに短剣のように突き刺さった。
イライラしながらも、自分自身に嫌悪感を抱きながら、メイラはため息をつき、目を回します。
「わかってる」メイラは囁く。もっと強くなりたい、大人のように心の冷たさを感じたい。しかし、渇きが脈打ち始めると、それは彼女を内側から引き裂く。
ルシンダは背を向け、その声は冷たく響いた。
「集合場所で会いましょう。他のメンバーはもうそこにいます。」
メイラはうなずき、肩をすくめて深呼吸をした。落ち着かなければならない。これ以上弱気になる余裕はない。
古びた鉄道線路下の廃墟となったトンネル網での待ち合わせ。そこは、腐敗臭が漂い、どんな深淵よりも深い静寂に包まれた場所。金属の梁、木の梁、そして湿った石の根が、古き吸血鬼の一族が集う闇へと続いていた。雪のように白い髪と透き通るような瞳を持つ族長セバスチャン卿。凍った湖のように冷たく、その娘イゾルデ。そして、メイラがまだ名前も知らず、声もかすかにしか感じられない無数の吸血鬼たち。
トンネルを進む彼らの足音は鈍く響く。メイラは心臓の鼓動の一つ一つを、まるで自分の鼓動のように感じる。静寂が彼らを包み込むが、やがて大広間に辿り着く。そこは天井が鋳鉄の梁で支えられた、広大な地下室だ。壁は錆びた蔓で覆われ、どこからともなく水が一定のリズムで滴り落ちている。
部屋の中央には円形の石の祭壇があり、その上には古い真鍮のカップに血管が既に置かれている。メイラは胃が締め付けられるような感覚を覚える。カップに注がれた一滴一滴に、無数の命のエッセンスが込められている。中には丁寧に調合されたものもあり、アドレナリンの奔流と恐怖が混ざり合い、その味わいをさらに引き立てている。また、路地裏で命を落としたばかりの逃亡者たちのものもある。さらに、ある特定の理由でこの世に生きる権利を失った人々のものもある。
セバスチャン卿が手を挙げると、たちまち一同が静まり返った。彼の視線はメイラに注がれ、メイラはまるで自分が彼の中心にいるかのように感じ、飲んだ血の一滴一滴に、自らの罪を弁明しなければならないかのように感じた。
「メイラ」彼は響き渡る声で言った。「誓約の選挙のために、君の名前を呼んだ。我々の大義に忠誠を誓う準備はできているか?」
メイラの背筋に冷たい戦慄が走った。誓いは彼女の忠誠心を固め、一族の陰謀と権力闘争に彼女を縛り付ける。拒否する者は追放され、あるいはそれ以上の目に遭う。しかし、この誓いは彼女を守るものであり、家族における彼女の居場所でもある。拒否した瞬間、彼女はすべてを失う。
彼女は祭壇の前に立つ。血と罪の跡が刻まれた錆びた壁に、彼女の姿が揺らめき踊る。震える声で話す。
「私はナイトウォッチ家のメイラです。セバスチャン卿に頭を下げ、私の血が流れる限り、卿の意志を全うし、一族の名誉を守ることを誓います。」
メイラが冷たい真鍮の洗面器に手を置くと、群衆にざわめきが広がった。血が沸騰し、彼女は自分の内側で何か暗いものが目覚めるのを感じた――自分よりも古い力が。彼女は恐怖を飲み込み、視線を上げた。
セバスチャン卿は頷き、親指をわずかに弾き、指を切る。鋭い痛みが走ったが、ほとんど感じられないようだった。赤く輝く血の一滴が祭壇の羊皮紙に落ち、消えないインクで誓約書に署名する。そして、彼はその血をメイラに差し出す。
彼女はほんの一瞬ためらい、頷いて族長の手から飲み物を飲んだ。彼女の体内で火花が散り、細胞一つ一つに温かさが伝わる。この一口は空腹ではない。義務であり、力を与え、そして鎖を繋ぐものなのだ。
カップを返すと、彼女の視線はより澄み渡り、決意に満ちていた。彼女は周囲の視線を感じる――羨望、尊敬、不信。しかし同時に、彼女は自分の中に湧き上がる力の波を感じ、自分の運命を軽蔑しながらも、二度と普通の人生を送ることはできないという自覚も感じていた。
総主教が集会で演説する。
「夜はまだ浅く、祝宴が我々を待っている。出でて、我々を養う魂を探しに。そして恐怖と血の物語を持ち帰って来い。」
ざわめきが沸き起こり、吸血鬼たちは四方八方に散り散りになり、人間たちを滅ぼそうとする。アヴェリンとルシンダはメイラと合流し、トンネルの入り口から爽やかな夜気の中へと足を踏み出す。
ロンドンの街路は、まるで可能性の網の目のように彼らの前に広がっていた。メイラは再び、以前よりも激しく喉の渇きに襲われるのを感じた。
しかし、彼女は準備ができている。闇へと飛び込む覚悟、どんなに過酷な運命であろうとも受け入れる覚悟。
彼女は視線を上げ、足元の街の鼓動を感じた。そして最初の影が隅へと消えていくと、メイラは裏切りと情熱、そして血に満ちた長く暗い夜へと最初の一歩を踏み出した。
第3章 最初の出会い
夜風がメイラのコートを引っ張る。彼女は交通量の多い田舎道の端にしゃがみ込み、焼け焦げた配達用バンの影に隠れている。通り過ぎる車のヘッドライトが、へこんだ金属板にきらめき、濡れた舗装路面に揺らめく光を反射している。エンジンの轟音、雨で濡れた路面を走るタイヤの絶え間ない軋み。すべてが混ざり合い、鈍いコーラスとなってメイラのこめかみを震わせる。
彼女は身動き一つせずしゃがみ込み、ほとんど息を吐き出さない。夜は湿っぽく、油、排気ガス、そして腐敗臭が空気を漂う。彼女の背後で、バイクが猛スピードで轟音を立てて通り過ぎる。メイラはひるむことなく、ヘッドライトが遠くに消えるまで視線を追う。
彼女の視線が揺らめく。飢えが皮膚の下、表面のすぐ下で燃え盛る炭のように燃えている。ここ二晩、酒を飲んでいない――というか、本当に。ホワイトチャペルの強盗から数滴もらったが、ほんの少し味見した程度で、喉の渇きはひどくなるばかりだった。歯茎に牙を押し付け、皮膚を突き刺そうとしている。唇をすぼめ、通りを見つめている。
銀色のBMWがゆっくりと通り過ぎる。車内ではカップルが笑いながら座っている。窓から音楽が響いてくる。生きる喜び、軽やかで、気ままな様子。メイラは首を傾げ、一瞬、肌の下で脈打つ血の匂いを嗅いだ。
しかし、彼女は攻撃してこない。まだ。まるで自分自身から身を守るために何かにつかまっているかのように、彼女の指は後ろの鋭いバンパーにしがみついている。
空腹は辛い。考えることも、議論することもない。ただ、あるだけ。
彼女は目を細めて、無理やりじっと動かないようにした。田舎道は狩り場にはならない。目撃者が多すぎる。光が強すぎる。騒音が強すぎる。そして、何かあった時の保護も薄すぎる。
対向車線で別の車が急ブレーキをかけた。メイラは意識を研ぎ澄まし、少し起き上がった。二人の男が車から降りてきて、彼女が隠れている場所から腕一本伸ばした距離の路肩で大声で言い争っている。一人は若くて運動神経が良く、脈拍が激しく鼓動し、メイラはそれを味わえるかのようだった。
彼女は影の中に身を預け、まるで彫像のようにそこに佇んでいる。暗闇の中で、彼女の青い瞳がほんの一瞬きらめく。それは、何を探しているのかを知っている者だけが見ることができる、確かな光だった。
しかし、誰も彼女に気づかない。ゴミ袋と錆びた金属くずの間にしゃがみこむコートを着た少女に、誰も気づかない。
彼女は頬の内側を噛んだ。血の味がした。自分の血の味がした。
彼女の一部は飛び上がりたい、狩りをしたい、燃え盛る炎が収まるまで酒を飲みたいと願っている。しかし、もう一方の部分――人間としての部分、あるいは残された部分――が彼女を阻んでいる。この内なる葛藤こそが、彼女を狂気へと駆り立てるのだ。
突然、タイヤがきしむ大きな音がした。二台の車。衝突、金属が砕けるような音、鈍い音。
メイラの頭がくらくらする。わずか20メートル先で事故が起きた。車が道路を横切り、ガードレールに激突しそうになった。もう1台の黒いSUVはブレーキも踏まずに走り去り、夜のバックミラーにテールランプが赤く点滅していた。
メイラは飛び上がる。感覚が麻痺し、鮮血の匂いが拳のように彼女の顔に突き刺さる。
彼女の中では、本能と人間性が、開いた線路上の2台の列車のように衝突しています。
彼女は走り始めた。壊れた車に向かって。血の跡に向かって。
メイラは、明らかに重傷を負った若い男を、最後の力を振り絞って、大破した車から引きずり出す。心臓が高鳴るのを感じながら。金属とガソリンの悪臭が鼻を突くが、ほとんど感じない。彼女の視線は、血まみれの若い男の動かない体に釘付けになっている。黒い髪がこめかみに張り付いており、そこには大きな傷跡が地面を貫いている。メイラは彼を狭い脇道へと運ぶ。遠くのランプのぼんやりとした光が、彼をかすかに照らしている。渇きが激しく、激しい嵐のように、彼女の胸を突き刺す。しかし、何かが彼女を阻んでいる。まるで見えない楔のように、欲望と抑制を不可分に分断している。
彼女は男を溝の湿った草の底に優しく降ろした。男はまぶたをぴくぴくさせ、メイラは身を乗り出し、そっと彼の頬に手を置いた。心臓の鼓動が耳の中で激しく鳴り響いた。
「一緒にいて」メイラは囁く。彼には聞こえていないと分かっていながらも。彼女はそっと彼の顔を両手で包み込み、眠たげな暗い瞳を見つめる。彼は小さくうめき声を上げ、荒い呼吸をする。その息には、あまりにも多くの苦しみと生が込められており、メイラの決意は鋼鉄のように強くなる。
何もなかったかのように車が勢いよく通り過ぎる。明るいヘッドライトが二人を一瞬照らし、それから車は勢いよく走り去る。若い吸血鬼とその犠牲者に気づく者は誰もいない。助けが必要かどうか尋ねる者もいない。メイラは辺りを見回すが、負傷した男と彼女以外、誰もいない。
彼女は最近、何も知らない学生から受け取ったハンドバッグを開け、救急用品を取り出した。銀箔で包まれた滅菌ガーゼ包帯、消毒ウェットティッシュ、そしてハサミだ。驚くべき手際で、彼女は彼の傷口を洗浄し、傷口の縁を軽く拭き、ガーゼ包帯を巻く。すべての動作は正確だが、思考は駆け巡っている。一瞬、ただ酒を飲もうかとも考えた。誘惑は容赦なく、喉のズキズキする感覚は手に取るようにわかるほどだった。しかし、彼女は思いとどまる。静かに、どこか異質な責任感が忍び寄り、ずっと前に失ったと思っていた人間らしさのかすかな火花が、彼女の心に浮かんだ。
若い男は目を開け、まるで自分が夢を見ているのだと確信するかのように彼女を見つめる。彼の視線は彼女の顔に留まる。澄み切った、美しい、それでいて死の表情そのもの。青白く、近寄りがたい。メイラはためらいがちに微笑む。
「大丈夫よ」と彼女は落ち着いた声で言った。「私の名前は…」彼女は少し間を置く。嘘をつくたびに、まるで真実を探しているかのように、血が脈打つのを感じる。「私の名前はマリアン」彼女はその言葉を嫌悪していたが、まるで本名であるかのように彼に囁いた。「病院まで連れて行くわ。もうすぐ救急車が来るわ」
彼女の説得力に、男は一瞬頷いたが、疑問の表情はそのままだった。息を呑んだ。
「キーラン」と、震える声でどもりながら、かすれた声が聞こえた。体がぴくぴく動き、まぶたが震え、そして再び目を閉じた。
メイラは背筋を伸ばします。
「キーラン」と彼女はまるで子供に話しかけるかのように繰り返した。「頑張ってね、いい?」
次の瞬間、遠くて近いサイレンの音が聞こえた。安堵のため息をつくと同時に、胃がきゅっと締め付けられた。救急車は医者、ライト、そして人見知りを意味する。身元を明かしてはいけない。サイレンの音がさらに大きくなり、路地の壁にぶつかる。救急車が角を曲がり、事故現場へと滑るように進んでいく。ドアが勢いよく開き、救急隊員たちが担架と機材を抱えて駆け込んでくる。
メイラはキーランの首筋に顔を埋める。彼の血に触れ、彼の心臓の味を確かめようと、最後の試みだ。しかし、無理やり体勢を戻して、袖で口を拭う。まるで何もなかったかのように。救急隊員が近づいてくる。彼らの明るい点滅灯が、辺りを赤と白の光で染める。
「これは何?」救急隊員がキエランを見て尋ね、同僚は急いで毛布を引き下ろした。
「事故に巻き込まれた車の乗員の一人が怪我をしました」とメイラは力強い声で答えた。「彼は意識不明です。あなたが到着するまで私が介助しました」
救急隊員は彼の怪我の状態を検査し、首にコルセットを装着し、慎重に担架に乗せた。メイラは彼らのそばに留まり、片腕で彼の膝の下を支えた。
「病院に一緒に行ってもいい?」彼女はできるだけ人間らしい口調で話そうとする。
救急隊員たちは顔を見合わせた。
「スタッフは十分にいますよ」と、一人が慎重に言った。「でも、もしよろしければ、車の中で一緒に座って患者さんを落ち着かせてあげてください」
メイラは安堵してうなずいた。「ありがとう。」
彼女は慎重に救急車に乗り込み、キーランの左側の隣の席に座った。車内は明るく照らされ、あらゆる機器と光るディスプレイがそこはまるで別世界のようだった。メイラは、蘇生器具、酸素マスク、モニターといった光の一つ一つに視線が吸い寄せられるのを感じた。どれも人命を救うために使われる道具ばかりだ。決して見るべきではない光景なのに、今まさに目の当たりにしている。
ドアが閉まり、救急車が走り去る。メイラはキーランの肩に手を置く。彼は動かない。ヘルメットのようなネックブレースが動きを制限しているからだ。彼女は息を吐き、頬の奥で喉の渇きがズキズキと痛む。しかし、看護師や救急隊員に疑われないよう意識を集中させる。救急隊員の一人が「事故を見ましたか?」と尋ねると、メイラは頷いた。
「ええ」と彼女は正直に言った。「ここのトンネルから出てきたところで…」彼女は地下道を指差した。「…その時、ドスンという音が聞こえたんです」
「わかりました。そのままお待ちください」と救急隊員が言った。「あなたの供述が必要です。」
メイラは頷いた。嘘の筋道を保つために、後ですべてを捏造しなければならないことを彼女は知っている。幾重にも重なる嘘の重みに圧倒されそうになったその時、腕に軽い感触が伝わってきた。メイラより少し年上の若い救急救命士が、温かい目でメイラを見つめていた。
「大丈夫ですか?」と彼は尋ねます。
「ええ、ありがとう」メイラは不安げに微笑む。その微笑みには、強い吐き気と切なさがこもっていて、彼女は落ち着かない。再び隣にキーランの体を感じ、彼を食べ物のように見たい衝動に駆られる。しかし、この男、この奇妙な救急救命士は、彼女の気持ちを見透かしていただろう。いや、彼女は違う行動を取らなければならない。彼を食い尽くすのではなく、救わなければならない。
救急車はロンドンの閑散とした通りを走り抜け、眠る家々や明かりに照らされた店の窓を通り過ぎた。メイラはキーランに寄り添い、青白い頬と血に染まった包帯を見つめた。彼女の視線は彼の手首に留まり、まるで密かに警告を与えているかのようだった。「強くなれ。私が君を生かしているから」
病院では、救急隊員がキーランを運び込むと、廊下に強烈なネオンの光が溢れかえっていた。メイラは彼らの後について行き、受付デスクを指さした。
「彼はひどい交通事故に遭って亡くなりました。」
二人の看護師が彼を優しく抱きかかえ、治療室へと案内する。医師が前に出て、二人を簡単に診察する。
"あなたは誰ですか?"
「マリアン」と彼女は言い、その言葉を発音したとき、初めて舌に奇妙な感覚がすることを実感した。
医者はうなずいた。
「ここにいてください」彼は治療室の中に消えていった。
メイラは病院の廊下に、緑と白の壁に囲まれた一人立ち尽くしている。廊下の奥からは、くぐもった叫び声と機械のビープ音が聞こえてくる。夜勤のせいで手足が眠気を催すのを感じる。しかし、ここで眠ってはいけない。キエランの心臓がこの病院の砲台の中で鼓動している限りは。
彼女は壁に寄りかかり、束の間目を閉じる。喉の渇きが激しく叫び出すが、無理やり自制し、飛び込んでキーランの血を味わいたいという衝動を抑えた。彼女は食べ物以上のものを求めているからだ。答えが欲しいのだ。なぜあのような男が群衆から彼女を阻むのか、なぜ彼の慢性的な傷を負った体を見ると、彼を守るという奇妙な義務感に駆られるのかを知りたいのだ。
かすかなビープ音が鳴り、メイラは飛び上がった。看護師がタブレット端末を持って治療室から出てきて、真剣な眼差しでメイラを見つめた。
「患者さんの状態は安定していますが、輸血が必要です。アレルギーはありますか?」
メイラはためらう。氷の破片が胸を突き刺す。アレルギーはファイルで調べられる。アレルギーには名前と医療記録が必要だ。落とし穴はどこにでもある。彼女は唇を噛んだ。
「わからない」と彼女はささやいた。「彼はただ私に…何も知らないって言っただけ」
彼女は困惑した様子で肩をすくめた。
看護師は眉をひそめた。
「では、まずは普通の缶詰から始めましょう。」彼女はタブレットに何かを入力して、また姿を消した。
メイラは深呼吸をした。一瞬、安堵した。しかし、この嘘がどれほど危険なものかに気づいた。医師と看護師は手順を定め、段階ごとにファイルを更新している。彼女はここに永遠に留まることはできない。
彼女はブロンドの髪を顔から払いのけた。少しでも人間らしく見せようと、弱々しく。それから彼女は振り返り、廊下へと姿を消し、静かに歩き去った。一歩一歩が重く、まるで現実の抵抗を感じているようだ。ついに彼女は階段に辿り着いた。彼女は素早く階段を上がり、別の廊下を抜け、患者エリアの外へ出た。
玄関ホールの外では、まるで何年も息をしていなかったかのように、涼しい夜の空気を吸い込んだ。ロンドンは眠り続け、診療所の地下墓地に何が隠されているのかを知らない。メイラは柱に寄りかかり、コートをきつく締めた。喉の渇きが体内でせわしなく高鳴った。まるで迫り来る誘惑を予感しているかのように、砂のような不安が血管に忍び寄った。
彼女は今、戻らなければならないことを知っている。何度でも。毎日、毎晩、彼女はキーランのもとを訪れ、その度に彼の血を味わいたいという衝動と戦う。そして彼は――もう彼女を「マリアン」と呼ぶことはないだろう。彼は彼女の本名を、もしかしたら彼女の物語を尋ねるだろう。彼女には答えられない疑問。答えることを許されない疑問。
しかし、頭の中の声がささやく。「あなたはそうしなければならない。そうすることでのみ、彼を守ることができる。そうすることでのみ、あなたの人間性の残りを保つことができる。」
メイラは顔を上げる。病院の正面にネオンサインが光る。「セント・バーソロミュー医療センター」。街の中心にある生命の殿堂であると同時に、死の場でもある。彼女は目を閉じ、息を吐く。
彼女は決意した。暗い通りを彷徨い、ロンドンの奥深くへと続くトンネルへと戻る。そこが彼女の故郷。彼女の心臓が鼓動する場所――守護者であり、復讐者でもある生き物の心臓が。
数え切れない犠牲者の血が彼女の血管を脈打つ。しかし今夜、彼女は再び、血を吸うことだけでなく、血を受け入れることの意味を目の当たりにすることになる。そして、大都市の灰色の石が彼女の傍らをすり抜けていくにつれ、メイラは自らの運命を書き換えつつあることを悟る。夜警としてだけでなく、生命の守護者としても。死から逃れたばかりの男の中に、彼女はあらゆる闇の向こうに潜む何かを見たのだ。吸血鬼でさえも守り抜くことができる希望を。
そして新たなゲームが始まる。そのルールは彼女自身もまだ書き残していない。ロンドンの街路が彼女の前に蛇のように暗く神秘的に広がり、メイラは夜の闇へと足を踏み入れる。影の中の影、獣の魂を持つ守護者として、彼女は自らの掟を見つけ出そうとしている。
第4章 メイラの裏側
メイラは屋根裏部屋のきしむドアを開け、狭い廊下に足を踏み入れる。その先の小さな部屋は天井が高く、屋根は傾斜していて、壁は真っ白に塗られている。本棚と小さなソファの間には使い古された机があり、その上には彼女のノートパソコン、数冊のノート、そして半分空になったティーカップがひしめき合っている。小さな簡易キッチンは半分の高さの仕切りの向こうに隠されており、部屋からの眺めは、通りの向こうの古い建物の屋根を見上げる小さな天窓を通してのみだった。
メイラは静かに後ろのドアを閉め、講義ノートの入ったバックパックを床に落とし、ブロンドの髪の毛を顔から払いのけた。太陽はすでに沈みかけている。午後の早い時間だ。少し目を閉じて休みたい衝動に駆られたが、無理やり目を覚まし続ける。疲労感や脱力感に囚われるのはもったいない。他の学生たちと同じように、彼女も常に万全の体調と規律を保っていなければならない。
リビングルームで、彼女はポケットからスマートフォンを取り出す。画面には同級生からのメッセージが十数件表示されていた。
「午後3時にカフェで会おうか?」とジョナスが尋ねます。
「午後5時にグループラン?」とララはすぐ下に入力します。
メイラは微笑んでこう返信した。「いいですね。参加します。」
送信ボタンの上で親指をためらわせながら、彼女は一瞬、キーランのことを、路地に横たわる血まみれの顔を思い浮かべた。心の奥底から湧き上がる衝動を抑え込んだが、彼女はそれを抑え込んだ。
彼女はティーカップをシンクに置き、マグカップを捨て、洗いたての洗濯物を急いでカゴに入れる。指に血が一滴もついておらず、疑惑を抱かせるような目の震えも一切なく、すべて目立たないようにしなければならない。彼女は深呼吸をして肩をすくめ、黒い革ジャケットの裾をなで、大きなバックパックを開ける。中には本、バインダー、USBメモリ、大学のポスターがきちんと整理されている。
彼女は午後3時ちょうどにアパートを出る。廊下には古い木材と、屋根から流れ落ちたばかりの雨の匂いが漂っている。陽光が降り注ぐ中庭に足を踏み入れ、光の中でクモの巣のように揺らめくワイヤーアンテナをちらりと見てから、狭い階段を下りて通りに出る。途中で、ゴミ出しをしている年配の女性に挨拶する。「こんにちは」と親しみを込めて言う。それは、彼女が生涯かけて丹念に作り上げてきた変装と同じくらい決まりきった言葉だった。
カフェまではわずか3つの通り。彼女はロンドンの長い歴史を物語る堂々とした砂岩の家々を通り過ぎ、歩道には近代的な自転車ラックと電動スクーターが立ち並ぶ。人々が彼女の前を急ぎ足で通り過ぎる。オフィスワーカー、小学生、若いカップル、新聞を脇に抱えた老紳士。そのブロンドの巻き毛の裏に何世紀もの歴史が隠されていること、その優美な顔の下に何世紀もの間、影の中をさまよってきた生き物が眠っていることを、誰も想像しない。
カフェの大きな窓から陽光が差し込む。淹れたてのコーヒーの香りが、甘いバニラとクロワッサンのサクサクした香りと混ざり合う。メイラは見覚えのあるバリスタに頷き、いつものダブルカプチーノにオーツミルク、そして軽食を注文する。今日はレモンケーキだ。ウェイトレスは微笑み、メイラの青白い顔に二度見もしなかった。
木のテーブルの一つで、既にグループが待っていた。スポーツウェアを着たジョナスは髪をボサボサにまとめ、デニムジャケットを着たララはスマートフォンを耳に当て、ネイサンはスケッチブックを手に好奇心に目を輝かせていた。彼らはメイラに温かく挨拶し、メイラはテーブルに両手を組んで真ん中に座った。
「議題は何ですか?」と彼女は尋ねた。
ジョナスはステンレスボトルから一口飲みます。
「後で公園を何周か走りたいんです。でも、まずは明日のプレゼンテーションについて話し合いましょう。」